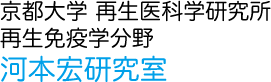ラボニュース 2025
2025 > 2024 >2023 > 2022 >2021>2020>2019 >2018 >2017 >2016 >2015 >2014 >2013 >2012 >2011 >2010 >2009 >2008
2025年11月25日(火)
前川さんがマイコースの研修を終了
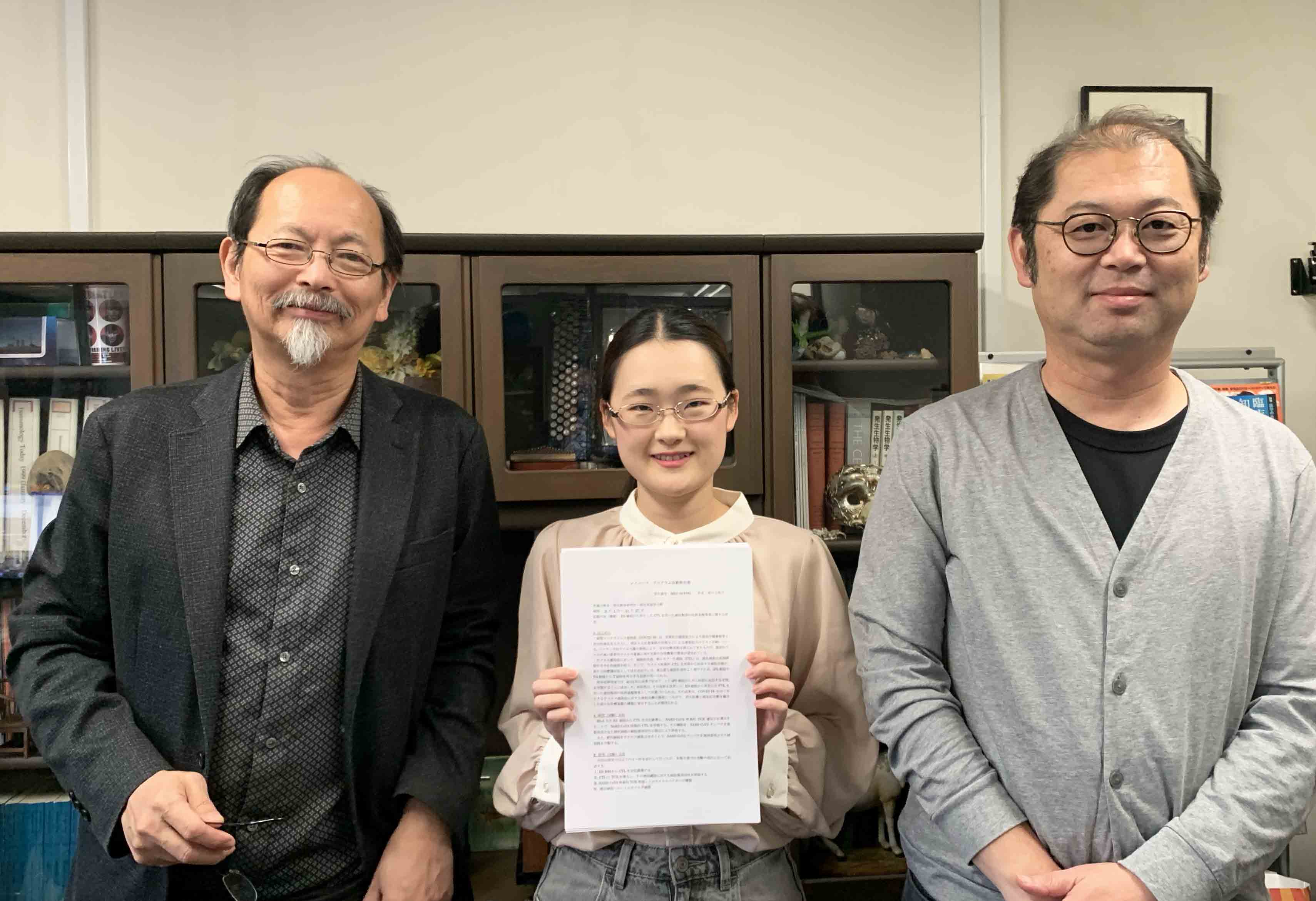 |
前川万侑子さん(京大医学部4回生)は9月初旬から2ヶ月くらい河本研で「マイコース」の研修を受けていた(2025年9月2日の記事参照)。主に上堀君の指導の下に、 ウイルス特異的T細胞の再生と機能評価などについて学んでいただいた。この日、報告書を提出いただいた。とてもよく書けていた。お疲れ様でした! |
2025年11月22日(土)
高校の同級生がやっているバンドと遭遇
 |
この日の午後、ネガティブセレクションの練習で河原町三条のRagというスタジオに行ったら、ちょうど高校の同級生らがやっているロックバンドとばったり出くわした。向かって右から3人目がリーダーの田中英雄氏で、かつては「R367ミヤコ・ロック・ショー」といういわゆるロックンロールのバンドを長らくやっていて、私はよく観に行っていた。何年か前に一旦解散になって、今のバンドは、確か「初心忘るべからず」という名前だったと思う。来年2月22日日曜日に西院のネガポジというライブハウスで、14時ごろからライブをやるそうだ。坂本氏(左端)と北野氏(右から二人目)が同級生。 |
 |
練習が終わった後、くうかいで会食。この時間が楽しい。向かって左から、大久保博志氏(Progress)、幸谷愛先生(大阪大学)、縣保年先生(滋賀医科大学)、私。 |
 |
シメに食したカニトマトソースパスタ。美味しかった。 |
2025年11月21日(金)
特許庁で講義
 |
この日の午後、特許庁で、免疫や細胞治療に関する講義を行った。質疑応答含め2時間を頂けたので、かなり色々な話ができた。今回の講義をコーディネートしてくれたのは、小田浩代先生。小田先生はかつて鈴木春巳先生(国際医療研究センター)のラボで基礎研究に従事されていて、学会などでよく話をしていた。何年か前に特許庁の審査官に転向されたとの事。久しぶりの再会で、とても懐かしかったのであるが、一緒に写真を撮るのを忘れて、残念だった。 |
 |
特許庁から見下ろした首相官邸。 |
2025年11月19日(水)
鴨川を散策
 |
この日、クリエーションコア御車(みくるま)にあるリバーセルのオフィスで用務を済ませた後、医生研まで鴨川沿いを歩いた。「カワウ」が沢山いた。 |
 |
春に花見をしたあたり。サクラは、秋の紅葉も、結構きれいだ。 |
 |
今年の花見(2025年4月4日の記事参照)の時の写真。 |
2025年11月18日(火)
向陽高校の生徒さん達が医生研を見学
 |
この日の午後、和歌山県の向陽高校の生徒さん達が医生研を訪れた。まず私が1時間ほど医生研の紹介、免疫学入門、今年のノーベル賞、若者へのメッセージなどの話をして、その後10人ずつくらいの3班に分かれて研究所を見学。 |
 |
引率者は、河本研の3人(永野君、西村君、板原君)。見学コースの一つはうちの研究室で、セルソーター、インキュベーター、クリーンベンチなどを見てもらった。写真は西村君がセルソーターについて説明しているところ。 |
 |
永野君がスライドを使ってフローサイトメトリーの仕組みを説明しているところ。 |
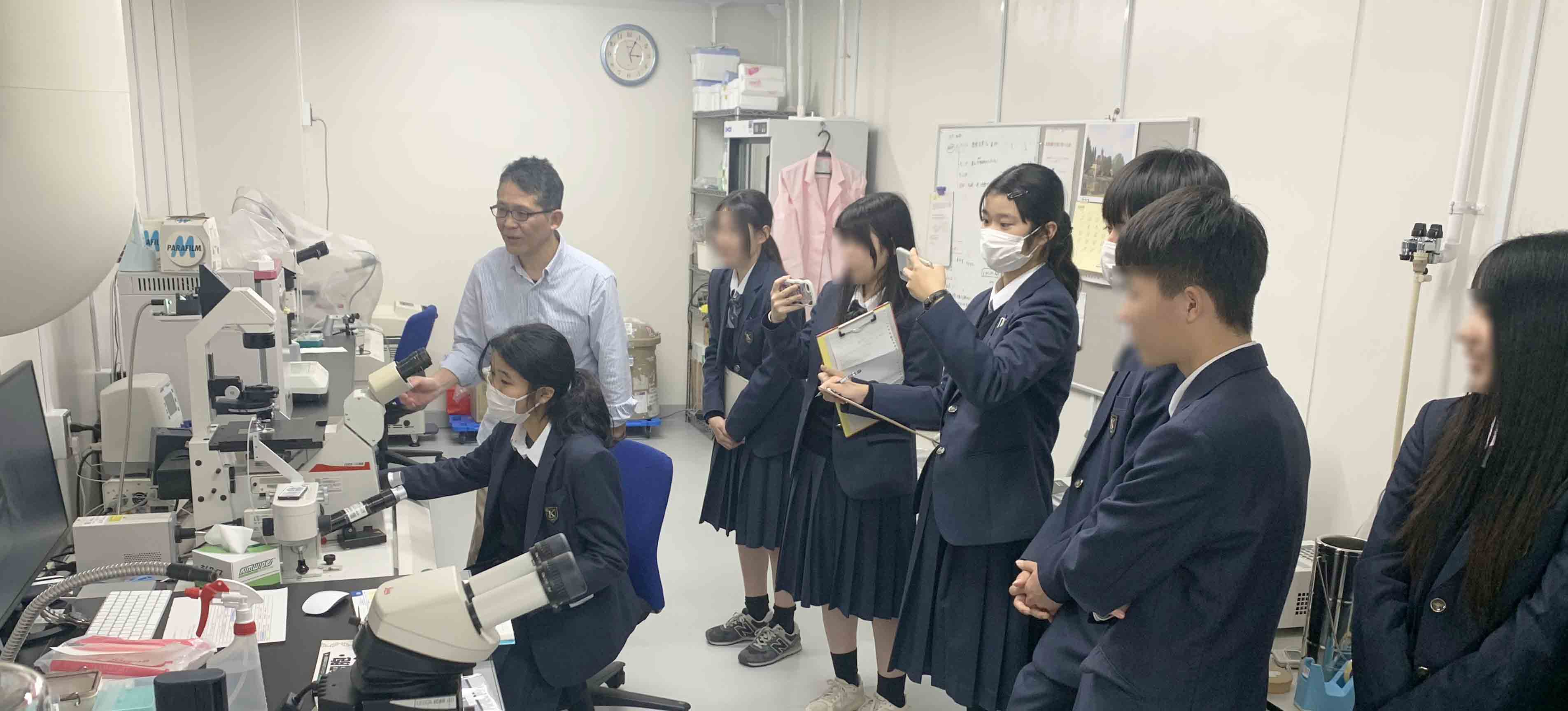 |
今回のハイライトは、胚操作室での、マイクロインジェクションの実習。遺伝子改変マウスの作製に用いる技術だ。 |
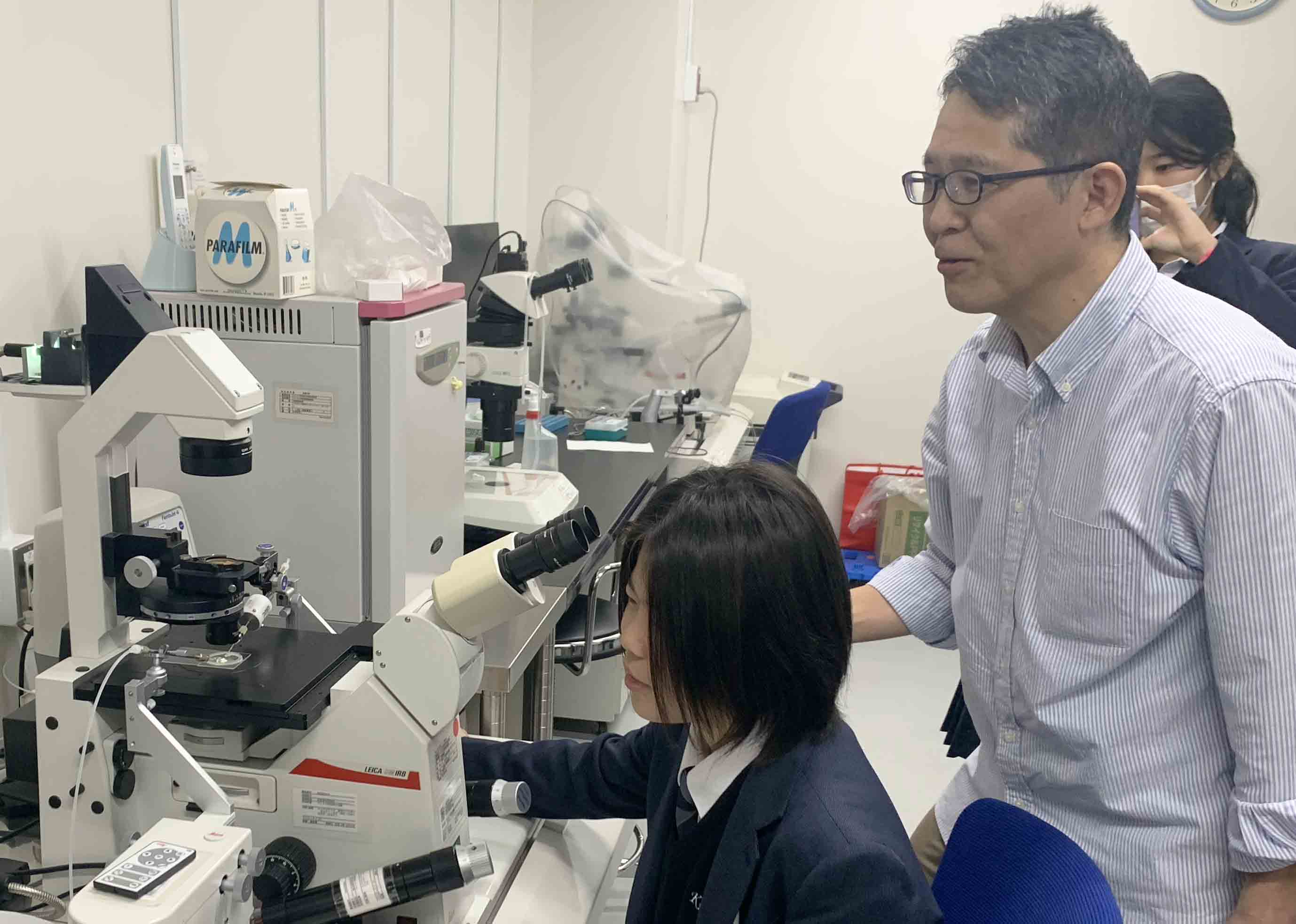 |
宮地均さん(技術職員)が手際よく、全員にマイクロインジェクションを体験させていた。 |
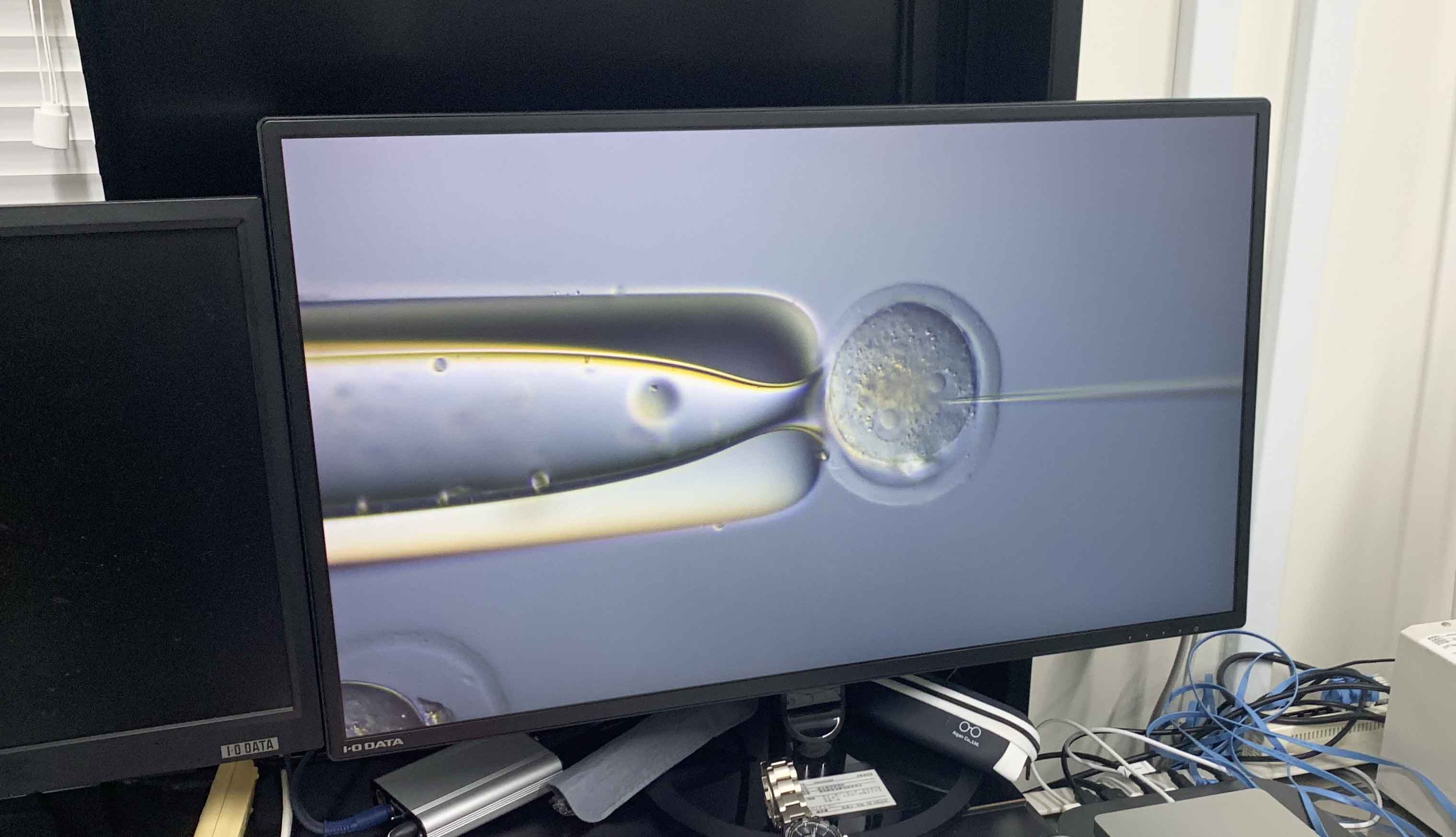 |
バーの先端のダイヤルをクリクリと回して、細いガラス管をマウスの卵に刺す、という作業をしてもらっていた。 |
 |
ES細胞施設では、高田圭先生(ヒトES細胞研究センター特定助教)が解説。 |
2025年11月16日(日)
川端通の紅葉
 |
まだイチョウは十分色付いてないが、サクラやトウカエデがいい感じに紅葉している。 |
 |
あるタクシーの運転手さんが「サクラは無料、モミジは有料」と言っていたが、確かにサクラはただで見られる名所が沢山あるが、モミジの名所の多くは、拝観料を払う必要がある。鴨川沿いには、サクラは沢山見られるが、モミジはあまり見られない。とはいえ、モミジがあまりなくても、十分きれいだ。なお、その運転手さんによると、今年の京都の名所のモミジは、全体的にイマイチだそうだ。 |
2025年11月13日(木)
令和7年度AMED再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト研究交流会
 |
表記の会が、水道橋のプリズムホールで開催された。 |
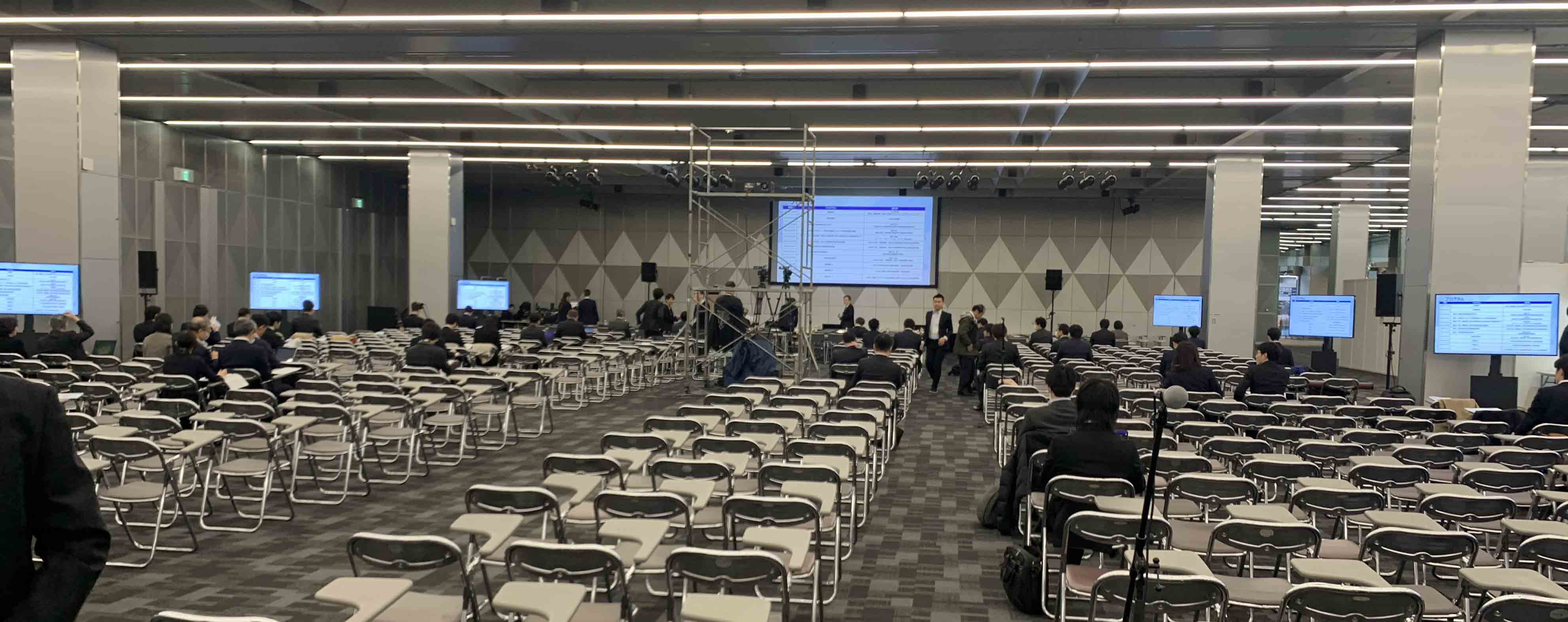 |
私は表記のプロジェクトの支援は受けていないが、AMEDの革新がんの支援を受けている研究者として参加。ポスターの掲示も行った。 |
 |
お昼は、水道橋の近くの横浜家系のラーメン屋さんに行った。 |
 |
濃厚なとんこつ醤油ラーメン。家系のラーメンは、ほうれん草と海苔が入っているのが特徴であるらしい。とても美味しかった。 |
2025年11月11日(火)
和田森麻悠さんが研修で河本研に参加
 |
和田森麻悠さんは、ニュージーランドのオタゴ大学 (University of Otago) 医学部の2年生で、11月10日から12 月下旬まで河本研で研修。麻悠さんは、和田森由紀子さん(東大柳井秀元研大学院生)のご令嬢。由紀子さんは今年のIC2NEMOの会(2025年1月28日の記事参照)、昨年の免疫学会(2024年12月3日の記事参照)、サマースクールなどに参加されていた。この日、永野君と西村君も加わって、「くうかい」でプチ歓迎会。 |
 |
この写真は11月14日、西村君の講義を受けているところ。 |
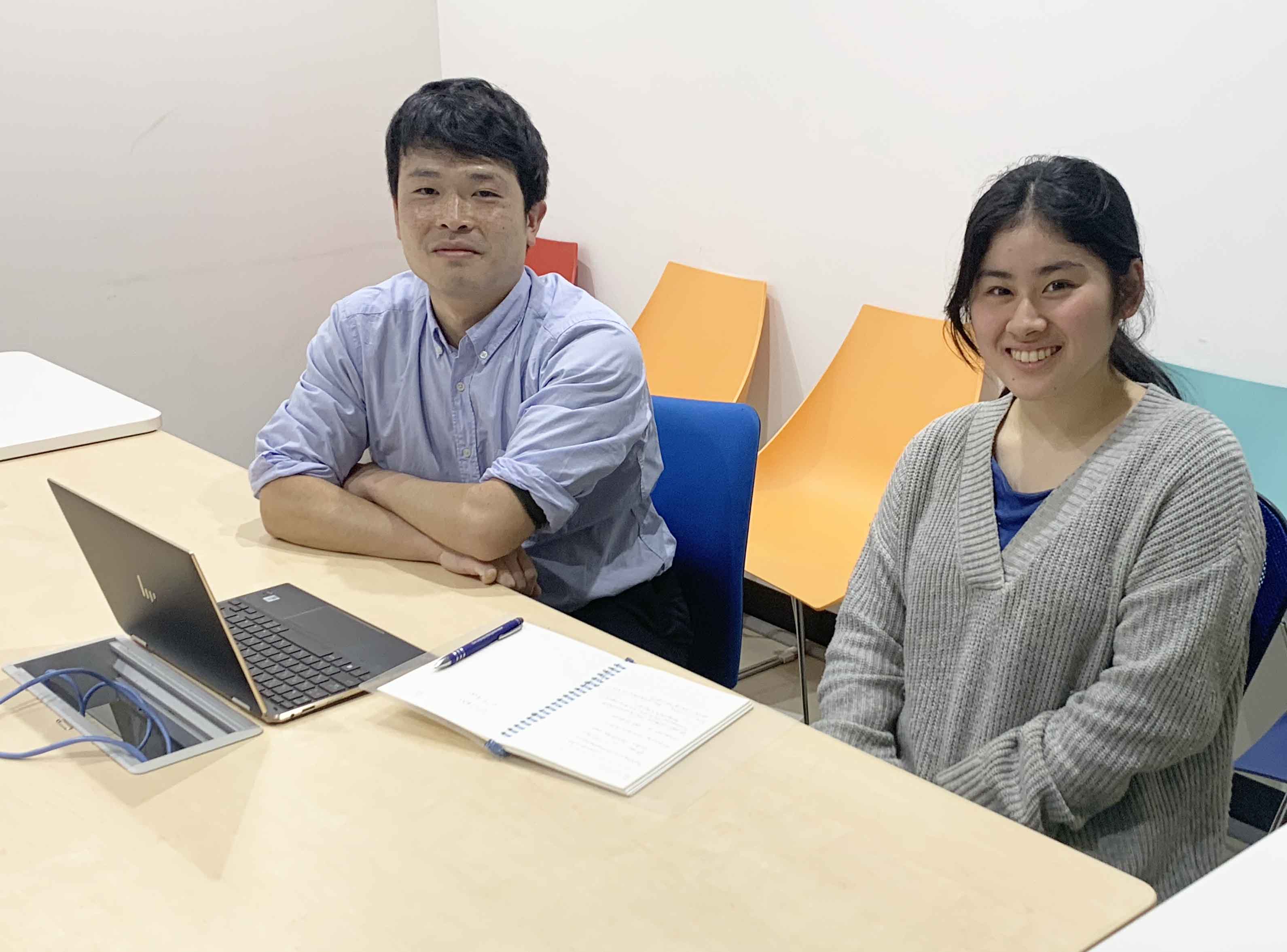 |
この写真は11月20日、板原君の講義を受けているところ。 |
2025年11月10日(月)
国際KTCC2026のHPがオープン
 |
国際KTCCは4年に一回、Thymus Global Networkの一環として、国際KTCCとして開催される。この日、HPがオープンになった。前回は私が集会長として2021年に開催する予定であったが、コロナ禍のせいで、諦めざるを得なかった(2021年4月30日の記事参照)。 KTCC2026 HP: |
 |
今回は谷内一郎先生(理研IMS)が集会長。写真は今回のオーガナイザー一同。 |
 |
今回は、運営方針が大きく変わり、参加費を、海外の学会に合わせた額にしようという事になり、一人7万円、学生5万円という設定になった。これまでは国際KTCCは2万円くらい設定だったと思うが、これは格安で、集会長は協賛金集めなどをかなり頑張ってする必要があった。今回のようにすれば、集会長は特にお金集めに必死にならなくても、何とかなるはずだ。それにしても、一人7万円となると、ラボメンバーにも、気軽に「参加したい人はどうぞ、全額支援しますよ」と言えなくなる。 |
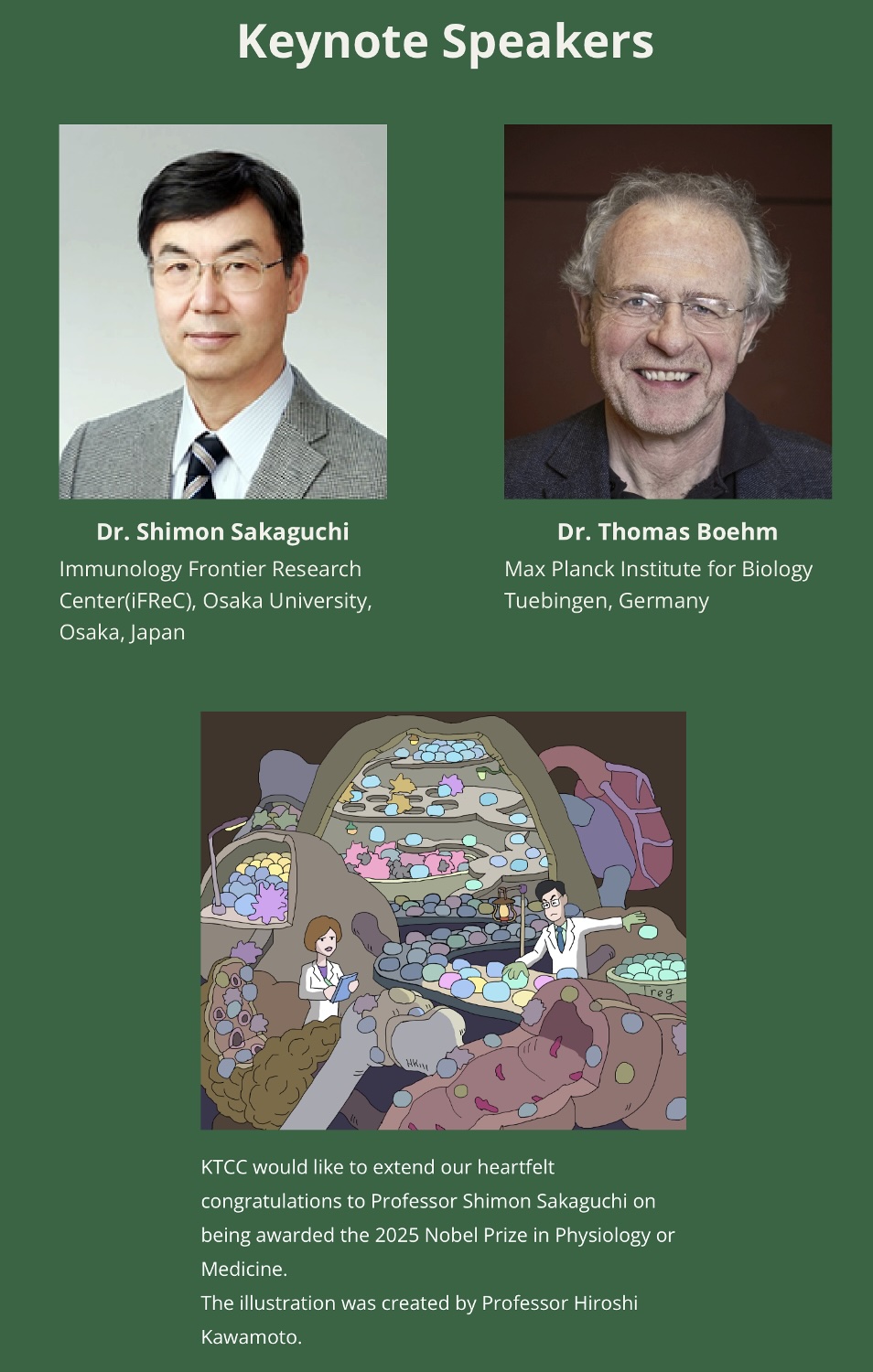 |
キーノートスピーカーは、坂口志文先生と、トーマス・ベーム先生。私は毎回、KTCC用にイラストを描いているが、今回は、坂口先生のノーベル賞受賞にちなんだイラストにした。その関係で、トップページではなく、キーノートスピーカー欄に埋め込む形になった。 |
 |
元の構想では、左のように、「延暦寺、修行僧、竜」というイメージで、胸腺の中の正と負の選択過程を、修行で昇進あるいは脱落していく若い僧侶、という感じで表そうと思っていた。昨年観た村上隆の影響が少し出ている(2024年8月14日の記事参照)。部屋が何層も重なる様子には、鬼滅の刃の「無限城」のイメージを使おうかと考え始めていたところだった。 |
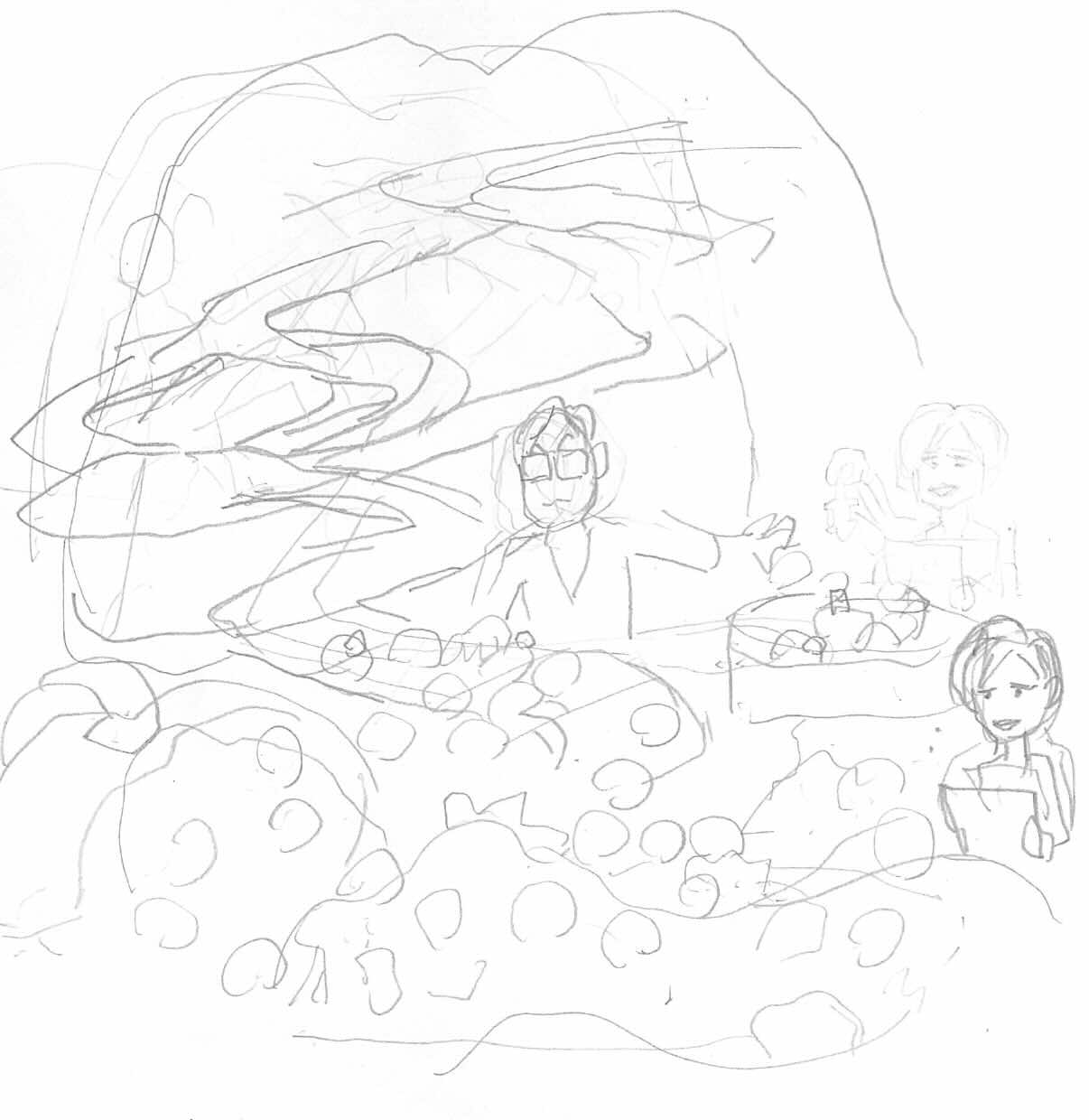 |
しかし、せっかくKTCCに関係してこられた坂口先生がノーベル賞を受賞された訳だし、しかもキーノートスピーカーとして話をされるのであるから、それをイラストにするべきだと考え直した。左は、最初の案。ちょっと気になったのは、胸腺のイメージを遠景に入れると、どうしても少し前に堀昌平先生が集会長をされた時のKTCC用のイラストと似てしまう事だ(2024年6月14日の記事参照)。 |
 |
構図は似てしまうが、色の雰囲気を変えたりしようということで、奥に胸腺、手前の末梢では血流中から坂口先生がTregを抜き出して、残された細胞がさらに手前の組織に浸潤して炎症を起こしている、という図案にした。 |
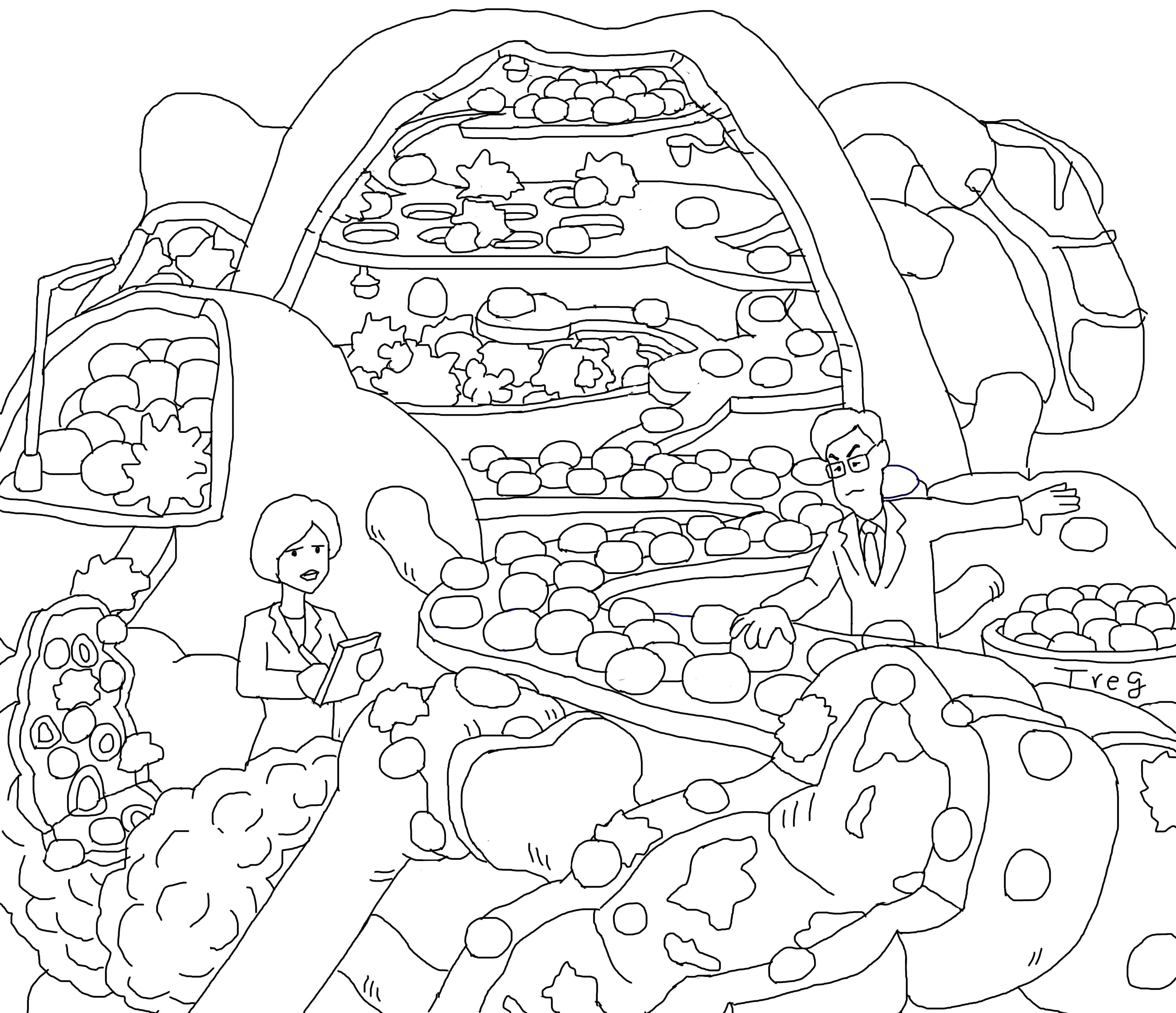 |
線描。 |
 |
彩色。坂口先生は、免疫学会サマースクールで、「街灯の下で鍵を探す」という例え話をされた事があった(と思う)。暗いところで鍵を落としたかもしれないのに、探しやすいからといって明るいところだけを探していては、見つからない。答えに辿り着くには、光があたってないところを探す事も大事、という教えだ。このイラストでは、暗い中、坂口先生がランプを灯して、こつこつとTregを取り分ける様子を描いている。奥様である坂口教子先生は、ご主人の研究を支援しつつも、skgマウスという関節リウマチを自然発症するマウスの系統を樹立され、そのマウスの解析から、胸腺での負の選択が関与する仕組みの発見もされた(Nature, 2003)。なので、教子先生が関節炎を注意深く観察されている様子も、絵の中に組み込んだ。 |
2025年11月10日(月)
腫瘍内科で講義
 |
この日の夕刻、京大の腫瘍内科講座で、免疫について、質疑応答込み1時間の講義をして、20人くらいに聴いていただけた。今回の講義は菊池理先生(向かって左端、がん免疫総合研究センター准教授)がアレンジしてくれた。菊池先生は免疫サマースクールに参加されていた(2025年8月25日の記事参照)。私の向かって左隣は、武藤学先生(腫瘍薬物治療学講座教授)。 |
2025年11月10日(月)
実験動物慰霊祭
 |
この日、実験動物の慰霊祭が開催された。 |
 |
医生研の動物実験施設には、以前はウサギやイヌもいたが、今はマウス、ラット、サルだけになっている。 |
2025年11月10日(月)
朝の虹と月
 |
この日の朝、御所で虹が見られたとの事。秘書の宮武さんが撮った写真。 |
 |
よく見れば左上の方に月も写っている。素晴らしい。 |
2025年11月6日(木)ー7日(金)
第38回日本バイオセラピィ学会学術集会に参加
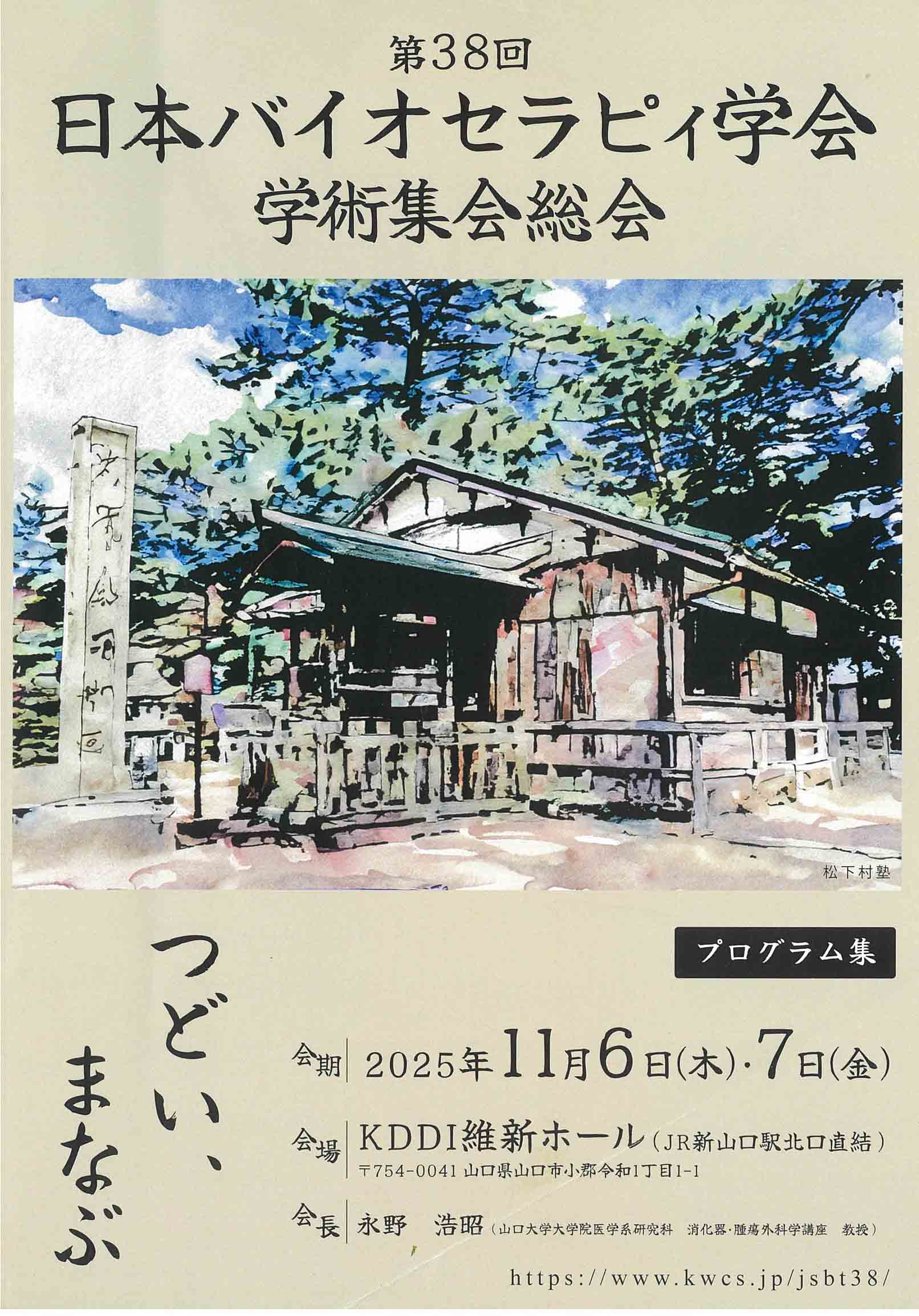 |
表記の会に参加した。場所は山口。 |
 |
私はこの学会では理事を務めている事もあって、山口には前日入り。理事会の後、湯田温泉のかめ福オンプレイスというところで懇親会。 |
 |
今回の集会長、永野浩昭先生(山口大学)による挨拶。 |
 |
学会の理事長、河野浩二先生(福島医大)による挨拶。 |
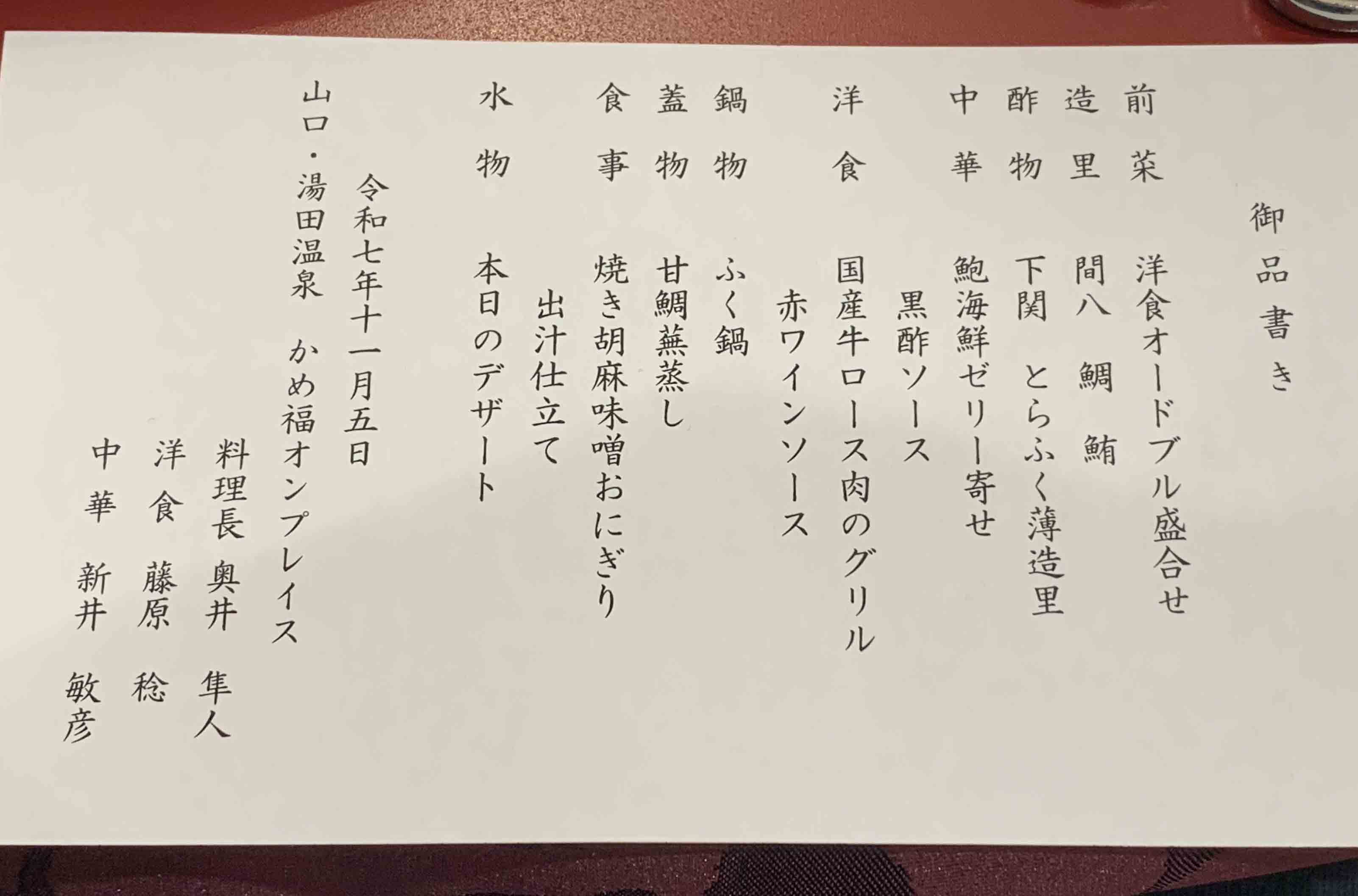 |
郷土料理を前面に出したメニュー。 |
 |
料理の一部。美味しかった。 |
 |
今回供された日本酒。 |
 |
今回供された日本酒の説明のプレゼンの中で使われたスライド。少しずつ、全ての銘柄を飲んでみたが、どれも美味しかった。 |
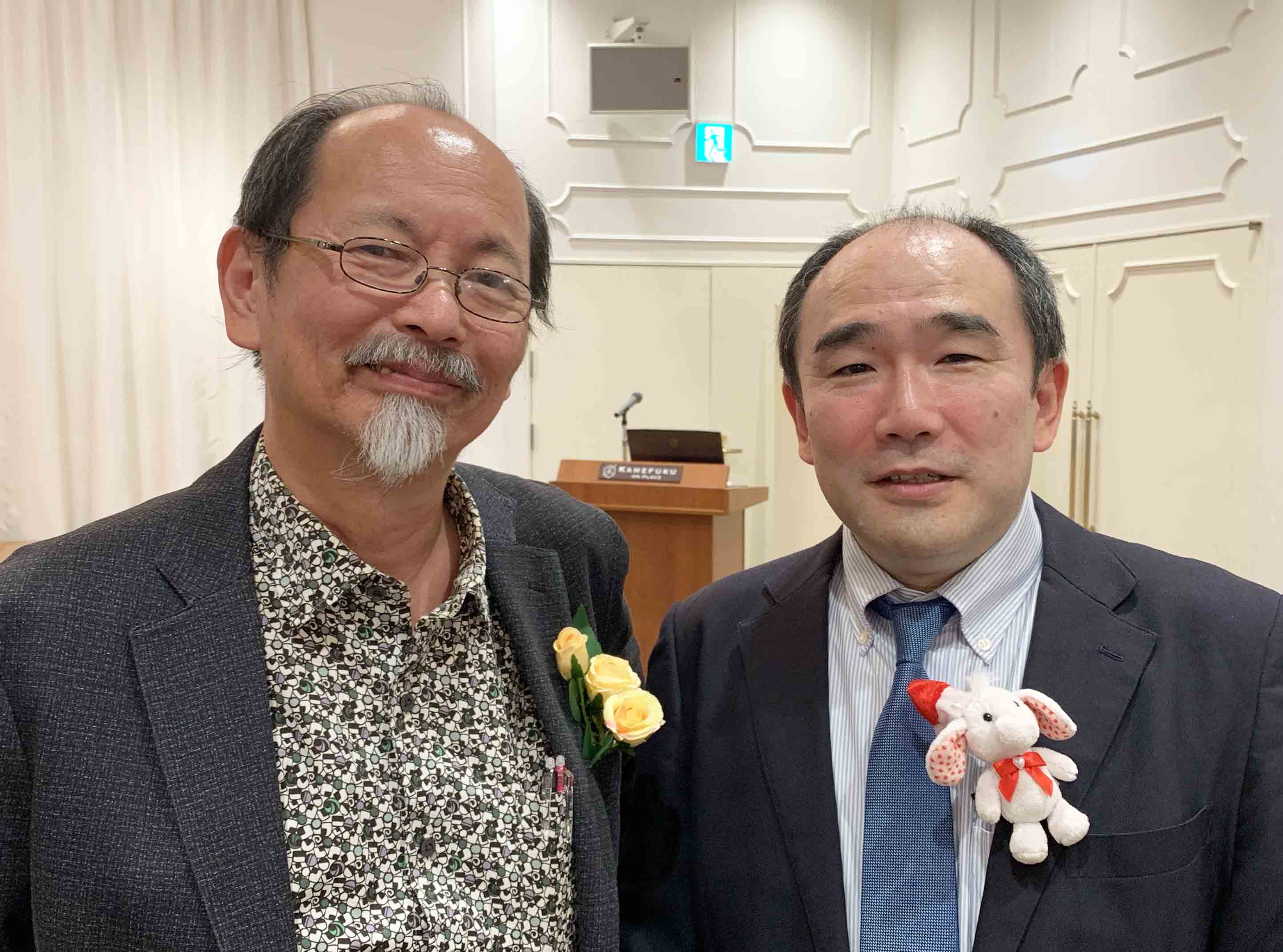 |
濱西潤三先生(京都医療センター産婦人科診療科長)と。少し前まで京大病院の産科婦人科におられていて、AMEDの先端バイオ創薬(2019-2023年度)では卵巣がんの腫瘍浸潤T細胞のシングルセル解析などの共同研究をご一緒した。今回、この学会の理事に就任された。 |
 |
新山口駅すぐ近くの会場。 |
 |
立派なホールだった。 |
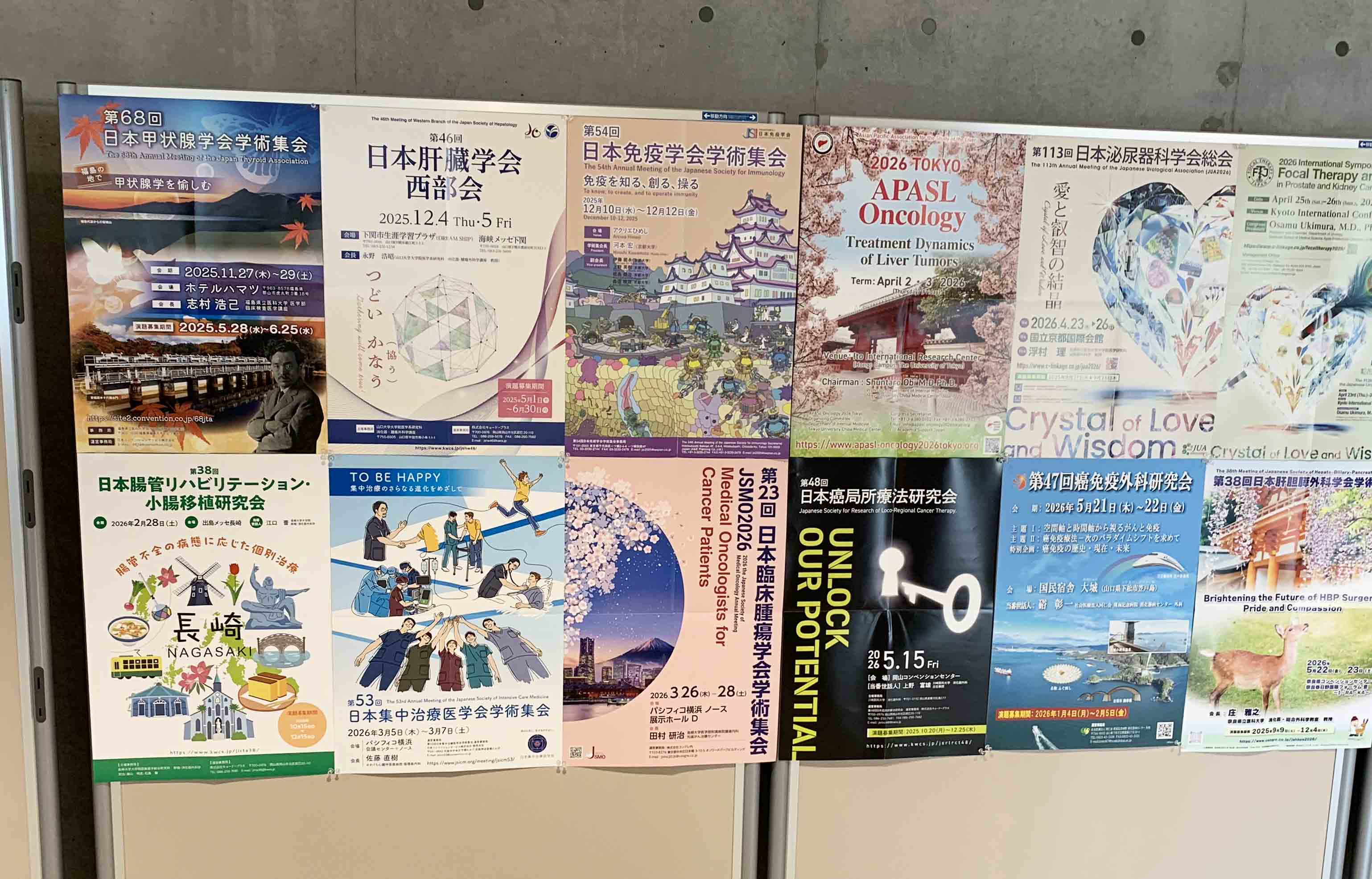 |
免疫学会のポスターが見られるのも後1ヶ月。 |
 |
懇親会。 |
 |
札幌医大の廣橋良彦先生と。TCRのクローニングや標的ペプチドの同定などで共同研究ができそうだ。 |
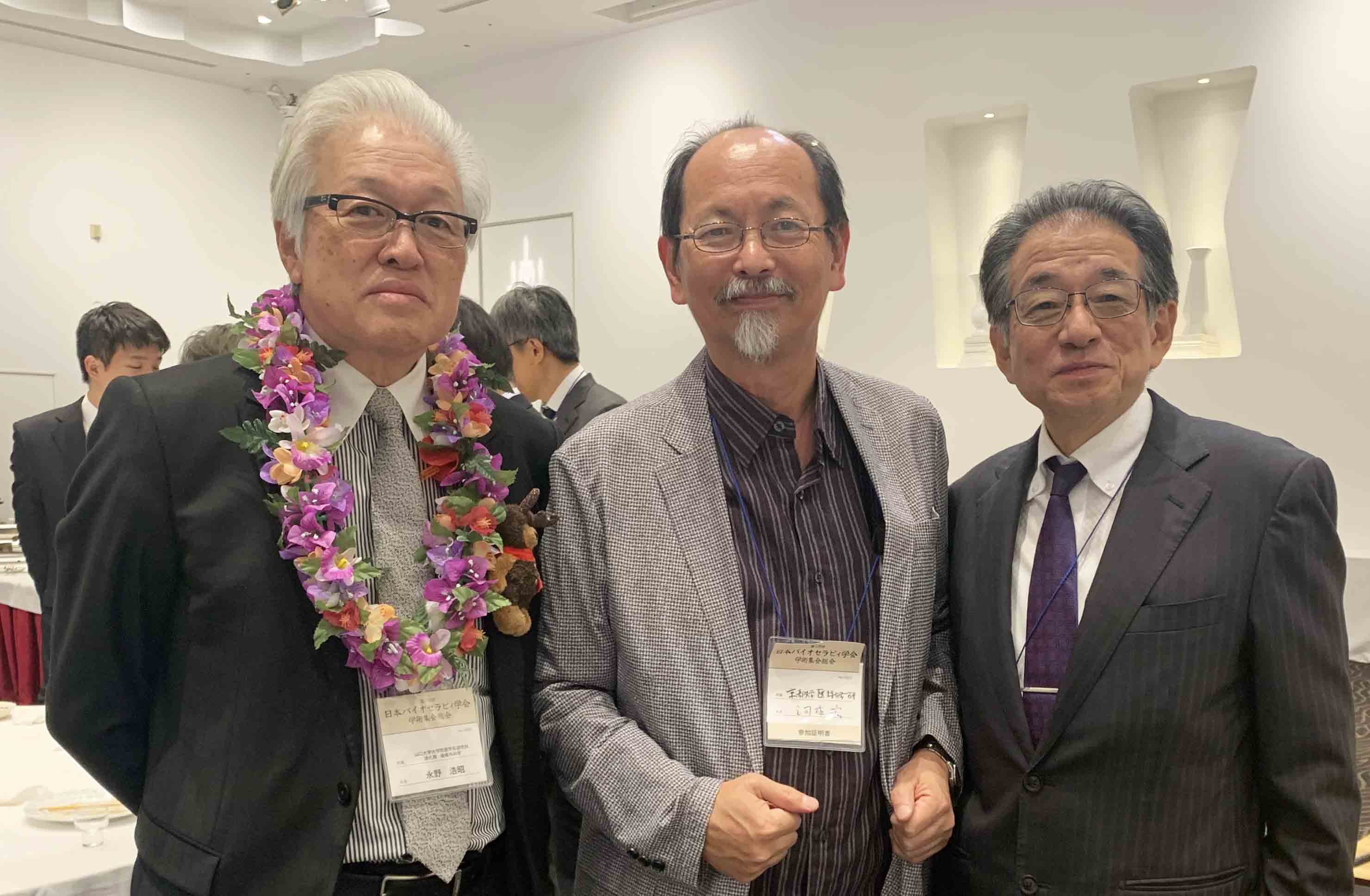 |
永野先生、硲(はざま)彰一先生(元山口大学、現周南記念病院)と。 |
2025年11月2日(日)
チームラボ京都を鑑賞
 |
チームラボ京都を、中宮さん、宮武さんと一緒に鑑賞。まずは京阪ホテルのイタリア料理屋で昼食。少し前に、開業前の内覧会に行ったが(2025年10月4日の記事参照)、今回はアルコールを入れた状態で楽しもうと思い、ワインを頂いている。 |
 |
ランプの部屋。インタラクティブで、人の動きに反応して色が変わる。 |
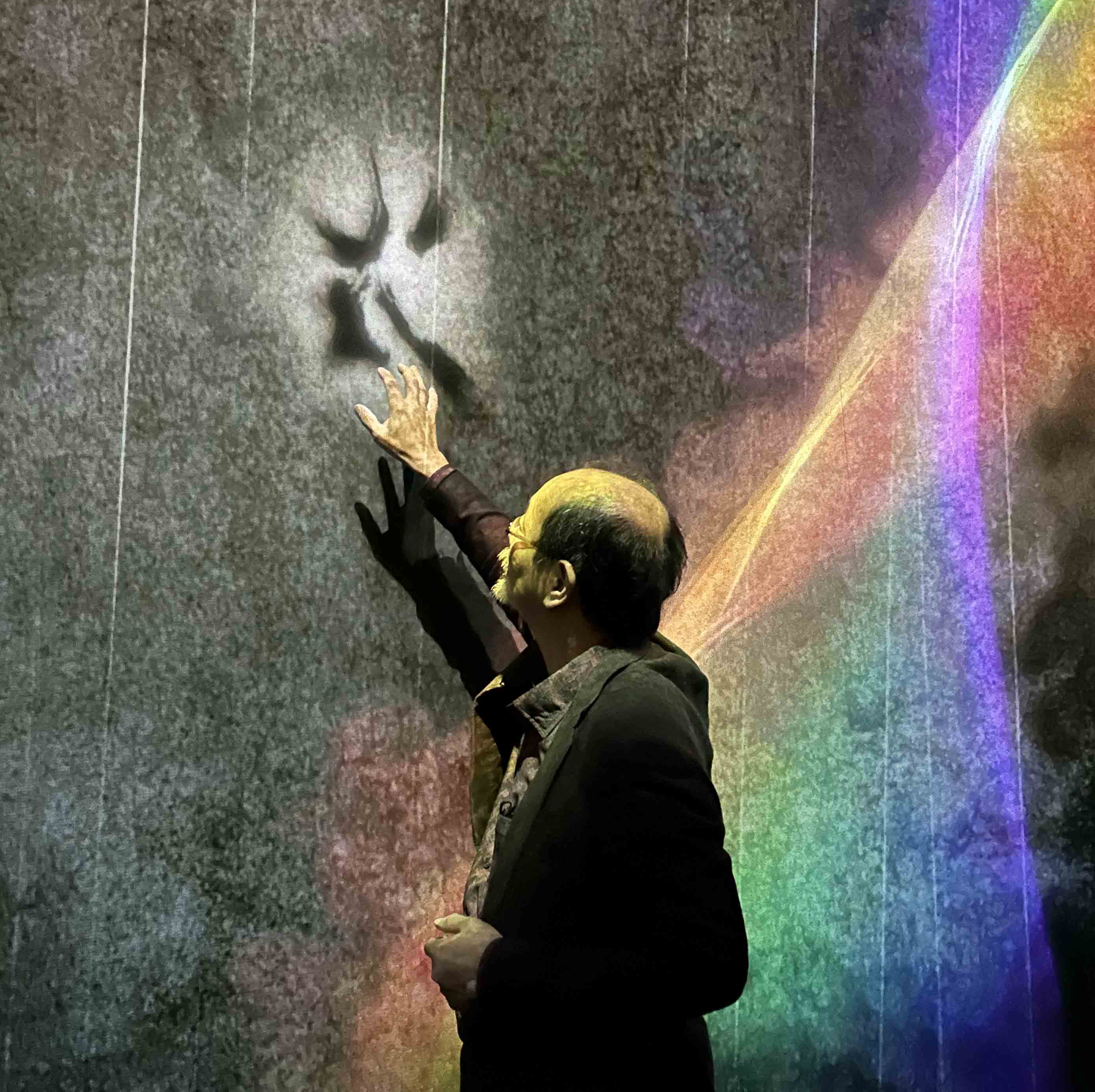 |
上からゆっくり降りてくる文字に触れると、映像が現れる。雷、蛍、虹など。 |
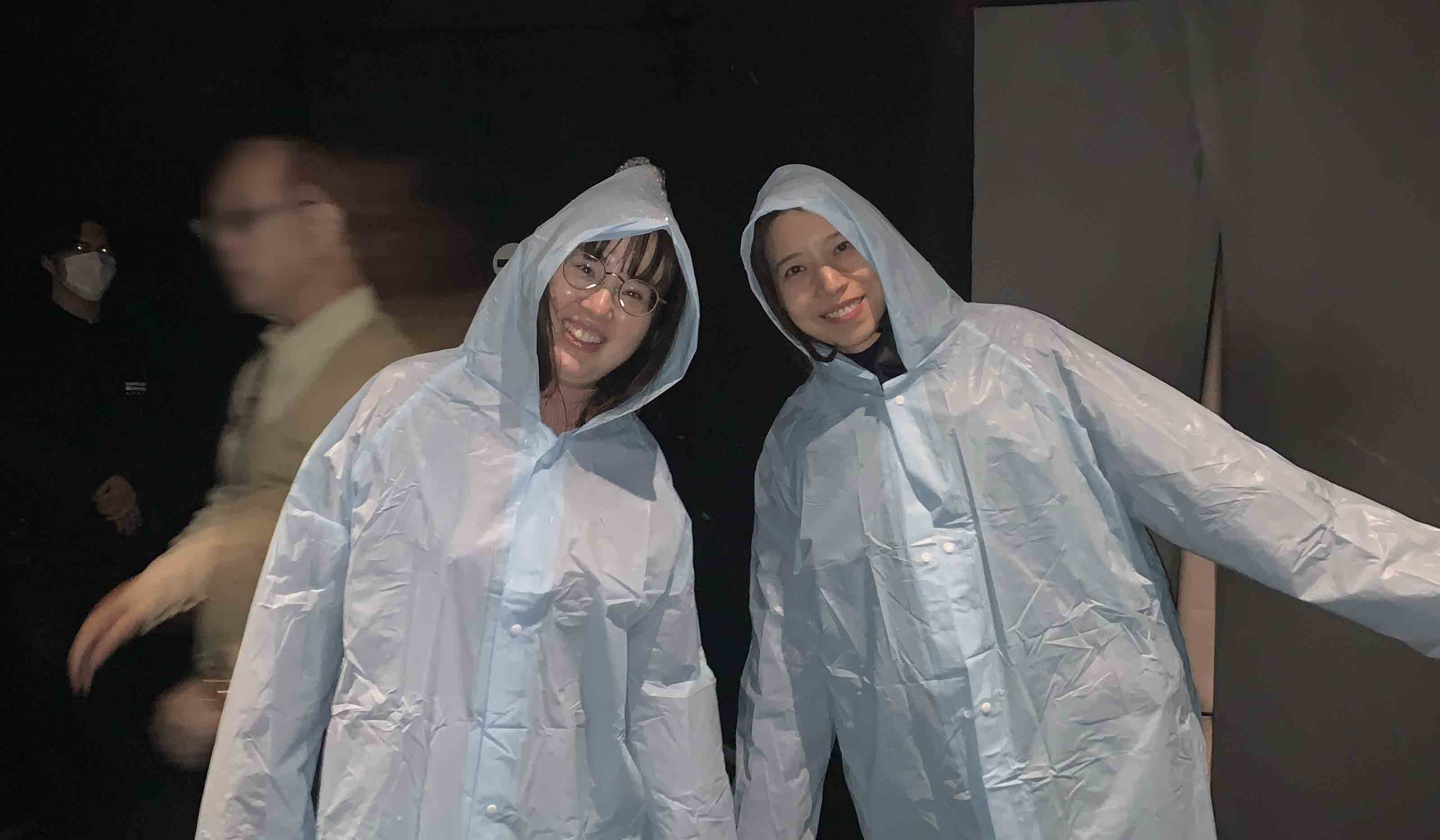 |
泡が渦巻いている部屋では、300円かかるが、こういう服を着て、マスクも着けると、泡の中に突っ込んでいける。 |
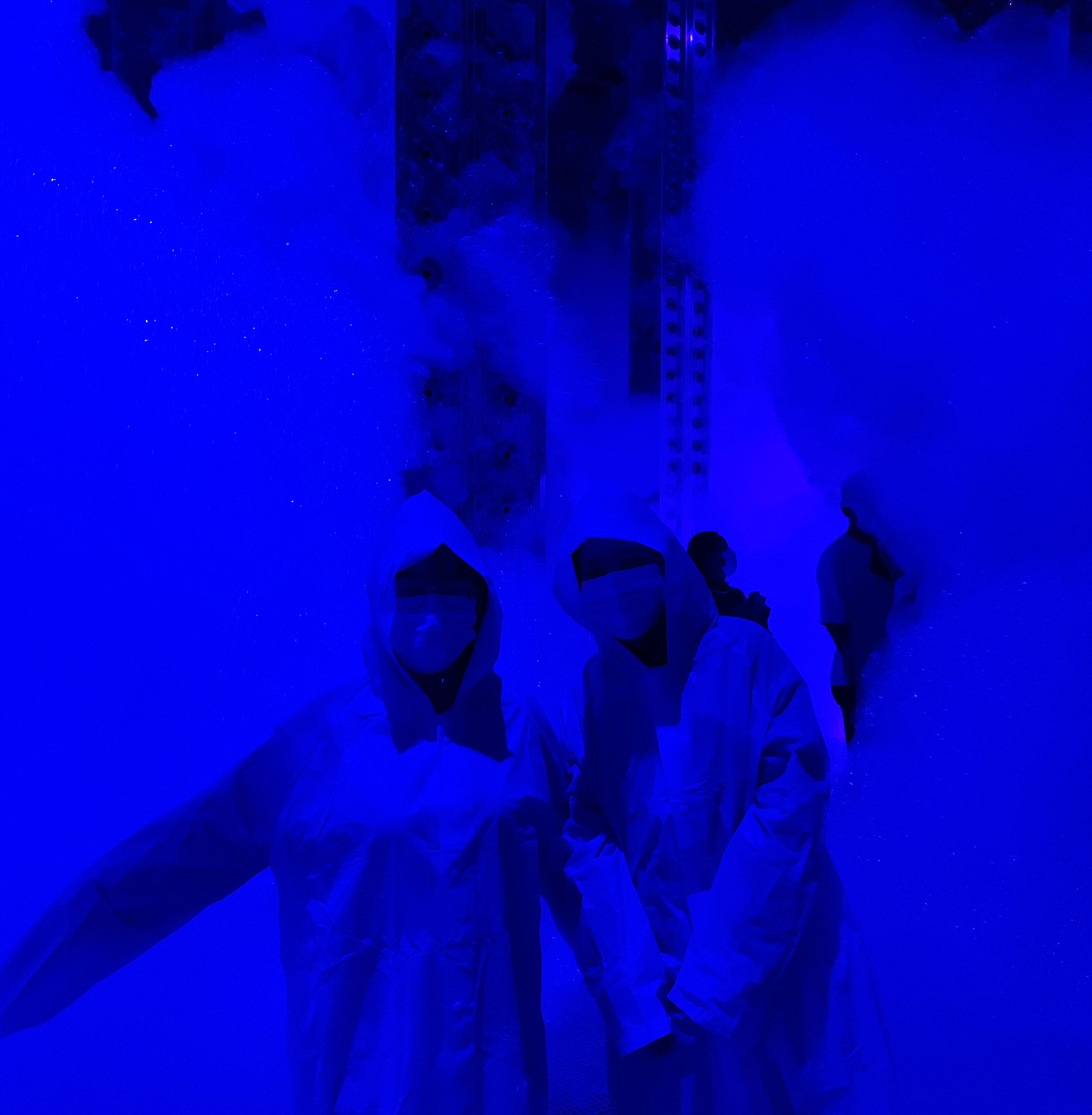 |
とても幻想的だ。泡の雲の中に入ると、遭難しそうな気分になる。 |
 |
長靴を借りて沼に入る。 |
 |
かき回しても、すぐにボコボコした対流模様が現れる。 |
 |
ガラスの岩がきれいだ。 |
 |
このオブジェは触ることができ、インタラクティブに色が変わったりする。 |
 |
お絵描きができるコーナー。キラーT細胞を描こうとしている。 |
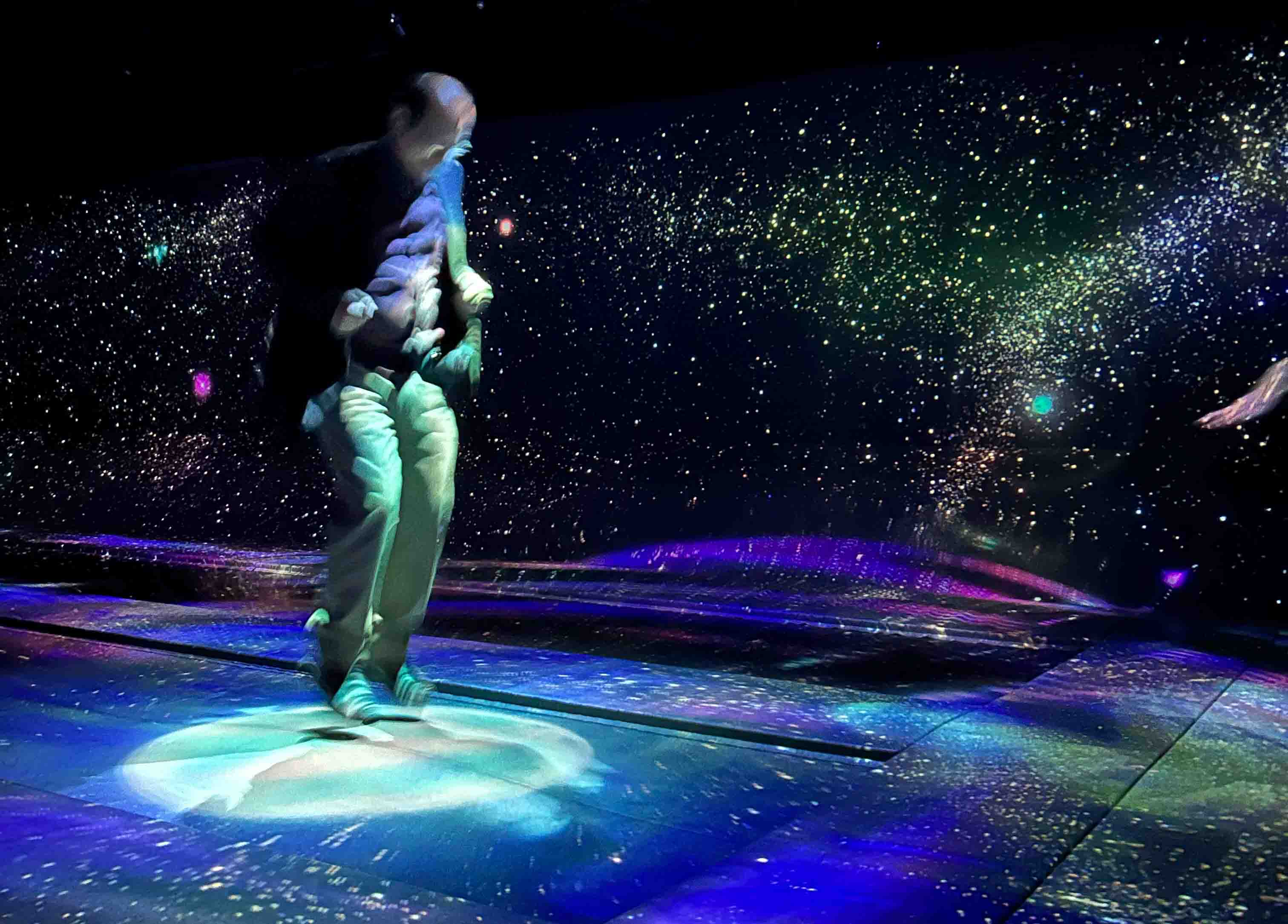 |
恒星の進化を辿るトランポリン。 |
 |
幻想的なフィールドアスレチックが面白い。やや駆け足で観て回って、それでも3時間近くかかった。ゆっくり見たら4-5時間かかりそうだ。楽しかった! |
2025年11月1日(土)
まほろば開店38周年の会
 |
「まほろば」は、高野川にかかる蓼倉橋の近くにある居酒屋。毎年11月1日は、開店記念の祝賀会になっており、常連の人達が参集する。この会に来ると、古き良き時代へのタイムスリップ感を楽しめる。 |
2025年10月27日(月)ー30日(木)
第31回東アジア合同シンポジウム
 |
表記の会が開催された。昨年は台湾だった(2024年10月29日の記事参照)が、今年は上海。 |
 |
このシンポジウムは1994年に始まり、以下の8研究所が参加していて、順番にホストしている。来年は医生研がホストする事になっている。 ・東京大学医科学研究所(日本)(IMSUT) ・ソウル国立大学分子生物学遺伝学研究所(韓国)(IMBG) ・順天郷大学順天郷医学生物科学研究所(韓国)(SIMS) ・上海生物化学・細胞生物学研究所(中国)(SIBCB) ・国立台湾大学医学院 生物化学・分子生物学研究所(台湾)(IBMB) ・京都大学医生物学研究所(日本)(LiMe) ・沖縄科学技術大学院大学(日本)(OIST) ・上海科技大学免疫化学研究所(中国)(SIAIS) |
 |
今回のマップ。この会は基本的には上記の研究所から、それぞれの所長と、PIクラス4人、若手4人の9名が参加、という方式で成り立っている。新任のPIを紹介するという役割もあるが、基本的には最近いい仕事をした人が参加して、研究所の活動をアピールするという感じだ。今年は医生研からはPI枠で今吉格先生、森博幸先生(秋吉研准教授)、宮﨑正輝先生(河本研准教授)、牧功一郎先生(安達研准教授)、若手枠では西淵剛平先生(遊佐研助教)、森田大輔先生(元杉田研助教)、大崎一直先生(伊藤研助教)、谷本佳彦先生(中台研助教)が参加した。 |
 |
泊まったホテル。 |
 |
ゴージャスな感じ。 |
 |
シャワーがベッドの横にある。妙なしつらえだ。 |
 |
お風呂はこんな感じ。 |
 |
今回は上海生物化学・細胞生物学研究所(SIBCB)の主催で行われた。会場。 |
 |
副所長のJinqiu Zhouによる挨拶。 |
 |
初日のディナーで、所長テーブル。 |
 |
右側半分は医生研からの参加者。 |
 |
奥の3人は医生研からの参加者。 |
 |
二日目のディナーはホテル近くの大型商業施設の中。 |
 |
楽しそうだ。 |
 |
この日は、「これでもか」というぐらい料理が来た。 |
 |
全てが美味しかったが、食べきれなくて、勿体なかった。余るくらい供するのが中国式のもてなしという事のようだ。 |
 |
夕食後、有志で、タクシーで上海の中心街へ。40分ほど乗ったのに、2000円くらいだった。安い。 |
 |
谷本先生と西淵先生。 |
 |
「ちいかわ」ショップがあった。 |
 |
上海の夜景ベストスポットで記念写真。夜9時50分くらいに撮った写真。 |
 |
この美しい夜景は夜10時まで。10時には暗くなってしまう。 |
 |
10時5分頃の写真。もう少し遅くまで明るくてもいいのに、と思った。 |
 |
近くのフードコートに皆で立ち寄った。 |
 |
ディナーで満腹だったが、少し追加で食べた。楽しかった! |
 |
三日目、若手科学者賞。大崎先生が入賞。 |
 |
三日目の夕食は、屋外の個室で、火鍋。メンバーは、「研究所ごとに」という粋な計らい。 |
 |
2種類のスープに具を投入。 |
 |
奥の方はかなり辛い。 |
 |
医生研チーム。 |
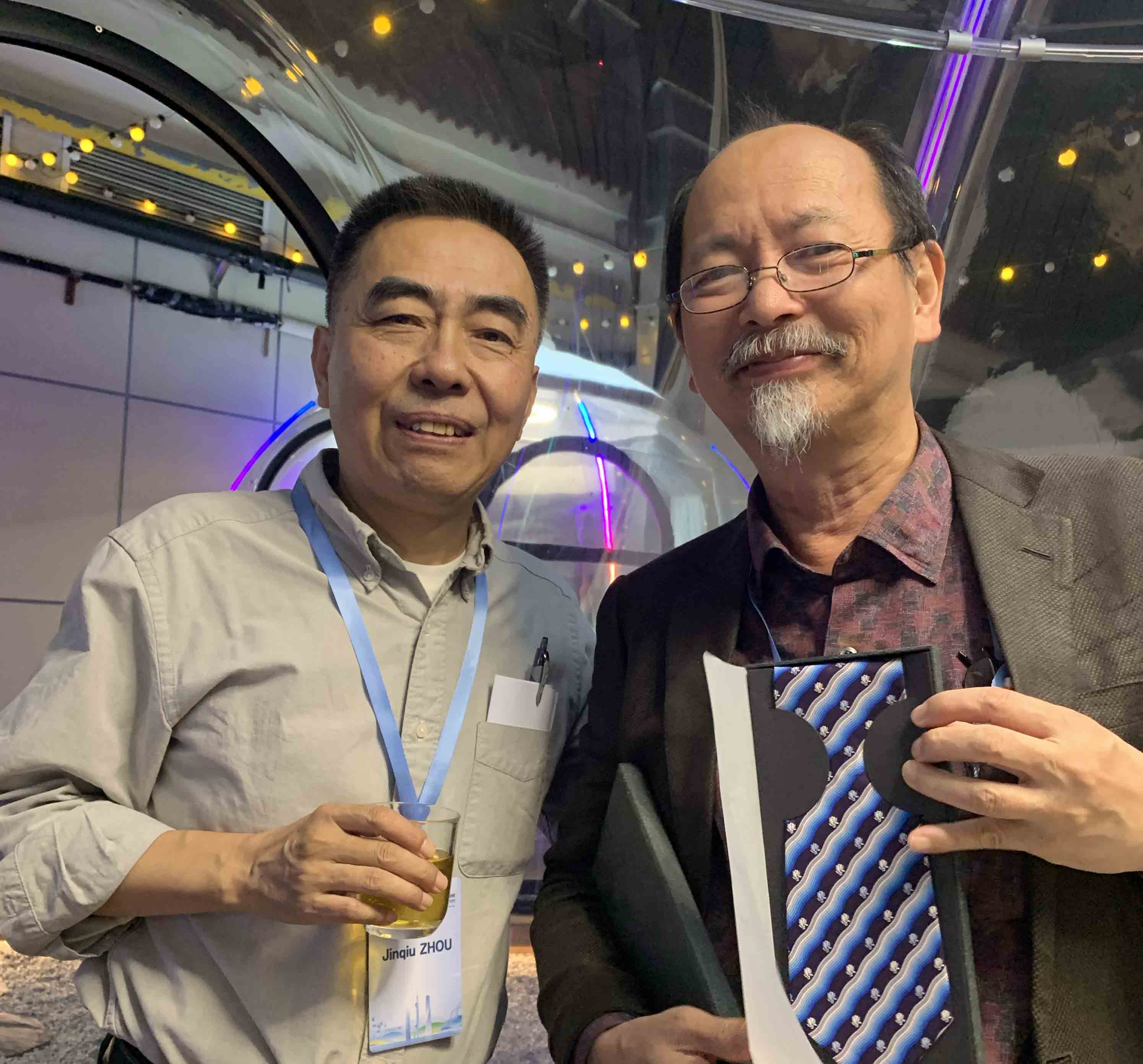 |
Jinqiu Zhouと。 |
 |
変面のパフォーマンスを楽しめた。 |
 |
コンビニの弁当の値段は、15元-20元くらい。一元=22円としたら、300円-400円くらいなので、日本より少し安いくらい。 |
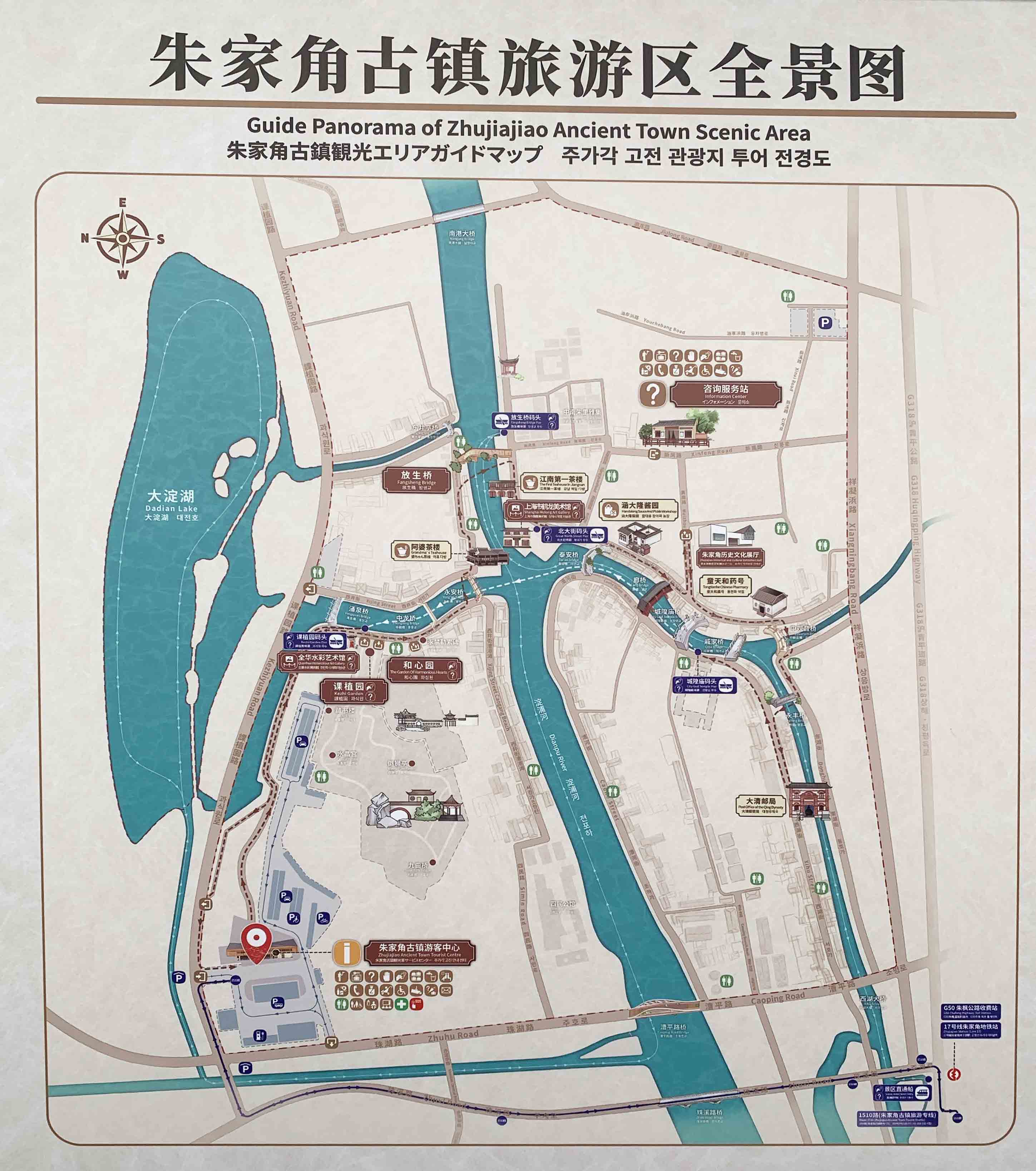 |
最終日、水郷の街のツアーに参加。以前に蘇州でシンポジウムに参加した時も水郷の街を訪ねた(2015年9月21日の記事参照)が、このあたりにはこういうところが多いのであろう。 |
 |
今回のコース。途中で船に乗った。 |
 |
水郷。いい感じだ。 |
 |
水の透明度が高い。これはとても不自然だと思われた。琵琶湖の北の方はこれくらい綺麗だが、大津のあたりや、琵琶湖の水をひく疏水も、これほどの透明度ではない。 |
 |
和心園という庭園を見学。 |
 |
ガイドの人の英語はわかりやすかった。 |
 |
盆栽が飾られていた。 |
 |
今吉先生と、椅子に座ってくつろぐ。 |
 |
ちょっと雰囲気のある建物。 |
 |
建物の2階。 |
 |
池もあったりする。 |
 |
こういう庭がいくつもつながっている。 |
 |
太湖石と呼ばれる奇岩。石灰岩らしい。上海の西の方に琵琶湖の3倍くらいの大きさの湖があって、その周辺で採掘されるらしい。 |
 |
船に乗った。 |
 |
5分くらいのコースで、6人で4000円くらい。 |
 |
大きな水路の船着場で船を降りた。 |
 |
船着場からは賑やかな路地になっていて、食べ物や土産物などが売っていていい感じだ。 |
 |
「ひし」の実が売られていた。子供の頃に食べたことがあるが、最近日本ではあまり見かけない。ホクホクした芋のような味だったと思う。 |
 |
橋の上で「LiMe」の人文字を再現。 |
 |
昼食。韓国のグループと同席。医生研グループだけがビールを飲んでいる。 |
 |
古物商の店で見つけた水タバコのパイプ。形に惹かれて、思わず購入した。5000円くらいした。後にネットで調べたら、メルカリなどで2000円くらいで売っているようだった。 |
 |
帰り道の途中で、水が湧いているところを見かけた。この水路の水が不自然なほど透明だったのは、ここから綺麗な水を流しているという事のようだった。 |
 |
空港で買ったお土産。左から、鴨の砂ずり、鴨の舌、鶏の脚。どれも美味しかった。 |
2025年10月24日(金)
医生研ES細胞チームとリバーセルの打ち合わせ
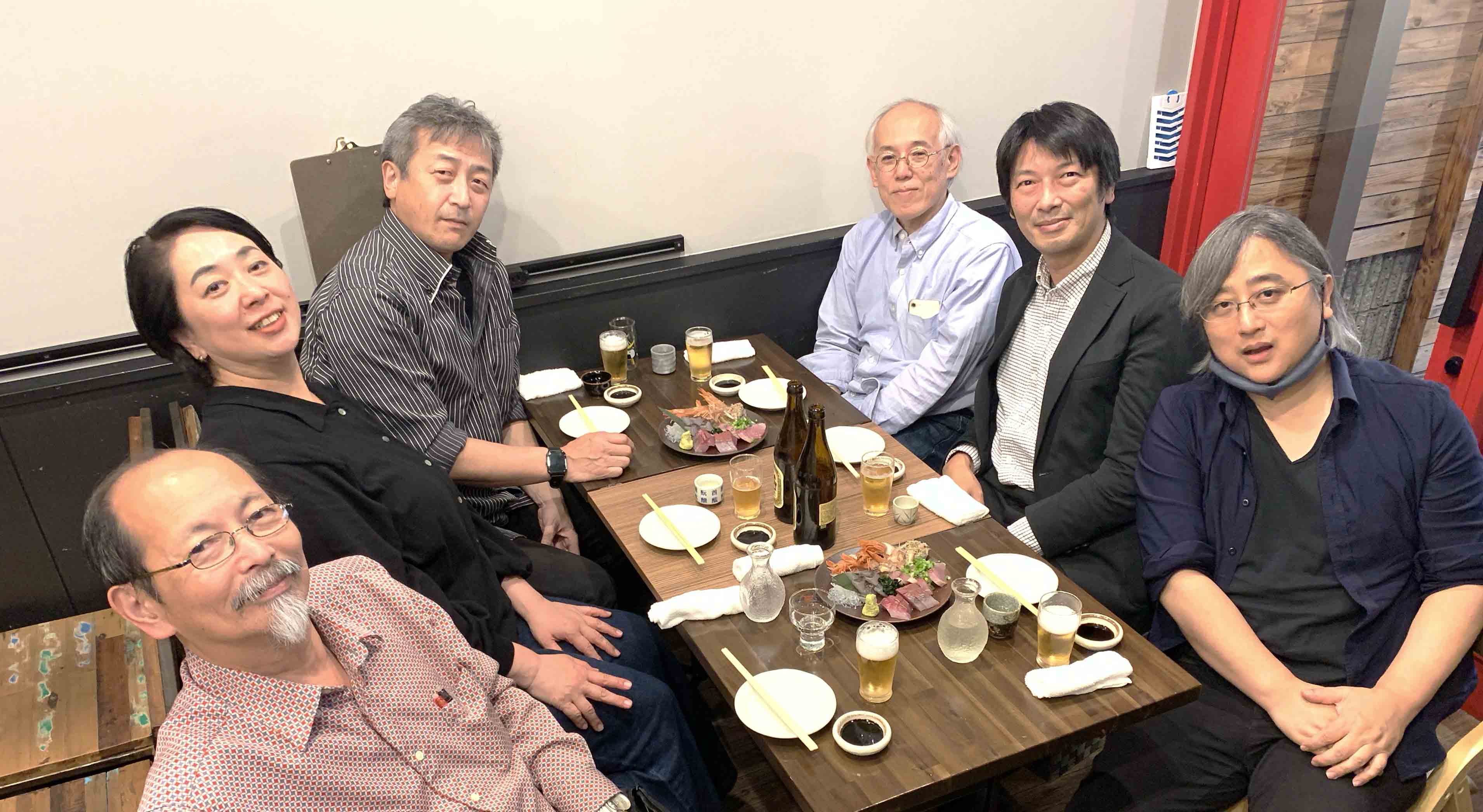 |
この日、医生研が提供している医療用のES細胞が産業にどう貢献できるかについて、ES細胞製造に関わるスタッフと、事業化を引き受ける可能性があるリバーセル株式会社の関係者で、話し合いの場が設けられた。その後、近くの「くうかい」で、一献を交わした。 |
2025年10月23日(木)
中日新聞の四方さん
 |
この日は中日新聞の四方さつきさんの取材に応じた。今回の坂口先生のノーベル賞の業績の出発点は、愛知県がんセンターの西塚泰章先生の研究だったので、「今回のノーベル賞は中京圏の成果」とも言えよう。 |
2025年10月21日(火)
高齢者大学で講義
 |
大阪には大阪府高齢者大学校」という認定NPO法人がある。シニアの方々に生涯学習の場を提供する認定NPO法人で、通称は「コーダイ」。生徒は2000人くらいで、昨年の4月には、大阪国際会議場で開催された入学式で講演をさせて頂いた(2024年4月8日の記事参照)。この日は通常の講義で、会場は鶴橋の大阪市助産師会館。 |
 |
今回はノーベル賞を記念して、制御性T細胞についての解説を入れた。また、万博について、5回分の訪問記をレポートした。 |
 |
鶴橋は、焼肉もいいけど、韓国情緒が溢れる商店街が、とてもいい感じだ。 |
2025年10月19日(日)
京大の学童保育Kusukuでお話し
 |
京都大学が教職員や学生のために開設した学童保育所「KuSuKu」。かつて京大会館と呼ばれていた建物が使われている。ここでは京大の教員や元教員が講師を務める「アカデミック・プログラム」と呼ばれるイベントが、毎日のように開催されている。私は、今回は2回目(2024年7月25日の記事参照)。前回は澄田先生と二人だったが、今回は一人。平日だったが、今回は日曜日。日曜日は生徒さんはやや少なく、前回は20人以上だったが、今回は11人で、全員が小学校低学年。持ち時間は1時間半。 |
 |
この日はこの絵を見せて、細胞人形を使って「この絵のように並べましょう」という作業をしてもらった。 |
 |
この細胞人形は、万博での展示に合わせ宮武さんが作ってくれたもの(2025年6月24日の記事参照)。 |
 |
ちゃんと並べてくれた。 |
 |
次に、もうちょっと簡単な絵を題材にして、描いてもらった。 |
 |
子供達は絵を描くのが好きで、皆熱心に描いてくれたが、今回気がついたのは、子供達は絵を描くのがかなり遅いという事。15分くらい描いてもらった。 |
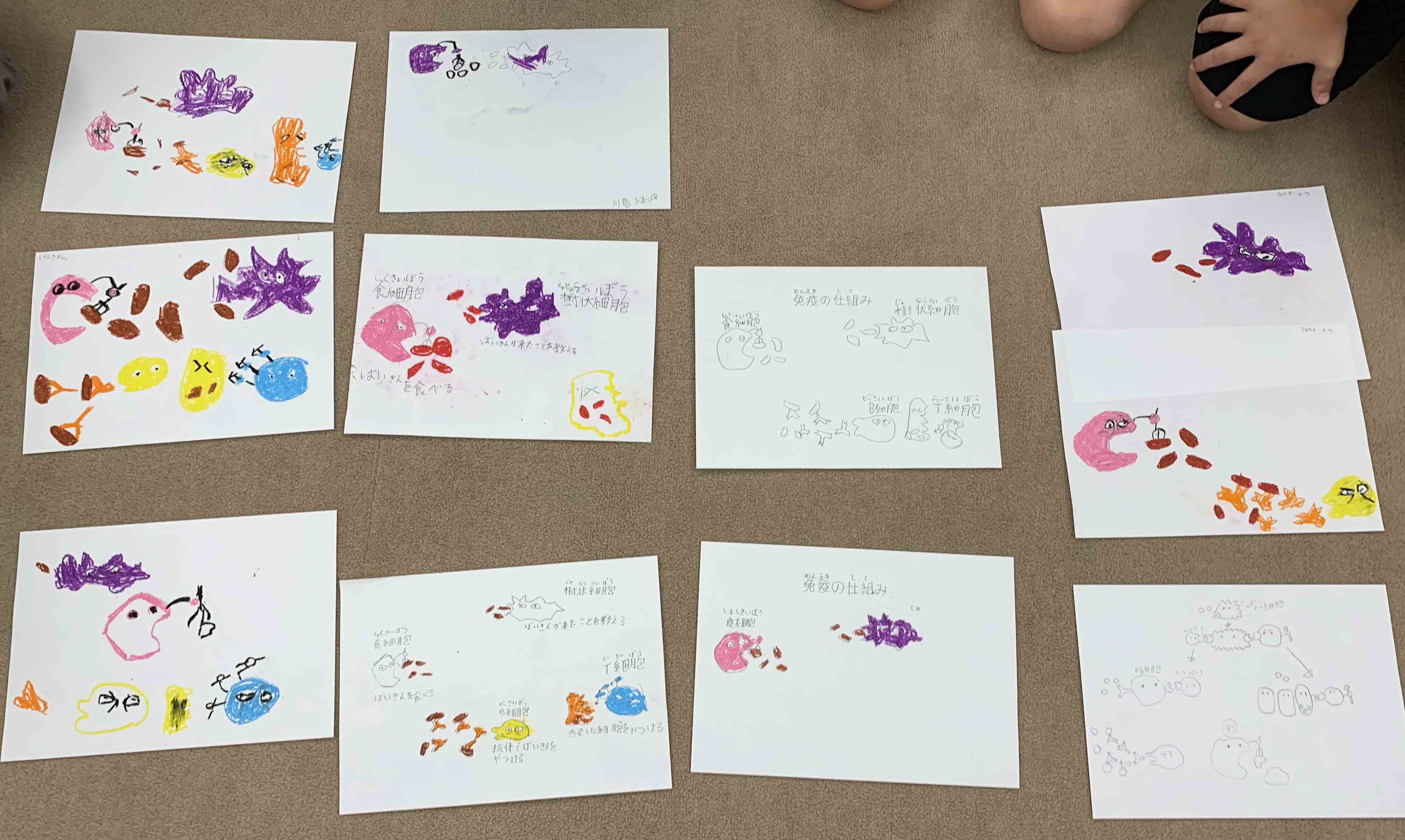 |
力作揃いだ。 |
 |
最後に、私がギターを弾いて、皆にリンパ節一人旅のサビの部分を歌ってもらった。その後、記念写真。 |
2025年10月14日(火)ー15日(水)
医生研リトリート
 |
昨年のリトリートは大津プリンスだった(2024年9月2日の記事参照)が、今年のリトリートは淡路島の淡路夢舞台で開催された。バンドメンバーは演奏用の機材を運ぶため車で移動。明石大橋を望むサービスエリアで休憩した。 |
 |
向かって左から、稲井早希さん (今吉研/生命M2)、石川芽依さん、(今吉研/生命M2)、髙橋くるみさん (今吉研/生命M2)。稲井さんと石川さんが食べているのは、玉ねぎとすり身を使った「ととたまスティック」(430円)。 |
 |
機材の搬入用の入り口付近。 |
 |
セッティング。モニターも完備。メンバーの持ち寄りであるが、自前でこれだけ揃えられるのはすごい。 |
 |
会場。今回の参加者は、昨年に続き150名超。 |
 |
午後の講演で、坂口志文先生が、ノーベル賞受賞後初となる講演を、このリトリートでされた。左の写真は、医生研チャンネルで坂口先生のインタビュー動画を載せた回(下記参照)の冒頭部分に出てくる、リトリートでの坂口先生の入場のシーンのキャプチャー画像。 医生研チャンネル:「坂口志文先生ノーベル賞受賞」記念特番 受賞4日後!坂口志文先生独占インタビュー+医生研坂口研究室 現役、OBインタビュー: |
 |
坂口先生の講演。制御性T細胞の発見に至った経緯や、その免疫学における意義などについての、重厚な話だった。 |
 |
ポスター発表の時間の前に、参加者で記念写真。 |
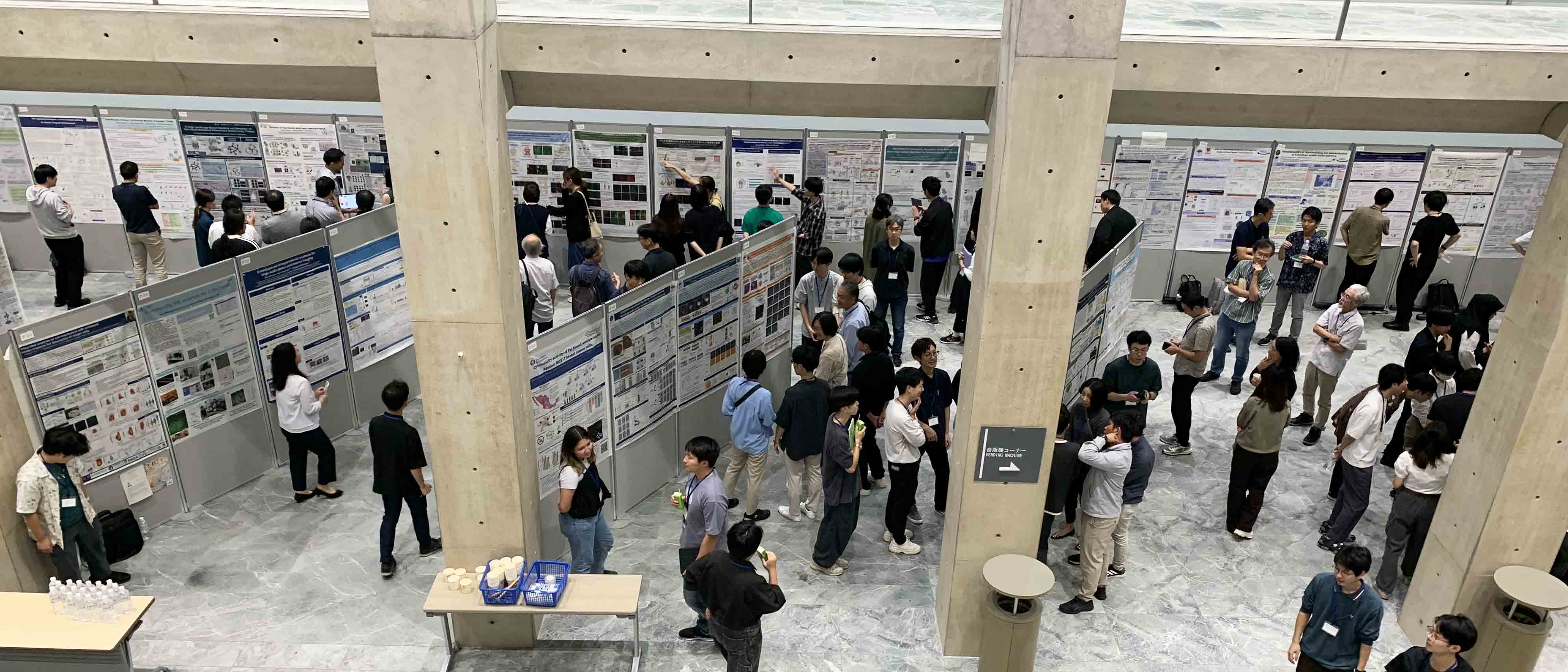 |
リトリートのメインイベントは、参加者のほぼ全員がポスター発表をする事で、これにはじっくりと時間がとられている。 |
 |
懇親会。 |
 |
永田和宏先生(JT生命誌館館長)による挨拶。 |
 |
河本研関係者と、坂口先生、永田先生との記念写真。 |
 |
会の半ばで、坂口先生からの若手へのエール。 |
 |
出番に備えるメンバー達。 |
 |
今吉先生が坂口先生に「このベースにサインを」と懇願。 |
 |
突然の依頼にもかかわらず、坂口先生は「2025年ノーベル生理学医学賞坂口志文」とサインをして下さった。「メルカリに出すのでは」というヤジが飛んだりした。このベースは、医生研1号館の所長室にケースに入れて陳列する予定。 |
 |
ライブが始まる。坂口先生、永田先生は最前列で聴いて下さった。 |
 |
最初の曲は後藤哲平先生(野々村研講師)によるB’z の「Love Phantom」。 |
 |
この曲のギターはかなり難しく、岡田優真さん (今吉研/総人B4)がリードをとってくれた。京大の軽音でもバンドをやっているとの事で、とても上手だった。ドラムは谷本佳彦先生(中台研助教)、ベースは今吉格先生。 |
 |
ギターソロの部分では私もツインリードのような形で絡んだ。 |
 |
2曲目は「残酷な天使のテーゼ」。歌は遊佐宏介先生と石川芽依さん(今吉研/生命M2)。キーボードは髙橋くるみさん (エバ2号機の装束、今吉研/生命M2)と 稲井早希さん (アスカの装束、今吉研/生命M2)。 |
 |
「ノーベル賞学者に、コスプレでのアニソン演奏を、“推しうちわ”を持って聴いていただく」という、シュールな写真。 |
 |
3曲目はMoon Childの「Escape」。歌は遊佐先生と谷本先生。 |
 |
4曲目で新宅博文先生が登場。「坂口先生、ノーベル文学賞、おめでとうございます!」というボケをかましたところ、谷本先生が「ちゃいますよ!ノーベル平和賞ですやん!」とたたみかけた。その後、二人で土下座。 |
 |
新宅先生と谷本先生でウルフルズの「ええねん」。歌詞カード表示役は峯岸美紗先生。 |
 |
アンコールで、新宅先生と谷本先生による西城秀樹の「ヤングマン」。 |
 |
「Y・M・C・A」という歌の部分を「L・I・M・E」と替える際に、新宅先生と谷本先生による「君はうちの研究所の略称を知らんのか。これや!」「えー、LiMeって書いてあるー!」というやりとり。笑えた。 |
 |
新宅先生が次々と多くの先生を引っ張り出して「L・I・M・E」をやってもらい、ついには、永田先生までも巻き込んだ。永田先生、突然のむちゃぶりにもかかわらす、対応していただき、誠にありがとうございました! |
 |
最後は、「L・I・M・E」で大合唱。今回のリトリートの世話人が登壇。 |
 |
ライブ終了後、記念撮影。 |
 |
バンドメンバーでの記念撮影。楽しかった! |
 |
メタ爺の推しうちわを作ってくれた人達と。ありがとうございました! |
 |
秋吉研の大学院生のLi Mingさんと。裏医生研チャンネルのファン、との事だった。 |
 |
懇親会終了後も、23時ごろまで、フリーディスカッションタイム。 |
 |
最後までいた人達。 |
 |
その後も、部屋飲み。色々な話をした他に、PCをテレビにつないで、YouTubeのカラオケなども楽しんだ。両隣の部屋の人は、身内とはいえ、迷惑だったであろう。 |
 |
リトリート二日目、永田先生による講演。とてもいい話だった。 |
 |
ベストポスター賞。河本研の貝谷君が入賞。 |
 |
ベストプレゼン賞。 |
2025年10月13日(月)
Retreatでのライブに向けての前日練習
 |
この日、本番を想定しての練習を行なった。ギターアンプ、ベースアンプ、PAシステム、モニターなどの音響に関する機材は、個人の所有物を持ち寄っている。 |
2025年10月10日(金)ー12日(日)
日本血液学会に参加
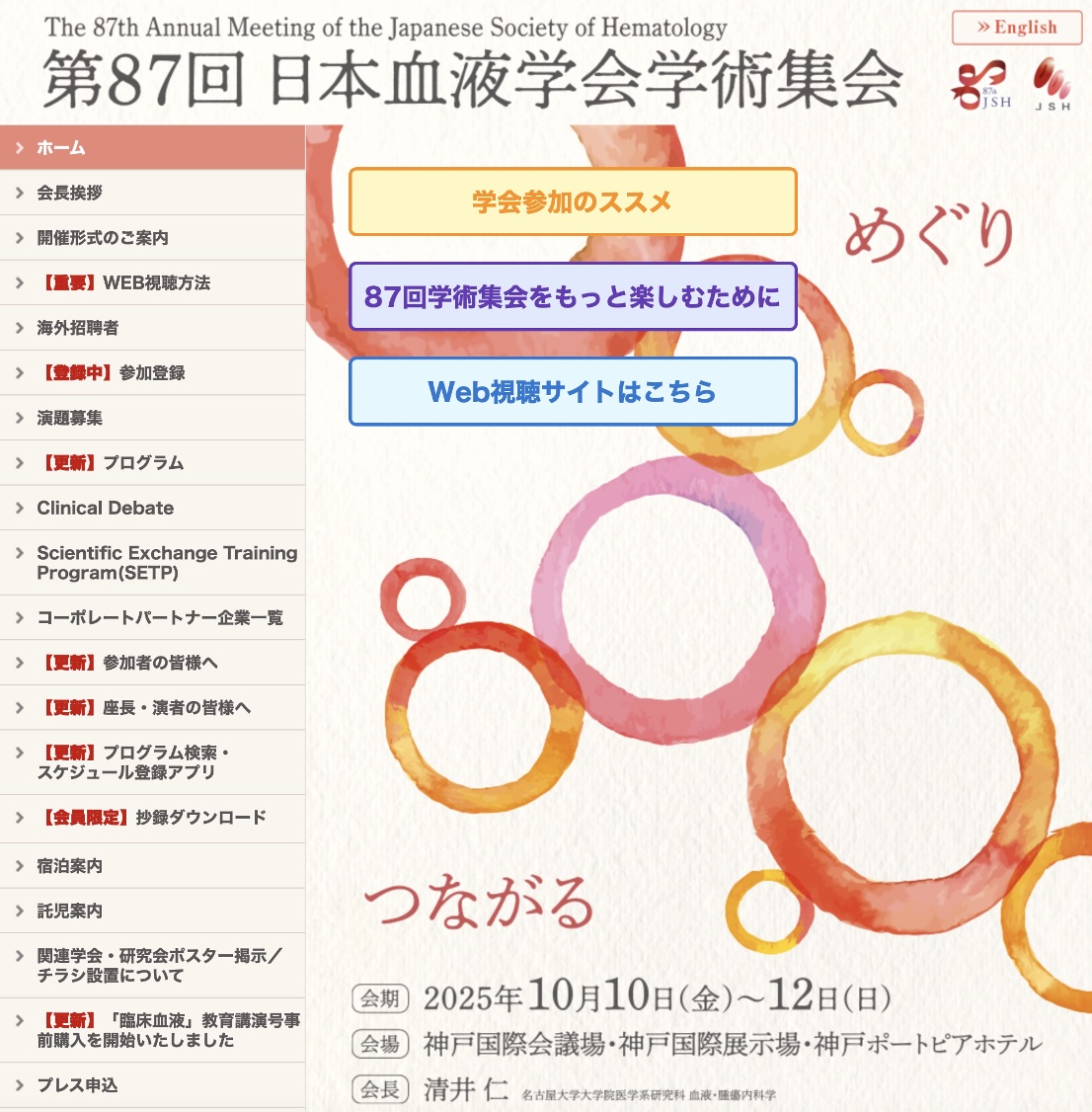 |
表記の会が神戸で開催された。キーヴィジュアルがなかなかfancyで、いい。 |
 |
今回はシンポジウムで話をするので、前日の会長招宴に参加。小川誠司先生(京大、向かって左)、千葉滋先生(筑波大学)と。 |
 |
向かって左から、保仙直樹先生(大阪大学)、須田年生先生(国家血液健康重点研究所)(天津)と。 |
 |
向かって右から、幸谷愛先生(大阪大学)、高折晃史先生(京都大学)、須田先生と。 |
 |
学会2日目。神戸国際会議場。 |
 |
ワークショップ会場の一つ。 |
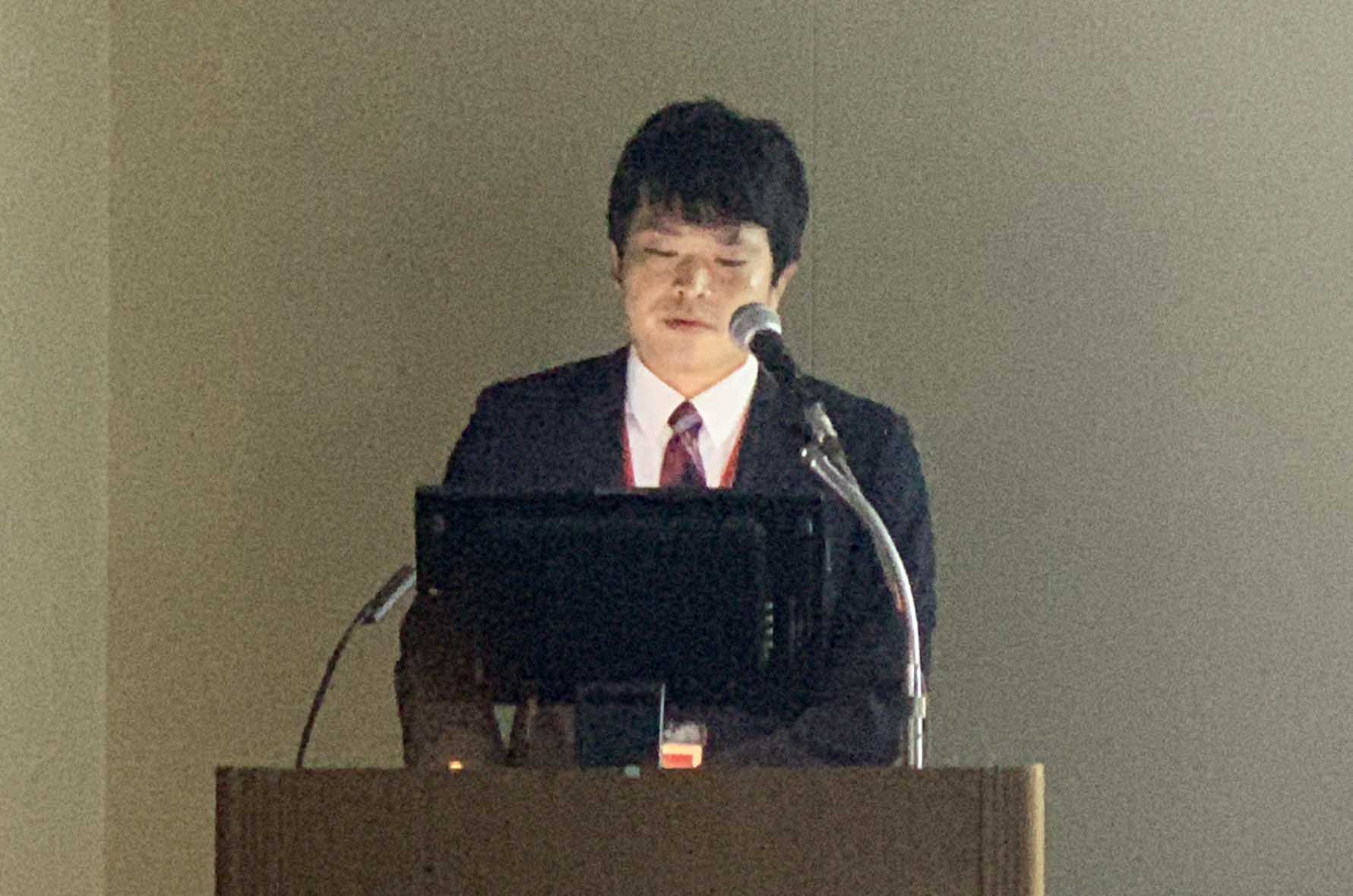 |
板原君が超汎用性技術について発表。 |
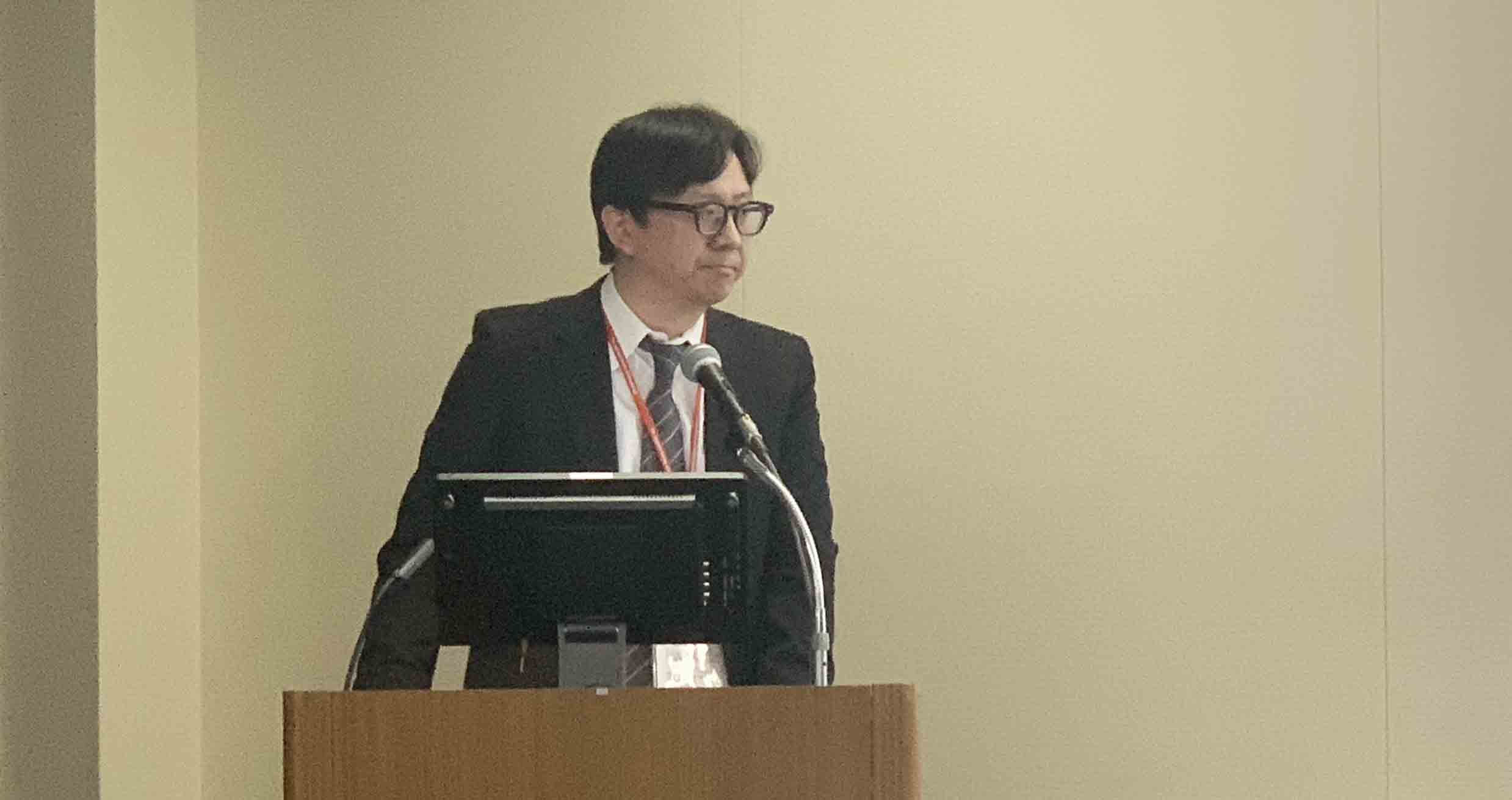 |
同じセッションで美山貴彦先生(藤田医科大学造血細胞移植・細胞療法学講師))も発表。新型コロナ特異的TCRのクローニングの話だった。 |
 |
藤田医大関係者と。向かって右から美山先生、稲本賢弘先生(藤田医大造血細胞移植・細胞療法学教授)、中村柚琳(ゆうりん)君(藤田医大医学部6回生)。 |
 |
展示スペースにはたらく細胞のコーナーがあった。坂口先生のノーベル賞を記念して「制御性T細胞さん」が前面に出されていた。 |
 |
この日の午後、私はシンポジウムで話をした。 |
 |
会場は、ポートピアホール。大きい。ここに登壇するのは久々で、前回はNegative Selectionとして近藤滋が企画された「2050年シンポジウム」という未来の分生を想定した6つのプレゼンの中の一つで登場した(2013年12月3日の記事参照)。 |
 |
懇親会。 |
 |
今回の集会長、清井仁先生による挨拶。 |
 |
今回の目玉の一つ、80kgのマグロの解体ショー。 |
 |
血液学会理事長の高折先生と清井先生によるマグロ入刀。結婚披露宴になぞらえて「初めての共同作業」と紹介されていて、面白かった。 |
 |
解体後。 |
 |
向かって左から板原君、山田大智先生(明石市民病院)、加覧(がらん)浩太郎先生(駒込病院)。山田先生と加覧先生は共に府立医大卒で、山田先生は軽音学部でうちの長男の先輩、加覧先生は水泳部での先輩とのこと。加覧先生は免疫学会サマースクールに参加されていた(2025年8月25日の記事参照)。 |
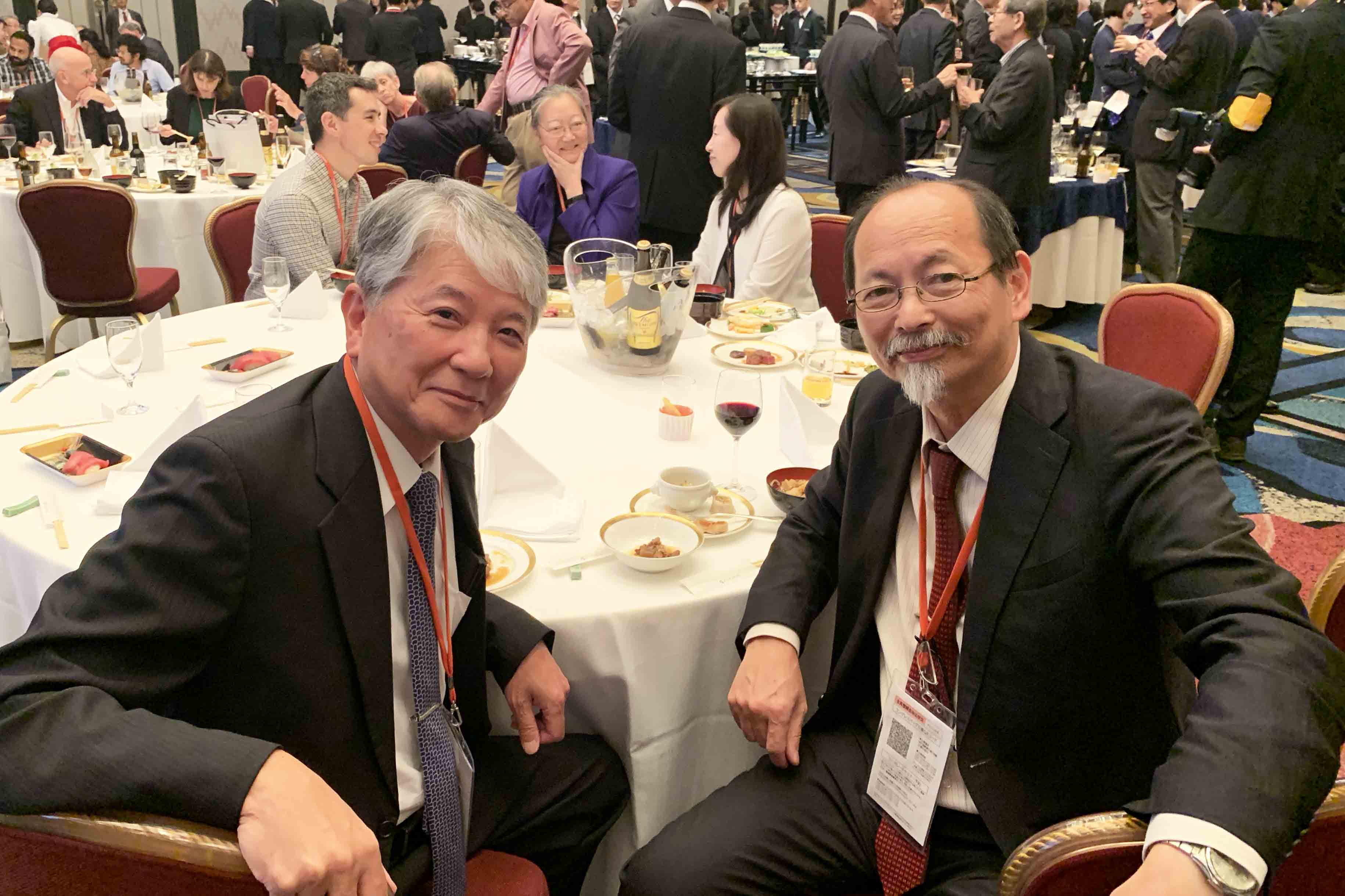 |
安川正貴先生(愛媛大学)と。現在河本研は革新がんの支援で急性骨髄性白血病を対象にした臨床試験の準備を進めているが、その中では安川先生らがクローニングしたWT1抗原特異的なT細胞レセプターを用いている。 |
 |
前田高宏先生(九州大学プレシジョン医療学分野教授)と。以前にT細胞分化に関わる転写因子LRF(別名Pokemon)の研究をされていて、私は理研時代に前田先生によるセミナーをホストしたことがある(2008年12月25日の記事参照)。 |
 |
安藤美樹先生(順天堂大血液学講座教授)と。安藤先生はiPS細胞から作製したT細胞を用いて子宮頸がんを対象にした臨床試験を進めている。我々はT細胞レセプターを遺伝子導入したiPS細胞を材料にしているが、安藤先生はT細胞由来iPS細胞を用いている。また、作製されたT細胞も我々が使っているT細胞とタイプが異なる。 |
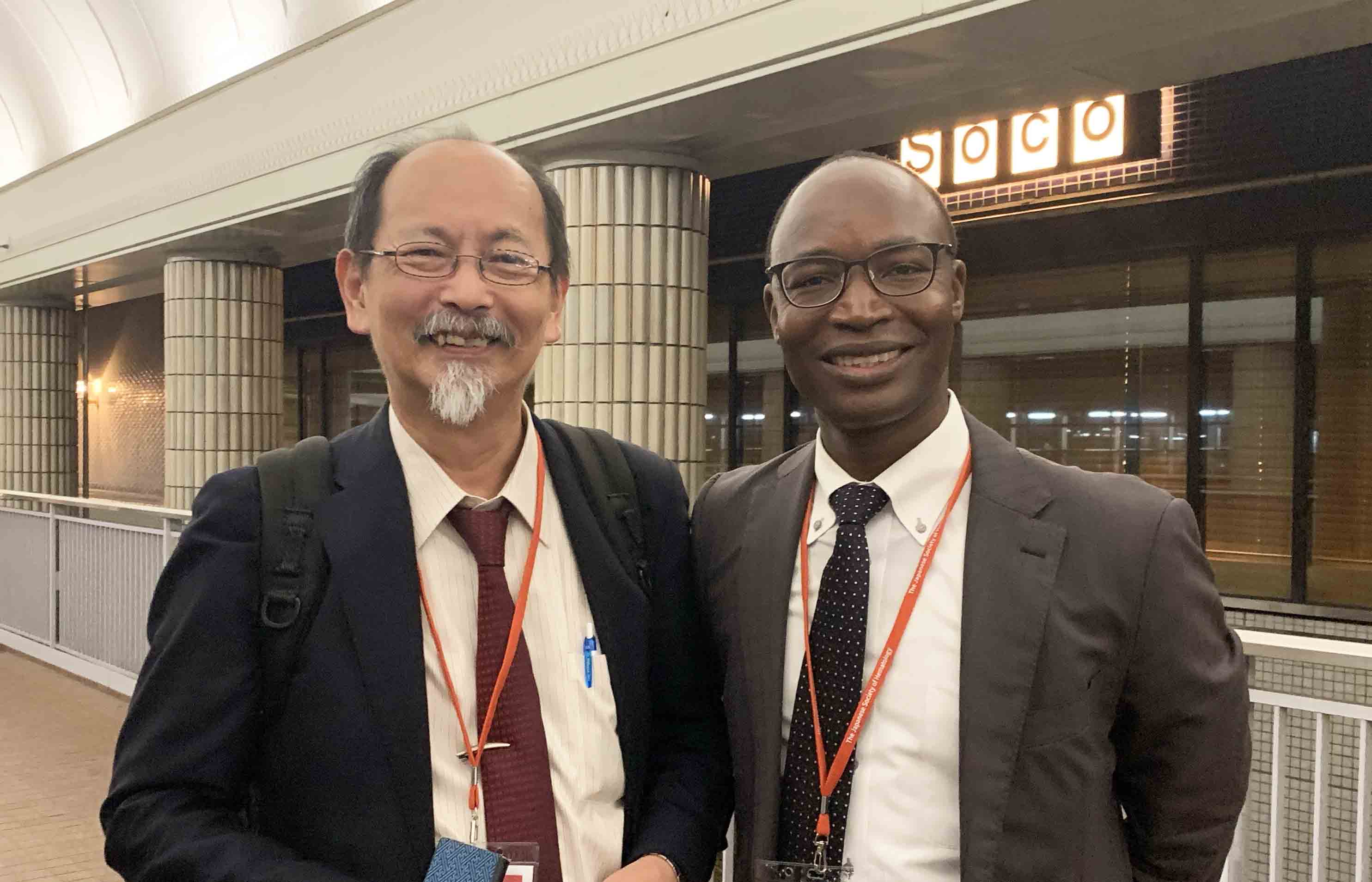 |
オケヨ・ケネディ・オモンディ先生(The Jackson Laboratory)と。少し前まで医生研の准教授を務められていた。 |
 |
三ノ宮で、増田さんも交えて、板原君のプチ慰労会。 |
2025年10月10日(金)
医生研チャンネル用に解説動画を作成
 |
この日の午後、坂口志文先生が医生研に来られたので、インタビューを敢行。 |
 |
10月24日に、医生研チャンネルにアップした。
「坂口志文先生ノーベル賞受賞」記念特番 受賞4日後!坂口志文先生独占インタビュー+医生研坂口研究室 現役、OBインタビュー: |
 |
医生研におられるお弟子さん達にも出演いただいた。まずは伊藤能永先生。 |
 |
廣田圭司先生とは、skgマウスが坂口研で発生した事について、失礼ながらと言いつつ、「持っている」という表現で意見が一致。 |
 |
川上竜司先生(特定助教)は、制御性T細胞への運命決定のメカニズムの研究について、「基礎的な理解が、安定な制御性T細胞の作製によって臨床応用に直結する、基礎と臨床を両輪で進めることが大事」という話をされた。大いに同意する。 |
2025年10月8日(水)
医生研チャンネル用に解説動画を作成
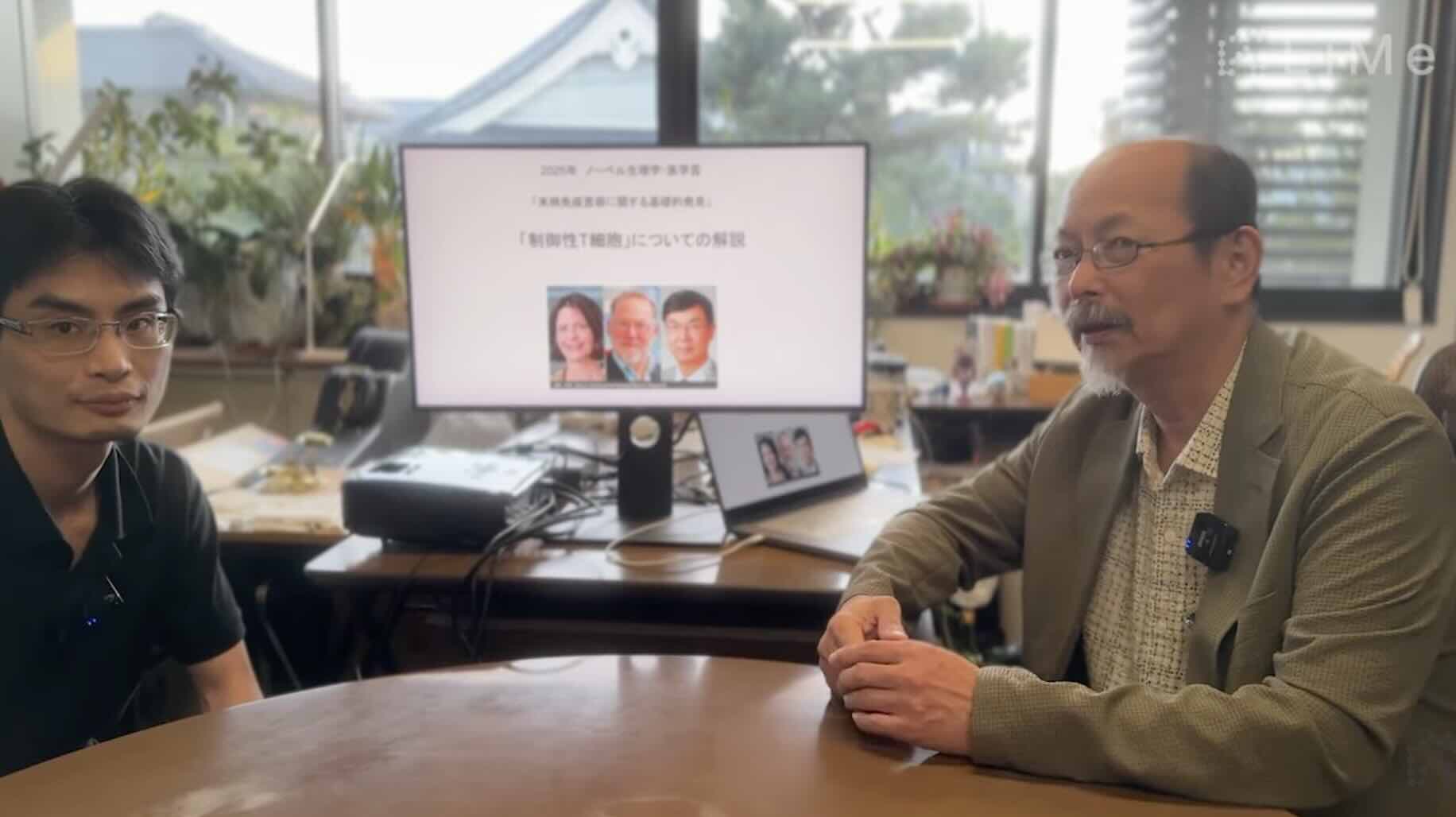 |
この日の夕刻、西村君に聴き手役をしてもらい、解説動画を収録。 |
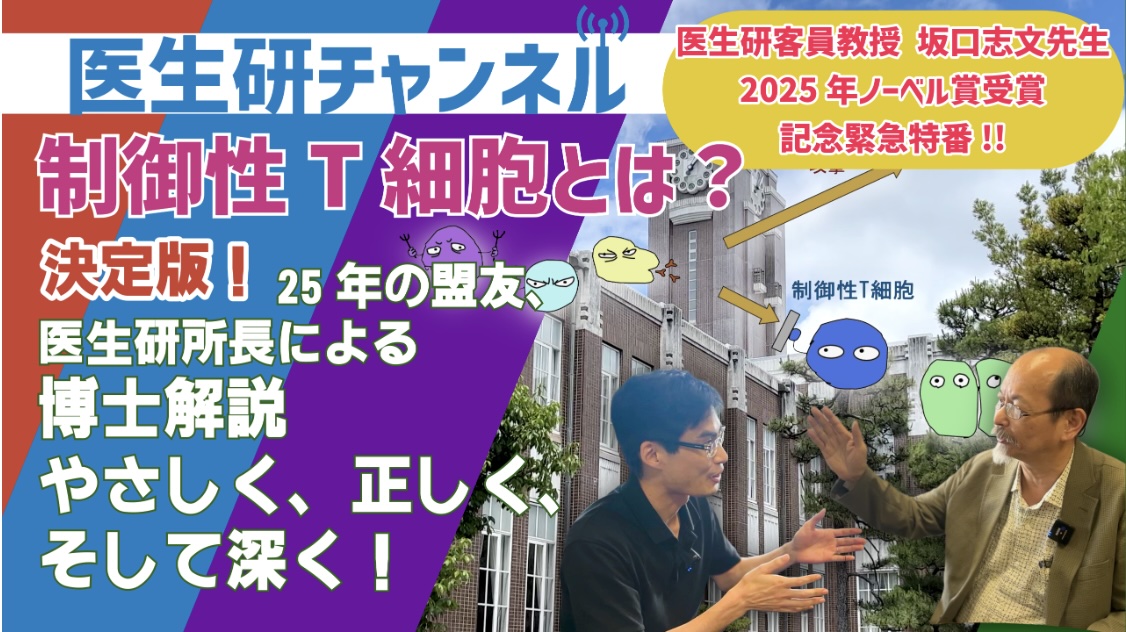 |
10月10日に、医生研チャンネルにアップした。
緊急特番「坂口志文先生ノーベル賞受賞」制御性T細胞とは? 決定版!25年の盟友医生研所長によるプロフェッショナル解説 やさしく、正しく、そして深く: |
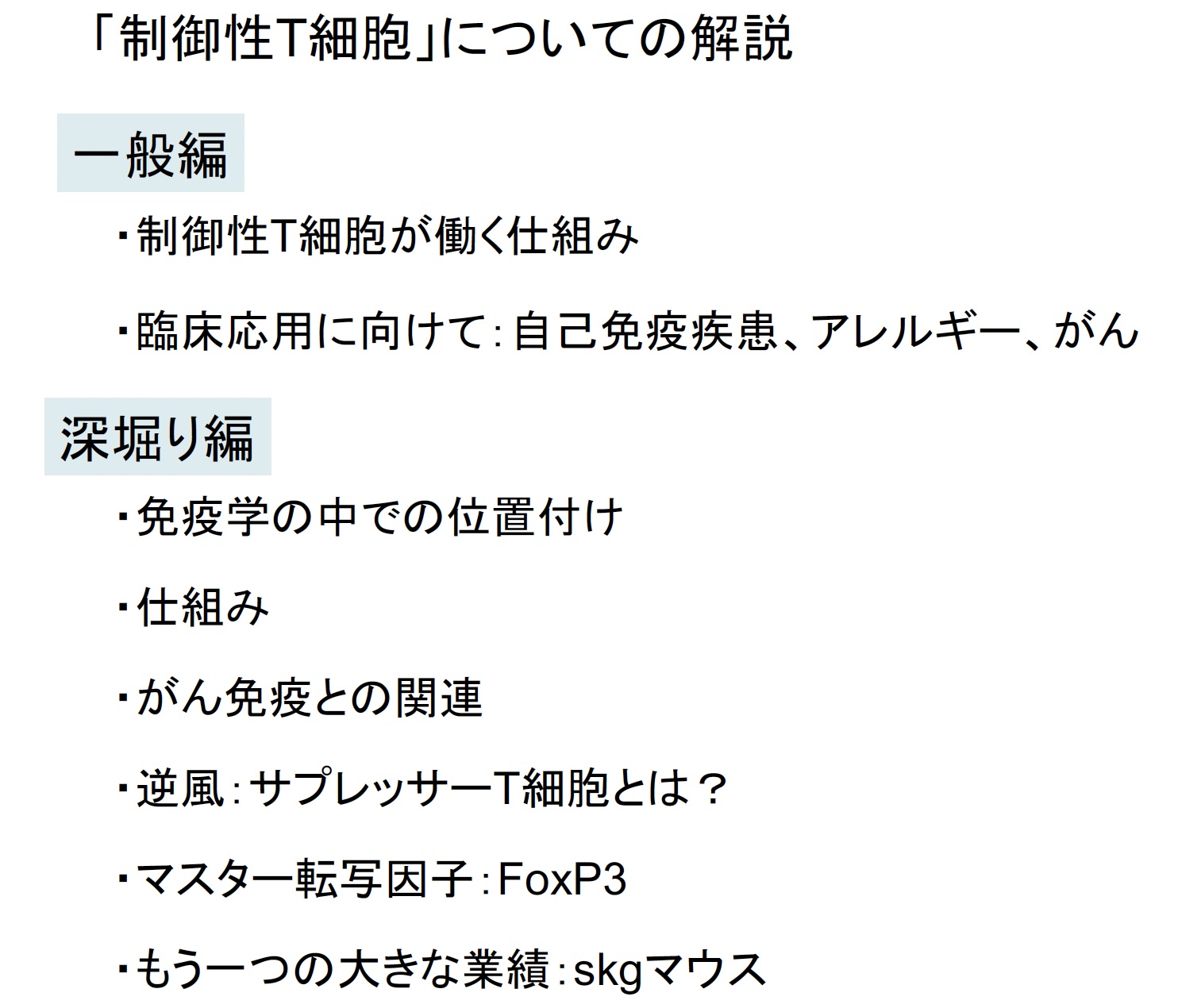 |
アップした動画の目次。 |
2025年10月7日(火)
「よんチャンTV」で制御性T細胞について解説
 |
毎日16時頃から2時間くらい続く毎日放送の情報番組「よんチャンTV」の冒頭に、「生出演」でノーベル賞についての解説をする事になった。その部分は切り取られて、YouTube動画として公開されている。打ち合わせの時に「私にとって坂口先生は大先輩で免疫学の師匠であるが一緒に会社を起こした時は同志という感じだった」という話をしたら、「盟友」という扱いになってしまった。ちょっと申し訳なく思う。
【ノーベル賞】滋賀出身の阪大・坂口志文特任教授は「揺るぎない信念をもつ研究者」逆風の中でも決して諦めず「こだわりのレベルが違う」 25年来の「盟友」が明かす人物像(2025年10月7日): |
 |
上記の「一緒に会社を起こした」は正確に言うとレグセルの起業の際に声をかけていた抱いたという事であるが、共同で創業したという形になっている。サクセスというクレスト絡みの支援事業から出資を受けた事に関する記事がこちら。 免疫難病やがんの細胞治療に挑む: |
 |
梅田茶屋町の毎日放送局のビル。 |
 |
「よんチャンTV」の看板。 |
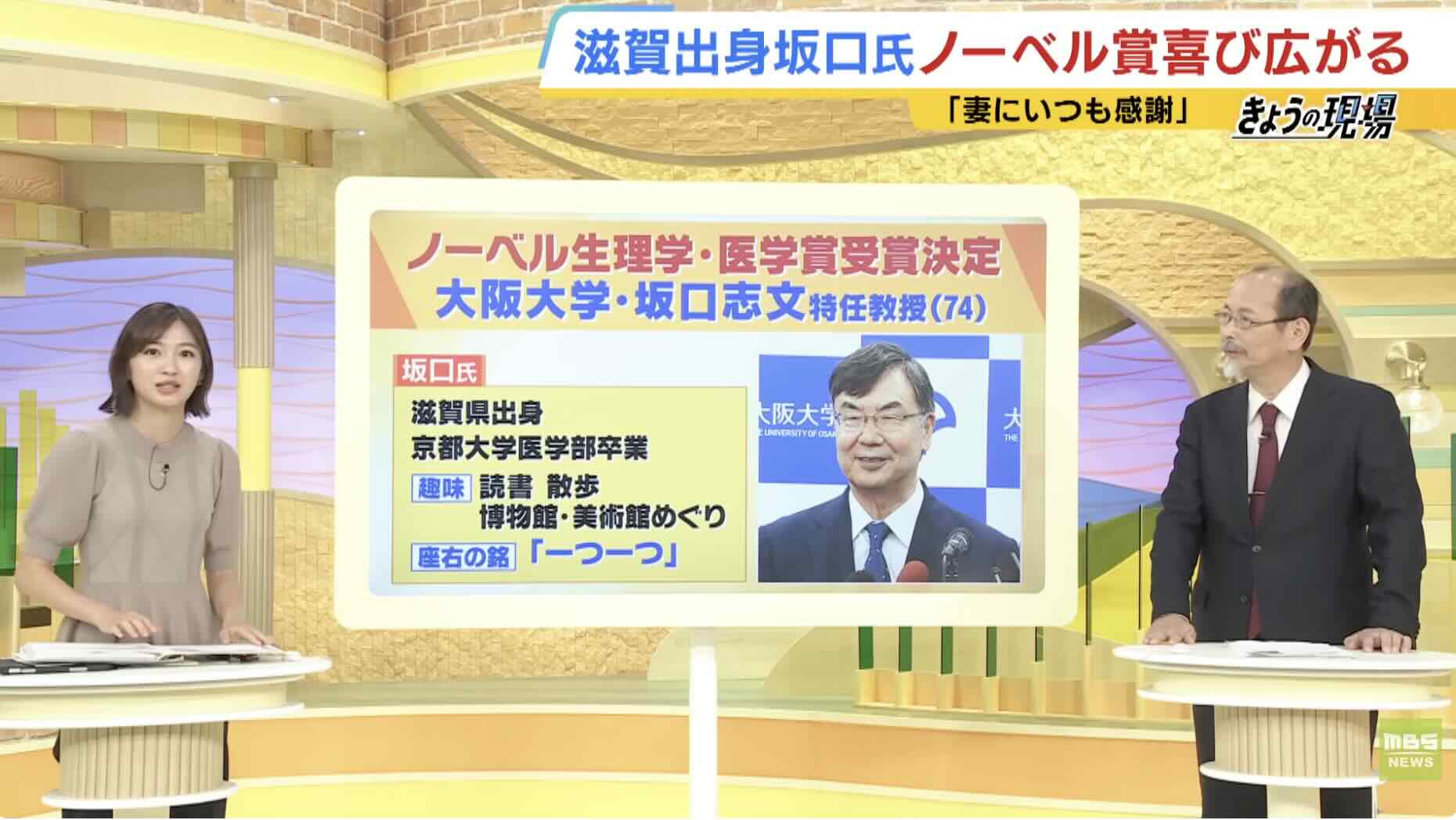 |
ナビゲーターは海渡未来アナウンサー。まずは坂口先生の人柄について。私は、散歩がお好きで、哲学者風、と紹介した。 |
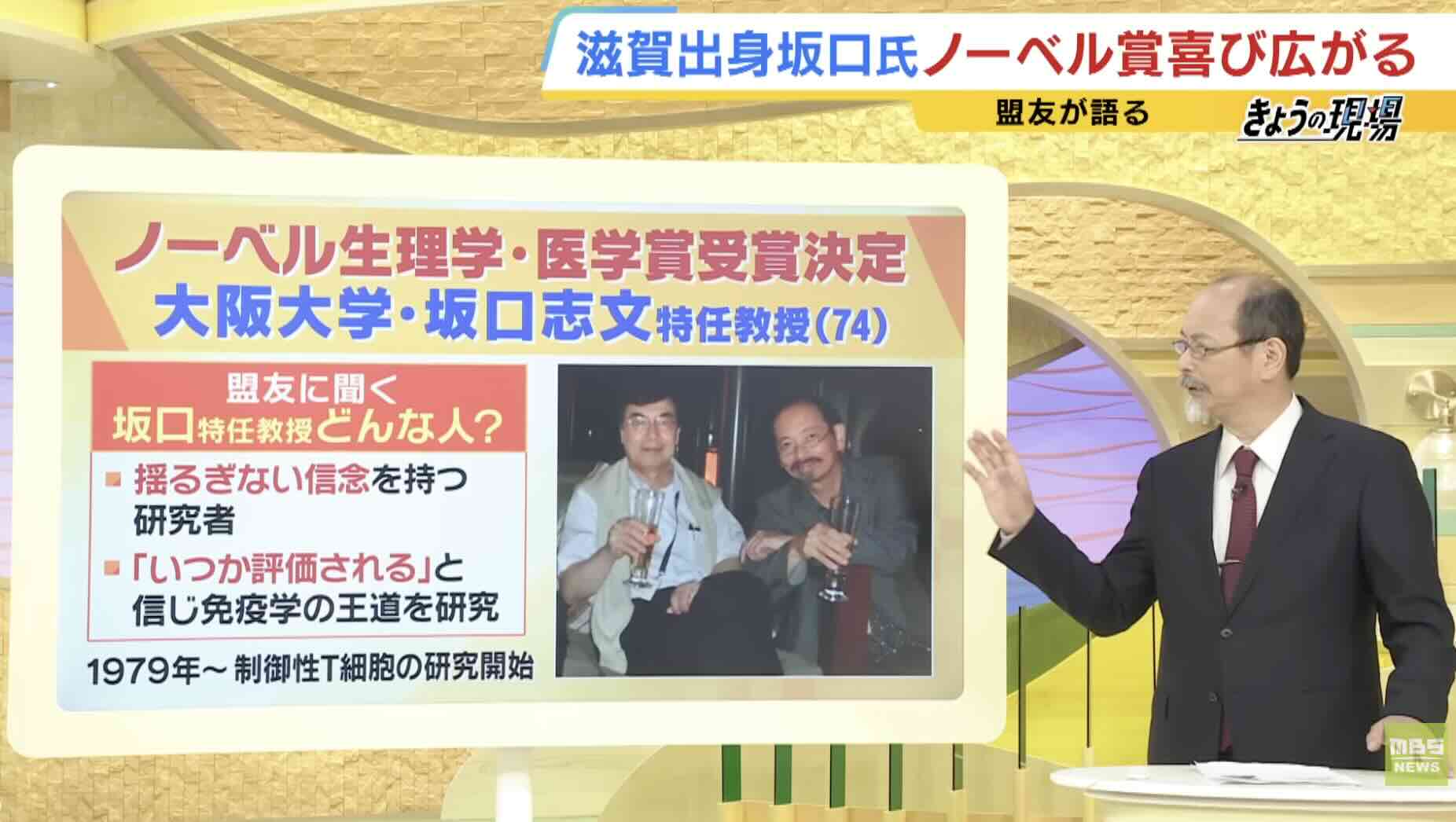 |
次にこの発見がどうすごいかを解説した。自分を攻撃する悪い細胞は、胸腺で作られる過程で除かれるという仕組みがまず証明された。皆がそれで納得してしまっている中で、「それでは説明ができない。末梢で抑制する仕組みもあるはず」と一人で挑み続けた、と解説。 |
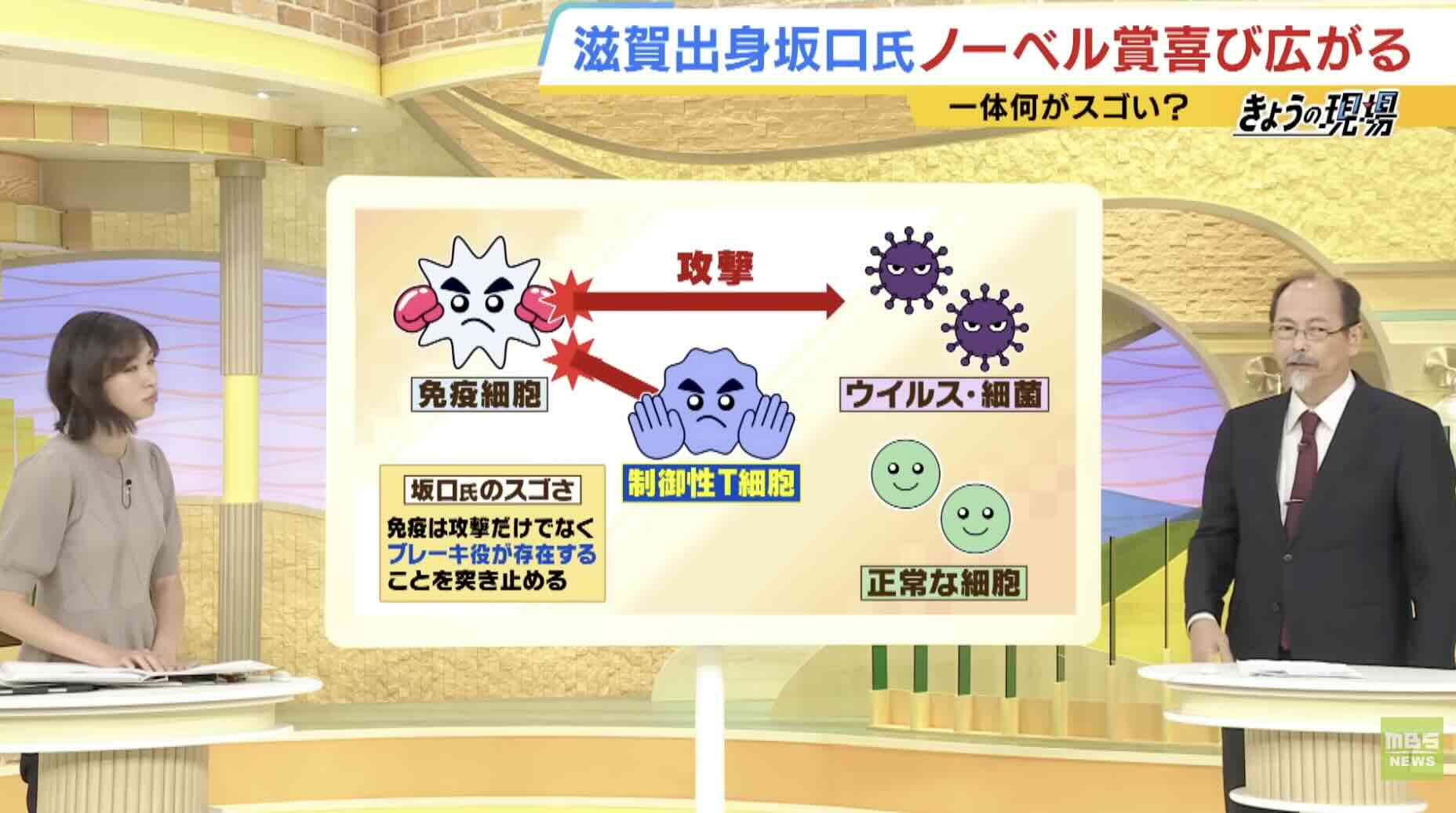 |
働く仕組みについては、海渡さんが説明をして、私は、はい、それでとても正しいですと、追認。「病原体に対する免疫が暴走して正常細胞も攻撃してしまう」と説明されたら、「ちょっと違う」と言おうと思っていたが、「免疫細胞の中には自分を攻撃してしまう細胞も混じっている」「制御性T細胞はそういう細胞を抑制する」と、正しく解説された。 |
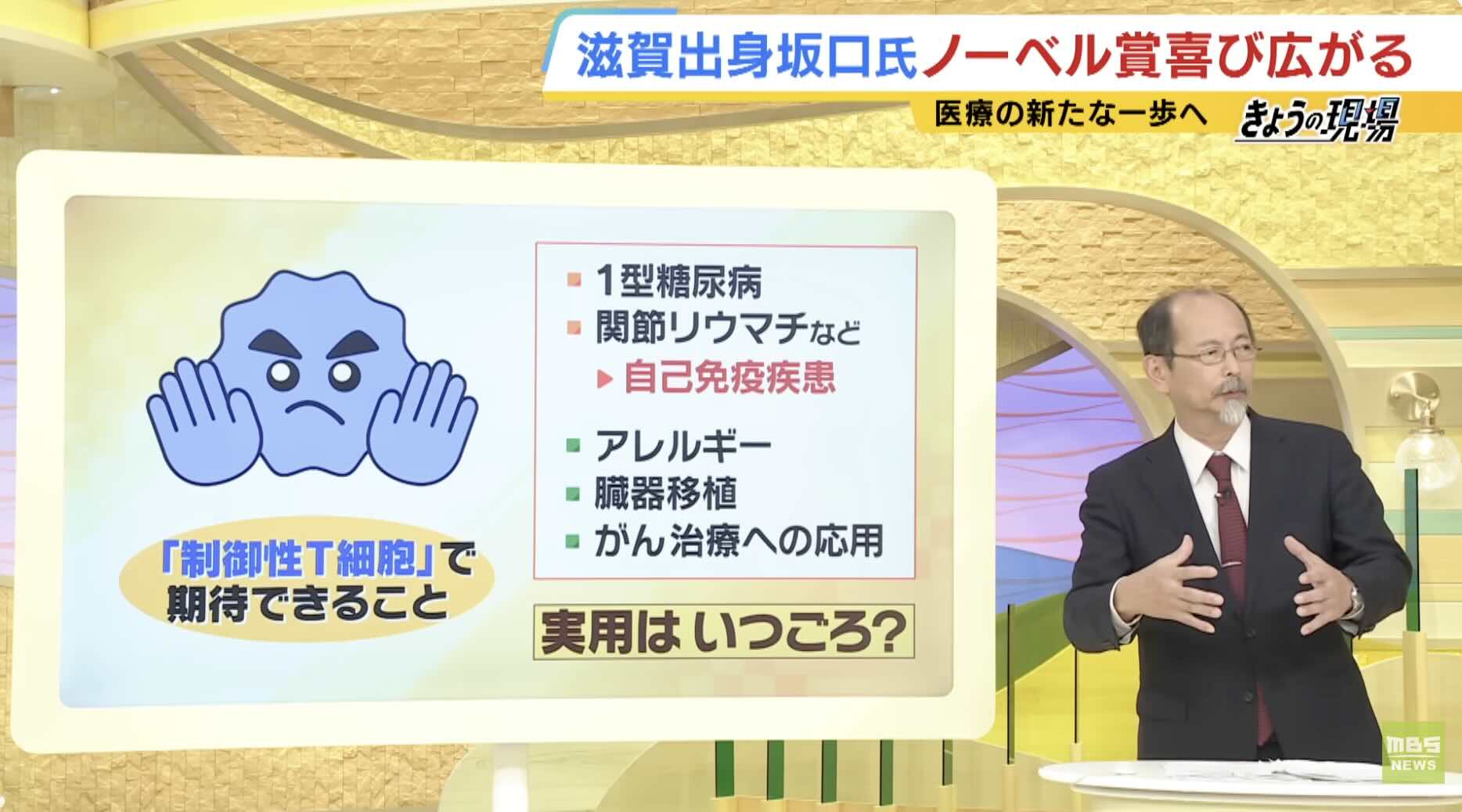 |
医療への応用については、「これまでの漫然とした免疫抑制ではなくて、悪さをする細胞だけを抑制する、次世代型の治療が可能になる」と解説。最後に、ストックホルムに行かれるのですかと訊かれ、自分が会長を務める学会があるので、残念ながら行けませんという話をした。 |
2025年10月6日(月)
坂口志文先生、ノーベル賞!!!
 |
この日の夕刻、Moffitt Cancer Centerの人達との面談の後、17時頃からリトリートに向けたバンド練習をした。18時半からはノーベル生理学・医学賞の発表があるので、一旦練習から離れて、近くの今吉先生の教授室で、YouTubeのライブ配信を観た。毎年、いくつかの新聞社から、「もし坂口先生がノーベル賞を受けられたら、コメントを下さい」と言われているので、生理学・医学賞の発表だけはライブで観る事にしている。見始めてまもなく、スウェーデン語で、人の名前を呼び出して、最初の二人はよく知らない人だったから、「ああ、今年もないか」と思っていたら、「シモン・サカグチ」と聞こえてきて、「え?え?今吉先生、今、シモンサカグチって言ったよね?」と言って今吉先生と顔を合わせた。 |
 |
言っている間に、画面上に名前の文字が現れた。その文字列を見た時に、ゾクゾクっと震えが来て、「これはえらいことだ」と思った。毎年候補に挙がっておられるし、いつかは必ず来るとは思っていたが、実際に身近な人の名前が、ノーベル賞受賞者として呼ばれる瞬間をリアルタイムで観ると、すっかり気が動転してしまった。今吉先生に「先生、楽器は後で持っていきますから、とりあえずご自分の教授室にお戻り下さい」と促されて、まずは教授室に戻った。すぐに読売新聞や共同通信の人が「今、時計台にいますが、そちらに向かいます」と連絡があった。 |
 |
受賞者3人の写真と名前。恥ずかしながら、左の2名の名前は知らなかった。だから、始めは、「どういう文脈?」と、とても不思議に思った。解説を聴いて、そうかIPEX症候群の遺伝子(FoxP3)を同定した人達か、と納得した。なお、坂口先生は3番目に名前が出ているが、これは名字のアルファベット順。 |
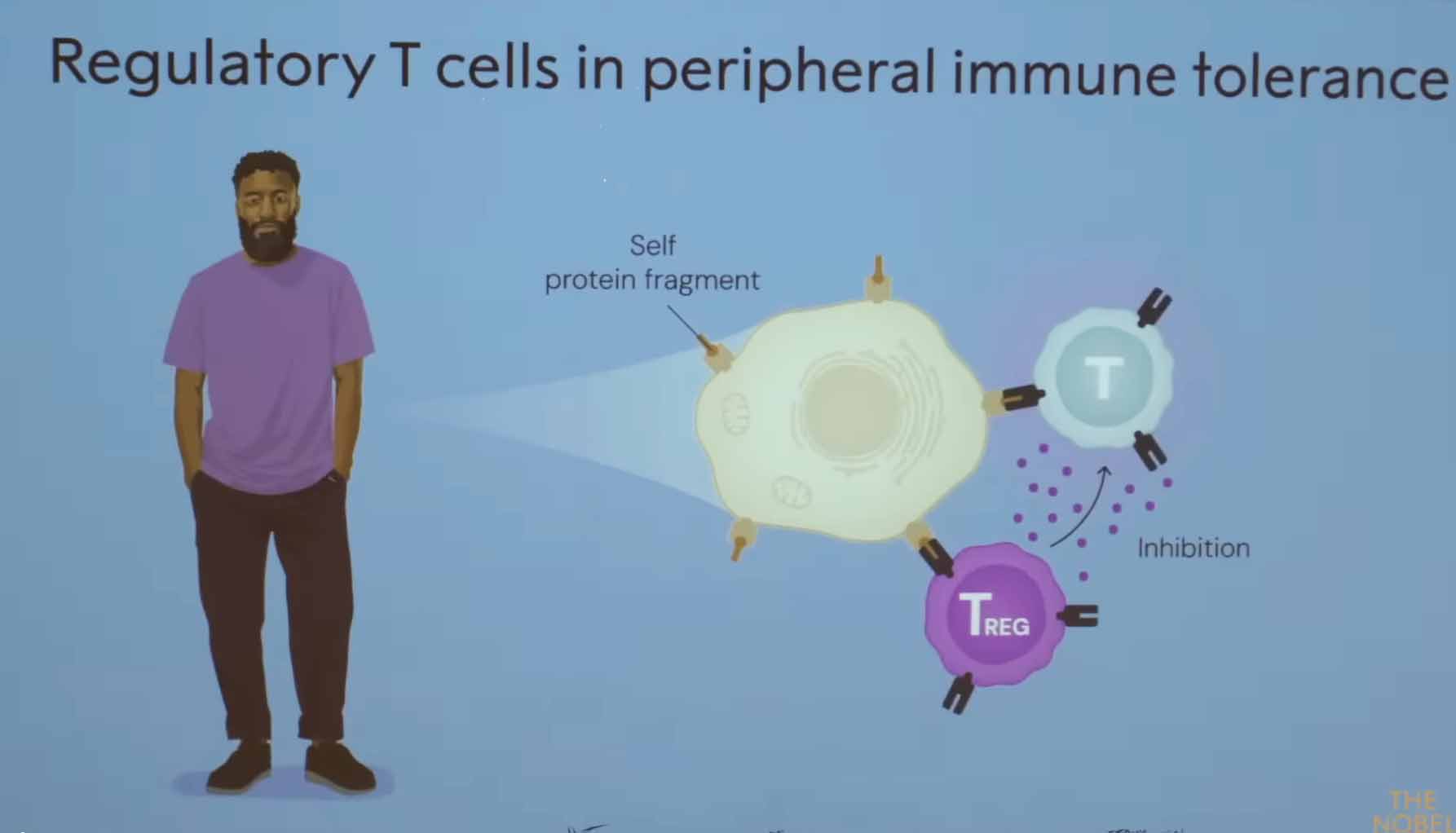 |
解説の中で使われた制御性T細胞が働く仕組みの図。あまり良い図解とは言えない。正く知りたい人は、医生研チャンネルに載せる解説動画をみて下さい。 |
 |
後に坂口先生から頂いた朝日新聞の号外と、読売新聞の人から頂いた読売新聞の号外。貴重だ。 |
2025年10月6日(月)
Moffitt Cancer Centerの人達と面談
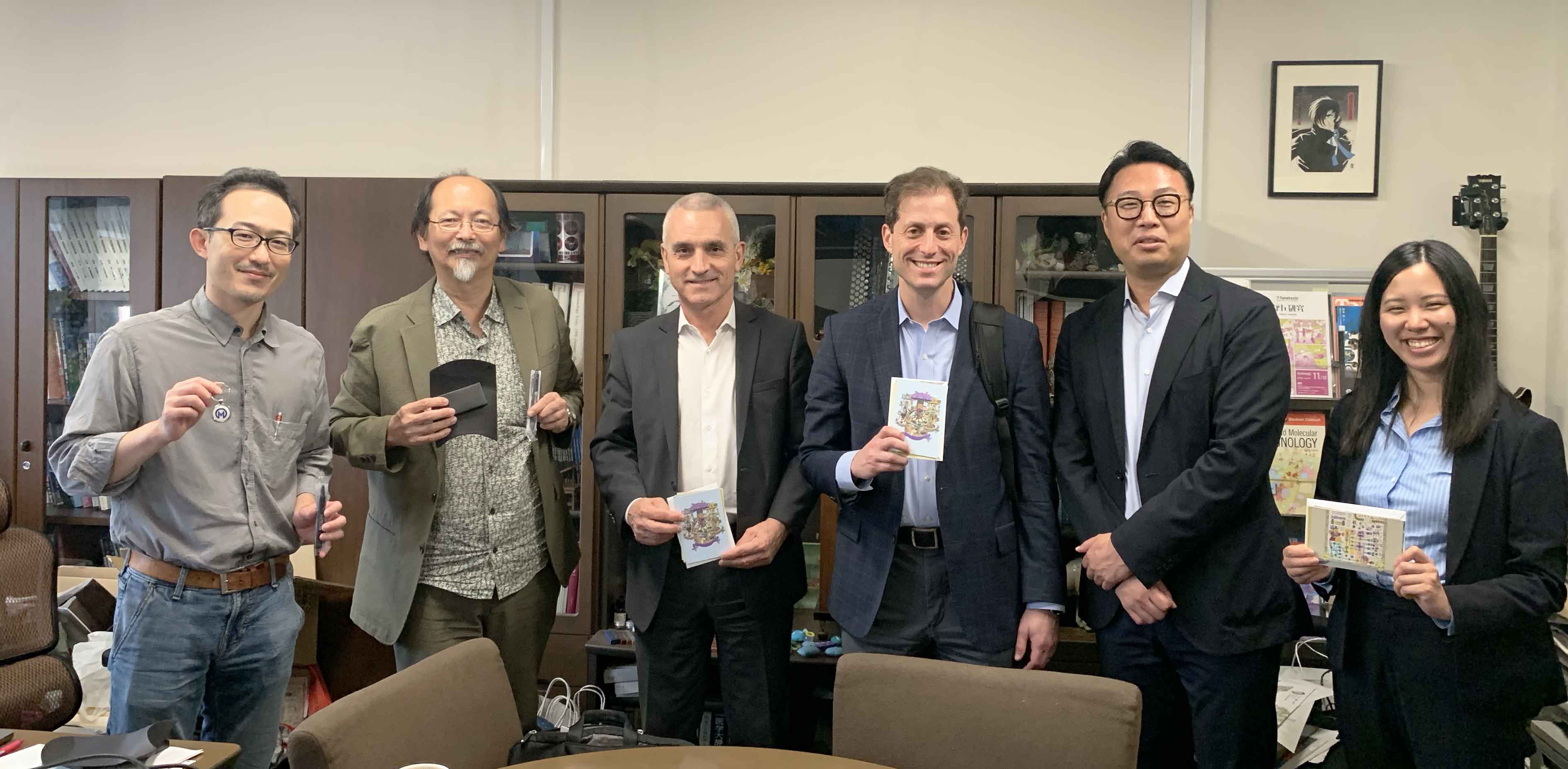 |
この日の夕刻、Moffitt Cancer Centerの方々と面談した。私の隣から順にXavier Avat氏(Executive Vice President & Chief Business Officer)、Jarett Rieger氏(Vice President, Business Development, Licensing, & Alliance Management)、三木 雄一郎氏(三井物産株式会社 ウェルネス事業本部 医療事業部 第三室 室長)、加賀若菜氏(三井物産株式会社 ウェルネス事業本部 医療事業部 第三室 マネージャー)。 |
2025年10月4日(土)
チームラボ京都の内覧会に参加
 |
チームラボは「チームラボ バイオボルテックス京都」を、10月7日に開業する。ある関係筋から、開業前の内覧会に参加することができた。場所は、京都駅の八条口を出て少し東に行ったところ。写真は、最初の部屋。プロジェクションマッピングであるが、壁に触れると、反応して動きが変わる。 |
 |
国内では、常設展示施設が豊洲と麻布にあり、これが3箇所目とのこと。京都にチームラボの常設展示場ができるのは、ありがたい事だ。この幻想的なランプも、インタラクティブで、人の動きに反応して色が変わったりする。 |
 |
宙に浮く球体が渦を巻く。すごい。 |
 |
青い泡が渦巻く中を、防護服を着て進んでいく。雲の中に入っていくような感覚。実際に没入するので、高度な没入感が味わえる。 |
 |
長靴を履いて不思議な沼を歩く。 |
 |
水面には怪しい渦が蠢いている。 |
 |
本物の苔の床とオブジェの組み合わせ。 |
 |
それぞれのぶら下がった光球を、ぼやっと光る暈(かさ)が取り囲む。実際にはそこにそんなものは無いのに、あるように見えてしまう。こういうのが、チームラボの真骨頂であろう。 |
 |
きれいだ。 |
 |
こういうオブジェも、触るとそれに反応して色が変わったりする。 |
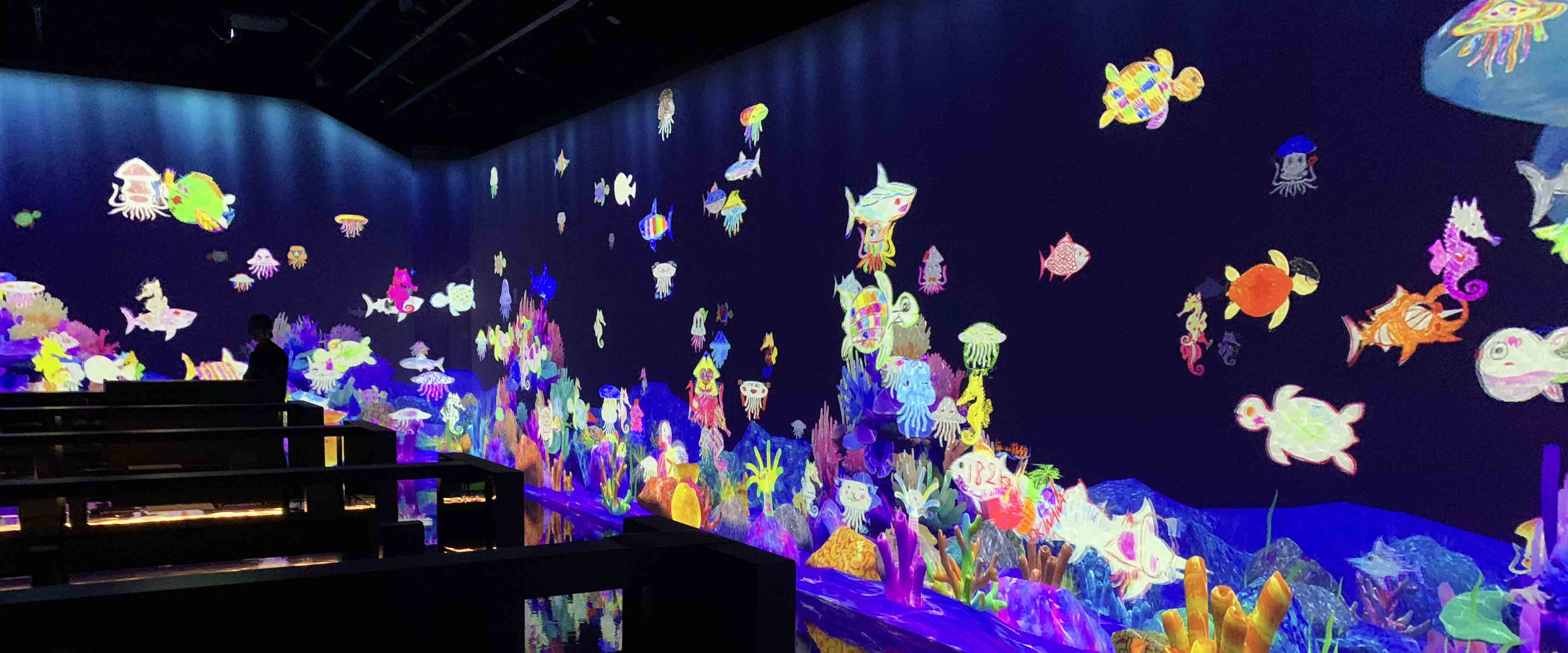 |
これは麻布にもあったもので、自分で魚、クラゲ、イカなどの絵を描いて、読み込んでもらうと、即座に画面に現れる。時々、海外も含めた他の展示施設に飛んでいくこともあるという。 |
 |
トランポリンなどのアスレチックがあるコーナー。細長いトランポリンのコースを、飛び跳ねながら進んでいくと、星の一生を辿れる。 |
 |
このバーの上を歩いていくことができる。 |
 |
内覧会の後は、エースホテル京都で開催されたパーティーに参加。 |
 |
向かって左から、不動美里さん(和歌山県立近代美術館館長)、本橋弥生先生(工芸繊維大学デザイン・建築学課程准教授)、吉岡恵美子先生(精華大学芸術学部教授)、大木絵美さん(チームラボ)、私。 |
 |
有名なアニメ監督/アニメーターの押山清高さんが来られていた。最近では「ルックバック」(2024年)の監督などをされている。名刺を渡したら、代わりにサインをいただけた。 |
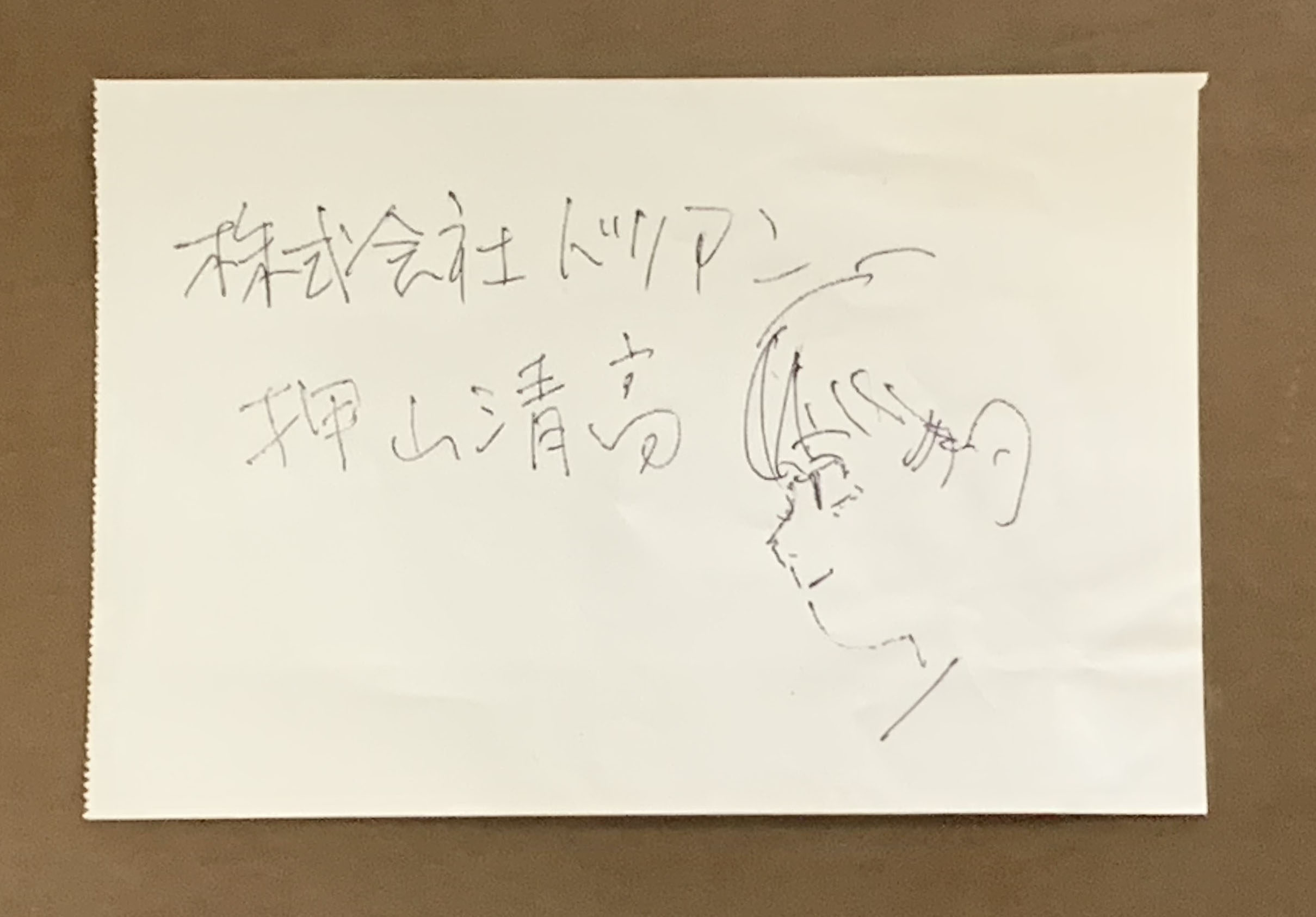 |
さすが、プロは、描線が違う! |
2025年10月4日(土)
「幹細胞の培養法・培養工学のためのコンソーシアム」で講演
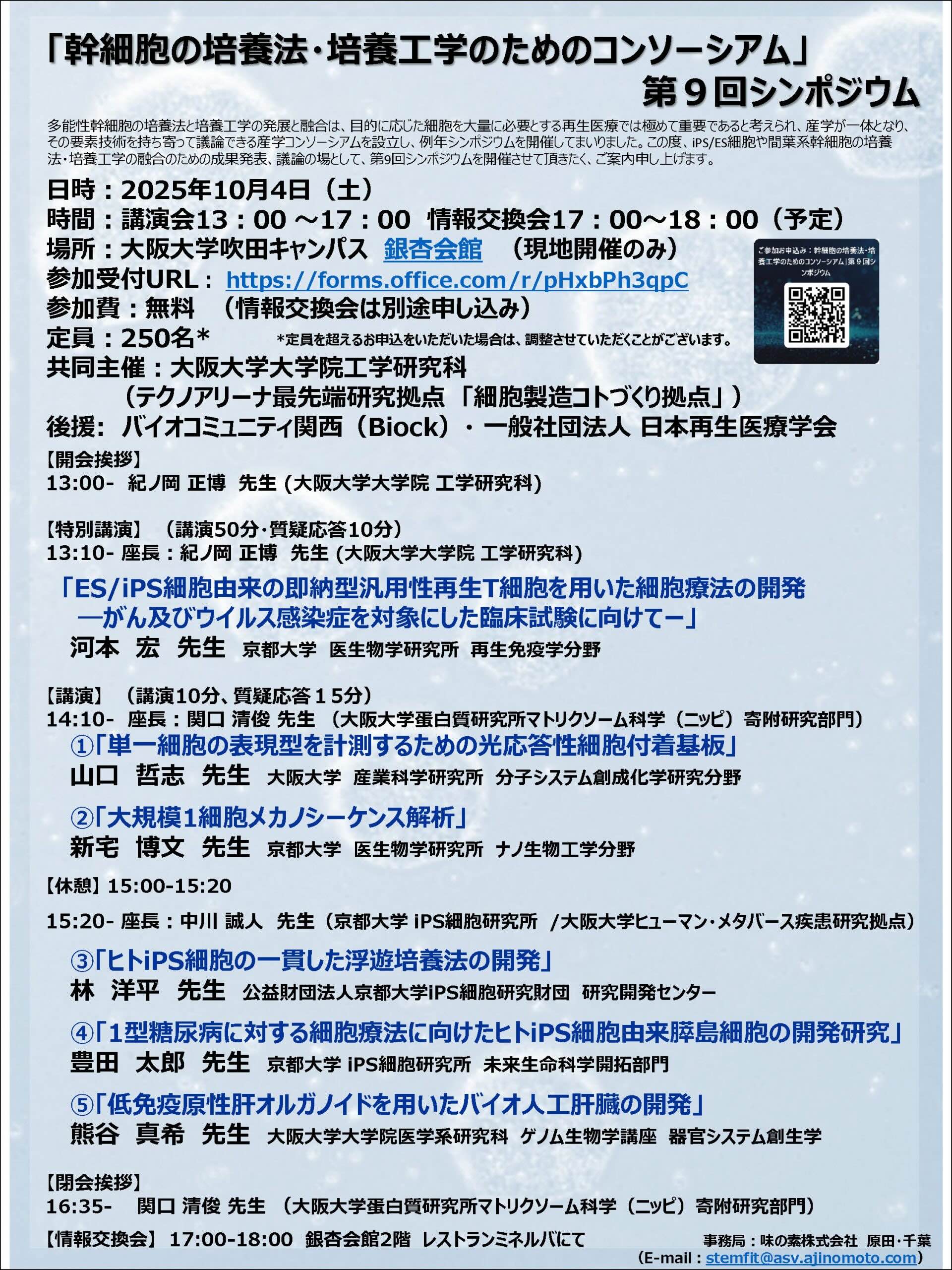 |
表記の会が大阪大学吹田キャンパスの銀杏会館で開催された。私は特別講演として、講演50分+質疑応答10分という十分な時間をいただけた。 |
 |
銀杏会館。 |
 |
立派なホールだ。 |
 |
紀ノ岡正博先生による挨拶。 |
2025年10月3日(金)
リトリートでの演奏に向けて練習を開始
 |
昨年のリトリートの懇親会でバンド演奏をしたが、今年もやろうという事になった。空いている部屋に楽器を持ち込んで、練習。向かって左から、石川芽依さん、(今吉研/生命M2)、 稲井早希さん (今吉研/生命M2)、髙橋くるみさん (今吉研/生命M2)、谷本佳彦先生(中台研助教)、岡田優真さん (今吉研/総人B4)、今吉格先生、後藤哲平先生(野々村研講師)。 |
2025年10月2日(木)-3日(金)
第20回生命医科学研究所ネットワーク国際シンポジウムを医生研が主催
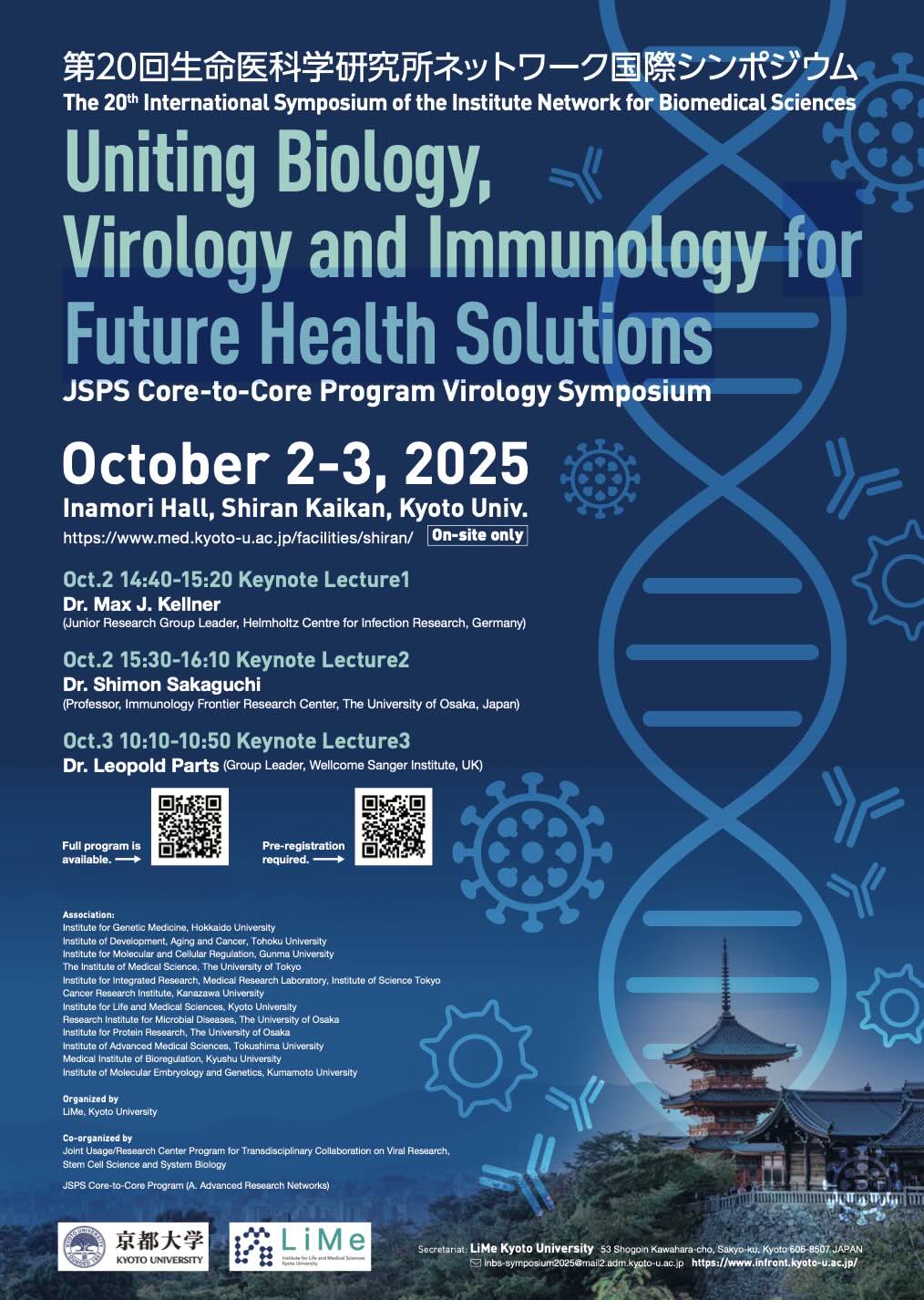 |
表記の会を医生研が主催し、芝蘭会館で開催された。 |
 |
このネットワークは、現在、12の研究所が参加している(北大遺制研、東北大加齢研、群馬大生体調節研、東大医科研、東京医科歯科大難治研、金沢大がん研、京大医生研、阪大微研、阪大蛋白研、徳島大先端酵素研、九大生医研、熊本大発生研)。医生研は、統合前にウイルス研と再生研がそれぞれ別個にホストしていて、再生研がホストしたのは2013年(2013年6月27日の記事参照)。今回、医生研に順番が回ってきた。 |
 |
キーノートスピーカーの一人は、坂口志文先生。ノーベル賞受賞前の、最後の講演となった。 |
 |
集合写真。 |
 |
徳島大学の大東いずみ先生(徳島大学教授、向かって左)と、藤森さゆ美先生(同助教)。 |
 |
向かって右から、鶴田真理子先生(熊本大小川峯太郎研育成助教)、丹羽仁史先生(熊本大教授)、川瀬栄八郎先生(医生研准教授)、私。 |
 |
向かって右から、逸見拓矢先生(医生研橋口研特別研究員)、板原君(河本研特定研究員)、私、倉谷歩美先生(大阪大学山本雅裕研特任助教)、森俊輔先生(大阪大学荒瀬尚研助教)。 |
 |
ポスター発表。 |
 |
永野君のポスター発表。 |
 |
向かって左から、中馬新一郎先生(医生研准教授)、竹田潤二先生(大阪大学招聘教授)、私。Cas3の話をした。 |
 |
ベスト口頭発表賞とポスター賞。 |
2025年9月29日(月)-30日(火)
「4D Omics in Development & Disease」に参加
 |
左記の会が熊本大学のくすのきテラスで開催された。学際ハブ(学際領域展開ハブ形成プログラム)という拠点の連携事業で、医生研は九大の生医研、熊本大の発生研と連携しており、今回は熊本大が主催している表記の国際研究会に、学際ハブの事業が共催という形を取っている。写真の奥に見えているのは、熊本大学病院。 |  |
会場。 |
 |
今回の会のホストを務める熊本大学発生研の所長、中村輝先生による挨拶。 |
 |
河本研からは、小林由佳特定助教が発表した。この事業の中で、人工リンパ節の組織の空間トランスクリプトーム解析を進めている。 |
 |
ポスター発表。 |
 |
情報交換会。 |
 |
情報交換会終了後、ホテルへ帰る途中、白川を渡る。 |
 |
望月淳史先生(医生研教授)、小林さんと、三人で郷土料理の店で二次会。 |
 |
馬刺し。美味しかった。 |
2025年9月26日(金)ー27日(土)
国際実験血液学会に参加
 |
熊本で開催された表記の会に参加。学会は24日から27日までの4日間開催されているが、今回は用務の関係で26日(3日目)から参加。前日25日に熊本入り。左は、宿泊したホテルの近くの路面電車の辛島駅から西を望んだ写真。夕焼けがきれいだった。この学会は基礎的な血液学の研究者の集いで、世界のいろいろな場所で開催され、毎回200人くらいが参加しているとのこと。英語の名称は「International Society for Experimental Hematology (ISEH)」。 ISEH2025 HP: |
 |
同じく25日入りをされた清野研一郎先生(北大遺制研)と合流。近くの居酒屋へ。 |
 |
馬刺し盛り合わせ、辛子蓮根、馬肉の炒め物、明太子山芋などを食した。馬刺しはしっかりとした旨みがあって、美味しい。 |
 |
学会は熊本城ホールの中の2会場で開催され、写真はメインホールであるシビックホール。 |
 |
ポスター会場。 |
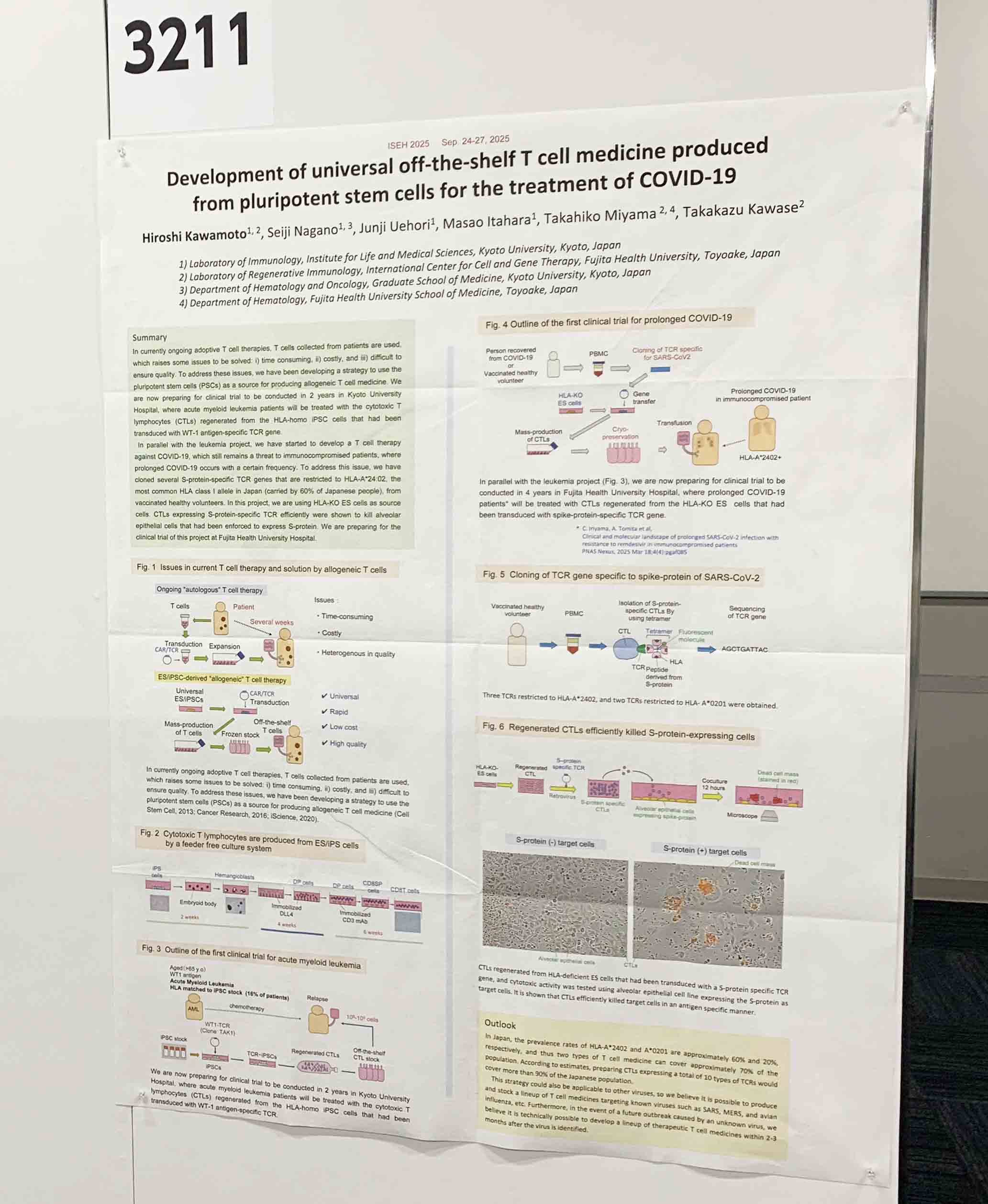 |
今回は久々にポスター発表。このポスターは板原君が布タイプで印刷してくれて、25日の朝に北村先生が貼ってくれた。 |
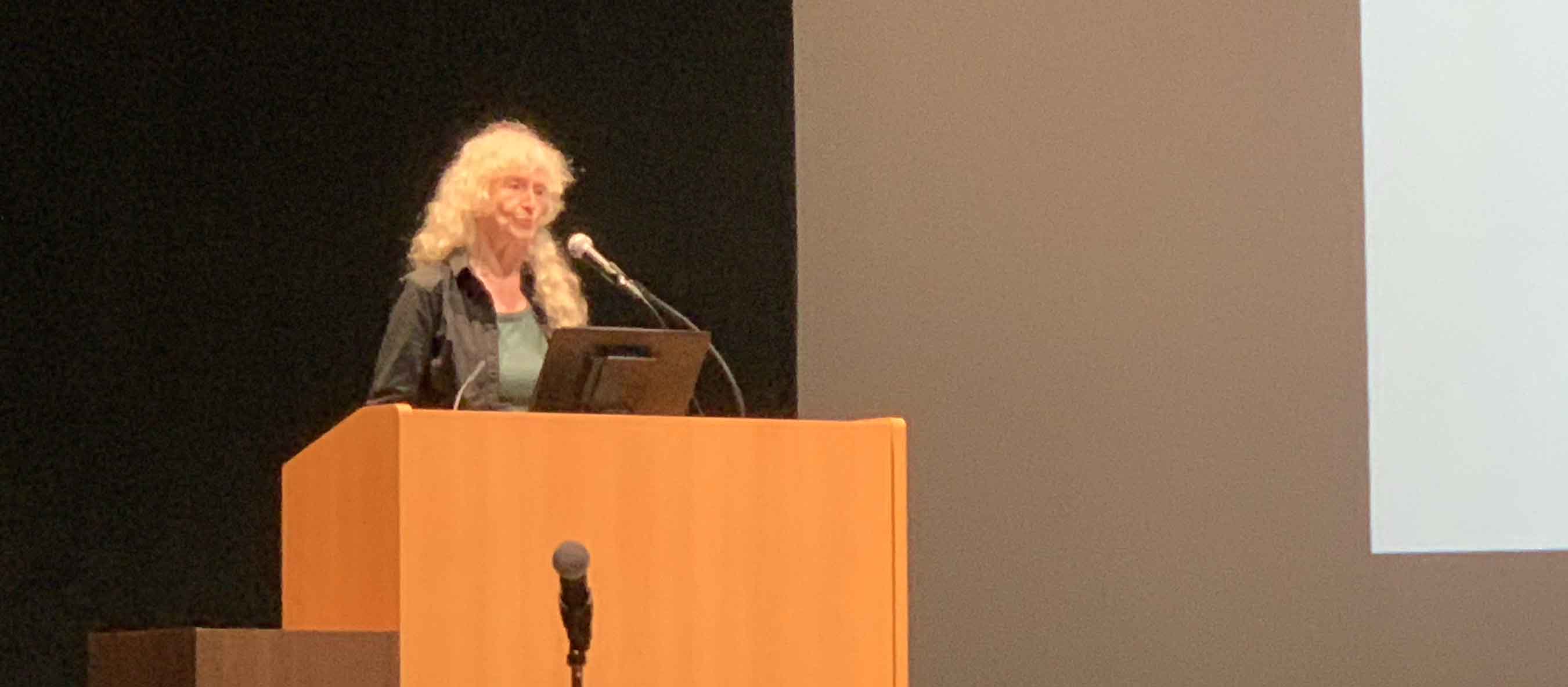 |
Ellen Rothenberg先生(Caltech)の講演。T細胞初期分化の転写調節の話。 |
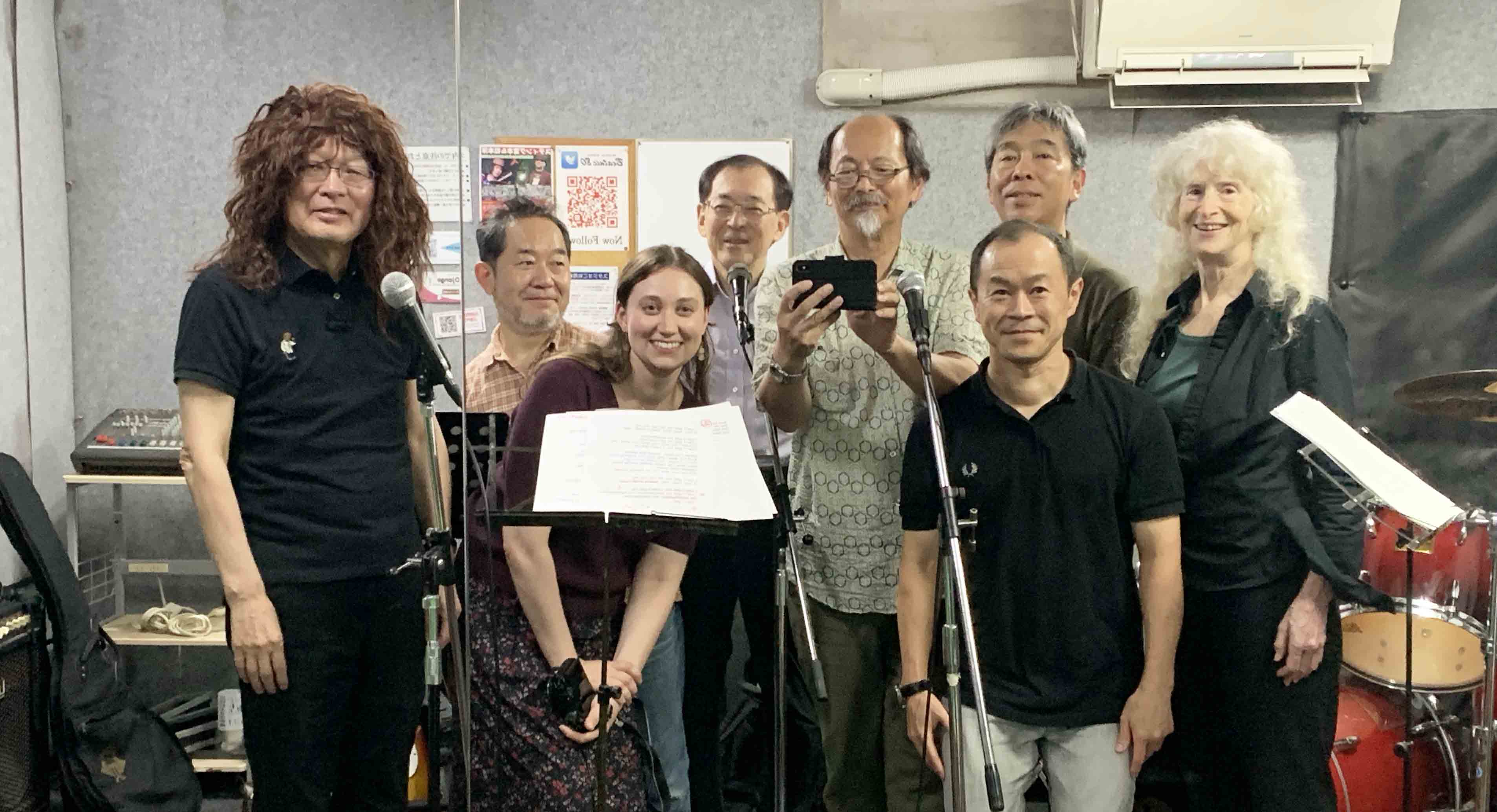 |
今回の学会では、最終日のフェアウエルパーティーで、Negative Selectionが演奏する事になっている(2025年9月6日の記事参照)。この日の夜、少し離れたスタジオBeatnic 80で練習。向かって左から、満屋裕昭先生(国際医療研究センター)、大久保博志さん(Progress)、Cara Trauschtさん(ISEH事務局)、北村俊雄先生(神戸先端医療研究センター)、私、滝澤仁先生(熊本大学)、清野先生、Ellen Rothenberg先生。滝澤先生は今回の集会のローカルオーガナイザー代表。 |
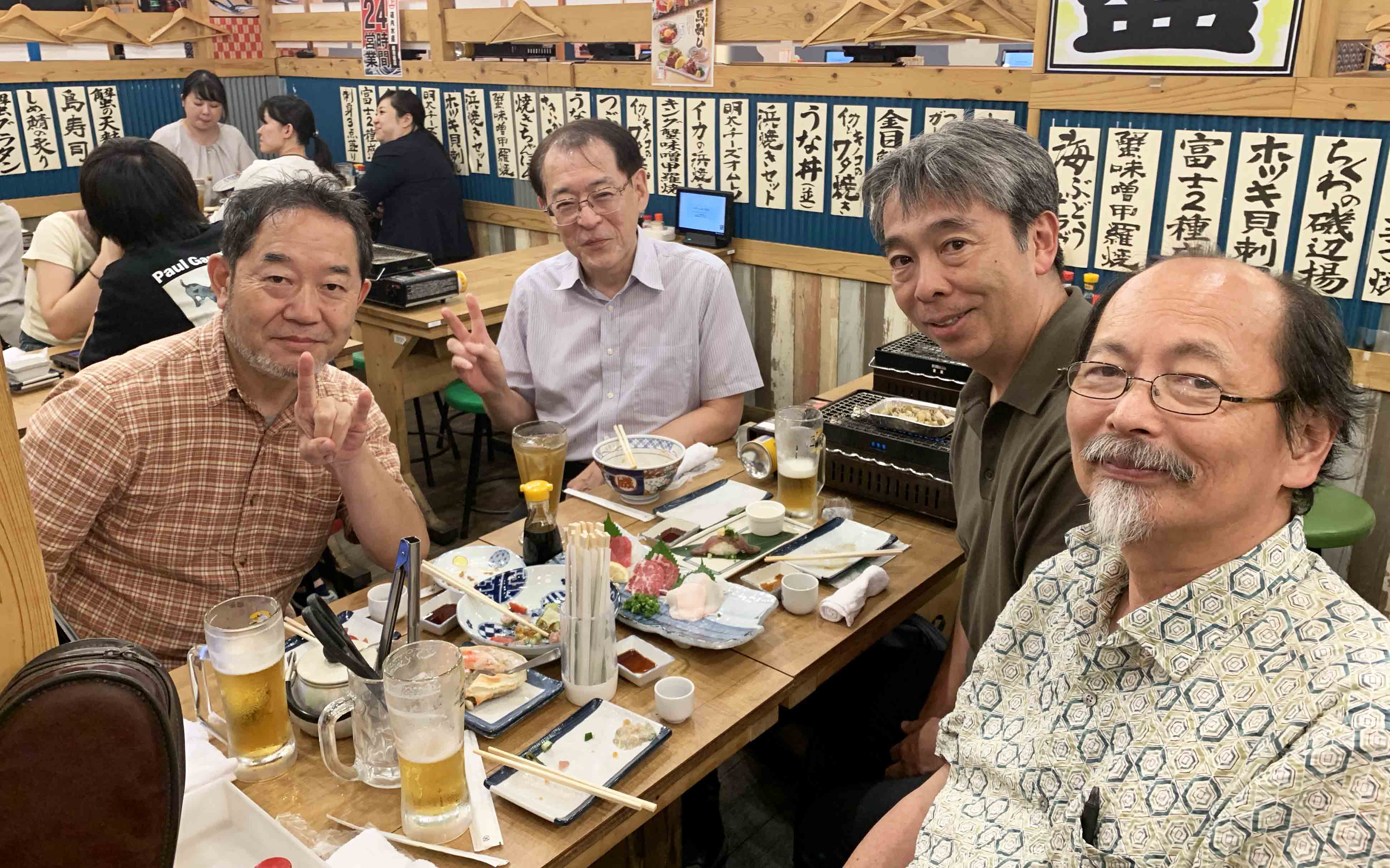 |
練習後、遅い夕食。こういう時間が楽しい。 |
 |
27日土曜日、お昼頃に駅前で九州産業大学のプロレス研究会が、プロレスのパフォーマンスをしていた。2019年に博多で日本がん治療学会に参加した時も、たまたま中洲で目にした(2019年10月24日の記事参照)。九州ではよくあることなのだろうか。ショーとしてよくできていて、実況中継の語りも面白い。ただ、2019年の時も書いたように、学生といえども体は十分鍛えているのであろうけど、危険な技は、見ていてヒヤヒヤする。親は見たくないであろうと思ってしまう。 ジャーマンスープレック3連発(約30秒の動画): |
 |
フェアウエルパーティーでのライブの前に、控え室で待機するバンドメンバー。幸谷愛先生(大阪大微研)は昨日の練習には来れなかったが、本番ではキーボード担当で参加。 |
 |
フェアウエルパーティーは、学会最終日の19時から、熊本キャッスルホテルで開催された。外国人率が高い。 |
 |
パーティーで、Daniel Tenen先生(シンガポール国立大学)、岩間厚志先生(東大医科研所長)と。 |
 |
木刀を使った二刀流の型のショー。型だから仕方ないかもしれないが、もう少し派手にやればいいのにと思ってしまった。 |
 |
民謡と踊りのショー。生の音楽隊の演奏が迫力あった。 |
 |
20時20分ごろから、Negative Selectionの出番。今回は、時間枠としては45分いただいていて、最初の依頼は「踊れる音楽を」という事だった。それで、オリジナル曲は封印して、自分達で分担して歌を入れて、60年代のロックンロールや、初期のビートルズ、ストーズの曲を演奏しようと考えた。しかしそのうち、学会関係者や、熊本に縁のある満屋先生に歌ってもらおうということになり、歌い手の希望に沿っているうちに、曲目はロックの曲を中心にシフトしていった。まずはオリジナル曲である「Openings」といういつも最初にやっている短い曲を演奏。北村先生がバンドメンバーを紹介。続いてCara Trauschtさんがエリック・クラプトンの「Layla」を歌った。今回は大久保さんは、ギターで参加。ボトルネック奏法でのソロが素晴らしかった。その後、Ellenが加わって、ビートルズの「A hard day’s night」と「Can’t buy me love」を二人でコーラス。いい感じにハモっておられた。それから、Ellenがリンダロンシュタットの「You are no good」。続いて、再びEllenとCaraでイーグルスの「Hotel California」。最後のソロの部分は私と大久保さんとのツインリードギター。やっていて、とても気持ちよかった。 |
 |
引き続いて、滝澤先生がニルヴァーナの「Smell like teen spirit」を熱唱。若い人達にウケていた。この曲は4つのコード(2小節)を最初から最後まで繰り返すだけなのに、とても盛り上がれる。いい曲だ。 |
 |
満屋先生が登場。一曲目はCCRの「Have you ever seen the rain?」。6年前に阿蘇シンポジウムでも演奏した曲だ(2019年7月26日の記事参照)。その後ビートルズの「Get back」と、「While my guitar gently weeps」。「Get back」のギターソロはジョン・レノンによるもので、これは大久保さんが弾いてくれた。「While my guitar gently weeps」はジョージ・ハリソンの曲であるが、ギターソロの部分はエリッククラプトンによるもので、泣きのギターの、名演とされている、これは、私が担当した。一度やってみたかったので、やっていてとても楽しかった。 |
 |
アンコールで、ストーンズの「Satisfaction」。写真から、聴衆がとても盛り上がって聴いてくれているのがわかる。 |
 |
ライブの終了後、メンバーで記念写真。暗い中で撮ったので、赤目現象が起こっていて、怪しい雰囲気だ。 |
 |
ライブの終了後、1時間くらい、DJによるダンスタイム。日本人はあまり踊らないが、欧米人はよく踊る。滝澤先生によると、さらにこの後、20-30 人を引き連れてカラオケに行ったそうだ。 |
 |
ホテルのラウンジで、満屋先生の奢りで、打ち上げ。 |
 |
翌朝、ホテルをチェックアウトした後、大久保さんと熊本ラーメンの有名店桂花本店へ。 |
 |
熊本ラーメンは、豚骨スープに、ニンニンを炒めたマー油が入っていること。独特の風味があって、とても美味しい。 |
 |
今回のライブでは、10曲も演奏させてもらえて、とても楽しかった。バンド関係の皆様、お疲れ様でした!滝澤先生、貴重な機会をいただき、ありがとうございました! |
2025年9月25日(木)
原さんが別な部署に異動
 |
医生研の事務部の総務掛長である原彰子さんが、10月1日から生命科学科に転属されることになった。統合される前のウイルス研や再生研におられたこともあって、諸事情に大変詳しく、相談相手としてとても頼りにしていた。いろいろな案件を抱えている上、もし来年度から京大が国際卓越に採択されたら、医生研も激しい改革を迫られる。もう少しいて欲しかったところだ。 |
2025年9月22日(月)
高折先生、林さんと会食
 |
7月に開催された京大医学部創立125周年記念祝賀会で、高折先生と林璃菜子さん(医学部5回生)と話をしていて「ワインを飲みにいこう」という事になり(2025年7月12日の記事参照)、この日の会食という運びになった。学部学生の生の声をじっくり聞くいい機会になった。林さんは、河本研の宮﨑正輝准教授の指導で研究をしていて、昨年度は免疫学会では英語で口頭発表(2024年12月3日の記事参照)、一昨年度の免疫学会ではポスター発表をしている(2024年1月17日の記事参照)。なお一昨年度の免疫学会に参加された時の様子は裏医生研チャンネルで紹介しており(以下のリンク)、再生回数は現在2万4650回に達している。 裏医生研チャンネル第82回:学部生が学会発表⁉~京大医学部生の研究発表に密着!~: |
2025年9月22日(月)
Camilla Forsbergとdiscussion
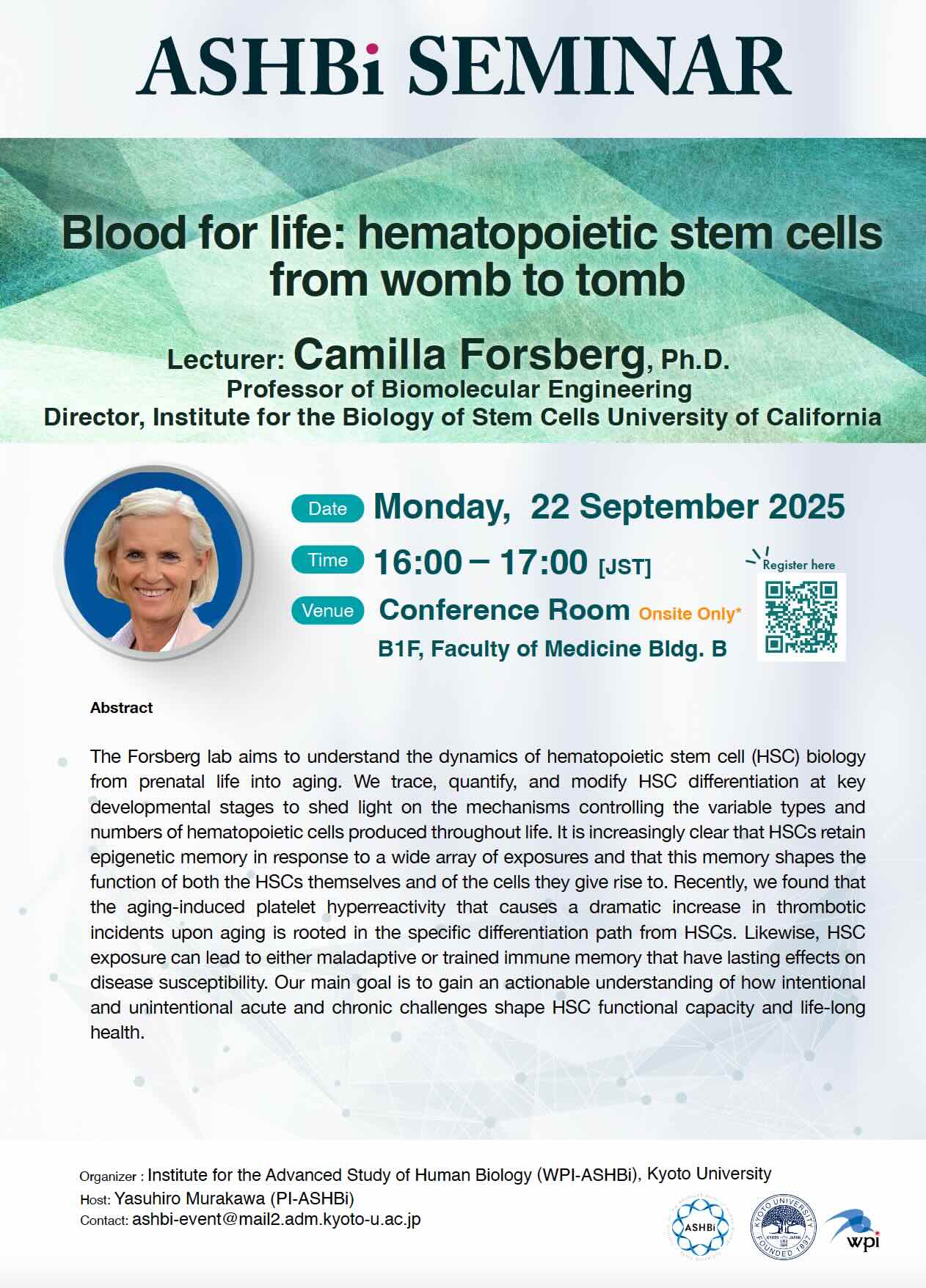 |
左記のセミナーがこの日の夕刻にASHBiで開催された。私は所用で参加できなかった。 |
 |
午後の早い時間帯に、Camillaが来訪。老化に伴って造血幹細胞から直で血小板が作られる分化経路が発生するというCell論文(187:3090, 2024)の話。血栓ができやすくなるなどの病理学的な意味はありそうという話であったが、生理学的な意味(脳出血を減らすとか)について訊くと、それは不明とのことだった。長畑君が今投稿中の血液細胞の進化の話を少し披露して、進化過程と分化経路の関係についてのdiscussionをした。 |
2025年9月22日(月)
Ran Jingのセミナー
 |
左記のセミナーがこの日の午前中にCiRAで開催された。 |
 |
iPS細胞から血球系前駆細胞を誘導する際にポリコム因子の一つであるEZH1を抑制するとリンパ球系に分化しやすくなり、それをT細胞にまで分化誘導するとab型T細胞になりやすいという話と、低分子化合物で同じ効果を得られる分子を検索するとGa9/GLPというエピジェネティック因子を阻害すると同じ効果が得られるという話。どちらもCell Stem Cell誌に掲載。実利的ではあるが、メカニズムがよくわからなくて、ちょっとモヤモヤしたものが残った。 |
2025年9月20日(土)
北海道大学CoSTEPで講義
 |
北大には科学コミュニケーションを扱う講座があり、講義は、学部や学年を超えて聴講できて、単位も取れる。CoSTEPは、Communication in Science and Technology Education and Research Programの略称で、日本語の名称は科学技術コミュニケーション教育研究部門。常勤の教員スタッフが8人くらいおられ、教育だけでなく、「サイエンスカフェ」などの、科学コミュニケーション活動の実践もされている。北大のキャンパスでは北の方に位置する「高等教育推進機構」(左の写真)の中にオフィスや教室を構えている。京都大学にもこんな組織があったらいいのに、と思った。 CoSTEPのHP: |
 |
駅から上記の建物へ向かう道中で見かけた雑草。ホソバウンランという帰化植物。オオバコ科に属するらしいが、形といい、色合いといい、いい花だ。 |
 |
上記の建物の中庭には、アキタブキが植えられていた。アキタブキのフキノトウは、相当大きいらしい。食べ応えがありそうだ。 |
 |
CoSTEPのオフィス。案内して下さったのは、特定助教の大内田美沙紀先生。2022年夏頃までは京大のCiRAで広報を担当され、多くのサイエンスイラストを描かれていた。 大内田先生のCoSTEPでのサイト: 大内田先生のサイエンスイラストレーターとしてのサイト: |
 |
今回は90分枠で講義をさせていただいた。現地での聴講は20人くらい、オンライン聴講が70-80人くらいとの事。学外者でも参加可能との話で、オンライン聴講は学外の人が多いらしい。 |
 |
左は、今回の講義のタイトル。科学コミュニケーションは、科学者と市民が対等に、双方向性に話し合うという事がベースとなるが、科学者側には何をやっているかを説明する義務があるし、市民側にも監視するという義務が生じる。しかし、今回の講義の主旨は、そういう義務に縛られる事なく、楽しくやりましょう、というポイント。 |
 |
少し前に、京都新聞の文化欄に、科学コミュニケーションについての、私見を載せていただいた事がある(2021年10月8日の記事参照)。今回の講義は、その中で書いた事と基本的には同じ内容。 記事: |
 |
時間が十分にあったので、免疫学、がん免疫、再生医学などの自分の研究の背景ととなる話、自分の研究の話、科学コミュニケーションについての私見などの後に、30分くらい、自分が科学コミュニケーションにどう取り組んできたかを紹介した。 |
 |
サイエンスイラストについてのチャート。自分のイラストはアートと説明図の間に位置すると思われる。 |
 |
これまで描いてきたイラストの制作の経緯などを紹介した。今年のKTCCの抄録集用のイラスト(2025年6月21日の記事参照)、清水免疫学・神経科学振興財団のHP用のイラスト(2025年4月28日の記事参照)、免疫学会のポスター用イラスト(2024年12月9日の記事参照)、「がんゲノム医療」の表紙用のイラスト、「がん免疫ペディア」の表紙用のイラスト(2022年2月14日の記事参照)、「理論生物学概論」の表紙用のイラスト(2021年3月30日の記事参照)など。 |
 |
動画制作についての話の中では、澄田先生のプチ歓迎会の写真を示した。懐かしい。この数ヶ月後、大内田先生は北大のCoSTEPに異動された。 |
 |
講義終了後、記念写真。イラストや音楽の話をたっぷりとさせていただけて、それを生徒さん館が熱心に聴いてくれたので、とても楽しかった。 |
 |
その後、大内田先生の案内で、北大校内を散策。気温は20度くらいで、涼しい。北大は、構内に原生林みたいな場所があったりする。左側に大きな実をつけて立っているのは、オオウバユリ。こんな植物が構内に生えているとは、素晴らしい。 |
 |
この他に、オオバナノエンレイソウの群生地もあった。この季節はすでに葉がなかったが、早春には賑やかになるのであろう。 |
 |
オオバナノエンレイソウのイメージは、北大のシンボルマークに使われている。左の写真はWikipediaより拝借。 |
 |
左の写真は、昨年、宇奈月温泉(富山県黒部市)の遊歩道で撮ったエンレイソウ(2024年5月11日の記事参照)。本州のエンレイソウは、こんな感じで、大変地味だ。それでも、ある程度深い山に行かないと見られないので、この花を山で見かけると、ちょっと嬉しくなる。 |
 |
構内にある、ローカル色の強いコンビニ、「セイコマート」。24時間営業とのこと。 |
 |
お酒も置いてある。うらやましい。少し前に南西地区の構内にコンビニが設置された事があったが、土日や深夜は休みで、お酒が置いてなかった。 |
 |
札幌駅を通り越して、駅の南側へ。北海道庁の旧庁舎である「赤れんが庁舎」。かっこいい。 |
 |
ホテルに荷物を置いてから、会食までの間、散策を続けた。大通公園では、オータムフェストというお祭りをやっていた。 |
 |
区画ごとに異なるテーマ。「食と音楽」という区画に行ってみた。 |
 |
中央にテントとテーブル、椅子が設置され、周囲を屋台が取り囲むような構造。 |
 |
会食までまだ時間があったので、おやつタイムを取る事に。ザンギ(唐揚げの事を北海道ではザンギと呼ぶらしい)、焼き鳥、タコの揚げ物などを肴に、ローカルなクラフトビールを楽しんだ。 |
 |
ステージではジャズを演っていた。 |
 |
お肉をテーマにした区画。若者が多い。オータムフェストは3週間くらい開いているようだが、夏や、クリスマスシーズンにも、同じような規模のお祭りがあるらしい。京都市もこの手のイベントを取り入れるべきだと思った。 |
 |
郷土料理の区画。こんなのが近くで開催されたら、毎日でも通うであろう。 |
 |
さらに南下して、狸小路へ。大きくて長いアーケード街で、飲食店が多い。 |
 |
さらに南下して、すすきのへ。 |
 |
ラーメン横丁。 |
 |
すすきの近辺の日本酒のお店で、会食。各種地酒が飲み放題という、夢のようなお店だった。写真向かって右は、奥本素子先生(准教授/部門長)。科学コミュニケーションについて、いろいろな話ができて、楽しかった。 |
 |
翌日、空港で見かけたゴールデンカムイとのコラボの、サッポロビール。お土産に何本か購入。札幌出張は、楽しかった! |
2025年9月13日(土)
5回目の万博:22万人の入場者の中での万博
 |
この日、家族と万博に行くことになった。テストラン(2025年4月6日の記事参照)、リバーセルの展示期間中の観覧(2025年6月24日、6月26日、6月30日の記事参照)を合わせて、5回目の万博。1ヶ月くらい前に予約したが、11時からの枠(東ゲート)しか取れなかった。10時くらいに来たが、すごく多くの人がすでに並んでいて、ゲートは遠い。通り雨も降って、ちょっとトホホな感じだった。なお、翌日の公式発表では、この日は最多入場者を更新。関係者を除いた一般入場者で21万8130人とのこと。これまでの最多は9月6日土曜日の20万9837人だったらしいので、それよりさらに8千人多い。この前日の金曜日は20万8163人と、平日なのに20万人越え。テストランの時は5万人弱、リバーセルの展示期間中の平日は10万人前後だった。終盤に向けて、入場者が激増している。 |
 |
11時入場という枠であったが、10時半くらいには動きがあって、ゲートの個別の列には10時半過ぎには並べて、11時頃には保安検査を通って入場できた。 |
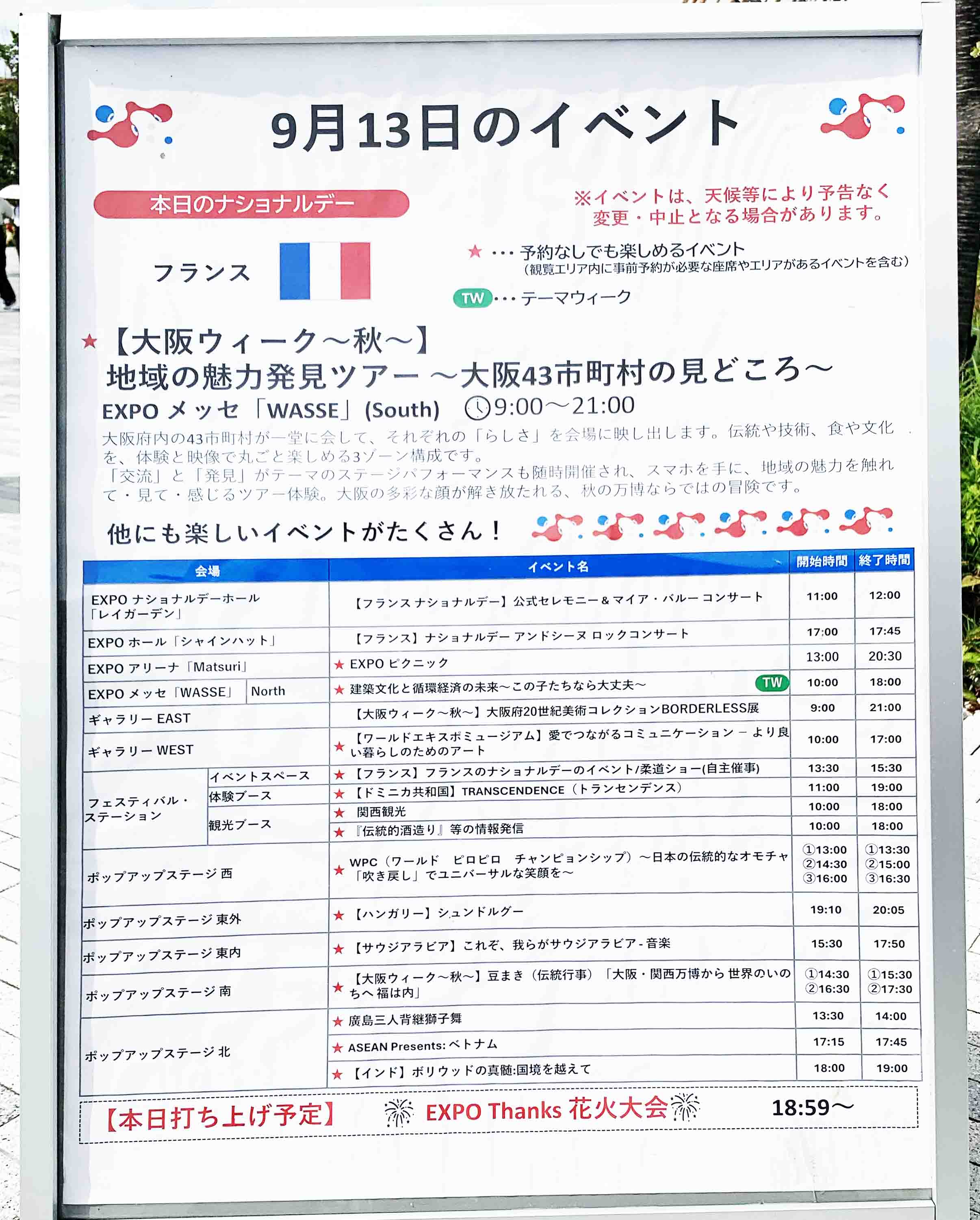 |
この日は一つも事前予約が取れなかった。入場後の当日予約も、並んでいる時や食事中に、携帯電話の画面から再三試みたが、一つも取れなかった。時々、いずれかのパビリオンの特定の時間枠に△マーク(混雑しているけど空いている)がでたり、稀に○マーク(空いている)が出たりはするが、大急ぎで登録しても、すぐに「取れませんでした」と返ってくる。そもそもすごい競争になっているのであろうが、会場内にある16台の当日登録端末機からの予約を優先しているという話もあったりする。従って、パビリオンを観たければ並ぶしかなかったが、その多くは混雑が必至だったので、この日はイベントを観てまわるのと、食べ歩きを軸にする事にした。 |
 |
入場後すぐに、リングサイドマーケットプレイス東、「サイゴン屋台」のベトナム料理で早目の昼食。ココナツミルクカレー、フォー、すでにかなり汗をかいて脱水状態だったので、ビール2種。カレーはとても美味しかった。 |
 |
昼食後、12時頃、コモンズAは並ばずに入れた。写真はボリビアの人形。 |
 |
トンガのブース。その国の人がいると、万博感が増す。各国にブースに一人現地人を配置するのを義務にすればいいのでは、と思った。 |
 |
この連休中(9月13-15日)のイベントとして、Expoメッセ会場で大阪の各市町村が「地域の魅力発見ツアー」展示をしていた。写真は「みなはれ」ゾーン。 |
 |
「たべなはれ」ゾーン。 |
 |
藤井寺市は鰻と地ビールを提供。 |
 |
早目のおやつとして、鰻の押し寿司とクラフトビールを堪能。「美陵鰻」という養殖鰻のブランドであるらしい。 |
 |
14時頃、大屋根リングの西からリング中央方面を望んだ写真。人が溢れている。 |
 |
インドネシアパビリオンではよく呼び込みのショーをやっているようで、この日も賑やかにやっていた。 |
 |
ドイツパビリオンでは、ダンス教室のようなイベントをやっていた。日本の「カワイイ」文化に合わせて作られたキャラらしい。ベートーベンまで可愛いキャラにしているが、ちょっと無理があるように思える。 |
 |
大屋根リングの東からリング中央方面を望んだ写真。 |
 |
6月24日に、ほぼ同じアングルで撮った写真。入場者10万5千人と21万8千人の差がわかる。 |
 |
15時半から、屋外イベントで、サウジアラビアの音楽のライブ演奏が聴けた。 「これぞ、我らがサウジアラビア音楽」Live動画(約40秒): |
 |
16時過ぎから、マーケットプレイス西の山東料理の店で早目の夕食。塩ラーメンと名物爆弾餃子。 |
 |
東ゲートマーケットプレイスにお土産を買いに行ったら、混みすぎで入場不可だった。花火と夜の噴水ショーの場所と確保しようと早目にウオータープラザ(海辺)に行くことにした。途中の経路が、ごった返していた。さすが20万人。 |
 |
「アオと夜の虹のパレード」は、19時10分と20時30分開始の2枠を事前予約したが、外れた。それで、枠外の席の中で、少しでも正面寄りの席を、と思って2時間前に来たら、すでに多くの人が座っていて、やや離れた場所しか取れなかった。 |
 |
18時半頃の写真。この日は「Expo Thanks花火大会」という花火の打ち上げもあって、多くの人が集まっていた。 |
 |
海側からの風が結構強かったので、「中止になるかも」と警告される中、19時から5分ほど花火の打ち上げが敢行された。尺玉の打ち上げもあったようで、火花がほぼ真上に来るくらいまで拡がり、すごい迫力だった。 |
 |
19時10分からの「アオと夜の虹のパレード」を観てから、より正面に近いところに席を移して、20時30分からの第2回も観覧。待ち時間の間、近くのチェコパビリオンの前で売っていたチェコの缶ビール2本を購入。 |
 |
2回目はより近くで観れたので、さらに迫力があった。炎が出る演出がとても良い。音楽も素晴らしい。作曲は菅野よう子とのこと。攻殻機動隊のテレビシリーズの主題歌など、アニメソングを数多く手掛けている人だ。 |
 |
「夜の虹」のイメージの演出。 |
 |
フィナーレ。色々な仕掛けが施してあり、見応えがある。 フィナーレの動画(約1分30秒): |
 |
この日は、花火とパレードは行われたが、ドローンショーは風が強いため中止。9時頃、帰路につく。さすがにこの後、観にくる予定はないので、これが見納めかと思うと、寂しさを感じた。 |
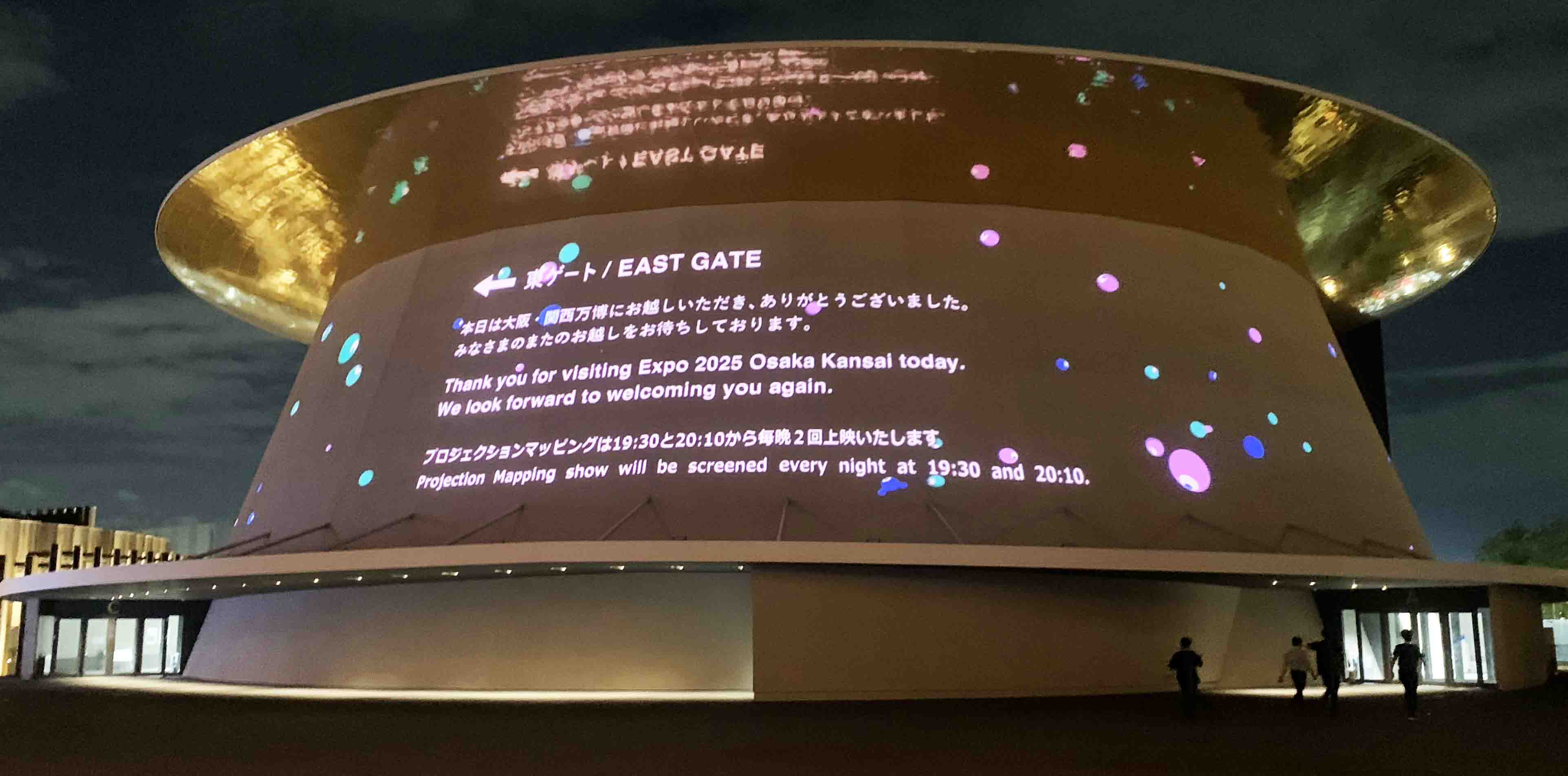 |
シャインハット。 |
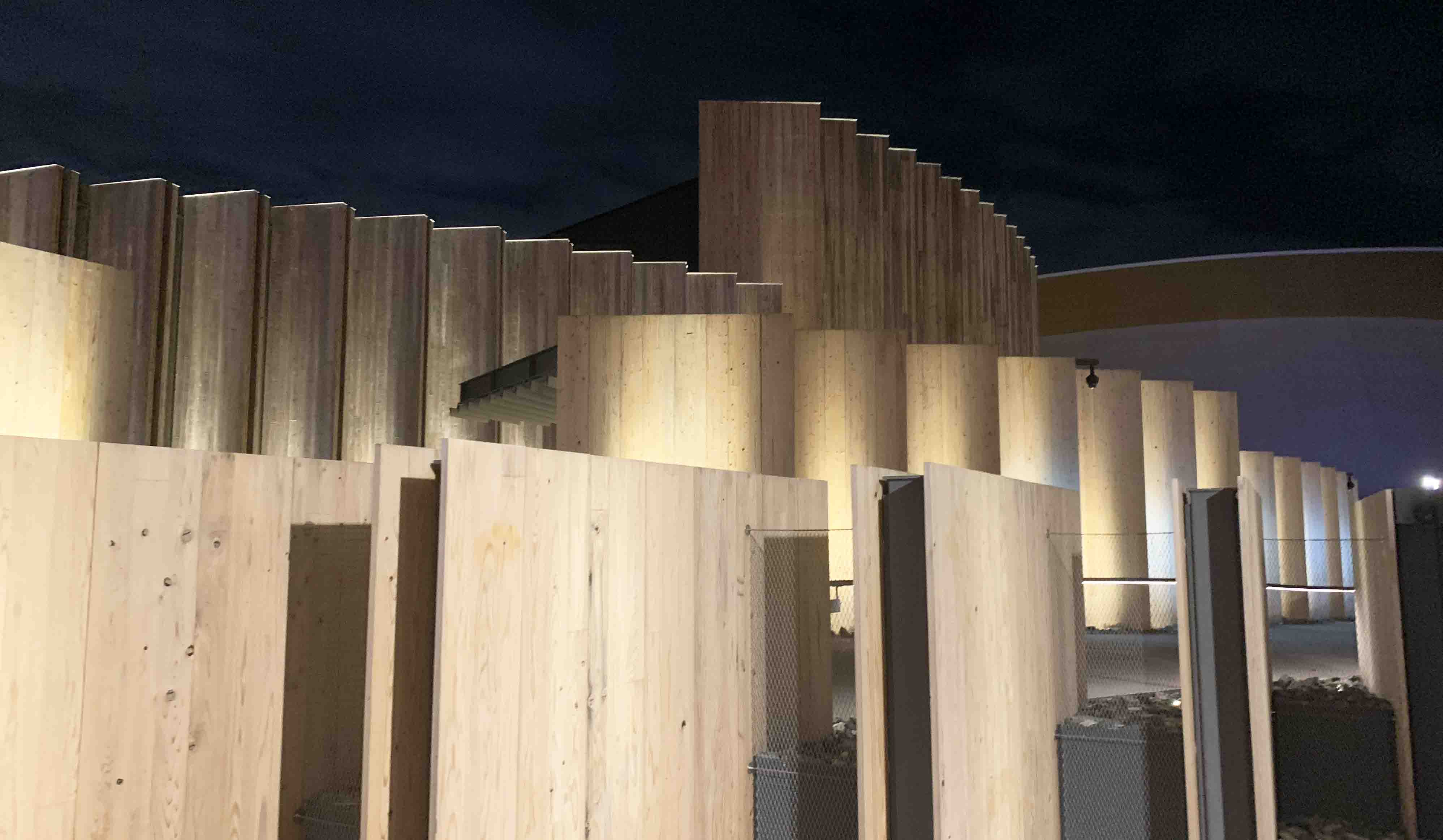 |
日本館。 |
 |
フランス館。万博では、ナショナルデーと言って、今日はxx国の日、という決め事があって、それに基づいたイベントが開催される。そういう日は、該当するパビリオンは、忙しいからか、閉館することが多いらしい。この日は、フランスの日だったからか、フランス館は閉館だった。フランス館を目当てに行っただけに、閉館は、残念だった。また、この日はナショナルデー関連のイベントとしてフランス館の隣りのフェスティバル・ステーションで午後に「柔道ショー」が開催されていたが、これも満席で、入れなかった。 |
 |
パナソニック館。 |
 |
9時40分にゲートを出た。その後、大きな行列の中で駅に向かってゆっくり進む。 |
 |
駅まで約40分かかった。駅に入ってから電車に乗るまでは早かった。22万人弱の入場者でパンパンだった万博であったが、食事にはありつけたし、夜のイベントも観れたので、結構楽しめた。 |
2025年9月12日(金)
日立製作所/日立ハイテクとの共同研究
 |
日立-京大-リバーセルの三者共同研究では、3年前から自動培養装置(iACE2)を使って多能性幹細胞からT細胞を作ることを目指した開発研究を進めている。この日は、今年度の研究のキックオフ会議が開かれた。 |  |
会議後の会食。前回、前々回も京都駅近くの「弘」で催されたが、今回も京都駅近くの弘で、前回とは違って八条口側の店舗。 |
 |
もう一つのテーブル。 |
2025年9月11日(木)
嘉島君来訪
 |
留学中の嘉島君(2025年1月24日の記事参照)が京都で開催された泌尿器科系の学会に参加する際に、ラボに顔を出してくれた。彼はWT1抗原を標的にして再生T細胞を用いた腎癌の治療の開発研究にたずさわった(iScienc, 2020)が、その戦略は今もリバーセルで臨床試験に向けて開発を続けている。 |
2025年9月8日(月)
皆既月食
 |
この日の午前2時頃から4時頃まで、京都でも皆既月食が観られた。3年前の皆既月食(2022年11月8日の記事参照)、4年前の部分月食(2021年11月19日の記事参照)の時は早い時間帯だったのでしっかりと観てスマホで写真を撮ったが、今回は深夜であったので、私は見そこねてしまった。一方で、秘書の宮武さんはちゃんと起きて、観たとの事。左は、その時の写真。赤い月が、妖しく、美しい。 |
 |
ついでに、前回の2022年の月食の時の写真を載せておく。娘(当時大学で写真部に所属)がちゃんとしたカメラで撮った写真。 |
2025年9月6日(土)
国際実験血液学会のフェアウェルパーティーでの演奏に向けて練習
 |
本年9月24日から27日まで熊本で開催される国際実験血液学会では、最終日の学術プログラムが終了後に、フェアウェルパーティーが開催される。そのパーティーでネガティブセレクションが演奏することになった。持ち時間が45分なので、今回はビートルズ、ストーンズ、イーグルス、クラプトンなどのロックの名曲を10曲くらい用意している。この日、清野研一郎先生(北大遺制研)と医生研で研究打ち合わせをした後、四条大宮のスタジオ246で他のメンバーと合流。今回のライブでは4人がシンガーとして登場する予定であるが、そのうちのお一人である満屋裕明先生(国立国際医療研究センター研究所長)が練習に参加された。写真向かって左から、幸谷愛先生(大阪大微研)、大久保博志さん(Progress)、清野先生、満屋先生、北村俊雄先生(神戸先端医療研究センターセンター長)、私。いい練習ができて、楽しかった。 |
 |
練習終了後、近くの串八がまだやっていたので、串八で遅い夕食。百万遍の串八の系列店。百万遍の串八には学生時代には何度も行ったが、それ以後ご無沙汰だったので、久々の串八であった。串5本セット(700円)/各自を基本に、もつ煮込み、タコカルパッチョ、水茄子サラダ、唐揚げ、キンパ、おにぎりなどを食したが、どれもとても美味しかった。幸谷先生も「串八ってこんなに美味しかった?」と絶賛。皆が、かなり空腹だった事もあるのかもしれない。その上に、ビールやお酒もかなり飲んだが、驚いた事に、それで一人3000円もかからなかった。美味しくて、安い。素晴らしいコスパだ。 |
 |
翌日、医生研で、朝から研究打ち合わせ。清野先生が帰られた後、北村先生、幸谷先生と医生研の近くのトンカツの店(カツ丼玄)で遅い昼食。私と幸谷先生は、この日も串カツ5本セットを食した。ここも美味しかった。 |
2025年9月2日(火)
前川さんがマイコースで河本研に参入
 |
昨日から、前川万侑子さん(京大医学部4回生)がマイコースで河本研に参加。少し前に書いたが、洛北高校の後輩でもある(2025年5月26日の記事参照)。ウイルス特異的T細胞の再生と機能評価などについて、主に上堀君の指導の下に、2ヶ月ほど研修される予定。 |
 |
くうかいの新メニュー、ムール貝の酒蒸し。日本のイガイとは違って、かなり大きい。東北地方で養殖されたものとの事。とても美味しい。汁も、スープとして美味しく飲める。 |
2025年9月1日(月)
友田先生来訪
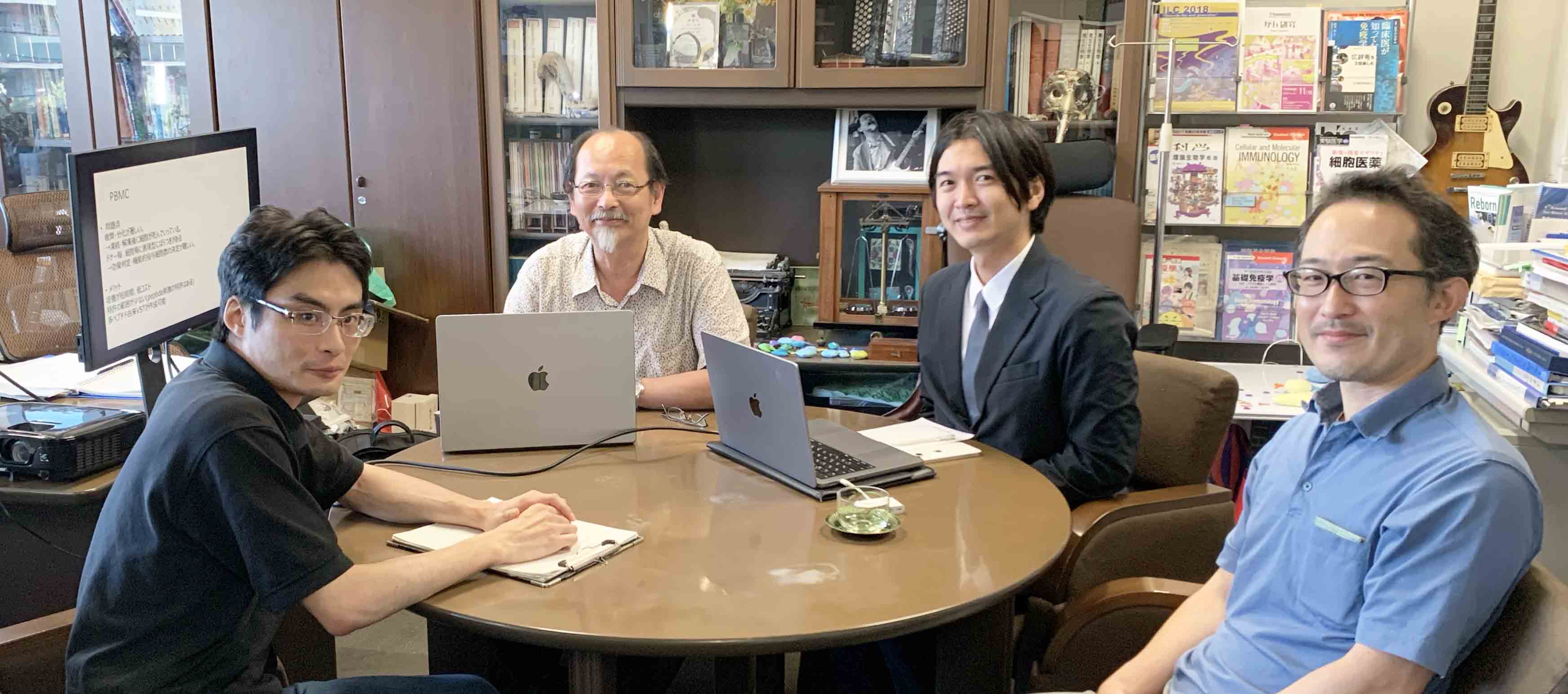 |
東京科学大学医学部の発生発達病態学分野(小児科)の大学院生である友田昂宏先生が研究室に来られた。ウイルス特異的T細胞を使った治療法の開発をされている。対象疾患は、造血幹細胞移植後に潜伏していたウイルスが再活性化した症例。河本研も藤田医大でウイルス感染症に対する細胞療法の開発を進めているので、この日は情報交換のdiscussion。友田先生が開発しているのは第三者(健常人)由来のT細胞を使う方法で、一方我々はES/iPS細胞を材料にしているという。材料として使う細胞は異なるが、基本的には共通している部分が多い。友田先生らの戦略は臨床試験直前まで至っており、T細胞の拡大培養や凍結保存法などについて、学ぶ事が多く、有意義だった。 |
 |
近くの「くうかい」で会食。いろいろな話ができて、楽しかった。 |
2025年8月28日(木)
サルスベリの花
 |
教授室から見えるサルスベリ。幹がツルツルなので猿が滑って落ちることからサルスベリと名付けられている。サルスベリは普通はそれほど大きくならないが、この個体は左右を挟まれている為か上に伸びて、大きな樹になっている。今年もいい感じで花を咲かせた。 |
2025年8月25日(月)ー28日(木)
免疫学会サマースクールに参加
 |
今年のサマースクールは米子で開催された。 |
 |
私は講師の一番手で、13時10分からの予定であった。この日に朝早くタクシーで最寄りの駅に行ったとしても、電車ではその時間には間に合わない。車で米子まで行ったら、間に合うかもしれないが、ゴルフをした次の日に、早朝に起きて、寝不足で7-8時間走るのは、危険だ。そこで、京都までは車で帰って、京都から電車で行く、という方法を取る事にした。左の写真は早朝のリゾートホテル蓼科。 |
 |
8時頃に医生研に着いて、8時半に医生研を出れば、9時発の新幹線に乗れる。蓼科高原から医生研までは、ナビの予想では4時間半ぐらいかかるとのこと。大事をとって、3時過ぎに出発。ナビの予想到着時刻は7時39分だった。結果的には、余裕を持って到着できた。早朝の中央高速は、がら空きで、走っていて気持ちが良かった。 |
 |
9時2分京都発ののぞみ号で10時5分岡山着、10時13分岡山発の特急やくもで12時25分米子着。会場は、駅から歩いて5分くらいの米子コンベンションセンター。 |
 |
左は、現在の教育推進委員会の委員で、この委員はサマースクールのオーガナイザーを務める事になっている。今回のオーガナイザー代表は、常世田好司先生(鳥取大学)。 |
 |
会場。 |
 |
現免疫学会理事長である竹田潔先生(大阪大学)による挨拶。私はこの後、イントロ講義5コマの、最初を担当した。 |
 |
初日の夕刻、ポスターセッション。25演題が出されていた。 |
 |
河本研からは、今年は日高さんと板原君が参加。二人ともポスター発表をした。 |
 |
初日の夕食は、米子名物が供された。どれもがとても美味しく、またそれぞれについて人数分が用意されており、ボリューム感に溢れていた。 |
 |
地酒が用意されているのも、ありがたかった。 |
 |
食事をとりつつ、そのままフリーディスカションへ。写っている若い人達は、とても元気な人達だった。向かって左から、奥田琉菜さん(九大生命科学3年)、中川智香子さん(東大薬学M1年)、長田羽未さん(鳥取大生命科学3年)、茂呂和世先生(大阪大学教授)、私。 |
 |
その元気さに巻き込まれて、フリーディスカッションタイム終了後、23時頃から、カラオケに行くことに。こういう時に、地元民(この場合長田さん)がいたので、速やかに移動できた。参入した男子は、左から山田卓郎さん(九大生命科学M1)、岩本知直さん(九大生命科学M1)、嘉亨真(よしみとおま)さん(九大生命科学M2)、武信翔さん(九大生医研M1)。1時頃、解散。 |
 |
二日目、お昼に集合写真。 |
 |
夕方から、バスで遠足。途中の道から見えた大山。山容が美しい。 |
 |
大山のすぐ近くの牧場でしばらく停車。大山を間近で、じっくりと観ることができた。 |
 |
山頂付近のアップ。良い。 |
 |
その後、少し裾野を下ったところの、ビアホフガンバリウスというビアホールで、夕食。 |
 |
カウンターから、効率よく生ビールが供される。 |
 |
一杯目はデフォルトでピルスナーであったが、二杯目からは選べた。この日は、あれこれと、計6杯頂いた。料理も美味しかった。 |
 |
店から望んだ日没。 |
 |
鏑木啓介さん(横浜市大外科)と。 |
 |
この日は、若い人達と沢山話をした。向かって左から、宮津美里有さん(東京科学大D2)、森わかなさん(鳥取大生命科学2年)、田辺こころさん(鳥取大生命科学2年)と。 |
 |
塚崎礼子さん(東大薬学D2)と。堀昌平先生の研究室で、Tregの抗原特異的な抑制のメカニズム解明に取り組んでおられる。 |
 |
西野凌平さん(筑波大膠原病M2)と。自己免疫疾患を代謝という切り口で攻めようとされている。 |
 |
尾花柊(しゅう)さん(東京理科大薬学D2)と。シート状の人工的なリンパ組織を移植してリンパ浮腫を治す、免疫を活性化するなどの面白い研究をされている。河本研で渡邊先生や小林先生が開発してきた人工リンパ節と通じるところがあるように思われ、興味深かった。 |
 |
久保文乃さん(鳥取大生命科学1年)、栗本美聡さん(鳥取大生命科学1年)と。 |
 |
カウンターの前に群がっていた人達と。大野博司先生(理研IMS、私の向かって右隣)は、この時点でかなり飲んでおられた。 |
 |
3日目の昼食は、各自食券を持参し、指定された3店の中で好きな店に行くという仕組みだった。私は、地元の黒毛和牛が食べられそうということで、焼肉屋を選んだ。たまたま居合わせた人達と、同じテーブルを囲んだ。向かって左から、菊池理先生(京大がんセンター准教授)、永野嵯乃さん(スタッフ:常世田研院生)、出原暁帆さん(スタッフ:常世田研院生)。菊池先生は腫瘍内科医で、すでに准教授であるが、免疫を勉強し直したくて、参加されているとの事だ。 |
 |
夕食時、加覧(がらん)浩太郎さんと。府立医大卒で、駒込病院で血液内科医をしているとの事。話によると、うちの長男は一時期水泳部に入っていたのであるが、その時の先輩であるらしい。血液内科医であるが、免疫にも興味を持っているとの事だった。 |
 |
この日、弁当とは別に供された郷土料理。炊き込みご飯を油揚げで包んだような料理。美味しかった。 |
 |
この日、缶ビールとは別に供されたクラフトビール。どちらも美味しかった。 |
 |
3日目の夕食時は、お弁当を食べながら、「恒例の免疫学者を囲む夕べ」。1時間経ったところで、席替えをして次の1時間。写真は、後半の組。向かって左から謝ウェイジェさん(北大D3)、永野嵯乃さん(スタッフ:常世田研院生)、私、安田和真さん(京大CiRA-D2)、大西拓人さん(日大生物資源D2)、塚崎礼子さん(東大薬学D2)、遠藤凛さん(横浜市大生命医科学D1)、工藤友喜さん(北大免疫代謝内科研究員)。 免疫学会のサマースクールは、いつもそうであるが、今回も多くの講師の人達の話が聞けて知識がアップデートできたのと、若い人達と沢山話ができて、とても有意義だった。 |
2025年8月24日(日)
蓼科で北村先生主宰のゴルフ合宿
 |
毎年、夏に北村俊雄先生(神戸先端医療センター)の主宰で、ゴルフ合宿が催されている(2024年7月21日の記事参照)。今年は蓼科。24日の朝10時頃からラウンドということで、関東からの人達は当日朝から来られるらしいが、私は蓼科には前日入り。今回は自分の車で行った。写真は18時10分頃、諏訪湖サービスエリアから望んだ諏訪湖。 |
 |
雲の部分のアップ。積乱雲はかっこいい。 |
 |
18時30分に上諏訪駅で清野先生をピックアップし、途中のスーパーで夕食を買い出ししてから、「三井の森ゴルファーズロッジ」に20時頃到着。24日にラウンドする「フォレストカントリー三井の森」のすぐ近くだ。 |
 |
清野研一郎先生(北大)がこのロッジにツインのシングルユースで予約されていたので、そこに合流させてもらう事にした。ほっこりとくつろいで、部屋で夕食。 |
 |
清野先生も酒飲みなので、スーパーではお酒に合いそうな惣菜類を中心に購入。 |
 |
清野先生が持ってきてくれた食品。このロッジにはレストランはないが、共有スペースに電子レンジがあり、そこで温めたサトウのごはんに、ツブ貝の炒め物をぶっかけて食べたら、とても美味しかった。 |
 |
翌朝、ロッジの窓からの景色。 |
 |
朝8時頃にフォレストカントリー三井の森のクラブハウスにチェックインして、その後優雅に朝食。私はシラス丼と、ビール。朝酒は、よい。 |
 |
この日の参加者で、ラウンド前に記念写真。 |
 |
八ヶ岳連峰を借景にしたコース。素晴らしい。私は火山が好きなので、雄大な山容に見惚れてしまう。 |
 |
昼食。第1グループ。向かって左から中西真先生(東大医科研)、田中ゆり子先生(東邦大学)、杉山諒先生(国立精神・神経医療研究センター病院)、清野先生。杉山先生は元東大ゴルフ部の部長とのこと。この組では、杉山先生と中西先生は、80台でまわられていた。 |
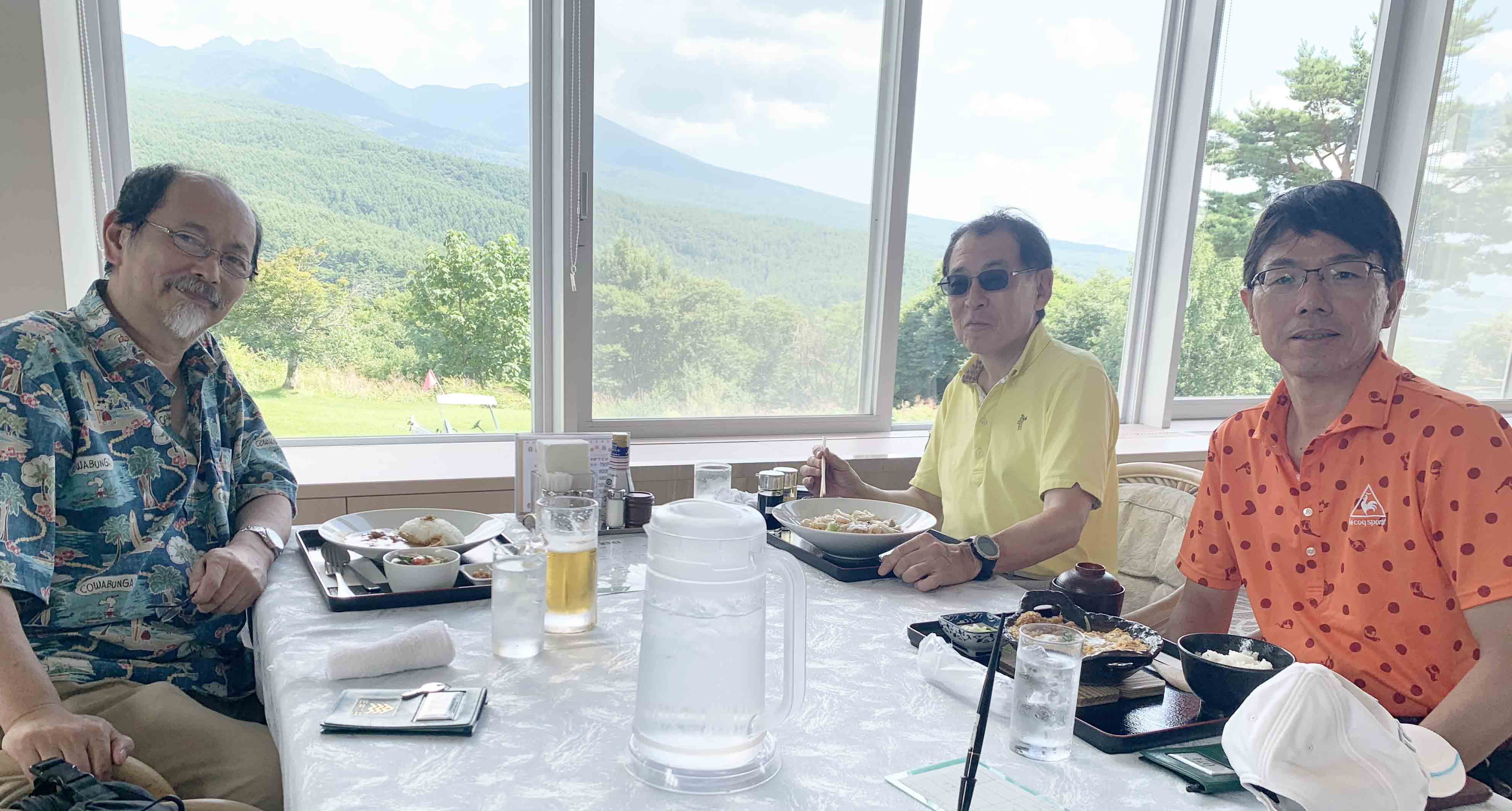 |
第2グループ。向かって右から、伊川友活先生(東京理科大)、北村先生。 |
 |
第3グループ。向かって左から、真下知士先生(東大医科研)、岩間厚志先生(東大医科研)、梶川益紀社長(リバーセル)。 |
 |
夜はコースからは少し離れたリゾートホテル蓼科に宿泊。夕食はビュッフェ形式。美味しかった。 |
 |
夕食時から、佐々木彩先生(昭和大学医学部の大学院生、外科医、写真向かって右から4人目)が参加された。この日のラウンドは、一応「コンペ」という事になっていた。各自のハンデの数字は、隠して選ばれた6つのホールでの成績を元に算出されるという方式。たまたまそのホールで大叩きをしたら、ハンデの数字が増えて、下手な人でも優勝できるチャンスがあるという事になる。いい仕組みだ。この仕組みのおかげで私は真ん中くらいの順位だった。4つのショートホールではニアピン賞が競われ、私は一つ獲得することができた。まず最初の組で、ティーショットが一番カップに近かった人が、名前を書いた旗をその地点に立てておき、次の組の誰かがそれより近かったら、旗を立てる場所と名前を更新するという方式。夕食をいただきながら、各賞が発表され、北村先生が賞品を手渡された。ニアピン賞は、高そうなCallawayのゴルフボール3個セットだった。 |
 |
岩間先生は、この4月から医科研の所長をされている。二人で「所長会談」を行い、附置研の今後の在り方について、熱い議論を交わした(と思う)。 |
 |
食後は、恒例の部屋飲み。これが合宿の大きな楽しみになっている。 |
2025年8月22日(金)
徳田先生御一同、来訪
 |
この日、徳田信子先生(獨協医大解剖学教授)が、その弟君である徳田和央先生(山口県立大教授)、和央先生のお嬢様達と一緒に京大に見学に来られるという話になり、せっかく京都に来られるのであれば、時間が許す限り車で行けそうなところを案内しようと思った。朝9時に京都駅の近くのホテルで御一同をピックアップし、まず比叡山ドライブウェイで山頂のガーデンミュージアムの駐車場へ。写真は10:02。 |
 |
この日のドライブコース。 |
 |
ミュージアムには入らず、延暦寺を拝観。大講堂の脇にある鐘は、100円/回のお布施で、つくことができる。向かって左が貴美さん、右が千夏さん。10:20。この後、根本中堂を拝観し、不滅の法灯を拝んだ。 |
 |
その後、土産物を少し物色してから、11時頃、延暦寺を後にして、奥比叡ドライブウェイを通って琵琶湖側に降りた。さらに北上して、琵琶湖大橋を渡ってから、琵琶湖の東岸を南下し、琵琶湖博物館へ。写真は琵琶湖の東岸を南下している途中。徳田信子先生が車中から撮られたビデオからキャプチャー。11:40。車窓の前方よりに頂(いただき)が見えているのは、先ほどまで居た比叡山。今回の報告記事の中の何枚かの写真は、徳田先生から頂いたものだ。 |
 |
博物館到着後、空いているうちにと、まずレストランに入り、近江牛を使った肉うどんを食した。12:00。 |
 |
琵琶湖博物館の売りは、日本最大級の「淡水魚」水族館があること。チョウザメの大きさには圧倒される。顔つきはサメに似ているが、チョウザメは軟骨魚類ではなく、硬骨魚類であって、サメの仲間ではない。12:28。 |
 |
ビワコオオナマズ。大きな個体は、120cm、20kgに達するらしい。 |
 |
カイツブリが水中を泳ぐ様子を観ることができた。写真は少しわかりにくいが、右下が頭側で、カエルのように足を開閉させて進む。とてもかわいい。水生昆虫などを食べているとの事だ。 カイツブリが水中を泳ぐ様子の動画(約12秒): |
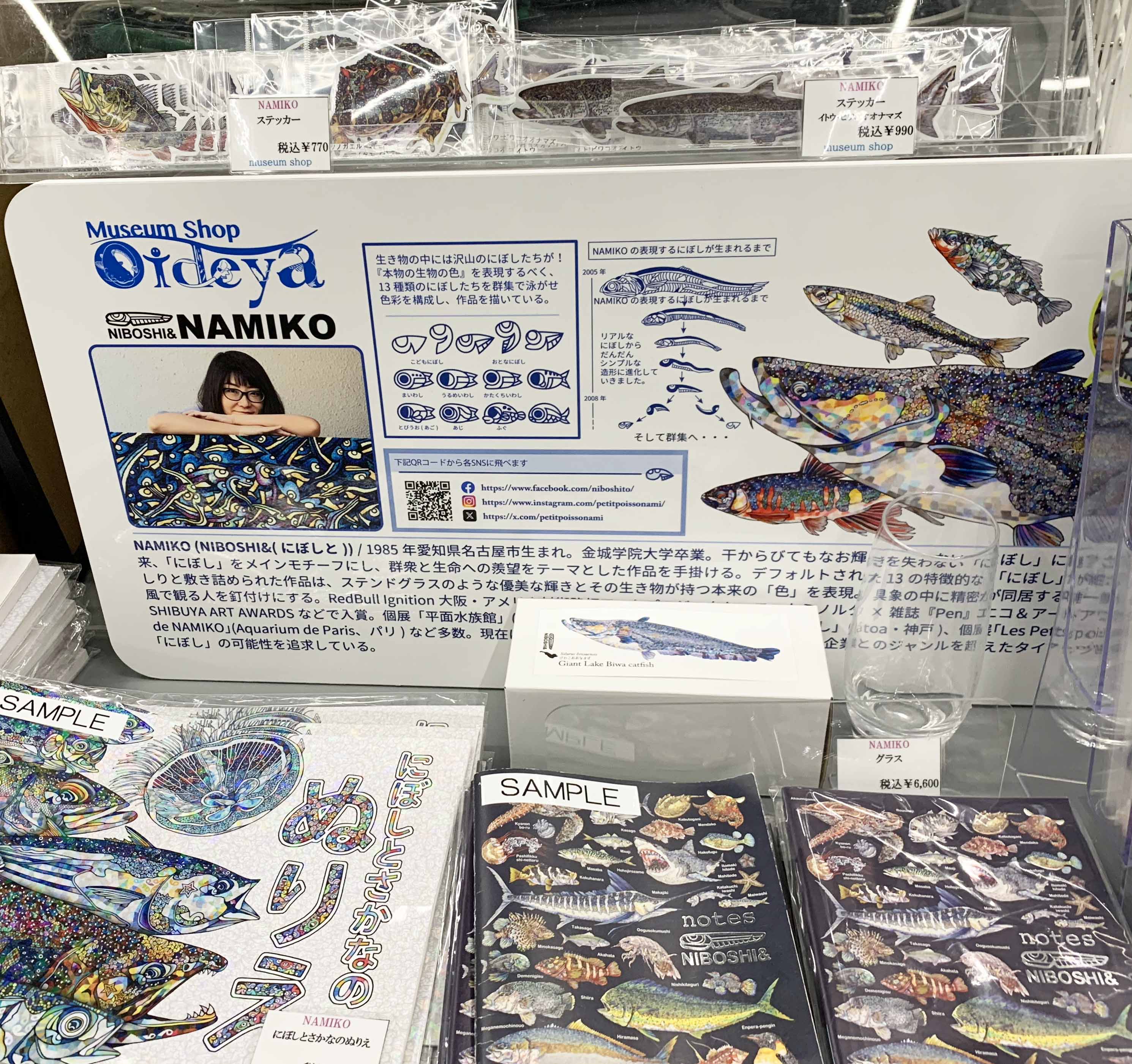 |
ミュージアムショップで、とてもきれいなイラストを見かけた。NAMIKOという人の作品らしい。 NAMIKOさんの作品を紹介しているサイト: |
 |
博物館を13:20頃に出発し、南下して、近江大橋を渡り、浜大津を通って、京大に戻った。写真は14:22。 |
 |
1時間半ほど講義と質疑応答をして、その後研究所をざっと見学。17時頃には、京都駅八条口に送り届けた。姪御様達には、とても楽しんでいただけたようだった。 |
2025年8月21日(木)
川床
 |
この日、ラボのスタッフと川床で夕食。雲がきれいだった。ただ、お盆の頃一旦落ち着いていた暑さが、ぶり返しており、日没後も30度以上あった。とはいえ、いい感じに風が吹いていたので、何とか納涼感はあった。 |
2025年8月21日(木)
木戸君、来訪。
 |
この日、木戸智仁君(奈良女子大学附属中学校2年)が、お母様と共に来訪。小学三年生の時に私が出ていたNHK高校基礎(生物)を見て、免疫学に興味を持ったとの話。免疫学についての講義の中で、脱線話の中で生き物の名前当てクイズをしたところ、全ての名前(クリオネ、オタマボヤ、テズルモズル、ユメナマコ)を知っていて、驚いた。 |  |
2年前にゼスト御池で開催された京都大学の一般向け広報イベント、アカデミックデイ(2023年9月24日の記事参照)にも来てくれていた。私はこの日は裏医生研チャンネル用の収録もしていたので、メタ爺に扮している。 |
2025年8月20日(水)
中馬先生、梶川社長と打ち合わせ
 |
この日、今後の研究の進め方について、リバーセルの梶川社長も交えて、打ち合わせを行なった。その後、「くうかい」で、プチ壮行会。 |
2025年8月19日(火)
一瀬君のセミナー
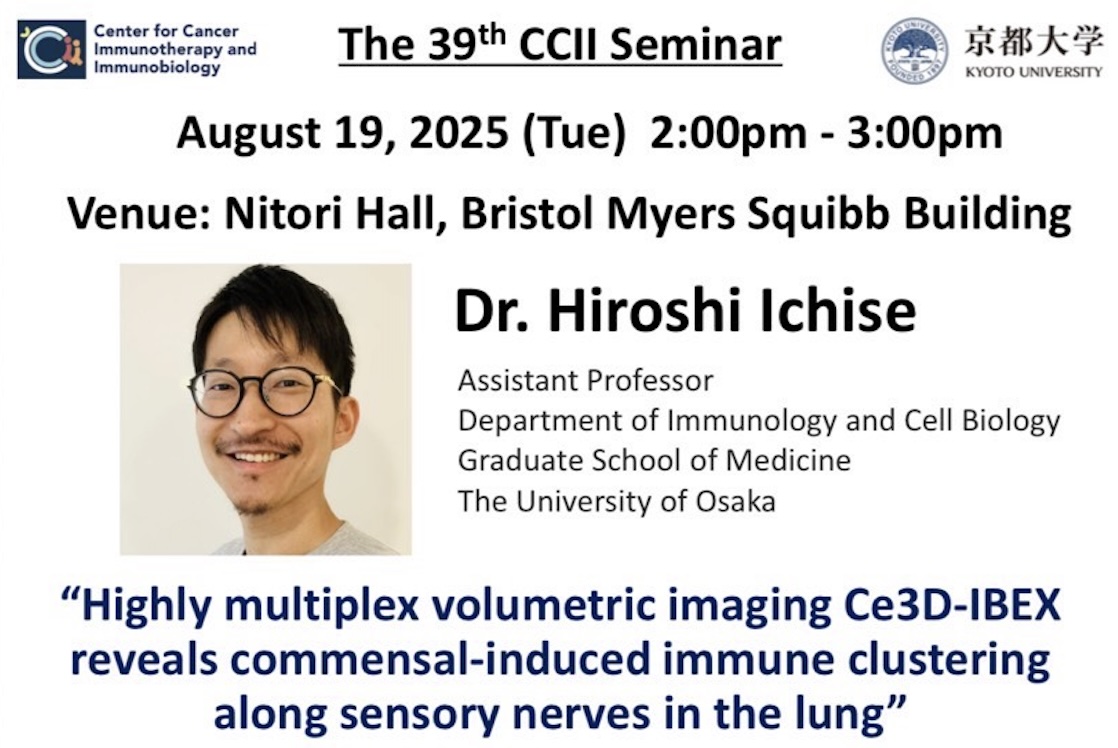 |
一瀬大志君は、河本研で学位を取った後、松田道行研に移り、その後、5年前からNIHのRonald Germainのラボに留学(2020年6月17日の記事参照)。トランプのせいでラボの予算が削られ、帰国となり、現在は石井優先生(大阪大学)のラボで助教を務めているとの話。 |
 |
この日は、CCIIでセミナーがあり、留学中の研究内容についての話を聴けた。 |
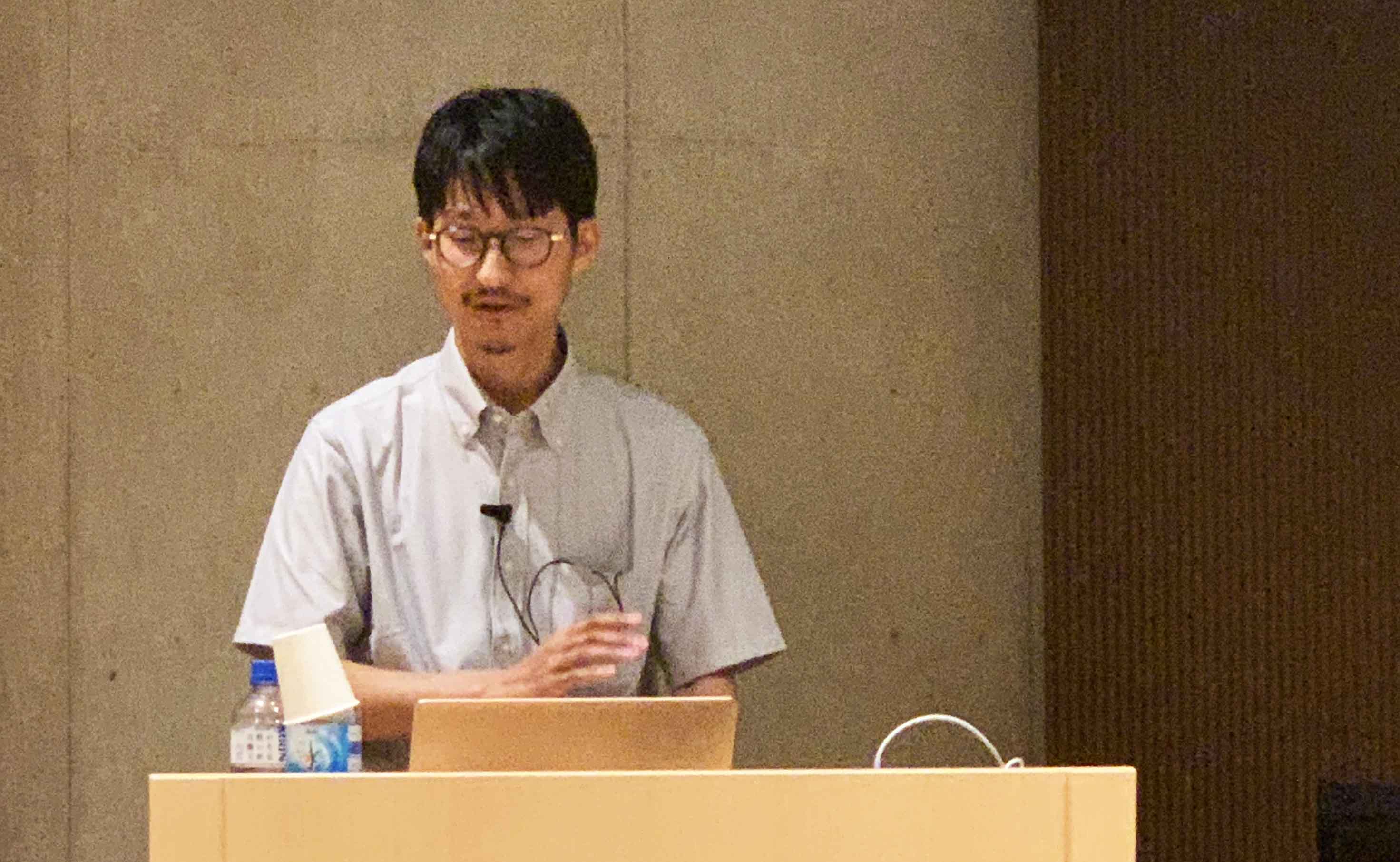 |
組織における40種類の遺伝子発現を3D画像として観察できるという技法(Ce-3D-IBEX)を用いて、肺の中に新しい免疫組織を見出したという話。画像がとてもきれいで、見応えがあった。一瀬君はこの他にも重要な成果をあげていて、最近、筆頭著者論文がScience誌にアクセプトされたとのこと。ウイルス感染に伴う肺の炎症の増悪のメカニズムの話であるらしい。 |
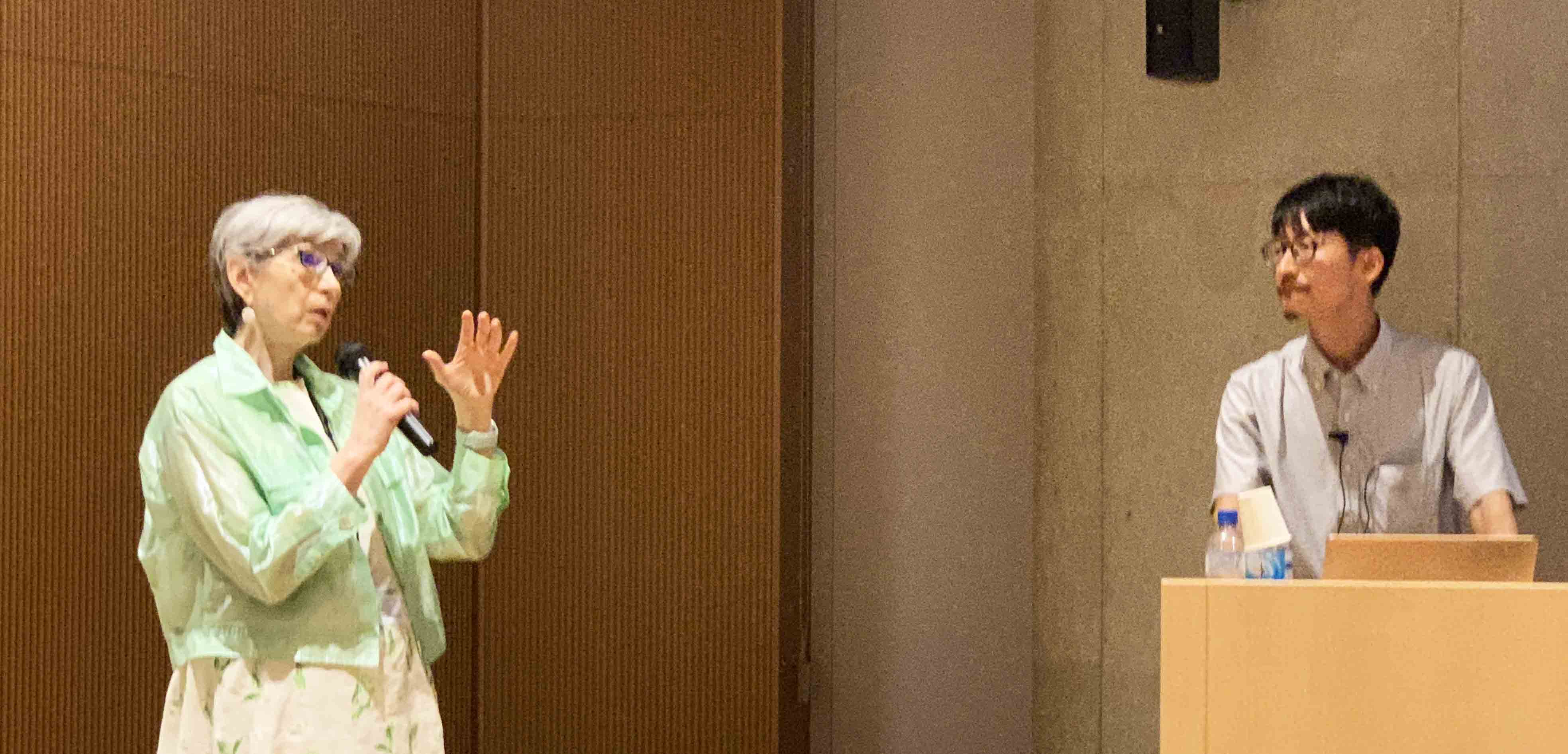 |
今回のホストはSidonia Fagarasan先生(理研IMS、CCII)。相変わらずお元気そうだった。 |
2025年8月18日(月)
夕焼け雲と虹
 |
通り雨が上がった後、教授室の窓から、虹が見られた。 |
2025年8月18日(月)
MMP Eveセミナー
 |
少し前からASHBiの李聖林先生とファイザーの三好聡氏らが中心となって、「数学x医学x薬学」という切り口でのセミナーの企画を進められていて、「医学」からは、私と、椛島健治先生(皮膚科)、柳田素子先生(腎臓内科)がアドバイザーとして参画している。第一回は今年の12月に開催する方向で進んでいるようであるが、この日は、そのキックオフ会という事で、表記のセミナーが開催となった。 MMPセミナーHP: MMPセミナーの案内: |
 |
今回の講師はDr. Saroja Ramanujan。薬物動態の数理生物学的アプローチの話なので、自分達の研究とはあまり関係がないかと思って気楽に聴いていたら、細胞製剤の話もあって、勉強になった。 |
2025年8月16日(土)
ヤマトxココアシガレット
 |
この日の夜、五山送り火を観覧しようと、親族で集まりがあった。その際、私の妹が、大阪なんばで開催された宇宙戦艦ヤマト放映50周年記念展示会「宇宙戦艦ヤマト全記録展」(7月19日-8月3日)のお土産をくれた。庵野秀明がプロデュースしたとの事。当時の企画書、設定画、原画、背景画などが展示されていたらしい。庵野秀明は劇場版ヤマトを新たに制作するとの話なので、とても楽しみだ。なお、ココアシガレットというのは、子供用の駄菓子で、昔よく流行っていた。これはこの展示会用のコラボ商品との事で、シガレットのイラストがヤマトの砲身になっていて、面白い。 |
 |
左の写真は通常の商品(Wikipediaより拝借)。ココアとハッカが混じった甘いお菓子で、子供がタバコを吸う大人の真似をして、喜んでいた。一時期喫煙を助長するという危険性から生産を自粛していたらしいが、最近はまた販売しているようだ。 |
2025年8月8日(木)
読売新聞でリバーセルの万博展示が紹介された
 |
この日の読売新聞の朝刊の12面の「医療ルネサンス」という医療関係の連載記事で、「万博が描く未来」という文脈で、リバーセルの万博での展示が紹介された(赤枠で囲った部分)。少し前の記事に書いたが、読売新聞は昨年リバーセルの万博での展示が決まった事を受けて昨年12月に朝刊一面で大きく取り上げてくれている(2024年12月14日の記事参照)。記事の中で私は「新たな感染症が流行しても、キラーT細胞の点滴で治せる時代が来る」と言っているが、言いっ放しにならないように、実現に向けて頑張ろうと思う。 |
2025年8月8日(木)
京大オープンキャンパスで医生研を案内
 |
この日と前日(8月7日)に、京大のオープンキャンパスの中のイベントの一つとして、南西地区見学ツアーが開催された。10人くらいの見学者が一組で、薬学部の薬草園、CiRA、医生研の3カ所を、1時間半くらいで周るというツアー。午前中に2組、午後に1組。医生研の滞在時間は25分。実際に使っている実験室を見てもらうということで、河本研の実験室をコースに組み込んだ。他は、ES細胞製造施設と、P3実験室を見てもらった。写真は、私が液体窒素タンクの中からケーン(バイアルをセットする棒)の入ったキャニスター(筒状の容器)を取り出して見せているところ。 |
 |
医生研の中での引率役は河本研が務めた。7日は西村君と板原君、8日は永野君と私。写真はES細胞製造施設で、説明役は高田圭助教と川瀬栄八郎准教授が担当。中には入れないので、外から見るだけ。左の写真で、説明しているのは高田先生。 |
 |
P3実験施設の見学。説明役は、7日は朝長研、8日は野田研が担当。ここも中には入れないので、外から見るだけであるが、施設の中で着る服を、デモしてくれていた。左の写真で、説明しているのは野田研の村本裕紀子助教。 |
2025年8月1日(金)
リバーセル関係者で万博展示の慰労会
 |
少し前の記事に何度か書いたが、リバーセルは大阪ヘルスケアパビリオンで6月24日〜30日の1週間、ブースに展示を出した(2025年6月24日の記事参照、6月26日の記事参照、6月30日の記事参照)。万博に展示を出すことになったおかげで、読売新聞では昨年12月に万博関連記事として朝刊一面で紹介されたり(2024年12月14日の記事参照)、京都新聞では万博開幕の日に朝刊一面で紹介されたりした(2025年4月13日の記事参照)。これは梶川社長や畑中さんを中心としたチームが大阪産業局の公募を勝ち抜かれたおかげで(2024年7月23日の記事参照)、その後は畑中さんと大久保さんが奔走して、展示内容をデザインし、ポスターや動画を作ってくれた。また、お二人には「細胞キャラをテーブルの上に置こう」というアイデアも出していただき、それに応えて宮武さんがまんじゅう大の細胞キャラのぬいぐるみを作ってくれて、観客には大いにウケていたようだ。万博展示関係の皆様、お疲れ様でした! なお、この日は三宅俊介さん(写真手前左側)の送別会も兼ねていた。三宅さんはリバーセルのごく初期からのメンバー(2021年3月31日の記事参照)で、本業が忙しくなったとのことでリバーセルを去られるが、今後も適宜協力して頂けるとのこと。5年間、ありがとうございました! |
2025年7月31日(木)
清野先生と「くうかい」で会食
 |
清野先生は炎症・再生医学会(7月31日〜8月1日、於ホテルオークラ)で京都に来られていて、この日の夕刻、研究室で少し共同研究についての打ち合わせをしてから、くうかいで会食。清野先生によると「くうかいは河本研のラボニュース欄によく登場するので、一度来てみたかった」とのことだった。清野先生はかなりの酒豪なので、つられてかなり飲んでしまった。 |
2025年7月30日(水)
京大のお酒「カンフォーラ」試飲会
 |
少し前に京大の時計台ホールで部局長の懇親会が開催され、そこで京大農学部プロデュースの日本酒「カンフォーラ」が供された(2025年7月22日の記事参照)。「カンフォーラ」は、京大のシンボルツリーである「樟(くすのき)」のラテン語名(Camphora)。会の終了後、残っていたお酒を少し持ち帰らせていただいた。すでに開栓してあったので早く飲む必要があることから、お酒好きの人達に声をかけて、「納涼カンフォーラ試飲会」を開催した。なお、カンフォーラは京大生協時計台ショップあるいは北部購買で2200円(税込)で買えるらしい。 |
 |
近くのライフに買い出しに行って、日本酒の肴になりそうな惣菜などを買い、一部をあらかじめ各自の皿に盛り付けて配膳。茎わかめ、ツブ貝のあえもの、うにくらげ、松前漬け、シラス、ネギ入りだし巻き卵、など。こういうアテをつまみながら、ちびちびと一献傾けると、日本に生まれて良かったとしみじみ思う。 |
 |
その他、中トロ、いくら、ナスの煮浸し、レンコンサラダ、かっぱ巻きなども供した。 |
 |
シメのご飯ものは、ミニ鰻丼。カンフォーラはとても美味しくて、皆、大満足だったようだ。 |
2025年7月28日(月)
金原さん来訪
 |
藤田医大河本研のテクニカルスタッフである金原理恵さんが、この数週の間、週に2、3回、フィーダーフリー培養法を習いに来られていた。福永淳一先生(研究員)(写真向かって右端)が指導にあたってくれた。この日の作業終了後、ラボの近所のくうかいで会食。 |
2025年7月27日(日)
免疫ふしぎ未来2025に参加
 |
「免疫ふしぎ未来展」は免疫学会が主催する科学コミュニケーションイベントで、毎年夏にお台場の科学未来館の7階のスペースで開催される。今年は、私はショートトークで話をするのと、打ち上げパーティーでNegative Selectionが演奏をするという形で参加。写真は、銀座のスタジオで、出演者で前日練習しているところ。中司寛子先生(千葉大学)が撮られたもの。 |
 |
今回は、鈴木春巳先生に登場頂いて、「逆襲の助教」と「リンパ節ひとり旅」を歌っていただくことになっている。久しぶりに一緒に演奏して、楽しかった。これも中司先生が撮られた写真。 |
 |
練習に参加したメンバー全員で記念写真。 |
 |
当日、開場の10分前。すでにすごい行列になっている。実験コーナーの混雑を緩和するために、来場と実験コーナーを事前に予約できるようにしたところ、来場の事前登録が2600人もあったらしい。「事前予約」とか聞くと、「万博か!」とツッコミを入れたくなる。 SNSでの発信や口コミで人気が広がったのだろうと思われる。このイベントは2007年から始まったので、18年の歴史があるが、10年くらい前までは、未来館の入り口でビラ配りをして集客していた事を思い出すと、隔世の感がある。いい展示を続けていると、世の中がちゃんと気がついてくれるということであろう。以下のリンクは、2022年に、裏医生研チャンネルで取材した時の動画。 裏医生研チャンネル第8回:免疫ふしぎ未来展を体験してみた!(YouTube動画): |
 |
何年か前から、ショートトークの会場も、同じ7階にある大きなホールに移っている。 |
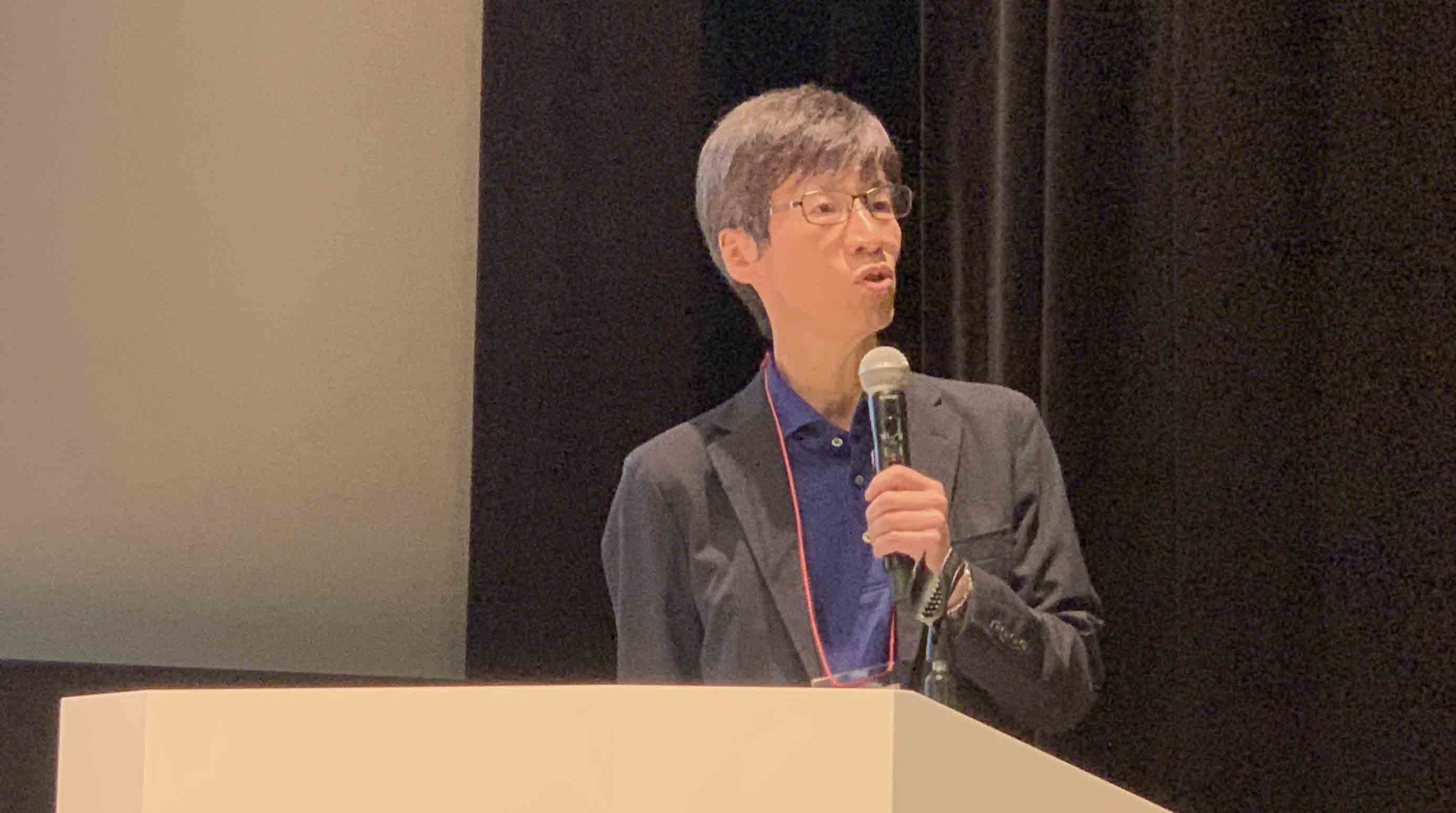 |
免疫学会の理事長である竹田潔先生(大阪大学)による開会の挨拶。この後、講演もされた。 |
 |
ショートトークのテーマと時間割。 |
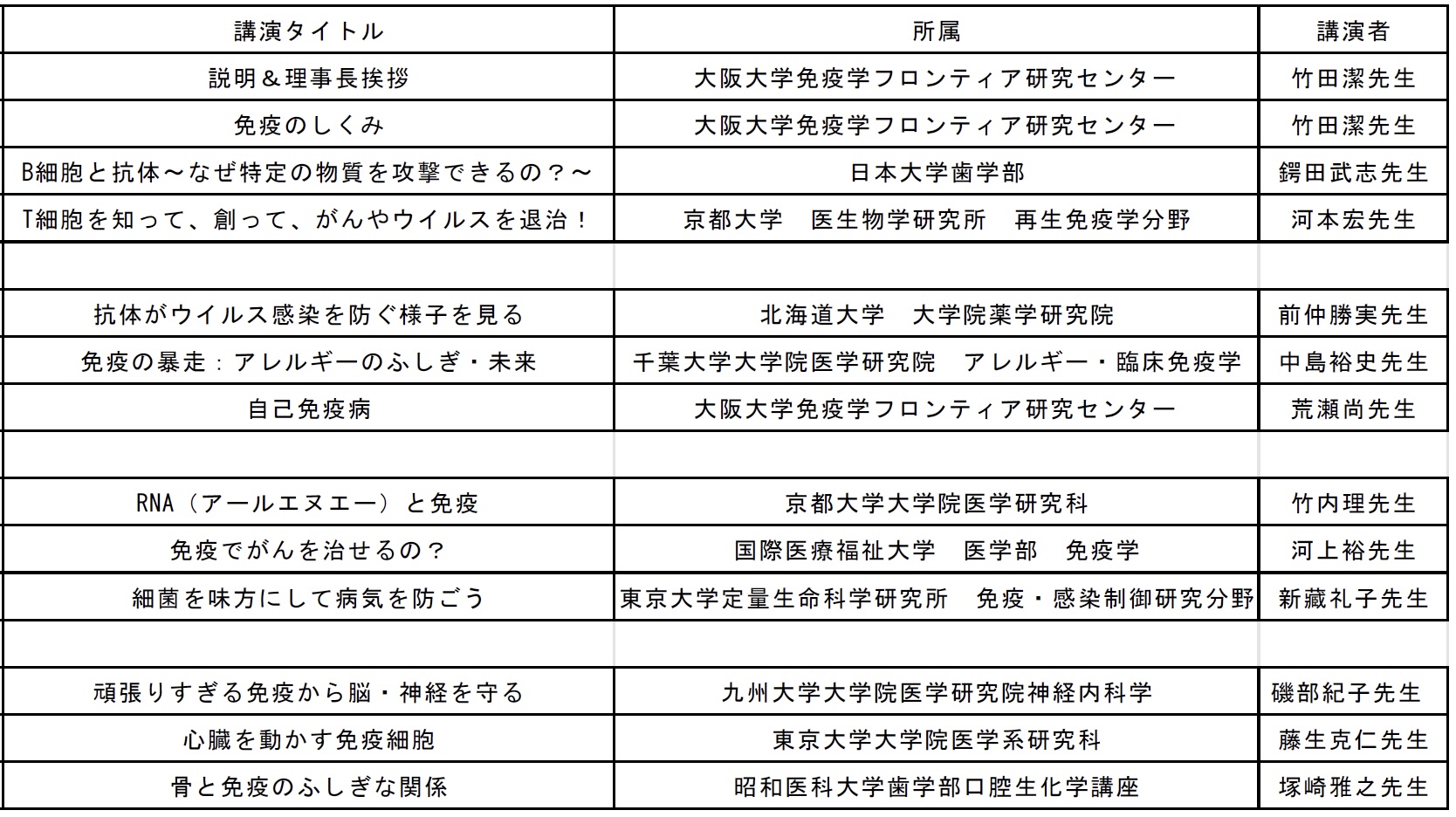 |
タイトルと演者一覧。 |
 |
演者の写真。実行委員会が37ページに及ぶスタッフ用の「開催マニュアル」を作っていて、その中には、「誰が誰か」をスタッフが分かりやすいように、このように顔写真が載っている。 |
 |
白血球を染色して観察するコーナーは、相変わらず大人気だ。 |
 |
以前ショートトークで使っていた部屋もこうやって展示で使っているので、展示スペースに余裕がある感じ。 |
 |
展示や実験スペースのそれぞれがとても充実していた。DNA抽出実験コーナー。 |
 |
かつて私がよく担当していた生き物コーナーも健在。 |
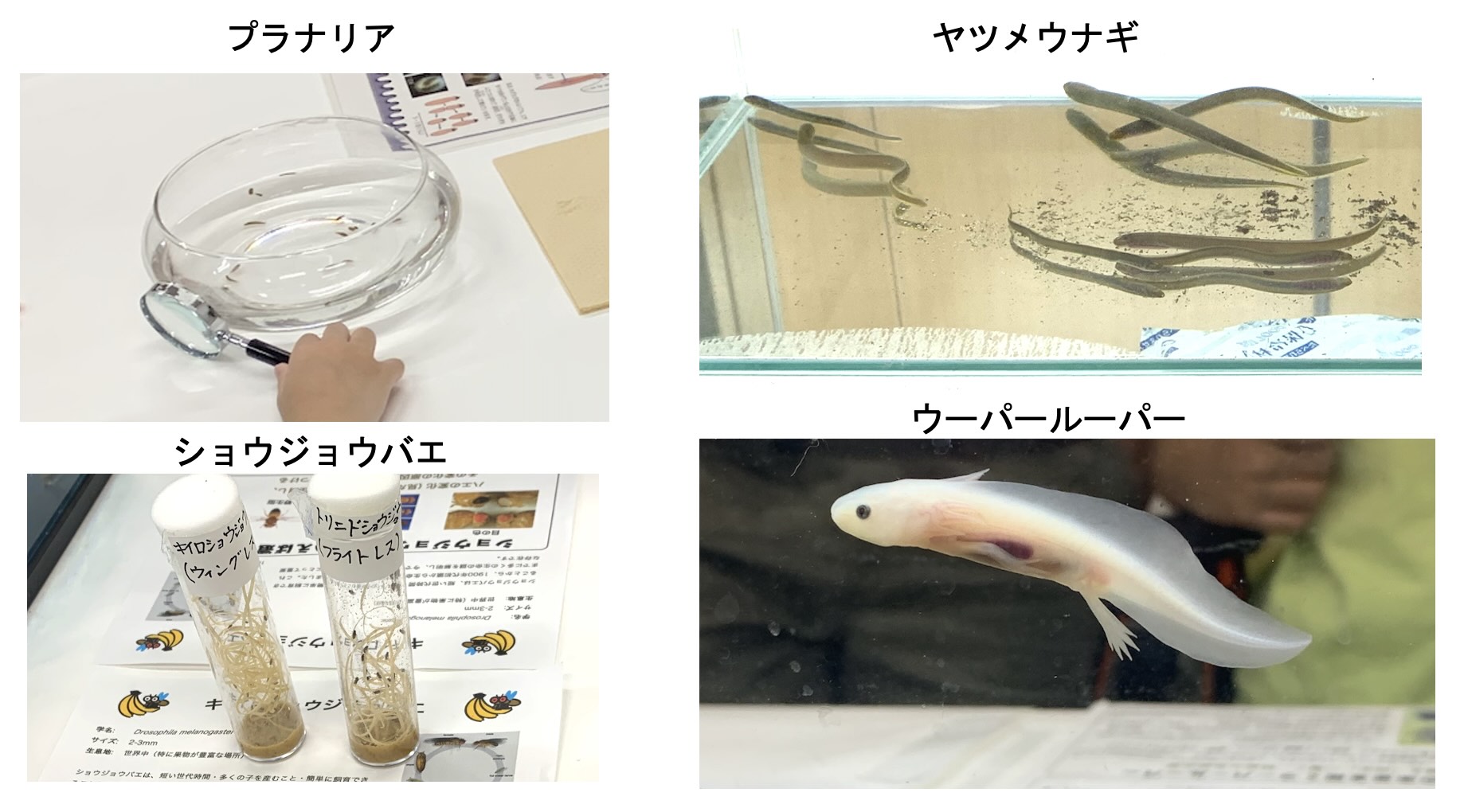 |
プラナリア、ヤツメウナギ、アフリカツメガエル、ウーパールーパー、ショウジョウバエなどが見られた。プラナリアは、欲しい人への配布も行っていた。 |
 |
もともと名物だった寄生虫コーナーが拡充。 |
 |
大きなサバが3尾並べられて、「アニサキスを見つけよう」コーナーになっていた。これはインパクトが大きい。 |
 |
名物の「サナダムシに触ってみよう」コーナーも、容器が大きくなって、サナダムシの大きさが実感できるようになっている。 |
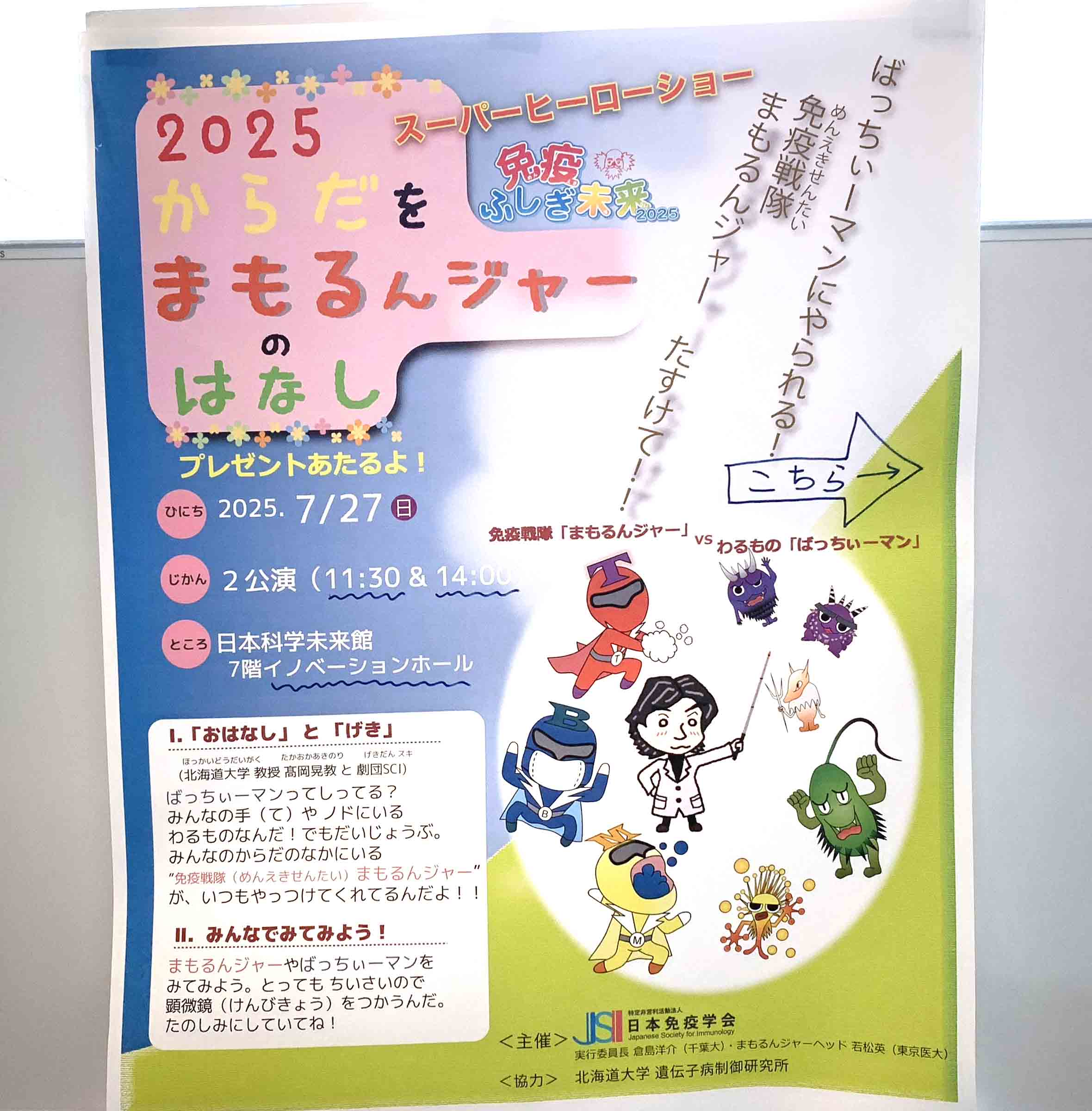 |
今回は、高岡晃教先生(北海道大学)が、ずっと前から就学前の子供達を対象に演っているイベント「からだをまもるんじゃー」が参入。 |
 |
1回40分くらいのショーを、一日2回上演。大人気だ。 |
 |
食細胞がカビと戦っている。 |
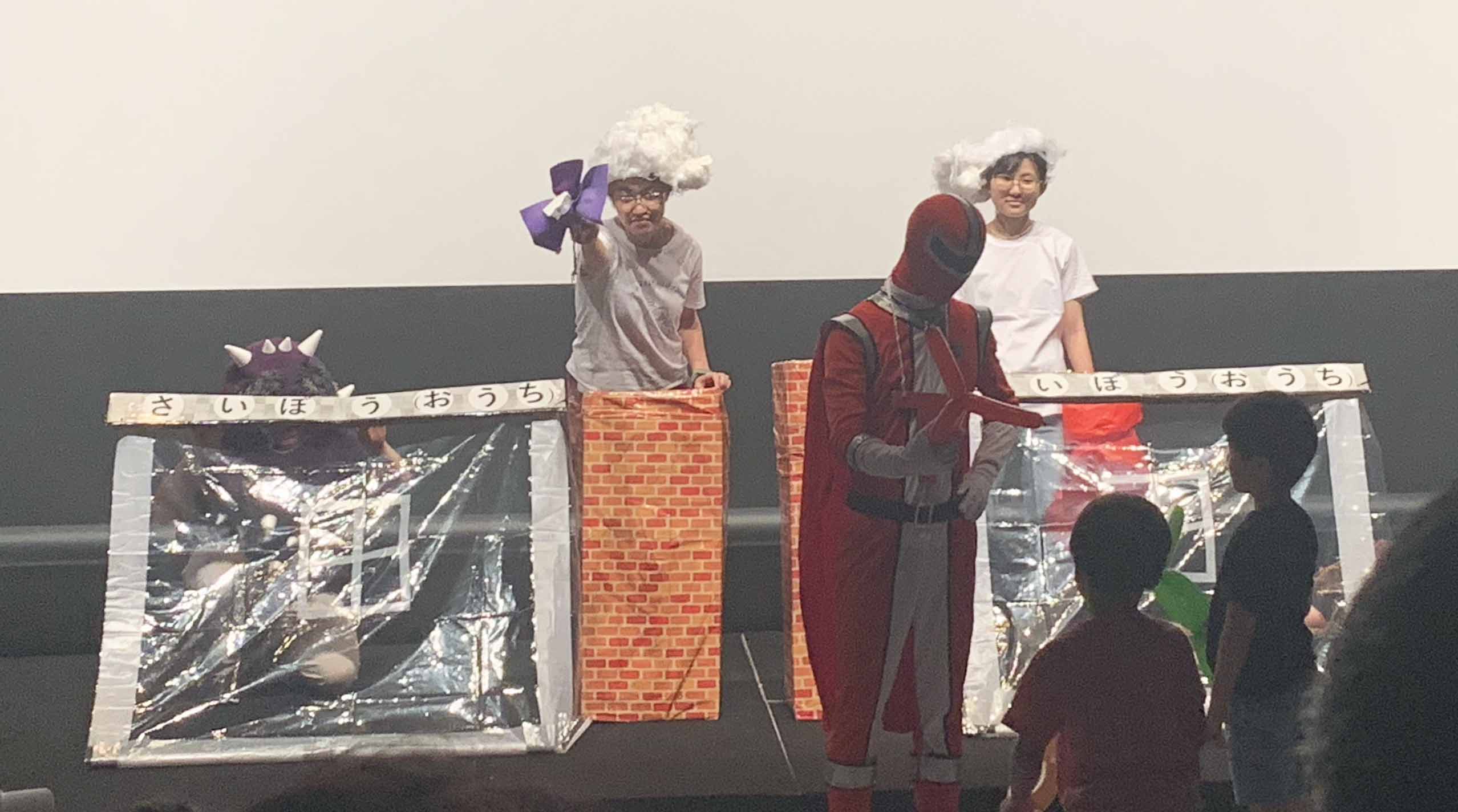 |
細胞の中に隠れたウイルスを、キラーT細胞がT細胞レセプター(作中では「ビリビリ棒」)で見つけてやっつけるという演出。素晴らしい。 |
 |
公演終了後、記念写真。 |
 |
控え室でショートトーク演者の方々と昼食。向かって左から河上裕先生(国際医療福祉大学)、竹内理先生(京都大学)、私、鍔田武志先生(日本大学)。 |
 |
「博士と話そう」のコーナー。科学コミュニケーション活動の基本形だ。 |
 |
打ち上げパーティーは、「銀座タクト」で催された。6年ぶりだ(2019年8月4日の記事参照)。実行委員長である倉島洋介先生(千葉大学)の挨拶。 |
 |
今回の打ち上げパーティーは、若い人が多く、80人くらいが参加して、盛会だった。 |
 |
フロアはぎっしりで身動きが取れないくらいだった。 |
 |
コロナ前は食べ放題メニューがあったが、コロナでスタッフが減り、料理はピラフなど、限られたものしか出せないとのことであったが、代わりにケータリングを使うのはOKとのことで、打ち上げパーティー側で12万円分くらいを取り寄せたとの事。一人あたり1500円分くらいであるが、かなり十分な量があった。フロアはギュウ詰めだったので、食べ物が乗ったトレーを回していくという方式が取られた。 |
 |
ライブが始まった。短い前奏(Openingsというオリジナル曲のイントロ部分)の後、今回のスタッフが歌う曲。一曲目は、中司寛子先生(千葉大学)(血液標本責任者)による「キューティーハニー」(倖田來未バージョン)。今回のライブに合わせてメルカリで買ったとかいうキューティーハニーのシャツが映える。この写真と次の写真は、中司研の学生さんが撮ってくれたもの。 |
 |
ドスが効いた歌声で締めくくる「ハニーフラッシュ!」が印象的だった。 |
 |
本村泰隆先生(東京理科大)(アトラクション統括)が「Escape」(ムーンチャイルド)を熱唱。とてもかっこいい曲だ。この写真以後のライブの写真は、中司先生が撮ってくれたもの。 |
 |
若松英先生(東京医大)(まもるんじゃー責任者)と「ええねんコーラス隊」による「ええねん」(ウルフルズ)。若松先生は何度か打ち上げライブでこの曲を演っており、さすがによくこなれていた。 |
 |
倉島先生による「ウィーアー!」(ワンピース初代主題歌)。少し前に記事に書いたように、普通にバンドでやるような曲ではなく、練習では大変苦戦したが、本番は、バンド演奏としては大きな破綻なくこなせた。 |
 |
倉島先生の歌は、とても上手くて、バリバリの安定感。麦わら帽子によって、ルフィ感もバッチリ。 |
 |
「ウィーアー!」、と盛り上がっているところ。ライブの熱気が伝わる、いい写真だ。 |
 |
トリは、鈴木春巳先生(国際医療センター)による「逆襲の助教」(下記リンク参照)。2022年の分子生物学会のテーマ曲として作ったNSのオリジナル曲。「学会でボロクソに攻撃されて失意のどん底に沈んだ助教が、夢枕に立った謎の老人に励まされ、奮い立って学会での議論に再度挑む」というような話。 【第45回分子生物学会年会公式テーマソング】逆襲の助教(YouTube動画) |
 |
鈴木先生は、ミュージックビデオを作製した時の装束で、絶唱。それにしても、すごい「いかつさ」だ。後ろでキーボードを弾いているのは、幸谷愛先生(大阪大学微研教授)。少し前の国際数理生物学会の懇親会のライブ(2025年7月10日の記事参照)では、大久保さんがベースを弾いたので、代わりにキーボードを弾いて頂いた。今回は、ベースは清野先生に弾いて頂いているが、「逆襲の助教」をライブで再現するにはキーボードがもう一人必要ということがあって、参加して頂いた。幸谷先生は、高校生くらいまでヤマハミュージックスクールの英才コースで鍛えられた強者で、加わって頂くと、大きな戦力になる。今回は、前出の難曲「ウィーアー!」でも、大活躍頂いた。 |
 |
北村先生は、今回はカツラを被って登場。「逆襲の助教」は、リズムパターンがコロコロと変わるのと、いわゆる「キメ」が多いので、かなり難しく、じっと曲に集中されているようだ。 |
 |
Negative Selectionのベースは普段は石戸聡先生(兵庫医大)であるが、今回は所用があって参加できず、代わりにベースを担当いただいたのは、清野研一郎先生(北海道大学遺制研)。清野先生は、私が理研にいた頃のNegative Selectionの、初代ベーシスト(2010年4月3日の記事参照)。 |
 |
Negative Selectionの音楽のレベルを支えるキーパーソン、キーボードの大久保博志さん(有限会社プログレス)。 |
 |
逆襲の助教では、曲の途中で謎の老人が失意の助教を励ます「語り」が入る。今回は、元の分子生物学会用の語りを免疫学会バージョンにして、「さすれば、命を統べる小さき“免疫細胞”の理(ことわり)が明らかになろうぞ」と語った。このキャラは、マグマ大使の「アース様」のイメージ。中司先生、いい写真を沢山撮って頂き、ありがとうございました! |
 |
シニアの先生を囲むテーブル。 |
 |
今回のイベントの各コーナーの責任者が挨拶。お疲れ様でした! |
 |
二次会は、有志で、近くのカラオケ(パセラ)へ。今日は一日、楽しかった! |
2025年7月22日(火)
部局長会議等合同懇親会
 |
表記の会が時計台ホールで開催された。18時過ぎ、徒歩で会場に向かう道中、京大病院の次世代医療・iPS細胞治療研究センター(Ki-CONNECT)(写真中央の建物)の上にかかる立派な積乱雲。私は積乱雲を見るのが好きで、これまでもラボニュース記事では積乱雲の写真を何度も使っている。以下のリンクは何年か前に鴨川の西の岸から撮ったタイムラプス動画で、逆襲の助教のMVの中で使われた。 鴨川から撮った積乱雲のタイムラプス動画: |
 |
湊総長の挨拶。大学にこれから起こるであろう競争的な状況について、檄をとばされていた。 |
 |
会場。 |
 |
今回は農学部が担当部局だったので、農学部のプロデュースで作られた日本酒「樟玉(カンフォーラ)」が供されていた。カンフォーラは、京大のシンボルツリーである樟(くすのき)のラテン語(Camphora)名。 |
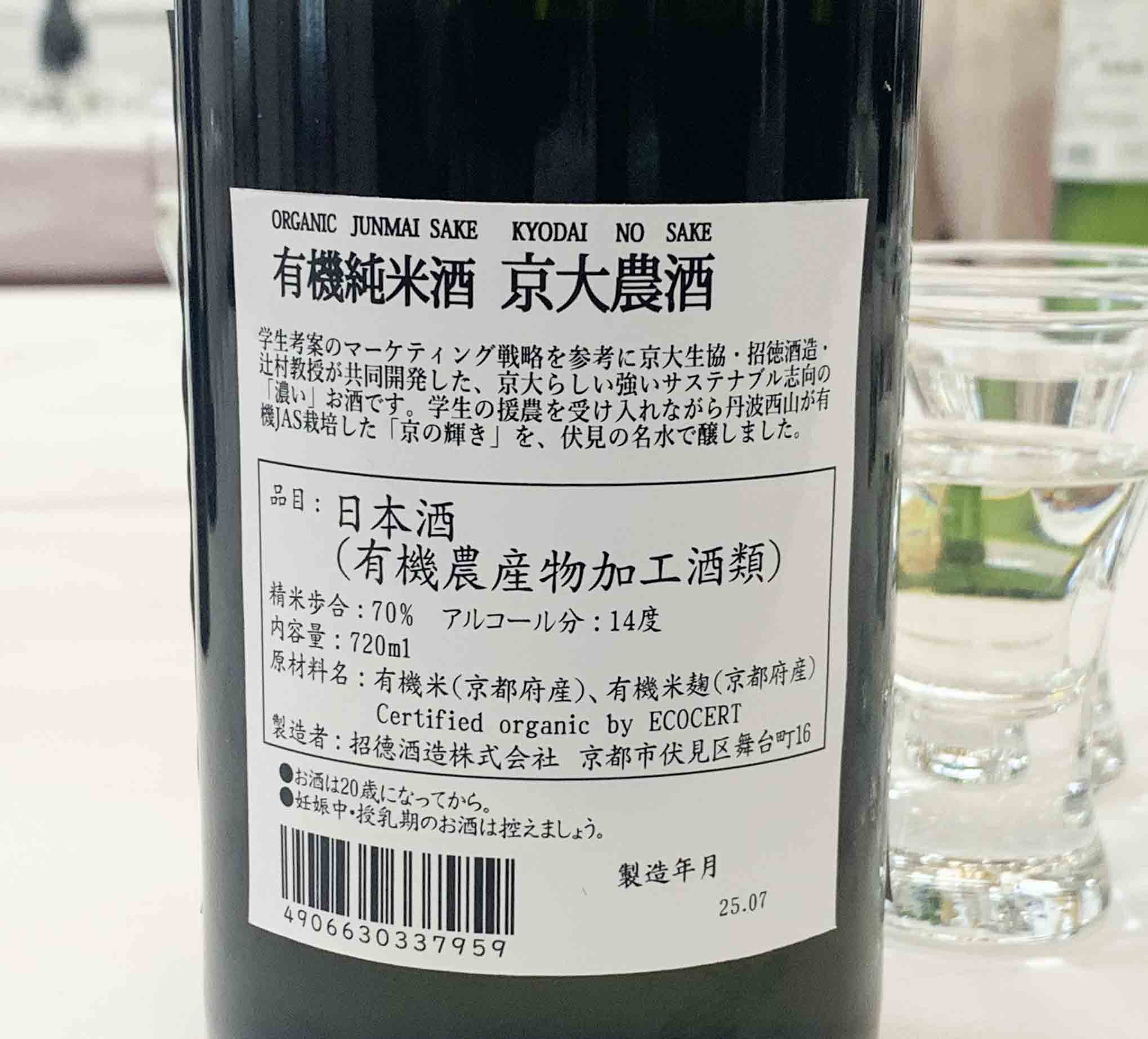 |
能書には京大らしい「濃い」お酒とあるが、雑味や酸味はあまりなく、辛口の、割とすっきりとした味だった。とても美味しかった。京大生協時計台ショップあるいは北部購買で2200円(税込)で買えるそうだ。 |
 |
京大発和牛ブランドもあるらしい。ネット情報によると、「京都大学大学院農学研究科附属牧場で生まれ、衛生的で高水準の健康管理下で育った黒毛和牛をブランド化した」ものらしく、京都市中央食肉市場に上場されていて、それなりの価格で取引されているようだ。とても美味しかった。 京都大学発和牛ブランド「京大紅牛(くれなゐビーフ)」が京都市中央食肉市場に初上場(2022年8月5日): |
 |
帰り際に、平島崇男(ひらじまたかお)先生(写真中央)と少しお話をした。平島先生は元理学部長で、現在は京都大学の理事、副学長、大学院教育支援機構長を務めておられる。私の兄は京大理学部の地学系の大学院で学んでいたが、当時、平島先生はその教室の助教で、兄の研究を指導していたという。兄の研究テーマ(岡山県でのフィールドワーク)の話や、兄が頑火輝石(がんかきせき)と言う鉱物名で呼ばれていた話などを聞けた。京都大学で兄の話を聞くのは初めてだ。なお、兄は卒業後は日本電気硝子に就職した。写真向かって右は研究連携基盤長の中野伸一先生(生態学研究センター)。 |
2025年7月17日(木)ー18日(金)
Singapore Cell and Gene Therapy (SCGT) 2025に参加
 |
表記の会がシンガポールで開催された。私はキーノートスピーカーとして参加した。 |
 |
前日入り。宿泊したホテル(Park Avenue Rochester)。 |
 |
ホテルの部屋。 |
 |
寝室。キッチンもあり、居心地は良かった。 |
 |
ホテルから歩いて3分くらいのところに大きなショッピングモールがあった。 |
 |
日本製の食料品専門の店。 |
 |
シンガポールドルは、110円くらいだから、日本酒の4号瓶は軒並み5000円くらい。日本の4倍くらいか。 |
 |
カップ麺は日本の2倍くらいの感じ。 |
 |
米は5kgで5500円。日本と同じくらいだ。 |
 |
別のスーパーでは日本の弁当の様なものが売られていた。この鮭弁当は800円くらいということで、日本よりちょっと高め。 |
 |
サンドイッチは2倍くらい。 |
 |
フードコートで夕食。 |
 |
こういう日常的な食べ物で物価を測るのが良いと思われる。500円-700円くらいということになるので、日本よりやや安いと言えそうだ。 |
 |
前のパネルの中段左端のLor Mee(ローミー)を食した。 |
 |
シンガポールやマレーシアで人気があるらしい。酸味が少しある、とろみがついたスープで、麺は太め。トッピングはゆでたまご、チャーシュー、春巻きのような揚げ物など。普通に美味しかったが、また絶対食べたいというほどではなかった。 |
 |
会場は、Matrixという名前のビルの中。ホテルからそう遠くなかったが、朝夕は送迎バスを使えた。 |
 |
会場のホール。結構大きな会だった。 |
 |
今回のオーガナイザー。Jonathan Loh教授とは、今年3月にタイで開催されたシンポジウムでご一緒した(2025年3月3日の記事参照)。 |
 |
コーヒーブレーク。若い参加者が多く、アジアの学会の熱気が感じられた。 |
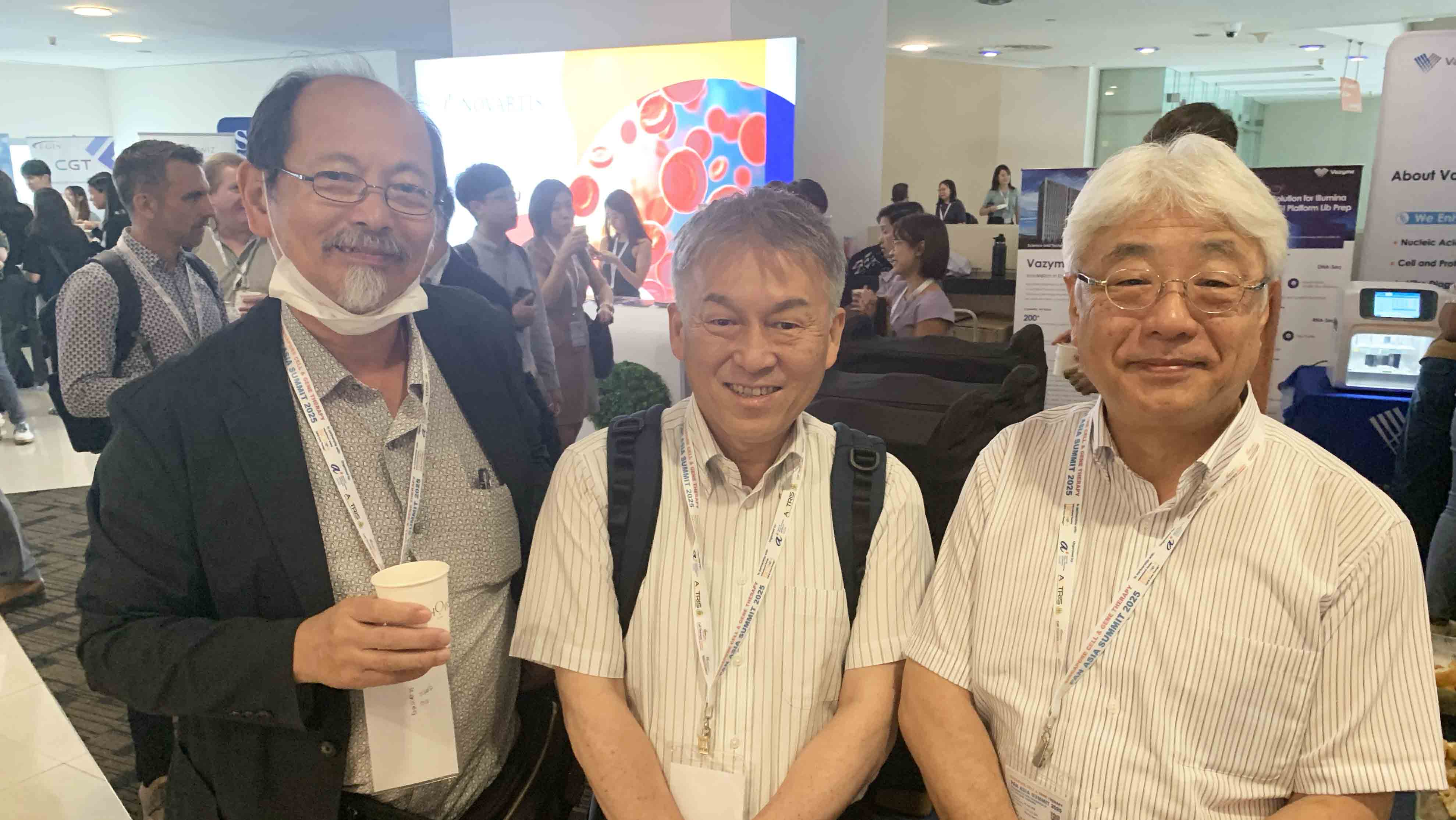 |
川真田伸新先生(向かって右端、神戸細胞療法研究開発センターセンター長)、紀ノ岡正博先生(大阪大学)と。 |
 |
昼食。 |
 |
会長招宴のディナー。 |
 |
同じテーブルの人達と記念写真。 |
 |
鈴木邦彦氏(メディネット、写真向かって左端)が、Miguel Forte氏(International Society of Cell and Gene Therapy :ISCTのPresident、Kiji TherapeuticsのCEO)を紹介して下さった。 |
 |
川真田先生と、タイのマヒドン大学の幹細胞グループ(SiSCR)の人達と。左から二人目はChanchao Lorthingpanich先生。3月のシンポジウム以後、タイのSiSCRのグループ、Loh教授を中心とするシンガポールのグループ、医生研のES細胞研究センターのグループの3者で、Zoom会議で交流を続けることになっていて、6月25日に第一回が開催された。Lorthingpanich先生は、その会のオーガナイザー役をされている。 |
 |
SiSCRのメンバーの一人、Sudjit Luanpitpong先生の講演。CAR-NK細胞療法の話をされた。 |
 |
今回のキーノートスピーカーの一人、Andras Nagy教授(トロント大学)と。彼の講演の中では、細胞療法の安全性と有効性を確認しながら進めることの大切さを強調するとともに、汎用性の高い細胞の作製についての話(Cell Stem Cell, 32:710, 2025)(HLAをノックアウトしなくても、8種類の免疫抑制性分子を発現させておけば、移植片が免疫拒絶を受けないという話)を聴けて、とてもおもしろかった。Nagy先生も、私の発表の中にあった超汎用性技術に興味を持ってくれた様だった。 |
 |
この日の夕食は、前出のホテルの近くのフードコートで、シンガポールカレーを食した。ココナッツミルクが入っていて、タイのグリーンカレーに近い感じ。とても美味しかった。 |
 |
シンガポールのチャンギ空港には、「ジュエル」というドーム型の商業施設の中で、庭園や大きな室内滝が観られるとの事であったが、ゲートエリアに入る前に観にいく必要があり、この日は時間がなかったので諦めた。写真は、ゲート内からみた「ジュエル」。 |
 |
滝は見損ねたが、空港のゲート内に、写真のような水槽や植物が設えてあり、いい感じだ。 |
 |
空港で、チキンライス(海南鶏飯:ハイナンジーファン)にようやくありつけた。私はチキンライスが好きで、タイ料理屋に行くと、カオマンガイ(タイのチキンライス)をよくいただく(2021年10月13日の記事参照)。前出の商業施設内にもチキンライスを供する店は有ったが、なぜかアルコール類を置いてなくて、持ち込みもNGだったので、諦めた。 |
2025年7月15日(火)
バンド練習
 |
一つ前の記事に書いたが、今回の免疫ふしぎ未来展打ち上げライブでは、難しい曲が多い。それで、この日に追加で清野先生抜きのメンバーで集まって、追加で練習することになった。練習前に、スタジオに山本正人先生(ミネソタ大学外科基礎・トランスレーショナル研究部教授)が北村先生と一緒に来られた。学会で日本に来られていて、北村先生と打ち合わせをされていたとの事だった。山本先生は腫瘍溶解性ウイルスの開発研究などをされていて、以前に共同研究の可能性について打ち合わせをしたことがある(2020年10月9日の記事参照)。 |
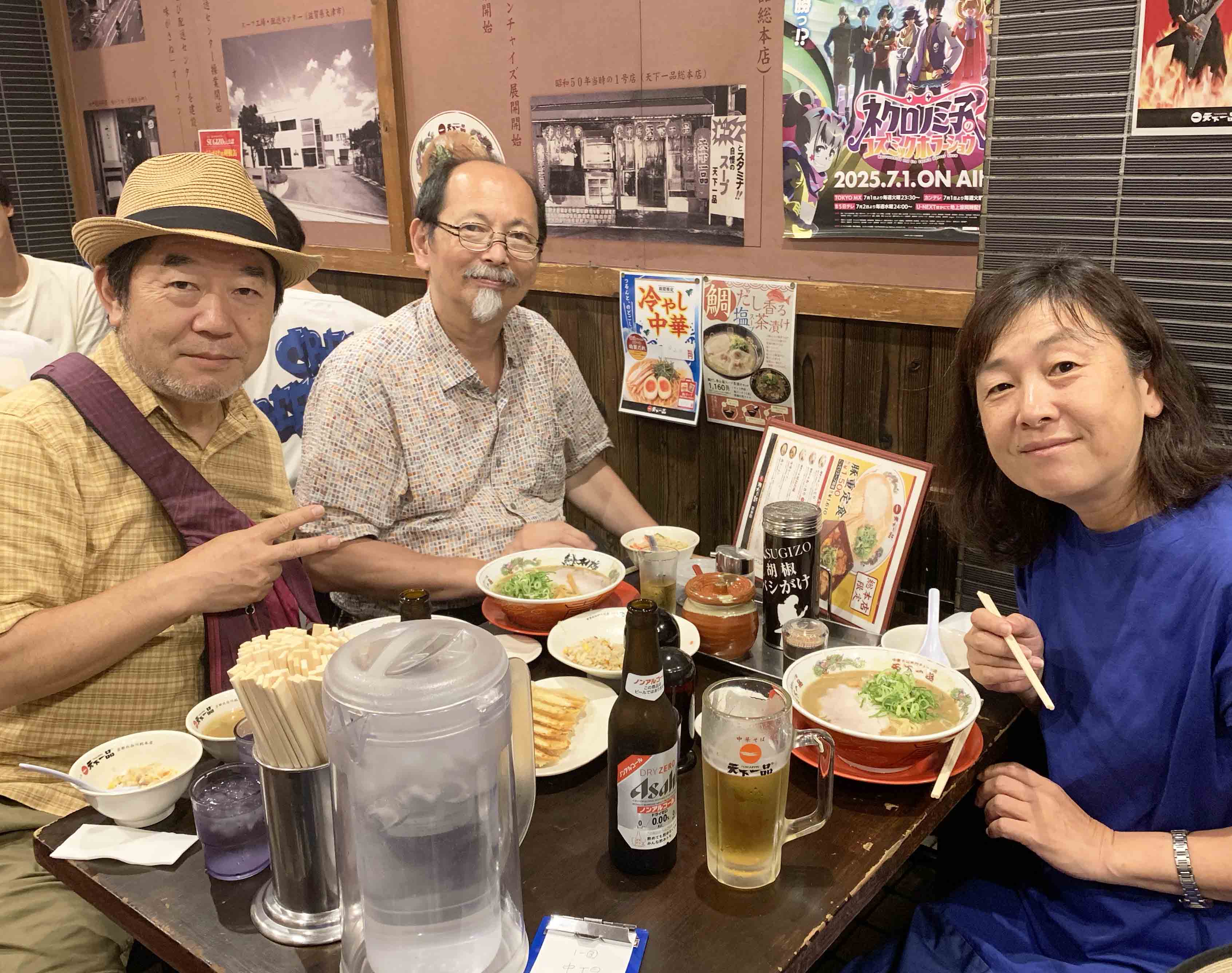 |
練習後、大久保さんが「風邪気味でしんどいので、体力をつけるために天下一品に行きたい」と言い出したので、北白川の本店へ。幸谷先生は、「学生時代にクラブ(医学部テニス部)の練習後よく皆で天一に行った」と、懐かしがっておられた。私も天一は久々。とても美味しかった。 |
2025年7月14日(月)
長谷川さんと桑原さん、来訪
 |
長谷川さと桑原さんが、京都小旅行の折、河本研に立ち寄られた。長谷川さん(写真向かって左)は2007年頃、理研時代の河本研で一時期秘書をしていただいた人で(2019年3月29日の記事参照、2024年8月9日の記事参照)、桑原さんは同時期にテクニカルスタッフを務めていただいていた。長谷川さんは、今は横浜で弁理士事務所に勤めておられる。桑原さんは、今は「necono」というネコ用品の制作と販売をされている。今回、桑原さんからはネコ用グッズをいくつかお土産でいただいた。 「necono」HP: |
 |
この日は天気予報では「雨」だったが、比叡山へのドライブを決行。写真は比叡山山頂の駐車場から。南側を望んでいる。 |
 |
その後、延暦寺へ。第一駐車場に停めて根本中堂に向かう。途中の大講堂の前には、「開運の鐘」という大きな鐘があり、1回100円のお布施で、誰でもつける。 |
 |
根本中堂は改修中であったが、中には入れて、不滅の法灯を拝むことはできた。写真はWikipediaより拝借。写真の様な灯明が三つ並んでいる。菜種油で灯すランプのようなものであるようで、西暦788年からとされているので、1200年以上ずっと灯っているということになる。さすがに1571年の織田信長による焼き討ちの際は一度途絶えたが、分灯してあった別なお寺から再分灯してもらって、復活したとの事。 |
 |
奥比叡ドライブウエイを通って、琵琶湖畔の、満月寺の浮御堂へ。近江八景の一つ。 |
 |
お堂はぐるっとまわることができる。写真は北側を望んでおり、琵琶湖大橋が見えている。 |
 |
先斗町で夕食。雨は降っていなかったが、降りそうな気配だったので、納涼床でなく、室内での食事になった。 |
 |
会食後、宵々々山を散策。雨模様ということで、人出は少なかったが、雰囲気は味わえた。 |
 |
桑原さんからいただいたネコ用の抱き枕を、うちのネコは、気に入ってくれたようだ。 |
2025年7月12日(土)
免疫ふしぎ未来展の打ち上げでのライブ演奏に向けて練習
 |
この日、清野先生と共同研究の打ち合わせと試料の受け渡しがあり、京都にこられた。打ち合わせの後、夜遅くから、バンド演奏の練習を行なった。スタジオは四条大宮のスタジオ246。写真はスタジオに入る少し前に、軽く腹ごしらえしているところ。今回は、新曲として「Escape」(Moon Child)と「ウィーアー!」(ワンピース主題歌)があり、どちらも難曲であるが、特に「ウィーアー!」をバンドで演奏というのは、結構きつい。また、自分達のバンドのオリジナル曲である「逆襲の助教」も演奏することにしたが、オリジナル曲でありながらかなり難しく、3年ぶりの演奏(2022年12月2日の記事参照)という事もあって、これも結構きつい。 |
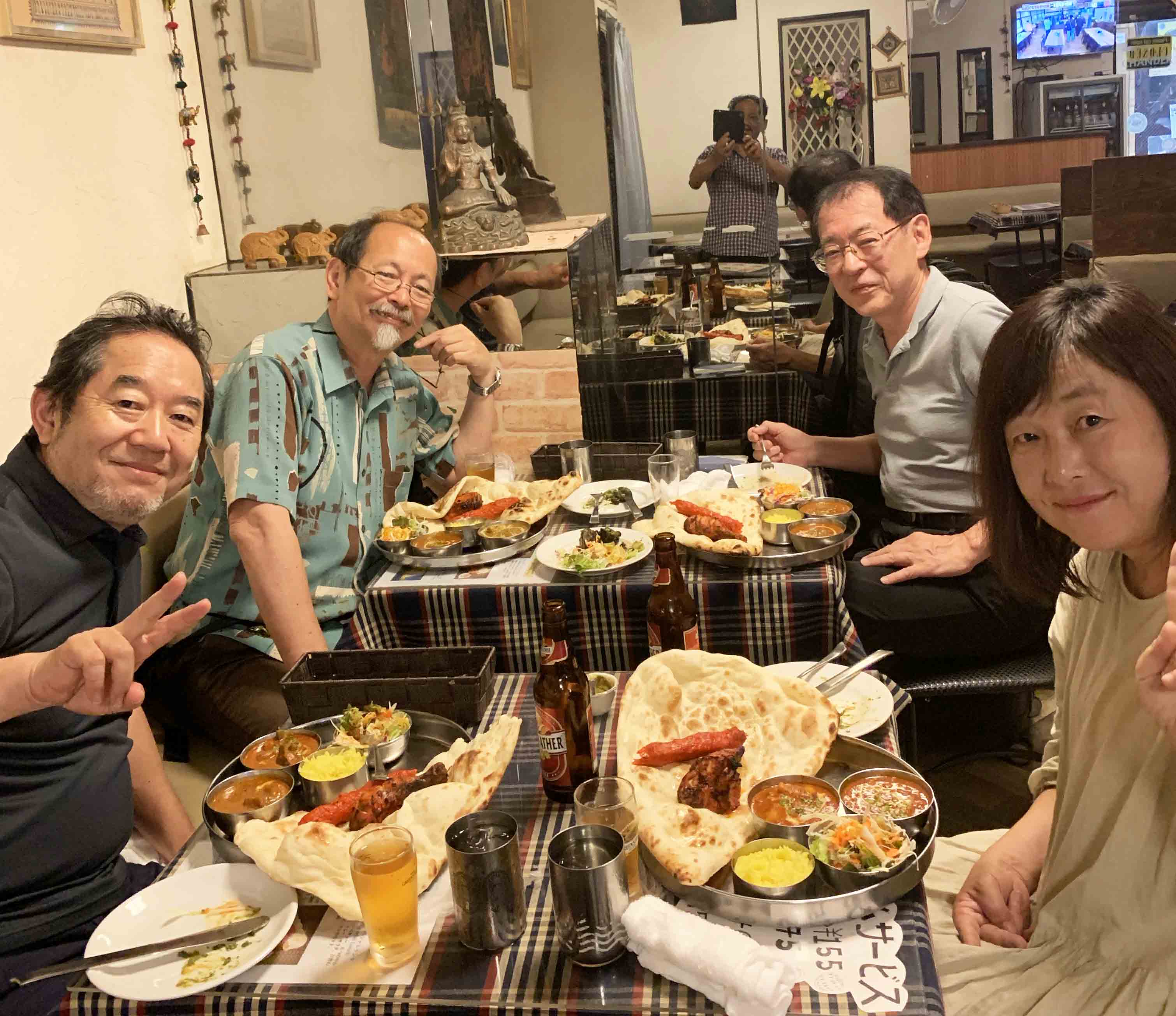 |
13日日曜日の午前中も練習し、その後、東山丸太町の「チャンダー」で昼食。 |
2025年7月12日(土)
京都大学医学部創立125周年記念式典・祝賀会
 |
表記の式典と祝賀会が京都ブライトンホテルで開催された。 |
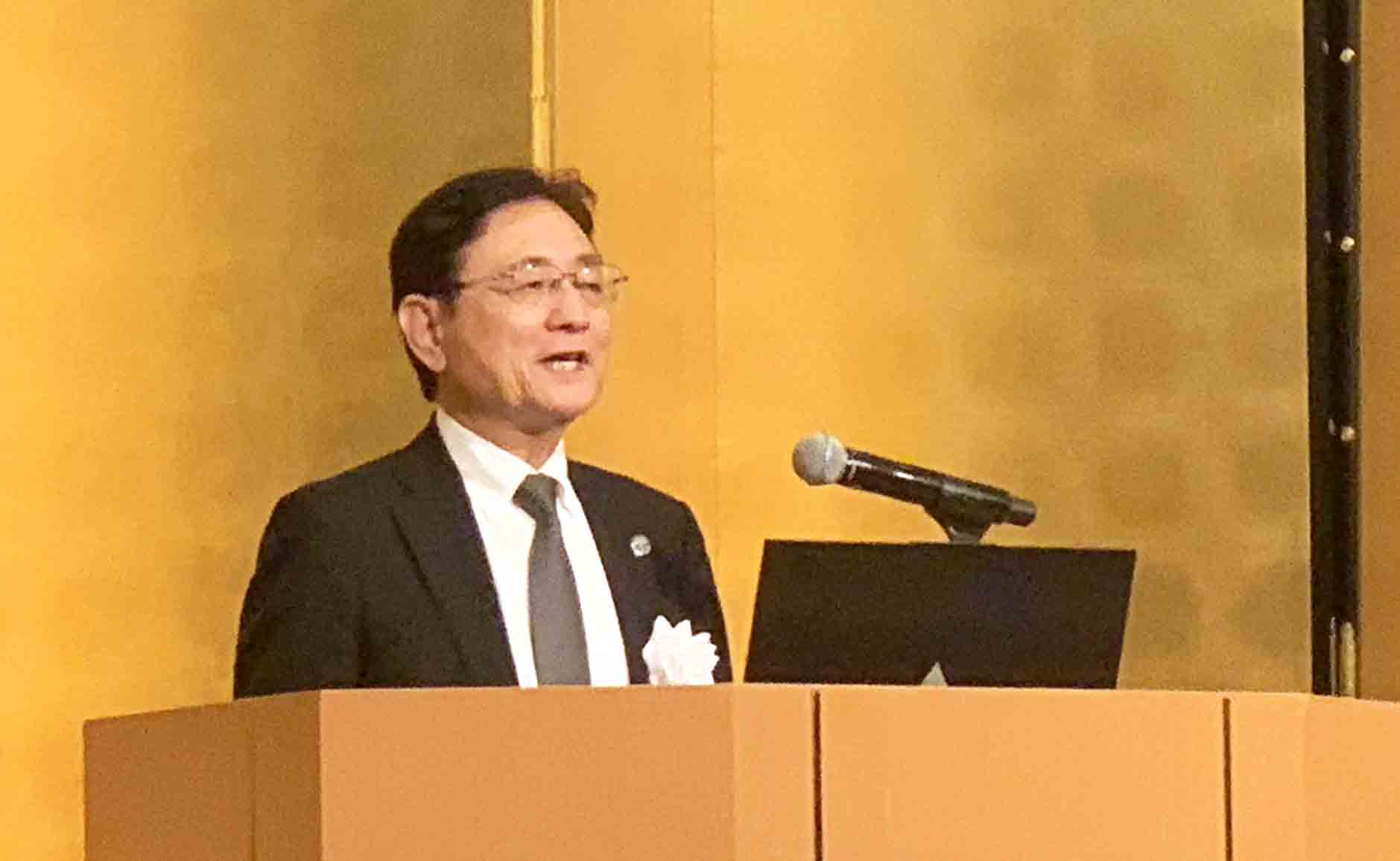 |
湊総長の挨拶。 |
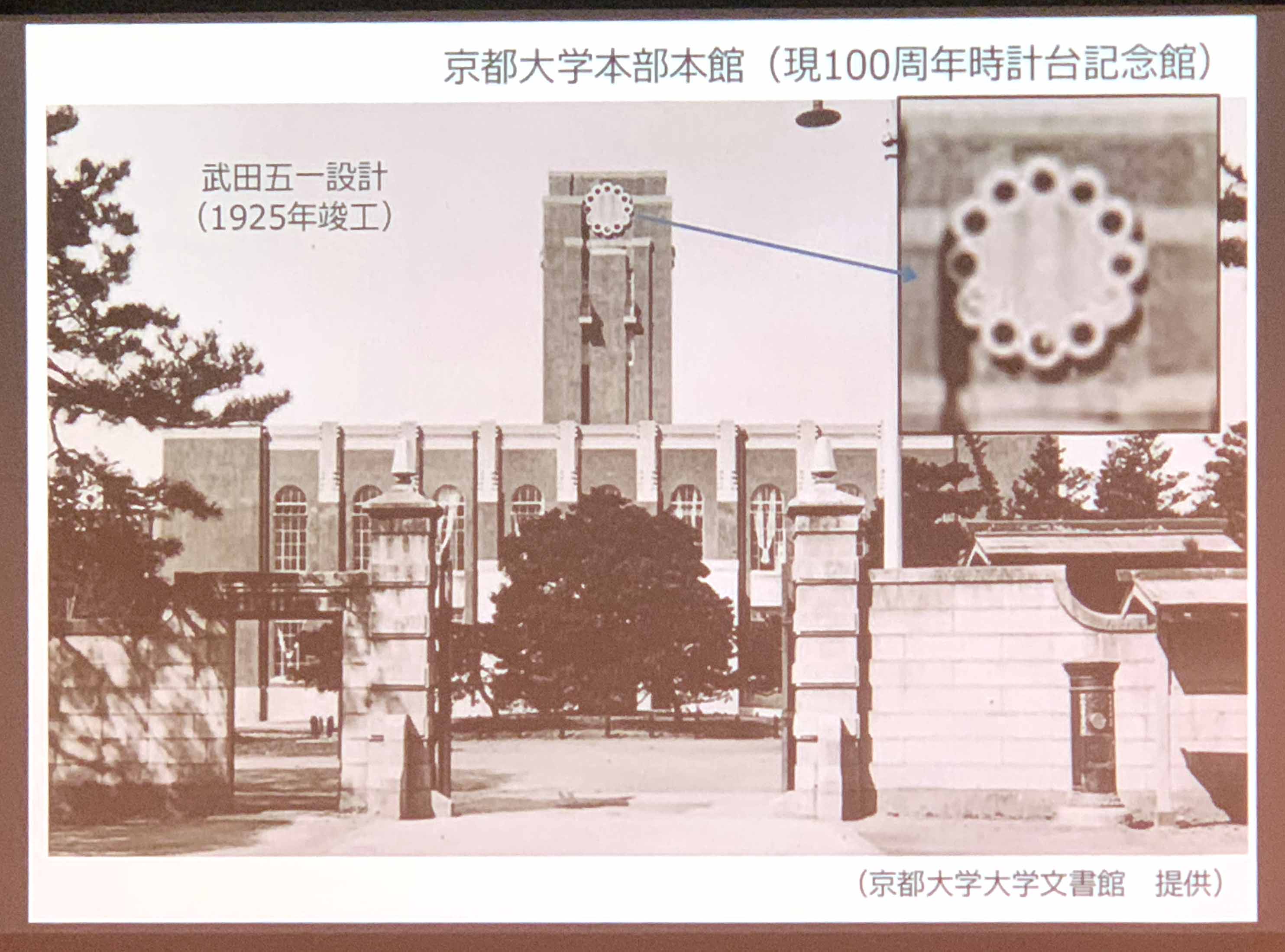 |
その後、湊総長による記念講演。針が付けられる前の時計台の写真が示され、面白かった。 |
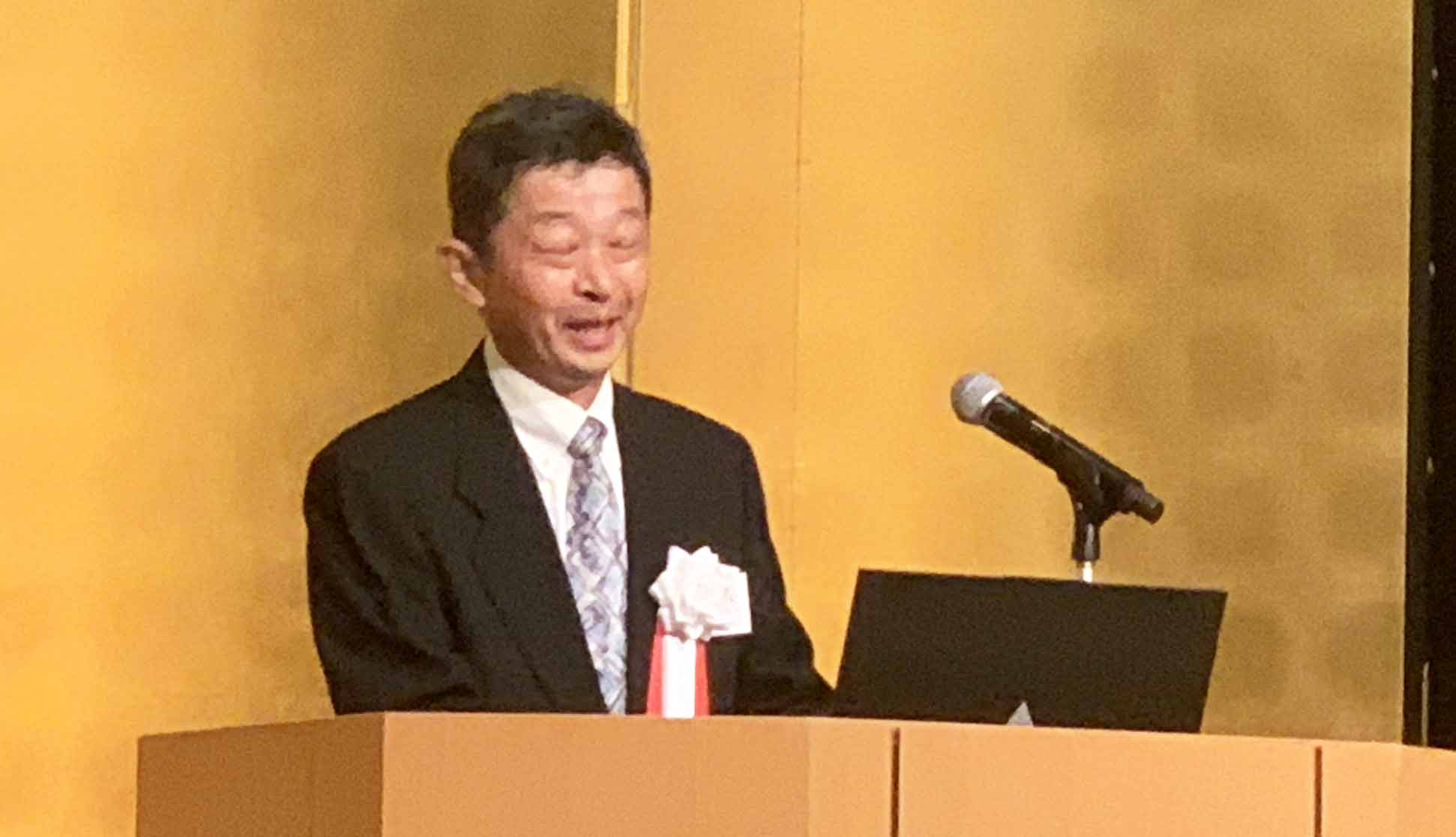 |
続いて、文学部の伊藤淳史助教による京大医学部領域の発掘調査の話。 |
 |
左の写真は医学部創立の10年前の医学部あたりの風景とのこと。建物らしきものは無く、畑が広がっている。 |
 |
ただし、このエリアにずっと何もなかった訳ではなく、平安遷都後、ながらく何らかの建物はあったらしい。 |
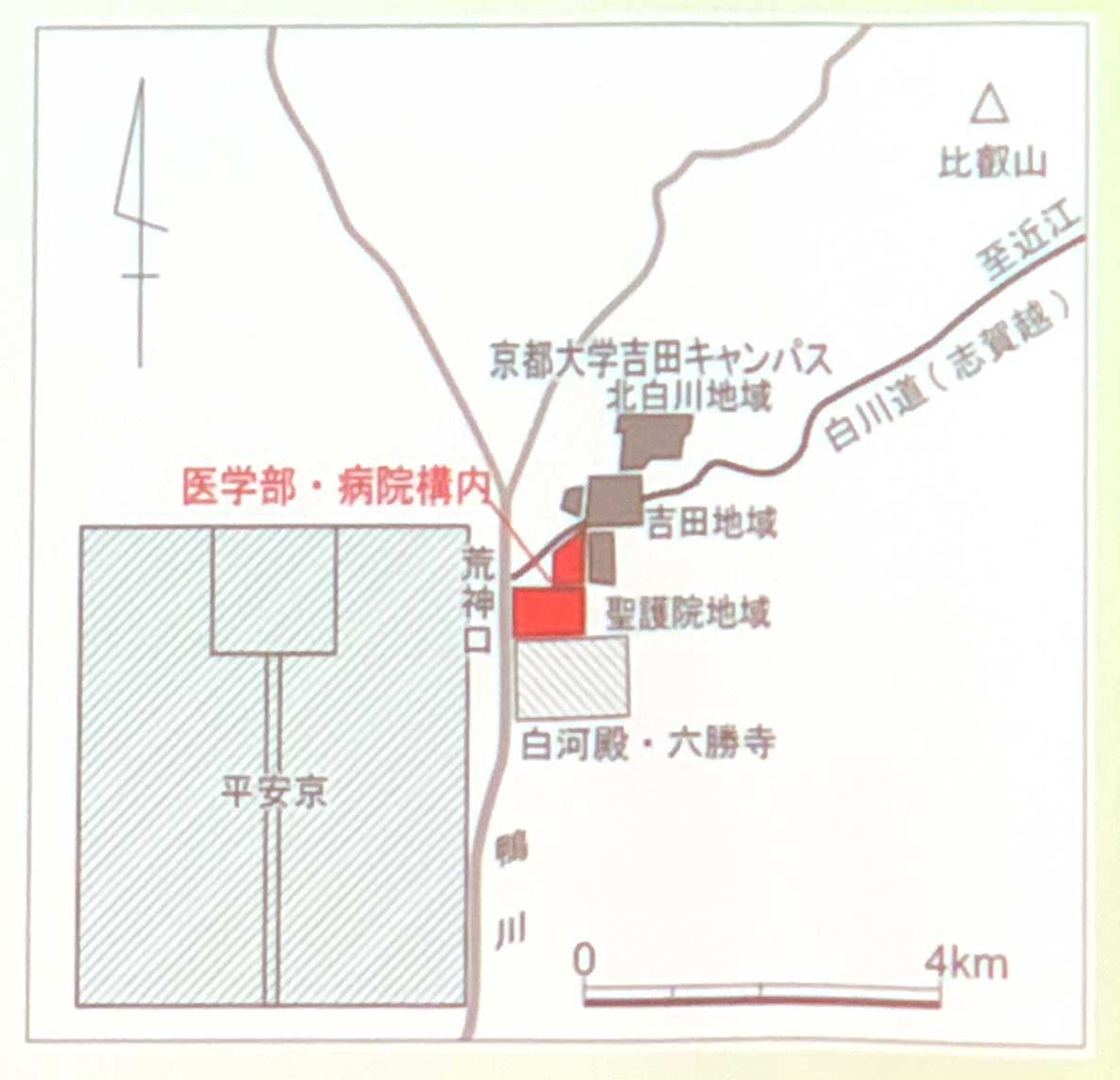 |
山中越えと呼ばれている街道は、かつては白川道とか滋賀越えと呼ばれていたらしい。医学部の北側の斜めの道がその名残り。 |
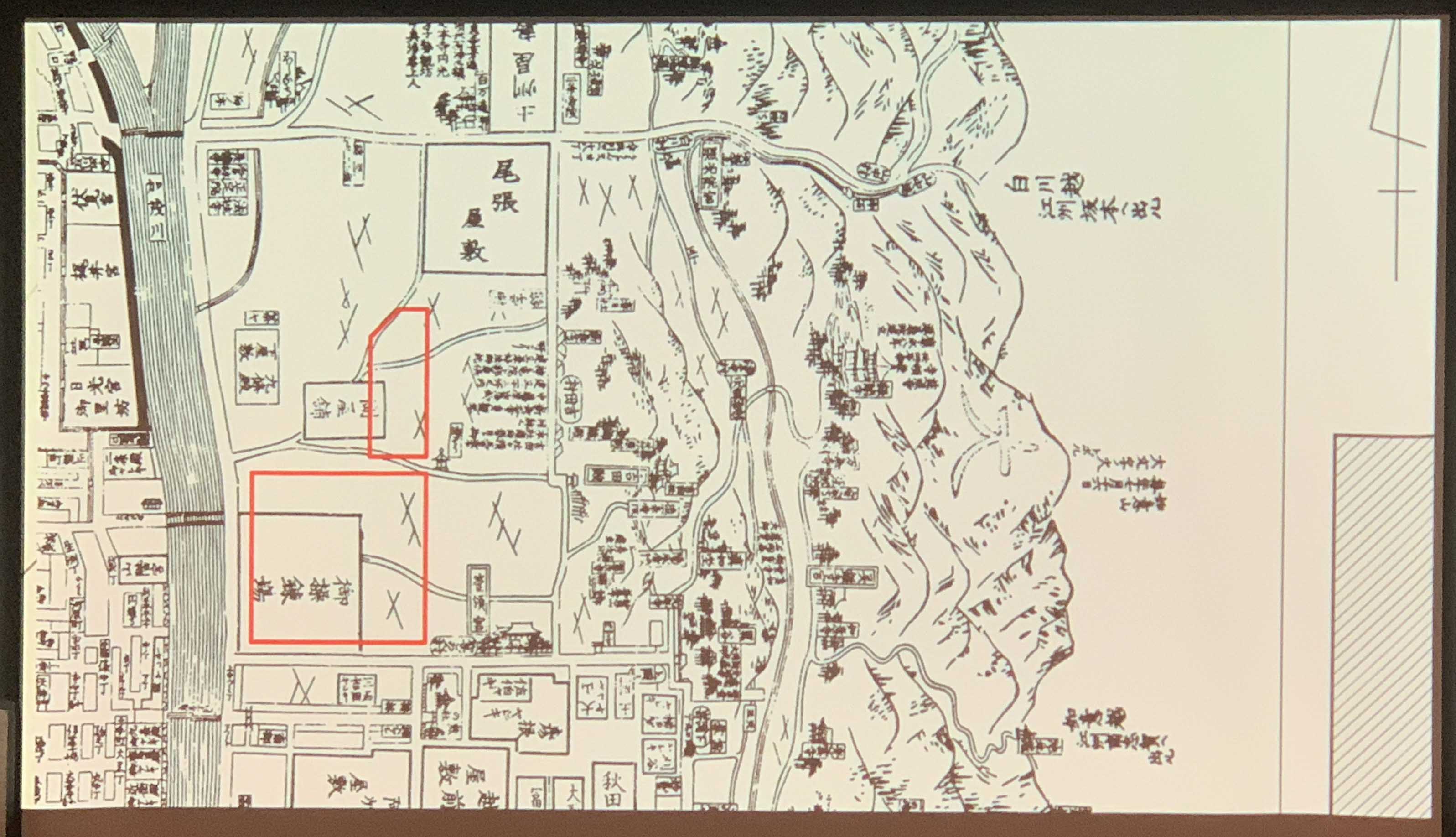 |
これは少し前のスライドにあるように、明治になってすぐの地図。なお、私は京大の本部キャンパスが作られた時に白川道を分断したのであろうと思っていたが、こうしてみると、白川道を分断したのは京大ではなく、その前にあった尾張屋敷のせいで、すでに白川道は途切れている。 |
 |
医学部構内の、白川道に沿ったエリアの発掘調査の様子。確かに、多くの建物が有ったことがわかる。 |
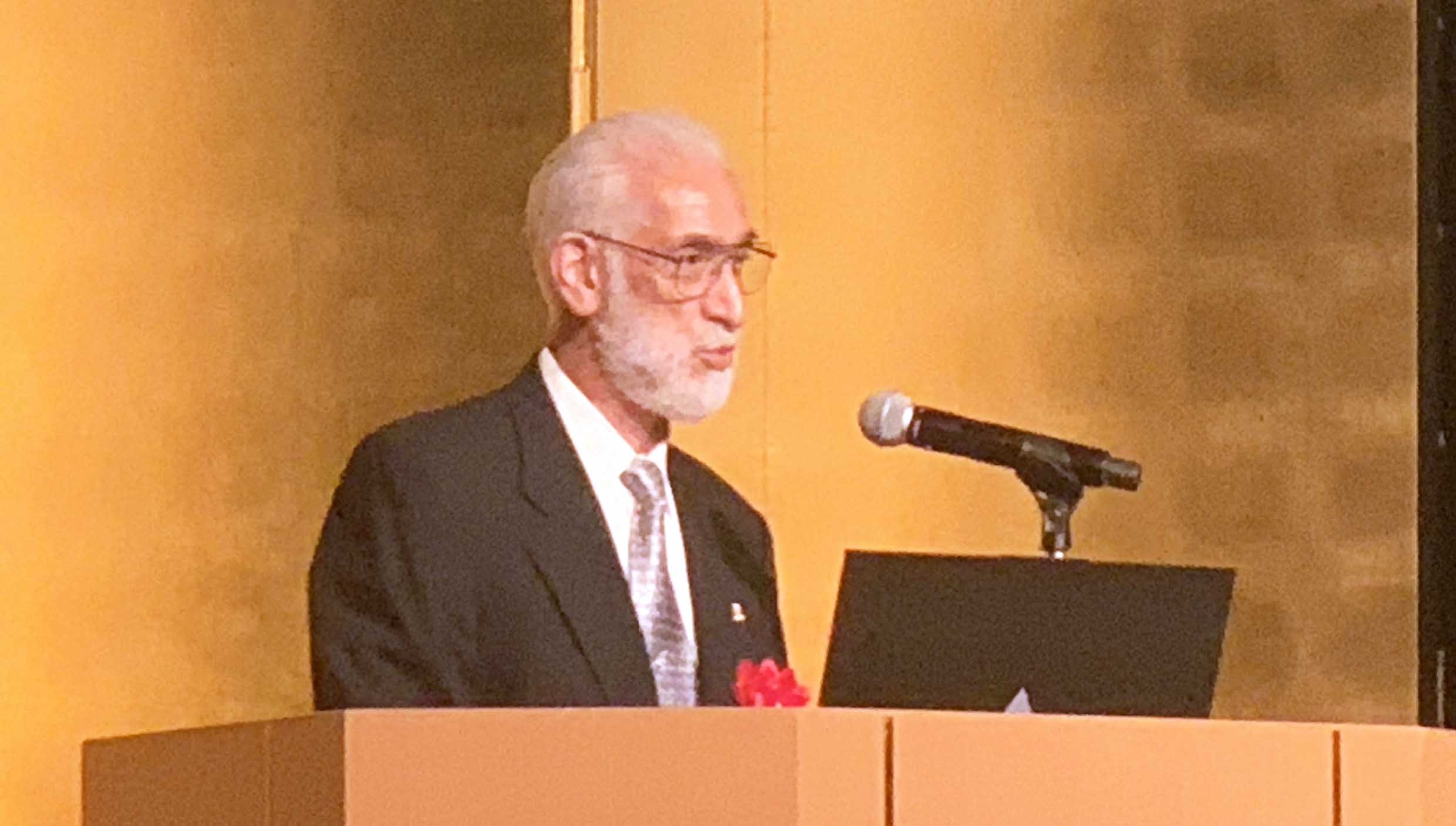 |
レシャードガレット先生による講演。アフガニスタン出身の、京大医学部のOBで、1976年卒。 |
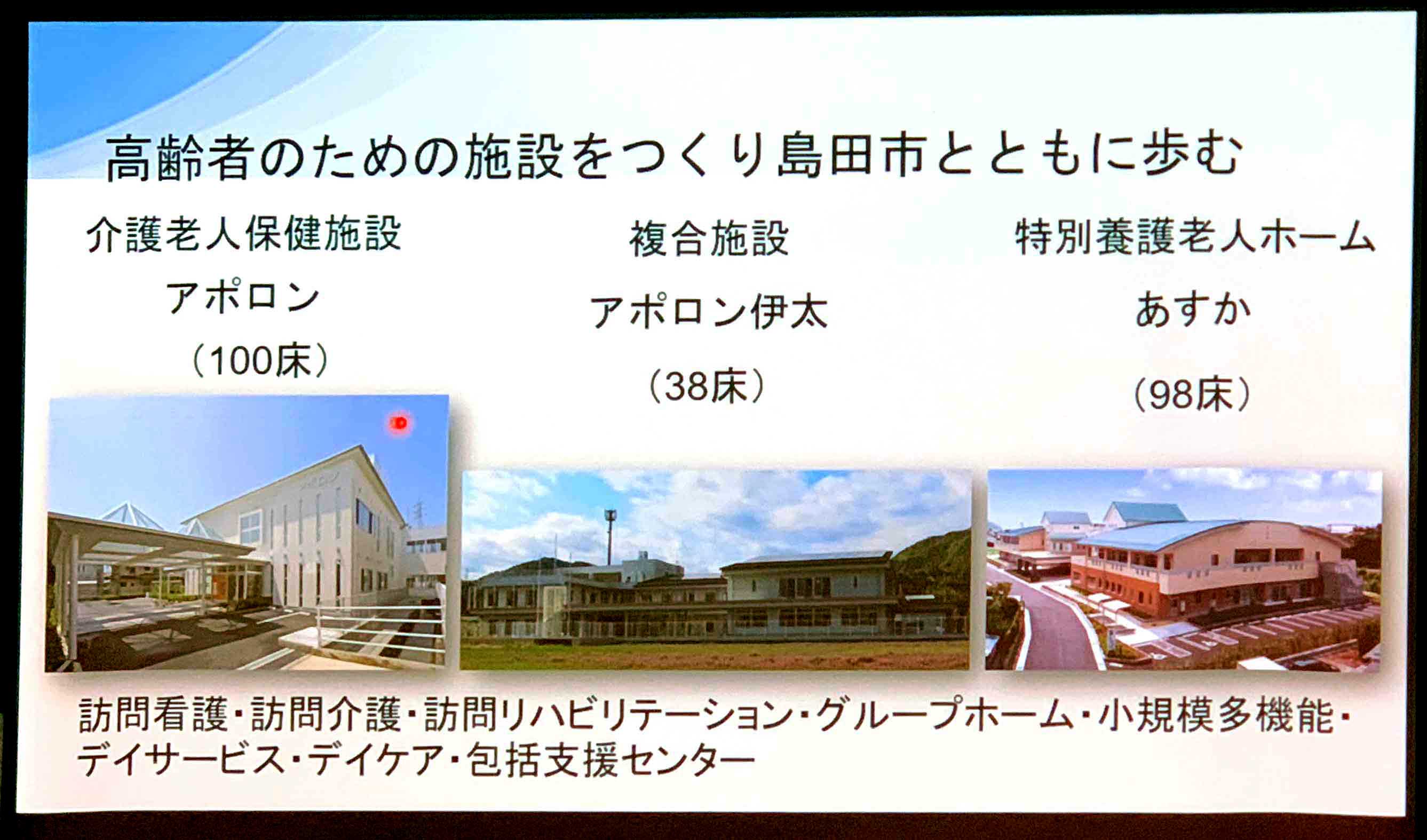 |
アフガニスタンでの医療支援をされつつ、島田市で地域医療にも大きく貢献されている。こういう先輩がおられるとは知らなかった。 |
 |
医学部のこれまでとこれからを語るラウンドテーブル・ディスカッション。 |
 |
10月から医学研究科長となられる波多野悦郎先生も参加されていた。波多野先生は医学部軽音学部の後輩で、2017年7月に開催された肝癌研究会の懇親会で、バンド演奏をご一緒したこともある(2023年7月28日の記事参照)。 |
 |
式典の後、祝賀会が開催された。 |
 |
井村先生による挨拶。私も会の半ばで医生研の所長として挨拶させていただいた。 |
 |
湊総長を囲んで。向かって左端から、新蔵礼子先生(東大)、渡邊大先生、湊総長、上野英樹先生、私、柳田素子先生。いい写真だ。 |
 |
医学部5回生の林璃菜子さんと。林さんは今河本研の宮﨑正輝准教授の指導で研究をしていて、昨年は免疫学会で英語で口頭発表している(2024年12月3日の記事参照)。一昨年の免疫学会ではポスター発表であったが、その時の様子は裏医生研チャンネルで紹介している(以下のリンク)。 裏医生研チャンネル第82回:学部生が学会発表⁉~京大医学部生の研究発表に密着!~ |
 |
医学研究科長の伊佐先生と。 |
 |
新蔵先生、鍋島陽一先生(京大)と。 |
 |
高折先生と林さん。林さんは、裏医生研チャンネルに出ていただいてた頃はまだ10代だったので、お酒はNGであったが、今は堂々と解禁であるようだ。 |
2025年7月10日(木)
国際数理生物学会年会の懇親会で演奏
 |
国際数理生物学会年会が7月7日-11日に、京都テルサで開催された。 2025年度国際数理生物学会年会HP: |
 |
懇親会は7月10日に京都リーガロイヤルホテルで開催された。200人以上が参加という、盛大な会だった。 |
 |
今回の集会長、望月敦史先生(京大医生研)による挨拶。 |
 |
会が始まって1時間くらい経ったあたりで、ネガティブセレクションが登場。短いオープニングのテーマを演奏後、リンパ節一人旅を演奏。 |
 |
その後、李聖林先生による「I love you」(尾崎豊)、聖林先生の研究室の若い人と聖林先生のデュエットで「残酷な天使のテーゼ」(エヴァンゲリオンのテーマ曲)、聖林先生の研究室の若い人二人のデュエットで「YMCA」(Village People)を演奏。「YMCA」の元の曲では3番まで歌って終わりであるが、西城秀樹の「ヤングマン」バージョンを採用し、「Y, M, C, A」とポーズを取るパート以後を追加した。写真はそのパート。 |
 |
バンド参加者で記念写真。 |
 |
本田直樹先生(名古屋大学教授)と。少し前まで、京大の生命科学科におられた。ネガティブセレクションの事をご存知だった。 |
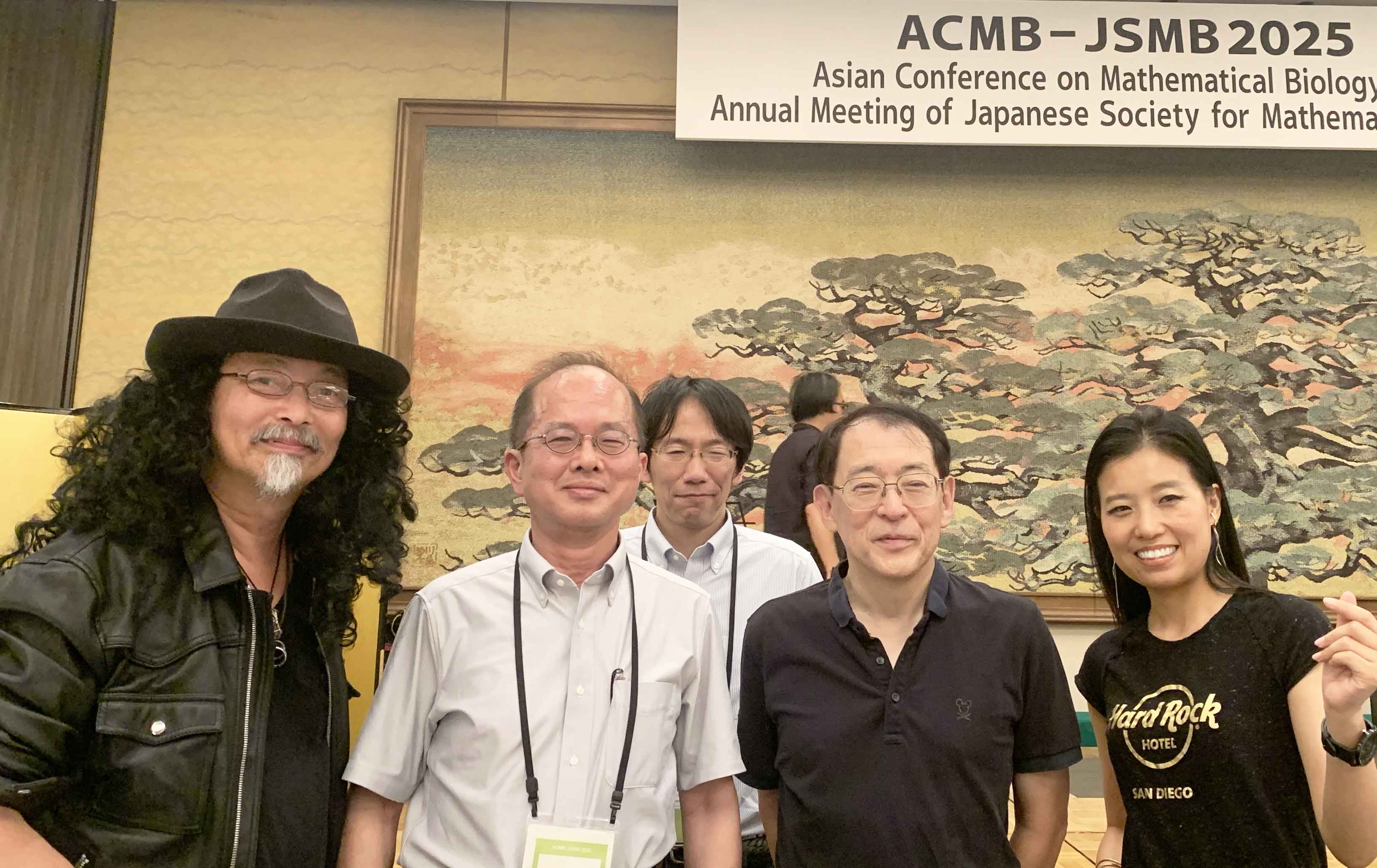 |
この会には影山龍一郎先生(理研、医生研OB、写真向かって左から二人目)が来られていたので、記念写真。4曲演奏しただけだったが、会場の皆がよく聴いてくれていて、ウケていたようだった。とても楽しかった! |
2025年7月9日(水)
前日練習
 |
少し前の記事に書いた(2025年6月12日の記事参照)が、国際数理生物学会(7月7日-11日、於京都テルサ)の懇親会(7月10日、於京都リーガロイヤルホテル)でネガティブセレクションが何曲か演奏することになり、この日の夜、スタジオRagで、歌い手さんを含めて、前日練習をした。スタジオの鏡に映った像を撮影している。歌っているのは李聖林先生(京大ASHIBi教授)。 |
 |
奥に写っているのは幸谷愛先生(大阪大学)。 |
 |
練習終了後、3人で「くうかい」でほっこり。 |
 |
くうかいの新メニュー、ヤングコーンを焼いて、カレー味をつけた一品。幸谷先生は「めっちゃ美味しい。またこれを頂きに来よう。」と言っておられた。 |
2025年7月8日(火)
LiMe Happy Hour開催
 |
1月から奇数月開催ということで始まったLiMe Happy Hourであるが、5月は新所員歓迎会があるからスキップして、今回が第3回。ポスターには、毎回私が描いたイラストを使っていただいている。新作ではなく、使い回しで、これは2007年に理研免疫センターで開催された「ヒトとマウスの研究者の集い」という副題に合わせて描いたもの。本当にマウスの研究者がいたら面白いなと思って描いた。右下の女子マウスが、「靴ぬぎマウス」と呼ばれ、「かわいい」と、当時の理研内ではちょっと評判になった。 |
 |
第2回から、16時-17時に「美味しいコーヒー&ドーナツタイム」が設けられており、16時に仕事が終わる人などに好評であるようだ。 |
 |
河本研の貝谷君(D3)と板原君(特定研究員)が、ドーナツにご機嫌だ。 |
 |
ドルチェグストというコーヒーメーカーを使って、店の味に近い、色々な種類のコーヒーが楽しめる。これで教員以外は参加費無料であるから、気前がいい設定だ。 |
 |
生ビールのサーバー。今回の目玉企画であるようだ。確かに、これがあると、テンションがあがる。 |
 |
定番となった焼きそばコーナー。野菜と肉を合わせても、一人前300円弱で提供できるので、とても経済的だ。 |
 |
17時からアルコール解禁。写真は18時ごろで、よく賑わっている。 |
 |
このテーブルはゲームに興じていた。そういえば、自分も若い頃は、クラブの合宿などで、よくゲームをしていたなあ、と思う。 |
 |
会の途中でちょっと抜け出して、三井優輔先生(永楽研助教、写真向かって左)に、アフリカツメガエル(ゼノパス)の飼育室を見せてもらった。写真右は鈴木美奈子先生(三井チーム特定研究員)。 |
 |
でかい。丸々としている。こういうのを見ると、うちのにももっと餌をやらないと、と思ってしまう。 |
 |
アルビノ。フォルムが際立ち、美しい。 |
 |
会は19時に終了し、片付けが終わった後、21時ごろまで、恒例となった反省会。教授室を提供している。この会も楽しみのうちではある。 |
2025年7月7日(月)
下鴨中学校プチ同窓会
 |
今年は梅雨らしい梅雨がなく、7月に入ってすぐに夏全開、という感じだ。 |
 |
森下あおい先生(滋賀県立大学教授、写真向かって右端)とは、2年前に先生が主催される研究会で講演をさせていただいて(2023年8月23日の記事参照)から、共同研究を続けていて、時々顔を合わせている(2024年3月24日の記事参照)。今回、同級生の立花茂樹さん(2024年12月16日の記事参照)と大久保博志さんで、納涼プチ同窓会を開催。昔話に花が咲いた。「納涼」とはいえ、川床でも、もわっと蒸し暑かった。時折吹く風が心地よかった。 |
2025年7月5日(土)
医生研公開講演会
 |
表記の会が時計台記念ホールで開催された。今年の演者は野々村先生と今吉先生。「感じる私・考える私・変化する私」という、興味をそそるテーマだ。 |
 |
お二人の講演内容。 |
 |
外はうだるような暑さであったが、講演会は盛況だった。 |
 |
若村智子先生(人間健康科学部教授)が来られていた。睡眠のメカニズムなどを研究されている。京大美術部の後輩(2013年4月15日の記事参照)。写真中央は若村研の学生さん。 |
2025年7月2日(水)
澤先生と面談
 |
澤明先生(Johns Hopkins University)が京大に来られたので、MIC棟で昼食(お弁当)をご一緒して、あれこれと話をした。澤先生は京大でも先端国際精神医学講座の教授を兼任されている。精神科の先生なので私とは分野は違うが、骨免疫学会のウインタースクールで知り合った。骨免疫学会のウインタースクールは、昨年から精神神経系の研究者との合同開催になっており、今年からはさらに内分泌/代謝の人も加わって、面白い会になっている(2025年1月28日の記事参照)。なお、この会は学術的にも有意義な繋がりの会になっているが、主宰者である高柳広先生は東大医学部スキー部のOBであり、澤先生もまた東大医学部スキー部のOBなので、そういう繋がりもあるようだ。 |
2025年6月30日(月)
4回目の万博観覧
 |
この日は家族と共に万博を観覧。先週の火曜日と木曜日に行った時は曇天であったが、この日は晴天で、とても暑かった。写真は東ゲート前。10時入場の枠で、30分くらいで入れた。 |
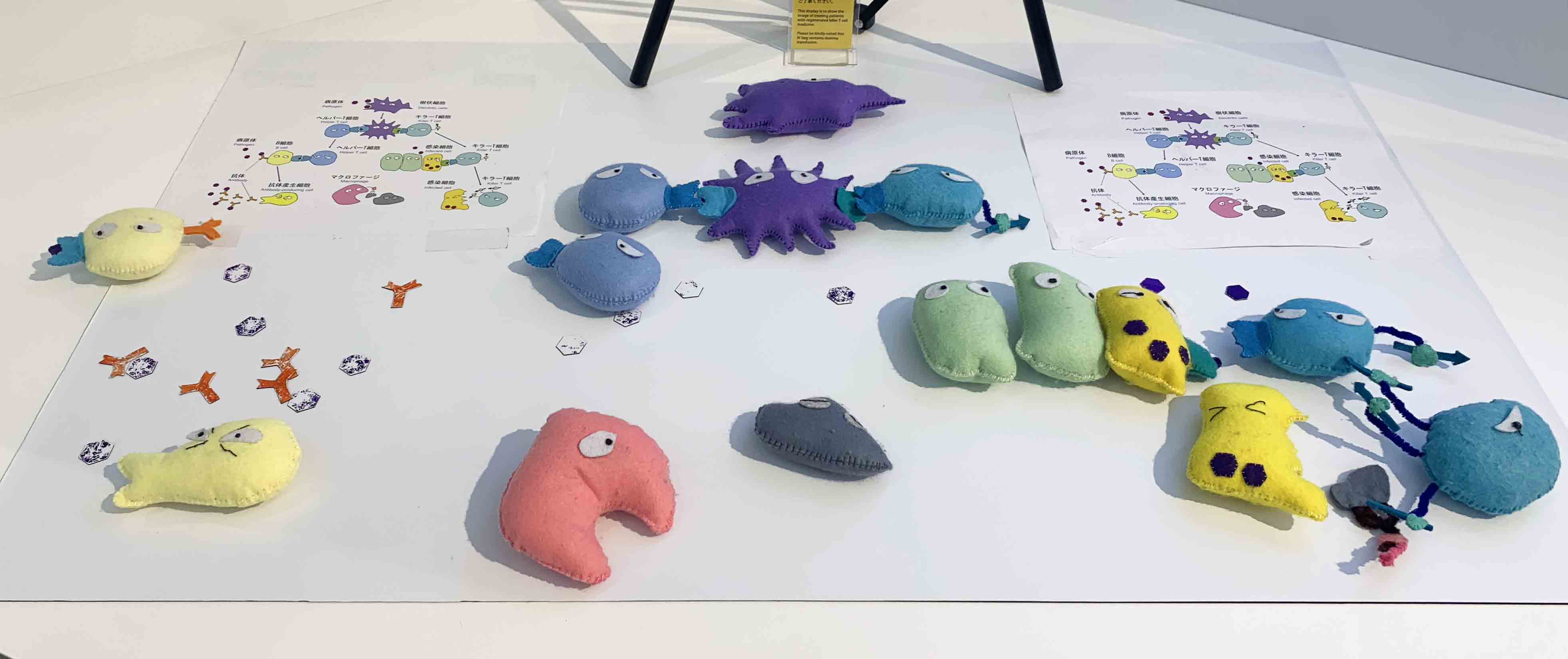 |
早速大阪ヘルスケアパビリオンのリバーセルのブースへ。展示7日目で、本日が最終日。目が無くなっていたり、腕が外れていたりしている個体もあるが、全部が残っていた。今日で最後と思うと、ちょっと寂しい。 |
 |
大屋根リングに接した北側に位置する「リングサイドマーケットプレイス西」の中にあるアフリカ料理屋で早めの昼食。安くはないが、珍しいものが食べられるのが、ありがたい。 |
 |
私は「クスクスセット」を食した。全ての食の原型のような感じがした。クラフトビールは、バニラ風味と、甘味がつけてあり、ちょっと苦手だった。 |
 |
昼食後、11時半頃に、あまり並ばなくても入れそうだったので、すぐ近くのスペイン館を訪問。 |
 |
スペイン館で、こういう構造の階段を登る際に、何かの写真を撮ろうと左側に少しはみ出してしまい、よそ見をしていたので40cmくらいの背の高い段にぶつかり、激しく転んだ。 |
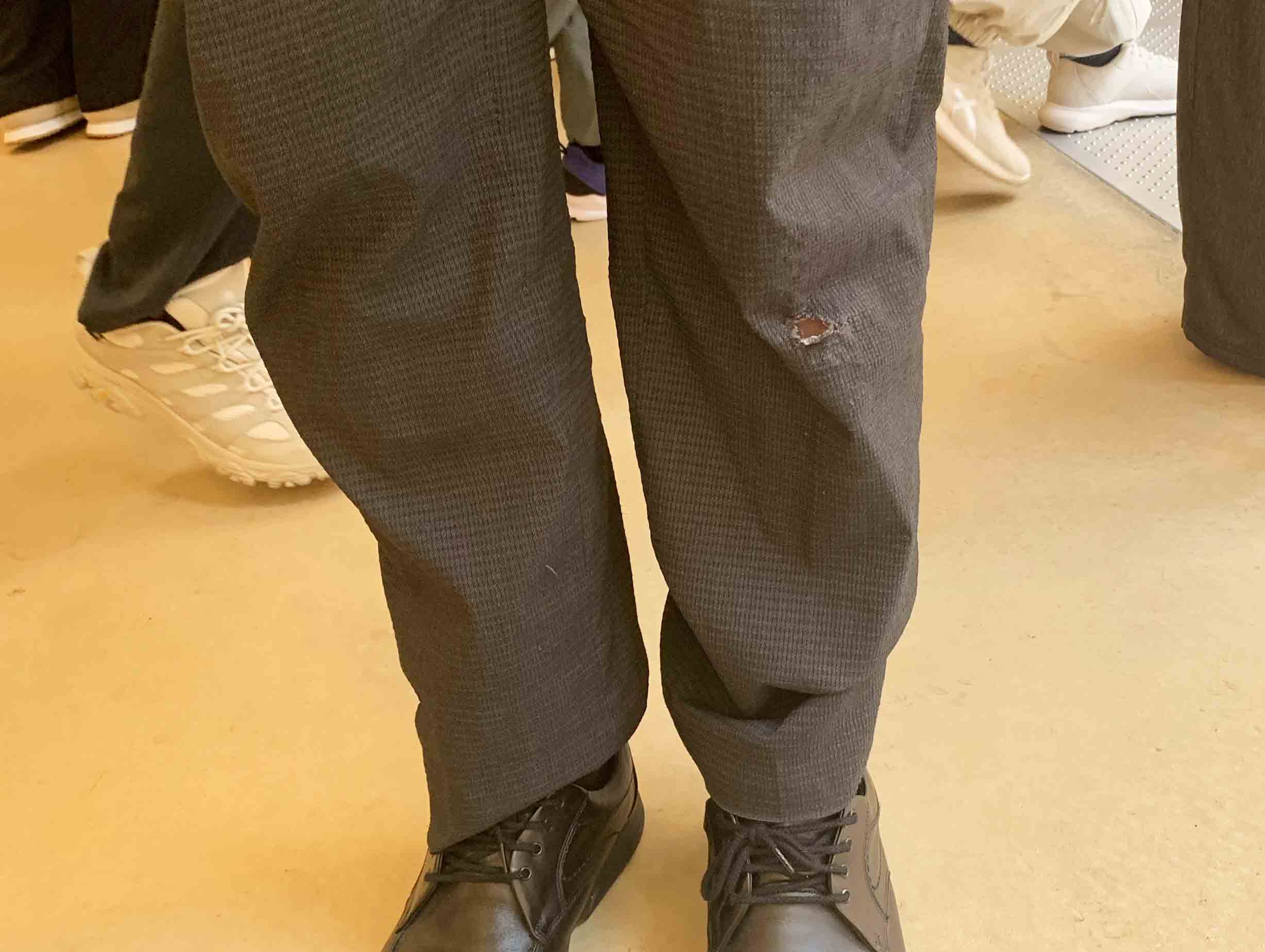 |
ズボンが破れ、膝の下あたりに出血を伴う創傷を負った。こういう事故が頻発してれば柵などが設けられると思うが、そうなっていないということは、もしかしたら私がこの階段での最初で最後の負傷者かもしれない。スペイン館自体は、映像や展示に迫力があり、中々良かった。 |
 |
リング内北西部にあるパビリオンの中で、ネットで人気のあったところのうち、あまり並ばず入れるところを順次訪問。オーストラリア館。ユーカリの林がいい感じ。 |
 |
インドネシア館。植物園の温室のようで、現物展示としてインパクトがあった。 |
 |
インド館ではお土産の販売があったが、通路が狭かったので、ゆっくり見ることができず、あまり売れていないような感じだった。 |
 |
北側のリング外エリアにあるトイレ。「2億円のトイレ」として有名になった。高級移動式簡易トイレという感じかと。 |
 |
マーケットプレイス東にあるトルコ料理屋で、一品(チキンケバブ)とビールで、少し休憩。 |
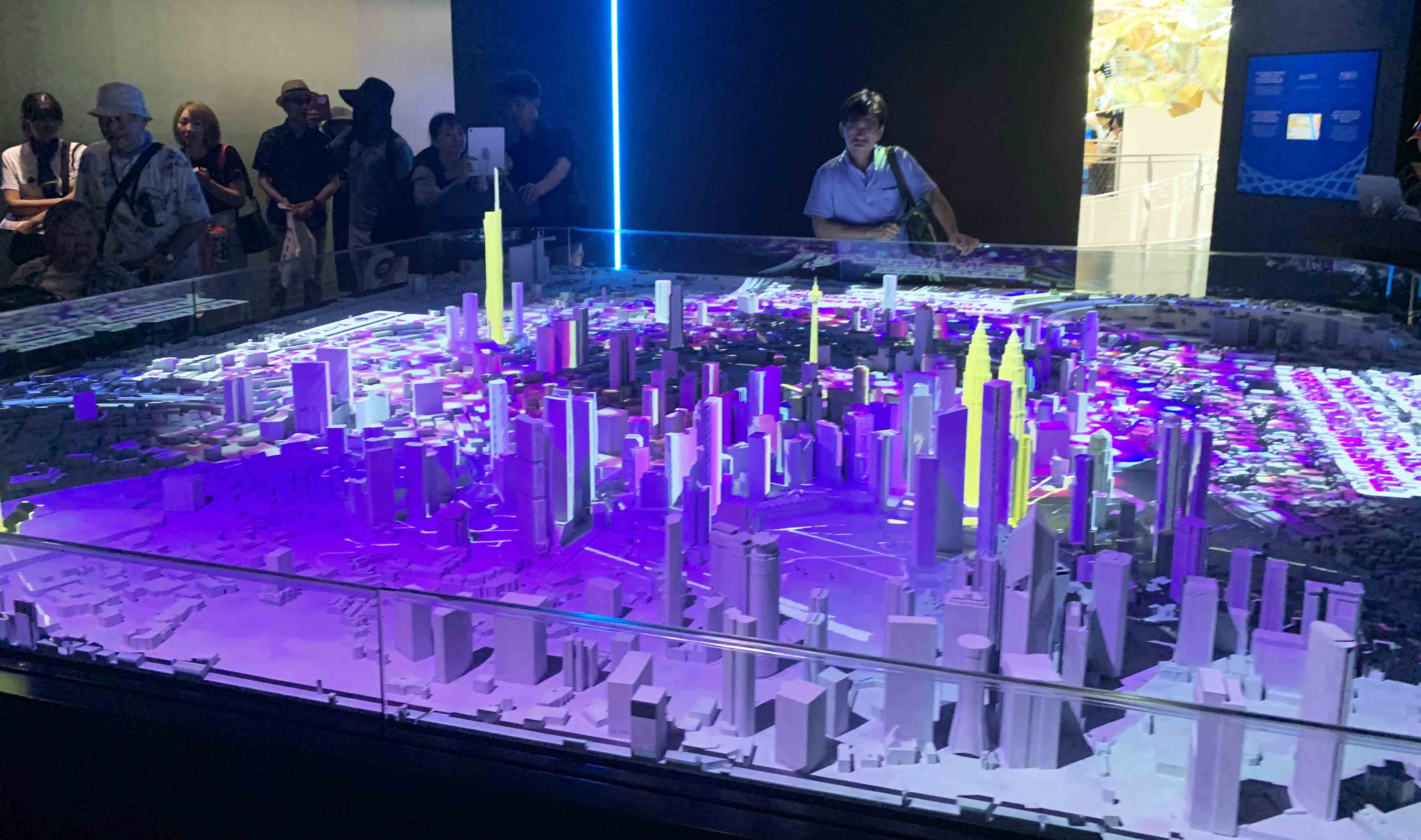 |
マレーシア館。巨大都市への発展をアピールしていた。 |
 |
万博の展示と関係ないが、リング内中央の「静けさの森エリア」で見かけた、巨大なネジバナ。高さ70cmはあったかと思う。普通はせいぜい40cmまでだ。ネジバナはラン科の植物で、日本の在来種であるが、ラン科の植物の中で雄一、雑草化した種。 |
 |
私はラン科の植物については「ラン科に属する」というだけで好きなので、ラン科の植物の自生に遭遇すると、ちょっと興奮する。これまでも何度もラボニュースに登場している(2024年6月24日、2023年6月26日、2014年6月20日、2011年6月27日の記事参照)。しかし、こんなに大きな個体は見たことがない。 |
 |
すぐ近くにも高さ60cmくらいの別な個体が見られたので、このあたりの個体は大型化する遺伝的な素質をもっているのかもしれない。もし1−2ヶ月後に来る機会があれば、是非種子を採取したいところだ。 |
 |
フィリピン館を観覧後、ブラジル館を訪問。アート性が高いとの評判。 |
 |
地球環境の悪化を防ごうというメッセージが、動画とインスタレーションで激しく表現されていた。アマゾンの熱帯雨林を抱えるブラジルが本気でこう考えているのであれば、いいことだ。 |
 |
夕食は、ハンガリー館附属のレストラン「ミシュカ」で。人気があるレストランであるが、あまり商売っ気がなく、この日も17時前に並んだら、そのすぐ後ろで「本日分はこれで終了」と列の最後尾が閉じられた。その後、1時間くらい待たされたが、それでも前菜のマトンのパテ(2000円くらい)とワイン(2000円くらい)にありつけると、嬉しそうだ。 |
 |
メインディッシュ。写真は玉子焼きの上にチキンが乗ったものと、大麦のリゾットの上にポークが乗ったもの(それぞれ4000円くらい)。ちょっと変わった味で、美味しかった。 |
 |
ポーランド館。仮想空間で薬草を自由にデザインするというコーナー。ポーランド館といえばショパンコンクール出場者のライブ演奏が聴けるというイベントをやっているが、これは予約制でとても激戦となっており、今回も2ヶ月前予約と1週間前予約で挑戦したがあえなく落選。なお、この日に観たポーランド館の一般向け展示の中には、音楽の要素はほぼ皆無であった。 |
 |
19時過ぎから20分ほど並んで、ハンガリー館へ。ハンガリーの民族音楽のライブショーが観られた。とても美しい曲だった。7分くらいであったが、目の前での迫力あるパフォーマンスに、心を揺さぶられた。なお、舞台は円形劇場になっており、中央にパフォーマーが立つ。以下の動画を見ていただくと、最初の方で、パフォーマーは歌いながらゆっくりと、とてもスムーズにまわっている。舞台に回転する装置が付いているのかと思ったが、後で見るとそのような装置はなく、どうやらゆっくり小刻みに自分でまわっているということのようだった。 ハンガリー館の民族音楽のライブパフォーマンス(約7分のフル動画): |
 |
20時頃、ドローンショーを観覧。 |
 |
QRコードが中空に浮かぶ様は、中々シュールだ。 |
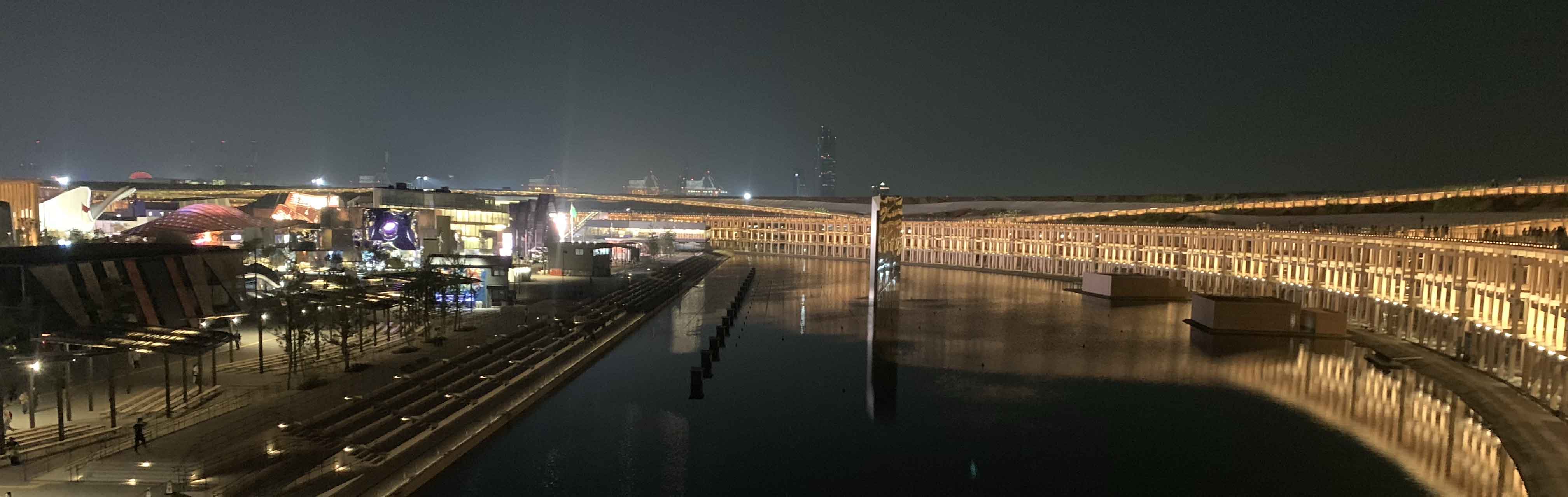 |
土産物を物色した後、大屋根リングを半周ほど歩いた。これで合計4回訪れたことになるが、機会があれば再訪したいと思った。 |
2025年6月29日(日)
「関電病院かえる会」に参加
 |
関西電力病院のOB/OGは、医師だけの会という形で年に1回開催されてきた。その会は昨年で最後ということになり(2024年9月8日の記事参照、2019年9月14日の記事参照)、今後は、看護師さんや検査技師さんも含めた職員全体のOB/OG会である「関電病院かえる会」に加わる形で移行することになった。参加者は100人近い、大きな会だ。なお、私(河本)は1986年卒であるが、京大病院で1年間研修医をしてから、1987年6月から1989年3月までの約2年間、関西電力病院で研修医として働いた。 |
 |
外科部長だった丸山泉先生による挨拶。 |
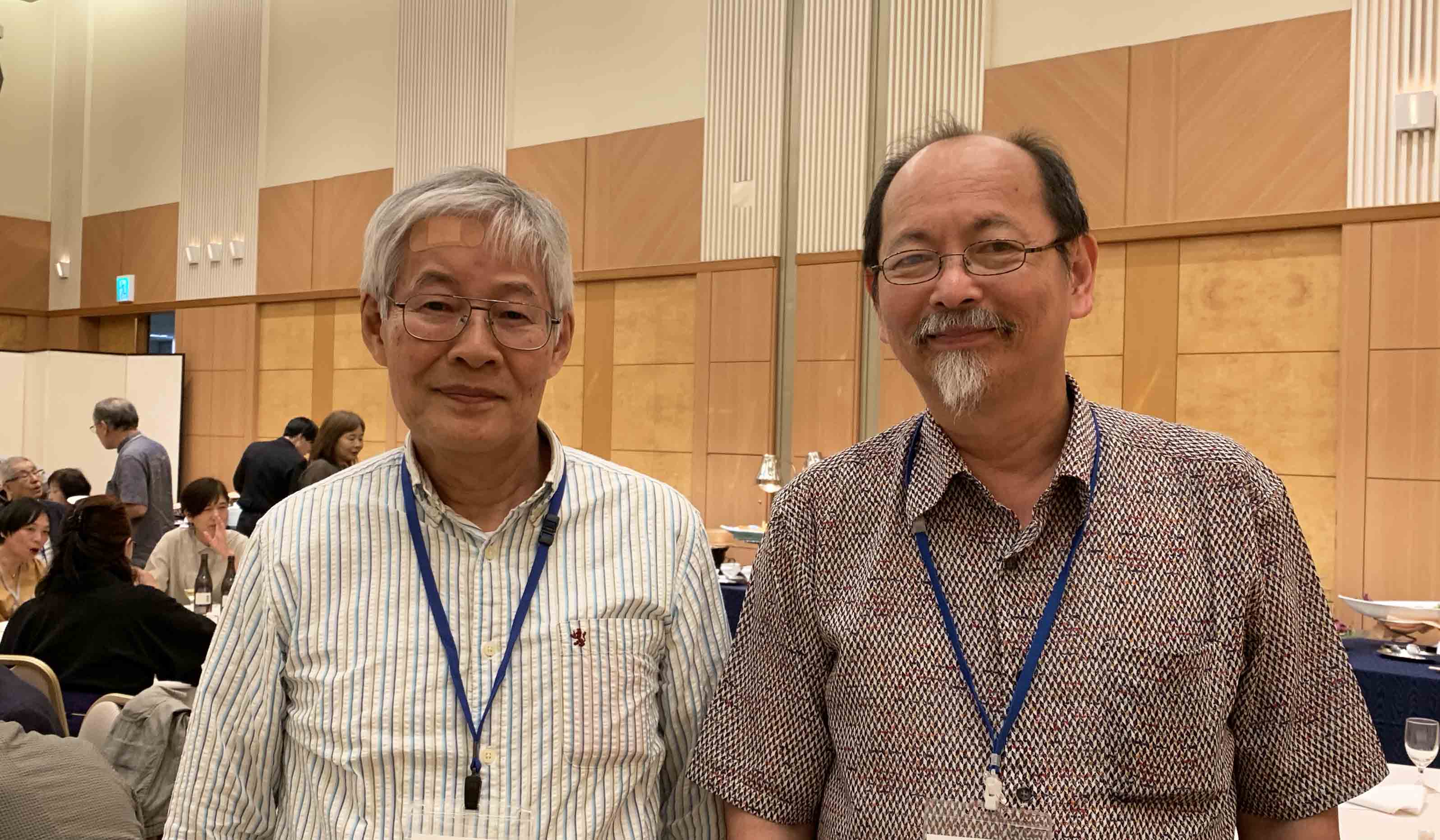 |
眼科の南求先生と。南先生とはスキー友達だった。シーズン中によく行ったのは八方、野沢、志賀高原などにほぼ毎週のように行っていたが、南先生は4月には青森県の岩木山での山スキー、5月には山形県の月山での春スキーなども企画され、何回もご一緒した。 |
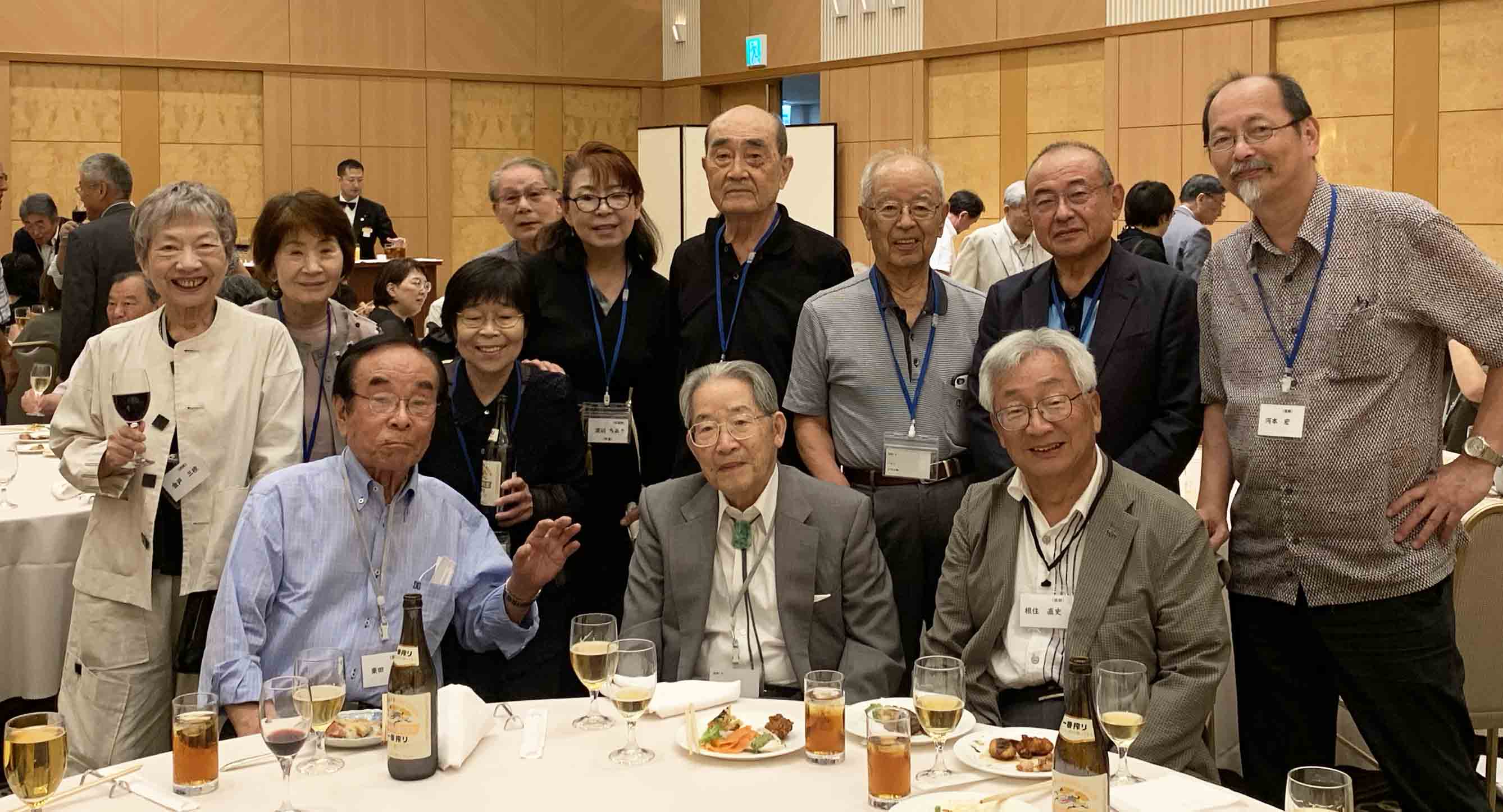 |
同じテーブルだった人を中心に集合写真。 |
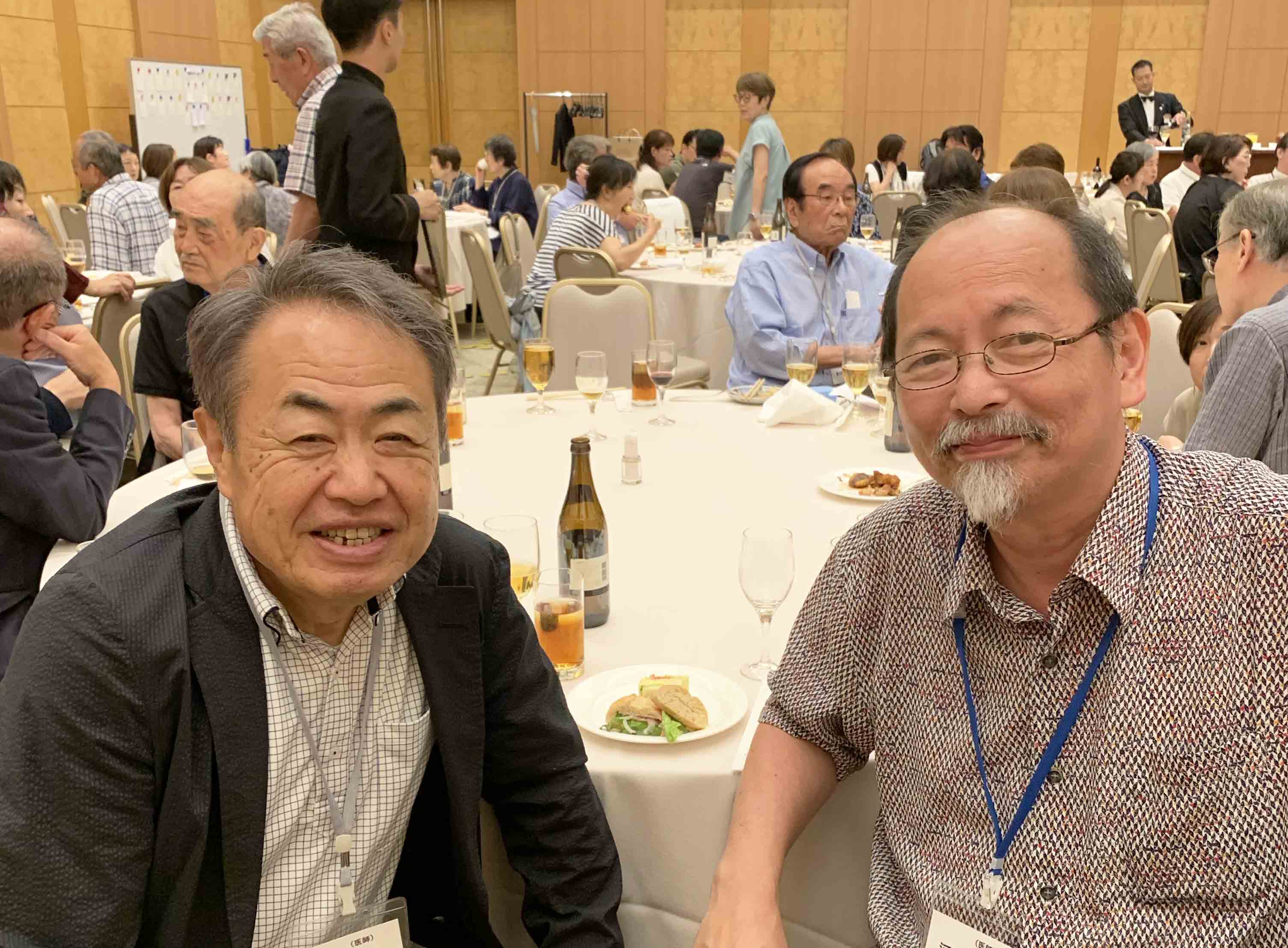 |
テニス部の先輩である筧善行(かけひよしゆき)先生と。私が1回生の時(1980年)筧先生は6回生だった。泌尿器科の先生で、2017年から2023年まで香川大学の学長を務められた。10年ちょっと前に、筧先生が集会長をされた日本泌尿器科学会総会で、話をさせていただいた事もある(2014年4月24日の記事参照)。 |
 |
人見滋樹先生と。私が胸部疾患研究所(現医生物学研究所)の桂研に参入した頃(1994年)は、まだ現在の医生研1号館の建物は京大病院の南西病棟として機能しており、胸部外科や呼吸器内科があった。人見先生は当時の胸部外科の教授。しばらくして、胸部研が生体高分子センターと統合して再生医科学研究所に改組された際に(1998年)、医療部門は京大病院本体へ移った。 |
2025年6月27日(金)
河本研歓送迎会
 |
ここのところ少し人の出入りがあったので、研究所にほど近い「ゆるり」という店で歓送迎会を開いた。テーブル1。 |
 |
テーブル2。 |
 |
送別される人として、テクニカルスタッフの松本健佑さんが挨拶。この1年間、細胞製造をよく支えてくれた。 |
 |
歓迎される人として、テクニカルスタッフの若林貴美さんが挨拶。4月から河本研に参加。 |
 |
6月から河本研に加わったテクニカルスタッフの村﨑冬美さん。細胞製造の経験を持っておられ、即戦力の人材。 |
 |
大学院生(D1)として5月から河本研に加わった岩下晶穂先生。中坊周一郎先生(京大病院臨床免疫学特定助教)との共同研究を担当(2025年5月26日の記事参照)。少し前の記事に書いたが、京大医学部テニス部の先輩である岩下靖史先生(音羽病院脊椎センタ―センター長)のお嬢様。 |
2025年6月26日(木)
関西電力北支店関係者と万博を観覧
 |
大学院時代から理研に単身赴任するまでの11年間、毎週金曜日の午後に関西電力北支店(天神橋8丁目)で産業医の仕事をしていた。その当時の関電社員だった高見明伸さんが万博関係の仕事をされていて、「未来の都市パビリオン」の副館長をされているということで、北支店で衛生担当の事務をされていた方達と万博に一緒に行きましょうという話が出ていたが、どうせならリバーセルが出展中に、ということで、この日、万博を訪問。この2日前と、4月のテストラン(2025年4月6日の記事参照)を含めて、3回目だ。左の写真は東ゲートを入ったすぐのところにある「Welcome」の文字。 |
 |
帰り際に逆の方向から見ると「Good bye」と読めるようになっている。 |
 |
向かって左から只埜(ただの)さん、暁山さん。只埜さんと暁山さんは、他の人達も一緒に何人かで医生研を訪問いただいたことがある(2019年3月30日の記事参照)。 |
 |
まず大阪ヘルスケアパビリオンへ。リバーセルのブースでは、ボールペンで描いた配置図を貼っていたにもかかわらず、並べ方はかなり乱れていた。 |
 |
キラーT細胞の腕が外れていたのを、暁山さんが裁縫セットで直してくれた。 |
 |
ブースの前で記念写真。 |
 |
配置を示す図を、新たにカラーで印刷し、左右に貼り付けた。 |
 |
リングの外、北側の「リングサイドマーケットプレイス」というエリアには、色々な国のレストランがある。パビリオンに付随したレストランよりも席が多く、混雑する時間を避ければ、わりと空いている。この日は、マーケットプレイス東にあるトルコ料理屋で早めの昼食。美味しかった。 |
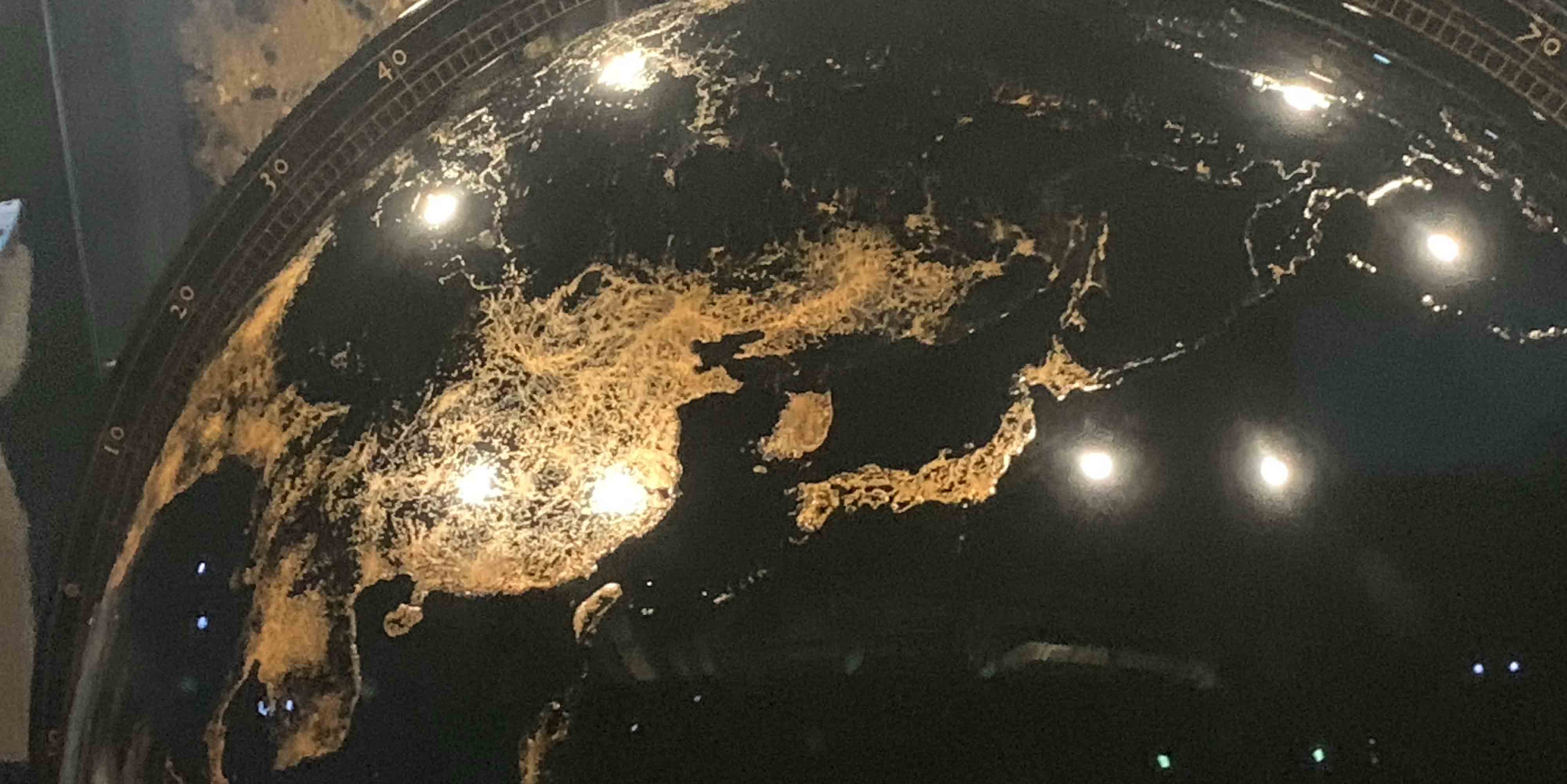 |
「夜の地球 Earth at Night」館の、輪島塗の地球儀。直径1m。北朝鮮の部分が暗いことが表されている。 |
 |
多くの国が参加している「コモンズ」という建物がいくつかある。その中の一つコモンズBで見たドミニカ共和国のブースでは、カーニバルの際に悪魔としてねり歩く時の装束が飾ってあった。夢に出てきそうで、ちょっと怖い。何らかのドラッグをやった人がデザインしたのであろう。 |
 |
この日も大変暑く、 エチオピアのブースで売っていたKINGFISHERというインドのビールで喉を潤した。 |
 |
土産物屋さんで見た「漆のミャクミャク」と「鍋島焼のミャクミャク」。漆のミャクミャクは一体だけ、鍋島焼のミャクミャクはごく少数だけ作られたとのことだが、それぞれ165万円、55万円とかなり高価であるにも関わらず、即完売となったそうだ。 |
 |
関西電力滋賀支店に勤務されていた我谷さん(写真向かって左から二人目)が、この日たまたま万博に来られていて、一瞬合流。 |
 |
高見さんが副館長を務める「未来の都市」パビリオンを観覧。日立やクボタなどの多くの企業が未来の都市のイメージを表現。見どころが多い。 |
 |
西の方のエリアを歩いていたら、柵の外に飛ぶはずだった「空飛ぶクルマ」が置いてあるのを見かけた。これが運行されなかったのは残念だ。ただ、よく言われることであるが、これはどう見ても人が乗れる「大型ドローン」であって、この形状のものを「空飛ぶクルマ」というのは、ちょっと無理があろう。 |
 |
会場の外側を巡回しているバス「e Mover」。西の端から、東ゲートに戻るときに乗ってみた。 |
 |
バスの車内。運賃は400円。 |
 |
車窓からは、埋立地の原風景が望める。便利ではあるが、こういうのは本来は園内を周るきもので、「夢の世界から現実に引き戻された」ようにちょっと感じがした。 |
 |
大屋根リングの南の端を、外側から見たところ。 |
 |
万博は早めに引き上げ、梅田の阪急グランドビルのレストランで会食。向かって左端が高見さん。今回の万博には、何年も前から準備にずっと関わってこられたらしい。苦労話をあれこれと聴けた。お疲れ様でした。 |
2025年6月24日(火)
万博でリバーセル社が展示
 |
以前に少し書いたが、私(河本)が創業したベンチャー会社であるリバーセル社は、大阪ヘルスケアパビリオンに1週間、出展できることになっていた。この日は、その初日。 |
 |
10時入場の枠。天気予報ではかなり雨が降るとの事であったが、うっすらと陽射しがあり、暑かった。気温は最高気温30度くらい。 |
 |
手荷物の検査場。 |
 |
11時前に、ようやく入れた。今回は、秘書の中宮さん、宮武さんと、特定助教の小林さんとご一緒した。 |
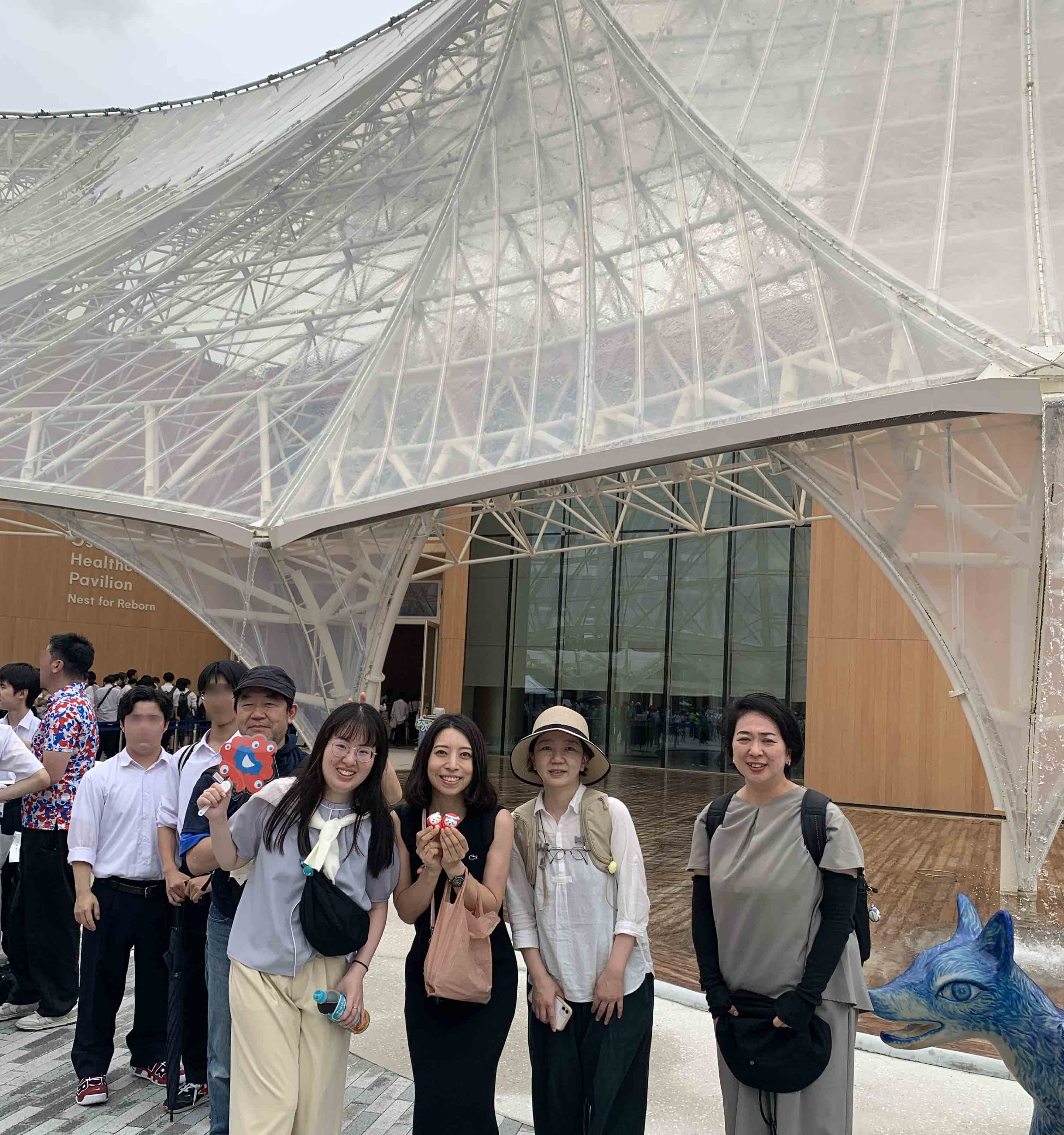 |
ヘルスケアパビリオンの前で、リバーセルの畑中さん(事業開発)、大久保さん(広報)と合流。 |
 |
このパビリオンの真ん中あたりのエリアは、iPS細胞を使った再生医療の常設展になっている。テストランで来た時の報告記事に書いた(2025年4月6日の記事参照)が、お世辞にも良くできた展示とは言えない。多くの疾患(網膜疾患、角膜疾患、パーキンソン病、脊髄損傷、貧血など)に対して実際に臨床試験が進んでいるのに、そのイメージがほとんど示されていない。勿体ない話だ。 |
 |
「未来のレストラン」「未来の美容院」などのテーマ別の柱状のブースが並んでいて、リバーセルの展示は「未来の病院」の中の一つ。左側のパネルは、3分くらいの動画をリピート再生していて、ちょうど私が出ている場面が写っている。なお、「会社名は出してはいけない」「パンフレットを置いてはいけない」「説明員を常駐させてはいけない」などのルールがあるようだが、動画の中で個人名を出すのはOKだったようだ。 |
 |
テーブルの上には免疫の仕組みを表した細胞キャラを並べるという演出。配置が乱れていたので、直しているところ。 |
 |
展示の全体像。左側のパネルで流した動画は、展示の終了後、YouTubeにアップしてあるので、興味のある方は、見ていただければと思う。 Expo2025 大阪・関西万博でも大好評!「リバーセルの再生キラーT細胞療法が未来の医療を変える!」(YouTube動画、約3分): |
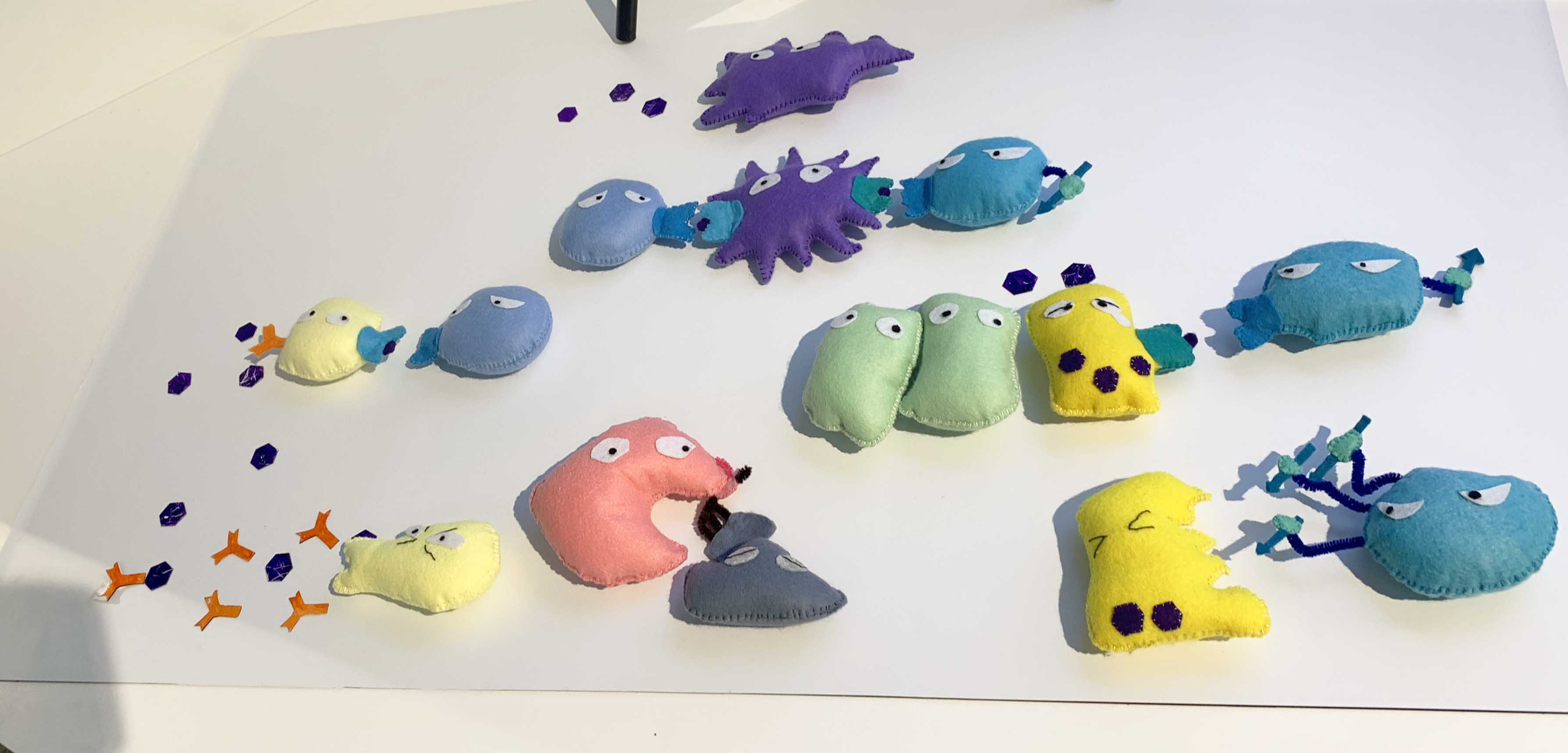 |
細胞キャラの部分のアップ。秘書の宮武さんが創ってくれた。 |
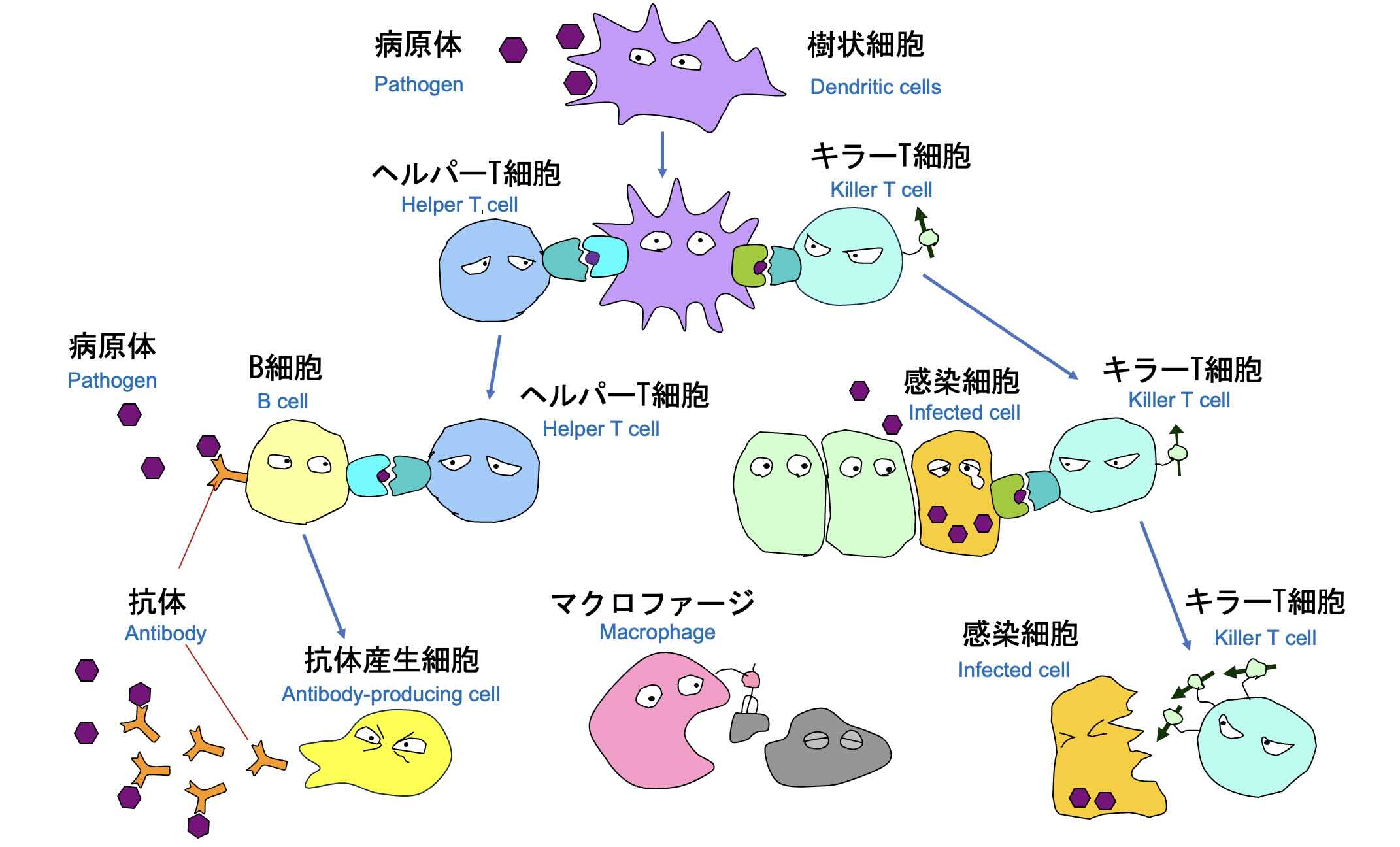 |
参考までに、原図と細胞名。 |
 |
リバーセルの関係者と一緒に記念写真。後列左から二人目は梶川社長。万博での展示は、出したい会社はどこでも出せるというものではなく、リバーセルのスタッフの奮闘により、大阪産業局が主催する「スタートアップが開発するイノベーティブな製品・サービスの展示」に採択されたおかげである。10倍以上の競争率だったらしい。一旦採択されると、出展料などは必要がなく、また動画の制作費などについても補助が出る。ありがたい話だ。 |
 |
大屋根リングの中の通路。スケール感に圧倒される。 |
 |
会場の真ん中あたりに、15分ごとに霧を噴き出すエリアがある。この日は風があまり吹いていなかったので、濃い霧が一帯に立ち込めて、動くと人にぶつかりそうで怖いくらいだった。 |
 |
お目当ての中東系のパビリオンのレストランが混んでいたため、リング外のマーケットプレイス西にある「550円で50分の席料」のフードコートに行ったところ、予約で満席。テストランの時はガラガラだったのに…。仕方なく外の席で食べる覚悟をしたところ、近くの中国山東料理の店に空きを見つけて、そこで昼食。麺類も美味しかったが、肉まんのように皮が厚い焼き餃子も美味しかった。 |
 |
ヘルスケアパビリオンに戻って、細胞キャラの配置を示す図を描いて設置した。来場者、特に子供達が手に取って、その後適当に置くので、すぐにばらける。「配置図があれば誰かが直してくれるのでは」という期待を込めている。 |
 |
大久保さんが会場内の売店などを探してくれたが、太字が書けるペンや色鉛筆などが見つからなかったので、ボールペンで描いた。 |
 |
テーブル面の左上の方に貼り付けた。 |
 |
作業を終え、動画に合わせて記念写真。 |
 |
その後大屋根リングに登り、北半分を半周。 |
 |
事前の予約で取れたのは関西パビリオン(15時45分〜)と夜のパレード(レジオネラ菌のせいで中止)だけだった。当日予約のページから検索しても、4人で入れそうなところはなかった。それで、並んだら入れそうな各国のパビリオンなどを見て回ることにした。ネットで見つけたランキングなどを指標に、まずはサウジアラビア館を訪問。 |
 |
20分くらいの待ち時間で入れた。靴職人が靴を作っている。 |
 |
楽器の演奏も聴けた。建物も雰囲気があり、全体的には十分楽しめた。 |
 |
事前予約で入れた関西パビリオンで、三重県のブースの入り口にある鏡のトンネル。過去へ旅立つタイムトンネルという設定らしい。スタッフが写真を撮ってくれた。なお、予約で関西パビリオンには入れても、それぞれの県の人気のブース(例えば福井県の恐竜、鳥取県の砂丘など)は再度並ぶ必要があった。なお、関西といえば基本的には京都、大阪、滋賀、奈良、和歌山、兵庫で、三重、徳島、福井はまあ広義には関西といえなくはないが、鳥取はちょっとどうよ、と思った。 |
 |
京都のブースに、カラフルな漆器の展示があった。これらも、週替わりであるらしい。 |
 |
関西パビリオンを出て、すぐ近くのベトナム料理屋(サイゴンカフェ)で休憩&おやつタイム。皆はソフトクリーム、私は春巻きとベトナムのビール。 |
 |
自分達で挙げた「行ってみたいパビリオンリスト」の上位にあった「トルクメニスタンパビリオン」を訪問。20分程度の待ち時間で入れた。 |
 |
入ってすぐに見せられた映像も良かったし、2階の展示もとてもしっかりしたものだった。トルクメニスタンは、カスピ海の東側に位置しており、面積は日本より少し大きいが、人口は700万人程度とのこと。独裁政権による全体主義国家との事だが、石油や天然ガスなどの資源が豊富で、まあ勿論いくばくかのプロパガンダはあるのだろうが、全体に「豊かな国」という印象だった。こういう事を体感できるのが、万博の本来の姿であろう。 |
 |
中央アジアの装束は、何故か懐かしいような気にさせてくれる。 |
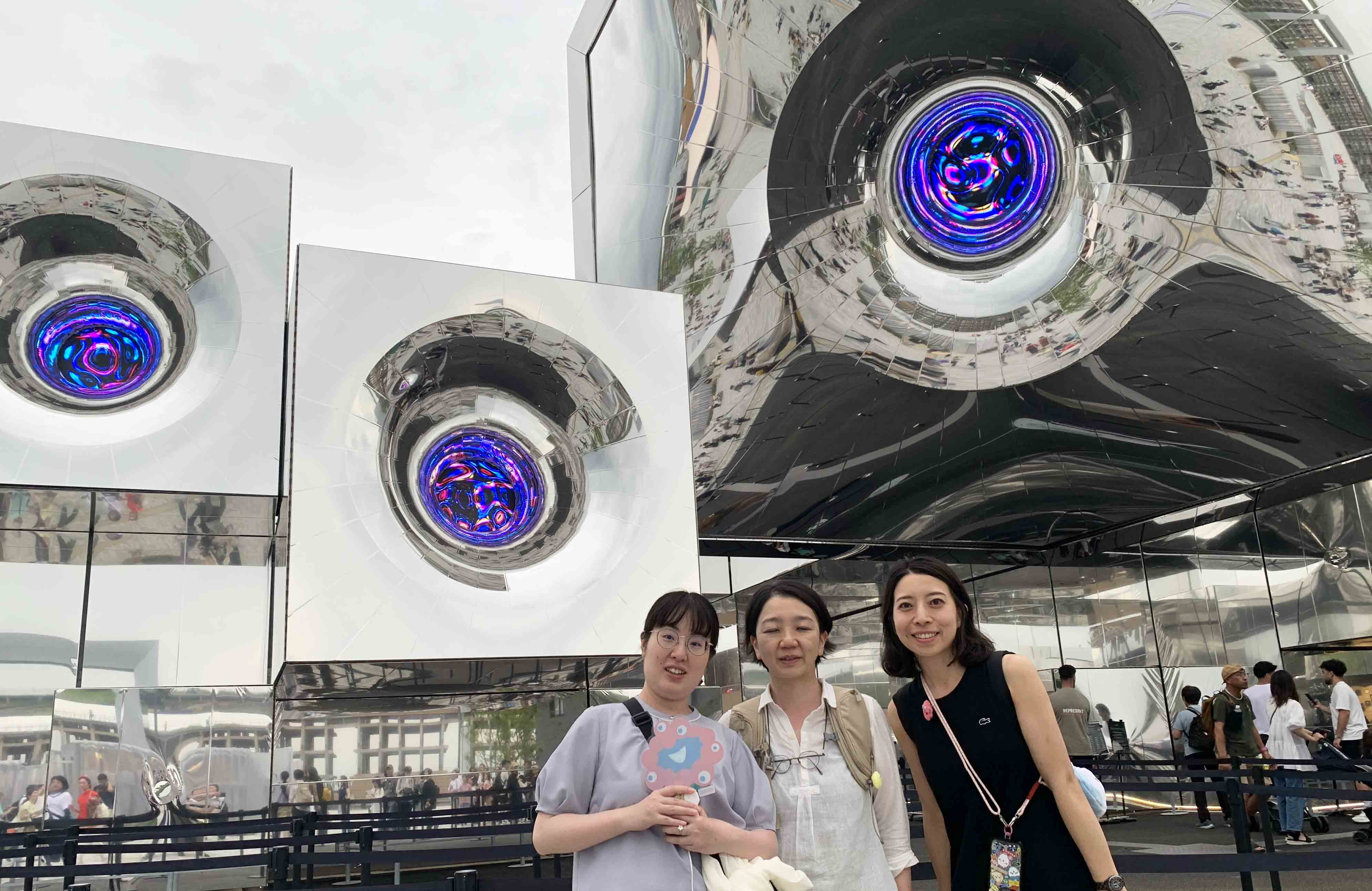 |
落合陽一プロデュースのヌルヌル館は、競争率30倍とのこと。しかし、中に入らなくても、外から建物を見るだけでも、十分見応えがある。鏡のように外界を反射している壁が振動したり、ぐにゃぐにゃと歪んだりしている。時折、地鳴りのような重低音が響く。写真の目玉のような構造物では、真ん中の円盤の図形が水面に落とした絵の具をかき混ぜるように変化し、悪い夢でもみているかのようだ。NOIZという建築・デザイン会社が手がけたらしい。 |
 |
18時半頃、夕食タイム。あてにしていたハンガリー料理やルーマニア料理はすでに売り切れ閉店となっていたが、すぐ近くのポーランド料理の店に入れた。 |
 |
セットメニュー。もう一つのセットはベジタリアン向けだったので、これ一択。手前左は「ポテトとチーズ入りピエロギ」。マッシュポテトと自家製トヴァルグチーズを詰めた餃子とベーコン。手前右はビゴスというポーランド風キャベツ煮込み。スモークソーセージが入っている。奥の左端はトマトスープ。奥の中央はライ麦プレッドにパセリとディル入りのハーブクリームチーズ添え。奥右端はレモンヨーグルトケーキ。飲み物は、お酒に関してはビールやワインはなく、酎ハイ的なものしかなかった。料理は税抜きで4500円。それぞれの料理が普通に美味しく、ポーランド料理なんて食べる機会はそうはないだろうからということで、一同、大満足だった。 |
 |
多くの国の展示が入っているコモンズという建物の中の一つ、コモンズDに入った。パキスタンのコーナーでは、岩塩のオブジェが印象的だった。赤いのは、鉄分によるものらしい。 |
 |
コモンズでは土産物屋さんが散見される。前から欲しかったカリンバが手頃な値段で売られていたので、購入。 |
 |
レジオネラ菌のせいで、夜のパレードは中止になっているが、この日は強風という予報だったので、ドローンショーも中止。チェコ館を訪問。チェコといえばボヘミアガラスが有名。 |
 |
螺旋状の通路を上がっていく。壁画は好きにはなれなかったが、ところどころいい感じのオブジェが見られた。 |
 |
いのちの遊び場クラゲ館は、夜に入るとライティングが結構良い。 |
 |
実物大ガンダム。夜見るとさらにかっこいい。 |
 |
西ゲート近くの土産物屋で買い物をした後、帰路につく。途中で見たネパール館。まだ開館していない。7月上旬の開館を目指してはいるらしい。 |
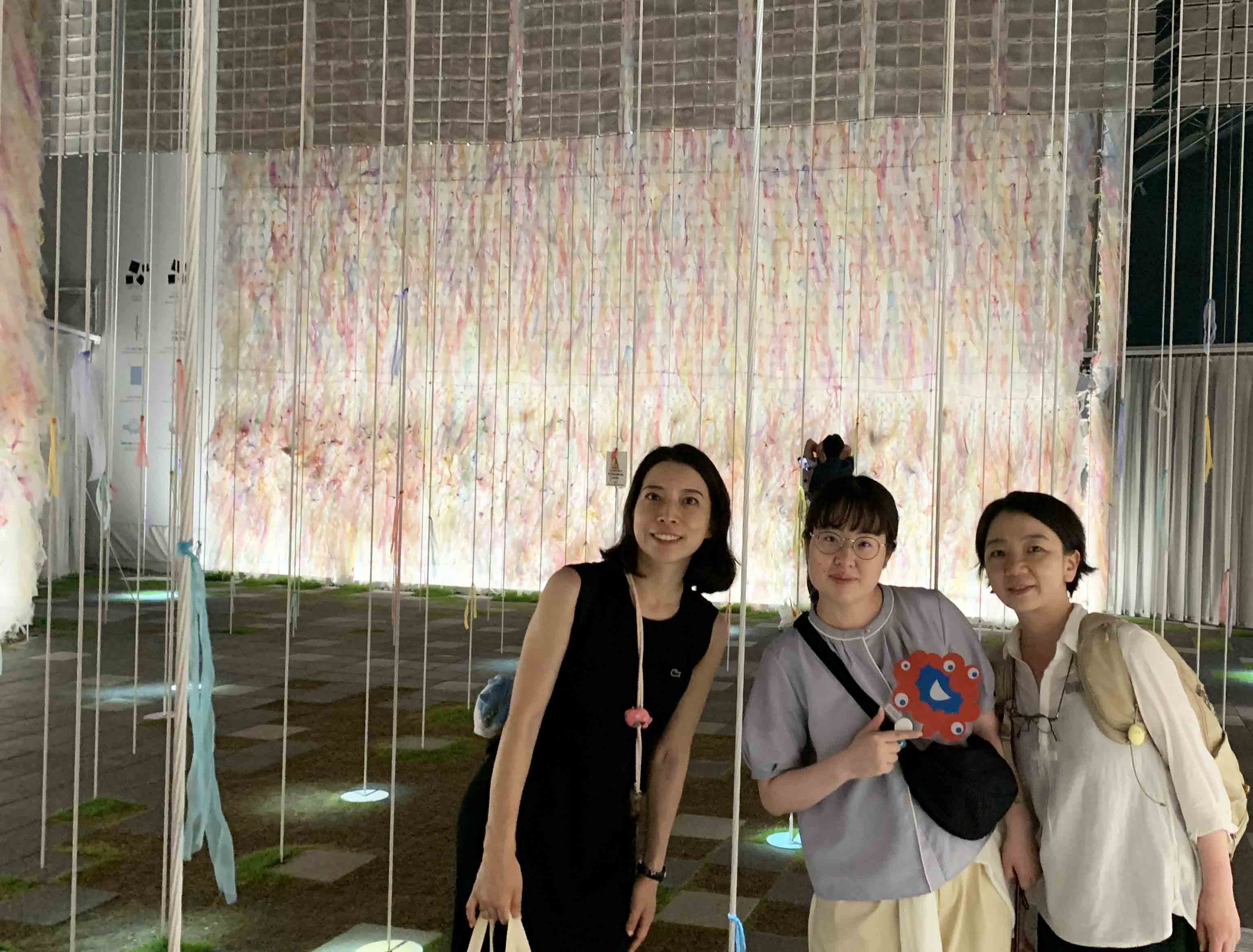 |
東ゲート近くのNTT館の一部は、通り抜けが可能だった。鉄線を弾くと、ボヨンとした音が鳴り響く仕掛け。この日、万歩計によると、「28000歩」、歩いたようだ。距離にしたら18kmくらいか。4時間以上歩いたことになる。タフな行程だったし、必ずしも予定通りに行かなかったが、それでも万博を十分に楽しめた。 |
2025年6月22日(日)
葵小学校6年1組のクラス会
 |
コロナでしばらく集まれなかったが、昨年、再開(2024年8月25日の記事参照)。葵小学校の近くの「かごの屋」で昼食。気が置けない人達ばかりで、いい集まりだ。 |
 |
この日は、誰が言い出したか知らないが、食後に、店の向かいにあるジャンカラに行こうという話になっていた。しかし、幹事の船越君が問い合わせたところ、夜まで予約で埋まっているとのことであった。船越君が近くの他の店もあたってくれたが、どこも満室。日曜日の昼間からカラオケに行く人がそんなにいるんだと、ちょっと驚いた(自分達もそうであるが)。あれこれ探してくれた結果、三条河原町のジャンカラが空いているとの事で、タクシ―2台で移動。元々は「歌うよりもゆっくり話をするスペースとして使おう」という予定であったが、実際には昔懐かしい曲を次々に歌いまくって、あっという間の2時間だった。私はいつもの「ボヘミアン」を歌った。 |
 |
「楽しかったので、また皆で行こうね」という事になった。皆、いい顔をしている。 |
2025年6月21日(土)
第3回京大-中国医薬大学合同シンポジウム
 |
この日の14時から18時まで、表記の会がCCIIのニトリホールで開催された。今回は第3回という事であるが、第1回は芝蘭会館で(2023年12月20日の記事参照)、第2回は中国医薬大学で(2024年11月19日の記事参照)、開催されている。なお、日本台湾生技協会(Japan Taiwan Biotech Association:JTBA)というのは、台湾から日本に来ている留学生を中心にしたコミュニテーで、一定の頻度で講師を招いて勉強会を催したりしているらしい。鈴木淳先生(iCeMS)が、それを聞きつけて、「そういう人達に聴いてもらったら、京大のオンサイトラボの宣伝になって、オンサイトラボで働きたいという人が増えるのでは」と言い出し、それで今回はJTBAとの共催という形になった。 |
 |
会場。現地とオンラインで総勢80人くらいが参加という事で、結構な盛会になった。私は16時までKTCCがあったので、16時半ごろに、情報交換会用の差し入れのビール(50本/クーラーボックス2箱)を持参して、参加した。 |
 |
Ling-Yo Yang教授(中国医薬大学Dean)による閉会の辞。これまでの経過を総括した上での、encouragingないい挨拶だった。 |
 |
情報交換会にて。向かって左から村松正道先生(神戸先端医療研究センター)、萩原正敏先生(京大)、私。 |
 |
向かって左から但馬正樹先生(CCII講師)、山口浩史先生(中国医薬大学教授)、私。山口先生は京大と中国医薬大学をつなぐ重要な役割を担われている。 |
 |
Ling-Yo Yang先生を囲んで。いい写真だ。 |
2025年6月21日(土)
KTCC用のイラストについて
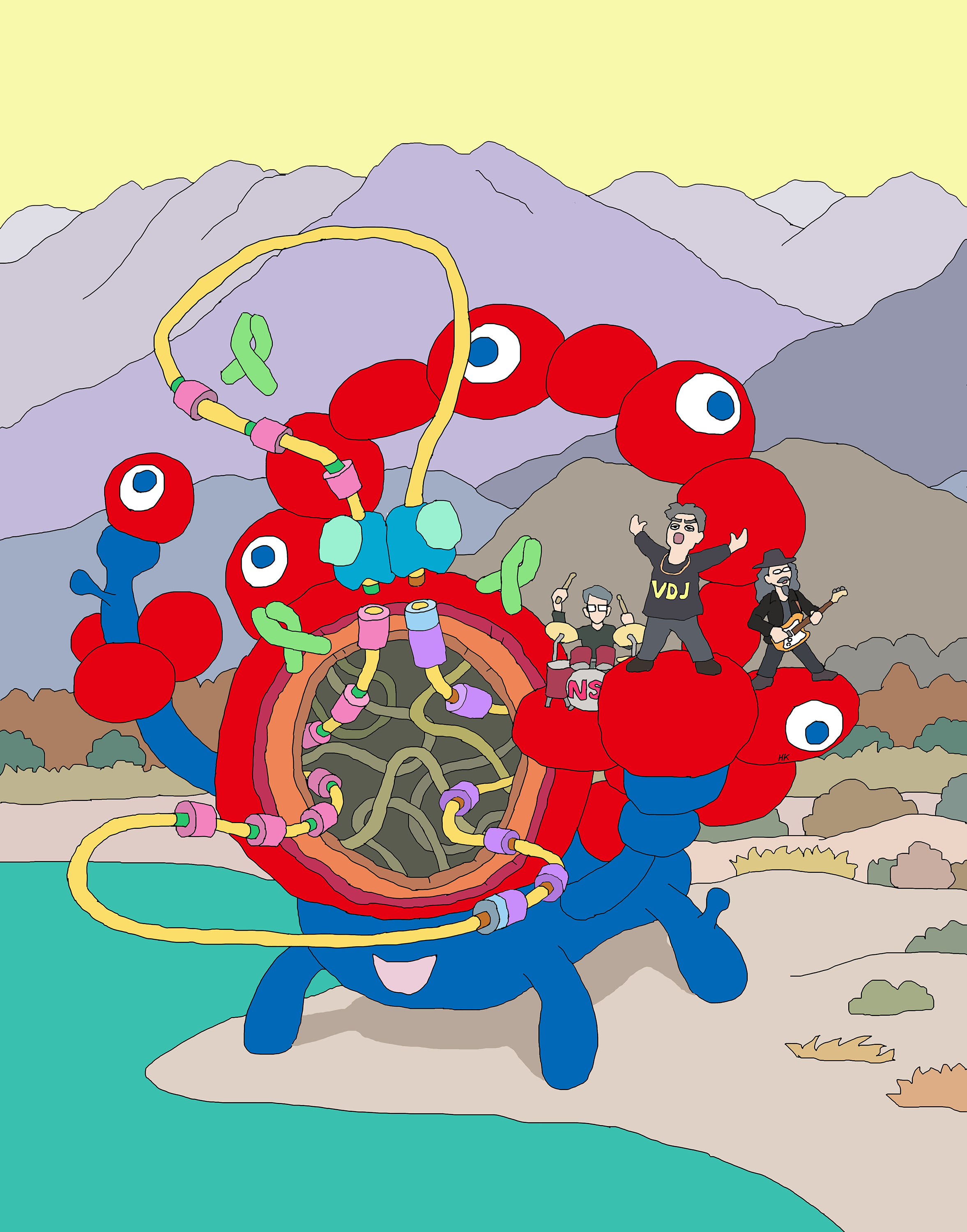 |
左は今回のKTCCの抄録集に載せるようにと描いたイラスト。どういう経緯で描いたかを解説する。 |
 |
今回の集会長である縣保年先生は、ネガティブセレクションのセカンドアルバムの中で「VDJ-recombined」という曲を歌っておられる。ミュージックビデオも制作し、Youtubeに載せている(下記リンク参照)。このビデオは冬の琵琶湖畔で撮影した映像が織り込まれている。 【T細胞の懊悩】VDJ-recombined(YouTube動画) |
 |
松ノ浦というところで撮影した。琵琶湖側から写すと、背後に比良山がそびえる。これらを基本イメージにしようと考えた。 |
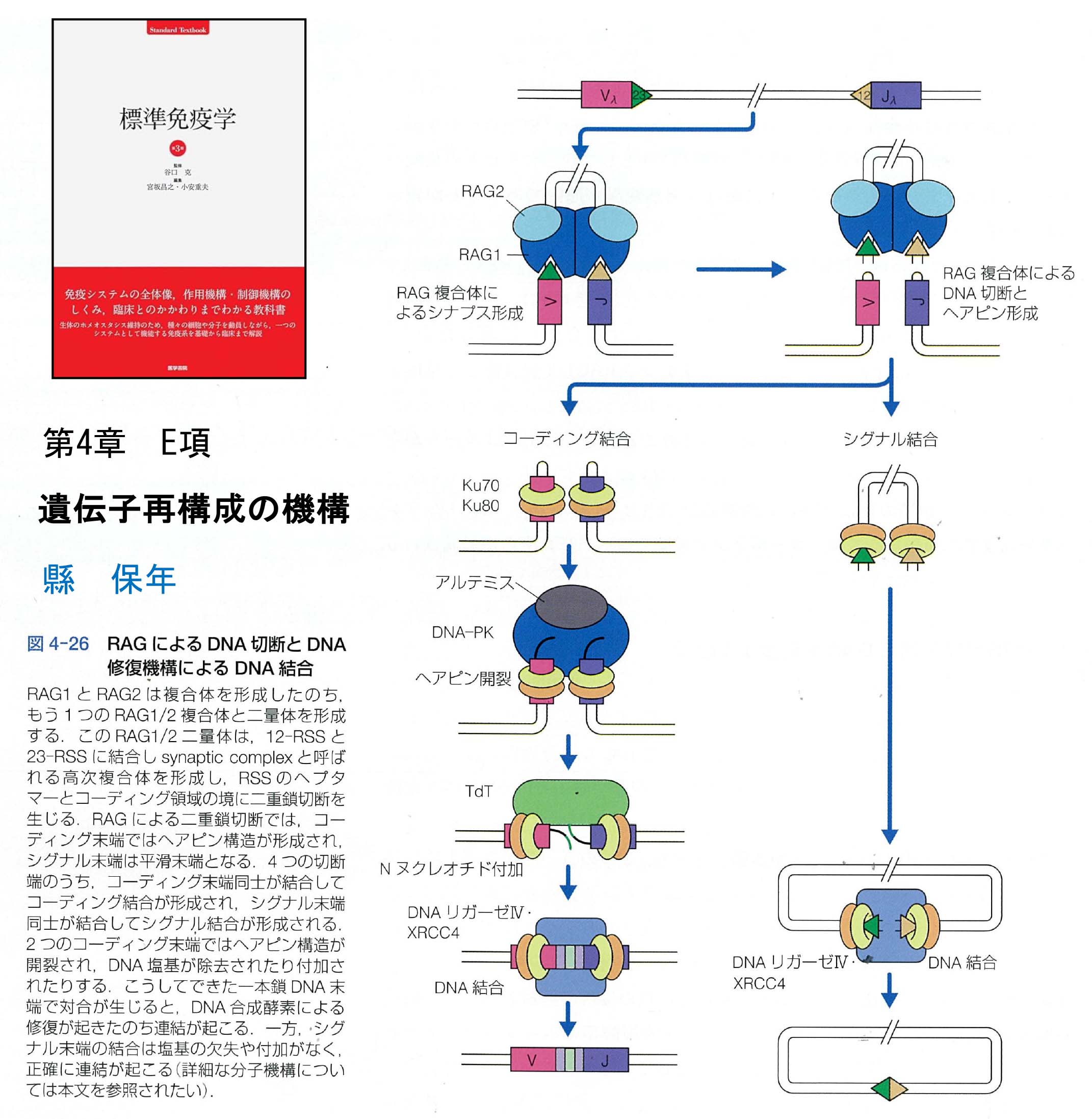 |
縣先生は標準免疫学の中の第4章E項「遺伝子再構成の機構」を書かれている。その図のイメージを使わせていただく事にした。この図は、青と水色の分子(RAG1とRAG2)がゲノムDNA鎖をループ状に切り出すことで、V領域とJ領域が繋がることを示している。 |
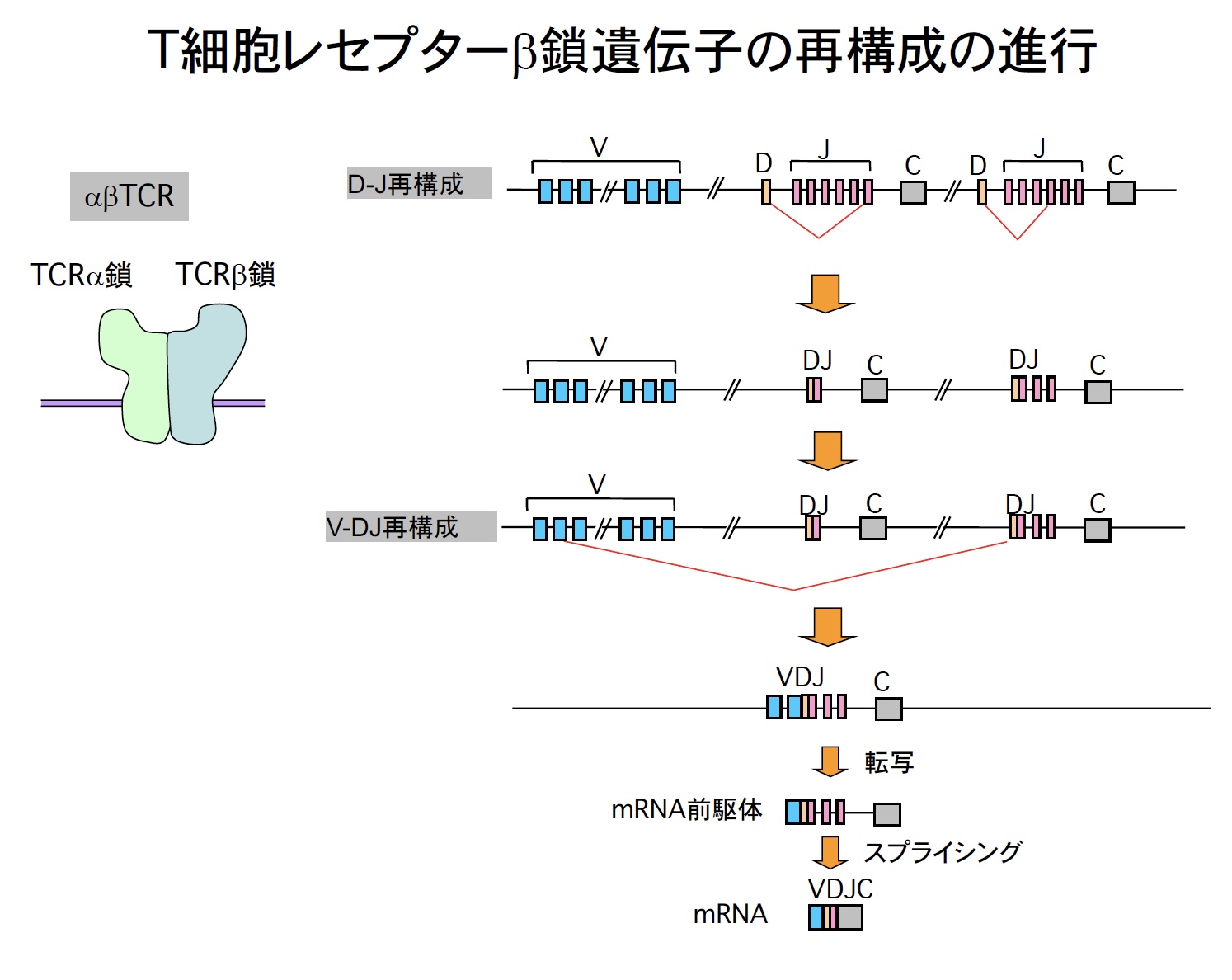 |
上の図はD-J再構成の機序を示しているが、例えばTCRベータ鎖の場合、V、D、Jという3種類の部位があり、まずD-J間がつながり、次にV-DJ間がつながるという順序で、VDJ再構成が完了する。左は、私が講義でよく使う図(自作)。 |
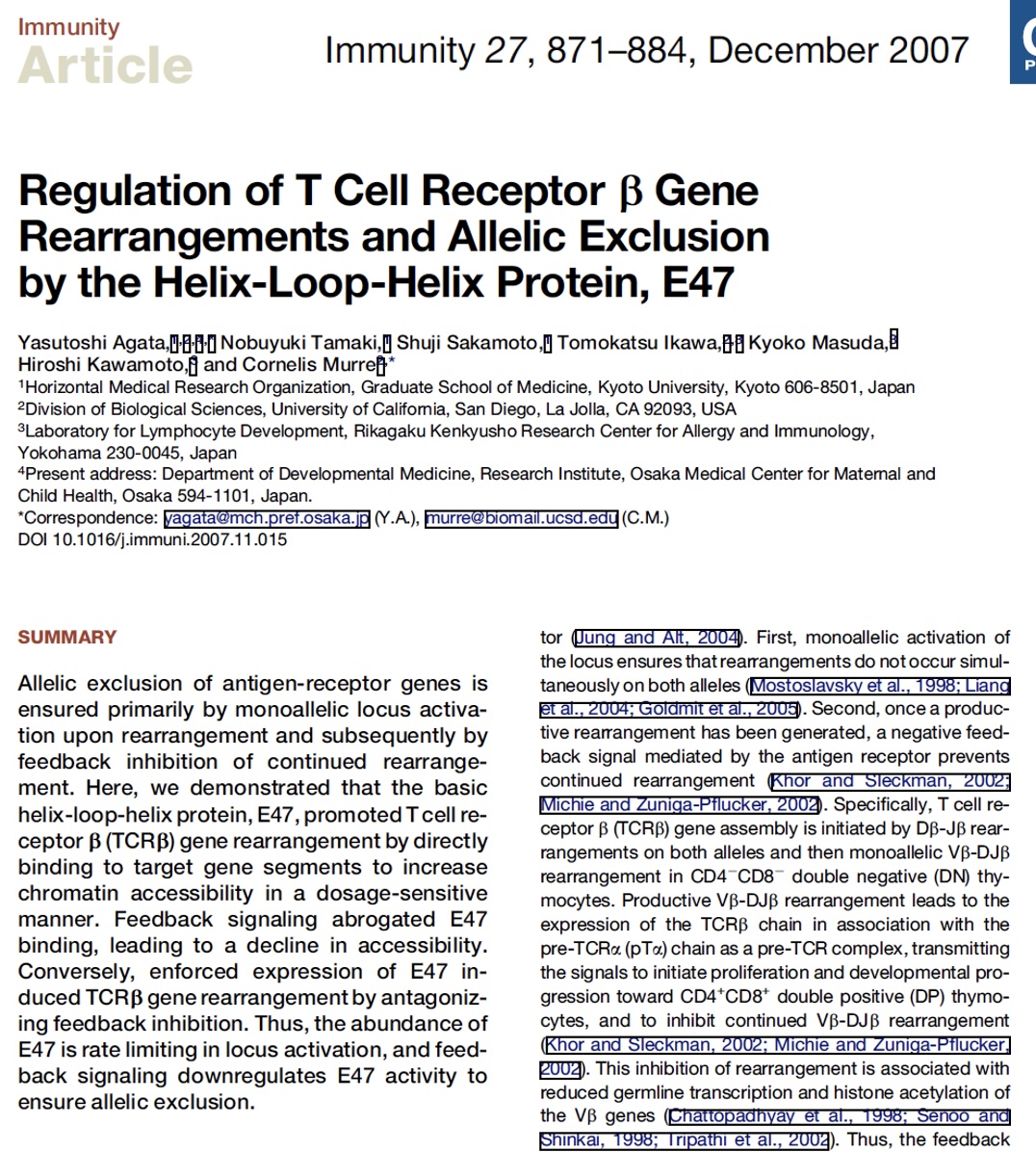 |
もうひとつ参照したかったのが、左の縣先生によるImmunity論文(2007年)。TCRベータ鎖はまず片方が再構成して、もしそれに成功したらもう片方が再構成されることはないという現象(対立遺伝子排除)が知られている。2種類の抗原レセプターを出さないようにするための、免疫にとっては重要な仕組みである。この論文は、片方だけまず再構成される際には、E2Aという転写因子が適度に少ない事が重要、ということを示した。E2Aが多すぎると、両方の対立遺伝子が再構成されてしまうことが示されたのである。この研究には増田喬子さんが湊研の大学院生だった頃によく協力したので、増田さんの名前と私の名前も入っている。 |
 |
スケッチ第1稿。琵琶湖からDNAの鎖が出てきている。 |
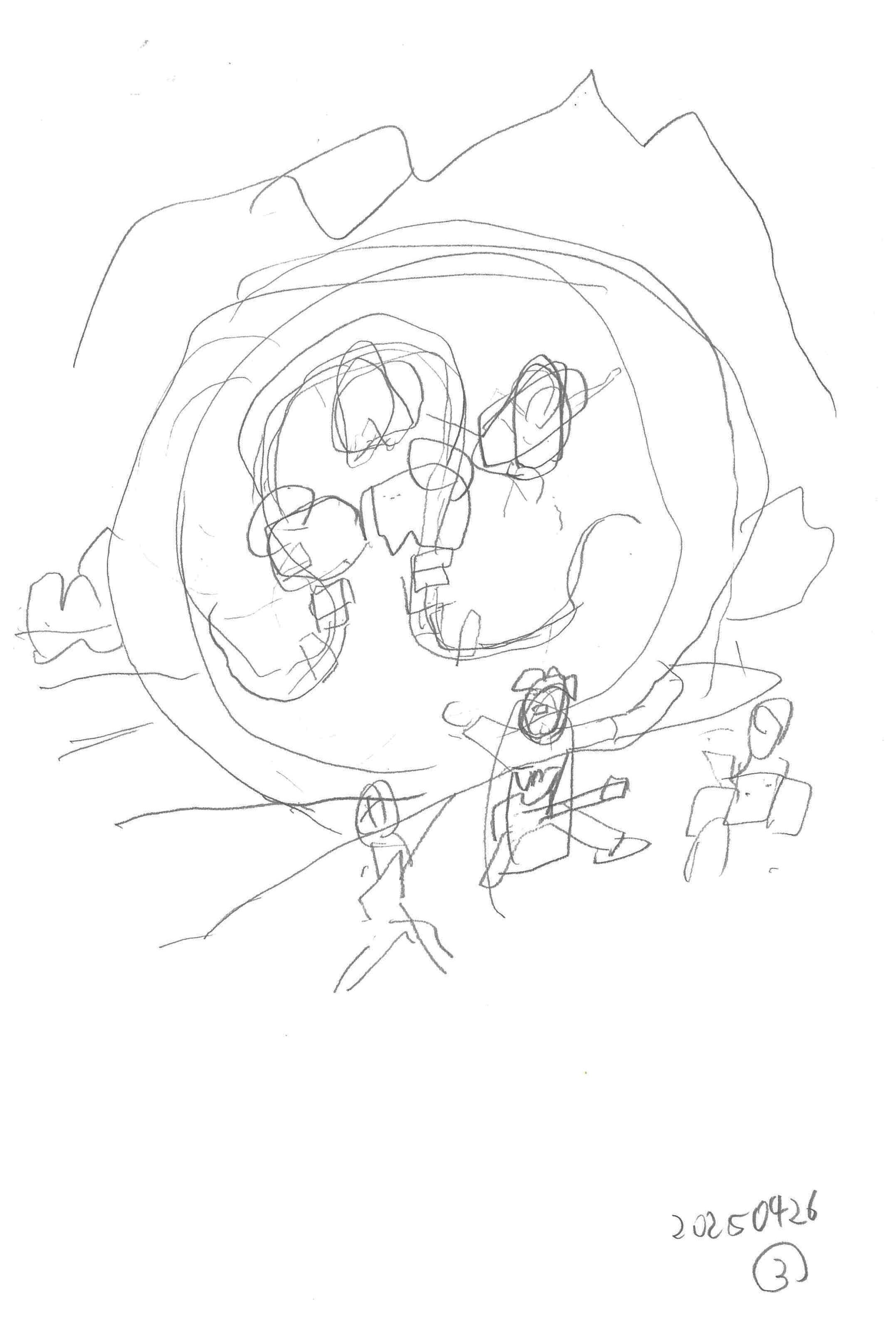 |
スケッチ第3稿。細胞の核の中で再構成が起こっているイメージにしてみた。しかし、何か物足りないような気がして、先に中々進めなかった。 |
 |
このあたりで、ちょうど万博の開催期間中だから、「ミャクミャク」のイメージを使おうと考えた。ミャクミャクの公式ページには、左図のように色々な形態を取りうることが示されていた。また、「商売に使わない限りは、二次創作は問題ない」という記載も見られた。なお、どの形態でも正面から見えている目は5個であるから、これは守らないといけない原則だと思った。実はしっぽにも目が一つ付いているので、体全体としては目は6つという設定のようだ。 |
 |
ミャクミャクの公式プロフィールにも、特技として「色々な形に姿を変えられる」とある。 |
 |
そこで、四つ足のミャクミャクのイメージを組み合わせる事にした。これにより「ああ、これはいけそうだ」と思った。 |
 |
その方針で、イメージを整理。 |
 |
前図に、色鉛筆で彩色してみた。 |
 |
このイメージで行こうと決め、本番用の下書きを作成。 |
 |
下書きをPCに取り込み、違うレイヤーでパッドやマウスを使って下書きをなぞるようにして、線描画を作成。これは抄録集の裏表紙に使ってもらった。 |
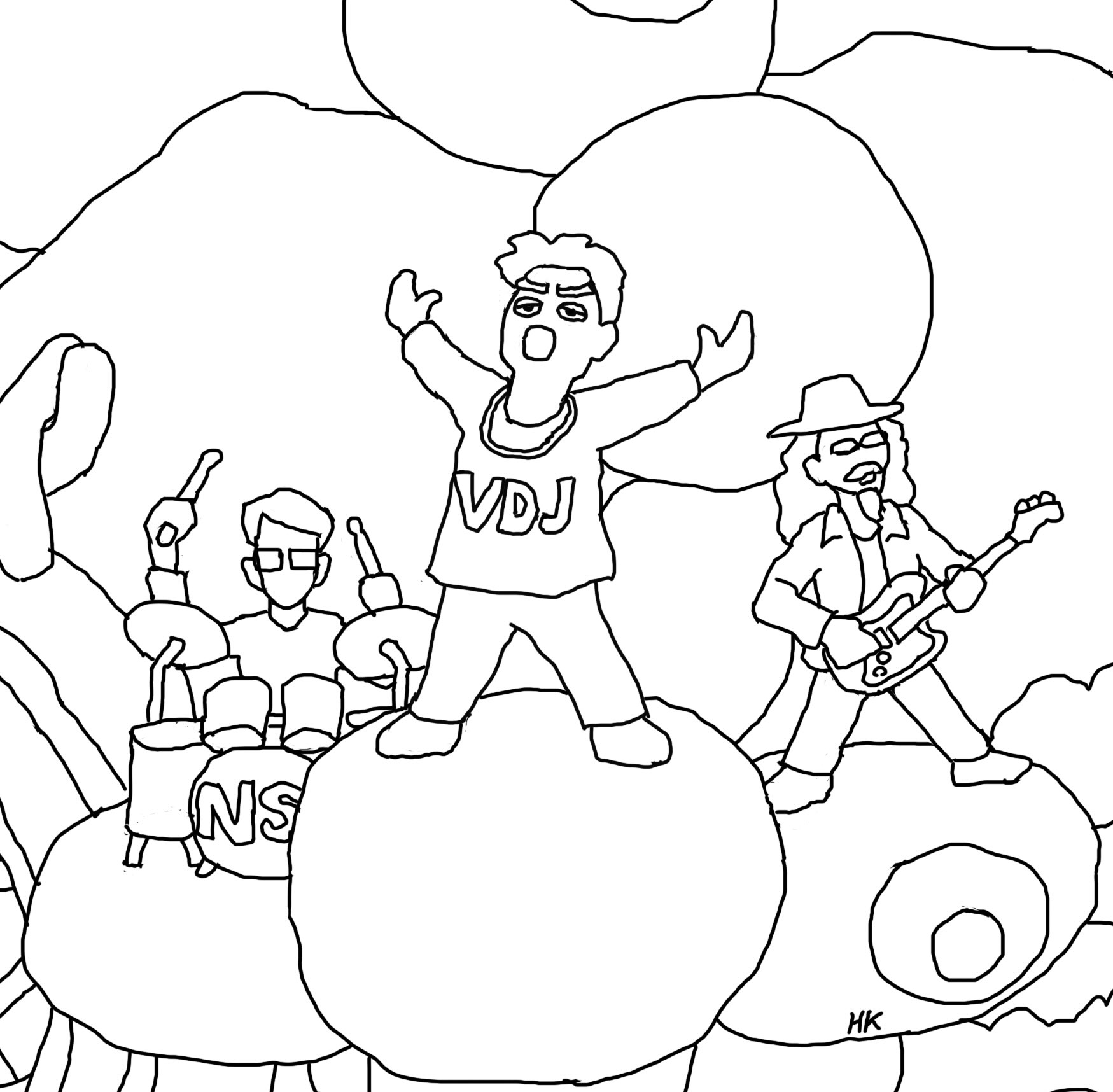 |
イラストの中の縣先生が登場している部分をトリミングして、抄録集の表紙に使用してもらった。 |
 |
彩色してバージョン(この記事の1枚目と同じ)。万博との絡みもあるので、今回の抄録集には、この彩色バージョンも挿入して頂いた。 |
2025年6月20日(金)ー21日(土)
第34回KTCC
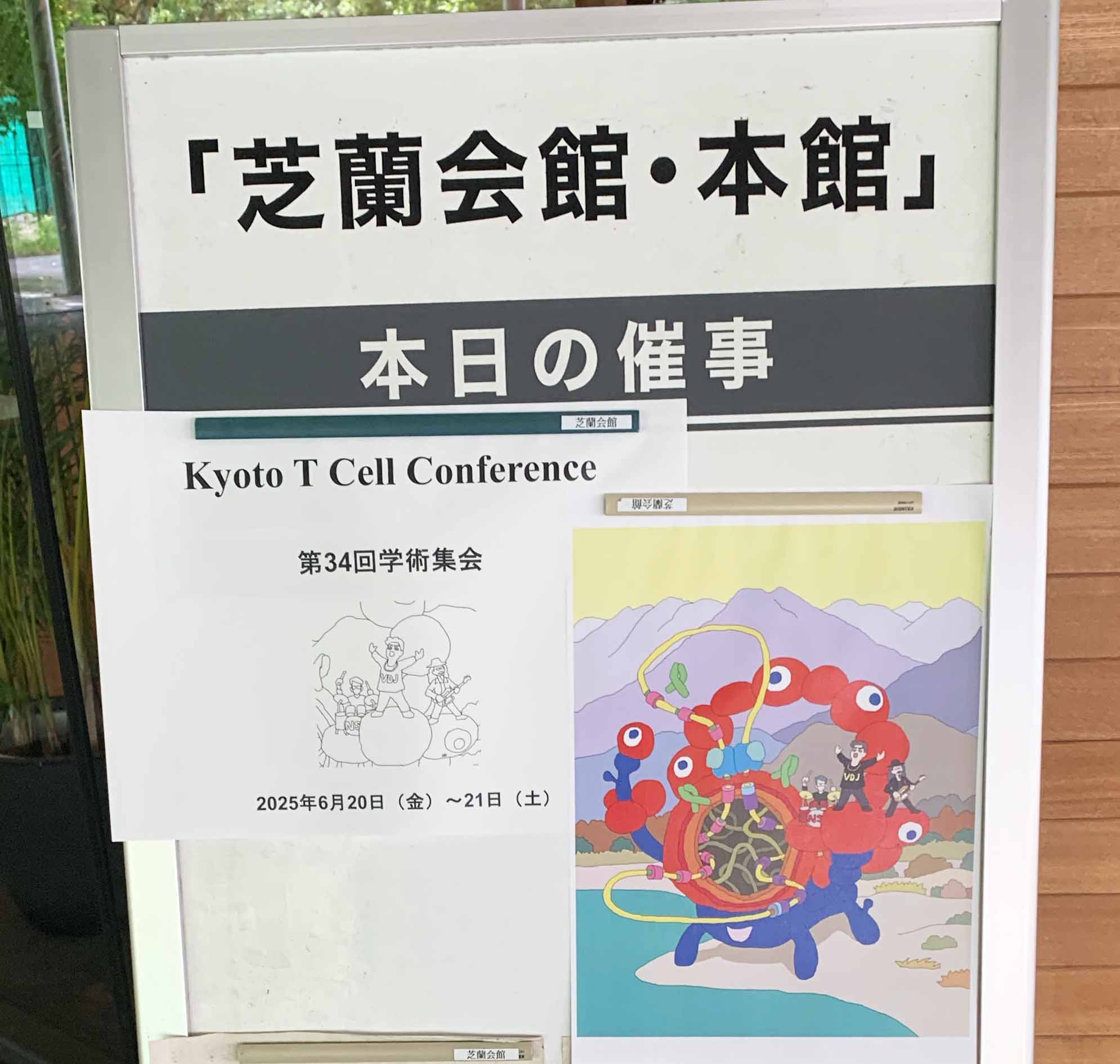 |
芝蘭会館の玄関口の看板。今回の会に合わせて描いたイラストも掲示した。 |
 |
受付。 |
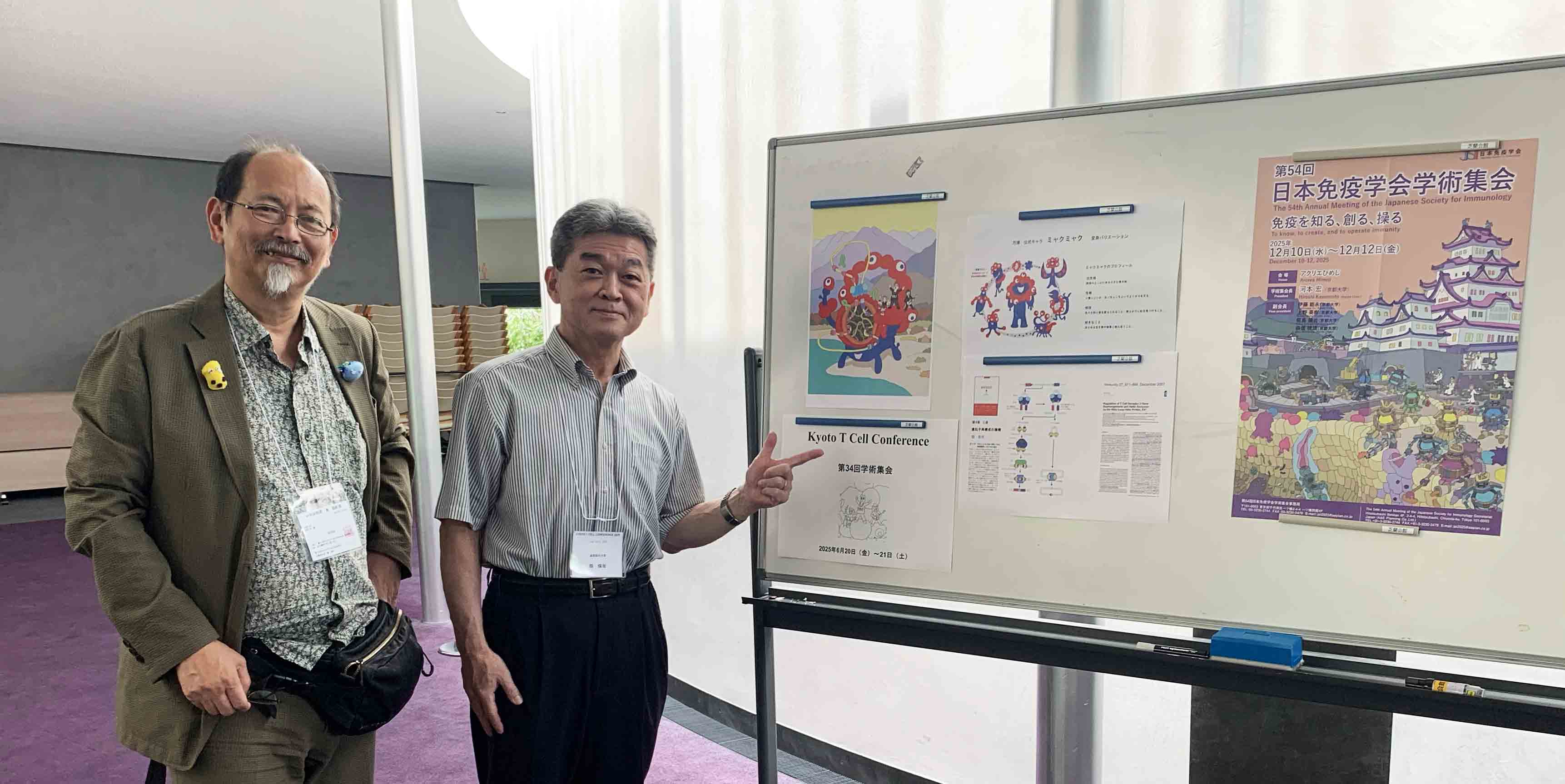 |
稲森ホールの入り口の横に、今回描いたイラストの説明などをホワイトボードに貼り付けて提示。集会長の縣保年先生(滋賀医大)と。イラストについては、次の記事で解説する(2025年6月21日の記事参照)。 |
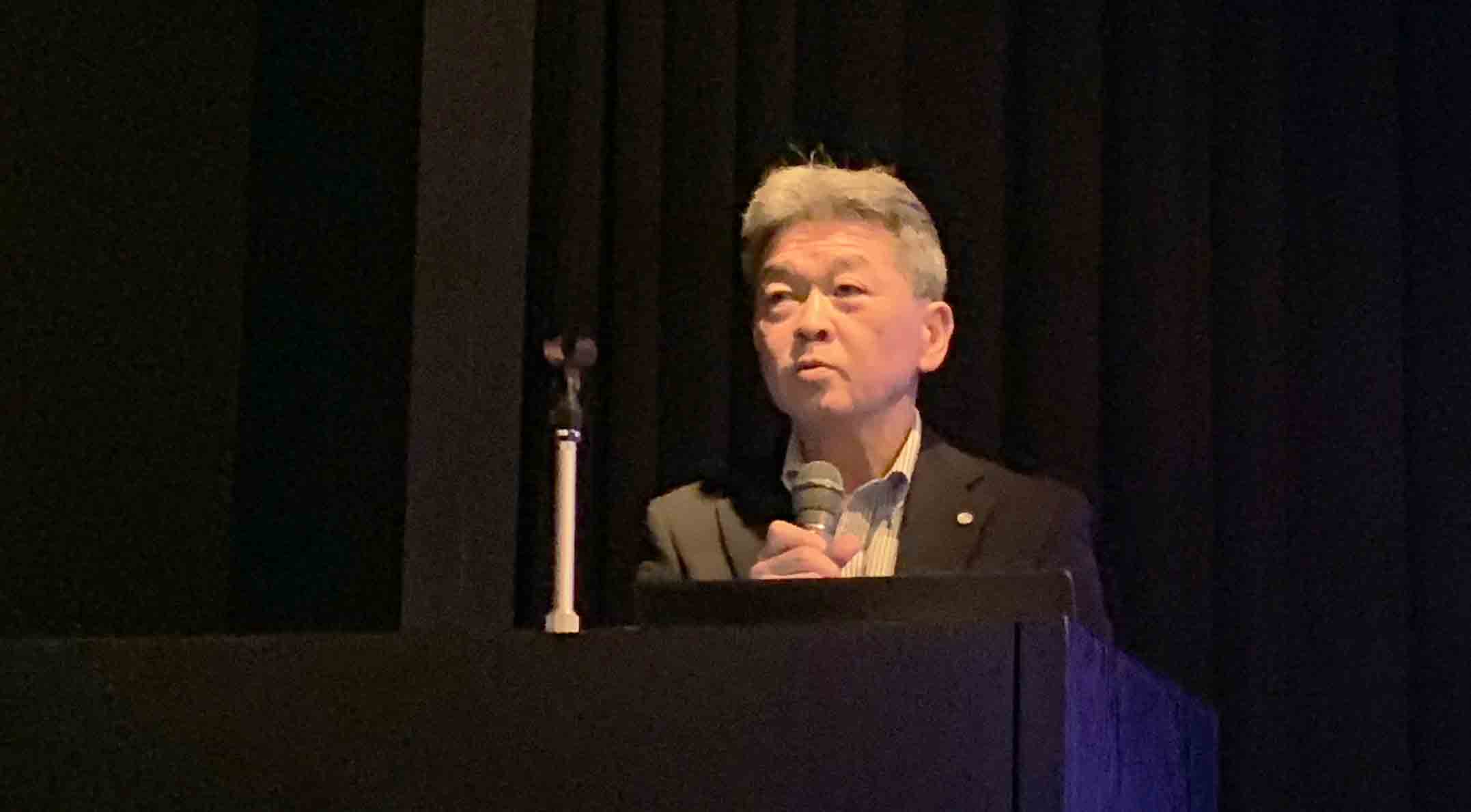 |
集会長の縣先生による挨拶。 |
 |
参加人数は150人以上になり、昨年に引き続き大盛況だった。コロナ前は130人くらいだったので、かなり増えている。いいことだ。5分発表、5分討論という討論中心の会であるが、昨年に続き、若い人が次々と質問に立ち、いい感じでKTCCのスタイルが引き継がれている。 |
 |
コーヒーブレーク。写真向かって右端より上田祐司先生(獨協医大解剖学准教授)、徳田信子先生(獨協医大解剖学教授)、縣先生、鈴木春巳先生(国際医療研究センター)、私。 |
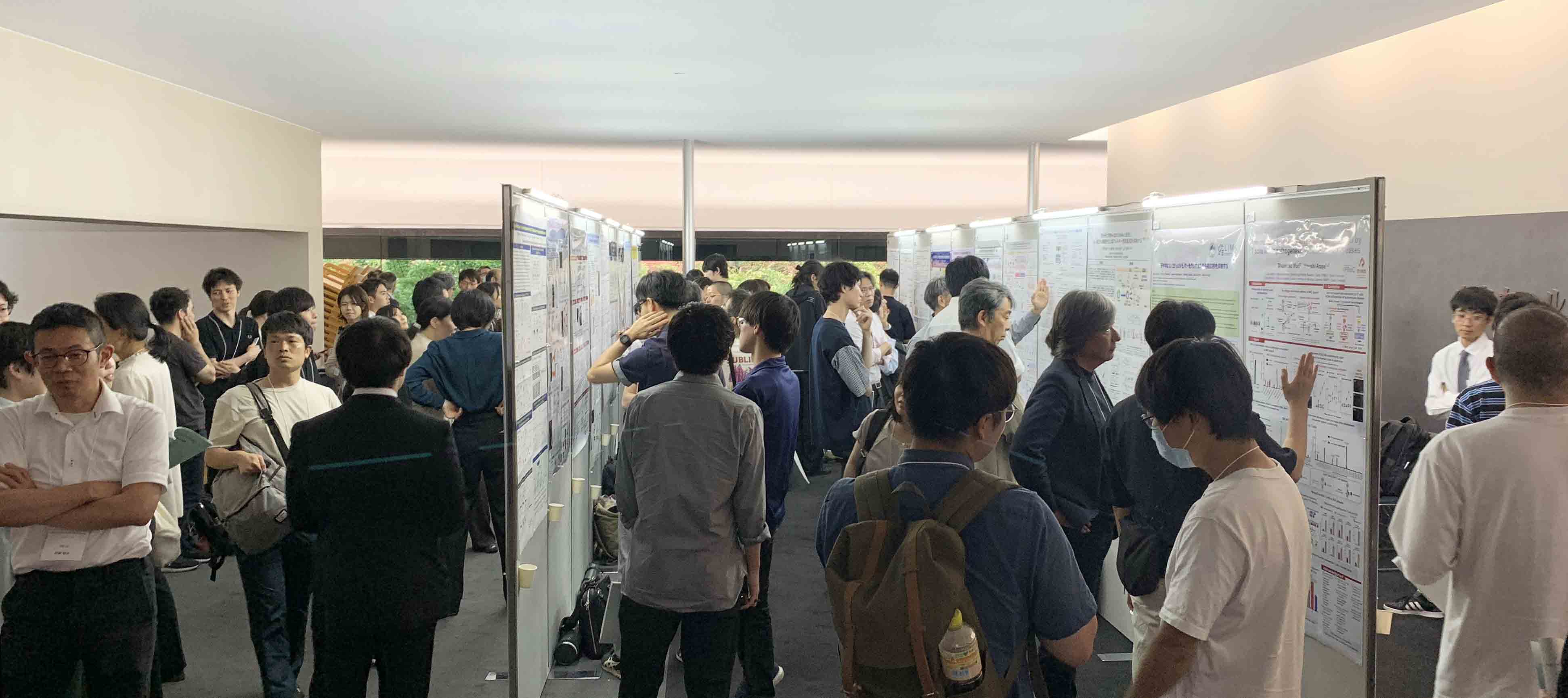 |
ポスター発表。KTCCは原則全員がポスター掲示+口頭発表であったが、応募演題数が増えたことから、一昨年と昨年は、10件くらいはポスターだけという事になっていた。今年は、全員が口頭発表できたようだ。 |
 |
山内ホールで開催された情報交換会。 |
 |
最初の挨拶は垣生園子先生(順天堂大)がされた。若い人を叱咤激励するような内容だったと思う。 |
 |
乾杯の音頭は小安重夫先生(量子科学技術研究開発機構理事長)がされた。「質問の前に”興味深い話をありがとうございました”みたいな賛辞は時間の無駄」「後ろに質問に立っている人がいる場合は質問を短めに切り上げるように」などのような説教をいただけた。同感だ。 |
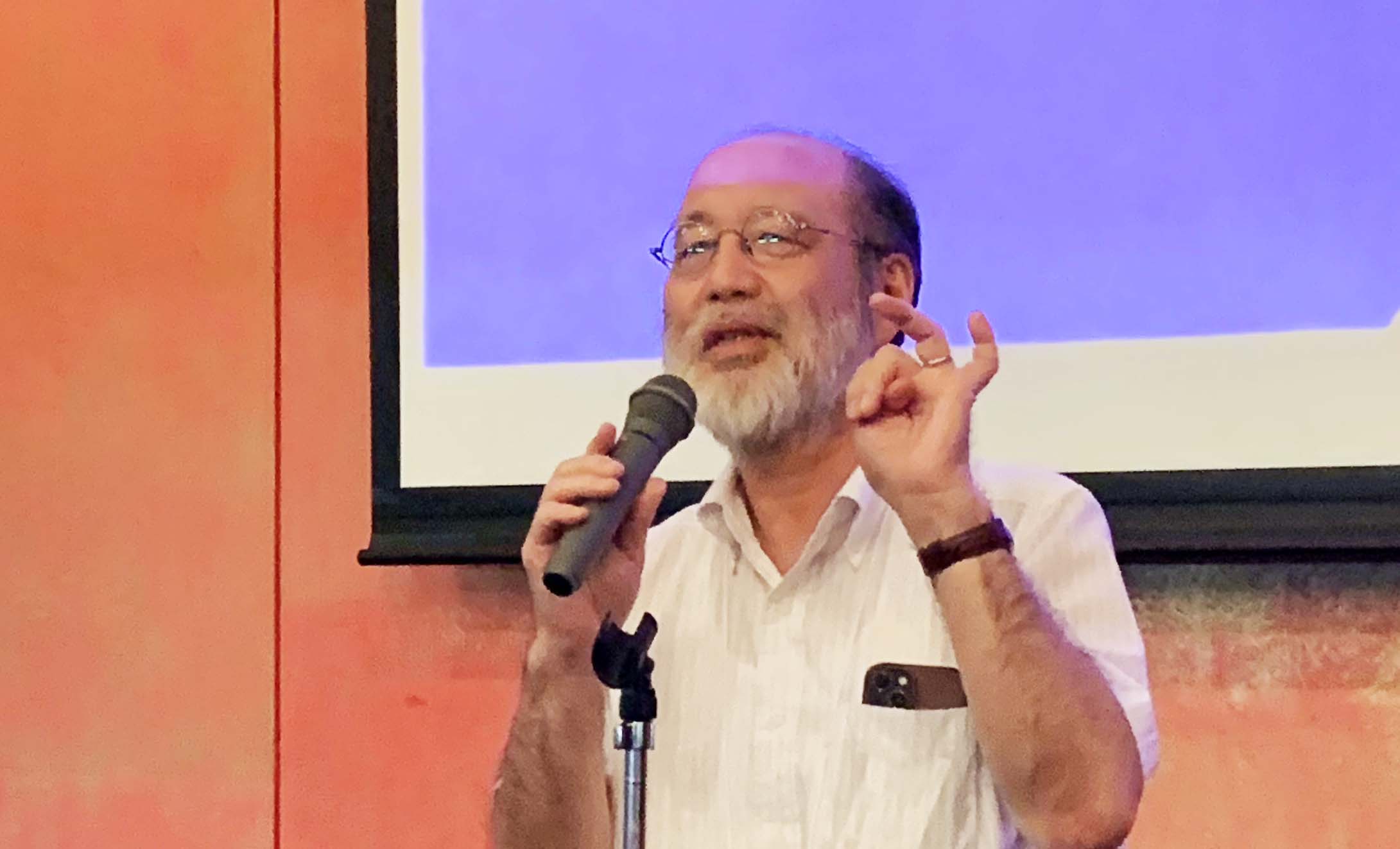 |
谷内一郎先生(理研IMS、現KTCC代表)が、来年の国際KTCCは参加料を他の国際学会並みに上げる可能性について話された。 |
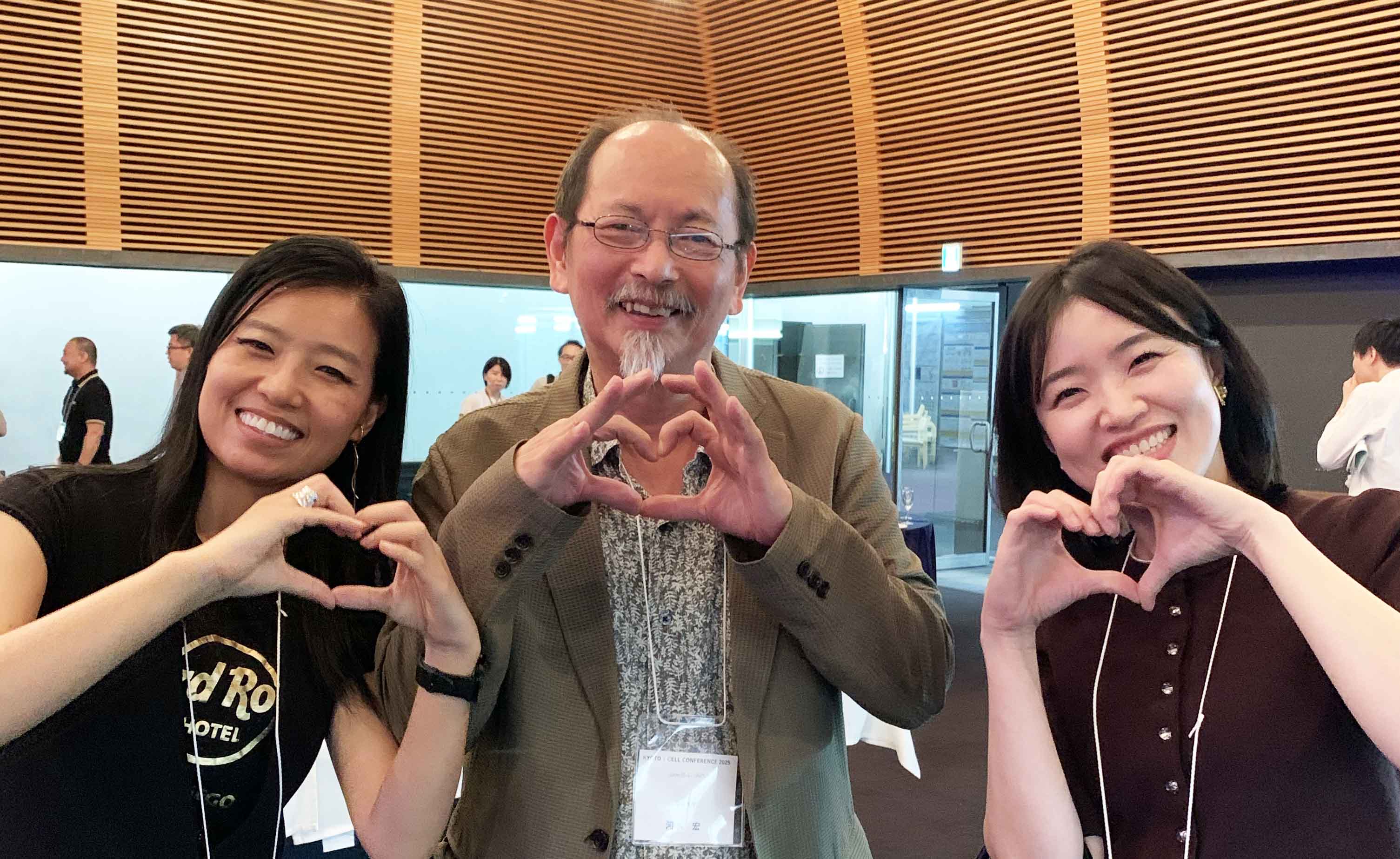 |
今回、河本関係者ということで、李聖林先生(写真向かって左、ASHBi教授)が参加された。李先生は数理生物学者(2024年10月1日の記事参照)。向かって右は皮膚科椛島研の赤木有沙先生(特定病院助教)。 |
 |
恒例になった百万遍の「くれしま」での二次会。今回も50人以上が参加。一次会の食事量が物足りなかったので、二次会はありがたい。 |
 |
テーブル1。 |
 |
テーブル2。 |
 |
テーブル3。 |
 |
テーブル4。 |
 |
テーブル5。 |
 |
<テーブル6。/td> |
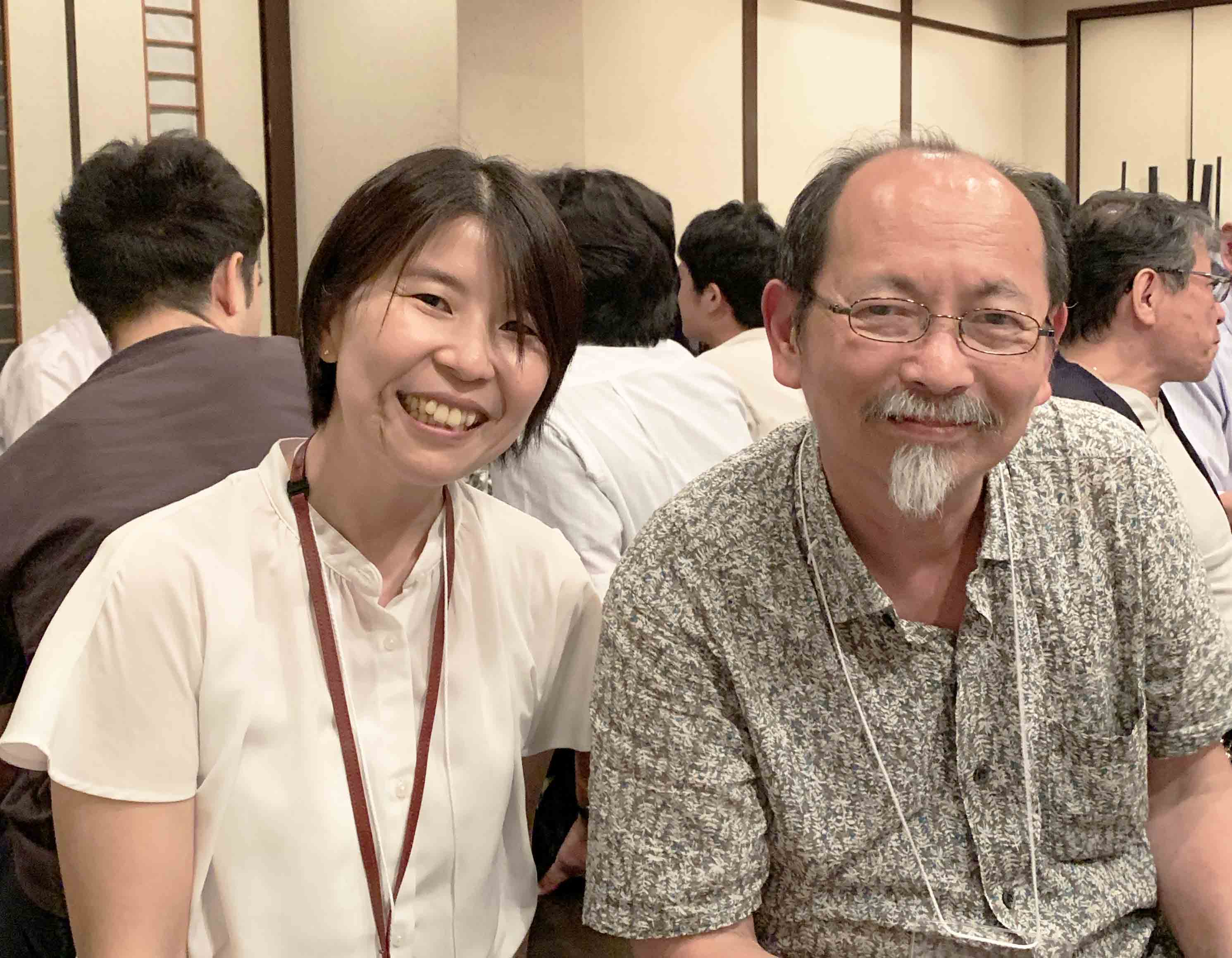 |
山崎加奈先生(縣研)と。今回はスタッフとしてよく働かれた。 |
 |
アルコールのまわりが良さそうな人達。向かって左端から久保允人先生(京大KIC)、山下克久先生(愛媛大)、茂呂和世先生(大阪大)。 |
 |
二次会終了後、有志で近くのカラオケに。いつものように、小安先生も来られていた。写真は午前1時頃、最後までsurviveした人達。昨年と似た顔ぶれだ。 |
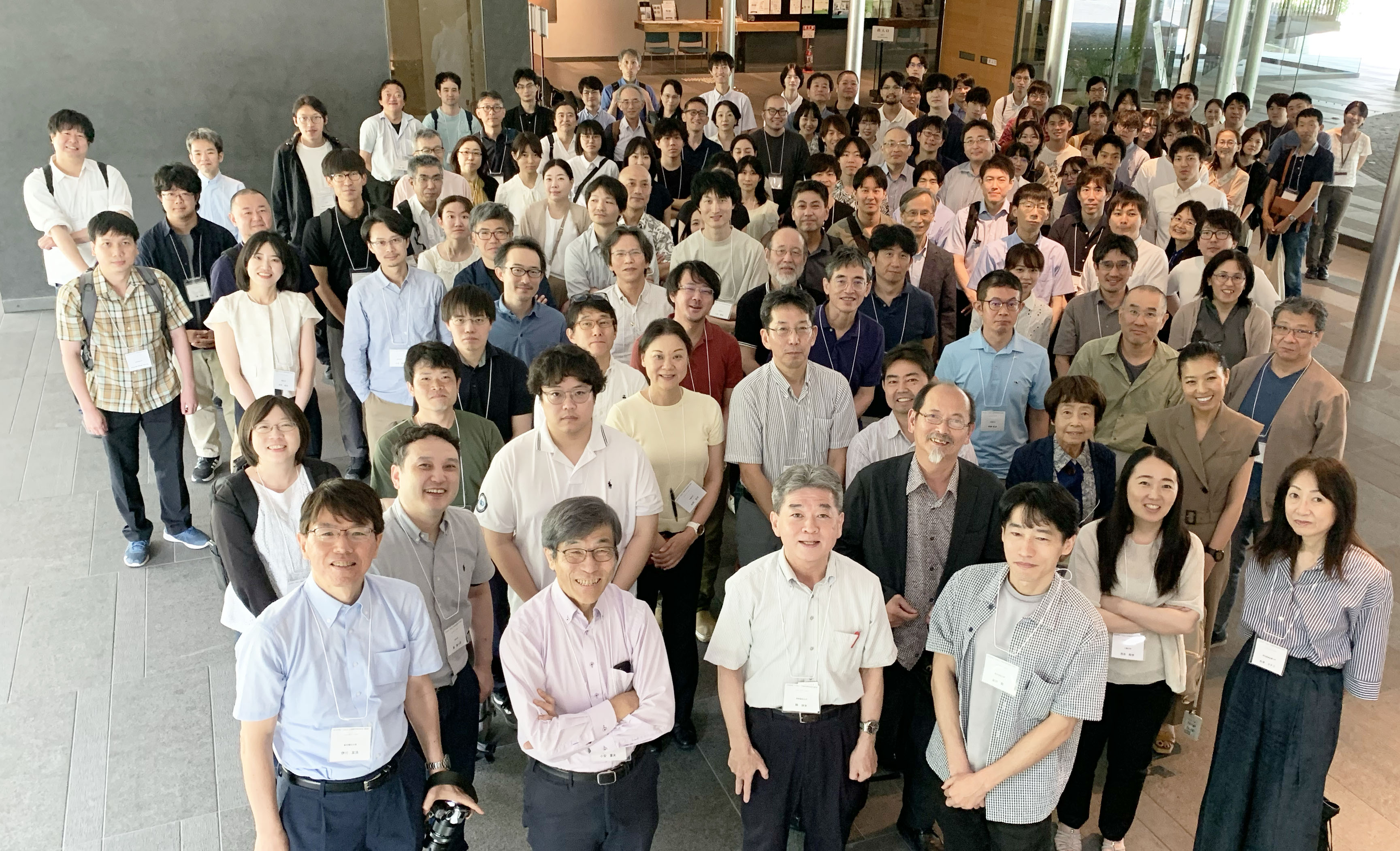 |
二日目のお昼休み前に、全員で集合写真。 |
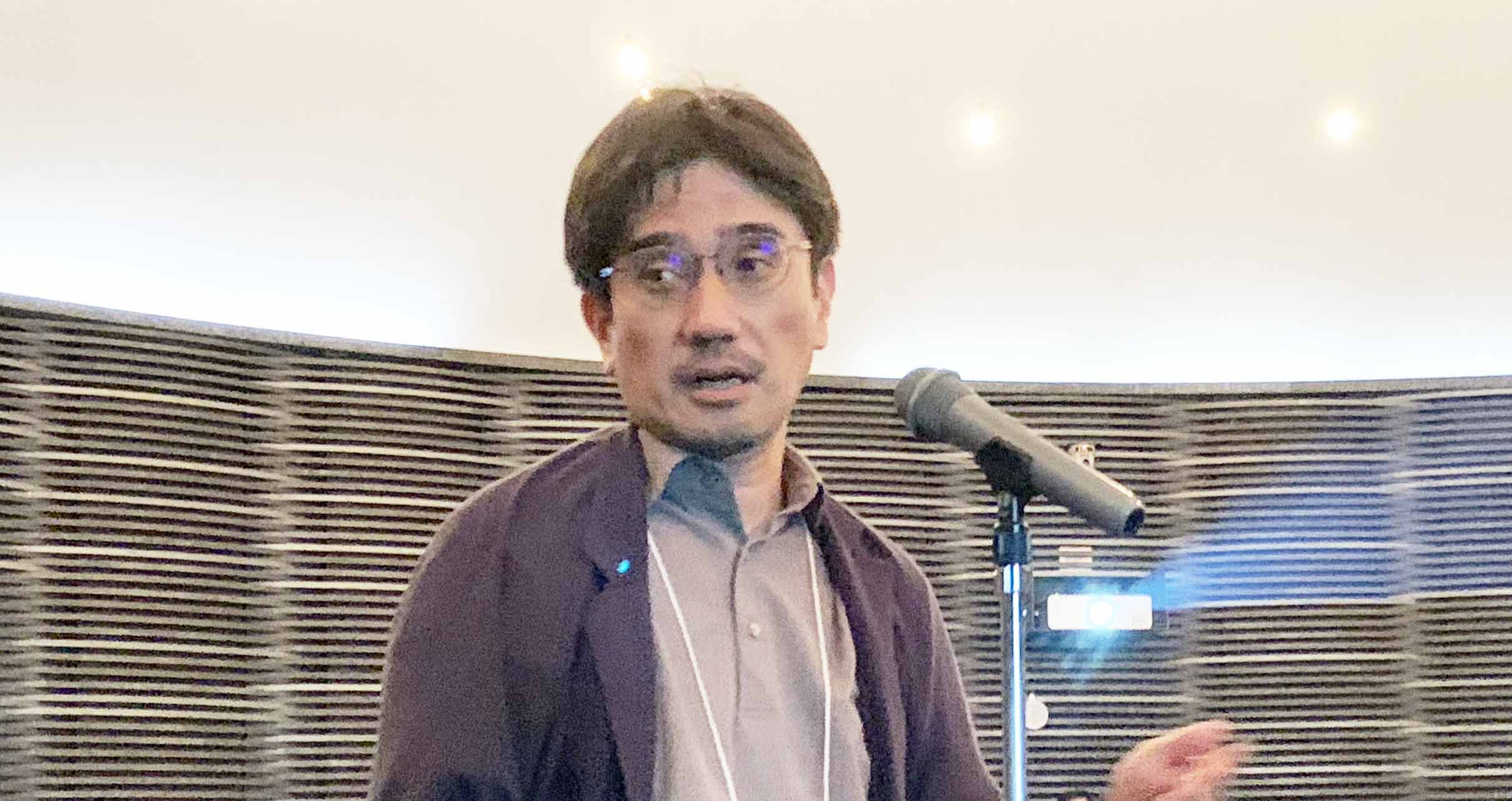 |
昼食後に開催された運営委員会で、次期KTCC代表を堀昌平先生(東大)が務められることが承認され、挨拶をされた。来年の国際KTCCまでは谷内先生が代表を務められ、国際KTCC終了後、堀先生に引き継がれる。 |
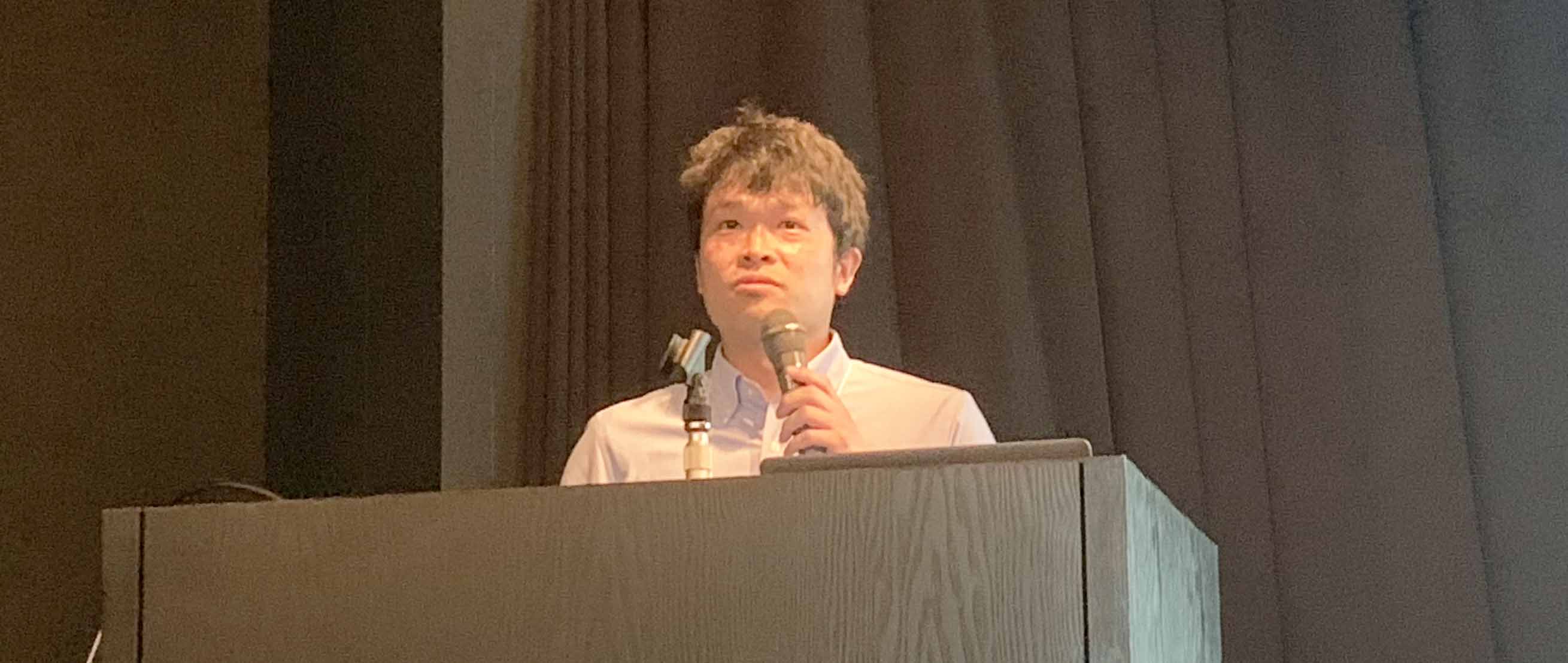 |
午後の最後のセッションで、板原多勇君(特定研究員)が超汎用性技術について発表。HLAをKOすると、移植組織はT細胞に拒絶されることは無くなるが、代わりにNK細胞が攻撃するようになる。そのNK細胞による攻撃を回避するための技術。 |
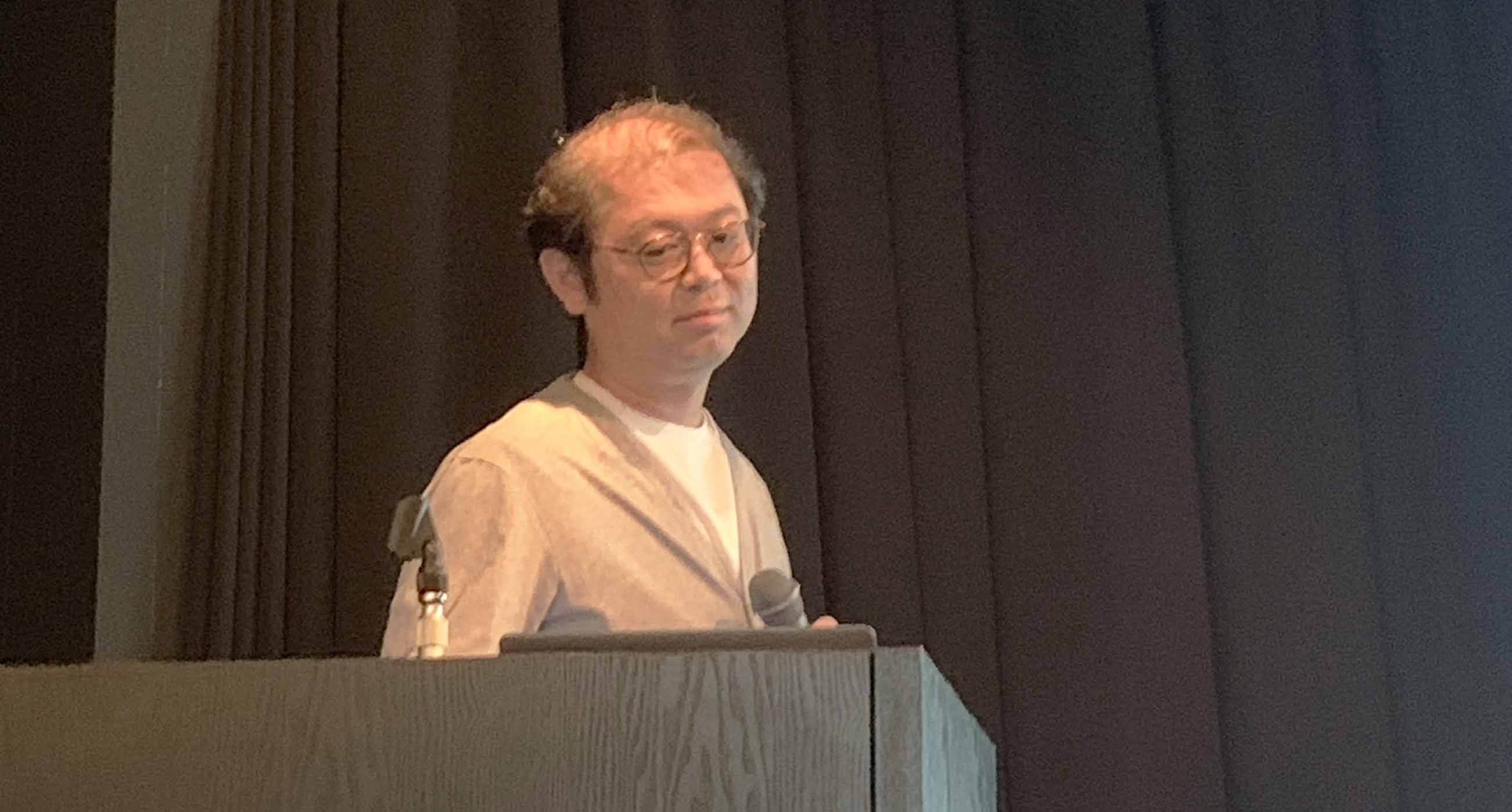 |
午後の最後のセッションで、河本研からもう一人、上堀淳二先生(特定助教)が、新型コロナ治療用T細胞製剤の開発について現状を紹介。Sタンパク特異的なTCRを使うと変異株では効果が失われるのではという質問が出たが、T細胞の標的エピトープには変異がほとんど起こらないと応答した。 |
2025年6月15日(日)
府立植物園の温室で催されているイベント「ライトサイクル キョウト」に行ってきた
 |
京都府立植物園の温室では表記のイベントが開催されている。昨年秋から冬にかけて開催されたイベントの評判が良かったので、万博に絡めるという意味もあって、再度開催された、ということらしい。2025年5月24日に再開となり、2026年3月31日までやっているらしい。営業時間 19:30~21:30で、最終入場 20:30とのこと。大人は前売り2300円、当日2500円。家に一枚だけ招待券が配られていたので、この日はそれを使って観覧。 ライトサイクル キョウトHP: |
 |
熱帯雨林を再現したジャングル室では、霧が漂う中に放射状に拡がる光線が揺らぎ、中々幻想的で、とても心地よい。チームラボ的な、没入感のある演出であるが、元々「異形」の植物が繁る熱帯雨林という状況を利用しているので、非日常感が湧きやすい。上手く利用しているとも言えるが、植物園での植物の観せ方としては、やや邪道だとも言えそうだ。 |
 |
池の周辺。霧が水面を這う。 |
 |
密林を奥に進むと神々しい光が…という感じ。「地獄の黙示録」に出てきそうだ。 |
 |
有用植物の部屋。虹色の光がかっこいい。 |
 |
砂漠・サバンナ室。サボテンにプロジェクションマッピンが映え、軽快なリズムと連動するように、目まぐるしく変化する。サボテンの形を上手く利用していて、見応えがある。 |
 |
ラン・アナナス室では、激しく上下する光の柱と、情動的な音楽が相まって、迫力ある演出。ただ、本来はランの花の色や形を観るだけで素晴らしいエリアなので、勿体無いようにも思われた。 私は植物が好きなので、本来の植物園の楽しみ方からはかなり外れているという点が気にはなるが、ほろ酔い状態で訪れた事もあってか、形、光、音を十分楽しめた。植物自体にそれほど思い入れのない人は、すごく楽しめると思う。総じて言えば、「とても良い。行くべき。」と言えるであろう。 |
2025年6月15日(日)
弟宅を訪問、食虫植物を鑑賞
 |
少し前の「あしかがフラワーパーク」の記事(2025年5月12日の記事参照)に食虫植物についてちょっと書いたが、私は子供の頃から食虫植物が好きで、理研のチームリーダー時代はリーダー室でかなり頑張って育てていた(河本宏の部屋「食虫植物のページ」参照)。今は家には少しあるが、教授室では育ててない。代わりに、時々自生地を見にいったりしている(2018年6月3日の記事参照)。一方で弟は、自分の家の2階のバルコニーで、かなり精力的に栽培を続けている。この日、久々に見せてもらった。サラセニア(北米原産)の花が盛りだった。食虫植物は葉っぱを観るので、花は割とどうでも良いが、元気である指標にはなる。 |
 |
ハエトリソウ(北米原産)もたくさん花を咲かせている。 |
 |
ビブリス・ギガンテアが咲いていた。オーストラリア原産。「花は割とどうでも良い」と前述したが、ビブリスは別だ。素晴らしい。小ぶりなビブリス・リニフロラは私もかつてよく育てていたが、ギガンテアは珍しい。栽培も難しいとされる。いいものが観れた。 |
 |
ドロソフィルム・ルシタニカムも上手く育っている。スペイン・ポルトガル・モロッコあたり原産。猛々しい草姿だ。 |
 |
ムジナモ。ハエトリソウに近縁で、水中で、ハエトリソウのように対になった葉を拡げ、素早く閉じることでプランクトンなどを捕食する。世界中に分布するが、残念な事に日本では絶滅したとされている。下に浮いているのはホテイアオイ。 |
2025年6月12日(木)
国際数理生物学会の懇親会(7月10日)での演奏に向けて練習開始
 |
表記の学会(7月7日-11日、於京都テルサ)の懇親会(7月10日、於京都リーガロイヤルホテル)でネガティブセレクションが何曲か演奏することになり、この日の夜、スタジオRagで練習を開始した。今回は、大久保さんがベース、幸谷愛先生(大阪大)(写真向かって右端)がキーボード、北村先生がドラム。今回は、NSのオリジナル曲1曲と、ゲストボーカルを学会から招いて3曲を演奏する予定。練習後、「くうかい」でほっこり。 国際数理生物学会HP: |
2025年6月11日(水)
東洋紡バイオテクノロジー研究財団の評議員会に出席
 |
表記の会が船場にある「綿業会館」で開催された。私は理事として出席。 |
 |
館内。歴史を感じさせる重厚なしつらえだ。綿業会館は1931年竣工で、重要文化財や、近代化産業遺産に指定されているとのこと。 |
 |
評議員会終了後の懇親会にて。向かって左から中山敬一先生(東京科学大)、新蔵礼子先生(東大)、私。帰り道では新蔵先生、篠原隆司先生(後列左から3人目)と京都までご一緒し、体外受精のリスクの話(J Clin Invest 133: e170140, 2023)など、いろいろな話が聴けた。 |
2025年6月9日(月)
64歳になった
 |
ラボの皆が誕生を祝ってくれた。写真は朝のmeetingの部屋。花束と、携帯のカバー、携帯充電用のバッテリーを頂いた。カバーはボロボロで替え時だったし、バッテリーは万博行きに必須なので、ありがたい。自分に向ける方のカメラで撮ったので、解像度がちょっと荒いのが残念。 |
 |
花束。初夏らしい、いい組み合わせだ。ヒマワリ、デルフィニウム(青い花)、アリストロメリア。 |
2025年6月4日(水)ー6日(金)
サンディエゴで開催されたワクチン拠点関連のシンポジウムに参加
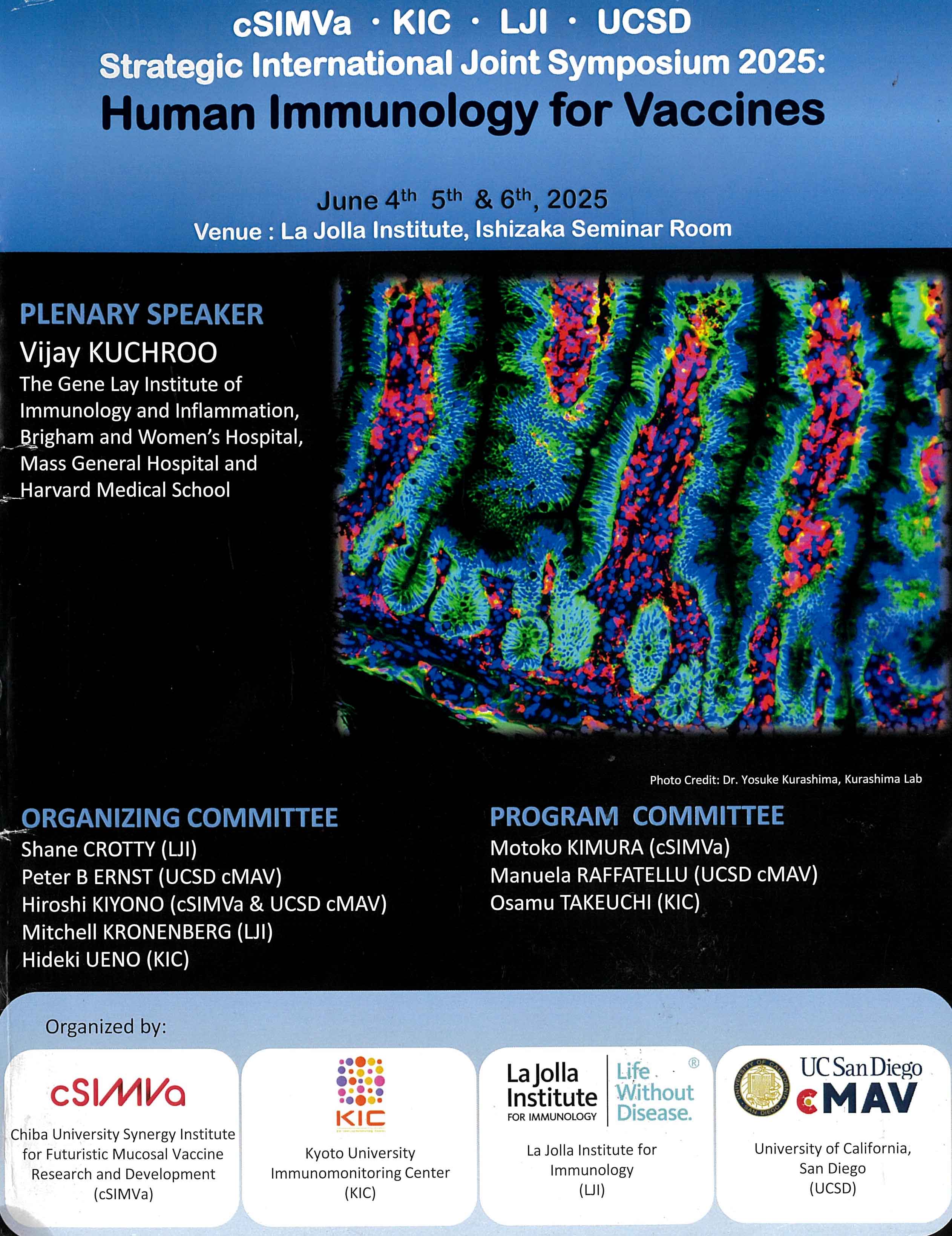 |
SCARDA(ワクチン開発のための先進的研究開発戦略センター)の中の事業として、千葉大学のシナジー拠点(清野宏代表、cSIMVa)と京大のサポート機関(上野英樹代表、KIC)、ラホヤ研究所(LJI)、カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)などの協同で、シンポジウムが開催されることになった。 |
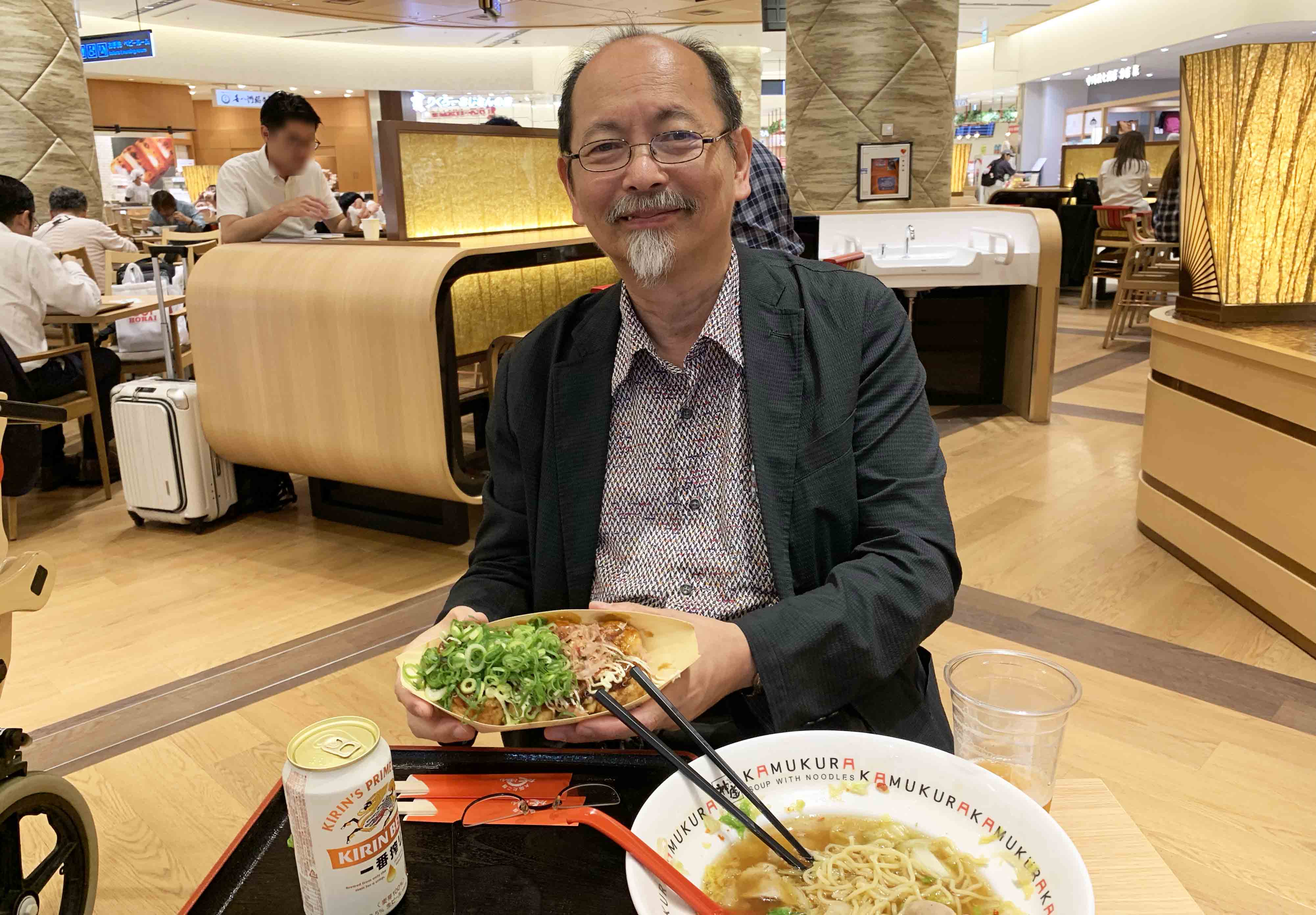 |
私と小林さんは、KIC関係者ということで、参加する事になった。伊丹空港から成田空港へ行き、成田空港からサンディエゴ国際空港へ。伊丹空港で、神座(かむくら)のラーメンとたこ焼きで昼食。 |
 |
サンディエゴ国際空港からホテルへは、京大からの参加者の一人である竹内理先生がウーバーを呼んでくれた。高速道路は道幅が広く、片側5車線。制限速度は65マイル/時(104km/時)であるらしいが、もう少し速く走っていた。サンディエゴでは晴れの日が多いらしいが、今回の滞在中は、残念ながらずっと曇天だった。 |
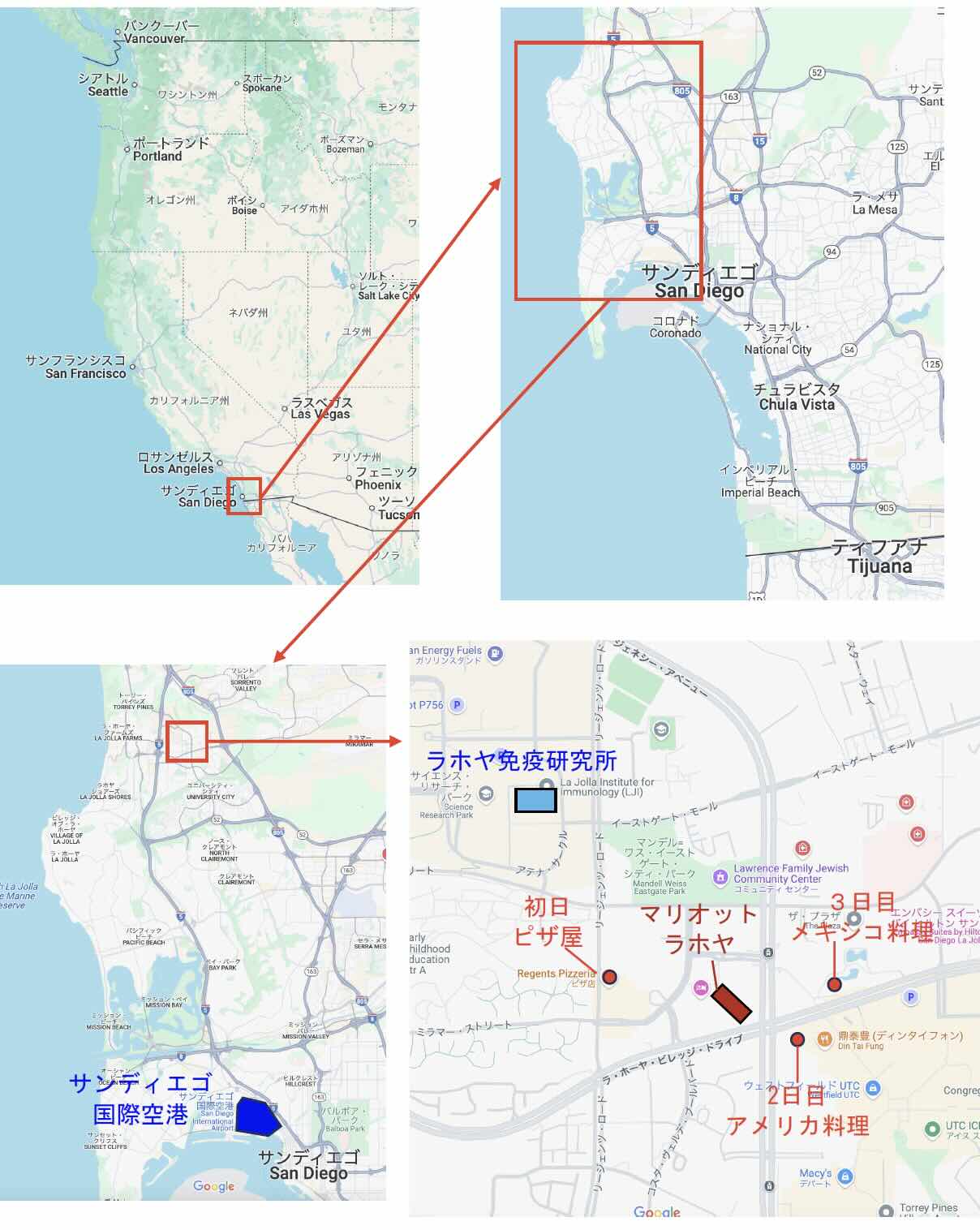 |
今回のシンポジウムの会場であるラホヤ研究所とホテルの位置関係を示す図。ホテルから会場まで徒歩で10分程度。期間中に外食した店の位置も示しておいた。 |
 |
初日のプログラムが朝からなので、参加者はほとんどが前日入り。お昼過ぎにホテルに着き、有志で近くのピザ屋で昼食。写真のサイズのピザがチップ込みで8ドルくらい(1200円)、ビールは1パイント(約500ml)で10ドルくらい(1500円)。感覚としては、日本の2倍くらいか。 |
 |
宿泊したホテル、サンディエゴ・マリオット・ラホヤ。 |
 |
部屋。 |
 |
部屋の窓からの景色。 |
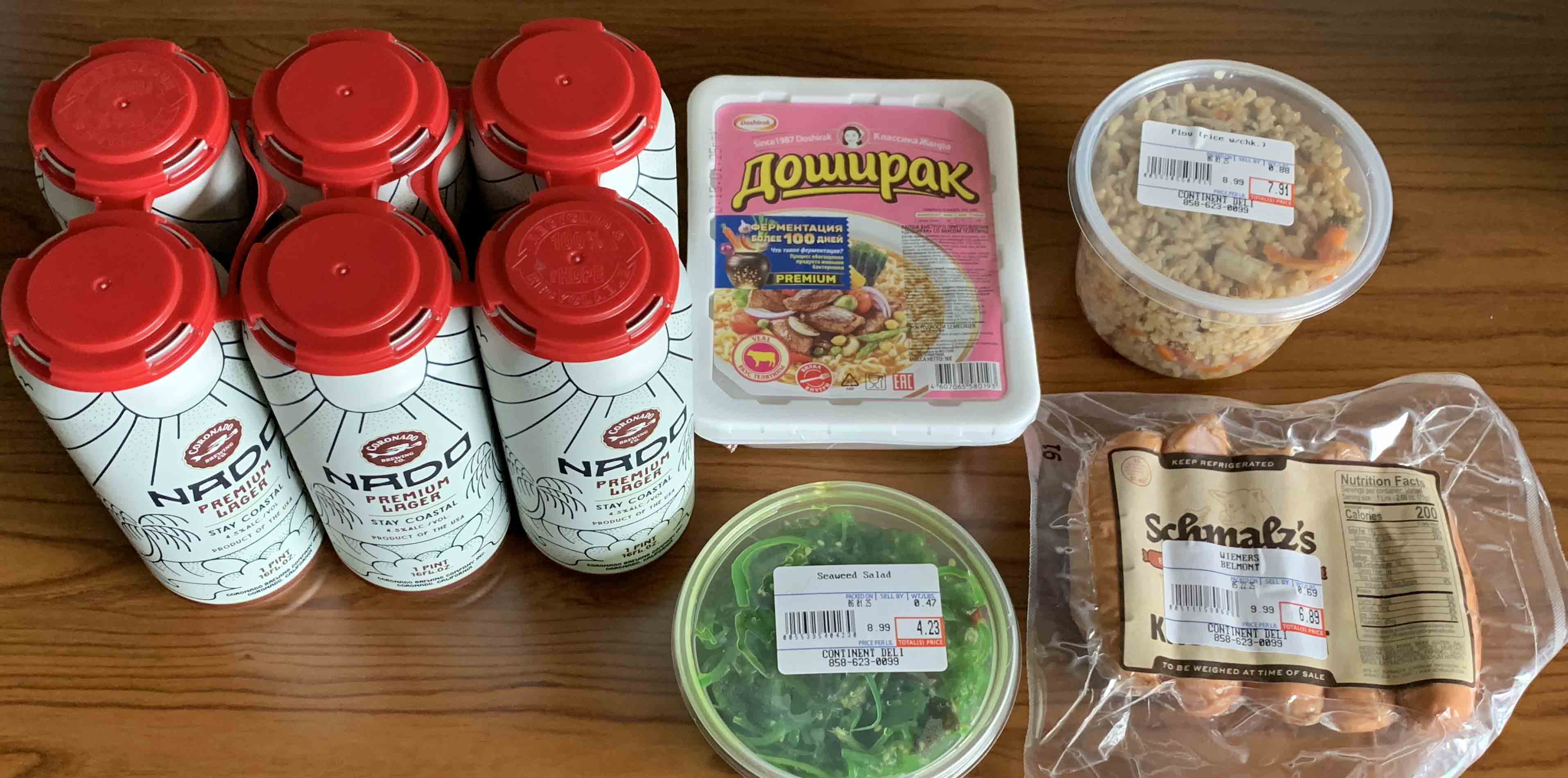 |
この日は、チェックインした後はすぐに寝てしまいそうだったので、夕食はホテルの近くの小さい食料品店でチェックイン前に購入した。チキンピラフ(約8ドル;1200円)、ソーセージ5本(約7ドル:1000円)など。 |
 |
翌朝、会場に向かう途中に路傍で見た猛々しい植物。調べてみたら「エキウム」という名の草だと思われる。この辺りの原産という訳ではなさそうだった。 |
 |
会場があるラホヤ免疫研究所。 |
 |
受付。 |
 |
会場。 |
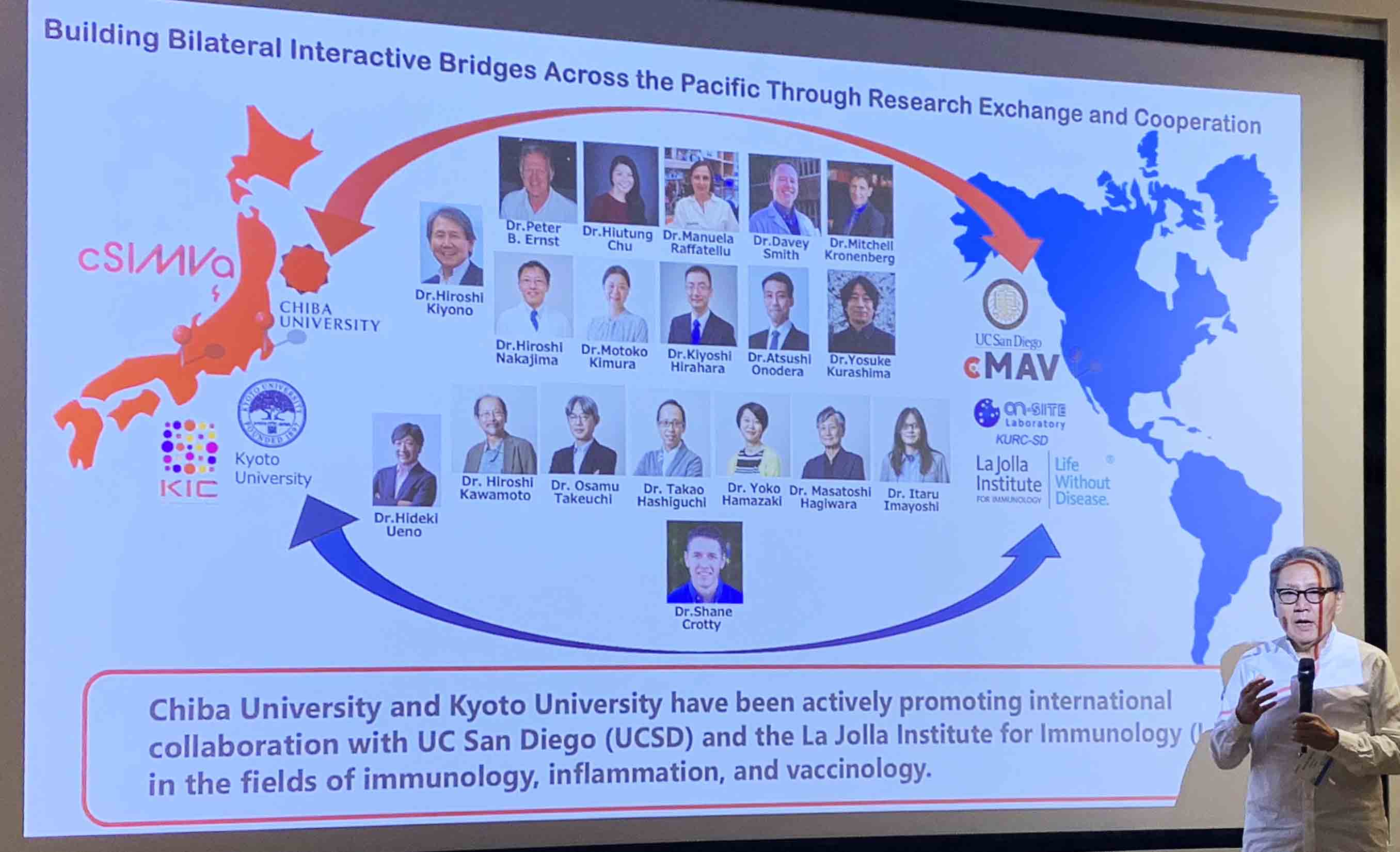 |
清野先生が今回のシンポジウムの主旨を説明。千葉大学は以前から清野先生を介してラホヤ研究所やUCSDとcMAVという組織体で粘膜免疫研究で連携しており、一方で京大は上野先生を代表としてUCSDにオンサイトラボを運営している。SCARDA関連としては、清野先生はシナジー拠点cSIMVaを、上野先生はサポート機関KICを、それぞれ代表として統括している。そこで、清野先生と上野先生がタッグを組んで、SCARDAのワクチン開発事業の展開を、cMAVや京大オンサイトラボと組み合わせて、ラホヤ研とUCSDも含めた協同体制で進めて行こうという構想のようであった。 |
 |
キーノートスピーカーはVijay Kuchroo(Harvard Medical School)で、この日は「組織が病原体に対して起こす最初の反応が、獲得免疫の反応の型を決める」というような話だった。 |
 |
研究所の中庭(Patio)で、初日の夕食。 |
 |
トルティーヤを軽く炙ってくれて、それにチキン、ポーク、ビーフのうちのいずれかを乗せて、二つ折りにして食べる。美味しかった。 |
 |
向かって右端はObonyoというUCSDの助教で、トランプ政権になってから、研究環境が悪化したことに怒っておられた。向かって左から橋口隆生先生(医生研)、逸見拓矢さん(橋口研院生)、中村和史さん(竹内研研究生)。逸見さんには、昨年浜松で開催されたサポート機関合同シンポジウムでは、大変お世話になった。台風のせいで新幹線が停止して最悪2日間移動できなくなりそうになったところを、とっさにレンタカーを手配してくれて、おかげで無事に脱出できた(2024年8月29日の記事参照)。 |
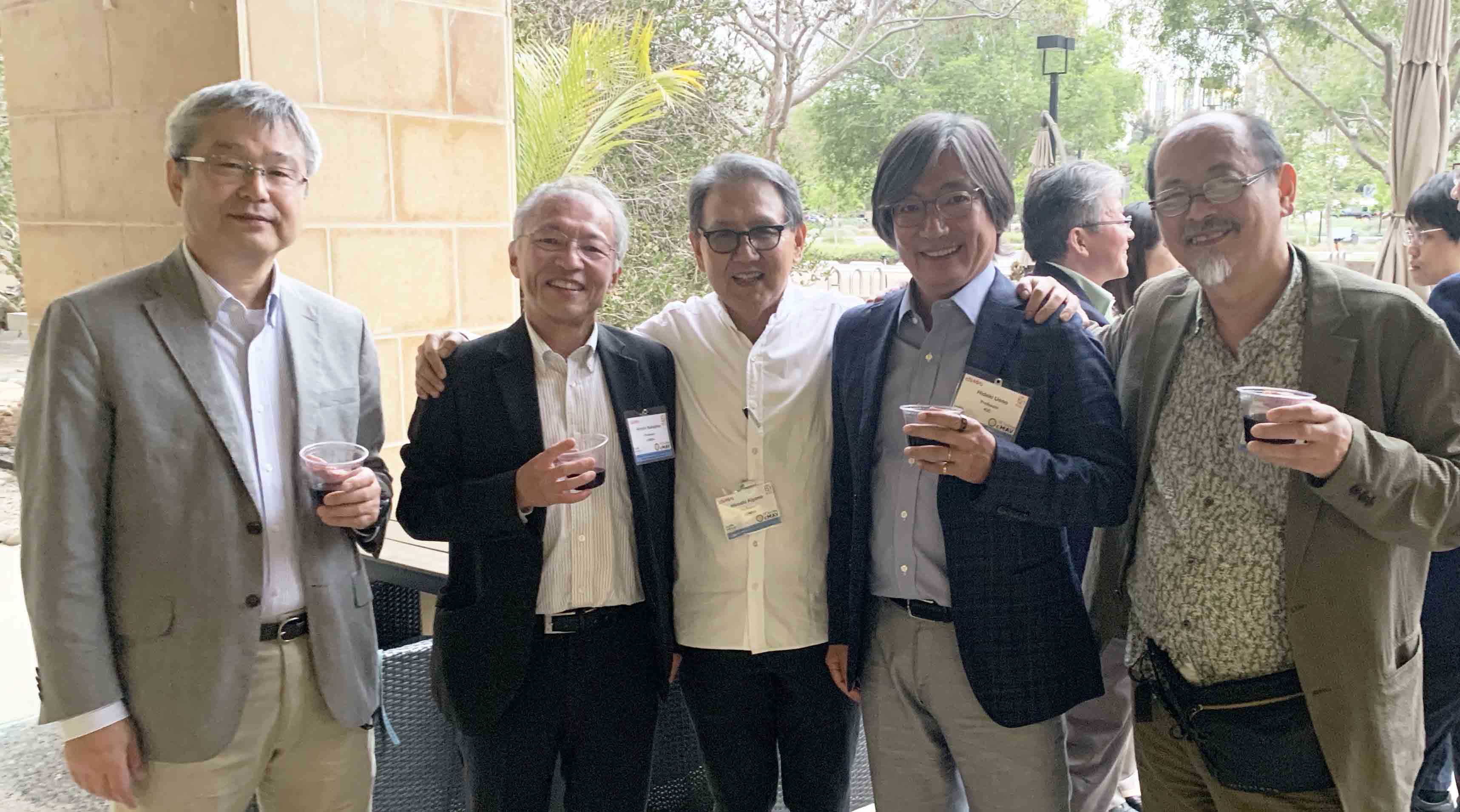 |
向かって左から三宅健介先生(千葉大)、中島裕史先生(千葉大)、清野宏先生(千葉大)、上野英樹先生(京大)、私。清野先生と上野先生のリーダーシップには感服した。 |
 |
2日目もシンポジウムは続き、その合間、昼食時と夕刻に計2時間ほど、ポスターセッション。 |
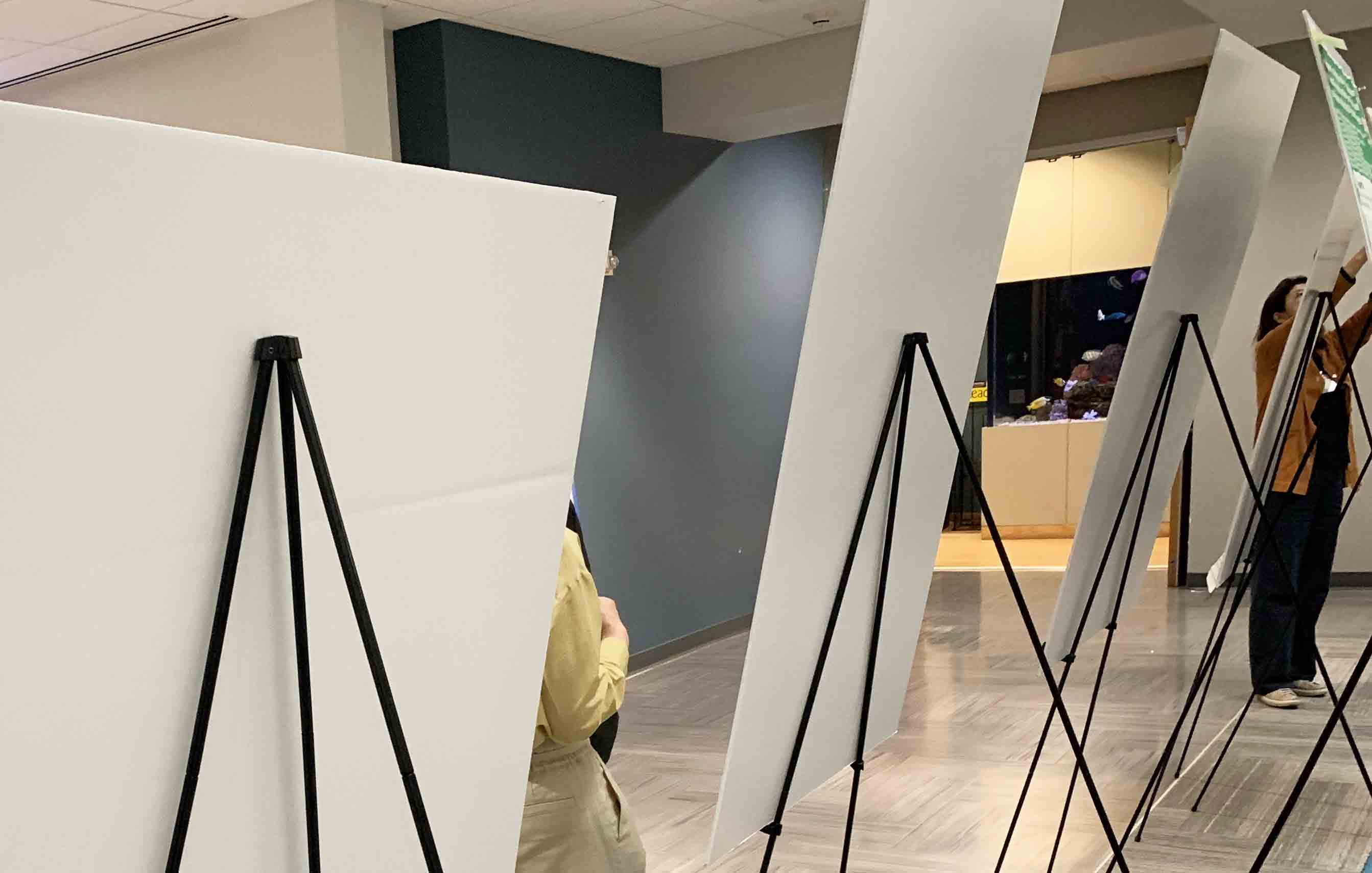 |
こういう簡便そうな台にスチロールパネルを置いてA0版ポスターを貼ってもらうというのは、いい方法だ。たいそうなポスター用ボードを設営することなく、安くすますことができそうだ。 |
 |
この日の夕食は、KIC関係者で行こうという事になった。日本の大通りは基本的には路上駐車禁止であるが、こちらは横断歩道の近く以外は、駐車可能なところが多いとのことだった。 |
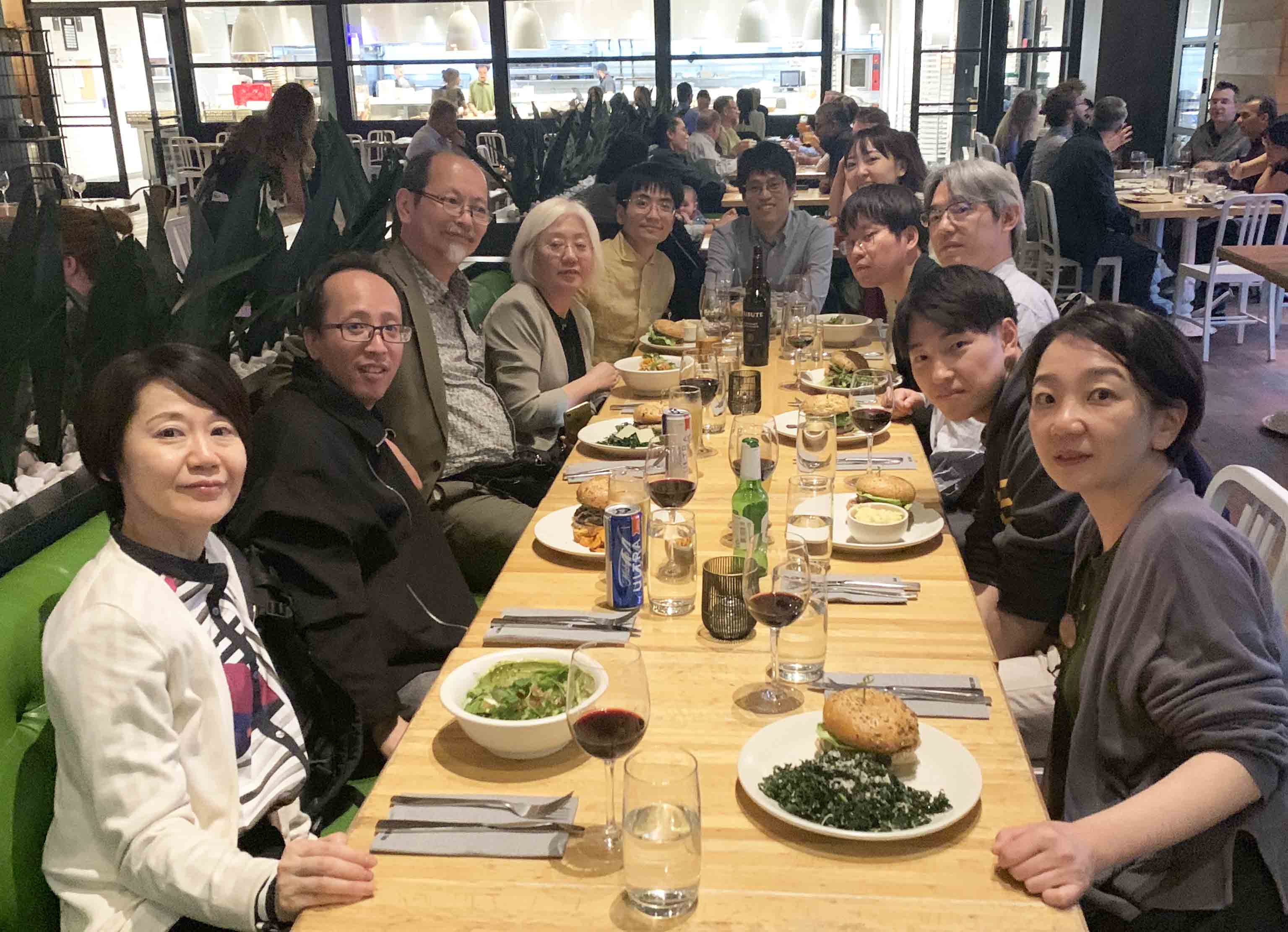 |
アメリカの通常の料理が中心の店で、ハンバーガーとか、丼ものとかがあった。上野先生は文科省関係のzoom会合があるとかで、不参加。 |
 |
私が食したのは七面鳥のひき肉を使ったハンバーガーとケールのサラダ。約20ドル(3000円)。美味しかった。 |
 |
3日目の午前中は、4つの分科会に分かれて、ブレインストーミング。テーマは、「粘膜ワクチン」「AIによるワクチン開発」「腸内細菌叢とワクチン」「ライフステージとワクチン」。私は「ライフステージとワクチン」に参加。上野先生がfacilitatorをされていた。浜崎研の院生の角南理己さん(写真向かって右端)がよく発言していた。えらい。 |
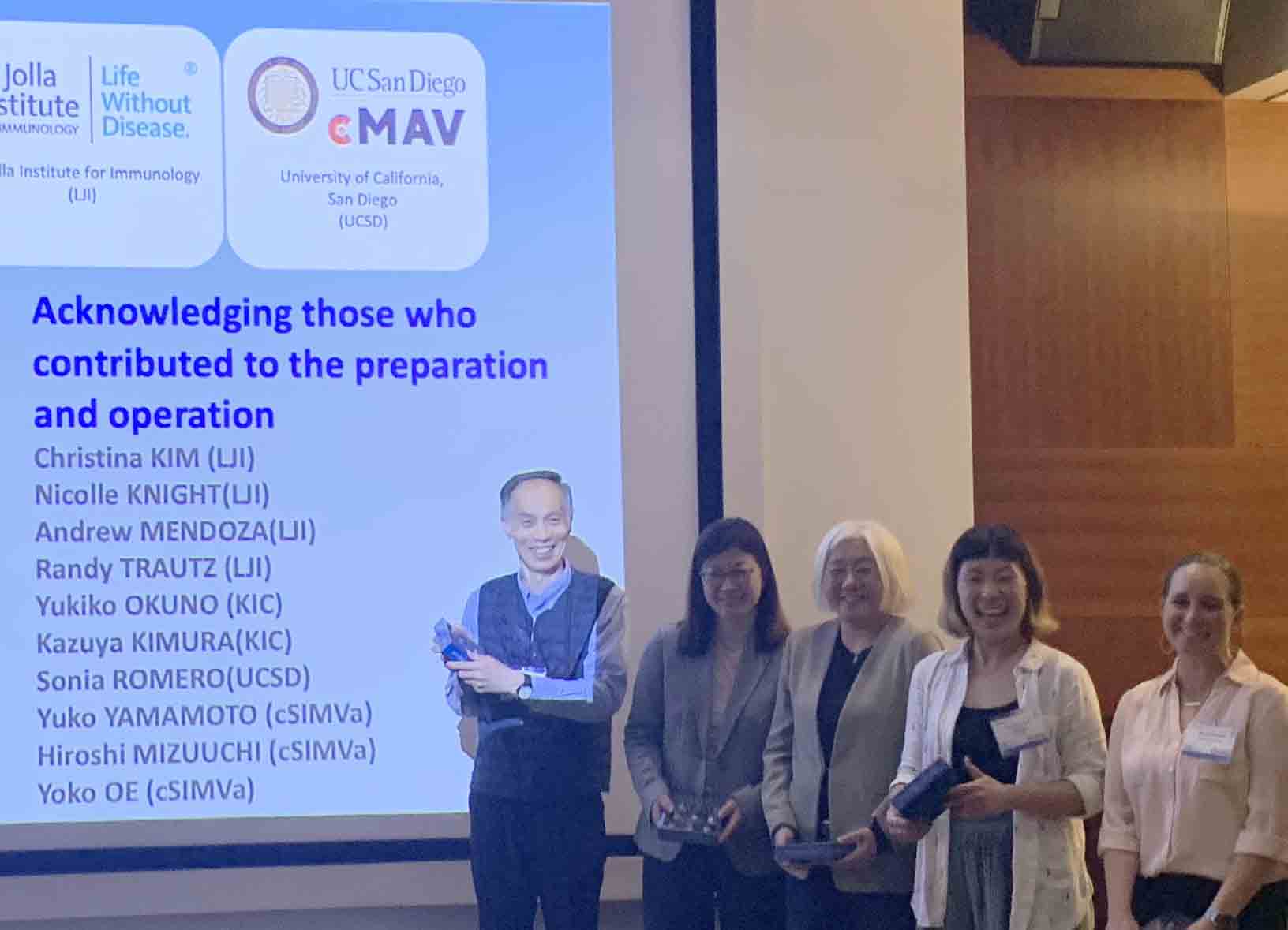 |
午前中のプログラムの最後に、シンポジウムの運営を担当して下さったスタッフに感謝が表された。 |
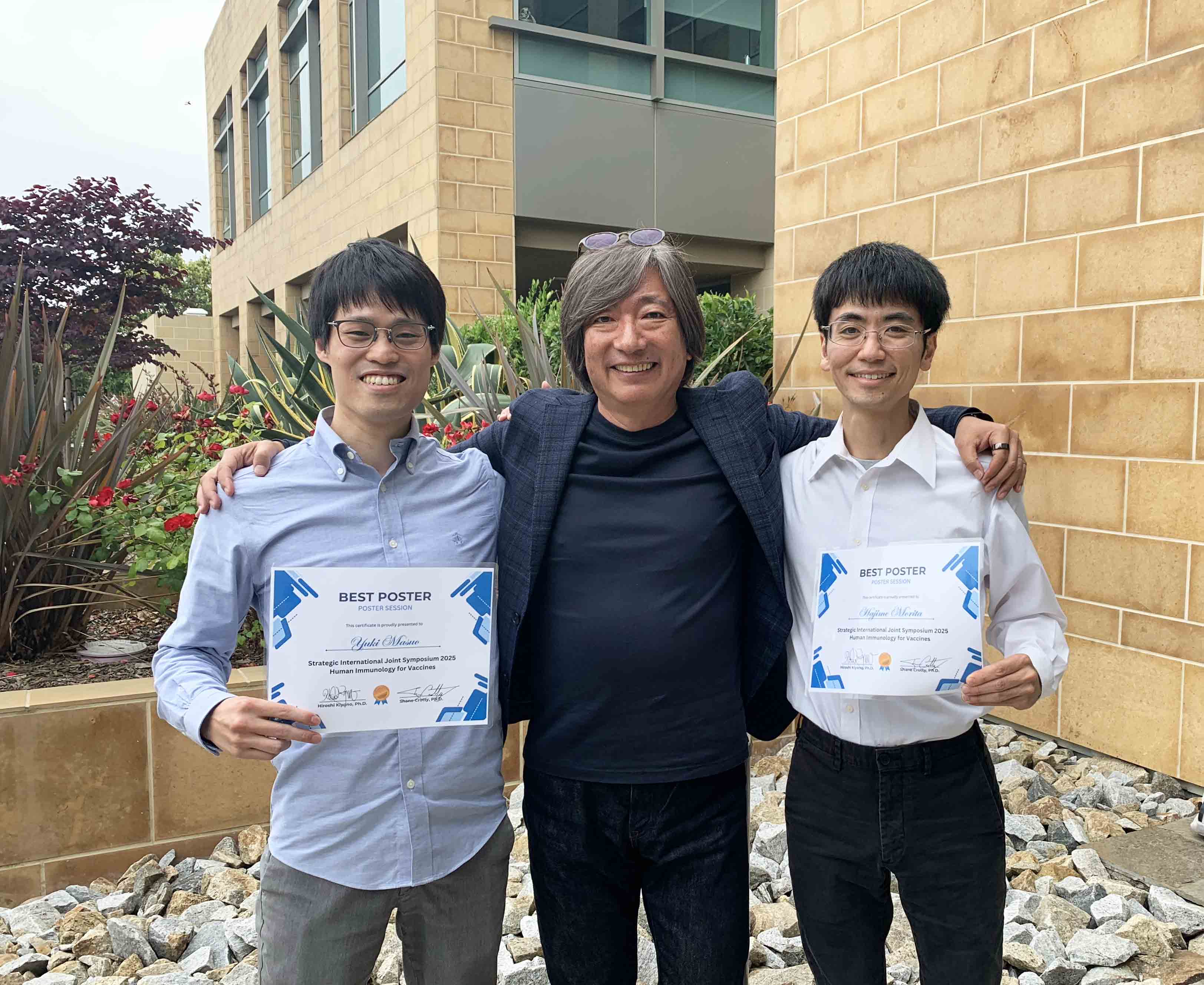 |
今回、ポスター発表は27演題あり、4人がポスター賞を受賞。そのうちの2人が、上野研の森田元さん(院生)(写真向かって右)と増尾優輝さん(院生)。確かに、二人ともとてもいい発表だった。増尾さんは医学部3回生の頃に河本研に出入りしていたことがある(2014年8月29日の記事参照、2014年11月26日の記事参照)。 |
 |
ハチドリを見かけた。蜜を吸う時にホバリングで止まった状態になるとはいえ、その時間は短く、写真を撮るのは難しかった。 |
 |
昼食後、分科会があり、その後閉会。閉会後、近辺を見てまわった。左は参考図。 |
 |
まずは海岸を見に、トーリー・パインズ・グライダースポットというところに行った。台地の先は100mくらい下の砂浜までが崖になっている。かっこいい地形だ。向かって左から大瀧夏子先生(千葉大特任研究員、元茂呂研)、上野先生、増尾さん、森田さん。 |
 |
北側の海岸線。いわゆる海岸段丘という地形ではないかと思われる。 |
 |
崖の上は、なだらかな大地になっている。この日はあまり見かけなかったが、普段は沢山のパラグライダーで賑わうそうだ。崖の下に降りていくのではなく、海から吹き上がってくる風に乗って上がって、台地の上で飛び回れるようだ。 |
 |
次にLa Jolla Cove(ラホヤコーブ)という場所にやってきた。コーブ(Cove)は「入江」という意味らしい。野生のアシカの群れが見られる事で有名。 |
 |
確かに、沢山いる。驚いたことに、すぐ近くまで寄ることができる。 |
 |
アップ。動物園のような臭いと、オスのアシカの「オウ、オウ、オウ」という鳴き声で、臨場感が溢れていた。 動画:オスのアシカが別なオスのアシカを攻撃(36秒) |
 |
驚いた事に、すぐ近くでヒトが泳いでいた。おおらかだ。 |
 |
海岸なのにリスがいた。 |
 |
大切にされていて人を怖れないという事なのかもしれないが、人慣れしすぎて野生を失っているとも思われた。 動画:かわいいリスがカメラを意識?(15秒) |
 |
少し離れたところの別の群れがいた。 |
 |
こちらの群れはかなり海から離れたところまで上がってきている。 |
 |
お父さんカモメが、自分たちの巣とお母さんカモメを守ろうとアシカを攻撃している。立派なものだと思えたが、他に海岸沿いにいくらでも場所はあると思われるのに、何でこんなところに巣を作るんだろうとも思った。 動画:巣を守るためにアシカに立ち向かうお父さんカモメ(12秒) |
 |
大自然を満喫した後、空港の近くの、「Stone」という有名ブランドのビールの醸造所へ。 |
 |
上野先生によると、ここはIPA(indian pale ale)という味も色も濃いタイプのビールが有名らしい。アルコール濃度も9%近かった。写真のグラスは10オンス(約300cc)。5オンスあるいは15オンスという選択肢もあった。とても美味しかった。 |
 |
ビールのおつまみとしいて注文したナチョスと、チリソースが絡んだチキン。 |
 |
夕食は、濱崎先生グループと合流して、ホテルの近くのキシコ料理店へ。 |
 |
マルガリータで乾杯。 |
 |
トルティーヤにチーズやトマトを乗せて、巻いて食べる。美味しかった。 |
 |
タコスと、豆のペーストと、ライス。タコスは美味しかった。 |
 |
往路の空港で、ゲート内で土産物を買った後、小腹が空いたのと、醤油味のものが食べたいという衝動に駆られて、カリフォルニアロールを買って食した。こんなもので1パック約12ドル(1800円)と高価だが、多くのレストランで一品20ドルというのが基本価格のように刷り込まれつつあったので、感覚が麻痺して「12ドルなら安い」と思ってしまった。醤油をかけて食べたら、それなりには美味しかった。 |
2025年5月30日(金)
たま麩
 |
この日、会社関係の用務で午後から日帰りの関東出張。その復路、品川で東北地方の物産展をやっていた。そこで写真のような巨大な麩を見かけたので、お土産に購入。ネットで調べたところ、特にどこの名物という訳でもなさそうで、あちこちで作られているようだ。この商品は愛知県岡崎市で作られたものだった。7個入りで900円くらいだった。 |
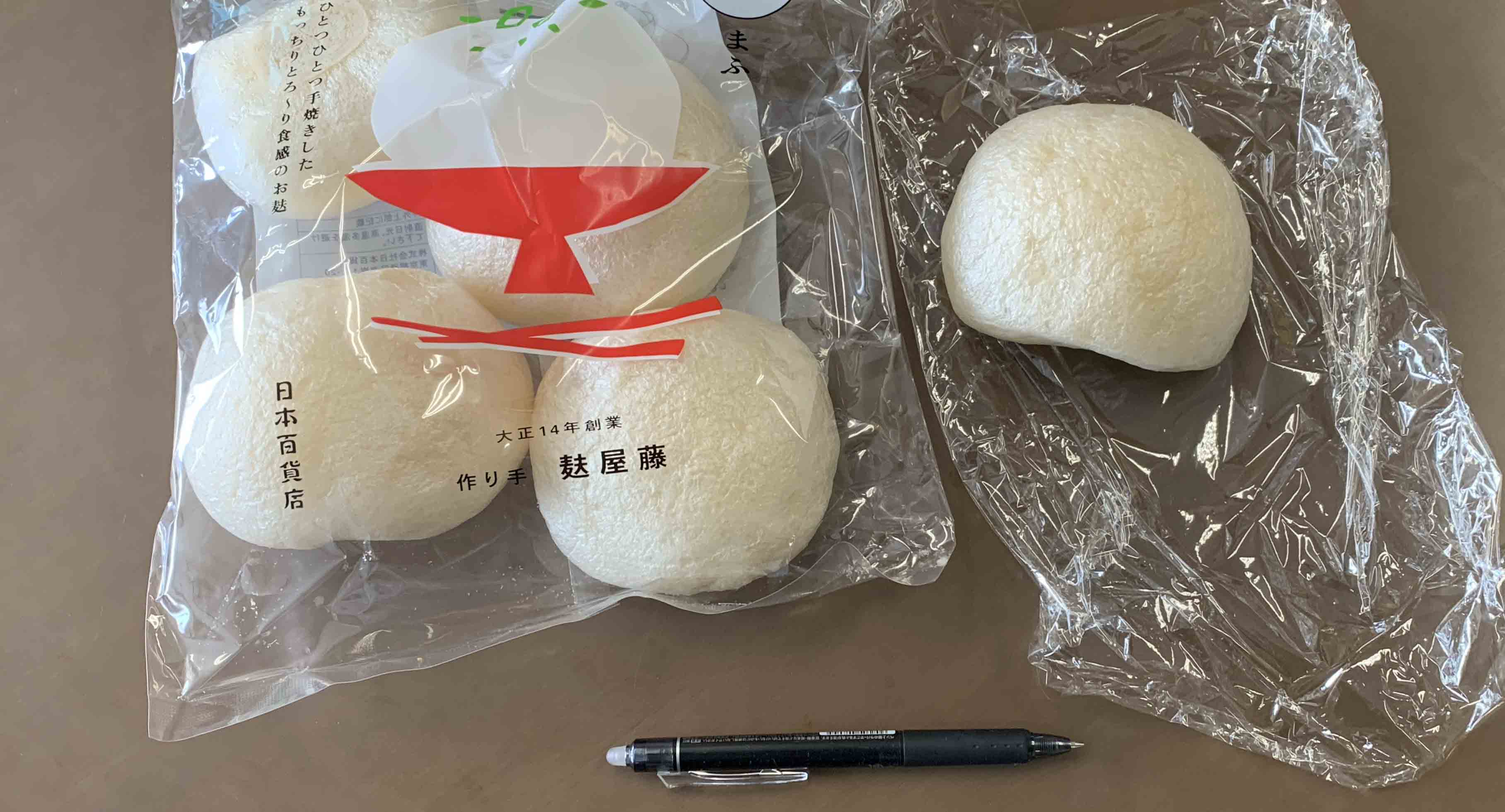 |
でかい。中空ではなく、中の方までスポンジ状になっているという感じ。 |
 |
スープが染み込みやすいように底にいくつか穴を開けて、上に置くだけで、1—2分でスープが染み渡り、いい感じになった。モチモチした食感で、とても美味しかった。 |
2025年5月28日(水)ー29日(木)
韓国出張
 |
会社関係の業務で、大学の方は2日間休暇をとってソウルに出張する事になった。11過ぎの関空発の便に乗るべく、バスで9時ごろに関空に着いてチェックインカウンターに向かった時、パスポートを教授室の机の中に忘れてきたことに気がついた。この日は15時ごろからソウル市内で会合がセッティングされており、血の気が引く思いがした。結局、この日は甥っ子の都合がたまたま良くて、私の母親と一緒にパスポートを運んでくれて、12時半くらいの便には乗ることができた。それにしても、今回は関係者に多大なる迷惑をかけ、自分のあまりのアホさ加減に自分でも呆れてしまった。 前日に韓国入りをしていた畑中さんと先方のスタッフによる迅速なリスケジュールによって、何とか全体としては予定していた行事はこなせたが、本当に申し訳ない思いでいっぱいだった。復路、空港で昼食。写真は私と梶川社長で、畑中さんが撮ってくれた。 |
 |
これで一人分。キンパ、おでん、スンデ、トッポギ。スンデは豚の血と春雨を材料にした腸詰料理であるが、血生臭い感じは全くなく、美味しかった。他には韓国式のラーメン、うどん、肉まん3個を、3人でシェアしながら、完食した。 |
2025年5月27日(火)
連携基盤懇親会
 |
連携基盤というのは、京大の附置研究所や研究センターで構成される機関で、附置研・センターシンポジウムを開催したり(2025年3月1日の記事参照)、「未踏科学ユニット」という形で機関間の共同研究を促進したり(2023年7月29日の記事参照)している。その懇親会が本部構内のラトゥールで開催された。 |
 |
この4月から基盤長を務めておられる中野伸一先生(生態研)による挨拶。 |
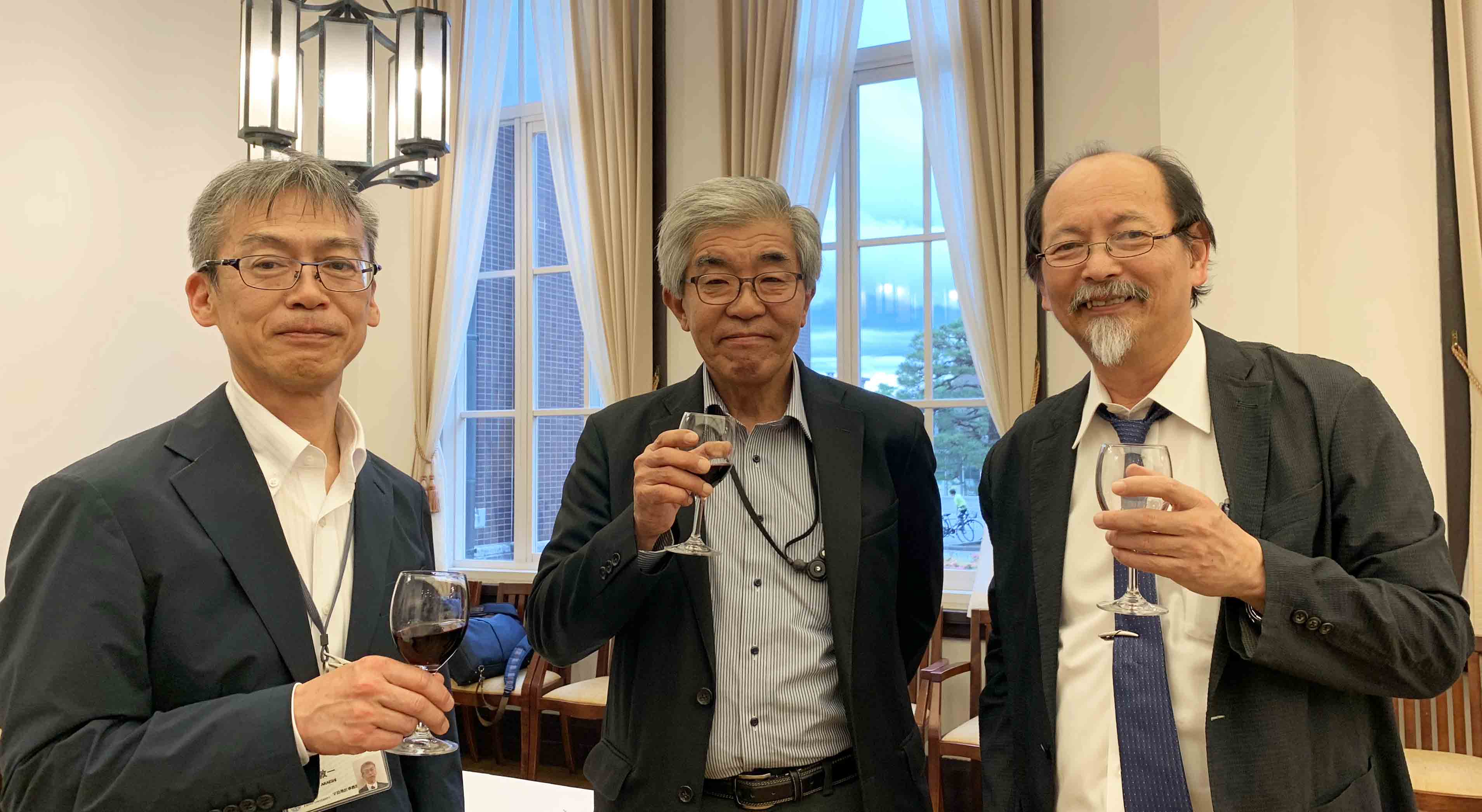 |
時任宣博先生(写真中央、現副学長、元化研所長、元連携基盤長)から、概算要求でうちが出した企画について、少し話がきけた。写真向かって左は、宇治地区の事務長。 |
2025年5月26日(月)
小野山さん来室
 |
小野山朋美さん(写真中央)はiPSアカデミアジャパン株式会社の社員で、ライセンス部で知的財産戦略を担当されている。今回来られたのは、iPS細胞の使用におけるライセンスの話ではなく、企業の広報戦略についての一般的な話であった。私が進めてきた医生研の裏医生研チャンネルの制作などに興味を持っていただけているようで、ありがたかった。同社のライセンス部の藤城修平さんも同席された。 |
2025年5月26日(月)
前川さん来室
 |
京大医学部4回生の前川万侑子さんがマイコースでこの秋、河本研に2ヶ月ほど来る事になった。前川さんは、洛北高校の出身とのことなので、高校でも私の後輩という事になる。なお、前川さんは中高一貫制の卒業生であるが、私の時は洛北高校は中高一貫という制度はなかったし、当時は京都では公立高校間の格差が無かく、洛北高校も全く進学校という感じではなかったので、厳密には先輩後輩とは言えないであろう。 |
2025年5月26日(月)
岩下先生が河本研に参加
 |
中坊周一郎先生(京大病院臨床免疫学特定助教、向かって右端)とは共同研究をする話が進んでいて(2025年2月20日の記事参照)、その研究を臨床免疫の大学院生(D1)である岩下晶穂先生が担当する事になった。打ち合わせの中で、岩下先生のお父様が岩下靖史先生であることがわかって、ちょっと驚いた。岩下先生は音羽病院の整形外科医で、脊椎センタ―のセンター長。私は医学部1回生の時には1年間テニス部に入っていて、当時岩下先生は先輩(4回生)だった。また、私が京都医療少年院の内科医として勤務していた頃、整形外科の担当として勤務しておられた。私がまだ桂研に参加する前で研究に真面目に取り組んでいなかった頃、岩下先生はNature誌に論文を出しておられて(Iwashita et al, Nature, 367: 167, 1994)、感銘を受けたことを覚えている。ラットの脊髄の損傷で失われた部分に、他のラットの脊髄の断片を移植してつなげたら、そのラットが歩けるようになった、というような話で、脊髄の再生医療につながる先駆的な成果だった。その岩下先輩のお嬢様をうちの研究室で指導する事になるとは…。 打ち合わせの後、キックオフ食事会。向かって左から西村君、岩下先生、中坊先生、小林先生、私。 |
2025年5月25日(日)
教授室のランの花
 |
少し前にオンシジウムの花が咲いたという記事を書いた(2025年5月4日の記事参照)が、今年はコチョウラン数株が同じ時期に咲いてくれて、教授室の窓際が賑やかだ。買った時から、特に植え替えもせず、水をやっているだけなのに、毎年よく咲いてくれて、ありがたい。多くの洋蘭は日照、温度の他に湿度を必要とするために、普通の居室では空調のせいで湿度が低いから、葉が傷んでうまく育たない。ここで育っているものは、この環境でも育つものだけが生き残っているということである。 |
2025年5月23日(金)ー24日(土)
第22回幹細胞シンポジウム
 |
表記の会が淡路島の夢舞台で開催され、参加した。この会はこれまでほとんど参加したことがないが、造血幹細胞、がん幹細胞、多能性幹細胞など幹細胞研究領域の専門家が集まる、いい会だ。 |
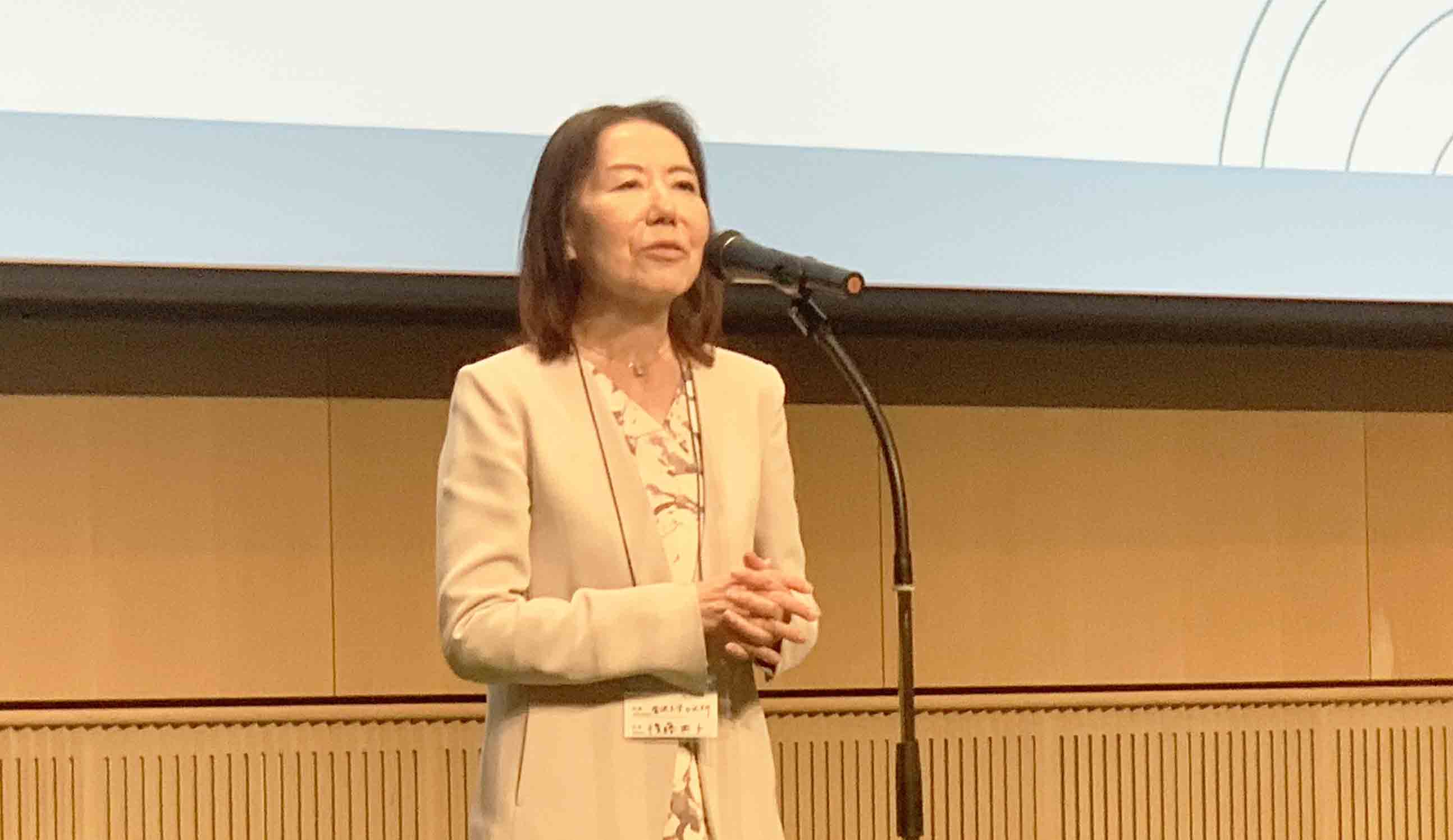 |
今回の集会長、後藤典子先生(金沢大学)による挨拶。 |
 |
今回のキーノートスピーカーは、小川誠司先生(京大)、北村俊雄先生(神戸先端医療センター)、西村恵美先生(東大)。写真は北村先生。 |
 |
ポスターセッションの後、レセプション。 |
 |
向かって左から、北村先生、濱崎洋子先生(CiRA)、私、木村壮輝先生(CiRA)、大石晃嗣先生(三重大学)。大石先生は留学先のIrwin D Bernsteinラボでの仕事で、固相化したノッチリガンドを用いてヒト臍帯血由来造血/幹前駆細胞をT細胞系列に誘導するという先駆的な研究成果を2002年に報告されており(J. Clin Invest, 110:1165-1174, 2002)、in vitroでのT細胞分化誘導研究のパイオニアの一人だ。最近もB細胞とプラズマ細胞様樹状細胞(pDC)の分岐点の分子機構の研究などをされている(Cell Report, 40:111260, 2022)。 |
 |
集会長である後藤先生を囲んで。向かって左から北村先生、平尾敦先生(金沢大学)、私、田賀哲也先生(熊本大学)。 |
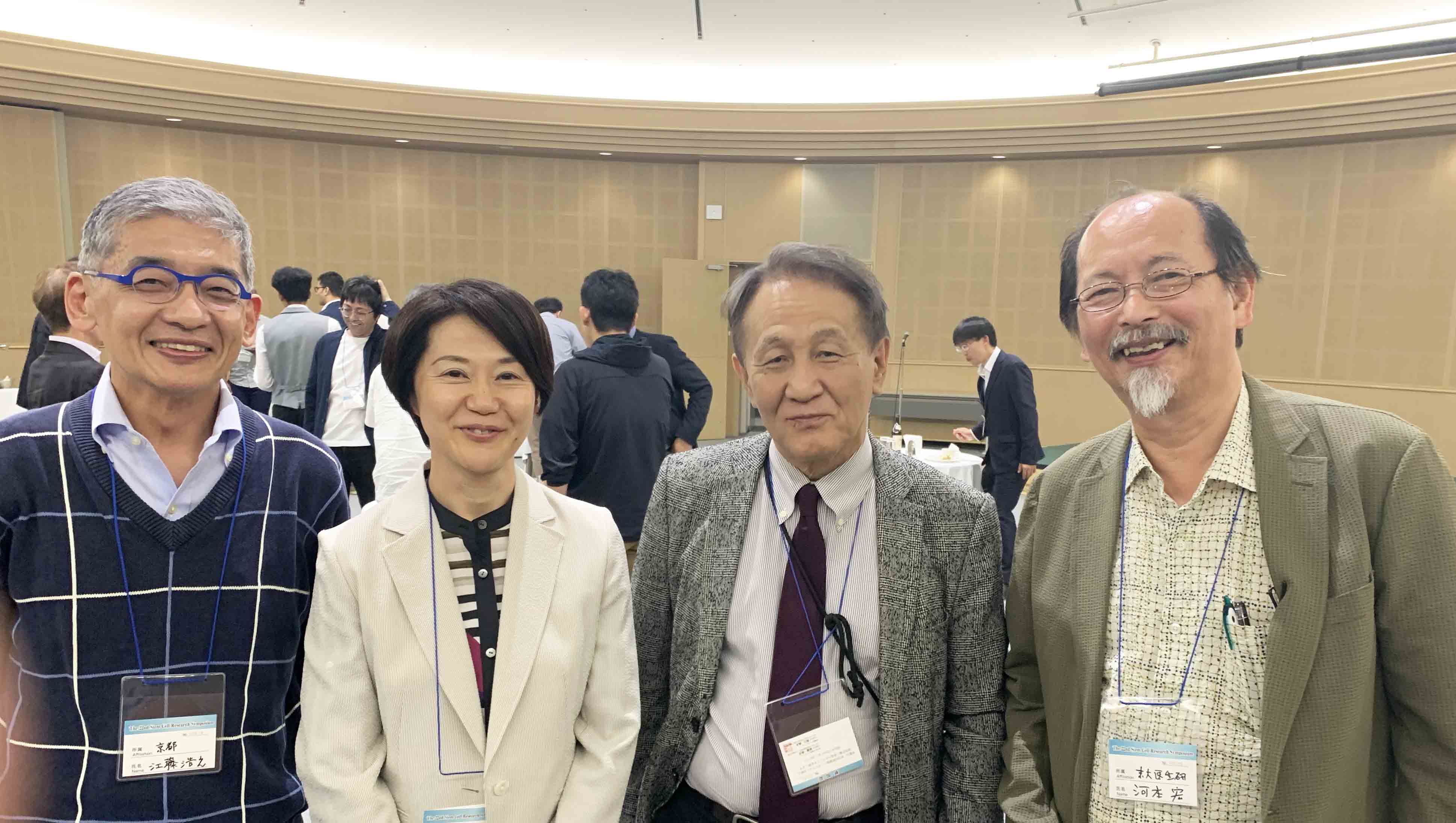 |
オヤジの会のメンバー(2025年4月11日の記事参照)と濱崎先生。濱崎先生を一度オヤジの会に呼ぼうという話になった。向かって左から江藤先生、濱崎先生、小川先生、私。 |
 |
2次会。この学会の人達は、仲が良さそうで、雰囲気がとても良い。 |
 |
部屋。今年10月に開催予定の医生研リトリートでは、ここを使うことになっている。 |
 |
部屋の窓からの景色。 |
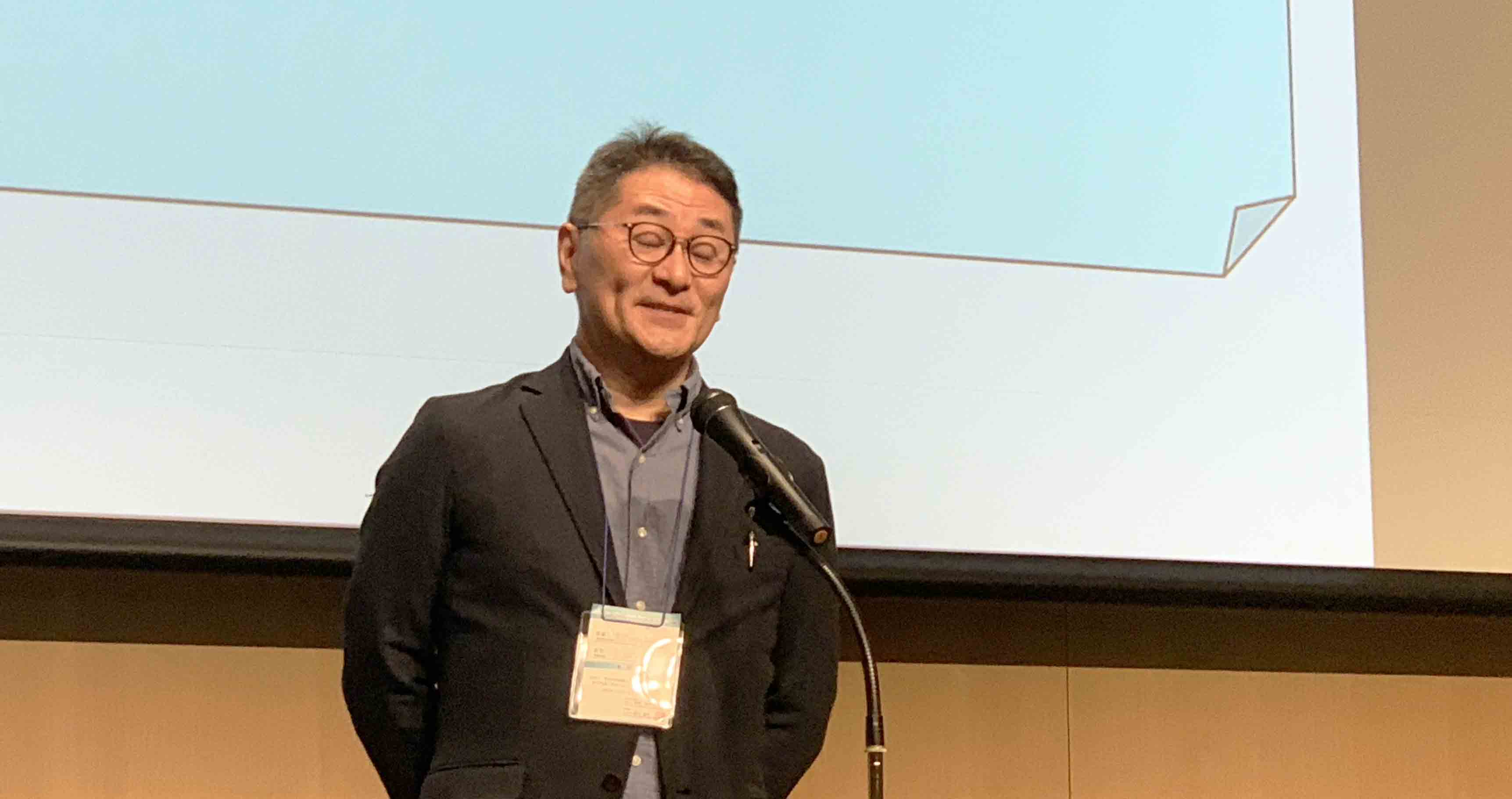 |
閉会式では、来年の集会長である吉田松生先生(基礎生物学研究所)が挨拶をされた。この会はこれまでほぼずっと淡路夢舞台で開催されてきていて、来年もここで開催するらしい。 |
2025年5月21日(水)
中国医薬大学訪問
 |
京都大学は、中国医薬大学にオンサイトラボを持つことになって、昨年11月にそれを記念する式典が開催されたりした(2024年11月19日の記事参照)。今のところ、ウエットラボとしては、萩原正敏先生(医学部)、鈴木淳先生(iCeMS)、私(河本)の、3つのラボが先遣隊として、話を進めている。 |
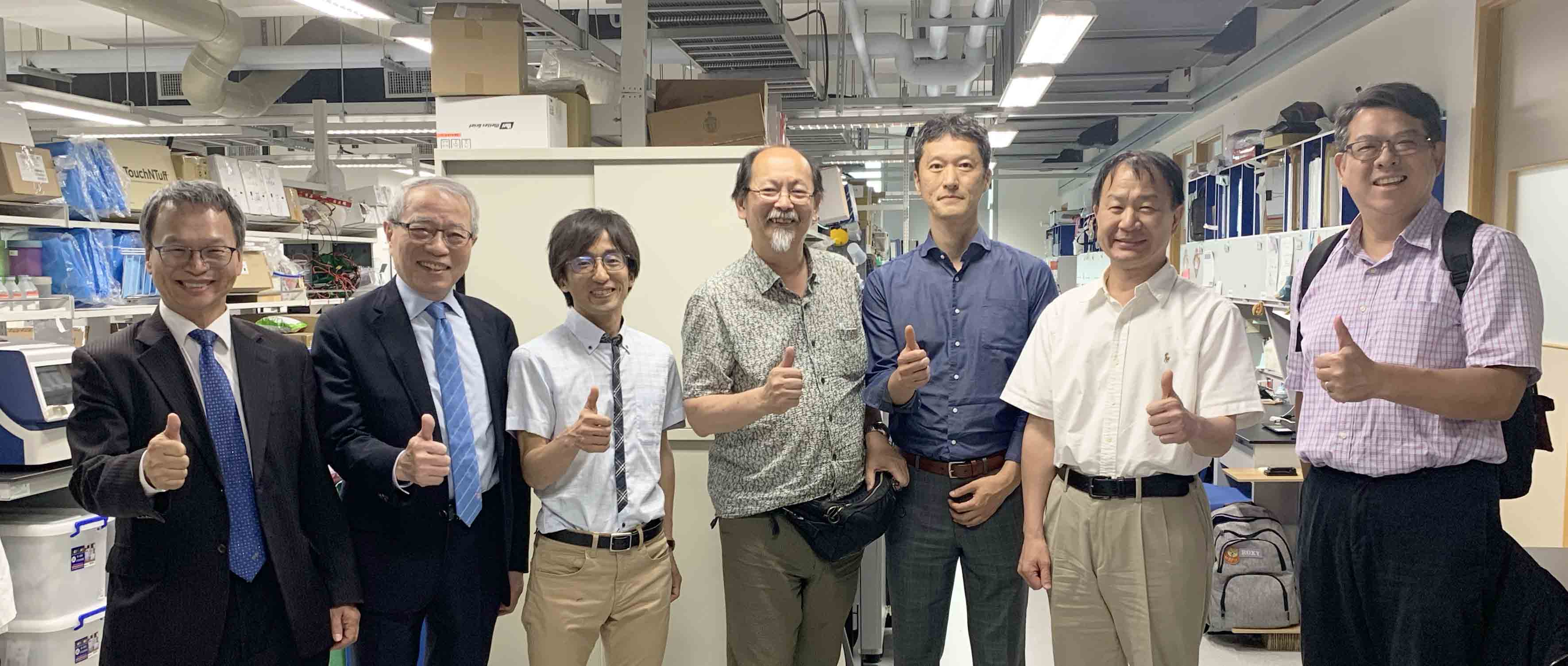 |
今回、医生研の中でその活動に興味を持っていただけた廣田圭司先生(近藤研准教授、私の向かって右隣)と森田大輔先生(杉田研助教)と一緒に、見学/打ち合わせの会を持った。 |
 |
打ち合わせでは、廣田先生と森田先生が、自己紹介として、研究内容についてプレゼン。 |
 |
その後、会食。台湾料理は、日本の料理に近いものも多く、どれもとても美味しい。山口浩史先生(向かって左端)は、Hung学長の共同研究者として3年くらい前から中国医薬大学に異動されてラボを運営されているとのことだが、京大のオンサイトラボの運営に際して、間を取り持つ役として働いていただいている、キーパーソンだ。 |
 |
フルコースの会食の後であったが、せっかくだからと、3人で廣田先生が呼んでくれたウーバーで、逢甲夜市に行った。 |
 |
夜の10時ごろであったが、中々の賑わいだった。 |
 |
「おでん」の店。 |
 |
日本とは違う具材も多く、あれこれ食べてみたいものだ。 |
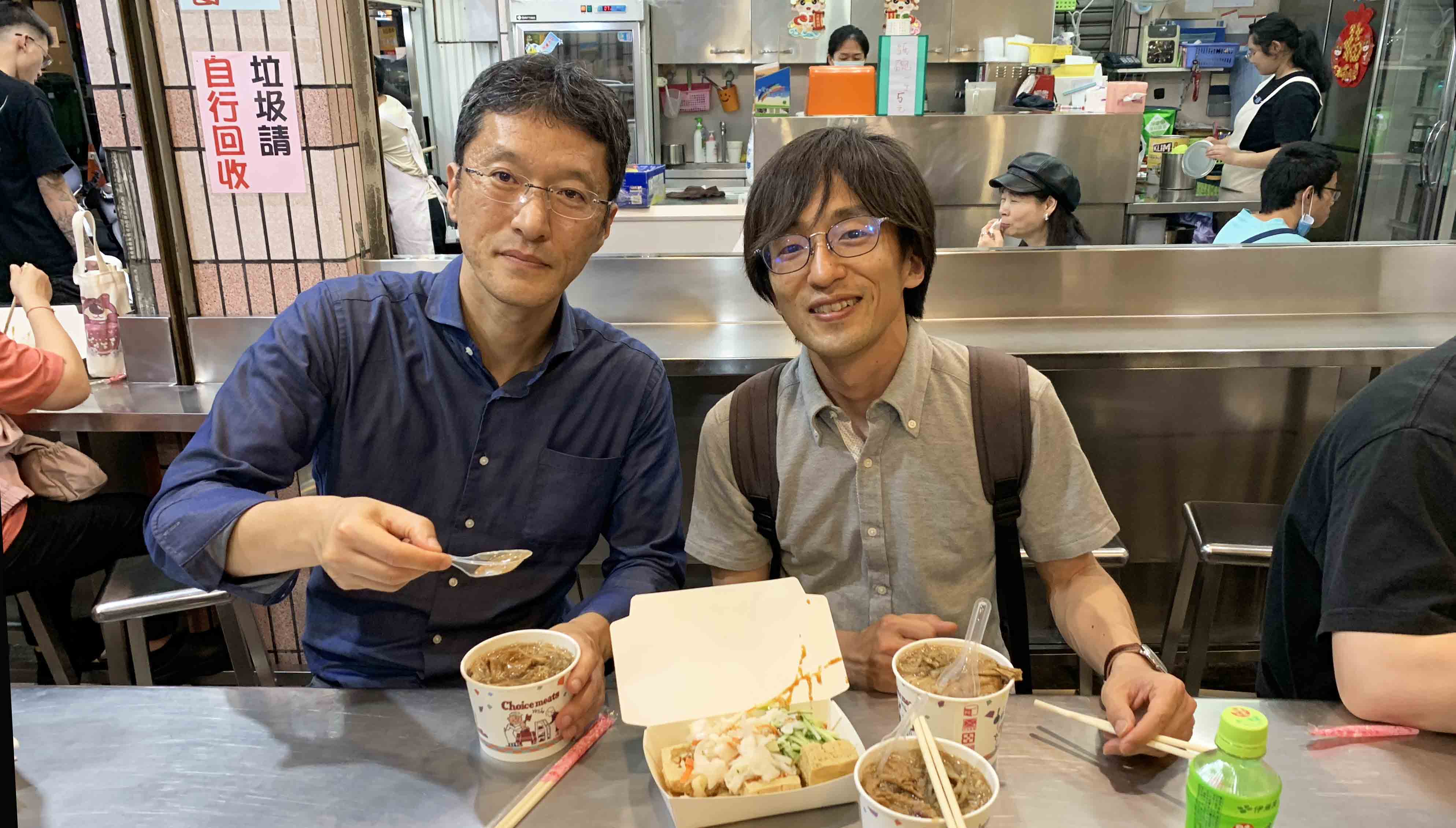 |
会食で満腹だったので、比較的軽い品として、麺線を食した。 |
 |
そういえば東アジアインポジウムで台北に行った時も、麺線をいただいた(2024年10月29日の記事参照)。麺線は、伸びきったソーメンにとろみがついたスープが絡んだような料理であるが、牛肉も入っていて、スープの味がよく、美味しかった。 |
 |
同じ店に「臭豆腐」が売っていたので、皆で試してみた。かなり前に台北の夜市で試した時は、煮た物は全く食べられなかったが、揚げたものは、何とか食べられた(2014年6月28日の記事参照)。ここで売っていたのは、揚げたもののようであったので、大丈夫と思い、一つ買って、皆で一切れづつ試した。結論をいうと、今回の臭豆腐は、私は全く受け付けられなかった。一口噛んだものをペッと吐き出す訳にはいかないので、涙目になりながら飲み込んだが、脳が「これは絶対食べたらあかんやつ」と激しく訴えかけていた。廣田先生も森田先生も、私とほぼ同意見で、台湾の方には申し訳ないが、「これは食べて良い物の臭いではない」との見解で一致した。 |
2025年5月19日(月)
藤田医大河本研で会食+カラオケ
 |
この日、午前中に私は今期の基礎免疫学講義の最後(9、10コマ)を終えた。午後に打ち合わせなどを行った後、有志でまず金山のハワイ料理の店で会食。向かって左から、金原さん、磯貝さん、私、川瀬先生、杉山さん、高柳さん。 |
 |
ハワイ料理には、写真にあるようにモチコであげた唐揚げ、ガーリック枝豆など、日本から伝わったものが多いとのことだが、特筆すべきは「ふりかけ」が大きく発展しているようで、ハワイでは塩味のふりかけをアイスクリームにかけたりしているらしい。 |
 |
会食後、近くのカラオケ店へ。藤田医大の河本研のメンバーは、皆カラオケが好きとのことで、今回も私が行こうと誘った訳ではなく、少し前から自然発生的に行く話になっていた。皆、それぞれ持ち歌があって、歌が途切れることがなかった。金原さんがベルばらの「愛あればこそ」を歌ってくれたのが、これまでカラオケで聴いたことがないという事もあって、印象的だった。 |
2025年5月16日(金)
共共拠点キックオフシンポジウム
 |
ウイルス研究所と再生位科学研究所が統合してウイルス・再生医科学研究所になったのが2016年10月だから、すでに9年近く経ったことになる。統合した時点ではどちらの研究所にも拠点事業があり、統合後はそれぞれの拠点を引き継いで、1研究所2拠点の体制で事業を進めてきた。 名称を医生物学研究所に変更したのが2022年4月であるが、それを契機として、それまで2つに分かれていた拠点事業も統合することになり、それ以後は1つの「ウイルス・幹細胞システム医生物学共同研究拠点」として運営している。 |
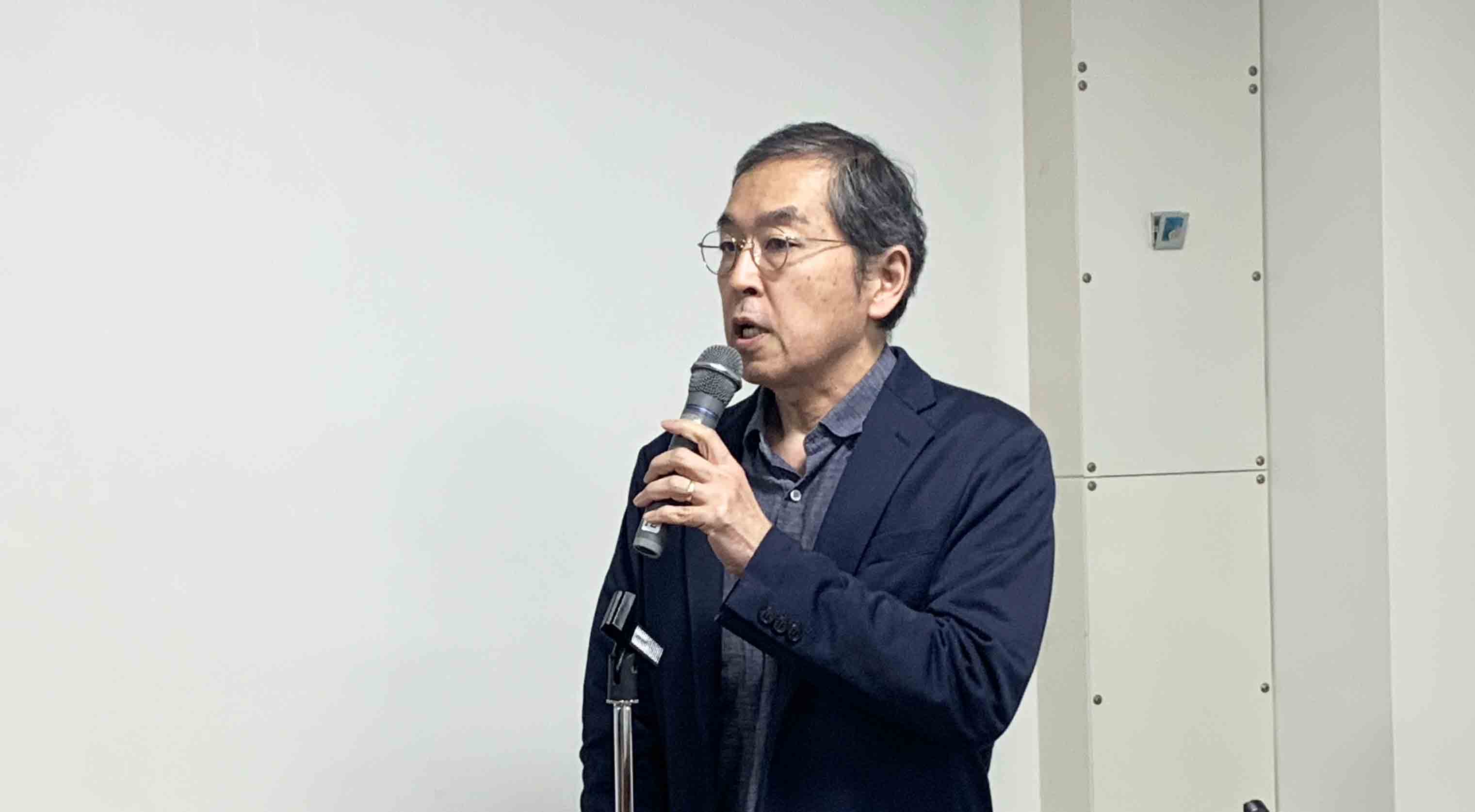 |
拠点長である朝長先生による挨拶。 この拠点の中核となる事業として、当研究所の教員スタッフとの共同研究を外部機関に広く公募し、採択された課題には100万円を上限として支援する仕組みを始めた。毎年20-30件が採択される。 3年程前までは、共同研究期間終了近くの3月に、採択課題の代表者による「報告会」が開催されていた。しかし、ホストラボ以外の医生研研究者や、採択された研究者間でも、この事業に参集したさまざまな研究課題を知ってもらい、新たな共同研究を生み出すきっかけとなるためには、研究開始直後の方がいいのではないかと考えて、3年前から年度初めにキックオフミーティングを開催することになった(2023年5月22日の記事参照)。 |
 |
採択課題代表者によるプレゼンが全て終了した後、代表者と医生研の研究者による情報交換会。 |
 |
中台枝里子先生(向かって左)と豊島文子先生。豊島先生は何年か前からクロスアポイントメントで東京科学大学と兼業されていたが、この4月から先方の専任となられた。 |
 |
向かって左から、縣保年先生(滋賀医大)、童友さん(鈴木淳研究室D3)、私。 |
2025年5月13日(火)
小嶋先生による講義
 |
ILASセミナーを5コマ担当していると書いたが、その第4回と第5回は、TBSの特別解説員をされている小嶋修一氏を外部講師として招いた。第4回のテーマは、臓器移植。 |
 |
小嶋先生には、以前に河本研が進めている新型コロナ治療用T細胞製剤の話を、報道特集で取り上げていただいた(2020年11月21日の記事参照)。下記動画の0.49あたりで教授室に入ってこられているのが小嶋先生。 TBS報道特集「重症者を救え 新型コロナの画期的な治療薬とは【報道特集】」2020年11月21日放送(Youtube動画): |
 |
この日の講義では、一人の提供で複数人の命が救われるという臓器移植の重要性を説かれる一方で、「脳死を人の死として良いか」「移植医療は現代医療の未熟さ故にあるツナギか、成熟した医療か」などが論じられた。さすが第一線のジャーナリストで、豊富で正確な情報と、世論の変遷も踏まえた素晴らしい内容の講義で、講義の後半の討論会では、深い議論が交わされた。 |
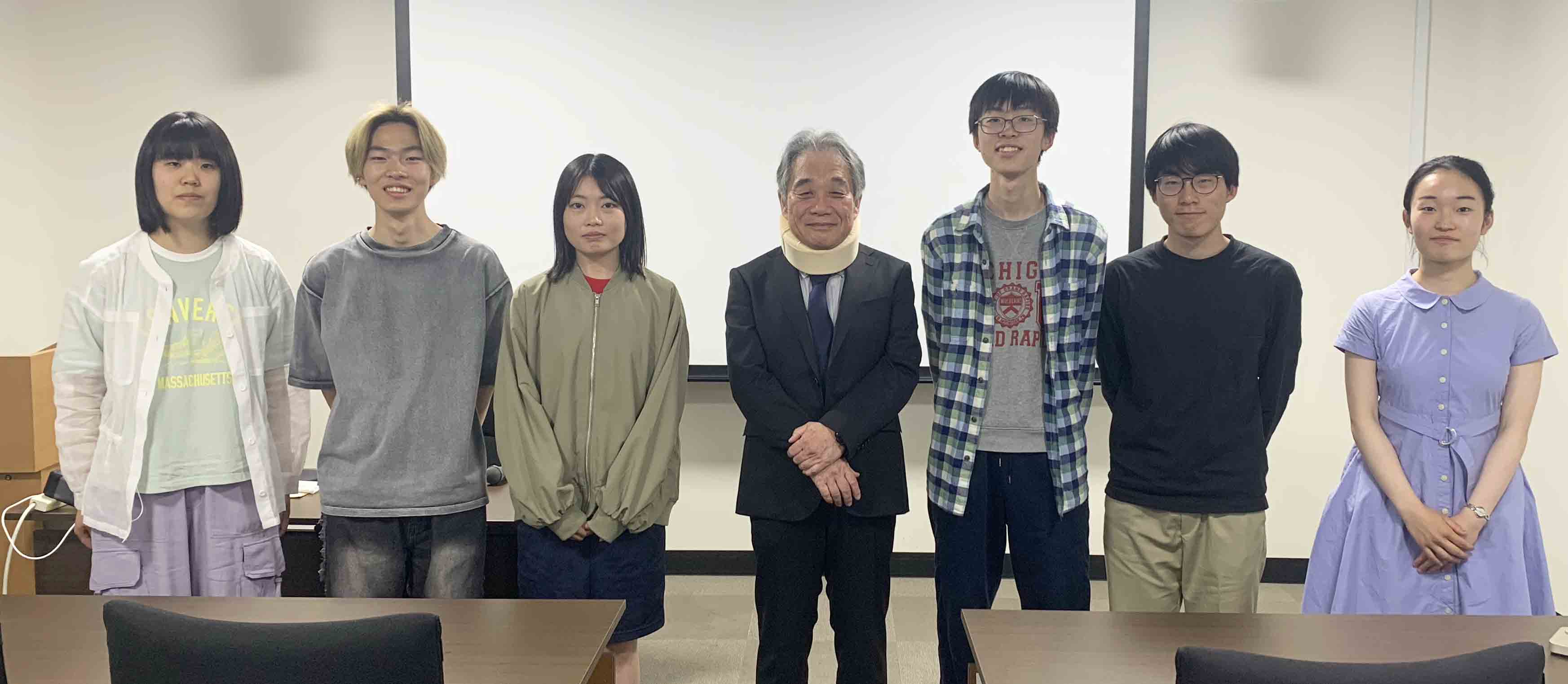 |
講義終了後、記念写真。生徒さん達は、小嶋先生の講義から、多くのことを学べたようだ。この次の週に行われた第5回では「日本に根深い反ワクチン運動を考える」というタイトルで科学と非科学の境界線についての議論をされた。 |
 |
少し前から、「ES細胞の良さをどのように世の中に伝えるか」「抗ウイルス感染症治療用T細胞製剤がいかに画期的か」などを議論するための有志の会を催しているが、今回は小嶋先生に講義終了後に参加してもらい、ジャーナリストとしてのアドバイスをいただいた。医療用ES細胞に関わっている先生方にも参加していただいている。向かって左から中馬新一郎先生、川瀬栄八郎先生、私、小嶋先生、大久保博志さん、高田圭先生。 |
2025年5月12日(月)
獨協医科大学で講義
 |
毎年この時期の月曜日に、獨協医科大学の解剖学の講義の中で、免疫の仕組みについての入門編の話などを、2コマさせて頂いている。午前中の講義なので、宇都宮には前日入りする必要があるのだが、移動日が日曜日ということで、少し早めに行って、観光をさせて頂いている。この日は、道中、富士山がきれいに見えた。 |
 |
徳田先生の案内で、「あしかがフラワーパーク」を訪問。一昨年も訪れて、クレマチスやショウブの花を楽しんだ(2023年6月5日の記事参照)が、今回はその時より1ヶ月ほど早いので、違う種類の花が楽しめそうだ。 |
 |
入場してすぐのところに、植物を小売りしているエリアがある。その中に、食虫植物のコーナーがあった。前回と同じように、セファロタス・フォリキュラリスという種が売られていたが、今回は販売されている鉢数がやたらと多くて、驚いた。 |
 |
セファロタスは、オーストラリア南西部に自生する、一属一種の希少な植物。1鉢1200円。一昨年は、もう少し大きくはあったが、1鉢2500円だったから、随分お求めやすくなっている。私の経験からは、セファロタスの栽培はかなり難しく(「河本宏の部屋」の「食虫植物のページ」参照)、こんなに沢山の株をこの値段で売れるように卸すとは、さすがに園芸業者のプロは違うなと、感心した。 |
 |
この鉢は「レアサラセニア」と書いてあるが、これは正しくは「ヘリアンフォラ」という、南米のギアナ高地にだけ自生する希少種。ヘリアンフォラも理研のリームリーダー時代にリーダー室で栽培していたが、長期間いい状態で維持するのは難しかった。この鉢は交配種のようではあったが、それにしてもこれだけの大きさの株を1000円台で売るとは、とても良心的だ。 |
 |
これはネペンテス・ベントリコーサというウツボカズラの原種の一つで、捕虫葉が印象的だ。この株は6000円と、まあまあの値段ではあったが、これだけ大きな袋のベントリコーサはあまり見かけないので、良い素質を持っていそうな株だ。 |
 |
小売店を物色した後、とりあえず昼食。フードコートで、案内役をしてくれていた徳田先生のお勧めで、「イモフライ」という、茹でたジャガイモのフライを食べてみることにした。「フライというか、串カツの一種では」と思ったりしたが、「肉類にパン粉をつけて揚げたものがカツ、それ以外のものにパン粉をつけて揚げたものがフライ」という定義があるらしく、それで言えばイモフライで良いということになろう。イモフライはご飯のおかずとして供されるらしく、つまり炭水化物をおかずにご飯を食べるらしい。まあそれをいうと、ラーメン+ライスという食べ方もあるし、関西ではお好み焼きをおかずにしてご飯を食べるという文化もあるので、特に特殊という訳ではなさそうではある。 |
 |
佐野市のゆるキャラ「さのまる」が腰にさしているのがこのイモフライとのこと。なお「さのまる」は、私はよく知らなかったが、ゆるキャラグランプリで、「ひこにゃん」(2010年初代王者)、「くまモン」(2011年)、「バリィさん」(2012年)(今治市)に続いて2013年の王者、とのこと。 |
 |
炭水化物の組み合わせという文脈で言うと、この地域には「ポテト入り焼きそば」もあるとの話だった。豚肉の細切れも申し訳程度に入っているとはいえ、この辺りではジャガイモはおかずとみなされているようだ。なお、この店では個々のポテトが小さいが、ネットで調べると、もっと大きな塊がゴロゴロと入っているのがスタンダードであるようだ。 |
 |
せっかくなので、佐野ラーメンもいただいた。どれも美味しかった。 |
 |
今年はいろいろな植物の開花が全体に1-2週間遅めなので、このフラワーパークの看板を背負っている「フジ」が見られるかと期待したが、残念ながら少し遅かった。ここは白いフジのトンネル。 |
 |
「奇跡の大藤」と呼ばれる巨大な藤棚。ここも少し遅かった。満開の時にライトアップされると、まるでアバターに出てくる「エイワの木」のようだと、世界的にも大人気のスポットであるらしい。 |
 |
キフジは、ちょうど見頃だった。きれいではあったが、この種はフジのように棚を頼りに拡がる蔓性という感じはなく、棚に無理やり絡ませている感じで、ちょっとどうかと思った。 |
 |
バラはやや早い感はあったが、満開の株も多く、十分楽しめる頃合いだった。 |
 |
赤い花、黄色の花、白い花、青い花など、色別に分けた花壇が見事だった。写真はピンク色の花を集めた花壇。 |
 |
青い花の花壇と、徳田先生。青の花の多くが、デルフィニウムと思われる。 |
 |
以前に青色の花はそもそもほとんど無い、という話を書いたことがある(2021年6月26日の記事参照)。その中で、どこにでも生えている「ツユクサ」は、「本当の青に近い」と記した。ヒマラヤの青いケシやネモフィラは淡いアオで、むしろ水色という範疇だと思われる。デルフィニウムの青は、ツユクサの青に比べると、やや紫色の成分が入っていると思われる。以前も書いたが、下記の「青いバラの開発に成功」という記事の中のバラは、普通に見るとウスムラサキだ。 青いバラへの挑戦: |
 |
ツツジはほぼ終わっていたが、シャクナゲが見頃だった。園内に多種多様なシャクナゲが植えられていて、見応えがあった。シャクナゲは日本でも深山や亜高山帯に行けば見ることができる。子供の頃に親に連れられて京都の北山方面をよく歩きまわったが、北山でも奥の方ではシャクナゲを見ることができ、この花を見ると、「深い山まで来た」という実感が沸いたのを思い出す。父が生前シャクナゲが大好きだったこともあって、思い出深い花だ。 |
 |
歩き回って小腹が空いたので、オヤツタイムを取ることにした。徳田先生のお勧めで、桐生名物の「ひもかわうどん」を食した。 |
 |
とても平たいうどんであるが、コシがありながら、もっちりしていて、とても美味しかった。 |
 |
12日午前中の獨協医大での講義では、「基礎研究者への道のり」という話の中で、「学会は闘いの場」という論点に絡めて、「逆襲の助教」のMVをフルで観てもらった。 |
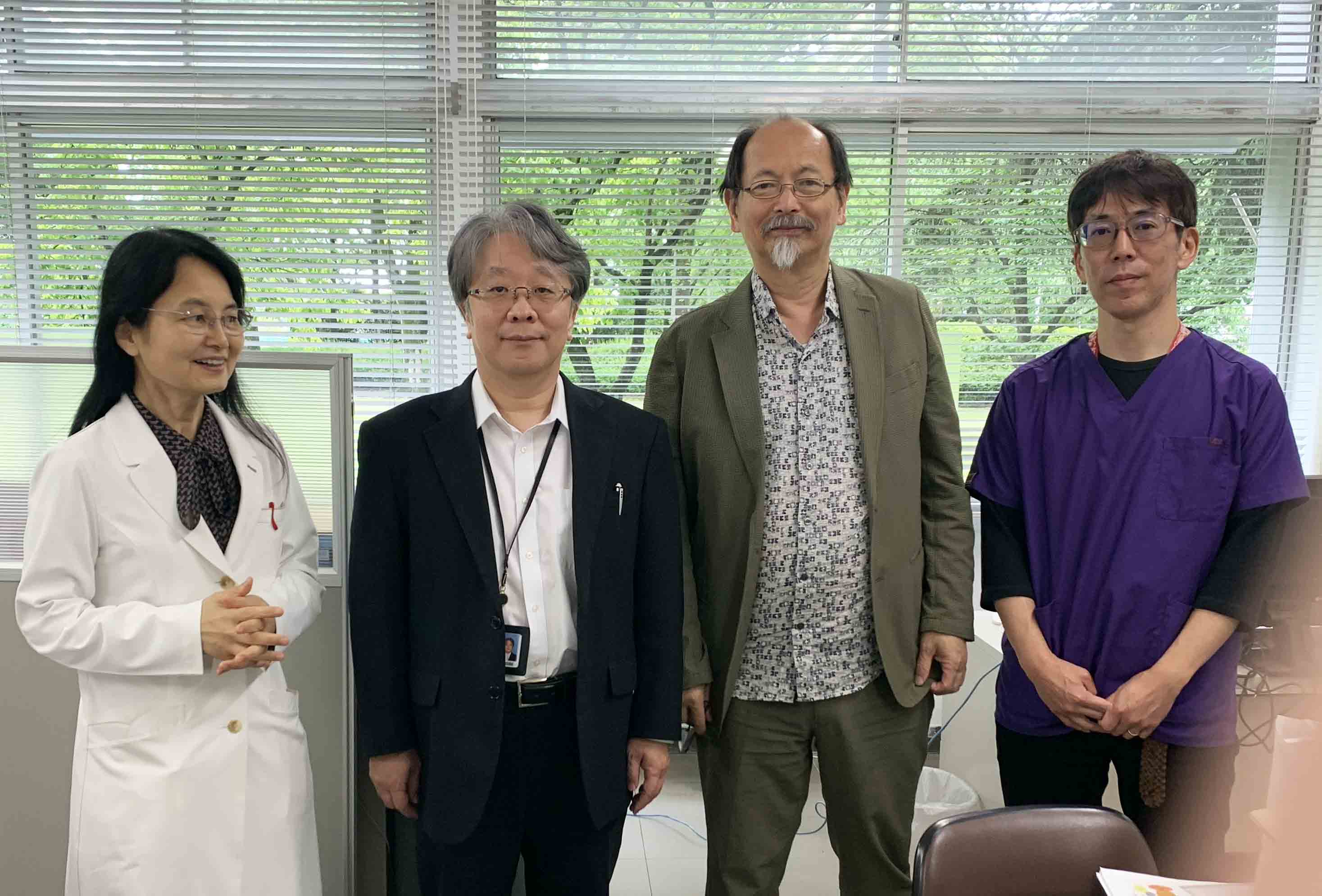 |
講義が終了した後、解剖学教室に神作憲司先生(生理学教室教授)が訪室された。聞けばご子息二人のうち御長男が東大医学部生(5回生)、御次男が京大医学部生(2回生)とのこと。御長男は2年前に私の免疫学の講義を聴いてくれたそうで、御次男は来年聴かれることになるであろう。向かって左から、徳田先生、神作先生、私、上田祐司先生(解剖学准教授)。 |
2025年5月10日(土)
庭のデンドロビウムが見頃
 |
デンドロビウムのノビル系と、日本の野生種であるセッコク(2024年5月8日の記事参照)を交配したと考えられる品種で、寒さに強く、屋外でも元気に育つ。デンドロビウム属のランはいわゆる着生ラン(樹木や崖などに着生して育つ種)であるので、壁に吊り下げた水苔玉を足場にして、いい感じで増えてくれている。昨年より少し遅く見頃迎えた(2024年4月28日の記事参照)。 |
2025年5月9日(金)
佐治先生主宰の昼食会
 |
表記の会はコロナで一時中断していたが、ちょっと前から復活し、年に数回開催されている(2025年1月10日の記事参照、2024年7月19日の記事参照)。 |
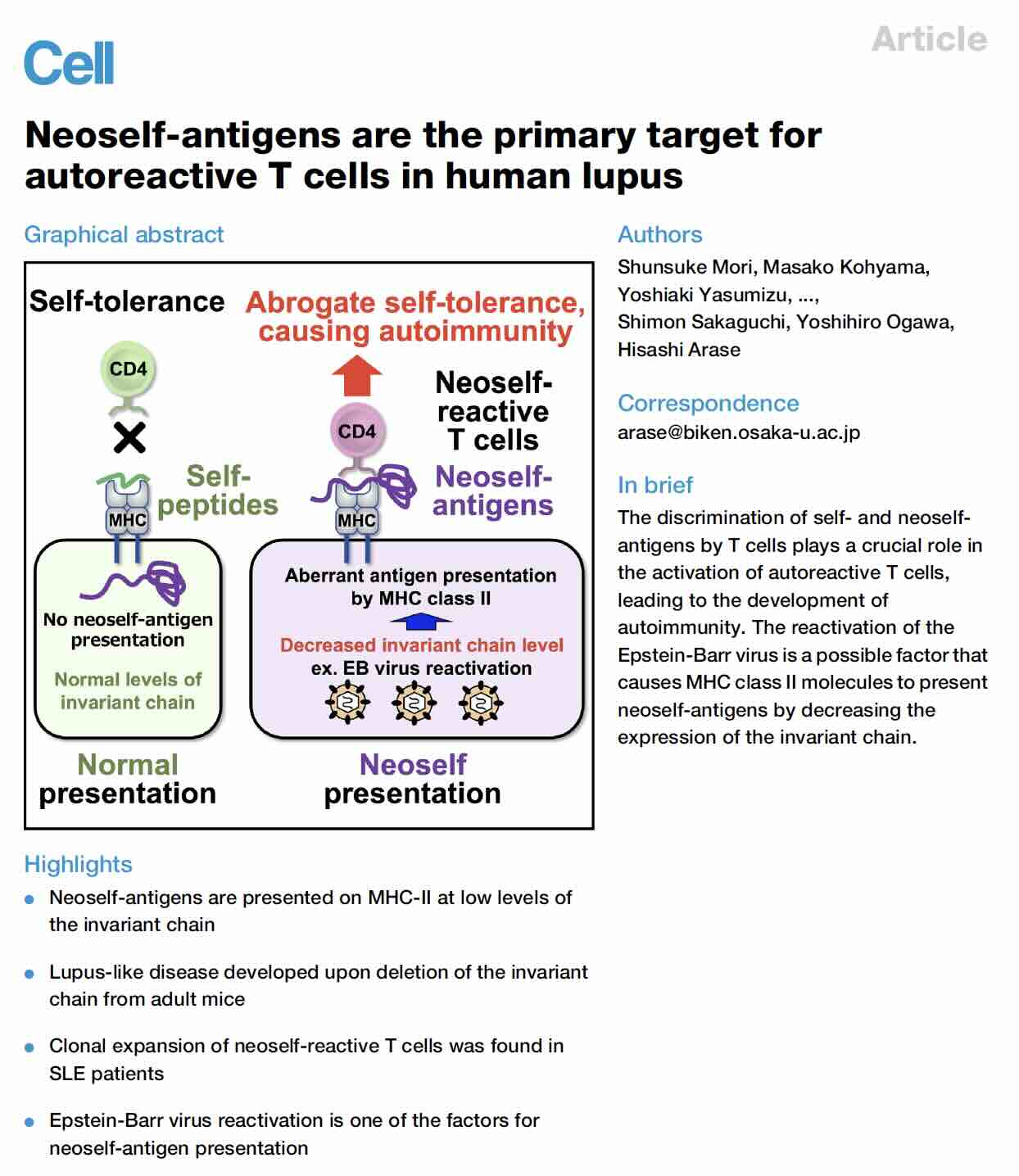 |
この会は勉強会を兼ねていて、この日は昨年の荒瀬先生のCell論文を共有した。荒瀬先生は、小包体の中できちんと折り畳まれなかったタンパク分子の一部がHLAクラスIIの溝に挟まって、その分子ごと細胞表面で提示されてしまうことが、自己免疫疾患の原因の一つであると以前から提唱されていたが、昨年、EBウイルスが感染した細胞ではクラスII分子にそういう形で異常なタンパク分子が クラスII上に提示されるようになって、それが自己免疫疾患を誘発するという話を、Cellに報告された(187:6071,2014)。 |
 |
その中でもう一つ紹介したのが、2017年にトロントの平野直人研から出された論文で、クラスII分子のうちのDP4と呼ばれる分子は、「小胞体の中でインバリアント鎖によって溝が塞がれる」という機構がうまく働かないので、「取り込んだタンパクの分解産物だけを提示する」というクラスIIの本来の仕事が果たせず、クラスI分子のように細胞質内のタンパク分子の分解産物を提示してしまうことになる。そのDP4は、珍しいアリルではなく、むしろ人類全体でみても最も頻度の高いアリル(20-60%)であるので、こういうまともに働けない分子が進化の過程で多く残るには、何らかの感染症に対してその方が却って有利だった可能性が考えられる。 |
2025年5月4日(日)
オンシジュームが開花
 |
オンシジュームというと、一般的には黄色い花弁の花が一茎に何十と咲くボリューム感が特徴的であるが、この種はそういう印象とは全く違って、日本の野生ランであるエビエに似た感じ。派手さはないが、こういうのが好みに合っている。 |
2025年4月28日(月)
清水免疫学・神経科学振興財団のHPのリニューアル
 |
表記の財団は1982年に創立され、毎年、京都府下の免疫あるいは神経科学領域の研究機関/研究集会に、助成を行ってきた。ここ数年はやや規模が縮小され、一件50万円の助成金を5件前後に配布している。KTCCもずっと援助いただいている。昨年6月の役員会をもって米川雅子さんが代表理事を辞任され、代わってそのお嬢さんである米川恵子さんが代わって代表理事になられた(2024年6月11日の記事参照)。もう一人の代表理事は坂口志文先生が務められており、私は理事を務めている。米川恵子さんが代表理事になったことをきっかけに、HPをリニューアルしようという話になり、昨年10月に新HP(下記リンク)のヘッダーのイメージのイラストを依頼された。11月に納品し、このたび、HPのヘッダーとして登場した。 清水免疫学・神経科学振興座財団の新HP: |
 |
ヘッダーの左側のアップ。 HPのお知らせ欄に、米川恵子さんが、解説文(以下)を書かれている。私のイラストの意図をしっかり汲んで頂いており、大変ありがたい文章だ。 「当財団のホームページのリニューアルにつき、理事の河本宏先生(京都大学教授)がキービジュアルを描いて下さいました。右側には、日本を代表する文化財の一つである「風神雷神図屏風」(京都・建仁寺)を元に、風神が実験に励み、雷神が論文作成に精を出しています。彼らの間を流れるのは、千年の都と京文化を育んできた鴨川です。そして周囲には胸腺、リンパ節、脳、脊髄、神経、心臓が絡まる感じで配されています。左側には、国宝「鳥獣戯画」(京都・高山寺)を元に、発生生物学のモデル生物としてよく使われるアフリカツメガエルとマウスが登場します。 免疫学、神経科学、京都が見事に絡み合い、当財団にピッタリでウィットに富んだ傑作を描いて下さった河本先生、どうもありがとうございました!」 |
 |
雷神の部分のアップ。 |
 |
風神の部分のアップ。 |
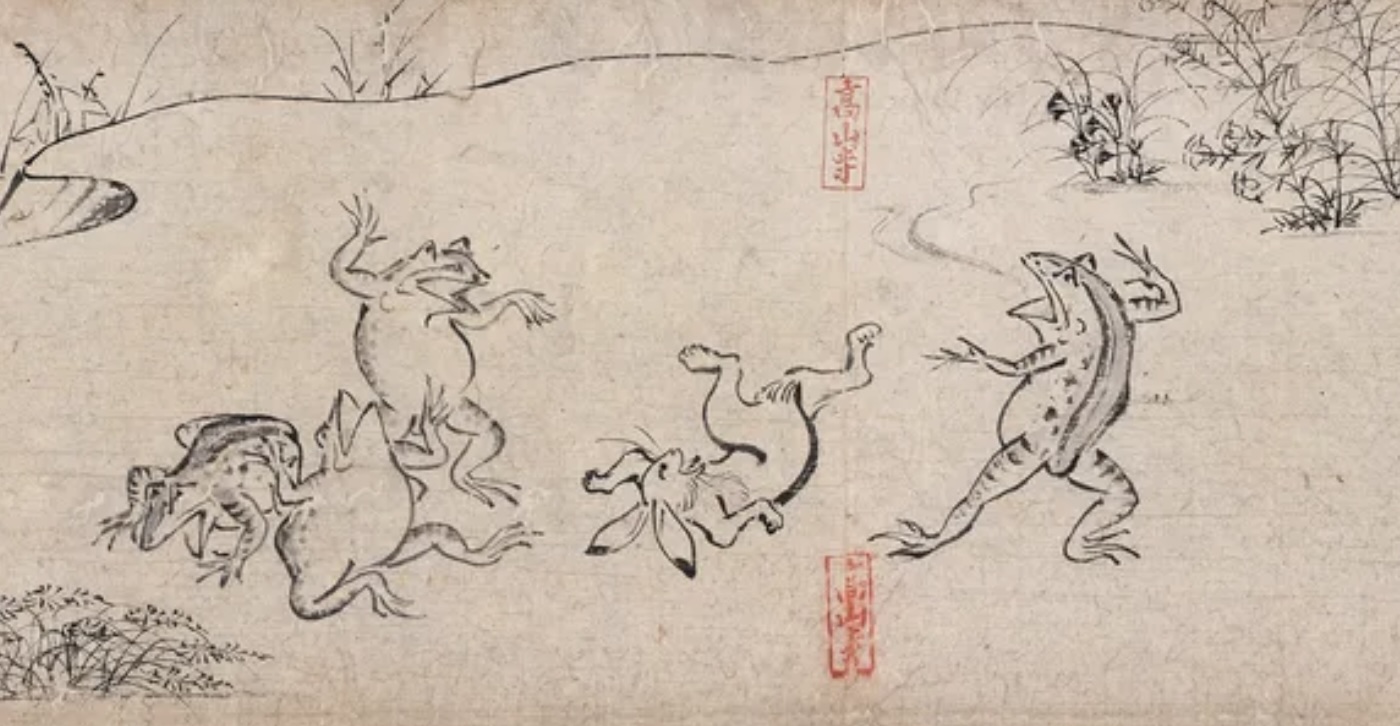 |
参考までに、鳥獣戯画の原図。 |
 |
風神雷神図屏風の、俵屋宗達による原図。 |
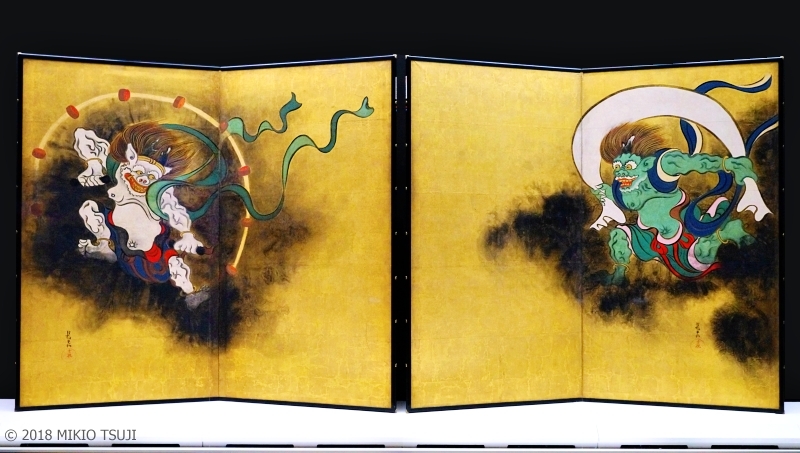 |
尾形光琳が模写という形で作成した屏風図。色彩的には、こちらを参照した。 |
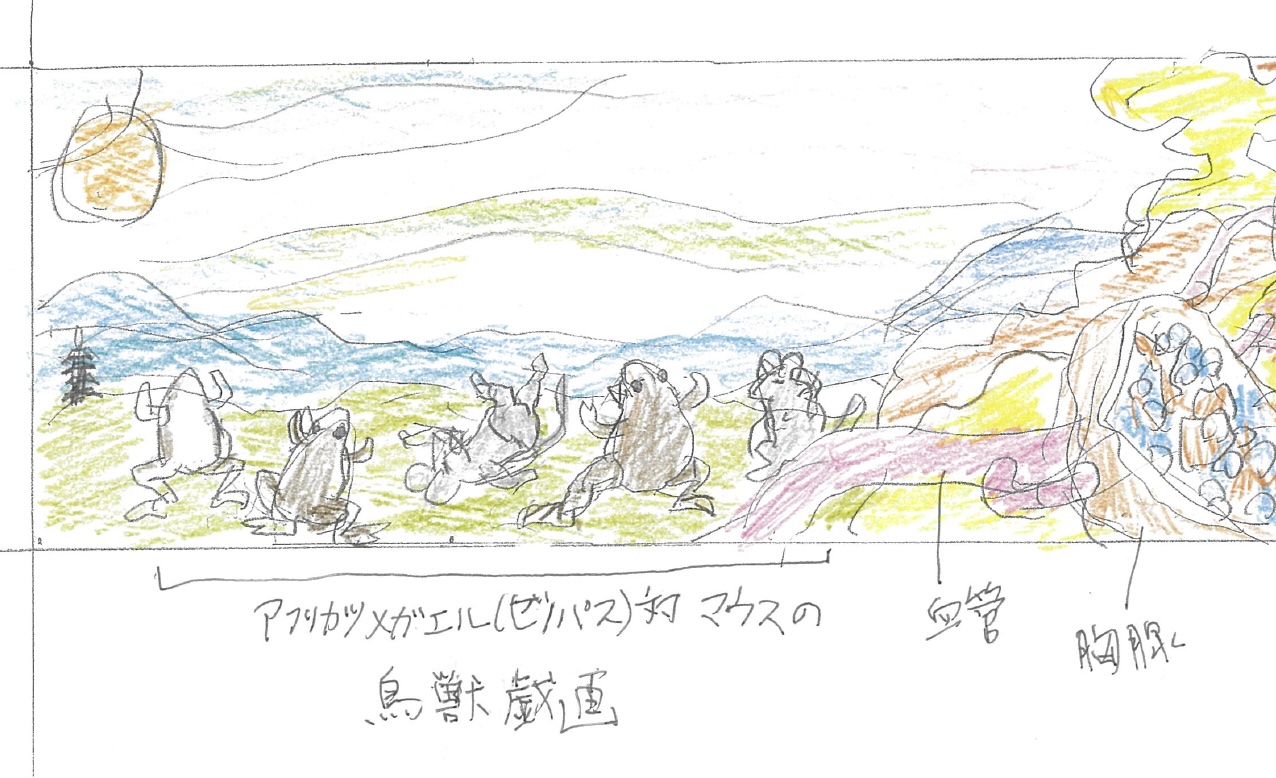 |
左図は、今回のイラストの草稿。ラフスケッチの最終稿に彩色して、能書を加えた図の、左半分。 |
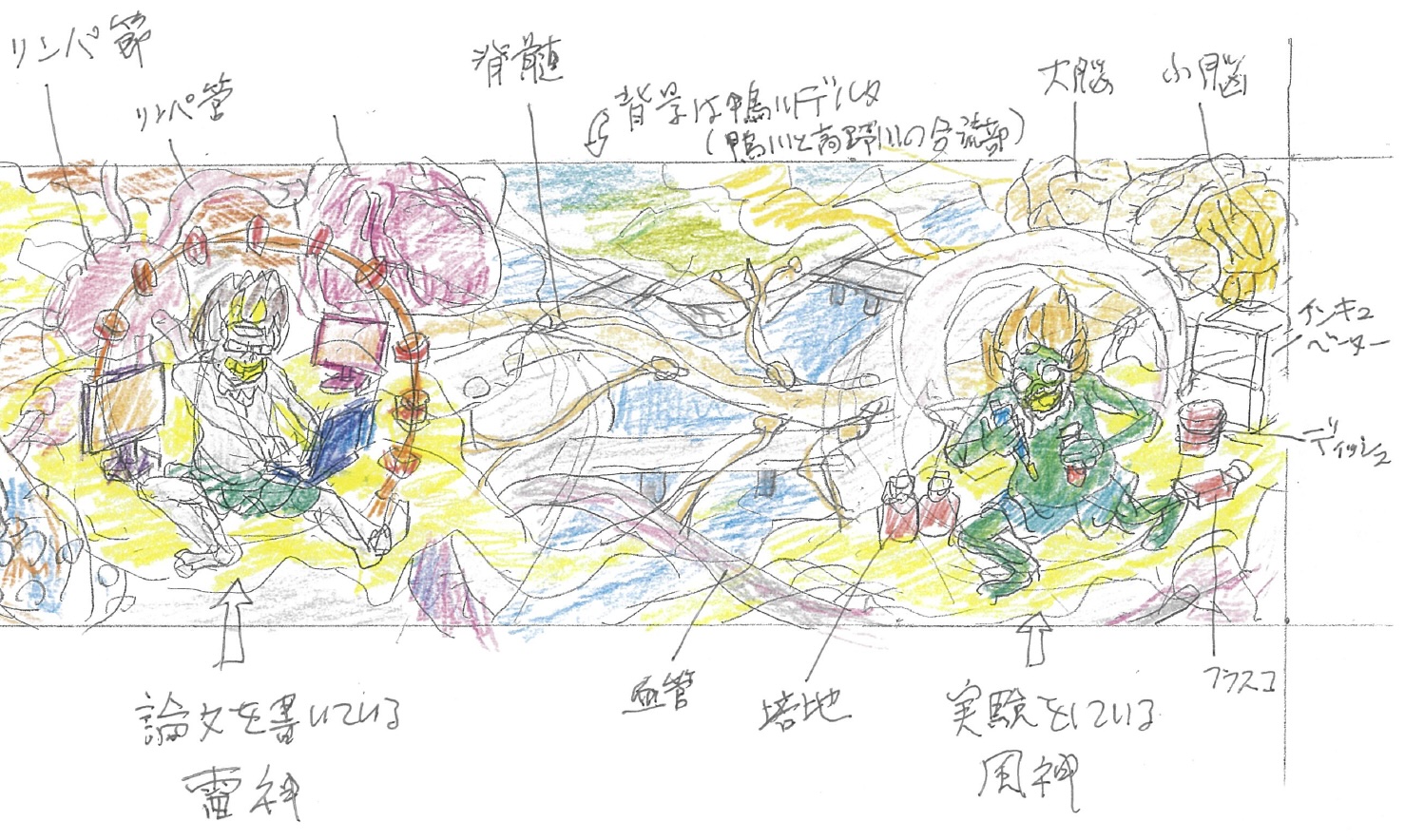 |
右半分。この図をまず米川さんに送って、了承いただいた。完成作ができてからも、真ん中あたりの心臓の表面を走行している冠動脈について、米川さんの指摘に基づいて、一度修正している。 |
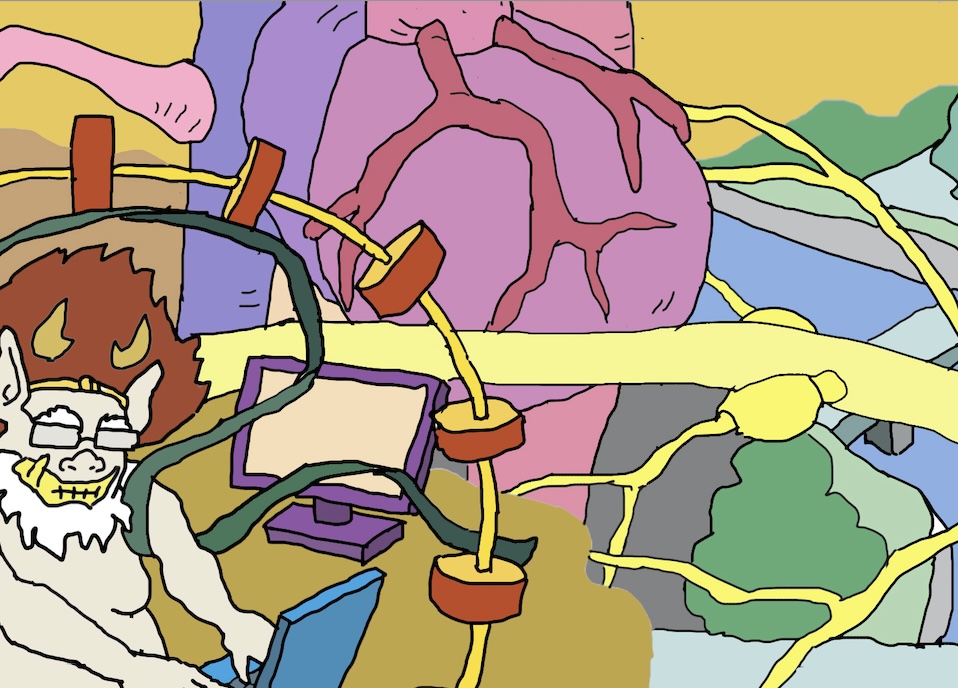 |
左図が初稿時の、テキトーに描いた冠動脈。米川恵子さんは、スイスで循環器系の医師をされているが、専門家だけに、そのあたりが気になったらしい。さすがだ。確かに、見直すと、かなりいいかげんだ。まず、この絵では右冠動脈の方が太くてしっかりしている点に、違和感があったようだ。また、左冠動脈は正しくは大動脈から出てすぐに前下行枝と回旋枝に分かれるのであるが、その点も描けていない。私は、関西電力病院時代にローテーションで半年間循環器内科で研修していた時には、心臓カテーテル検査を何度も近くで見学して、その時点では冠動脈の走行は画像として頭に刷り込まれていた筈であるが、40年も経つと、すっかり忘れてしまっていた。熱心に指導してくださった石井克久先生(2022年3月20日の記事参照)、すみませんでした。 |
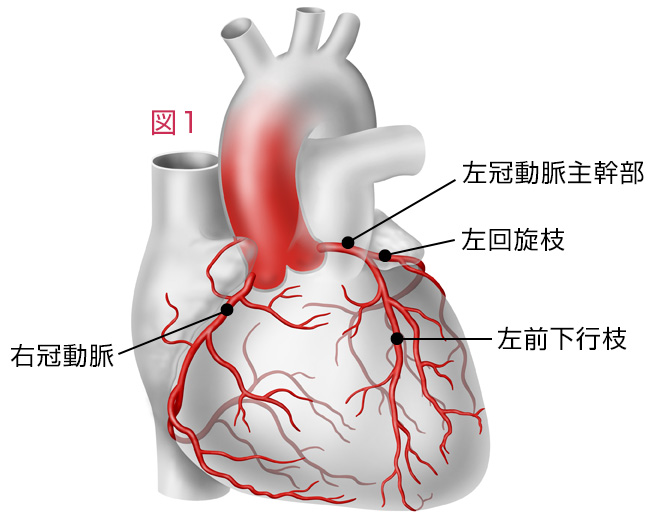 |
参考までに、冠動脈の図解。日本医科大学附属病院心臓血管外科のHPから拝借させていただいた。 |
2025年4月27日(日)ー5月1日(木)
ThymUS2025にオンライン参加
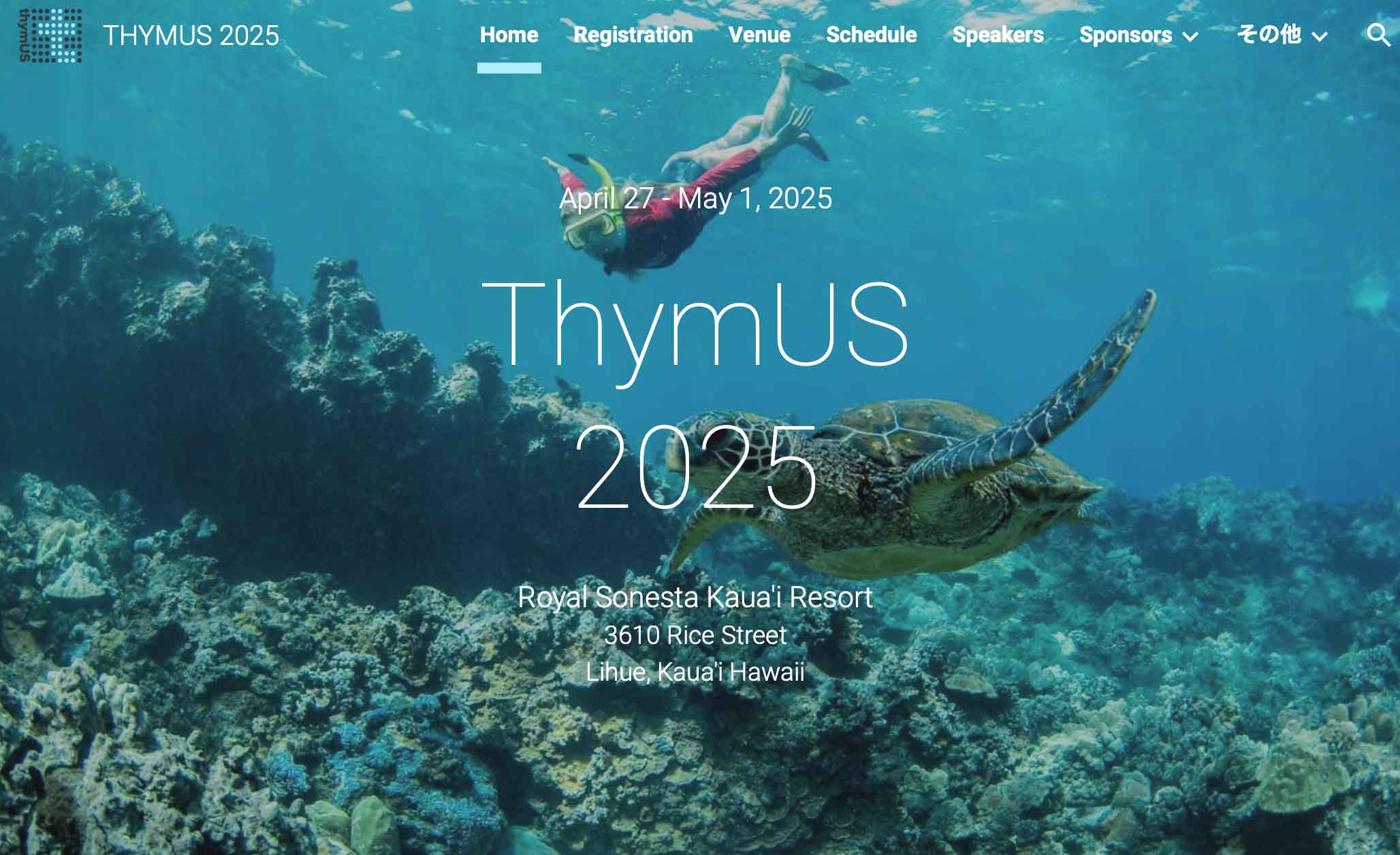 |
この学会は胸腺あるいはT細胞を研究対象にする国際学術集会で、参加者は200人くらい。同じような主旨の4つの集会が、ローテーションで開催されている。4つの学術集会とは、KTCC(京都T細胞カンファレンス)(日本)、ThymOz(オーストラリア)、ThymEU(ヨーロッパ)、ThymUS(アメリカ)。ThymUSは、2001年に第1回が開催された。これまでのところ、マイアミ、プエリトリコ、ハワイなど、いろいろな場所で開催されてきた。前回はハワイのマウイ島で開催される予定であったが、もろにコロナの影響を受け、少人数の若手を中心としたオンライン開催になってしまっていた(2020年11月3日の記事参照)。今回はハワイのカウアイ島で開催された。 |
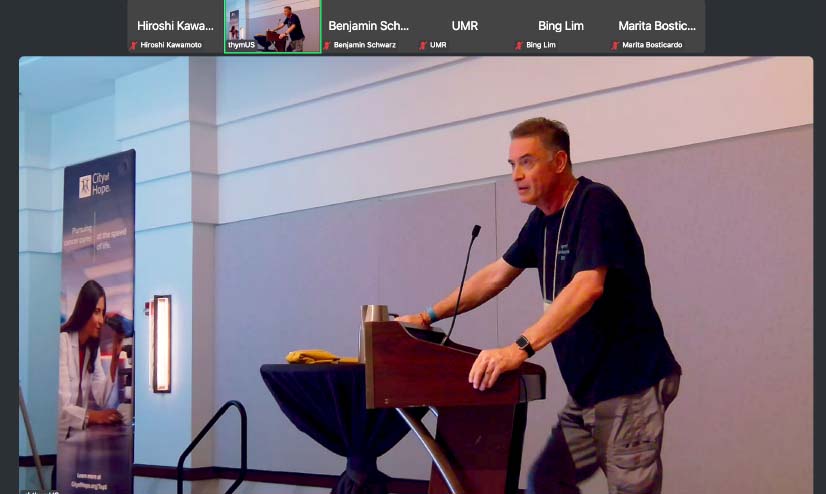 |
私は現地参加する予定で、演題も出し、登録も済ませていたが、ある用務が期間中に発生してしまい、参加を断念した。どうやらトランプ政権のせいでアメリカからの旅費が工面できずに現地参加できない人が複数人出たようで、オンラインでの参加も可能になった。現地での朝8時半からのトークは日本では午前3時半からという事になるので、さすがにフル参加はできなかったが、聴きたい話はおおむね聴けたので、ありがたかった。左の写真はJanko Nikolich-Tugich (University of Arizona)。免疫老化の研究者で、2001年の第1回ThymUSの開設者二人のうちの一人。 |
2025年4月21日(月)
ILASセミナー
 |
京大では1回生向けにILASセミナーという少人数相手のゼミをやっている。4-7月の火曜日5限目(16:45-18:15)、計15回。医生研はそんなILASセミナーを3本担当しており、私は今年はそのうちの一つの中の「医生物学の最前線」というセミナーの、最初の5回分を受け持っている。この日はその第3回で、河本研で進めている再生T細胞療法について講義をした後、河本ラボや研究所のES細胞施設(左の写真)、P3実験施設などを見学。その後、優生思想に関するdiscussionを行った。普段は生徒は6人であるが、この日は1名が欠席だった。 |
2025年4月21日(月)
水野篤先生来訪
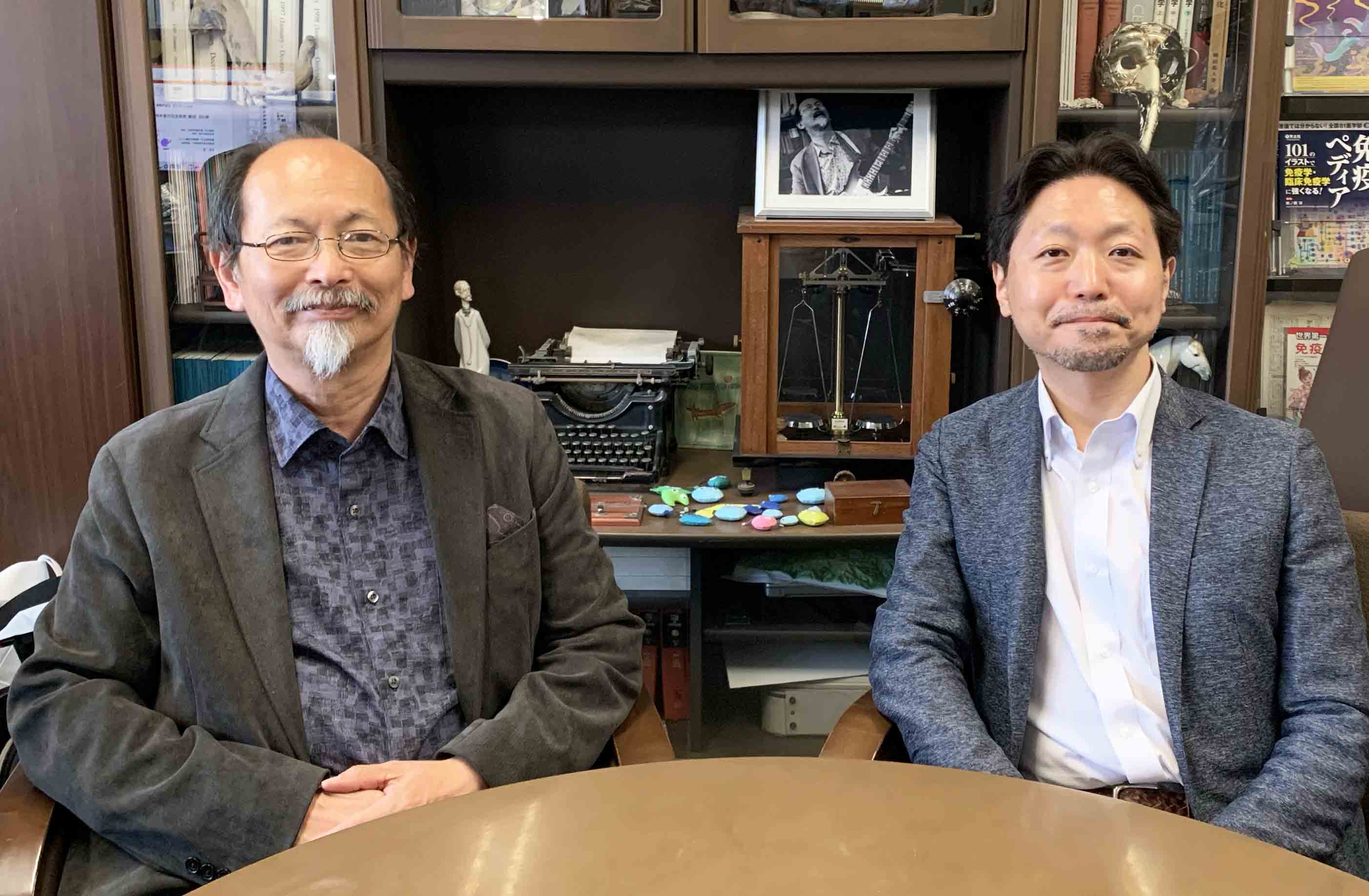 |
水野篤先生(聖路加国際病院循環器内科・QIセンター医療の質管理室室長)は2005年京大医学部卒。少し前に開催された芝蘭会東京支部総会での講演で、私の後の演者であったが、私が少し時間を超過したため、水野先生の講演時間が短くなってしまい、申し訳なかった(2025年2月1日の記事参照)。その話をしっかり聴きたいと思って、「京大に来られることがあったら是非お立ち寄り頂いて話の続きを聴かせて下さい」と言っていたら、この日、それが実現した。 |
 |
東京支部総会での講演タイトルは「医療現場における実装科学と行動経済学」だったので、それを踏襲しつつ、わかりやすい話にしていただいた。話の内容自体は容易ではなかったが、語り口が上手だったので、1時間があっという間に思えた。選択肢からどれかを選ぶ際、人の持つ思考過程にパターンがあって、誘導も可能、というような話だった。あまり聴いたことがないような話ばかりで、とても面白かった。 |
 |
セミナー終了後、近くの「くうかい」へ。店内は満席だったので、店の前の屋外テーブルで会食。セミナーの続きの質疑応答が飛び交い、楽しかった。 |
2025年4月21日(月)
藤田医科大学で講義
 |
5年前から藤田医科大学で基礎免疫学(医学部2回生、4-5月の月曜日の午前中70分x2コマを5回、計10コマ)を担当している。この日は、第6回「免疫細胞の分化と免疫組織」の講義の中で、基礎研究者への道のりの話を絡めつつ、「学会は議論を闘わせる場」という話になった際に、Negative Selectionのセカンドアルバムを紹介し、「逆襲の助教」のミュージックビデオ(2022年10月24日の記事参照)をフルで観てもらった。 「逆襲の助教」ミュージックビデオ(YouTube) |
 |
この時期、藤田医科大学では、ツツジが美しい。右側に見えている丸屋根ドームがある建物は「プレアデスチャペル」という建物で、かつては集会場であったらしいが、現在は売店として機能している。 |
2025年4月19日(土)
医生研進学説明会
 |
表記の会が医生研1号館会議室で開催された。 |
 |
「大学院生として医生研に来たい」という人向けの説明会。私が10分ほど研究所の概要を説明した後、各研究室が5分ずつラボの紹介をした。その後、各自がお目当てのラボを見学。2箇所まで見て周れる事になっている。 |
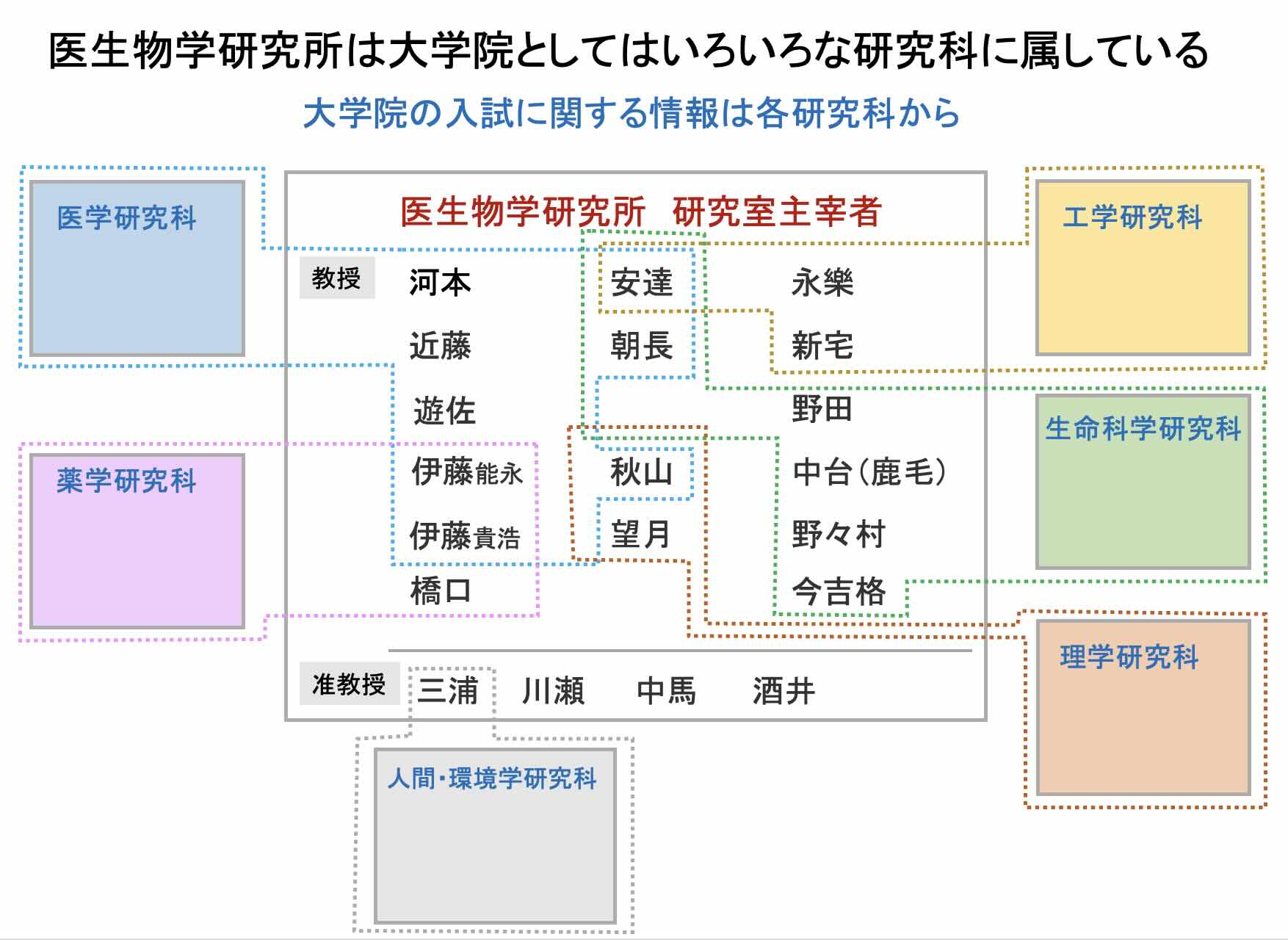 |
大学院という仕組みは医学研究科や生命科学研究科といった「研究科」が有しており、医生研の教授は左図のようにいずれかの研究科に属している。医生研自体は独自の研究科を有している訳ではないので、医生研の中の「この研究室に入りたい」と思ったら、そのための大学院の試験は、その研究室が属している研究科で受けていたく必要がある。以下、医生研としての大学院生募集のページにリンクを貼っておく。 医生研の大学院生募集のページ: |
2025年4月18日(金)
新所員講習会
 |
毎年4月の第3週の金曜日に、その年度から医生研に来るようになった人達70-80人を対象に、研究費の適正な使用、研究不正の防止、安全、衛生、情報セキュリティー、動物実験などについて、3時間くらいの講習会が開催されている。会場は研究所の近くの京都教育文化センターの3階。 |
 |
講習会終了後、同センターの一階で、新所員歓迎会。軽食と飲み物が用意されている。既存の所員も、学生を含め多数参加し、盛会だった。 |
 |
歓迎会終了後、有志で教授室にて歓談。向かって左から、この日たまたま京大河本研に実験をしに来ていた川瀬孝和先生(藤田医科大学河本研准教授)、小原乃也(だいや)先生、中馬新一郎先生、小西理予先生。 |
2025年4月15日(火)
「ドナルド・マクドナルドハウス京都」建設予定地
 |
クリエーション・コア京都御車にあるリバーセルの事務所で用務を済ませた後、賀茂大橋(今出川通が鴨川を渡る橋)を歩いた。この橋の西詰すぐの南側にはずっと廃寺があって、一等地なのに勿体ないなと思っていたが、その廃寺が取り壊されて、跡地にドナルド・マクドナルドハウスという病気の子供とその家族のための宿泊施設が建つらしい。世界中に400近くの施設があるとのこと。日本でもすでに12施設あるようだ。 |
 |
左の完成予想図は、京都府のHPより拝借。京都府立医科大学附属病院と京都大学医学部附属病院の共同利用施設という設定で、2026年秋に開設の予定とのこと。 「ドナルド・マクドナルドハウス京都」整備応援事業HP: |
 |
左の写真は敷地内から東北の方向を望んだもので、開設募金委員会のHPから拝借。比叡山、大文字山、鴨川デルタなどが見渡せる、中々の絶景だ。 「ドナルド・マクドナルドハウス京都」開設募金委員会HP: |
 |
この日、橋の上から望んだ大文字山。雨の後で空気が澄んでいて、早春の樹々やヤマザクラがよく見えた。 |
2025年4月10日(木)
長浜バイオ大学で講義
 |
例年、この時期には長浜バイオ大学2回生の免疫学講義(90分)を、1コマだけ受け持っている。「総論」を担当しているので、通常は第1回を務めているが、今年はスケジュールの関係で、第2回を担当した。この日、校舎の前のサクラが、まだ見頃だった。一昨年は4月10日だったが、すでにサクラは終わっていた(2023年4月10日の記事参照)。 |
 |
長浜バイオ大学から5分ほど歩くと湖畔に出られる。講義後、帰りの電車までの時間に、いつものように湖畔を少し散策。ここでも満開のサクラが見られた。 |
2025年4月13日(日)
万博開幕!京都新聞でリバーセルの展示が紹介された
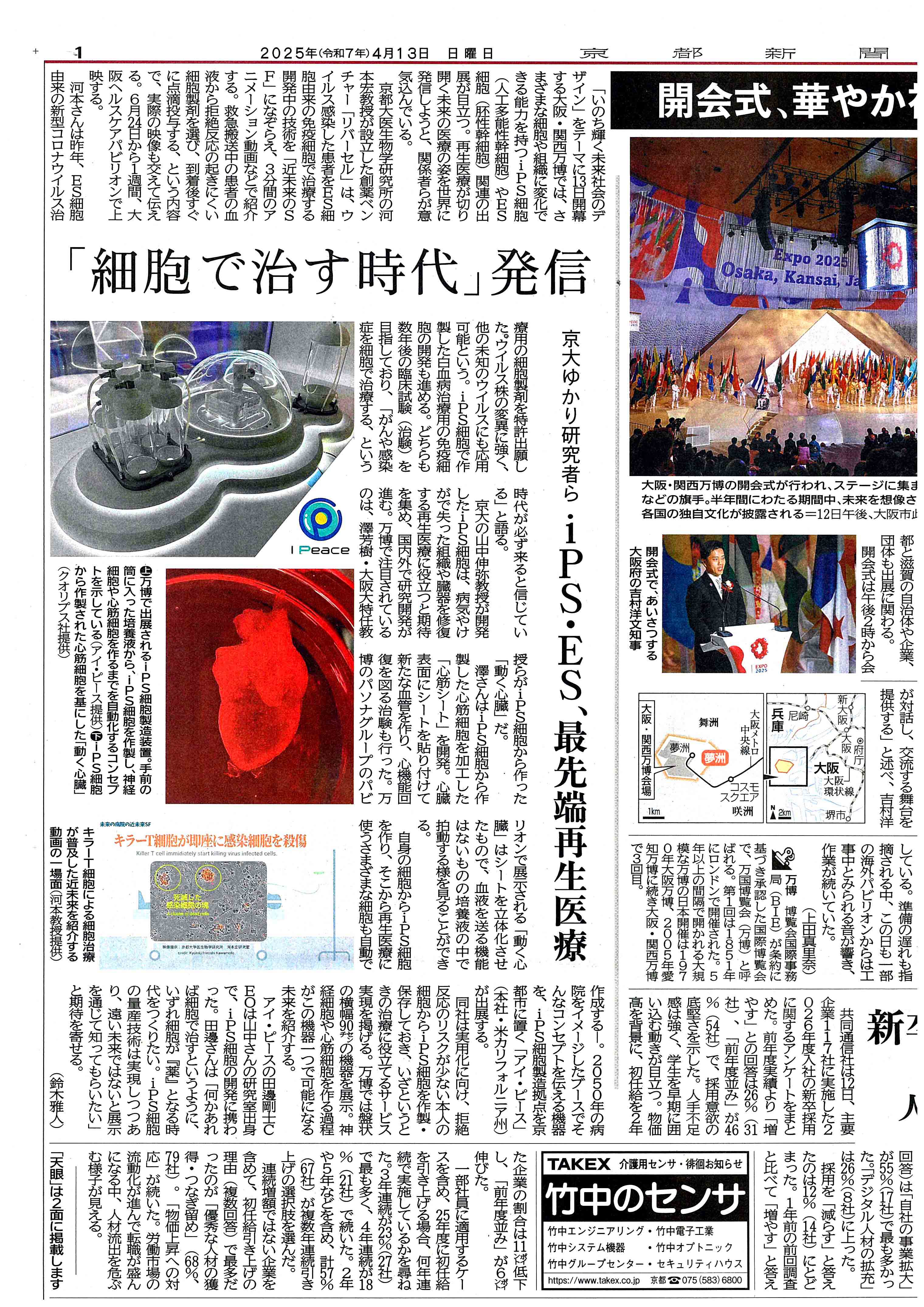 |
以前に少し書いたが、リバーセルは6月24日から30日までの1週間、万博のヘルスケアパビリオンに出展することになっている(2025年4月6日の記事参照)。その展示に関して、開幕日に京都新聞の朝刊の一面記事で紹介いただけた。 |
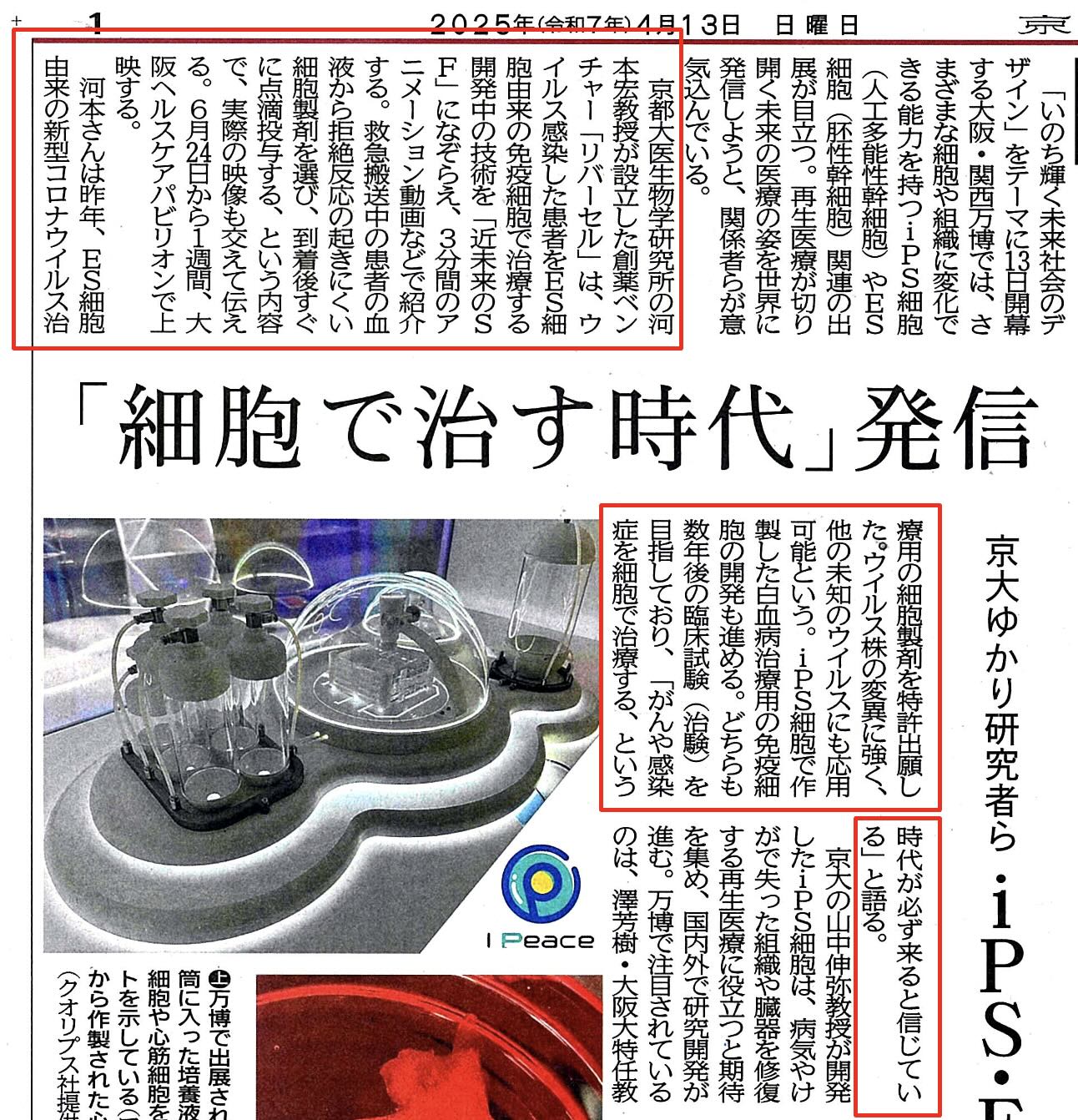 |
紹介記事の部分のアップ。河本研としては白血病を対象にした臨床試験に向けての準備に主に取り組んでいるが、今回の万博では、それに続いて進めているウイルス感染症の治療法の開発に焦点を当てて紹介することにした。 |
2025年4月13日(日)
探究学舎のイベント「京都大学 医生物学研究所ツアー」が開催された
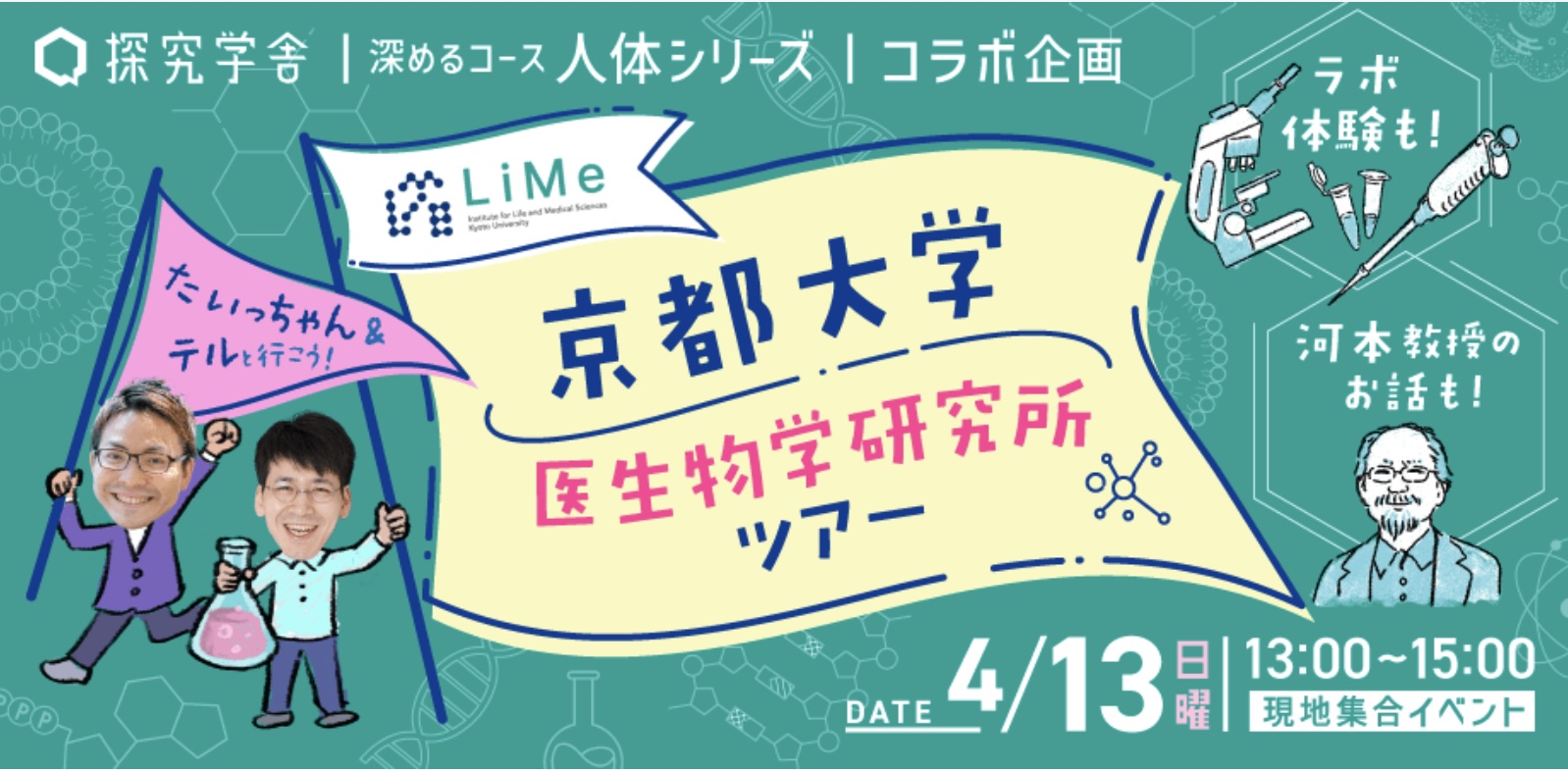 |
「探究学舎」は、受験勉強のための塾ではなく、子供達に学ぶことの楽しさを教えるという方針の私塾。全国の塾生にオンラインでのライブ授業を行なっている。昨年12月にそのうちの一回に取材協力し(2024年12月12日の記事参照)、同じ月にその取材内容も含めたオンライン事業も行われた(2024年12月21日の記事参照)。今回は、そのシリーズの授業の延長線上にあるイベントして、医生研の見学ツアーを企画された。科学コミュニケーション活動の一つとして、協力した。 探究学舎HP: |
 |
ツアーは2ラウンドあり、参加者はそれぞれ生徒20名と、その保護者の方。生徒は小学校3-4年が中心。関西だけでなく、遠方からの参加者も多かった。私の講義が1時間、研究所見学(ES細胞製造施設、P3実験施設、細胞児童培養装置、河本研実験室など)30分、実習30分という構成。 |
 |
実習の様子。 |
 |
永野君のアイデアで、ピペットマンを使って1μl、10 μl 、100 μl 、1mlを測り取ってみようという実習。私たちにとっては簡単な操作であるが、生徒さん達は手が小さいこともあって、結構苦労していた。 |
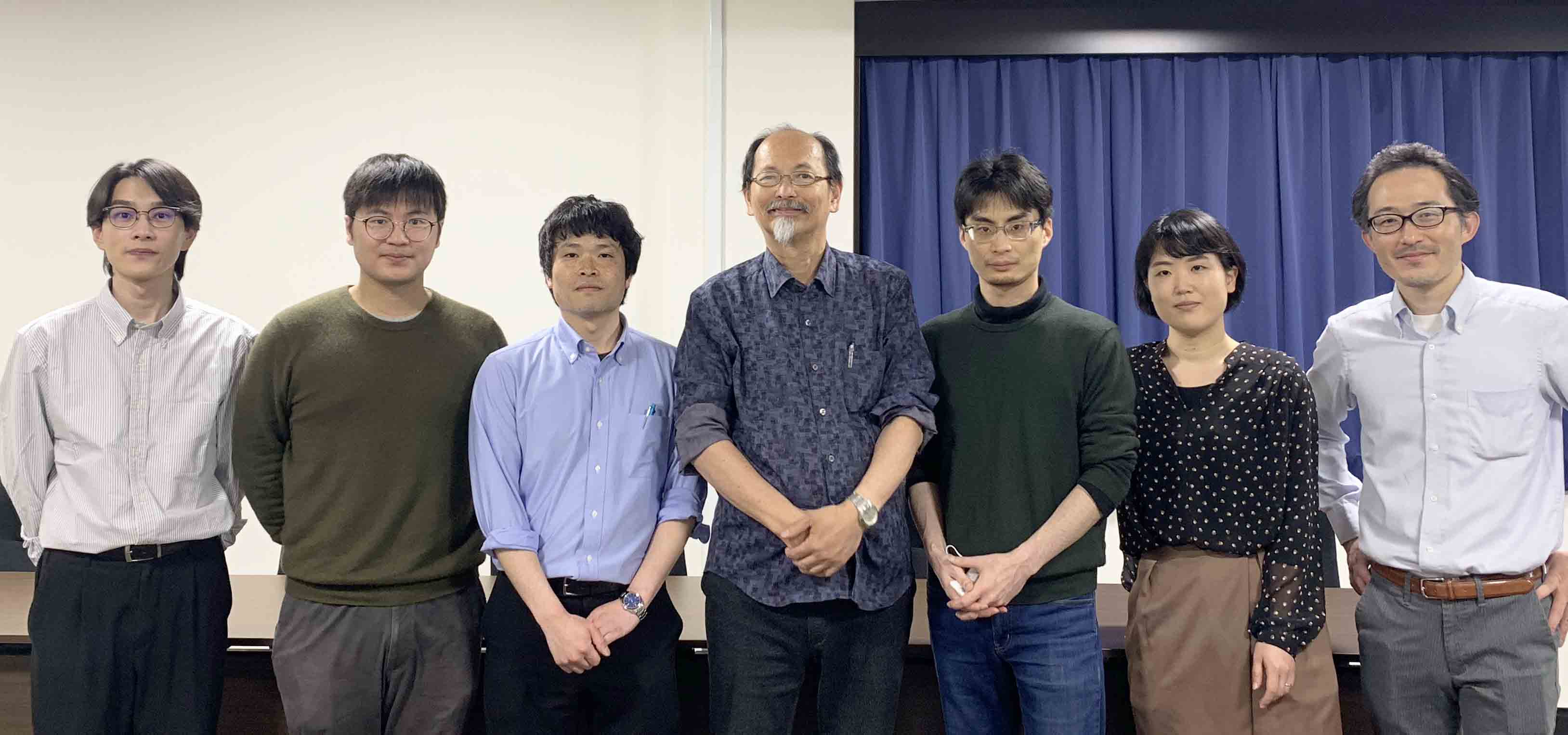 |
今回のイベントに協力してくれた河本研メンバー。「希望者にだけプラナリアの配布を」と思って呼びかけたところ、ほぼ全参加者が希望したので、その対応が大変だった。お疲れ様でした! |
 |
イベント終了後、探究学舎のスタッフの方達と、教授室で軽く打ち上げ&反省会。おおむね首尾よく進められ、参加者にも喜んでいただけたようだった。 |
2025年4月11日(金)
オヤジの会
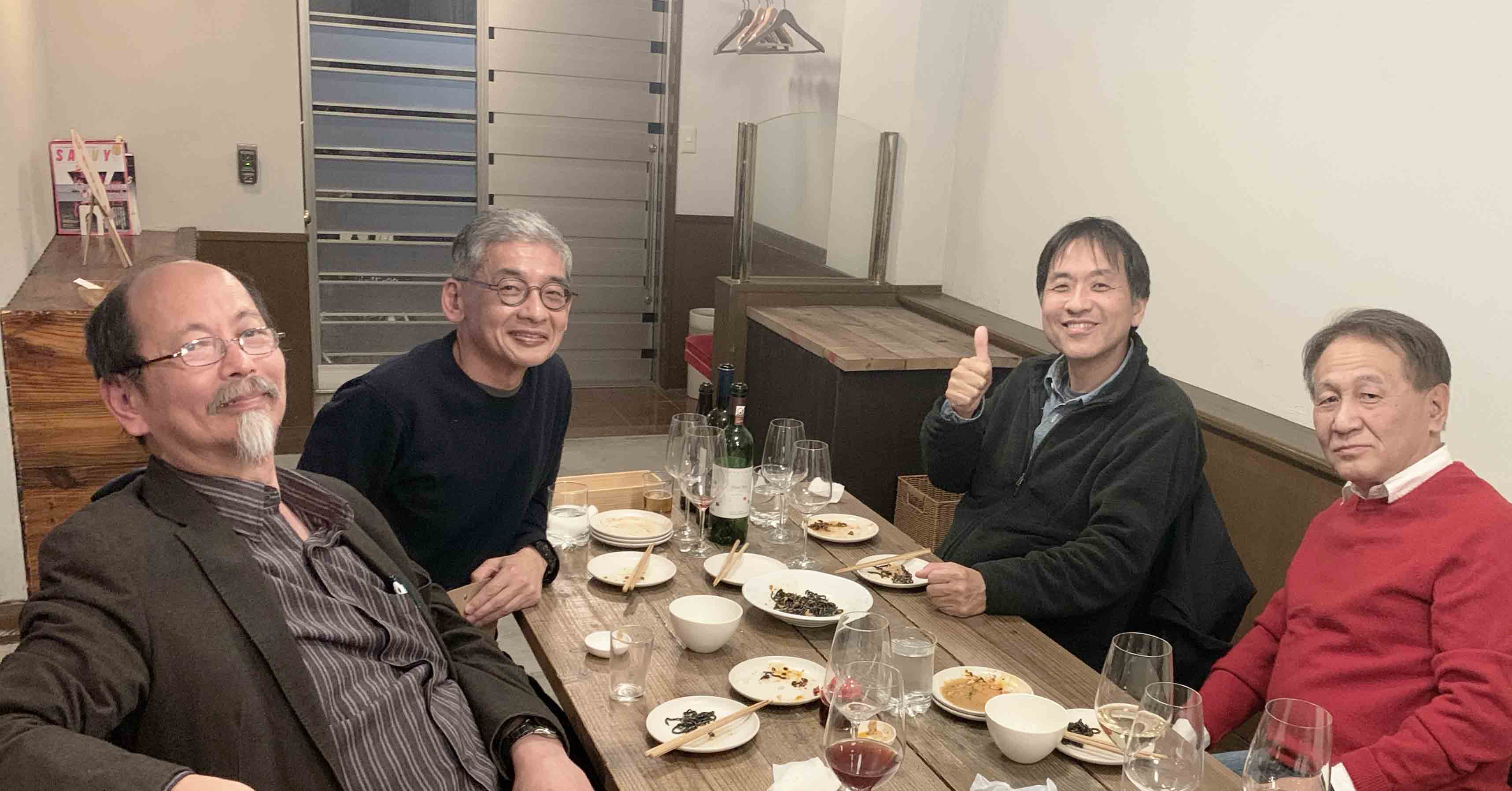 |
表記の会であるが、前回は昨年5月だった(2024年5月8日の記事参照)から、久々の開催。少し前の話になるが、江藤先生が率いるグループがNEDOの大きな予算(5年で総額50億円!)を獲得された件についての、祝賀会も兼ねた。色々な話が飛び交い、楽しかった。お店は七条のシャオシャオ。向かって右から小川誠司先生、藤田恭之先生、江藤浩之先生、私。 「経済安全保障重要技術育成プログラム/有事に備えた止血製剤製造技術の開発・実証」に係る実施体制の決定について(2024年9月11日): |
2025年4月10日(木)
京大医学部3回生に講義
 |
京大医学部3回生の免疫学の講義を、この日と翌日、合わせて4コマ(90分/コマ)受け持った。講義の中で、ネガティブセレクションの曲のうち、講義内容に関係した曲として「VDJ-recombined」を視聴してもらった。 |
2025年4月9日(水)
Cornelis Murre先生のセミナー
 |
Cornelis Murre先生(UCSD)は縣先生(滋賀医大)、伊川先生(東京理科大)、宮崎先生(京大)の留学先での師匠。その関係で今回は宮崎先生がホスト役を務めた。 |
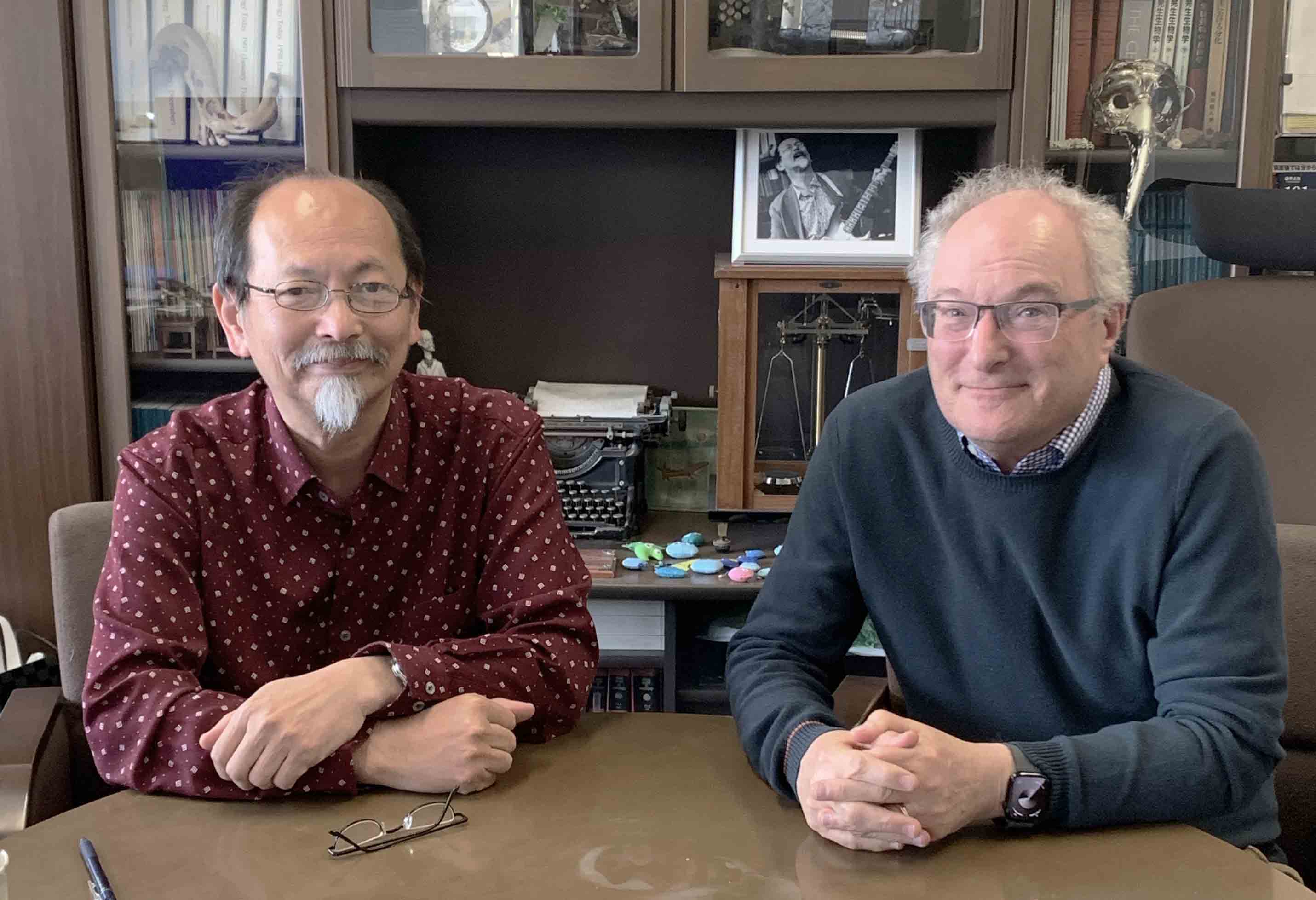 |
午後イチに1時間半ほどdiscussion。長畑君の最近の研究内容について紹介したりした。 |
 |
夕刻、セミナーが開催された。 |
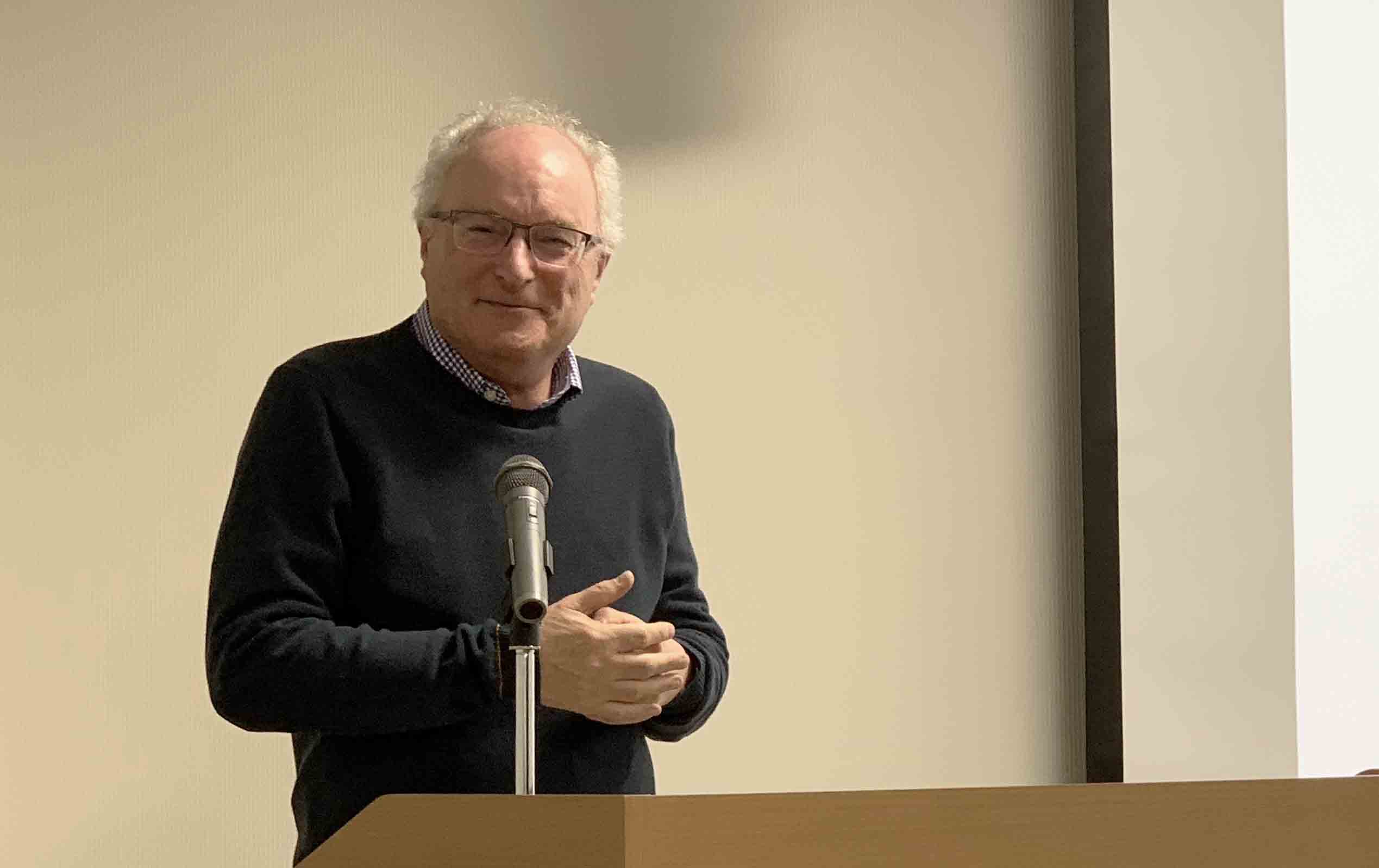 |
セミナーでは、昨年Natureに掲載された好中球の分葉核が形成されるメカニズムに関する話を聴けた(Nature. 2024 Mar; 627(8002):196-203.)。分葉化に伴ってゲノムのループ構造がダイナミックに変化し、それに応じて分化や機能発揮に必要な遺伝子が発現するようになるという話。とても面白かった。 |
 |
セミナー後、先斗町のかっぱ寿司で会食。向かって左から糸井まなみ先生(明治国際医療大学)、宮﨑先生、私、縣保年先生(滋賀医大)、Murre先生、日高礼子さん(河本研D1:宮﨑先生が指導)。トランプ政権下のアメリカのアカデミア界隈の事情などが聴けて、面白かった。 |
2025年4月8日(火)
高野川のサクラ
 |
高野川沿いのサクラは、医生研付近の鴨川沿いのサクラに比べると北に位置する分、2-3日遅れて咲く。この日、満開だった。写真は出町柳の橋から上流側を望んだ景色。今年はサクラはやや遅いという印象であるが、昨年は同じような写真を4月11日に撮れているので、昨年と比べると同じくらいという感じだ。年によっては、3月のうちに満開になることもあったりする(2021年3月29日の記事参照)。 |
2025年4月7日(月)
藤田医大河本研メンバーで会食
 |
このところ毎年4-5月には藤田医科大学で基礎免疫学の講義を10コマ(70分/コマ、2コマx5日)担当している。この日は午前中に最初の2コマの講義を行った。夕食は、金山駅近くの肴屋八兵衛で、藤田医大の河本研メンバーと久々の会食。次の機会にはカラオケに行くという話になった。 |
2025年4月6日(日)
大阪・関西万博テストランに行ってきた
 |
以前に少し書いたが、リバーセルは6月24日から30日までの1週間、万博に出展することになっている(2024年12月14日の記事参照、2024年7月23日の記事参照)。その関係で、リバーセルにテストランの招待状2枚(正確にはテストラン参加登録用IDが二人分)送られてきた。展示ブースのデザインや展示動画の制作を進めてきたのは私と、リバーセルの大久保、畑中であるが、今回は河本、大久保の二人で行くことになった。大阪メトロ中央線の夢洲(ゆめしま)駅で下車。写真は駅から地上に出るところ。 |
 |
入場ゲート前の広場。開場から少し経った10時半頃だったからか、それほどは混んでいなかった。 |
 |
空港の保安検査と同じような感じで手荷物はX線検査で調べられる。ここまでする必要はあるのだろうか。これのせいで入場に際して大混雑が発生しているようだ。なお、私達の場合は、30分弱で入場できた。 |
 |
東ゲート入ってすぐの広場。広い。大屋根リングが見え、万博会場に来た実感が湧く。 |
 |
東ゲート入ってから、大屋根リングの少し手前右側に「ヘルスケアパビリオン」がある。ここの下見が今回の主な仕事だ。 |
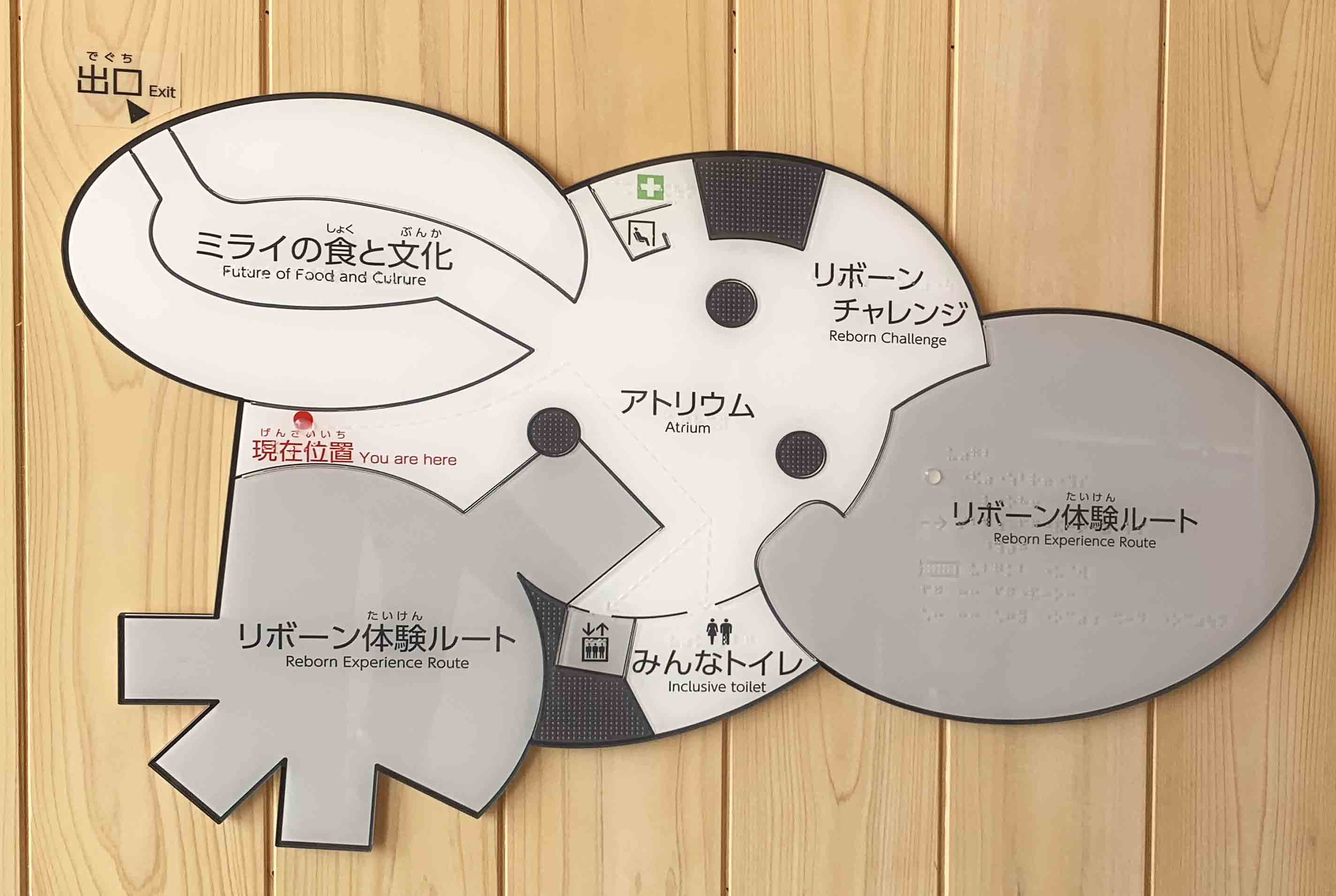 |
ヘルスケアパビリオンの案内図。おそらく「リボーンチャレンジ」というエリアに展示することになると思われる。 |
 |
中心のアトリウムは吹き抜けになっている。 |
 |
アトリウムにはiPS細胞を使った再生医療についての展示があった。CiRAや、iPSを用いた事業を進めている会社が集まって進めている「p.s.i love you」という集まりが万博に参戦している気配がなかったので、ちょっと心配していたが、大阪産業局はちゃんと再生医療をアピールする展示を作っていたということのようだ。 |
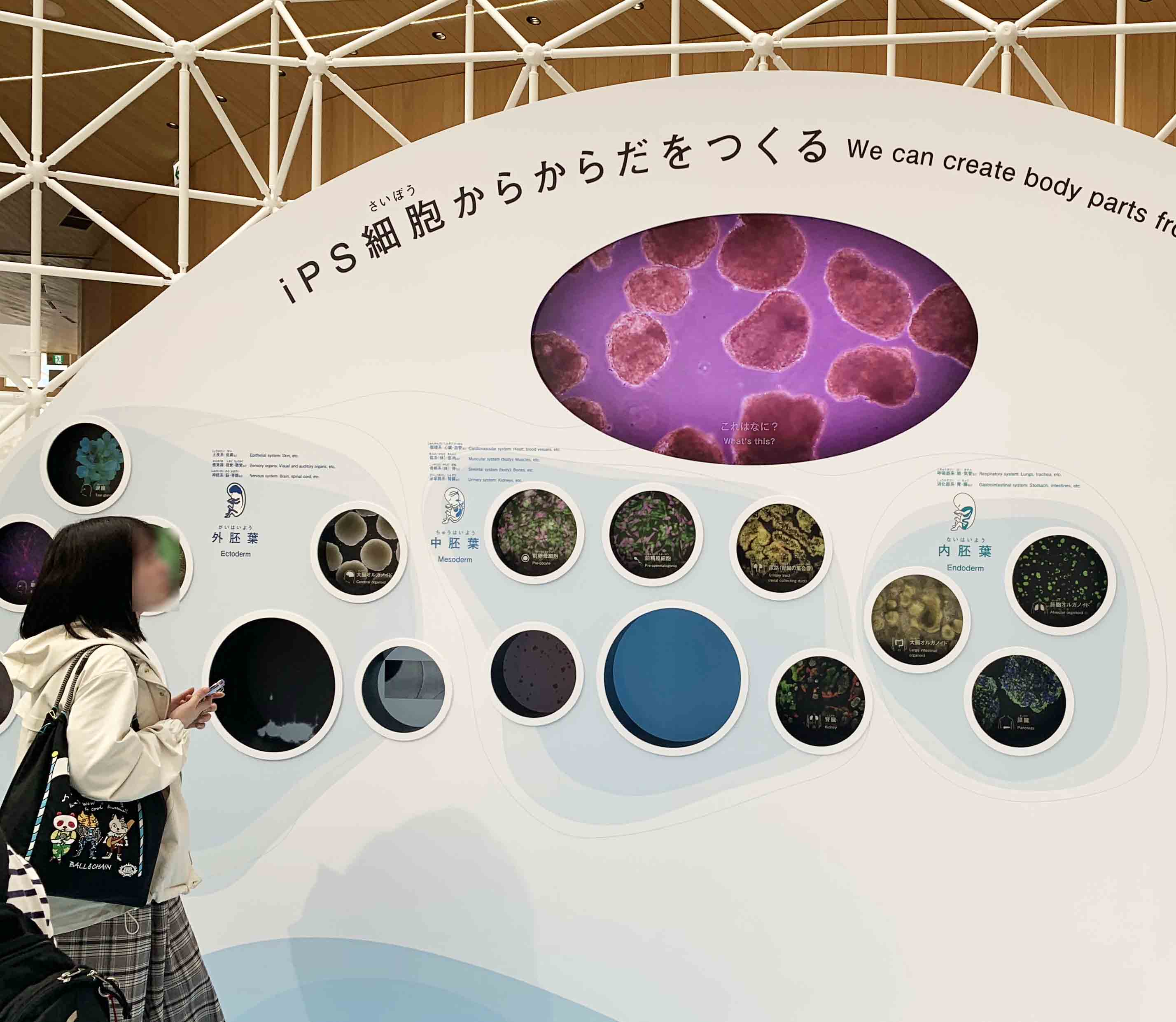 |
ただ、各プロジェクトごとの具体的な進捗状況を示すような展示ではなく、generalな情報を提示しているという感じだった。 |
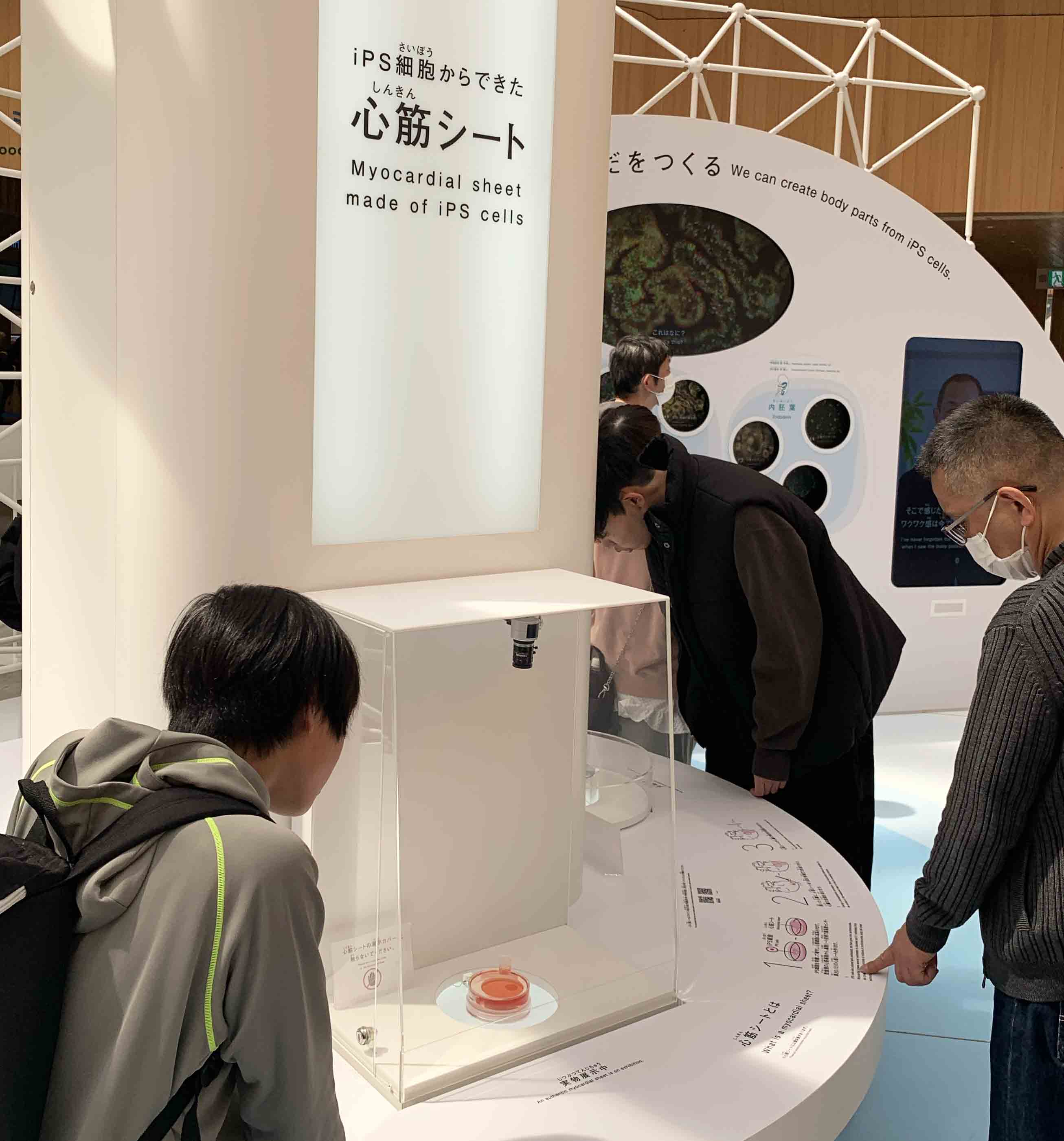 |
そんな中、iPS細胞由来の心筋シートの展示はあった。 |
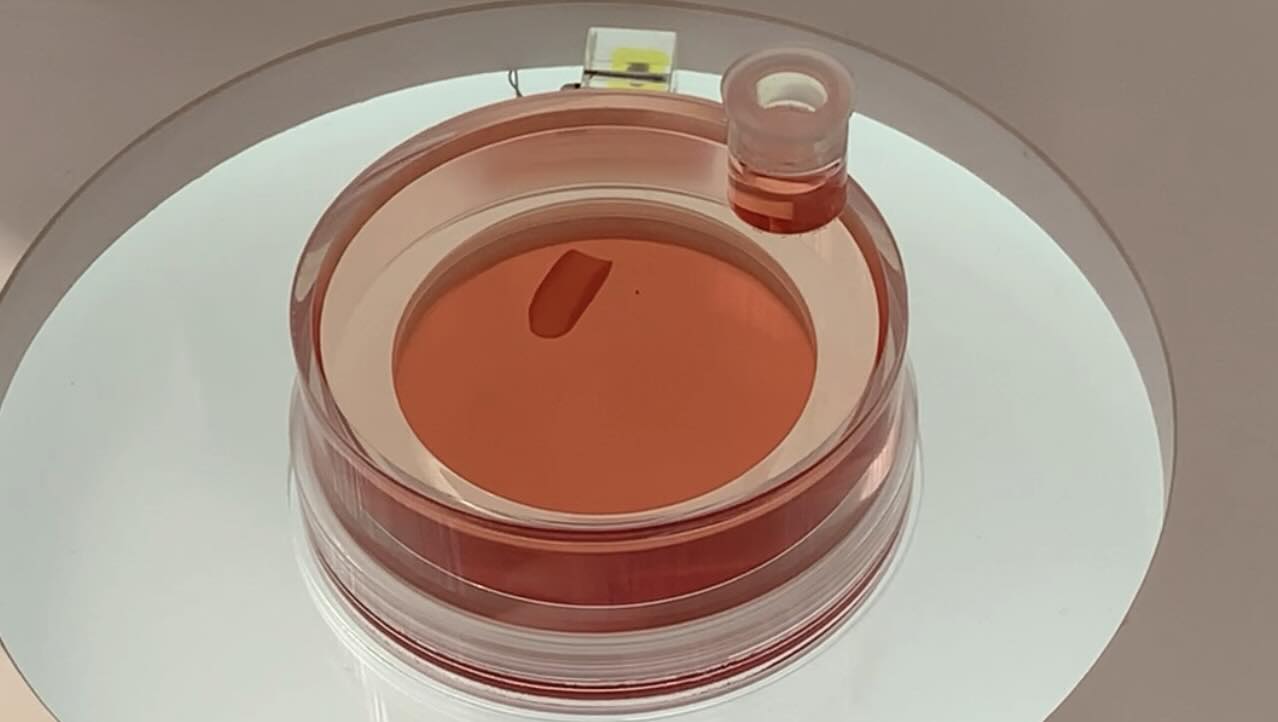 |
ディッシュの中で、3cmくらいの丸いシートが、時折くるっと筒状になるような形で拍動していた。パソナ館のiPS心臓(後述)とちょっと被っている感があった。 |
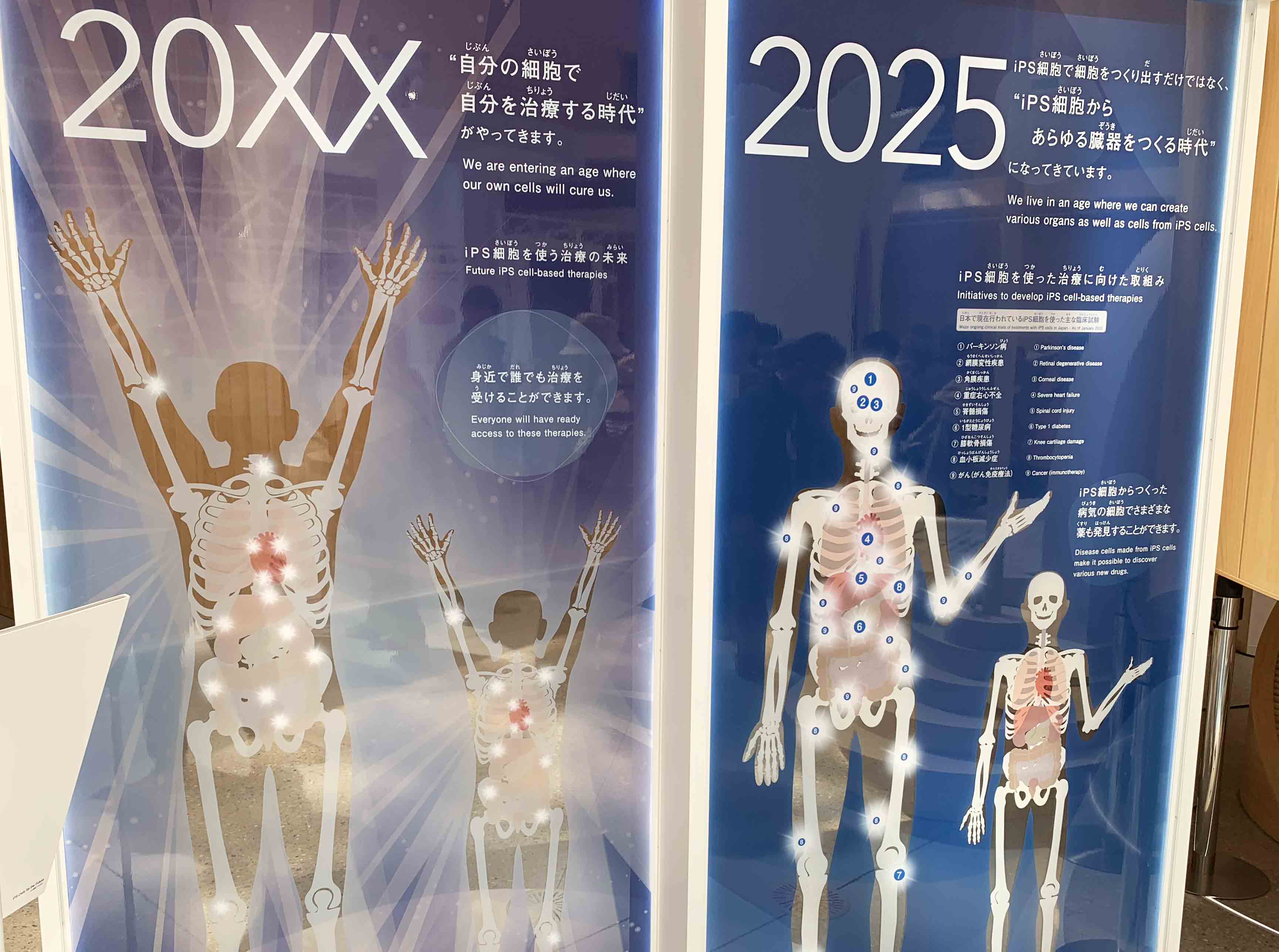 |
再生医療において現在進められている各疾患への臨床試験は、右側のパネルにそれぞれ小さく書かれているだけだったので、もう少しアピールしてもいいかと思った。左側のパネルは、「自分のiPS細胞を使って体を治す時代が来る」ということで、CiRA財団が進めている「my iPS細胞」という事業をアピールしているようだった。 |
 |
ヘルスケアパビリオンの「未来の食と文化の」コーナーには、何軒か食べ物のテイクアウトの店があった。そのうち一軒で、「ランチボックス」を購入し、早めの昼食。スムージーと合わせて2600円。確かに、ちょっと高いように思う。 |
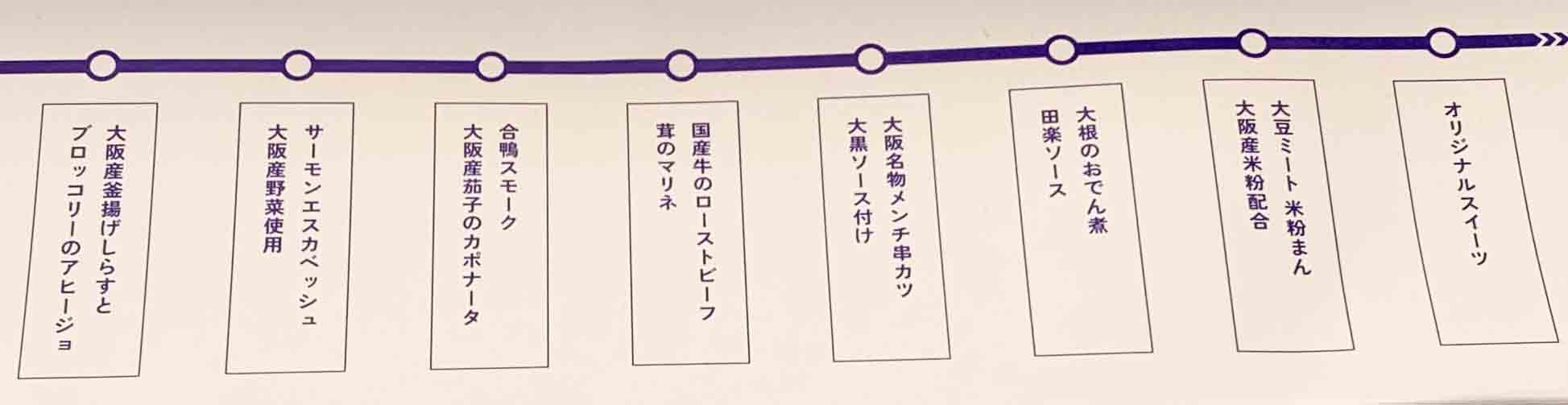 |
とはいえ、フタに書かれていた能書きを見ると、まあこれくらいしてもいいかと思えた。 |
 |
この日は5万人とのことだったので、それほど混んでいた訳ではなく、座るところを探すのにはそう苦労しなかった。 |
 |
大屋根リングの下。テレビで見ていた限りでは特にどうということはなかったが、現物を見ると、スケール感に圧倒され、とても印象的だった。 |
 |
所々にエスカレーターが設置されている。 |
 |
エスカレーターで上に登ると、さらにスケール感が増し、また南港や神戸を見渡せて、中々素晴らしい光景だった。ただ、4月だから気持ちが良かったが、夏は暑いだろうなとも思った。 |
 |
中国館とクェート館。1970年の万博では各パビリオンの形状のユニークさがとてもインパクトがあったが、その後の筑波博、花博、愛・地球博などでは球体とか直方体の延長線のものが多く、あまり感心しなかった。そういう点で言うと、今回の万博のパビリオンは、結構良いものが多い気がする。 |
 |
福岡伸一プロデュースの「いのち動的平衡化館」。当日予約で入れた。 |
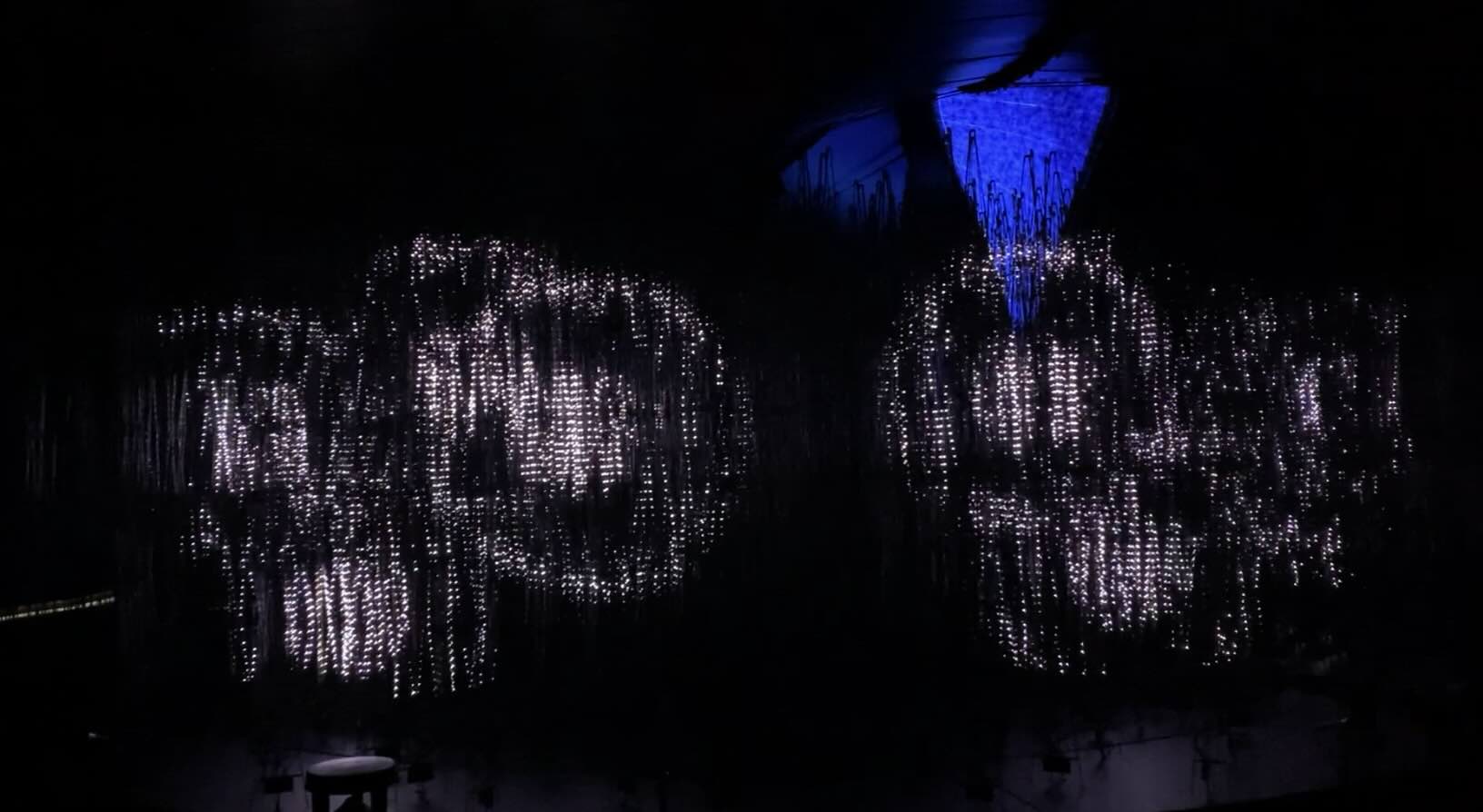 |
背丈くらいの棒にLEDライトが多数ついていて、生命の発生の歴史が立体動画で表される。私は解像度が荒いのが気になったが、人によっては幻想的と感じるかもしれない。 |
 |
落合陽一プロデュースの「null2(ヌルヌル)館」。中々奇抜な外装だ。ここはこの日は予約が一杯で入れなかった。 |
 |
ガンダムの巨大な模型。立てば17mとのことで、作中での設定サイズらしい。意外に小さい。 |
 |
15時ごろ、リングの外、北側のフードコートでオヤツタイム。席料が50分500円ということで、評判が悪いが、おじさん二人にとっては席料を払うよりも、立ち食いだとか、外のベンチまで食物を持っていく手間の方が嫌ということで、おじさん二人は着席。神座(かむくら)のラーメン(1200円)と煮卵(200円)で1400円。ネットで調べると神座のラーメンは700円であるようなので、2倍近い値段とは言える。ビールはここのフードコートでは900円。すでに歩き回って脱水状態であったので、各自二杯ずつ注文した。 |
 |
日本館。入れず。 |
 |
アラブ首長国連合館は入れた。林立する柱がかっこいい。 |
 |
海が入り込んでいるエリア(ウオータープラザ)の東側のフードコートを下見。ここはかけうどん780円、きつねうどん980円と、1000円以下で食事が取れ、割と良心的な価格だ。 |
 |
シンガポール館は少し並んだら入れそうだったので、入ってみた。 |
 |
ドーム状の天井一面に、ファンシーな動画が映写され、わりと良かった。 |
 |
西ゲート方面へ移動。写真は「EXPOアリーナ」という大きなイベント会場。 |
 |
17時頃だったが、この日の最後のイベントとして、「やぶさめ」をやっていて、疾走する馬の上から矢で的を射るところを見ることができた。子供の頃に近くの下鴨神社で見て以来だ。 |
 |
18時ごろ、西側のエリア内のフードコートで夕食。こちらはお昼に行ったフードコートと異なり、予約席の制度はなかったが、それでも席にはかなり余裕があった。名店「だるま」の串カツ、6本で1200円くらい。こちらはビールも安く、600円だった。 |
 |
エリアの西の端に行くと、夕日を拝むことができる。 |
 |
実はいのち動的平衡館に入った後に、予約システムにバグが生じていて、他のパビリオンに予約ができなくなっていた。しかし、夕食をとっていた頃に回復し、西のエリアにある「未来の都市館」を予約して訪問。内容は、まずまず、というところ。 |
 |
日も暮れてから、今回の万博の目玉の一つであるiPS心臓が見れるパソナ館を訪問。 |
 |
ブラックジャックとアトムが動画で登場。重症を負ったアトムを、未来の都市でブラックジャックが手術で治すという設定のアニメが流れ、手塚治虫ファンである大久保君や私からしたら、「よくこんな設定を虫プロあるいは遺族が許したな」という感はあった。しかもロボットにiPS心臓を移植するというトンデモ話。しかし、映像そのものは美しく、まあごちゃごちゃ言わずに楽しめばいいということであろう。 |
 |
iPS心臓。ピーマンくらいの大きさがあるかと思っていたが、ウメくらいだった。 |
 |
拍動というよりも、ピクピクと細動している感じであった。しかし、見た人は一様に「すごい!」という表情をしていた。やはり動くものはインパクトがある。 拍動するiPS心臓のビデオ: |
 |
海のエリアで、20:00から噴水とレーザーの、約25分間のショー。アオという主人公が、夜の虹を見に行くという話で、霧でできたスクリーンに動画が映写される。 |
 |
このショーは絶対オススメで、音、色、スケール感に圧倒される。予約すれば正面で観れるが、今回の私達のように予約無しでも見れる席からでも、十分楽しめた。 「アオと夜の虹のパレード」の編集動画(1分30秒): |
 |
炎も出る。 |
 |
帰路につきかける頃、ドローンによるショーも観られた。 |
 |
夜の万博は幻想的で美しいので、できるだけ遅くまでいるのが良いと思われる。この日は、21時半までという事であったが、かなり最後まで楽しんだ。 |
2025年4月5日(土)
ラン(リカステ)の花
 |
写真は「リカステ」という洋蘭の一種であるが、非常に強健で、窓際に置いているだけなのに、毎年花を咲かせてくれる。バルブ(根元の膨らんだ部分)があって、その上からシュッとした葉っぱが出ていて、根元から花茎が伸びて花が咲くという、ランのお手本のような草姿。良い。 |
2025年4月4日(金)
河本研お花見
 |
3月中旬〜下旬が寒かったためか、今年のサクラの開花はやや遅れ気味で、鴨川沿いのサクラは4月に入ってからようやく咲き始めた。この日はまだ8分咲き程度であったが、週明けはお昼に都合がつけられない日が続くので、この日のお昼休みに決行。ラボから徒歩2分くらいのところに絶好のお花見サイトがあるので、花見に行かない手はない。 |
 |
12時にラボの廊下に集合して、出発。食べ物と飲み物を持参し、堤防の緩やかな斜面の、桜の花の下、木陰になっている部分に、各自透明なビニール袋を1枚ずつ下に敷いて、昼食。ラボメンバーとの花見は実に6年ぶりだ(2019年4月5日の記事参照)。2023年5月にコロナは5類に格下げになったので、昨年の4月から堂々と花見ができたはずだが、昨年は諸事があって開催しそこなった。 |
 |
私達から見えている景色。 |
 |
鴨川の流れの向こう側にも、立派なサクラが咲いている。桜の奥に見えているのは「ザ・パークハウス 京都鴨川御所東」というマンションで、2015年に販売された際に7億円越えの物件が即日売れたと話題になった。少なくとも当時は西日本1の価格であったらしい。 |
2025年3月31日(月)
第53回JSI&第54回JSI:最終報告会&引き継ぎ会
 |
第53回免疫学会は大野博司先生(理研IMS)が集会長を務められて、2024年12月3日-5日に、長崎の出島メッセ長崎で開催された(2024年12月3日の記事参照)。この日、その収支決算の最終報告を含んだ反省会が集会長と組織員会のメンバー、免疫学会事務局と学会の運営を行なったエー・イー企画の人達によって開催された。そこに第54回の集会長である私と副会長の一人伊藤能永先生(京大)が参加して、収支の数字を聞きつつ次回の開催に繋げるという「引き継ぎ会」も兼ねていた。重要な議論が沢山できて、有意義だった。写真前列向かって左から長谷耕二先生(慶應大)、大野先生、私、後列左から川上純先生(長崎大)、金井隆典先生(慶應大)、新藏礼子先生(東大)。 |
 |
もう一つのテーブル。前列向かって左から伊藤先生、佐藤尚子先生(理研IMS)、後列左から下河満里子さん(エー・イー企画)、内田知孝さん(エー・イー企画)、石川瑞歩さん(免疫学会事務)、外山謙治さん(免疫学会事務)。 |
2025年3月30日(日)
ユキヤナギが満開
 |
ユキヤナギはサクラより少し早く咲き始める。 |
 |
以前は秋に刈り込まれていて、春の開花期にこういう風情はなかったが、2年くらい前から秋の刈り込みが行われなくなったようで、今年もいい感じだ。昨年の晩秋に紅葉がきれいだったので写真を載せた(2024年12月24日の記事参照)が、そのわずか3ヶ月後に満開。ユキヤナギはいい。 |
2025年3月28日(金)
「みのミュージック」で紹介された件を大久保君とプチ祝賀会
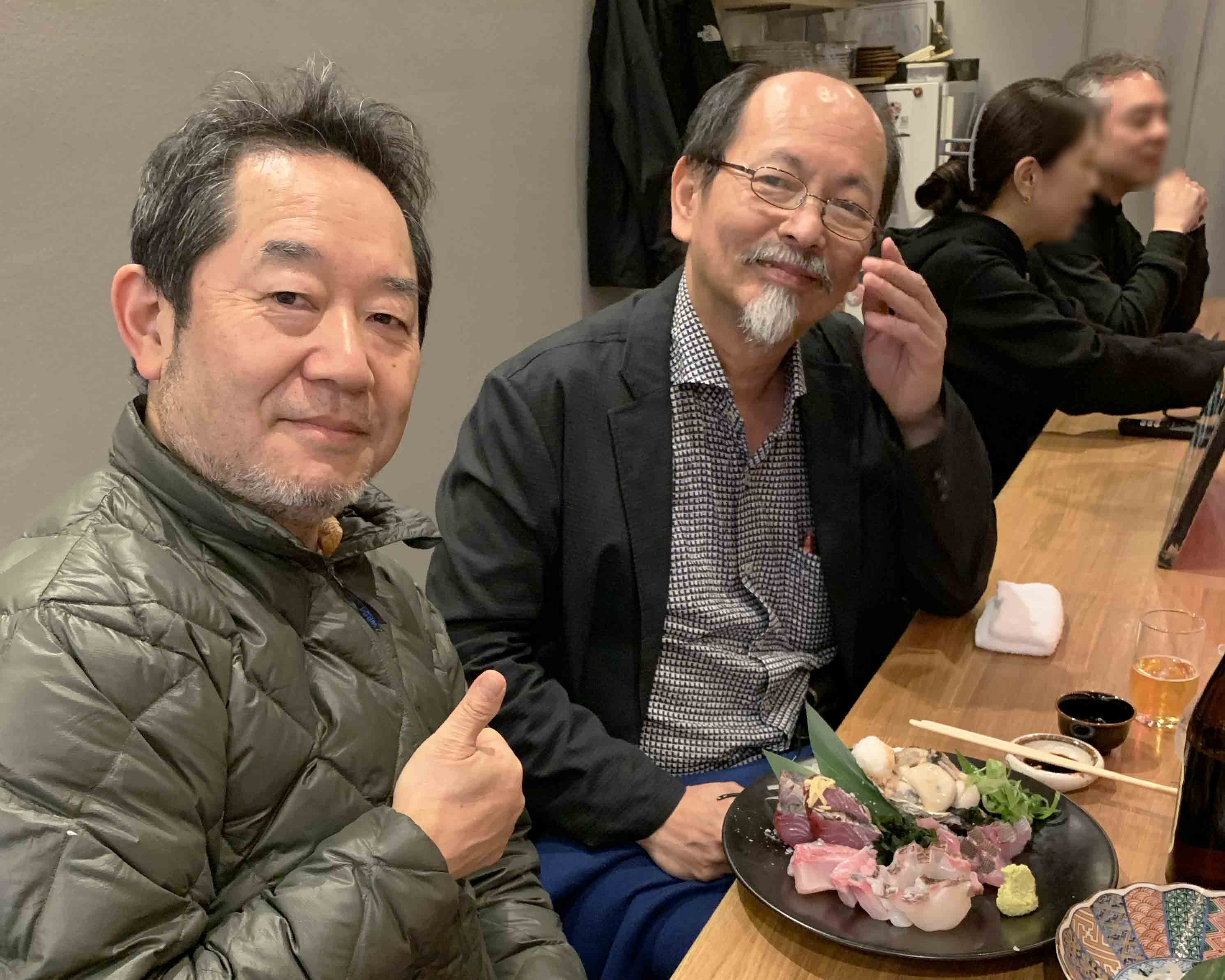 |
ちょっと前の記事に書いたが、3月26日にNegative Selectionが「みのミュージック」で取り上げてもらえた。大久保君の発案で、手紙などをつけてセカンドアルバムのCDを郵送したところ、応答があって、さらに追加資料やYouTubeに載せているミュージックビデオの原版ファイルを送ったりした。その結果、3本の動画をまるまる流していただけ、みのさんからはいい感じのコメントを沢山言っていただけた。この記事を書いている時点(4月14日)では再生回数が3万回に至った。YouTube視聴者のコメントも130件を超え、おおむねいいコメントが寄せられていて、ありがたい限りだ。 |
2025年3月27日(木)
Wilfredファミリー来訪
 |
Wilfred Germeraadはマーストリヒト大学の血液内科学の准教授。私とほぼ同い年であるが、桂研で彼が学位を取って卒業した後、入れ替わるように私が桂研に参加した。その後もずっと共同研究などで付き合いがあり、年に1回は行ったり来たりしてきた。理研時代には彼のラボの大学院生を1年くらい預かって、学位取得に寄与したこともある(2015年2月12日の記事参照)。コロナの直前にも一度会っている(2020年2月25日の記事参照)。それ以来だから、5年ぶりということになる。 |
 |
彼が属するグループはNK細胞を効率よく増やす方法を独自に開発しており、それを自家あるいは他家の細胞としてがん治療に使う戦略の開発をしている。 |
 |
Wilfredの次男がこの3月に東北大学で学位を取得したということで、今回は家族で来日したとのこと。教授室でWillfredファミリーと記念写真。 |
2025年3月26日(水)
「みのミュージック」でネガティブセレクションが紹介された
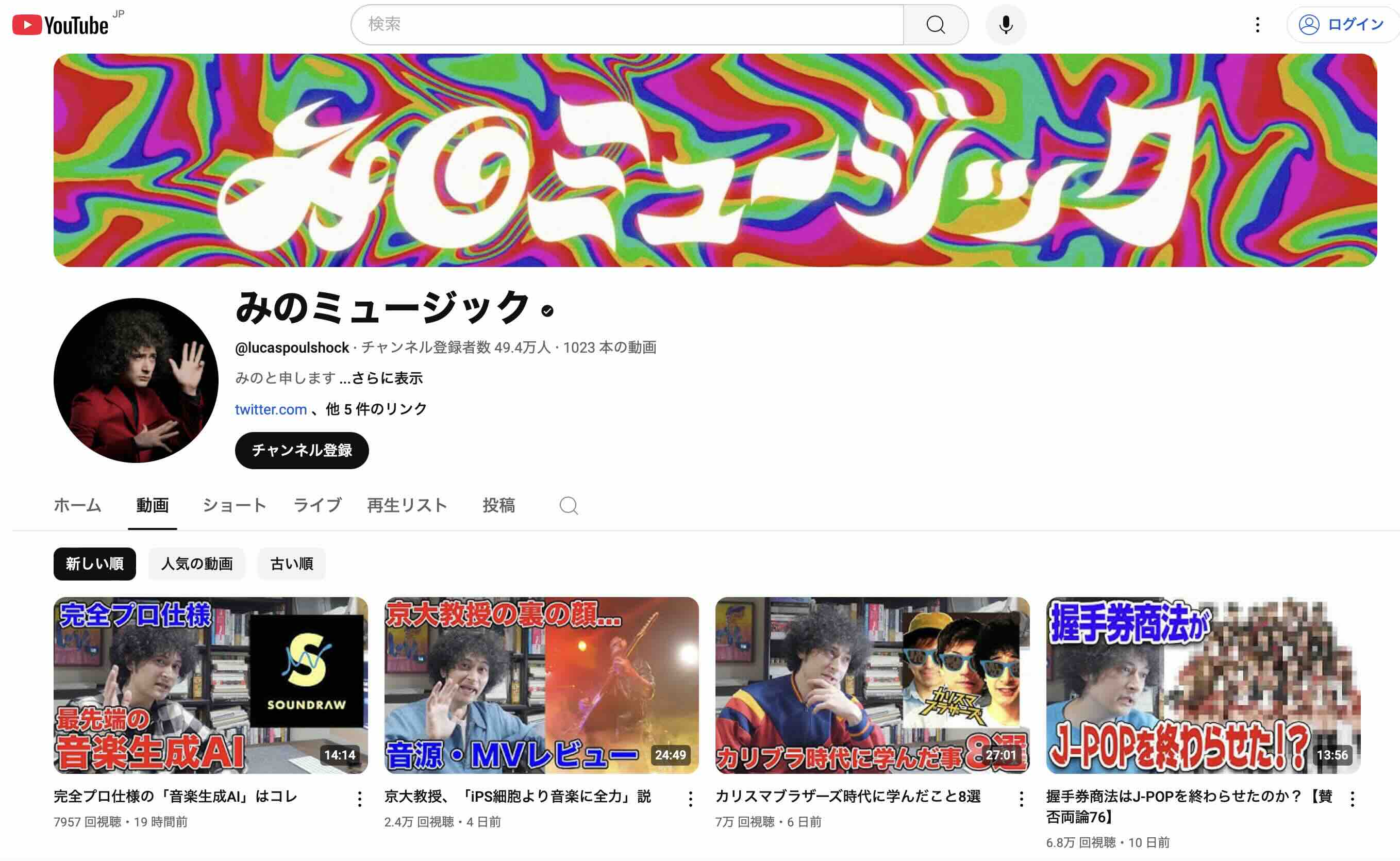 |
「みのミュージック」というYouTubeチャンネルがある。このチャンネルは「みの」という人がポピュラー音楽についての解説をしていて、チャンネル登録者は約50万人、毎回の紹介動画が数万回再生される、人気番組。みのさんは洋の東西今昔を問わずにポピュラー音楽を広範にしかも深く知っている人で、音楽の歴史の本も上梓している(下記リンク参照)。少し前に、大久保君のアイデアで、この「みのミュージック」に、ネガティブセレクションの紹介をお願いする手紙と、2枚のCD、手書きの楽譜の一部などを送った。すると、応答があり、追加でYouTubeに載せているミュージックビデオの原版の動画ファイルをギガファイル便で送り、またイラスト集や、残りの手書き楽譜などを郵送した。 戦いの音楽史 逆境を越え 世界を制した 20世紀ポップスの物語 にほんのうた 音曲と楽器と芸能にまつわる邦楽通史 |
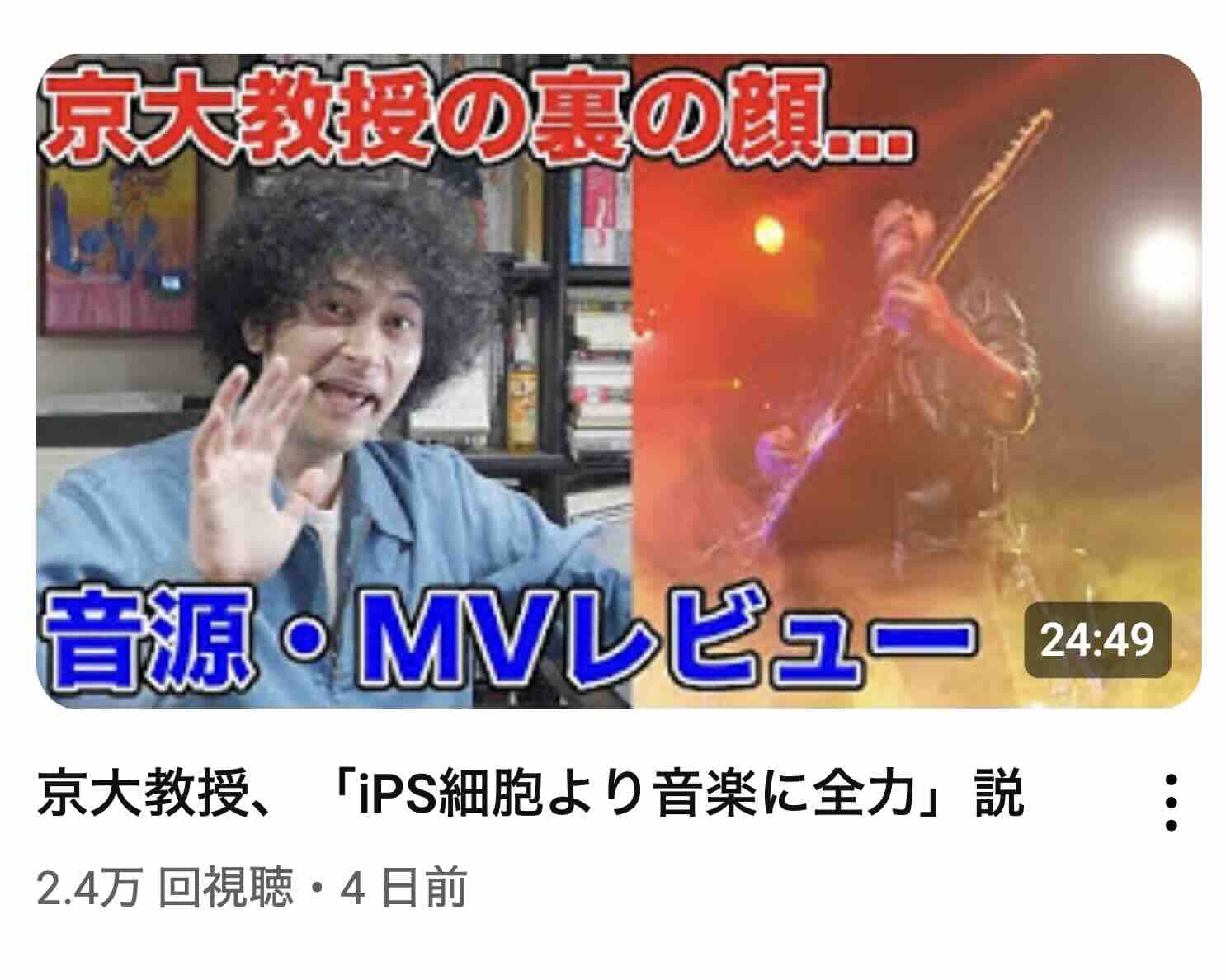 |
この日の20時に、その紹介動画が公開となった。左のサムネイルは4日後にスクショしたものであるから、すでに再生回数2.4万回になっている。 京大教授、「iPS細胞より音楽に全力」説 |
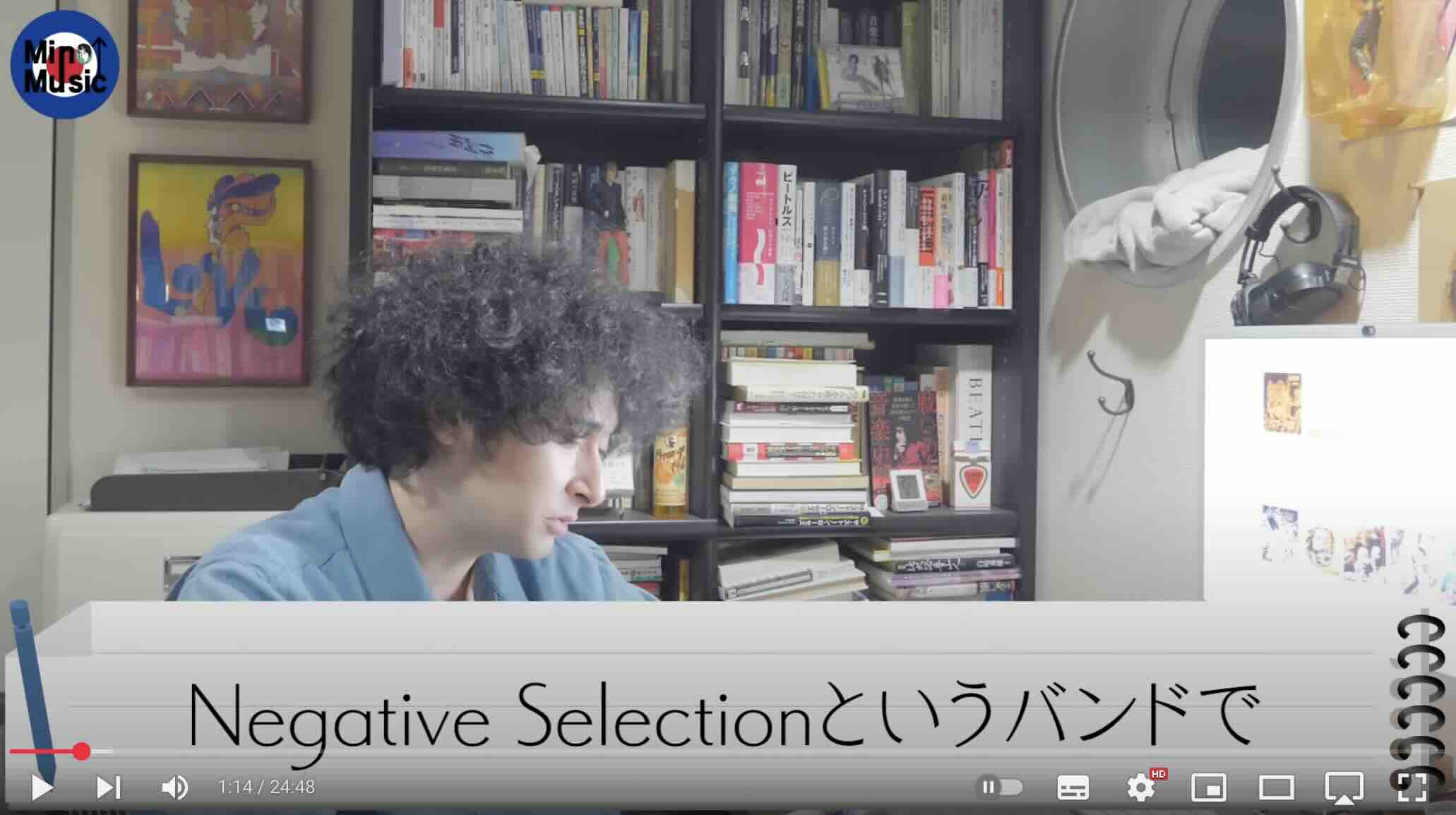 |
ここから動画の内容を紹介する。まず私が出した手紙の冒頭部分が読み上げられた。 |
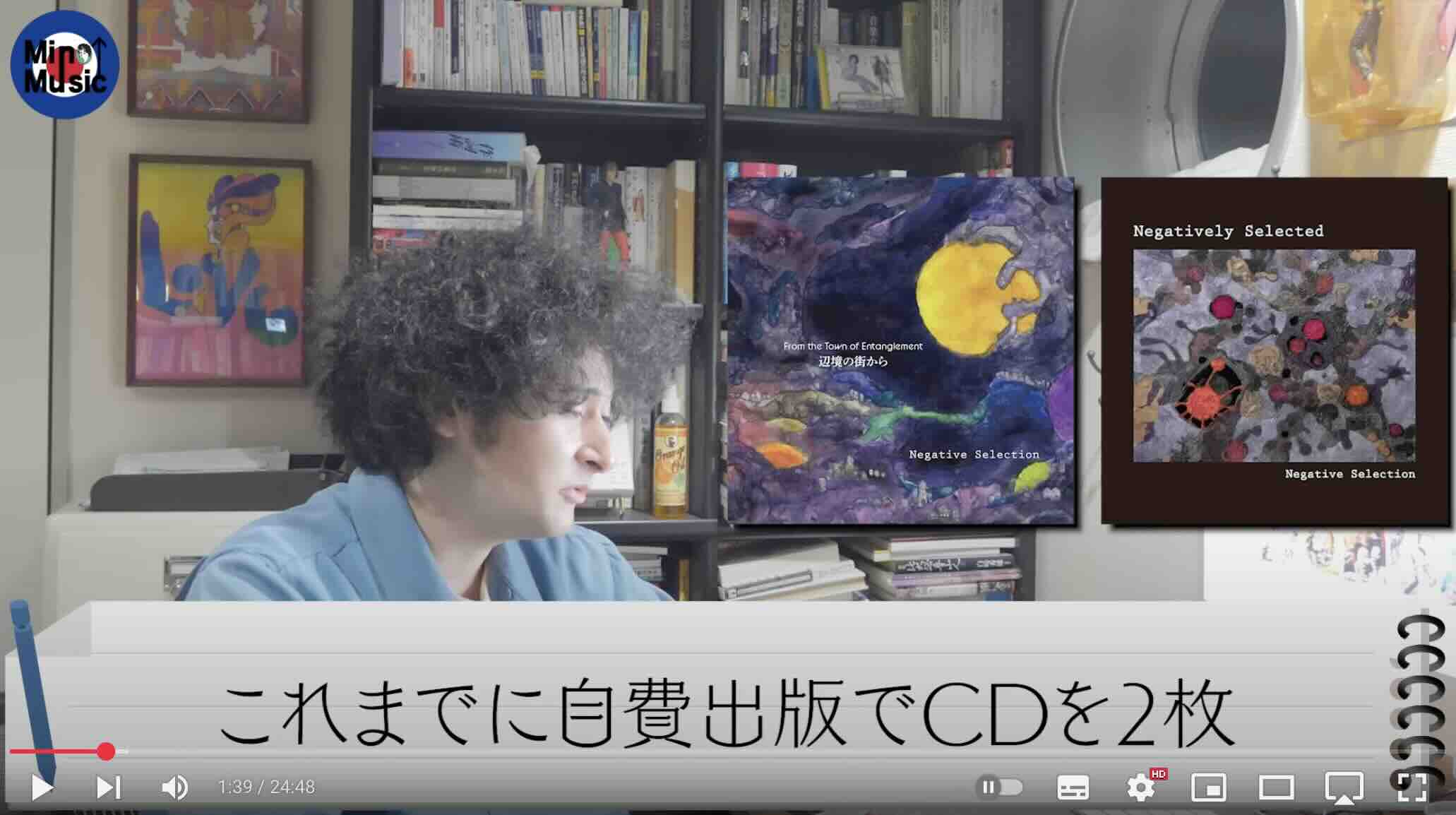 |
「曲のジャンルとしては、プログレッシブロックを志向したハードロックで、プログレハード、という感じかと思います。」と続く。 |
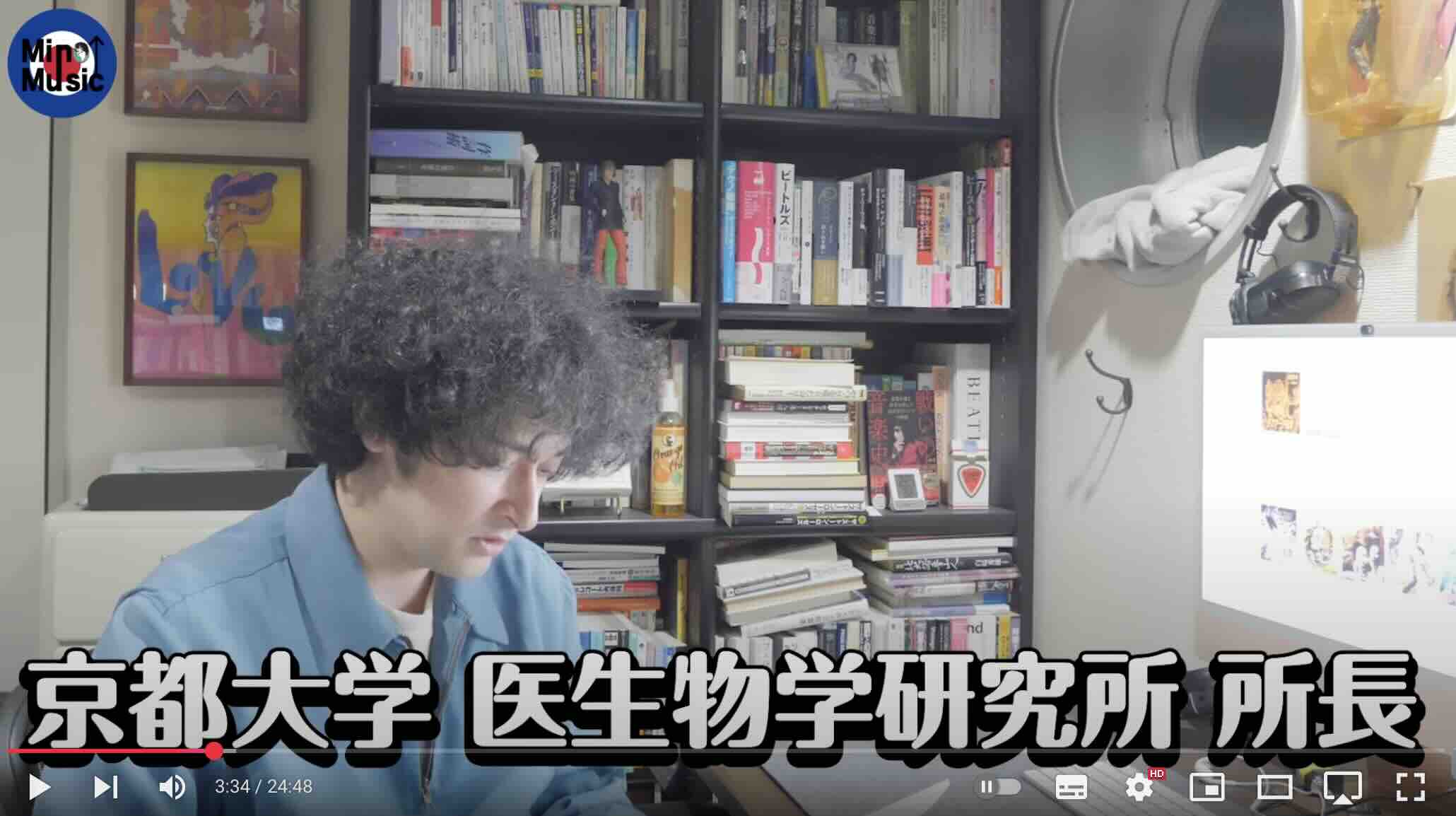 |
その後、バンドメンバーと、2ndアルバムにボーカルとして参加したメンバーの名前と所属が順次読み上げられた。 ・Drums:北村俊雄 東京大学 名誉教授、神戸医療産業都市推進機構 先端医療研究センター センター長 ・Bass:石戸 聡 兵庫医科大学 医学部 病原微生物学講座 教授 ・Keyboards & Guitar:大久保博志 有限会社プログレス(この人は学者ではなく、プランナー、河本の旧友) ・Vocal: 大野博司 (Hiroshi Ohno) 理化学研究所 生命医科学研究センター 粘膜システム研究チーム チームリーダー ⇒腸内フローラ研究の第一人者 2023年度紫綬褒章受賞 縣 保年 (Yasutoshi Agata) 滋賀医科大学 生化学・分子生物学講座 教授 ⇒本庶佑先生のノーベル賞論文のセカンドオーサー 石井 優 (Masaru Ishii) 大阪大学大学院医学系研究科・生命機能研究科 教授 ⇒骨組織・骨髄内の生体イメージング法を世界に先駆けて開発 茂呂和世 (Kazuyo Moro) 大阪大学 大学院医学系研究科 生体防御学教室 教授 ⇒2型自然リンパ球の発見者 免疫学における新しい潮流の開祖 青木智子 (Tomoko Aoki) 近畿大学医学部 消化器内科 医員 鈴木春巳 (Harumi Suzuki) 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 免疫病理研究部 部長 |
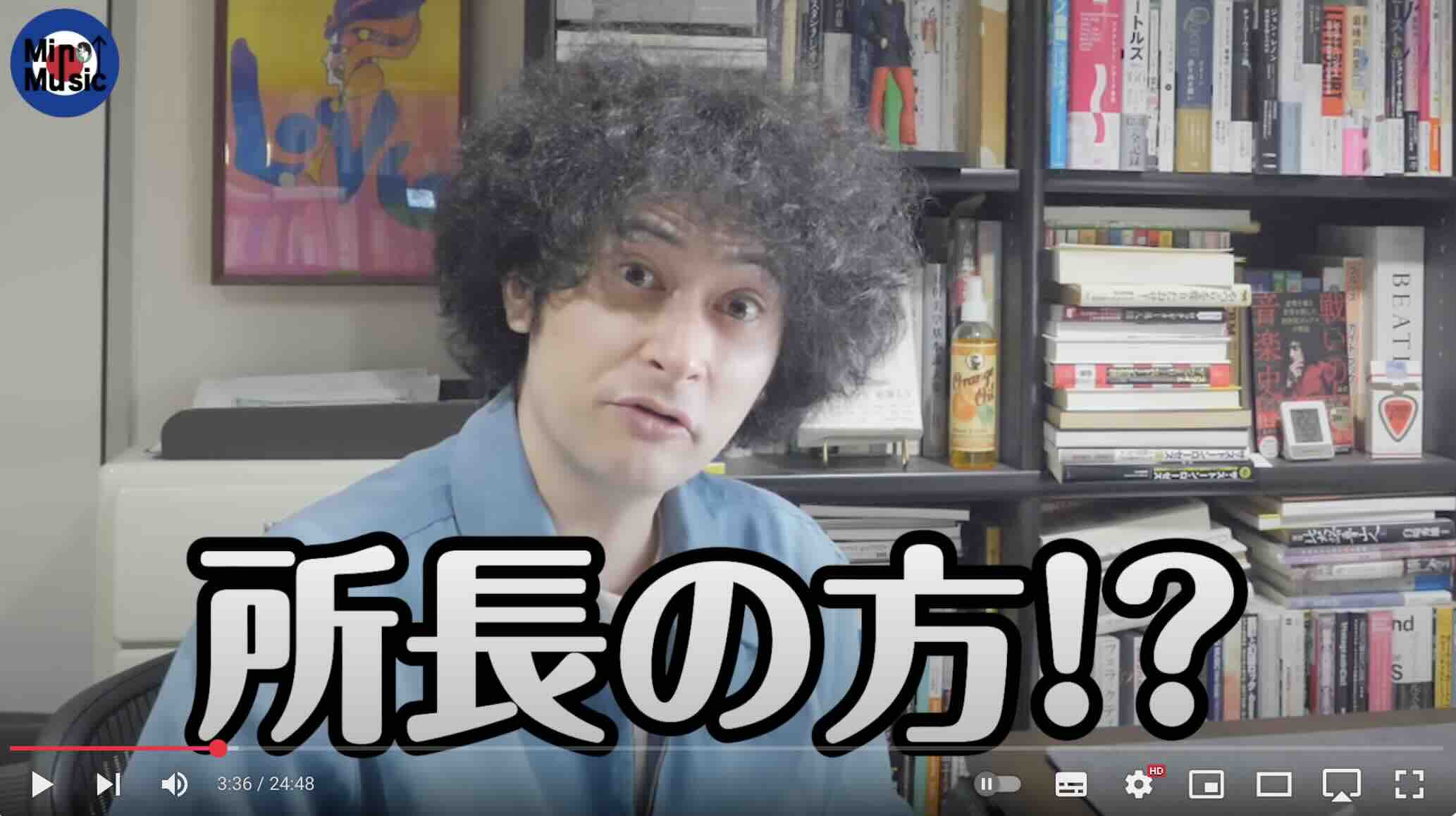 |
私については「所長?」と反応。 |
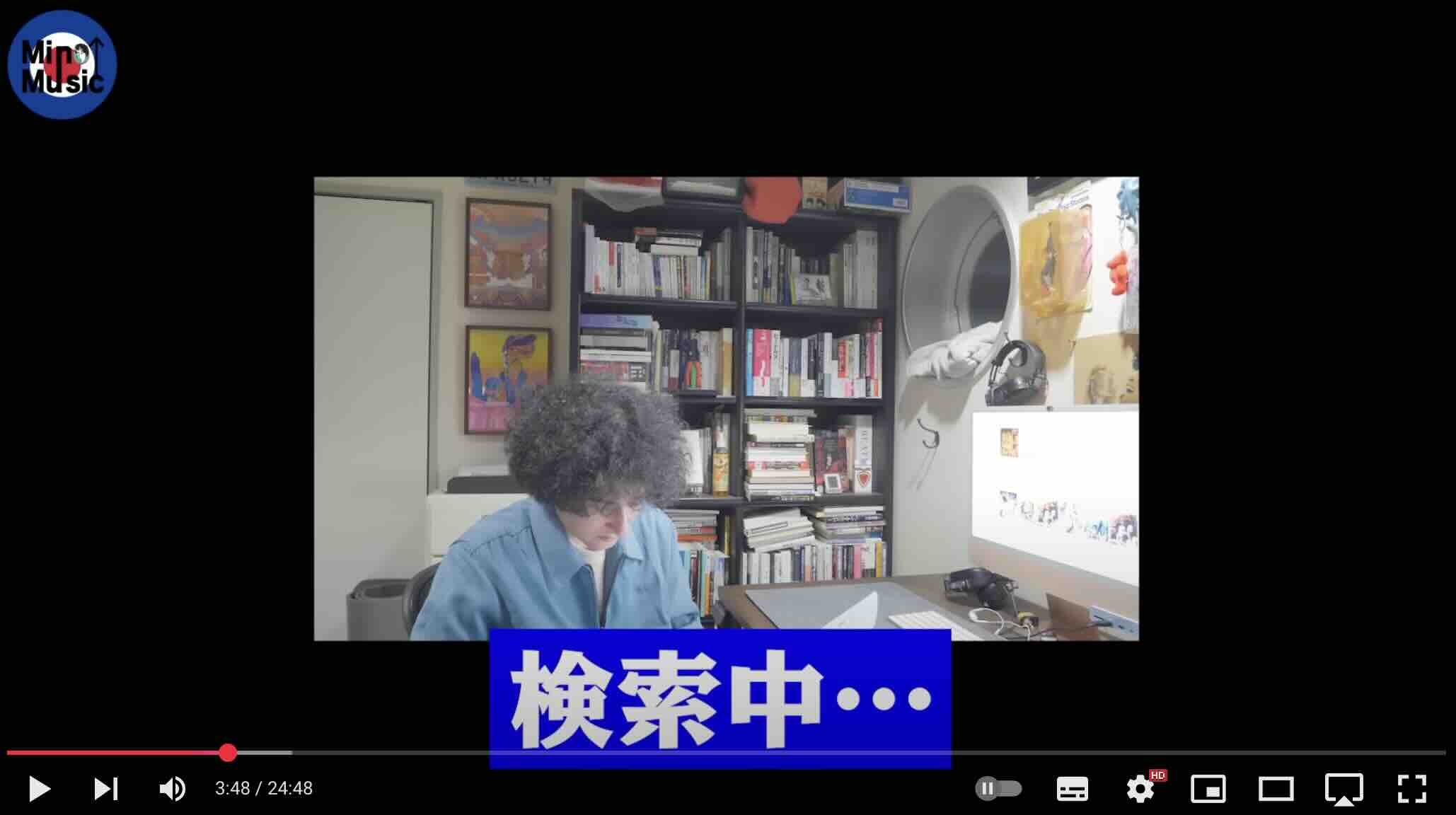 |
「医生物学研究所」を検索中の模様。 |
 |
山中先生は医生研(当時再生医科学研究所)におられた時にiPS細胞の作製に成功され、論文発表された(マウス2006年、ヒト2007年)。だから、「ノーベル賞をとってる研究所」という表現は正しいと言えよう。 |
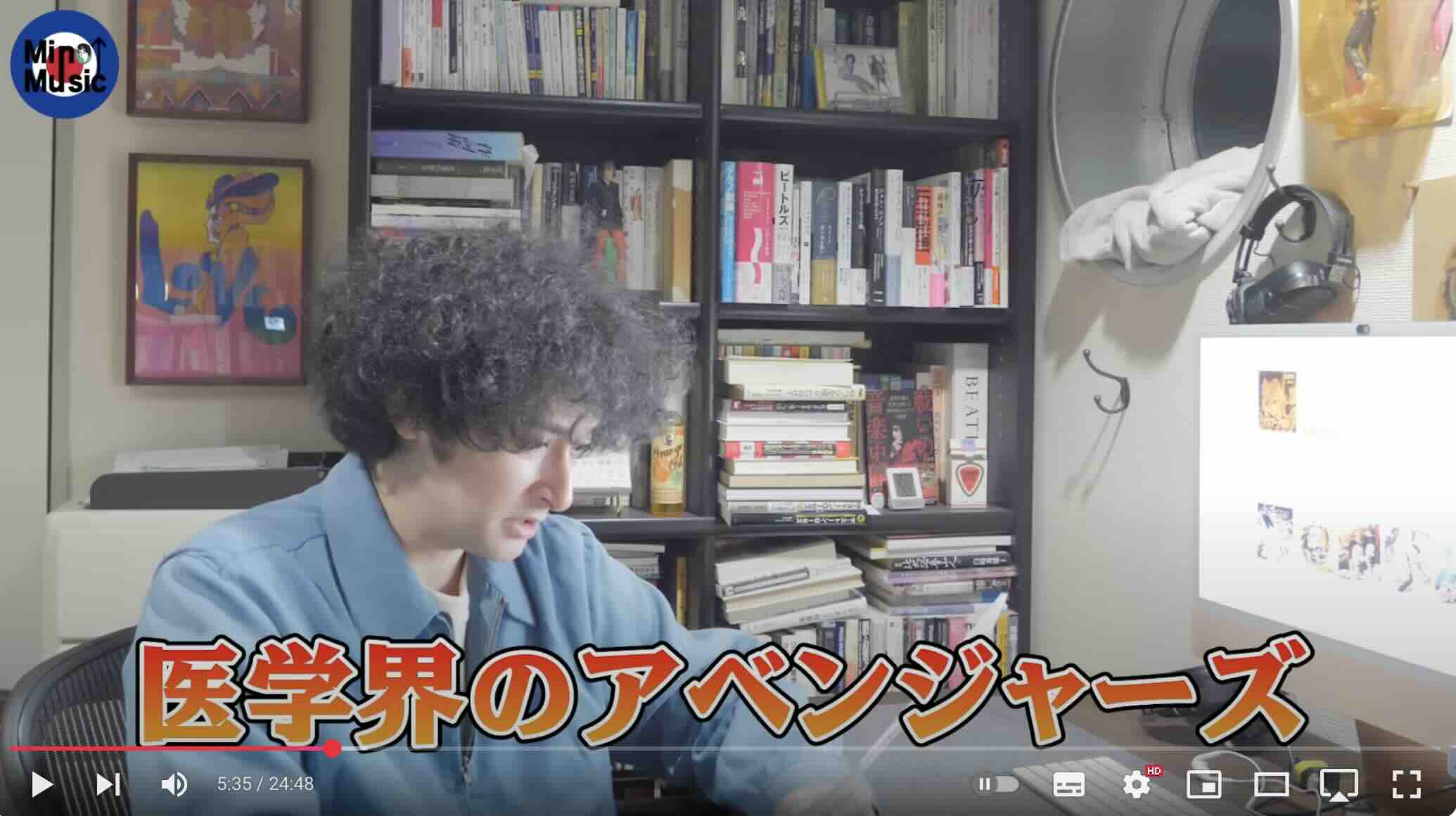 |
他のメンバーの肩書きや一言メモなどを一通り読み終えた後、「医学会のアベンジャーズ」と表現された。面白い表現だ。 |
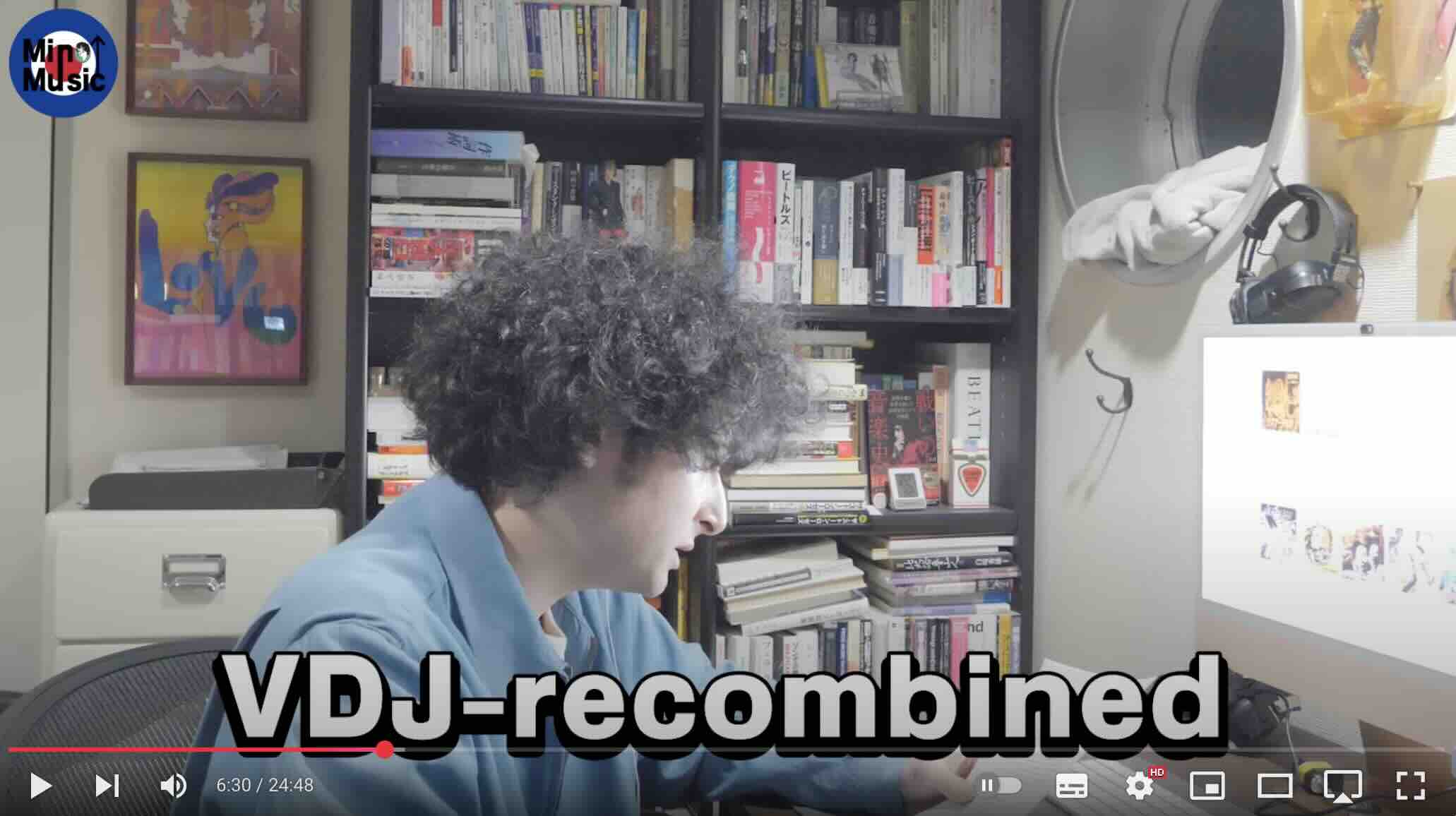 |
まずは「VDJ-recombined」が紹介された。 Negative SelectionがYouTubeに載せている動画へのリンクは下記。 【T細胞の懊悩】VDJ-recombined: ラボニュース欄に載せた解説記事は下記。 「VDJ-recombined」のミュージックビデオを公開(2024年3月11日) |
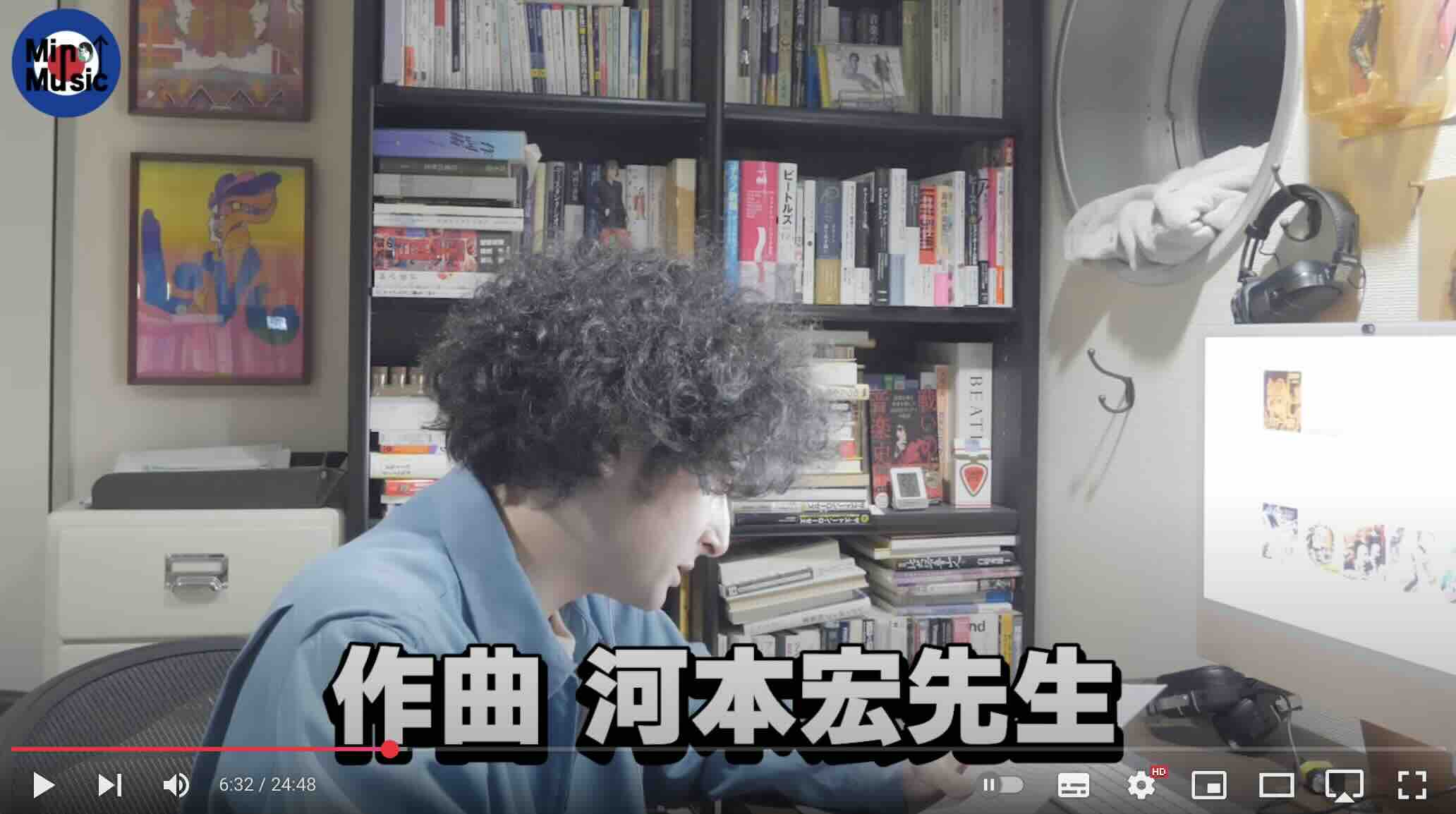 |
作曲、河本宏 |
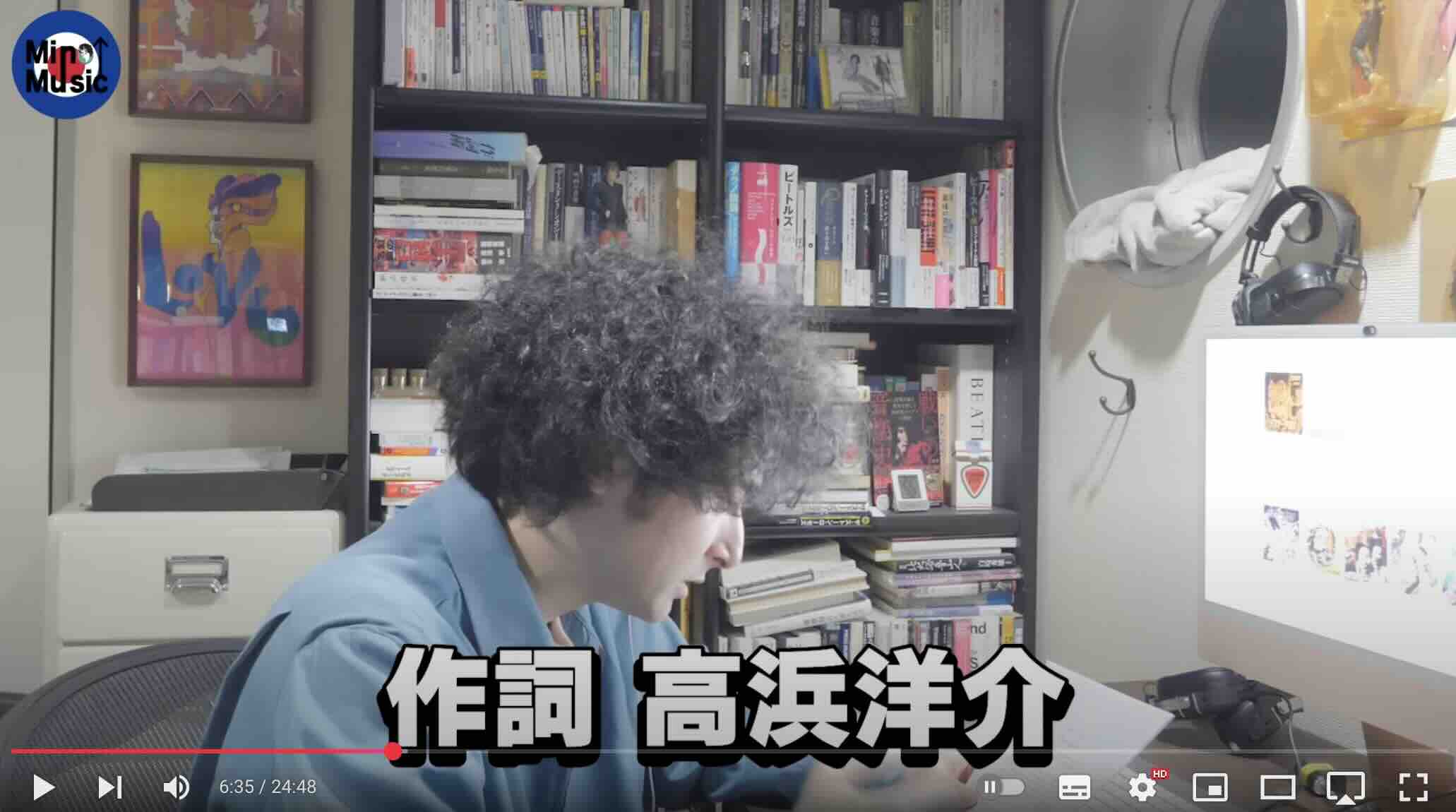 |
作詞、高浜洋介。高浜先生の所属については「NIH Senior Investigator Experimental Immunology Branch」と紹介。 |
 |
静かなピアノで始まる様子をまるでトニーバンクスとコメント。トニーバンクスはジェネシスのキーボーディスト。ピアノで始まる曲といえば「Firth Of Fifth」あたりか。 |
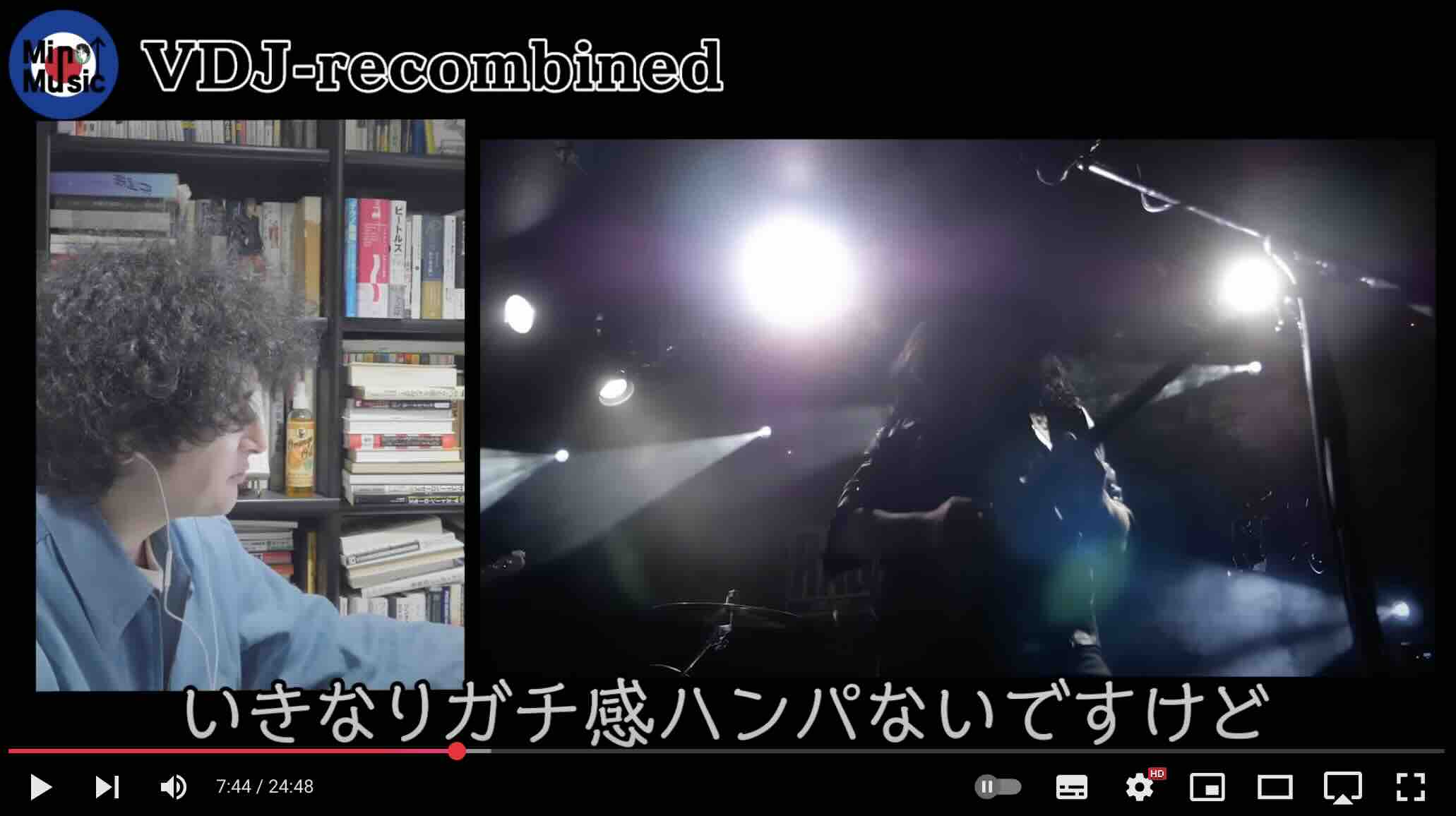 |
突然同じ旋律でバンドが加わってヘビメタ調になる部分のコメント。 |
 |
コードが変わって曲調が変わったところで、冬の琵琶湖畔で、ドローンで撮影した動画に切り替わる。 |
 |
引き続きイントロで、私が4部音符刻みでギターを弾いているシーン。 |
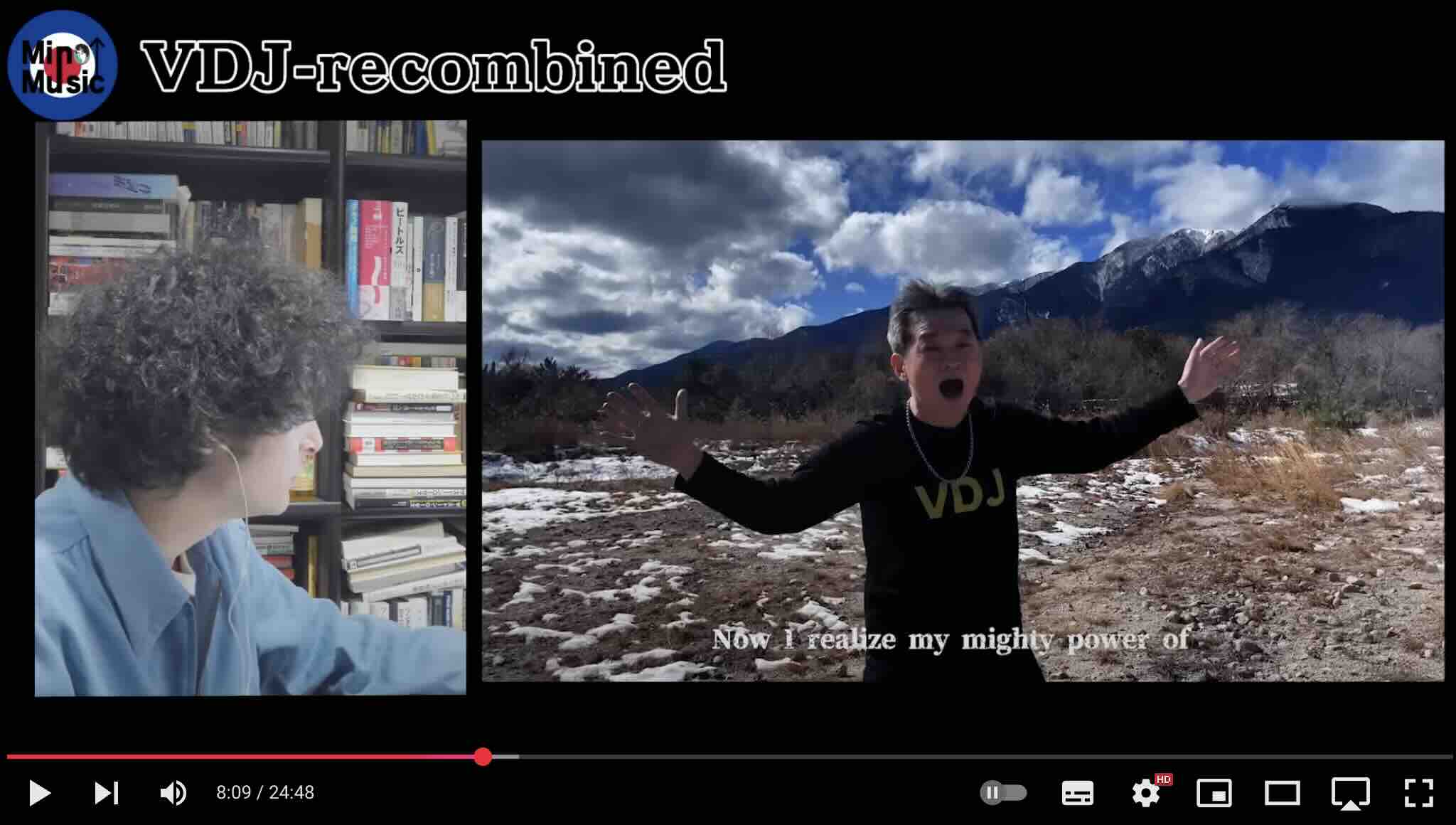 |
縣保年先生(滋賀医科大学)が登場。学生時代バンドをやってボーカルもされていたとのことで、歌は上手だ。実はギターも弾かれ、20年以上前に私がまだ湊研にいた頃、縣先生がギター&ボーカル、私がドラム、という形で一瞬バンドを組んだこともある。 |
 |
I can nail you downという部分だけ縣先生が自ら重ね録りでハモリを入れられたのであるが、そこをしっかり聴き取られて、コメントを入れていただけた。 |
 |
1番と2番の間の感想で、大久保君のキーボードサウンドへのコメント。 |
 |
2番が始まる直前に無調性な音列が2小節入っているが、その部分へコメントいただけた。 |
 |
「Yes, we can fight, we can help, we can kill」という部分についてのコメント。 |
 |
2番と3番の間の間奏ではギターソロのパートがあるが、その部分のバッキングは5拍子になっている。 |
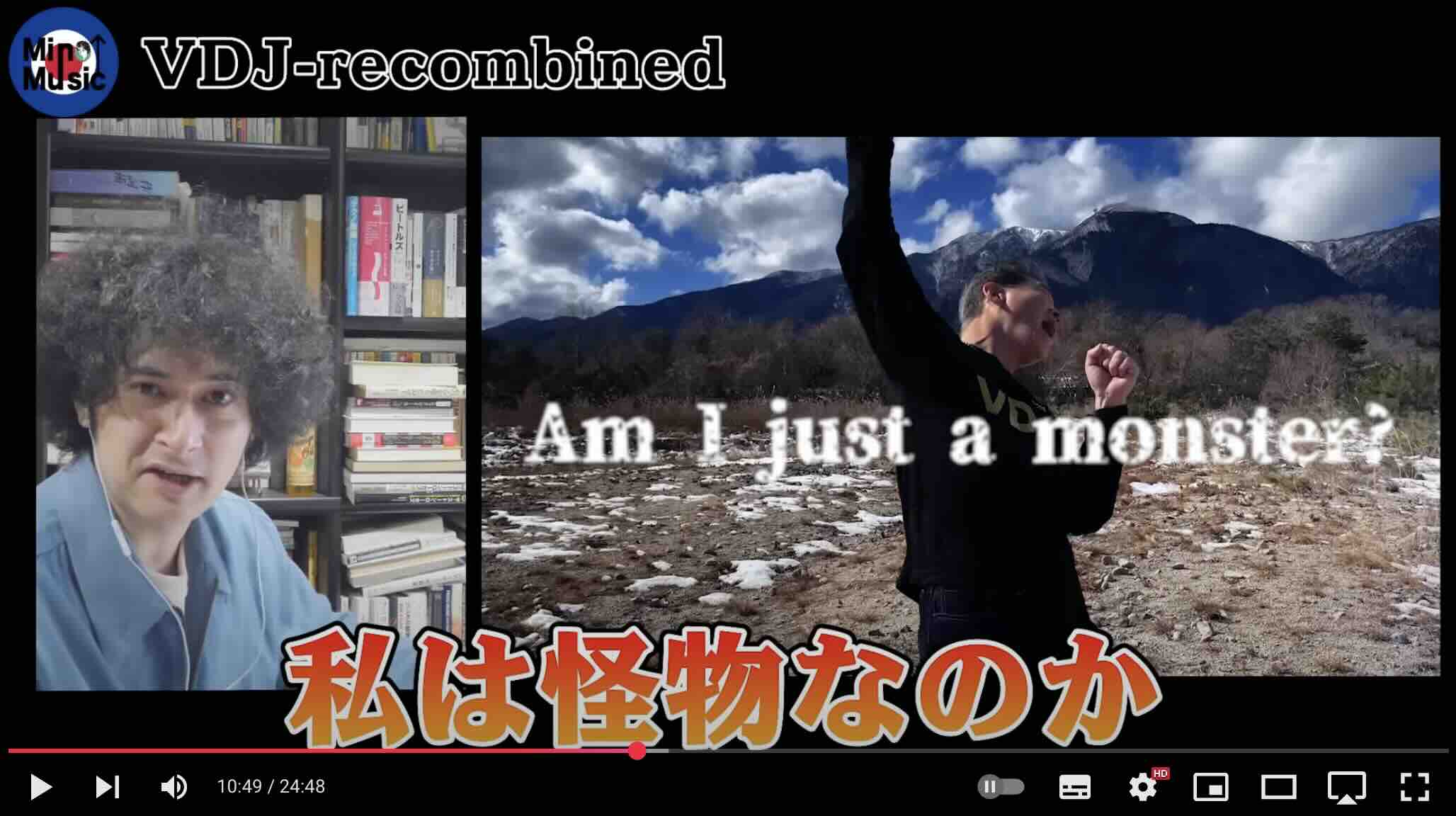 |
3番の歌詞では、「Am I a mutant? Am I a stranger? Am I just a monster?」と、生まれたてのT細胞が、自分のidentityについて悩み始める。 |
 |
それでも「自分は幾千ものレセプターを持っているんだ」と自信を取り戻す。 |
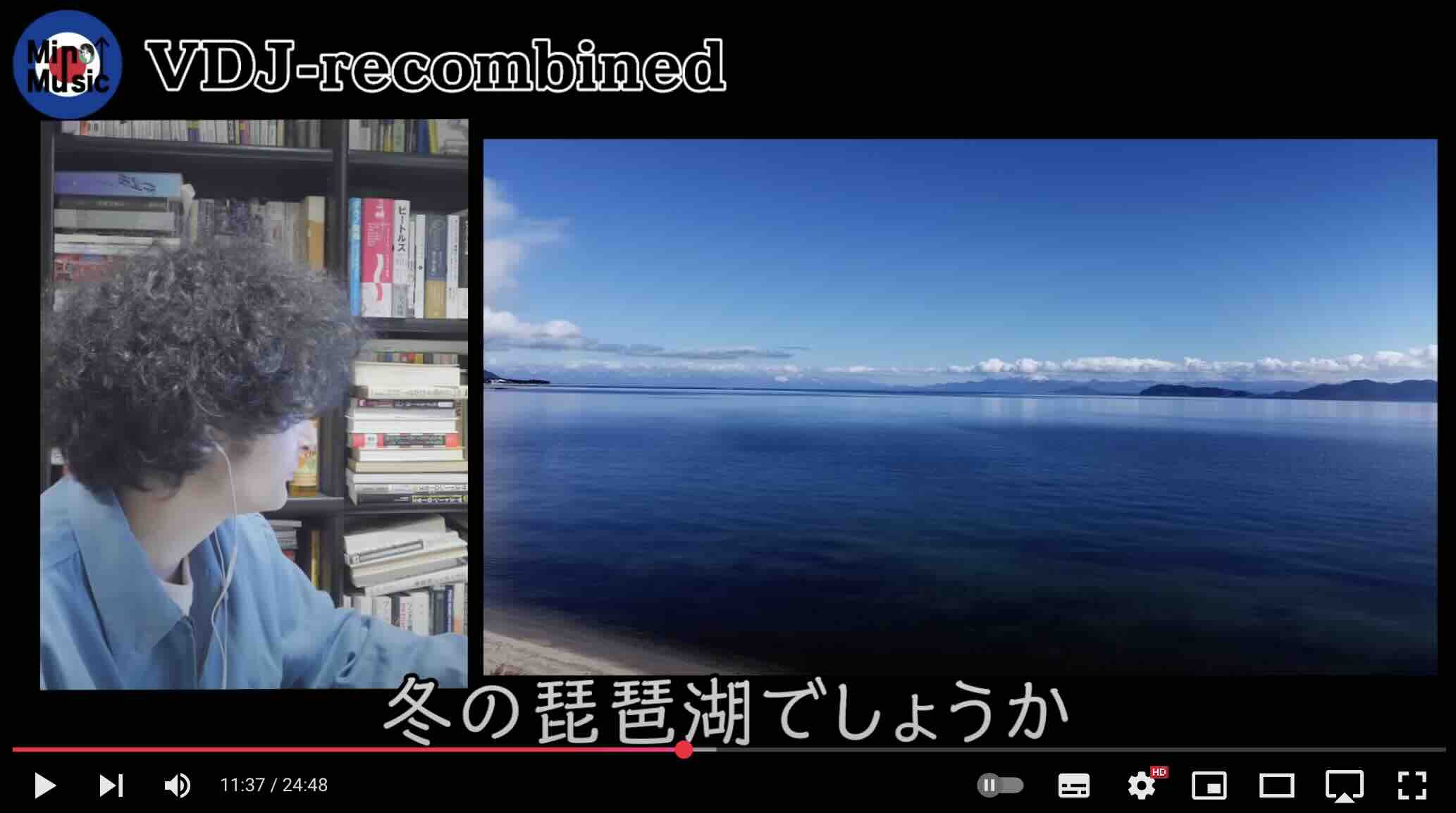 |
ロケ地は琵琶湖西岸の松ノ浦というところ。振り返れば比良山が見える。到着当初は風がほとんどなく、湖面は凪いでいた。エンデイングのこの動画は、到着してすぐにとったドローン映像。ダリの絵のような非現実感が漂っている。 |
 |
琵琶湖でのロケは成功だったと言えよう。 |
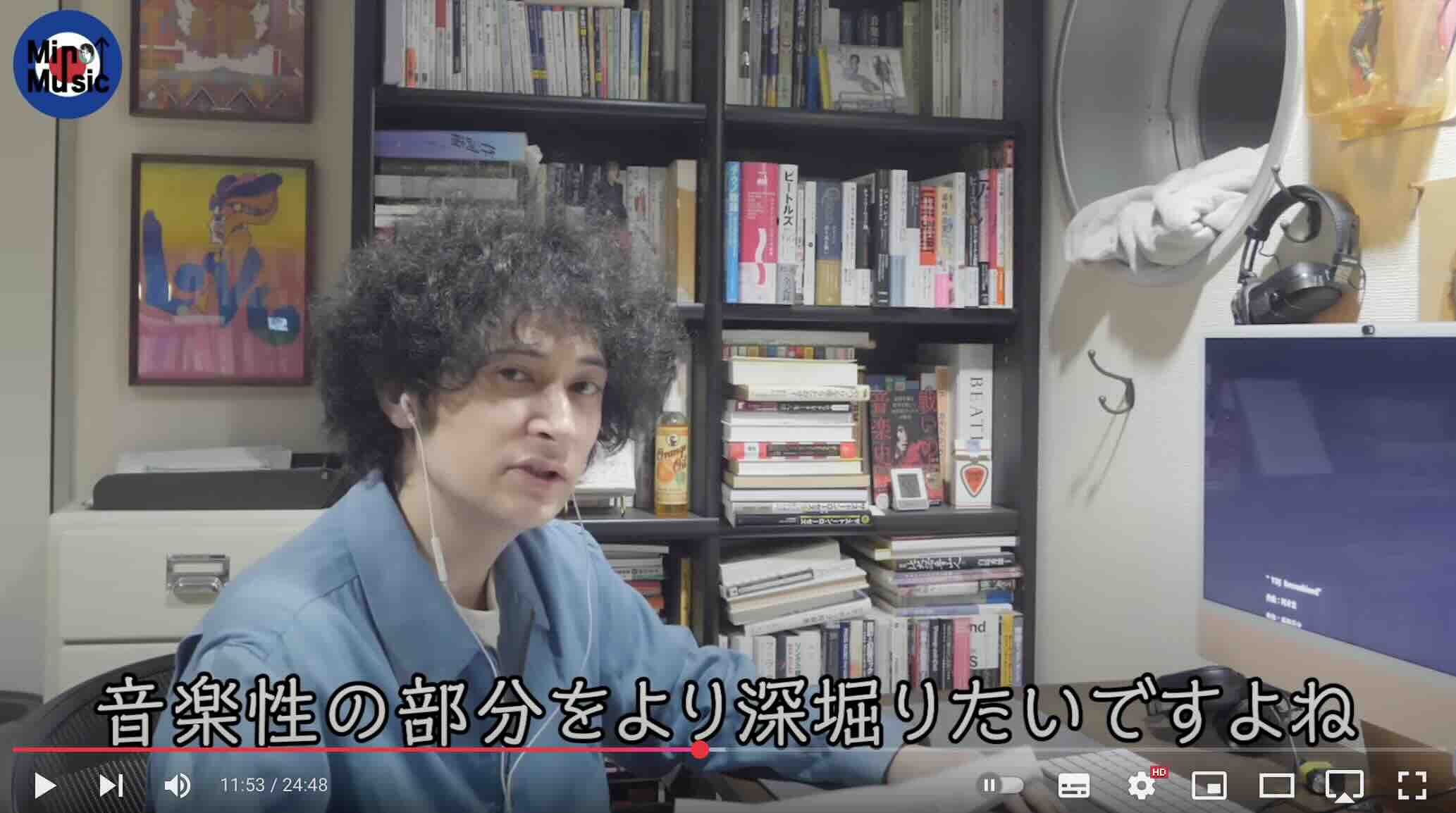 |
「次の動画ではビデオをあまり見ないで楽譜に集中しよう」と言われた。 |
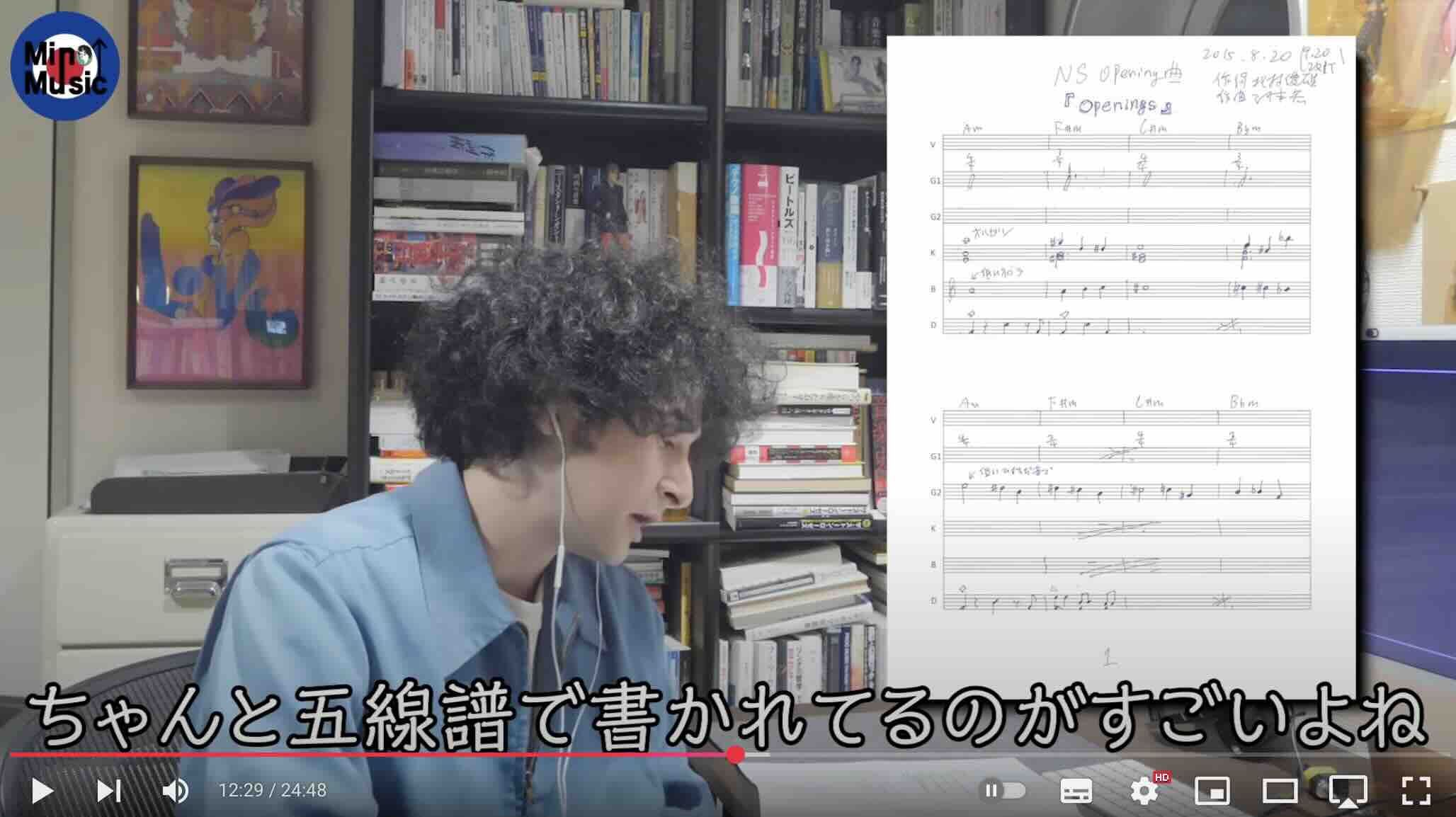 |
荒っぽく描かれた手書きの見づらいスコアであるが、五線譜で書いていることに温かなコメントをいただけた。 |
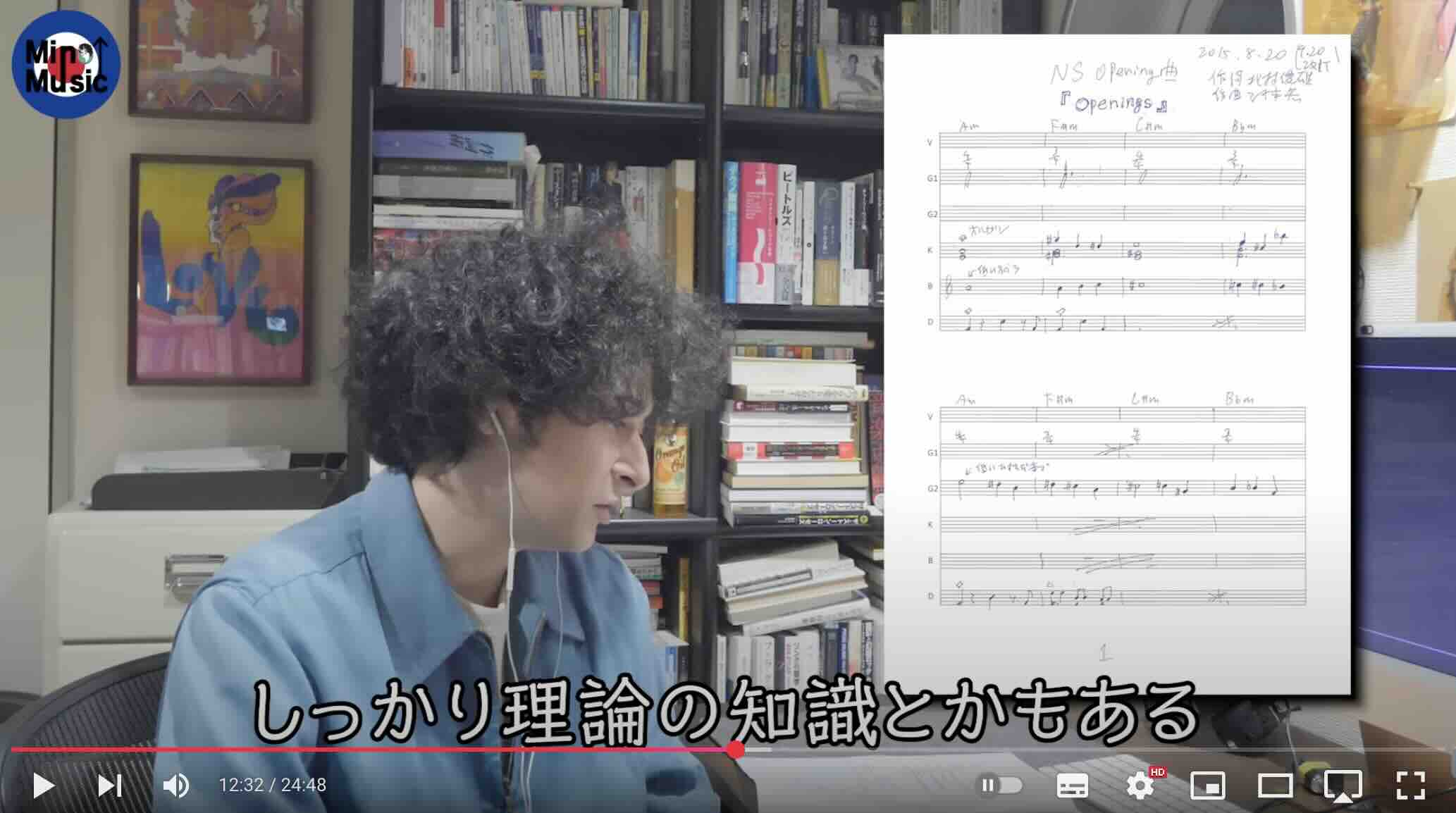 |
コメントをありがとうございます。 |
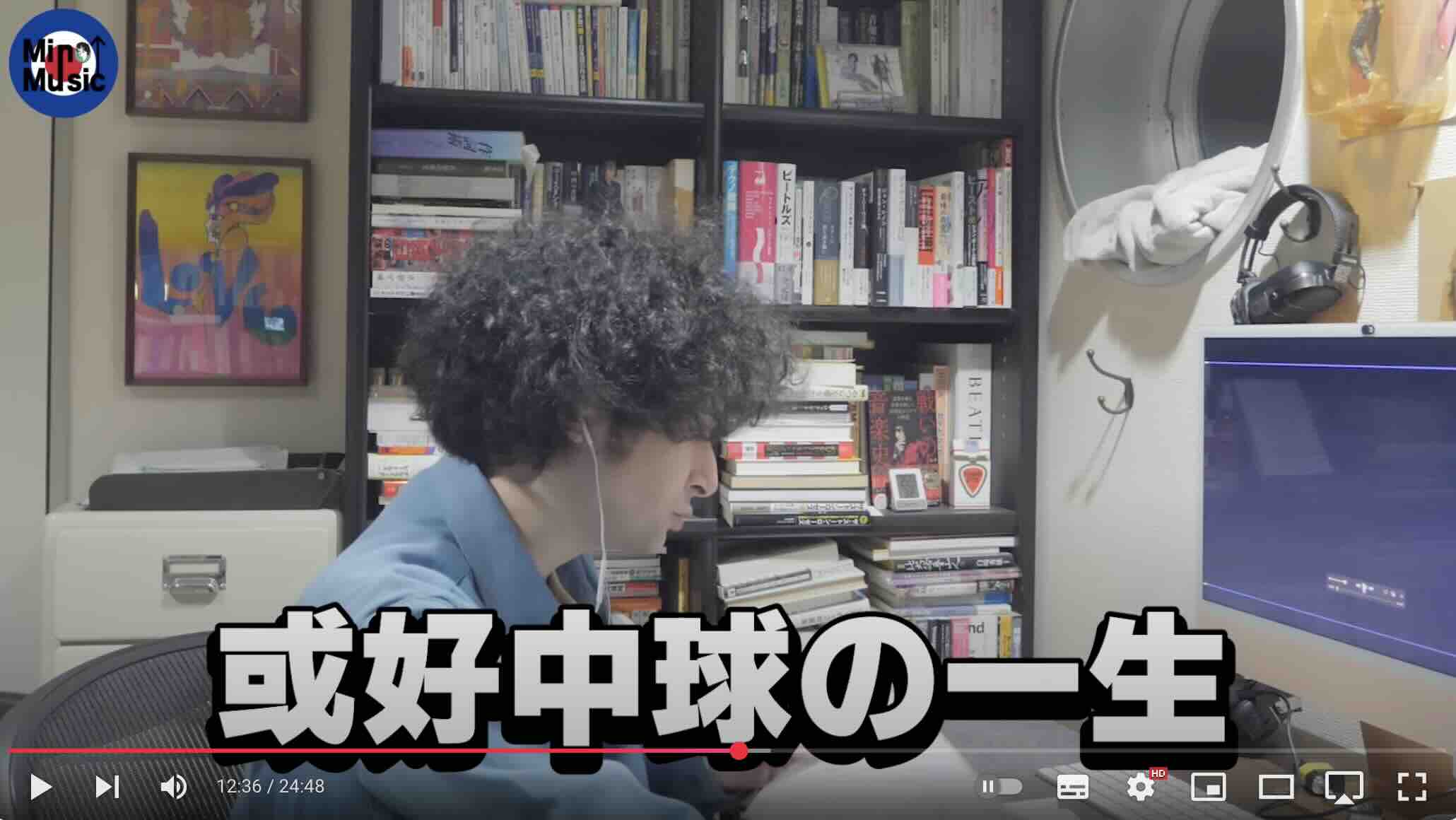 |
2曲目は「或好中球の一生」。 Negative SelectionがYouTubeに載せている動画へのリンクは下記。 【好中球の憂愁】或好中球の一生: ラボニュース欄に載せた解説記事は下記。 「或好中球の一生」をYouTubeで公開(2024年4月3日) |
 |
芥川龍之介の「或阿呆の一生」のもじりかな?と。はい、その通りです。 |
 |
この曲のボーカルは石井優先生(大阪大学)。1番は骨髄でぬくぬくと育ち、ふらふらと旅に出た好中球が、ある日炎症部位の近くを通った時に、自分の使命に気が付く、という話。 |
 |
歌のバッキングに入っているオルガンの音に対するコメント。 |
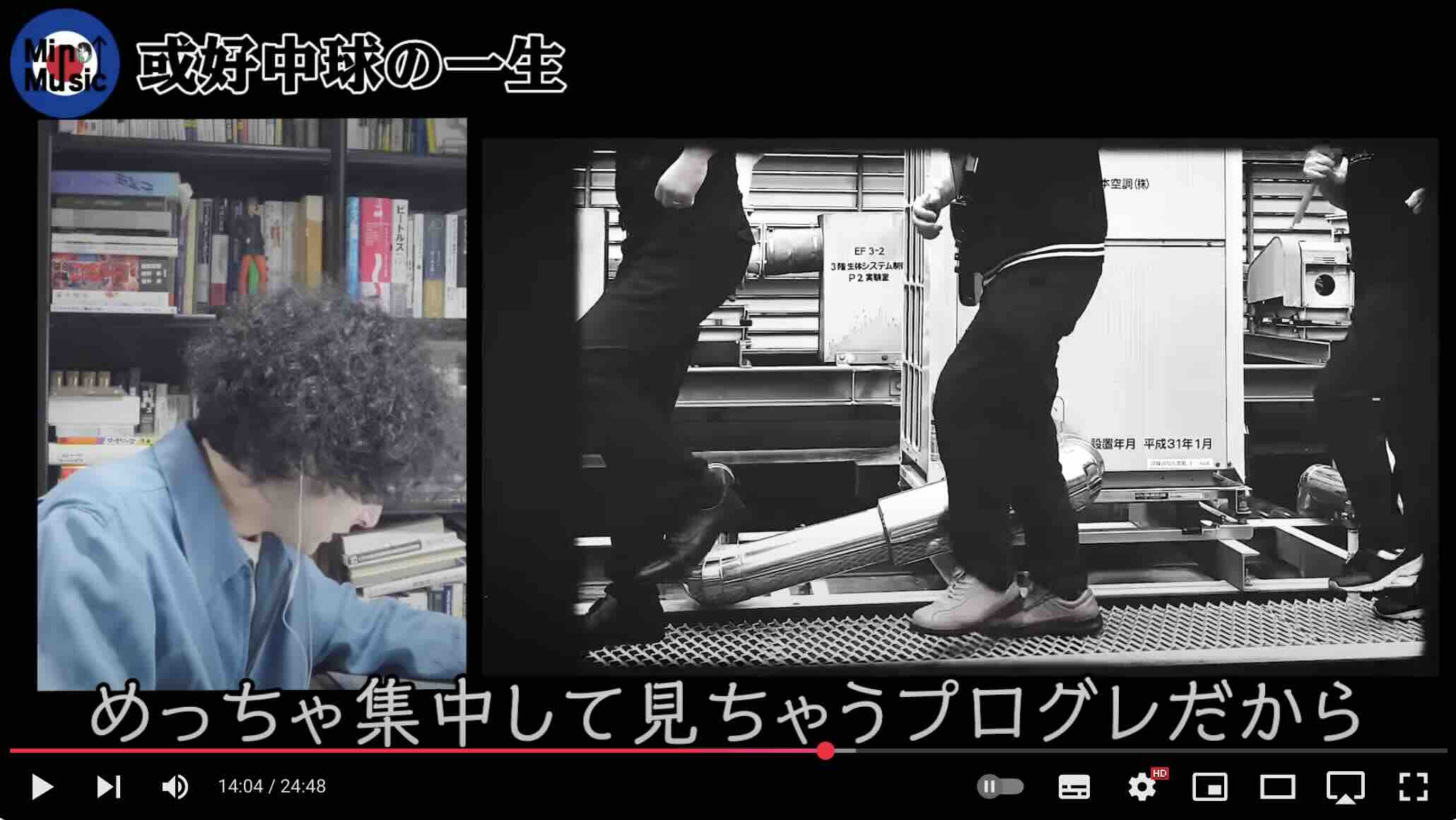 |
1番と2番の間の間奏部では、ホーン系のシンセの旋律2つが行進曲風に絡む。 |
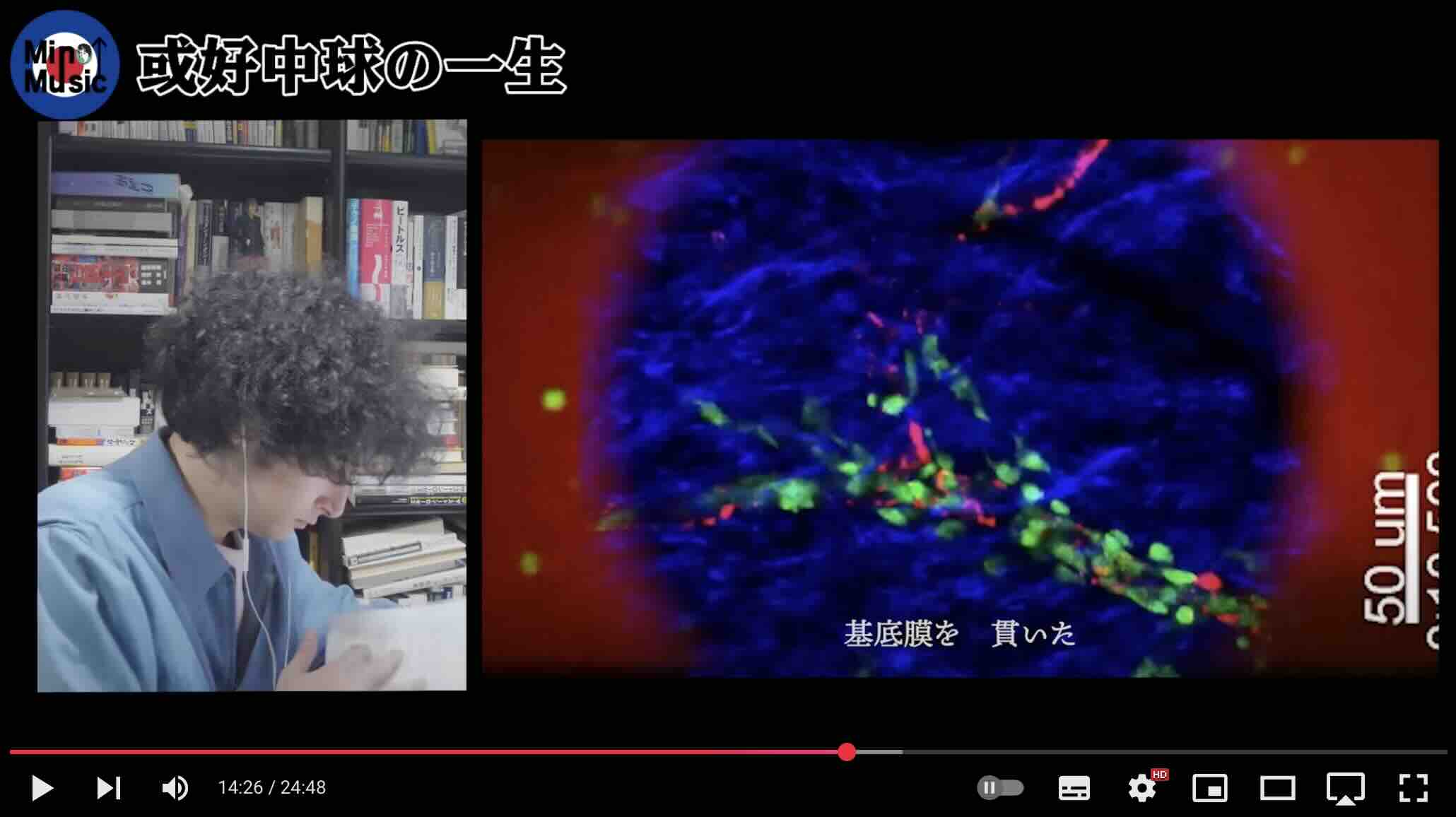 |
2番ではいよいよ好中球が、基底膜を貫いて、現場に赴く。この曲のMVでは、随所に石井先生から提供いただいた貴重な動画が貼り付けてあり、1)好中球が骨髄で育つ、2)血管内を流れる、3)血管壁をローリング、4)基底膜を貫いて組織に浸潤、5)組織で病原体を貪食、などの映像を観ることができる。 |
 |
2番と3番の間の間奏部では、Emだけのギターソロの後に、ちょっと複雑なコード進行のキーボードソロが続く。 |
 |
3番では好中球が食べまくり、やがて死んでいく様が歌われる。 |
 |
歌の部分は聴きやすいコード進行、間奏の部分は複雑なコード進行というメリハリが成功しているとコメントいただけた。 |
 |
イラストについても紹介いただけた。これはよく講義でも使うイラスト。 |
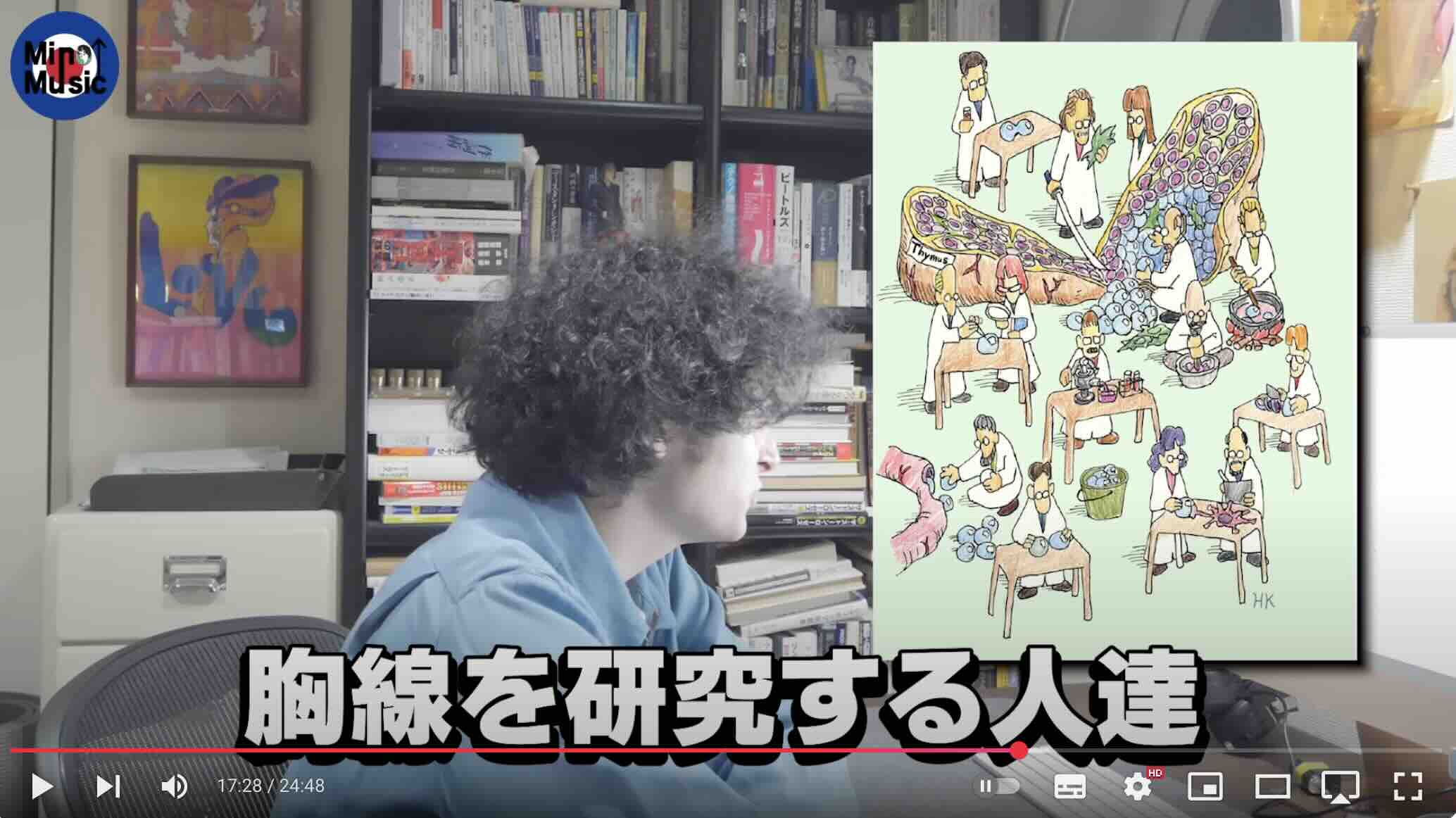 |
これは20年以上前にKTCC用に描いたイラストで、色鉛筆で彩色している。 |
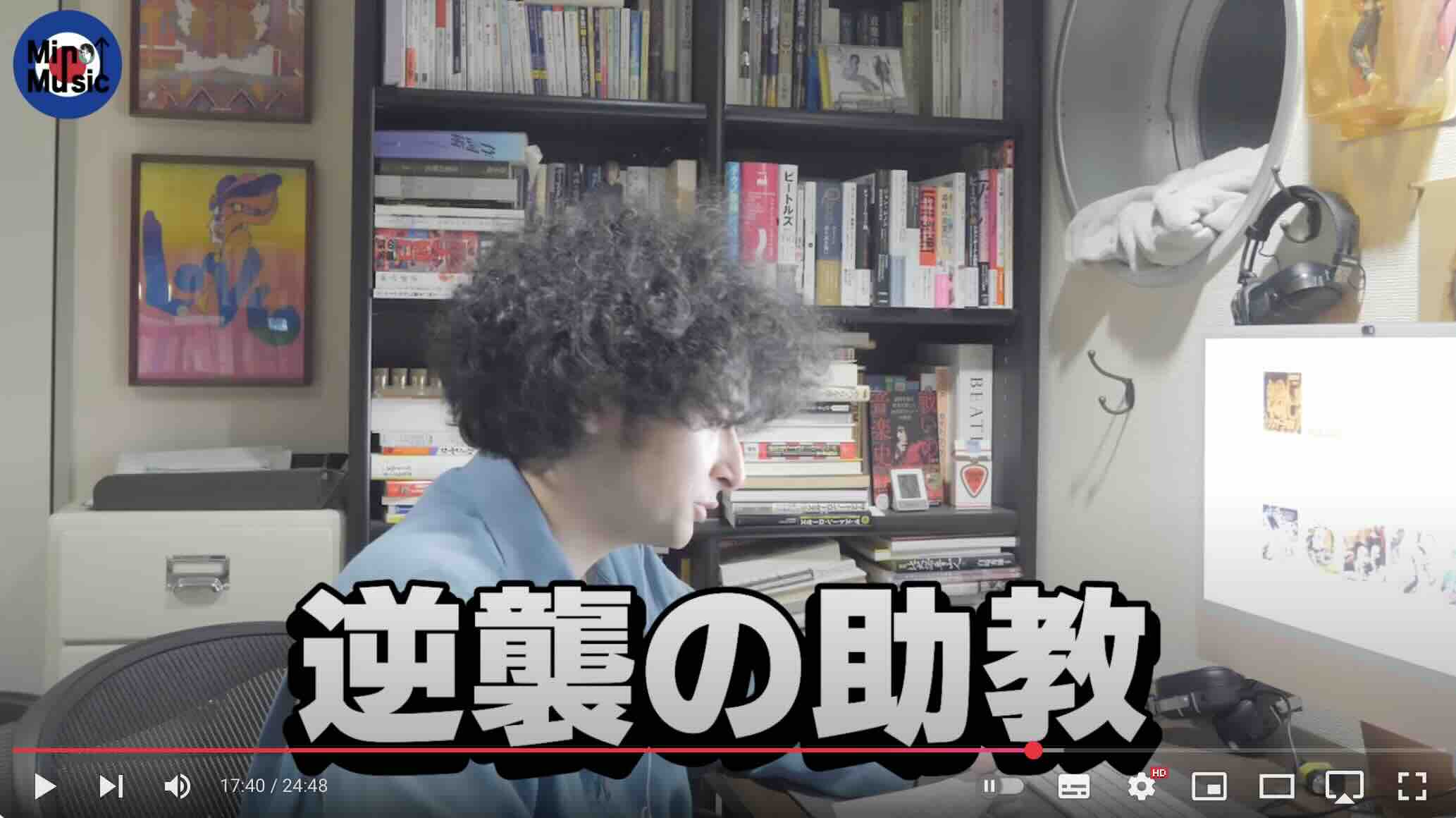 |
3曲目は「逆襲の助教」。 Negative SelectionがYouTubeに載せている動画へのリンクは下記。 【第45回分子生物学会年会公式テーマソング】逆襲の助教【Negative Selection】: この曲については、裏医生研チャンネルでメイキング動画も公開している。 第14回:【とびだせ医生研】分生テーマソングのメイキング! ラボニュース欄に載せた解説記事は下記。 分子生物学会テーマソング「逆襲の助教」公開!(2022年10月24日) |
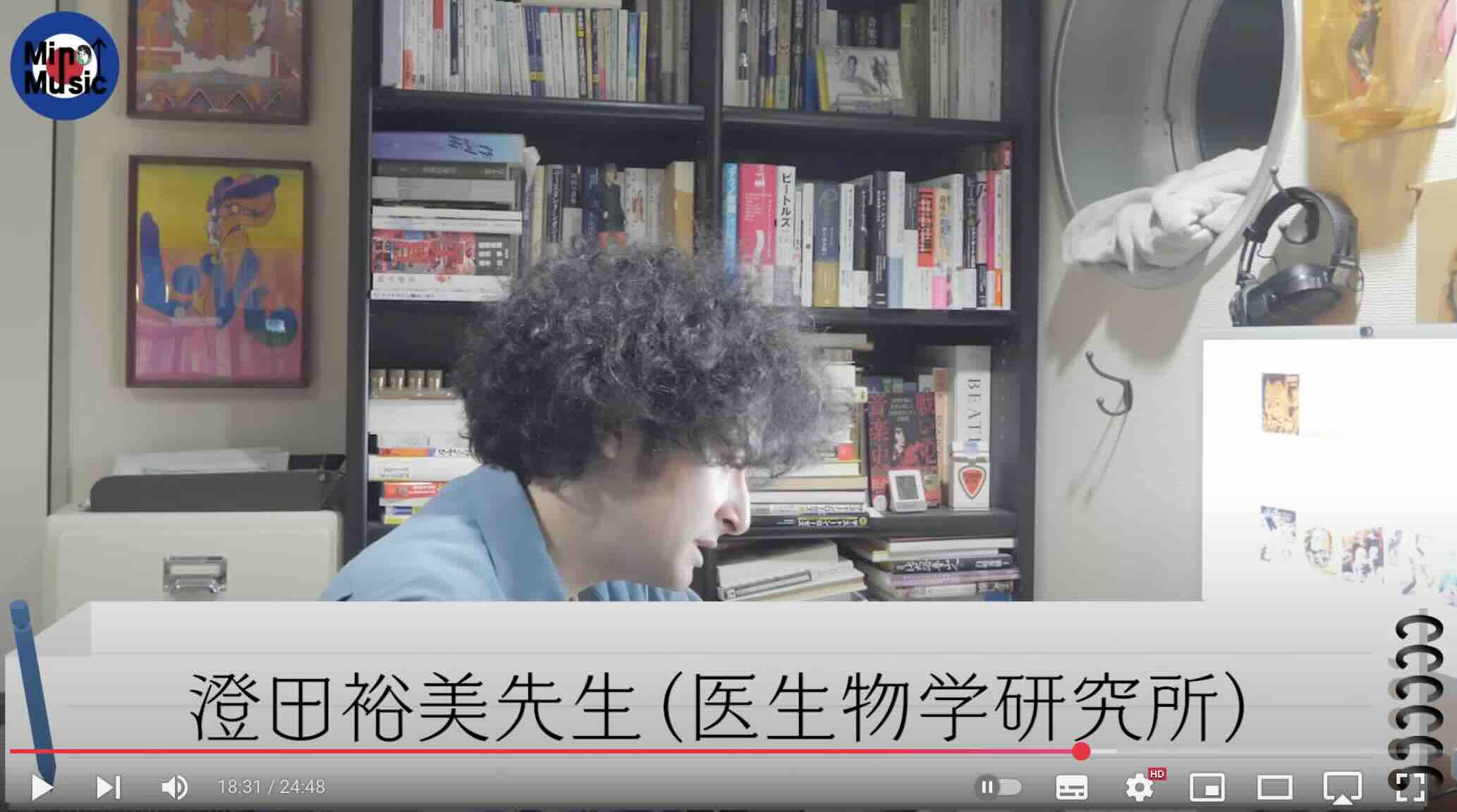 |
この曲では澄田裕美先生(医生物学研究所助教)が多数の3DCGを作成してくれた。 |
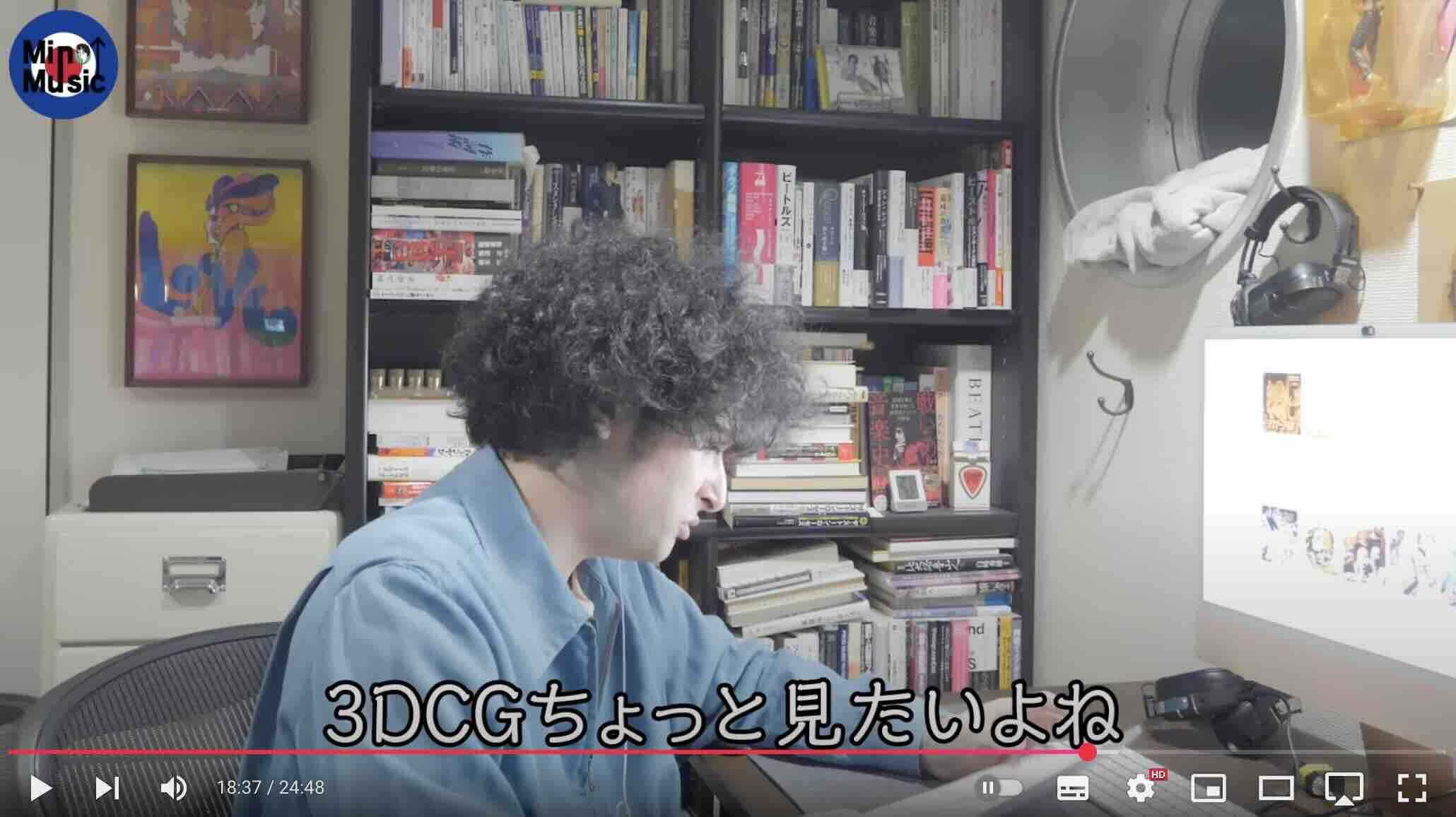 |
この3DCGのおかげで動画のクオリティはとても高くなった。 |
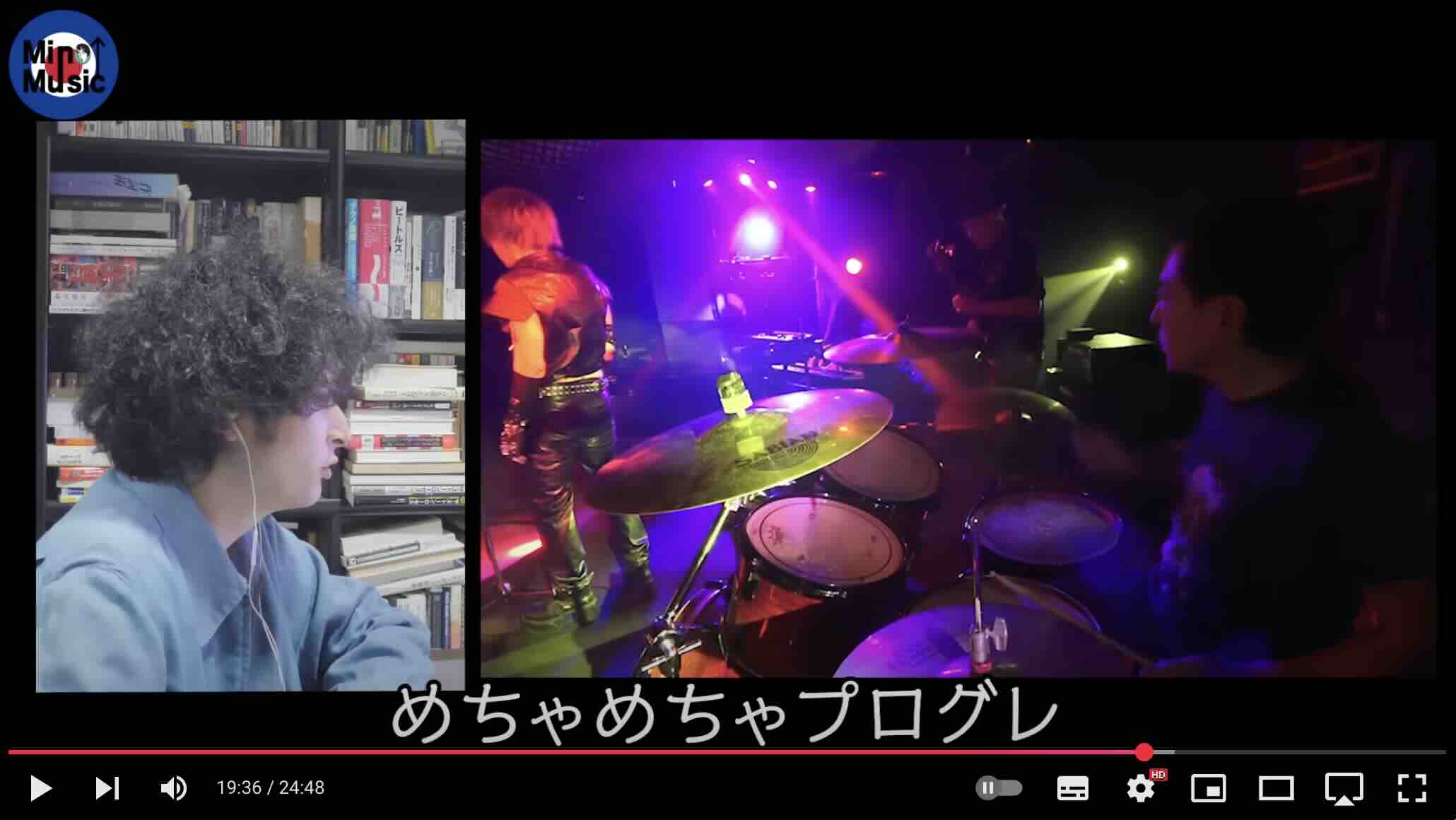 |
イントロの変拍子っぽいギターのフレーズが曲をリードする部分へのコメント。 |
 |
鈴木春巳先生登場!学会で自分の研究内容についてボロカスに言われ、すっかり意気消沈する。 |
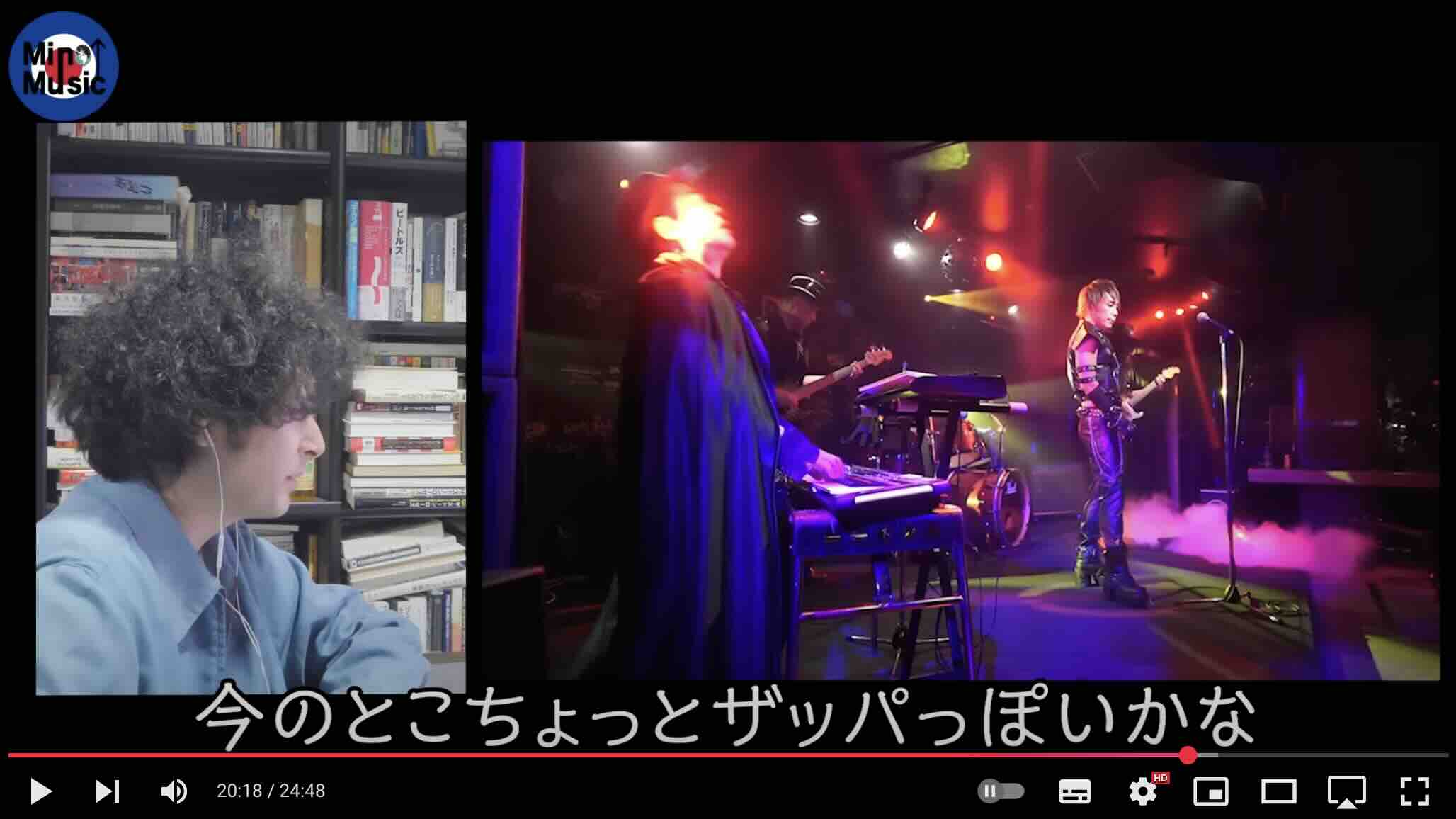 |
最初の間奏で、無調性な音階を使った4小節を入れたら、しっかりと拾っていただけ、「ザッパっぽい」と言っていただけた。 |
 |
そのザッパっぽい部分には、確かに特定のコードとか、スケールは無い。 |
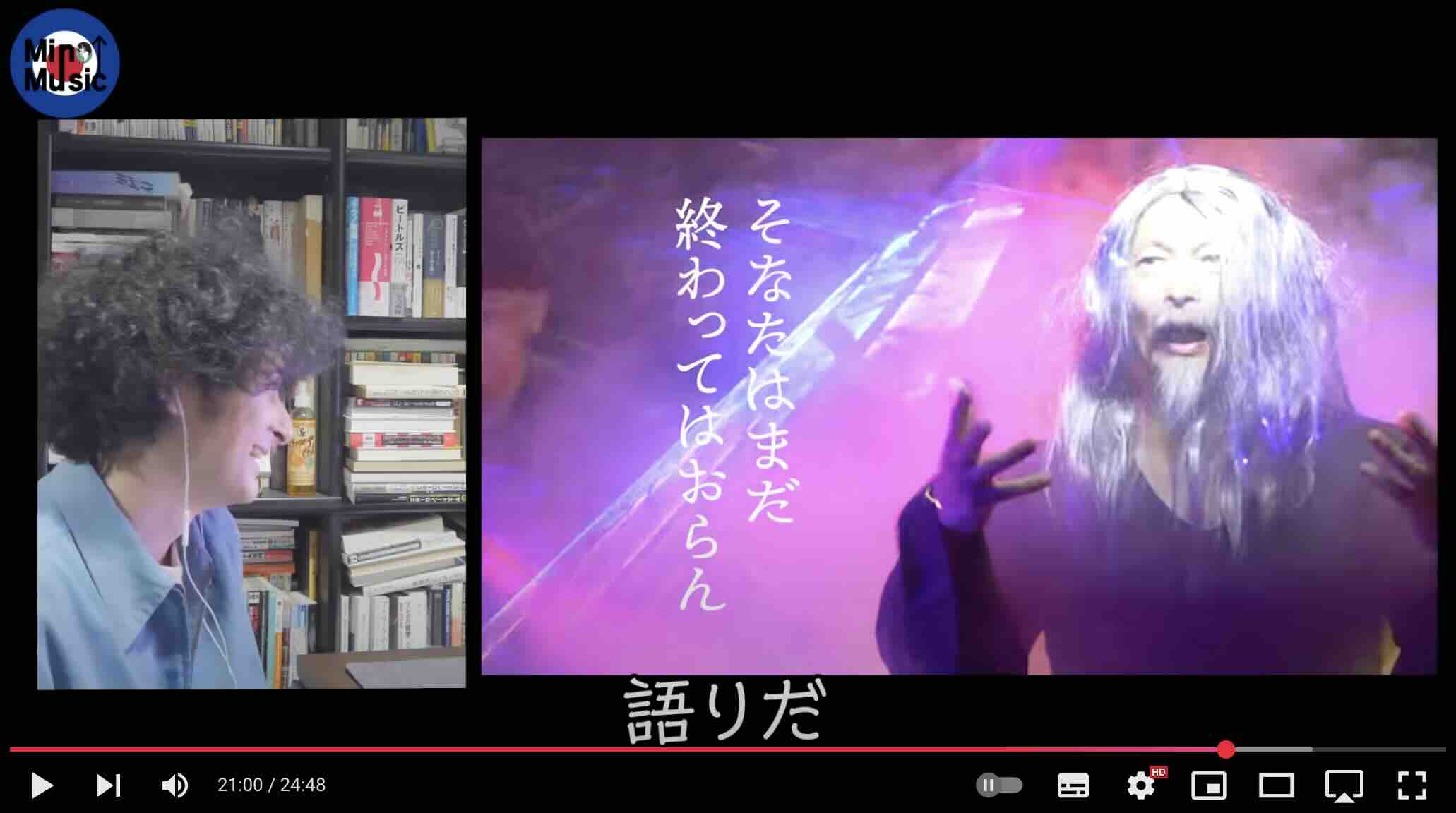 |
ここで河本が扮する神様(アース様)による励ましの語りが入る。 |
 |
励まされた助教は学会に復帰する。 |
 |
「血潮のしぶきが匂い立つこの地」という言葉を拾っていただけた。 |
 |
ここからはちょっと長い間奏。澄田先生作成の新型コロナの3DCG。 |
 |
戦士同士のチャンバラ。 |
 |
ギターソロの部分は、バッキングは7拍子。冒頭の部分はグリッサンド(弦の上で指を滑らせて音を上下させる方法)を効かせて入り、タッピング(右手の指で弦を叩く)のフレーズを続けた。そのあたりをしっかりと拾っていただけて、ありがたい。 |
 |
結局助教は、再度負ける。 |
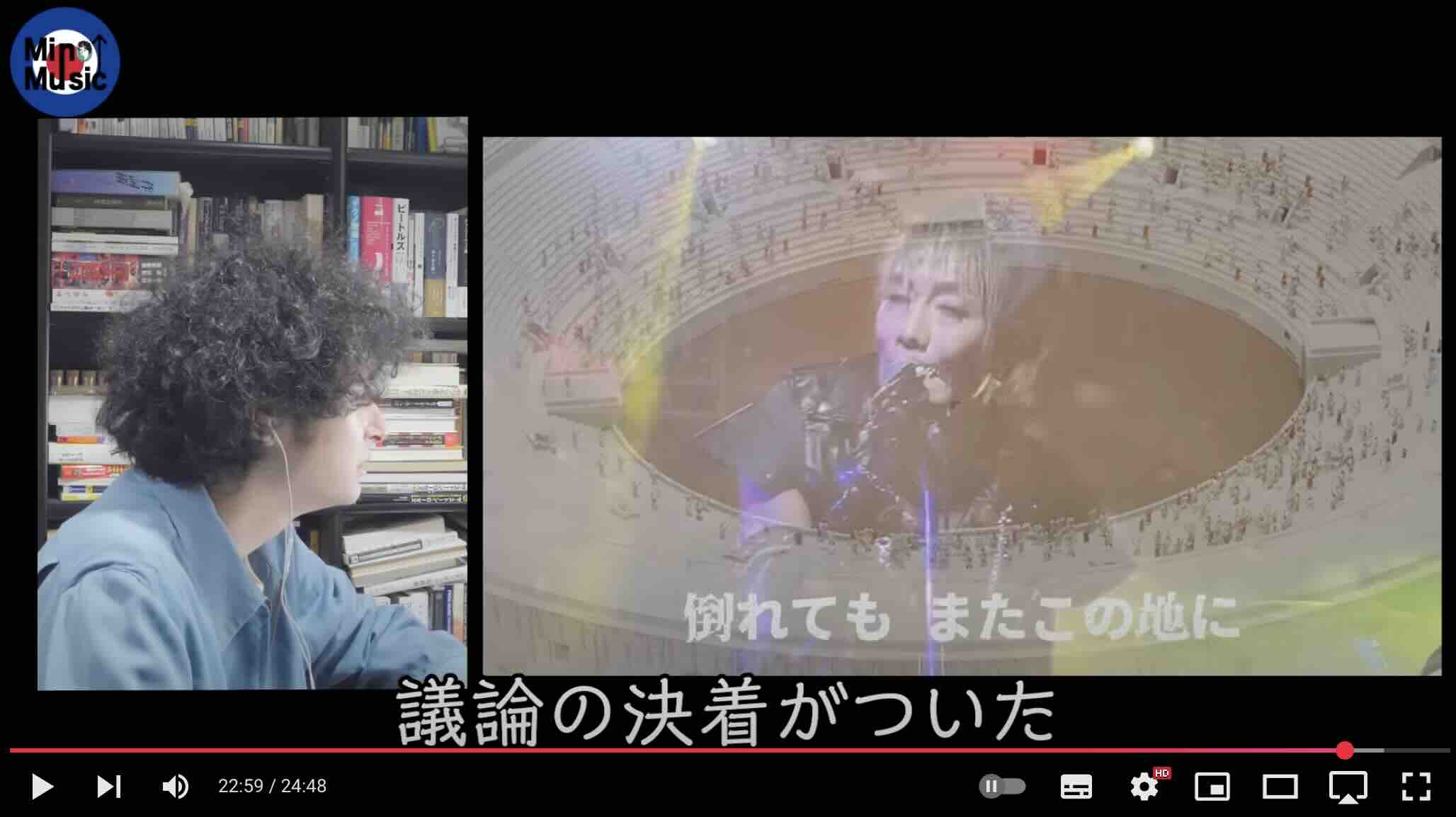 |
「倒れてもまたこの地に帰ってくるんだ」と最後の部分の歌が始まる。 |
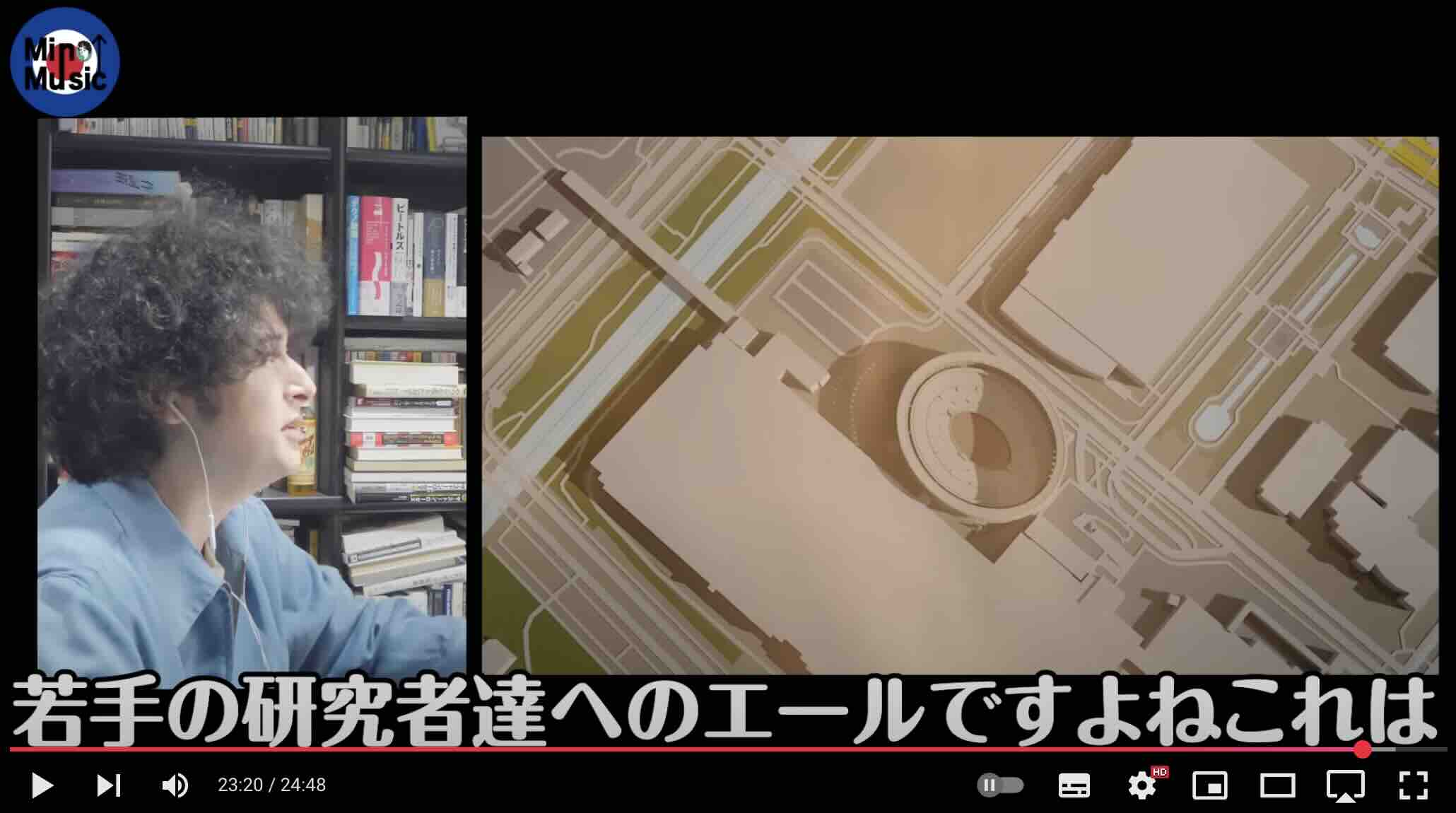 |
若手を励ます歌だと解説していただけた。 |
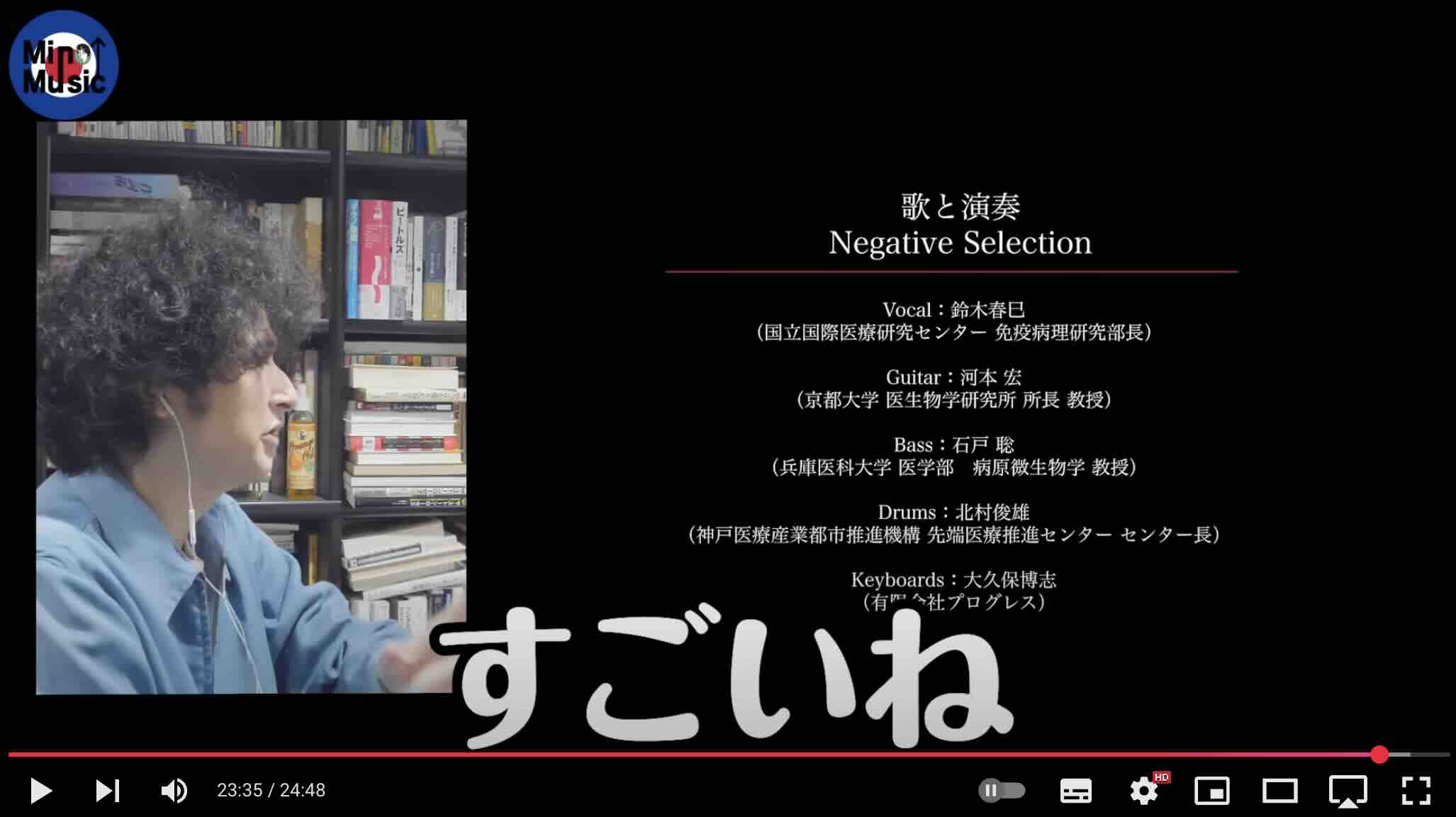 |
「すごいね」と言って拍手していただいた。 |
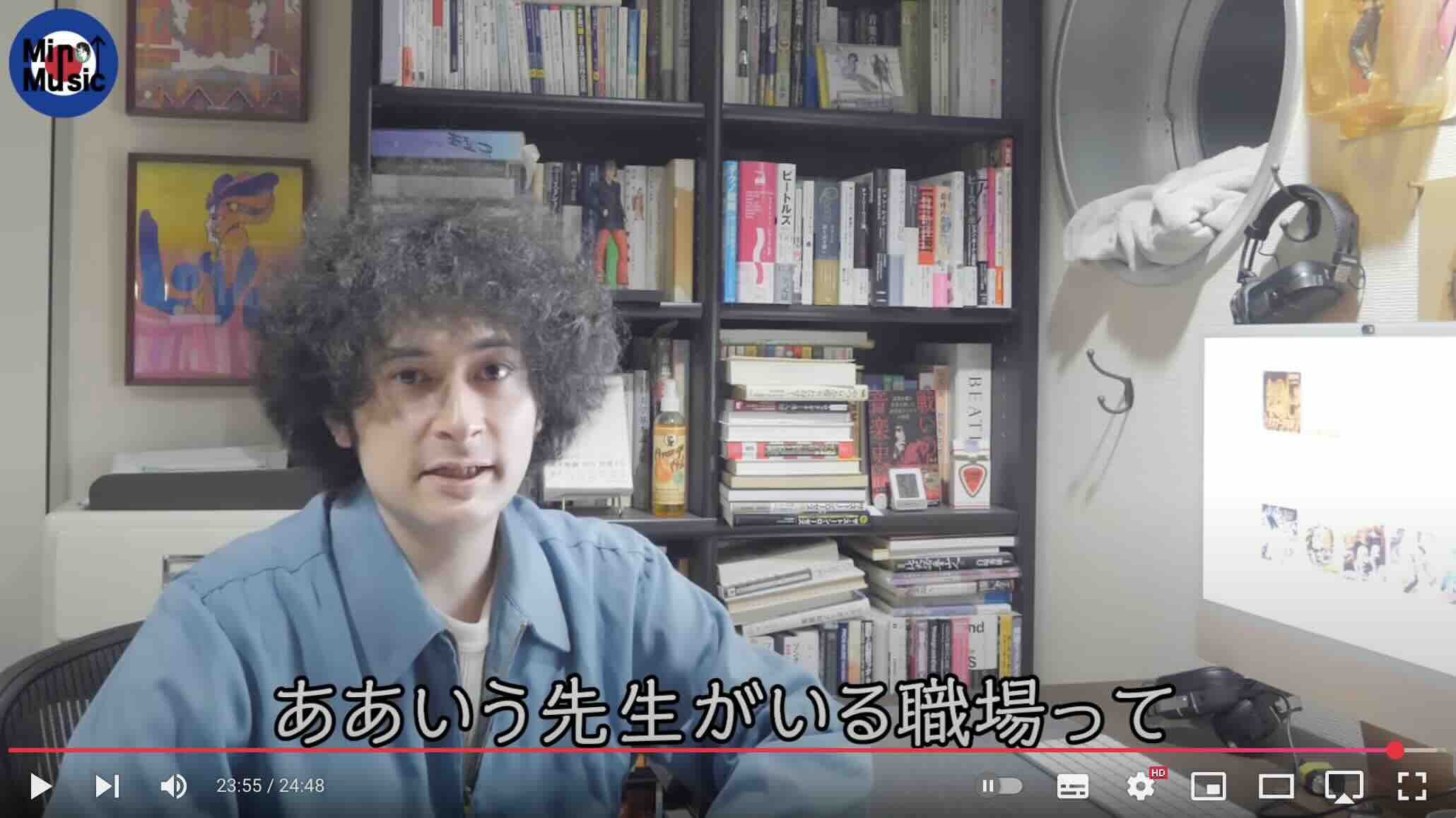 |
意図を汲んでいただけたようだ。 |
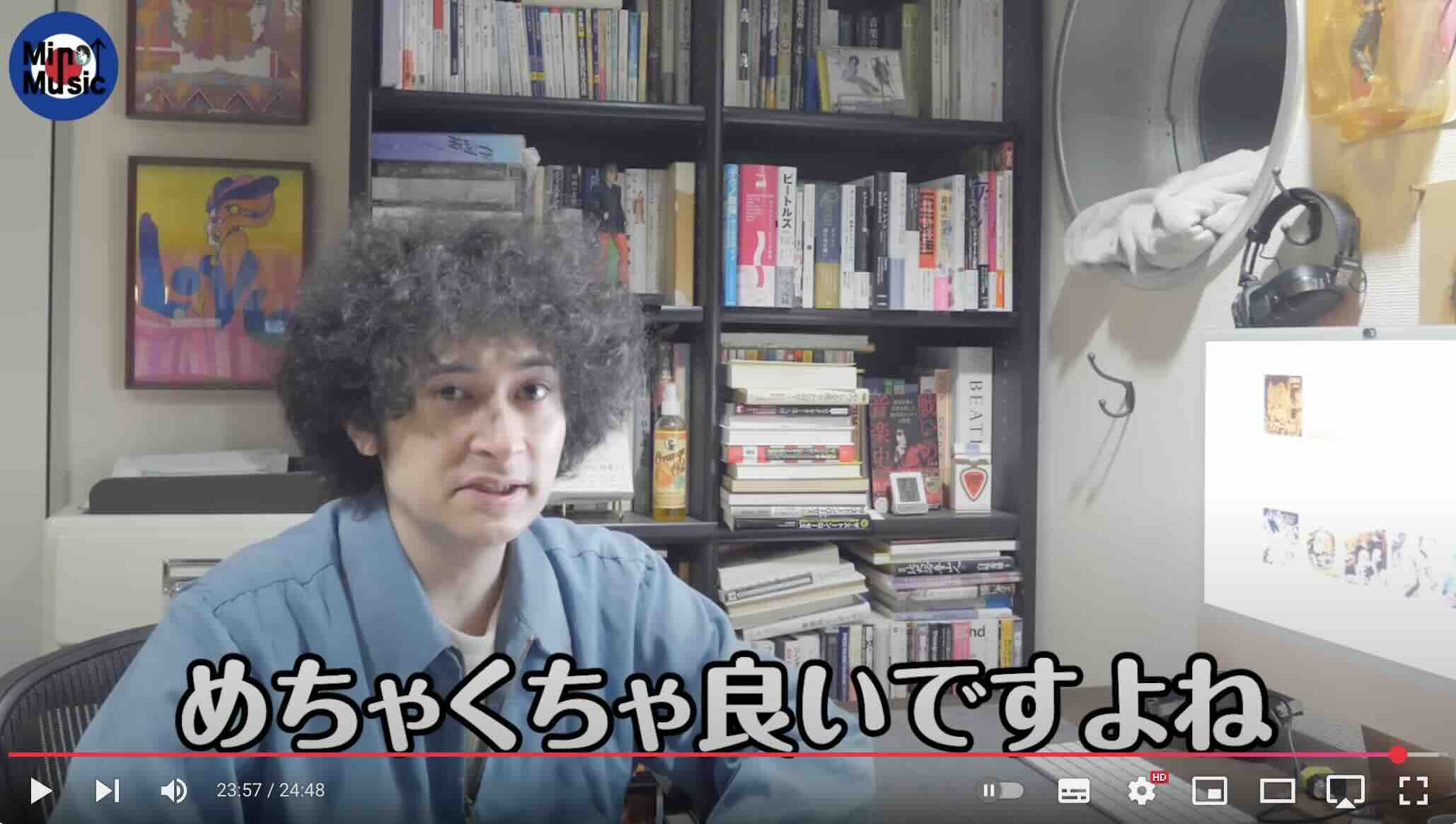 |
私自身はいいわゆる「頑張れソング」は好きではないが、図らずもそうなってしまった。 |
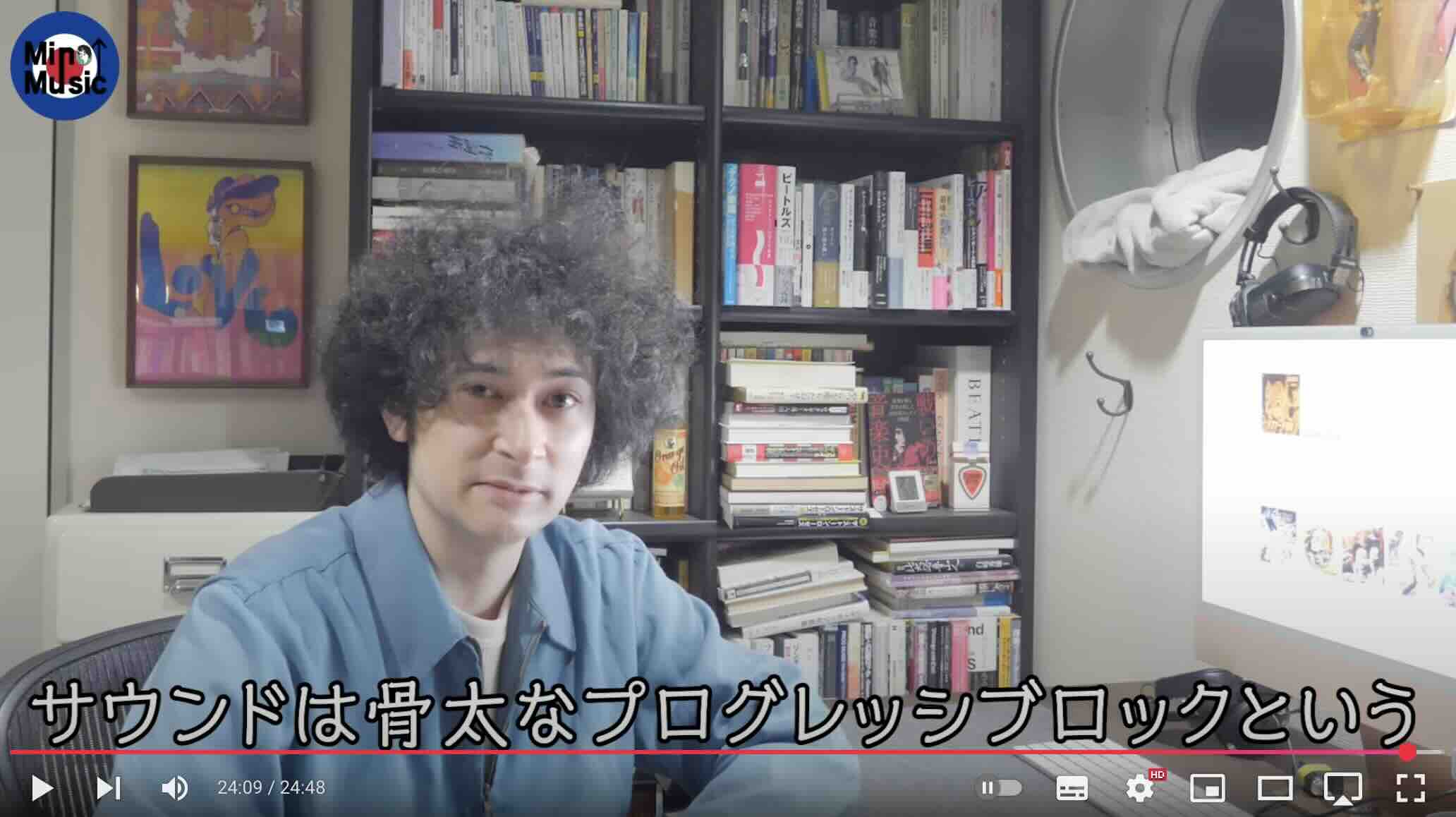 |
みのさんにこのように言っていただけると、本当にありがたい。 |
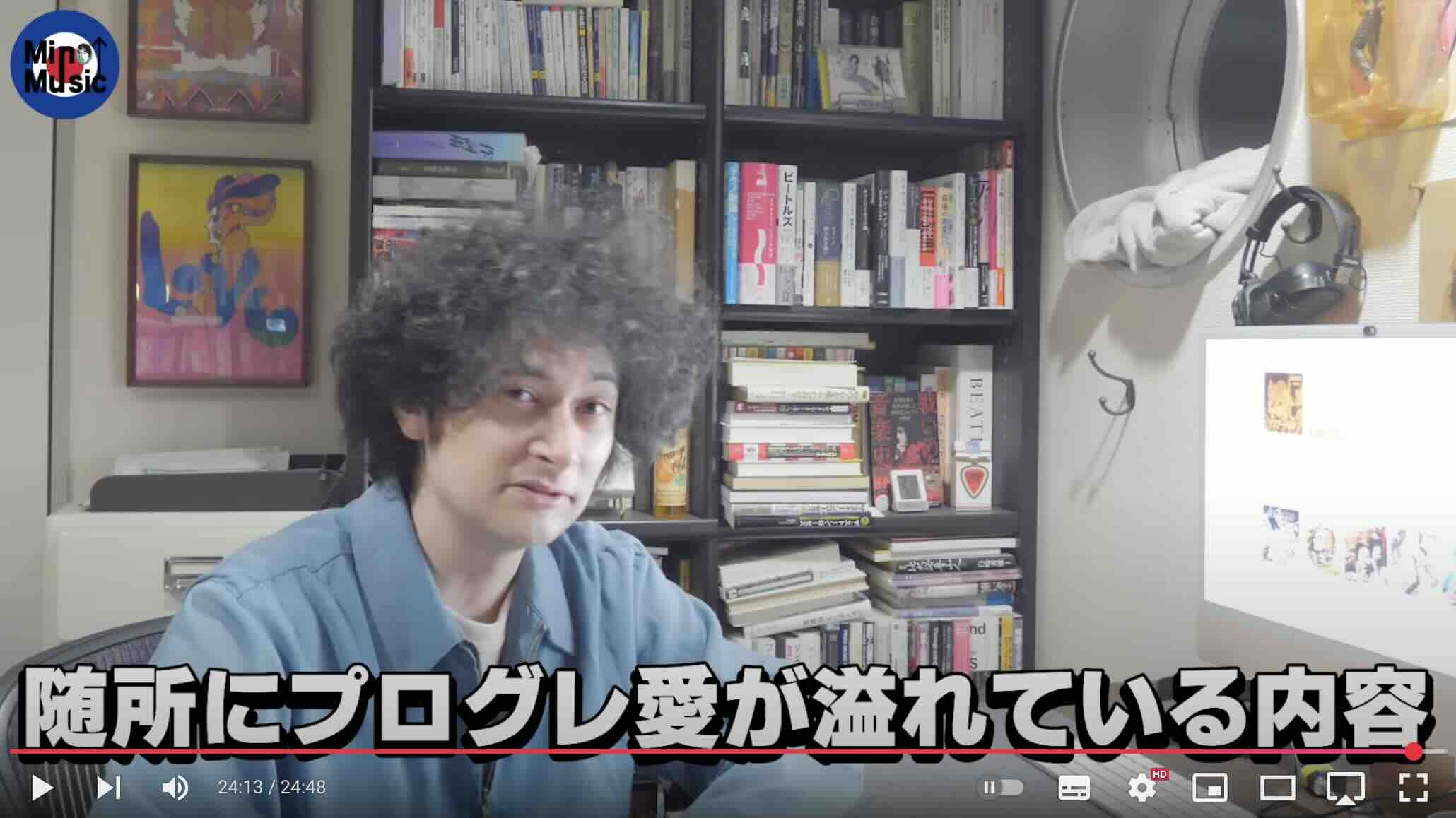 |
「プログレ愛」。いい言葉だ。今回はみのミュージックで紹介していただけたおかげで、多くの視聴者に観ていただけた。みの様、本当に、ありがとうございました! |
2025年3月26日(水)
黄砂来襲
 |
この2,3日は、黄砂が酷い。東山が霞んでいる。 |
2025年3月25日(火)
実験動物中央研究所の方々との打ち合わせと会食
 |
実験動物中央研究所(実中研)は多くの種類の実験動物を供給しているが、河本研では、ヒト組織の移植実験や、渡邊先生と小林さんが進めてきた人工リンパ節の実験などに、NOGマウス(重度の免疫不全マウス)やNOG-dKOマウス(NOGマウスでMHCクラスIクラスIIをKOしたマウス)などを使わせていただいてきた。そんな中、2年前から、ヒト人工リンパ節を使った共同研究を開始した(2023年4月25日の記事参照)。この日、その共同研究に関する打ち合わせを行い、その後大学近くのお店で会食。再生医療の現状などについてあれこれと話ができて楽しかった。 向かって右から伊藤亮治先生(実中研室長)、小林由佳先生(河本研特定助教)、渡邊武先生(河本研研究員)、中畑龍俊先生(実中研理事)、伊藤守先生(実中研前所長、理事)、私、片野いくみ先生(実中研室長代理)、金子凜先生(実中研研究員)。 |
2025年3月20日(木)ー22日(土)
第24回日本再生医療学会総会に参加
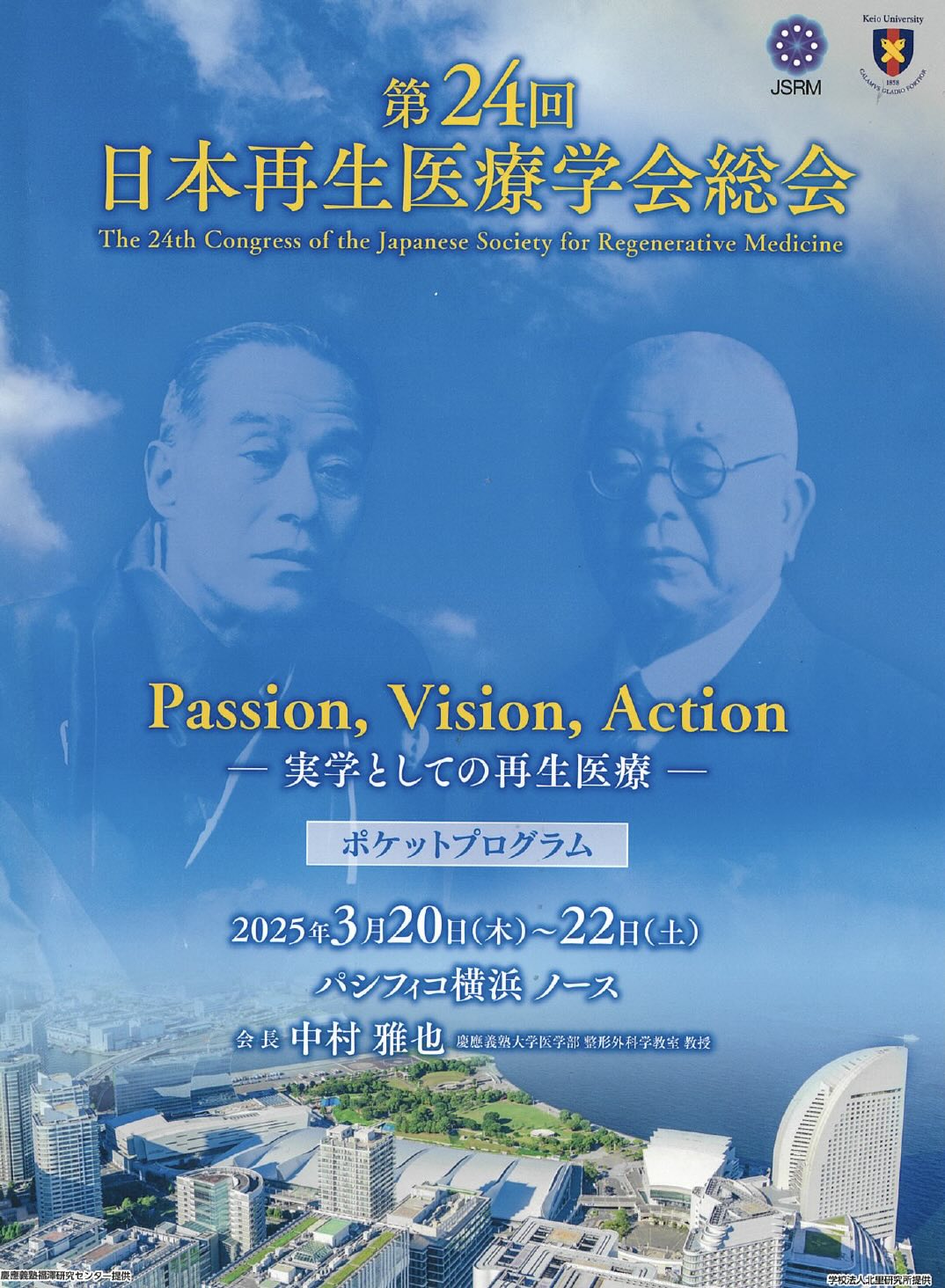 |
表記の会がパシフィコ横浜ノースで開催された。今回の集会長が慶應大学の整形外科の中村雅也先生ということで、ポスターは慶應色の濃いものになっている(福沢諭吉は慶應大学の創始者、北里柴三郎は慶應大学医学部の初代医学部長)。 |
 |
初日の早朝、京都では気温は0度で、玄関先の植木鉢の受け皿の中の水が凍っていた。 |
 |
パシフィコ横浜ノース。 |
 |
展示会場。多くの企業の出典で賑わっていた。 |
 |
横浜ベイホテル東急で懇親会。今回の学会の参加者は初日ですでに3500人を超え、懇親会も600人以上参加との事だった。 |
 |
集会長である中村先生による挨拶。初日の後イチに基調講演をされた古川俊治先生(参議院議員)も慶応大医学部出身で、中村先生と同期との事だった。再生医療学会の理事長である岡野栄之先生も慶應大医学部卒なので、今回は慶應大医学部色が濃い。 |
 |
山口大学の山本美佐先生(写真中央)と、小金丸理世さん(大学院生)。免疫学会の宣伝をさせていただいた。 |
 |
アトラクションでは、慶應大学の応援団とチアガールが、再生医療学会にエールを送ってくれた。 |
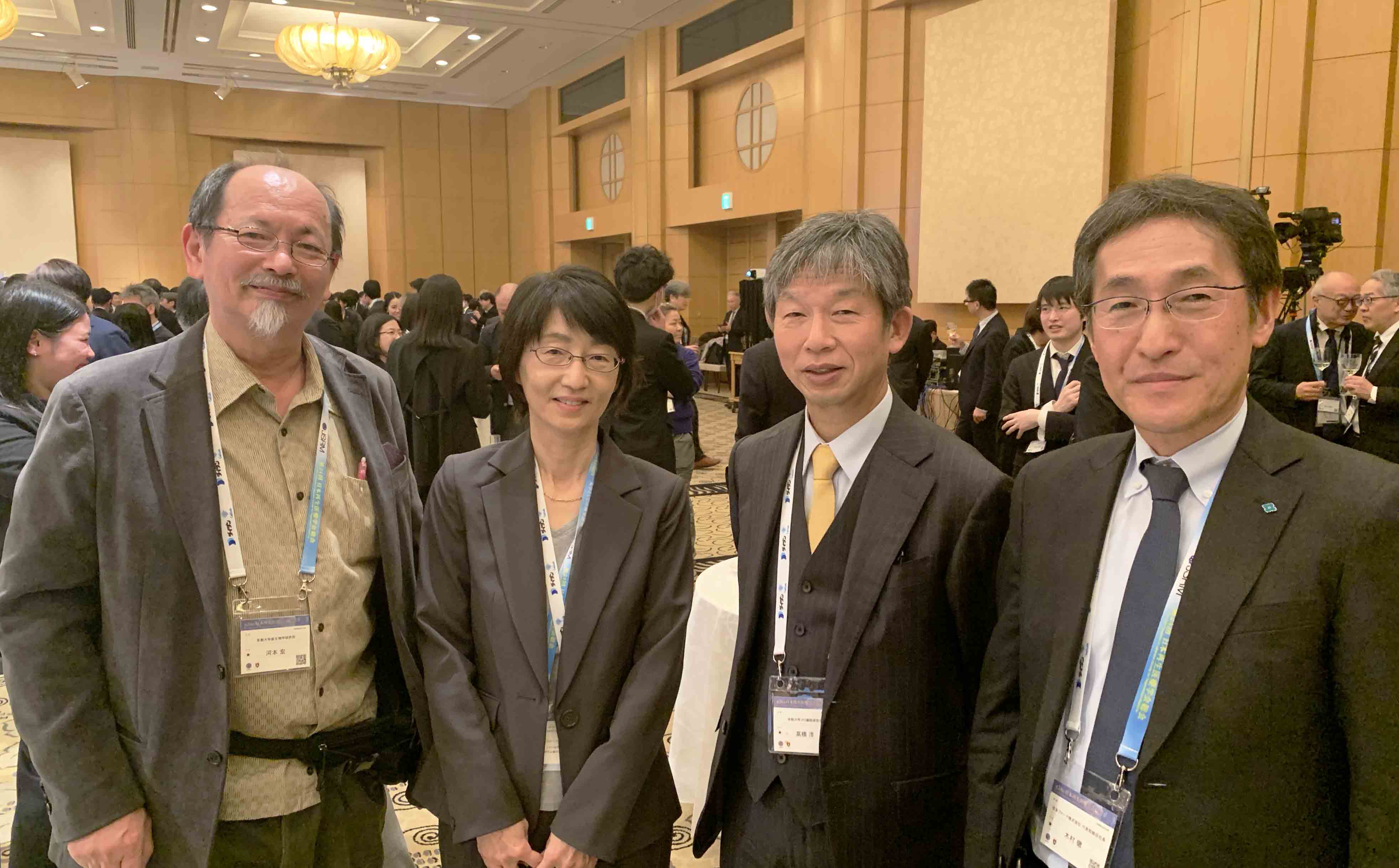 |
向かって右から、 木村 徹氏(住友ファーマCEO)、高橋淳(CiRA所長)、武田志津氏(日立製作所研究開発グループ技術長)、私。アメリカでのパーキンション病の治験に向けての準備状況などについて話を聞けた。 |
 |
来年の学術集会長を務める高橋政代先生(ビジョンケアCEO)による挨拶。 |
 |
ホテルに帰る途中の景色。 |
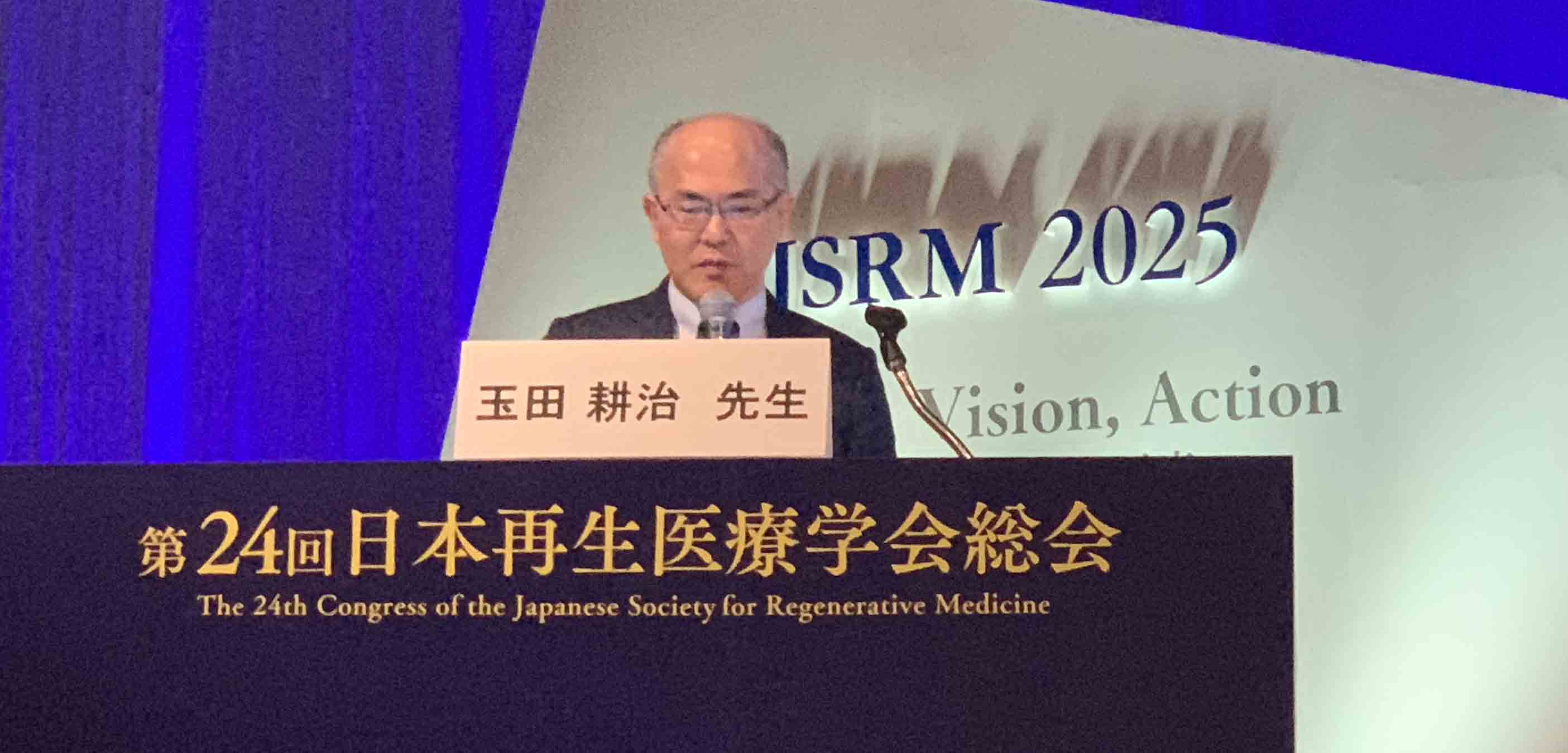 |
2日目、日立製作所が主催のランチョンセミナーで、玉田耕二先生の話が聴けた。 |
 |
2日目の夕方、一般講演のセッションで、板原君が発表。 |
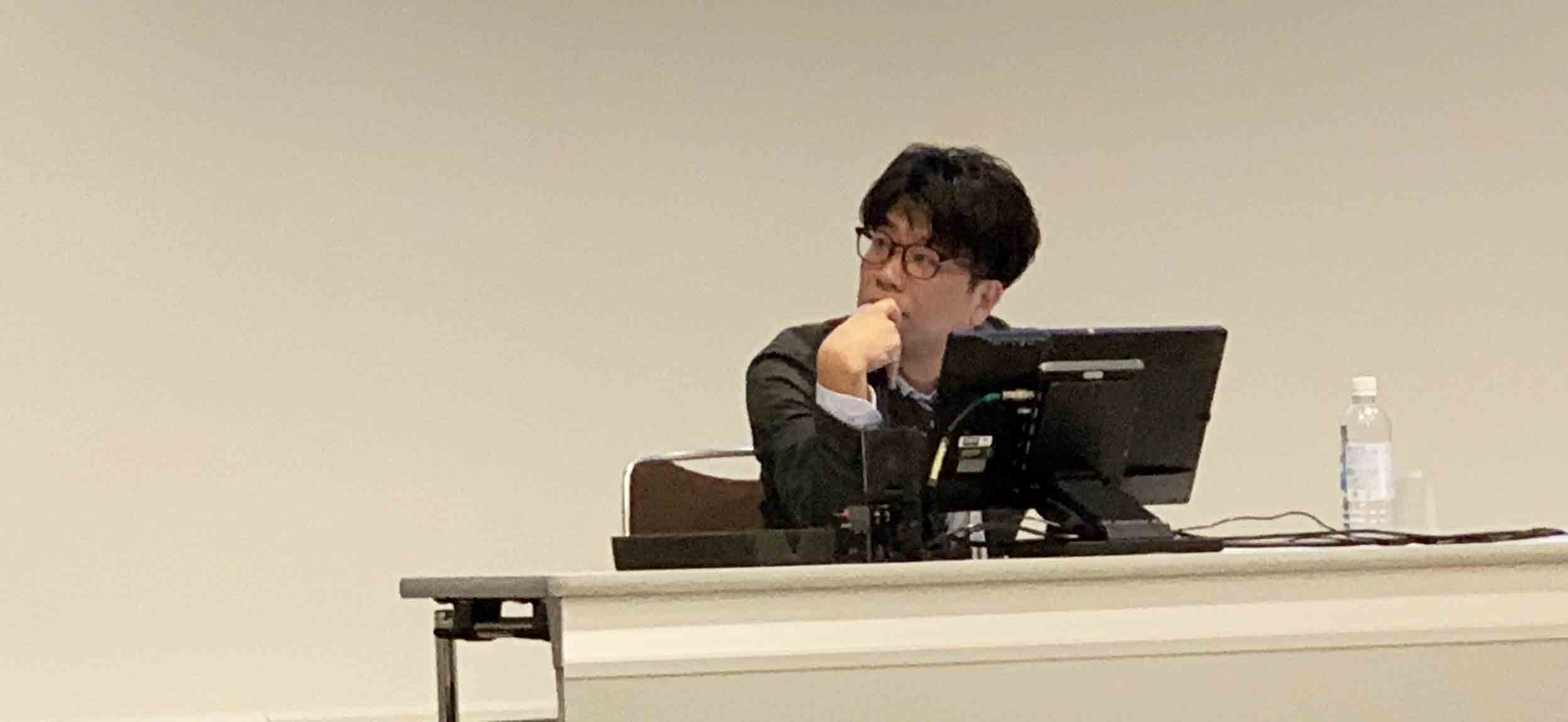 |
座長は山崎聡先生(東大医科研)。 |
 |
先端バイオ創薬(2019-2023年度)で開発してきた「超汎用化技術」を、初公開という形で紹介。移植組織/細胞において、汎用性を上げるためにHLAをKOすると、T細胞による拒絶は防げるようになる。しかし、HLAが失われたことをNK細胞が感知して、攻撃を始める。このNK細胞による攻撃を抑制するための新技術。再生医療全体に関わる可能性があるすごい技術だと自負しているが、この日の聴衆の反応はイマイチだった。 |
 |
板原君の発表終了後、桜木町の駅の近くの居酒屋で、慰労会。この研究に深く関わってきた増田さんも参加。 |
 |
「熱中屋」という店で、各種九州料理が美味しかったが、活きたサバを捌いて一尾まるまる使った刺身盛りが、とても美味しかった(税込4048円)。 |
 |
最終日、閉会式にて、再生医療学会の次期理事長の寺井崇二先生(新潟大学)から、現理事長の岡野先生へ、慰労の花束を贈呈。 |
 |
会の終了後、新横浜で日立製作所の方々と会食。今後の共同研究の進め方について打ち合わせをした。 |
2025年3月17日(月)ー19日(水)
ワクチン開発拠点の合同シンポジウム
 |
2022年から始まった先進的研究開発戦略センター(Strategic Center of Biomedical Advanced Vaccine Research and Development for Preparedness and Response : SCARDA)に含まれる拠点全てが集まる合同シンポジウムが、神戸国際会議場で開催された。昨年は京都で開催された(2024年1月31日の記事参照)。 |
 |
主な発表は一階のメインホールで行われた。 |
 |
フラッグシップ拠点の拠点長である河岡先生による挨拶。 |
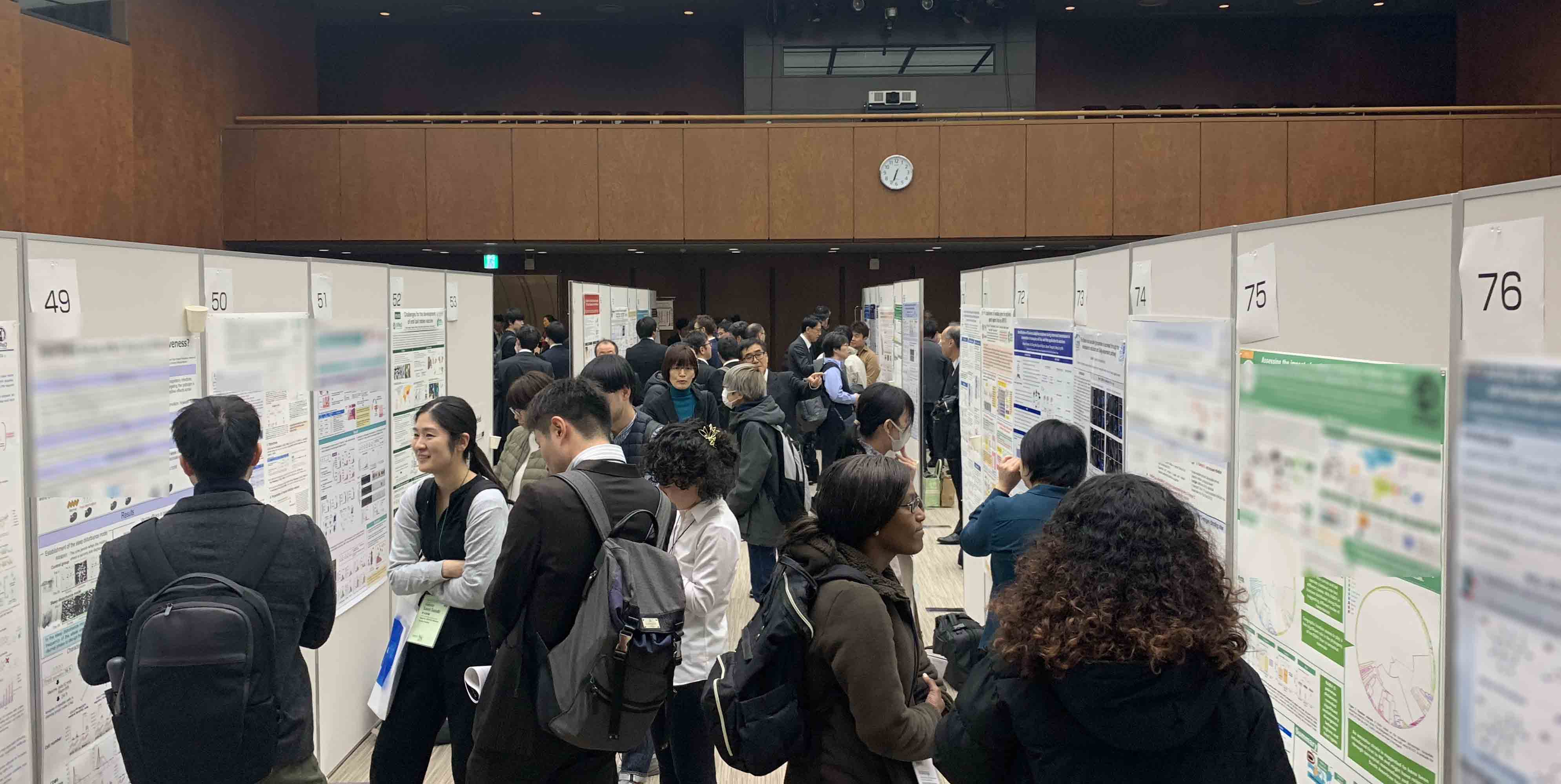 |
ポスター発表は3階の国際会議室。 |
 |
情報交換会はお互いの親睦を深めるために、いろいろな組織の人が混じる形でテーブルが指定されていた。写真は初日のテーブルで一緒だった人達。 |
 |
フラッグシップ拠点Utopia(東京大学)で広報を担当されている北原愛子さんと。北原さんは裏医生研チャンネルのファンであるそうで、「どうして更新が止まっているんですか?」と、最近新作を出せてないことを残念がっていただけた。私自身は続けたいところではあるが所内には様々な意見があり、現在は休止中。なお、Utopiaは以下のYouTubeチャンネルを運営されていて、定期的に新作動画があがっている。 東京大学 新世代感染症センター (UTOPIA) (YouTube): |
 |
宿泊したポートピアホテルの窓からの景色。 |
 |
二日目には小林さんの発表があった。ヒト型人工リンパ節の話。水痘に対する記憶B細胞を持っている人の場合、それらを免疫不全マウスに埋め込んだヒト型人工リンパ節で増幅して検出することができる、という話。 |
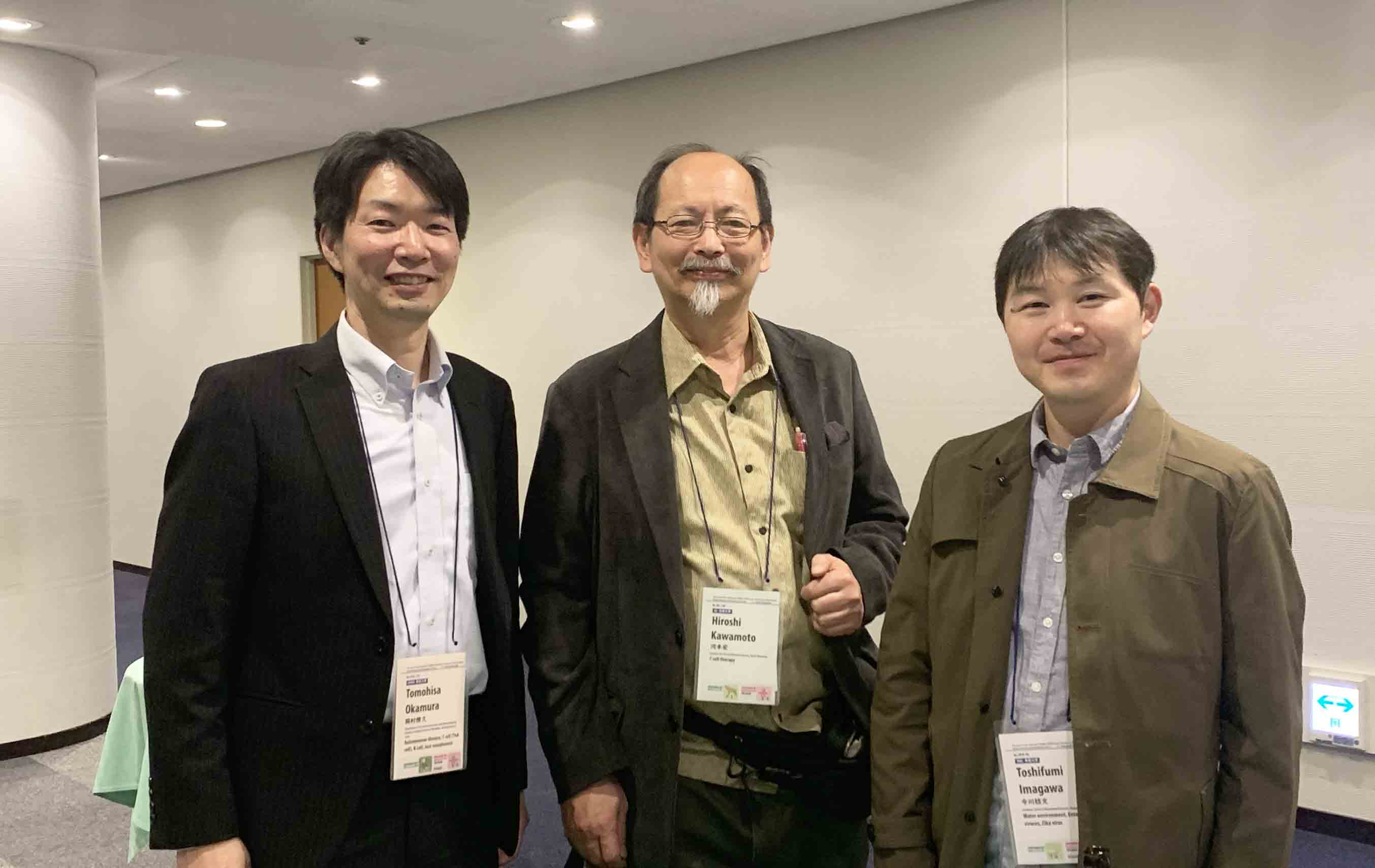 |
二日目の情報交換会の時に同じテーブルだった先生方。 |
 |
石井健先生(東大医科研、写真中央)、荒瀬尚先生(大阪大学微研)と。 |
2025年3月13日(木)
第2回LiMe Happy Hour
 |
一月に開催された第1回LiMe Happy Hour(2025年1月16日の記事参照)が好評であったので、第2回が開催された。今後、原則、奇数月に開催される事になる(ただし5月は新所員歓迎会、9月はリトリートがあるのでパス)。教員、研究員、大学院生だけでなく、テクニカルスタッフ、秘書さん、事務の方々も参加できる。教員は1000円、それ以外の参加者は参加費無料という気前のいい会だ。16時までという勤務形態の人が結構多いとのことから、今回は、新しい試みとして、16時から「喫茶タイム」が設けられた。左はポスター。私が昔描いたイラストを流用している。 |
 |
喫茶タイムの模様。賑わっている。ミスドのドーナツが供された。 |
 |
ネスカフェのドルチェグストというカプセル式コーヒーメーカーで、カフェラテやラテマキアートなど、スタバのような一杯を楽しめる。 |
 |
17時からはアルコール類が解禁。 |
 |
前回はオードブルの調達や焼きそばの材料の準備などは河本研で行ったが、今回は幹事役の人達にお任せ。焼きそばは、美味しいのにとても安く(一人前200円程度)、こういう会にはうってつけだ。 |
 |
もう一つのホットプレート。 |
 |
皆、楽しそうだ。 |
 |
会は19時にはきっちりと終了。後片付け後、幹事+有志で私の教授室で二次会(反省会)。今回も70人くらいの参加があったとのこと。楽しかった。 |
2025年3月10日(月)
研究連携基盤所長・センター長懇談会歓送迎会
 |
表記の会がブライトンホテルで開催された。京大には18の附置研究所とセンターがあり、連携基盤はそれらで構成される。例年3月には歓送迎会が行われる。 |
 |
辻井敬亘先生(化学研究所)は3年間基盤長を務められたが、今年度末で辞められるということで、挨拶をされた。私が所長になってからはずっと辻井先生がされていたので、何だか寂しく思う。 |
 |
向かって左から次期基盤長を務められる中野伸一先生(生態研所長)、青木愼也先生(基礎物理学研究所長)、時任宣博先生(京大副学長)、私。 |
2025年3月3日(月)
バンコクで開催された幹細胞学会に参加
 |
9th Annual Meeting of the Society for Stem Cell Researchという会がバンコクで開催され、その会でキーノートスピーカーとして招待された。主催はSiriraj (シリラートと読む)Center of Excellence for Stem Cell Research (SiSCR)という組織で、Mahidol (マヒドンと読む)Universityの中の幹細胞医療を担っているグループ。もう一人のキーノートスピーカーはシンガポールのA*STARのJonathan Yuin-Han Loh。私は、タイは初めてなので、楽しみにしていた。 |
 |
プログラム。 |
 |
3月2日日曜日に、関空11時発のタイ航空便で、6時間45分かけてバンコクのスワンナプーム空港に到着。時差が2時間あるので到着はタイでは15時45分。空港に降り立った時の気温は35℃で、蒸し暑い。研究員二人が空港まで車で迎えに来てくれた。市内までは車で40分くらい。写真はこの日に泊まったホテル(Theater Residence)のロビー。会場から歩いて10分程度のところ。 |
 |
ホテルの中庭。 |
 |
部屋。 |
 |
部屋から東側を望んだ景色。チャオプラヤー川が見える。 |
 |
ホテルのすぐ近くのSupatra River Houseというレストランに招いていただいた。チャオプラヤー川に面したテラスで会食。向かって右側からPhatchanat Klaihmon(SiSCR研究員)、Sudjit Luanpitpong(SiSCR, PI)、私、Parinya Samart (SiSCR研究員)。PhatchanatとParinyaは、空港に迎えに来てくれた二人。この日と翌日はこの二人がずっとアテンドしてくれた。 |
 |
青菜の煮物と、トムカーガイという鶏肉のスープ。トムカーガイはココナッツミルクがベースで、少し酸味があり、スパイスは効いているがそう辛くなく、とても美味しかった。 |
 |
パッタイ。平べったいライスヌードルを使った焼きそば。味が濃くて、美味しい。 |
 |
ヤムトゥアプーという四角豆を使ったサラダと、トムヤムクン。トムヤムクンはトムカーガイよりはかなり辛かったが、十分美味しく食べられた。 |
 |
四角豆のアップ。少し苦味があるが、いい味だった。 |
 |
四角豆の写真。Wikipediaより拝借。 |
 |
食後、ナイトマーケットに連れて行ってもらうことになった。車に向かう道中、西の空に浮かぶ三日月が目に入った。この三日月の見え方には、少し違和感を感じた。日本は緯度が高くて黄道(太陽が通る経路、月も基本的にはこれに沿って動いている)が傾いているから、夕方に西に見える三日月は右下が光っているが、タイは緯度が低いので、写真のように左下が光っていることもあるという事であろう。 |
 |
チャイナタウンの近くのナイトマーケット。 |
 |
Sudjitの車で行き、PhatchanatとParinyaが案内してくれた。 |
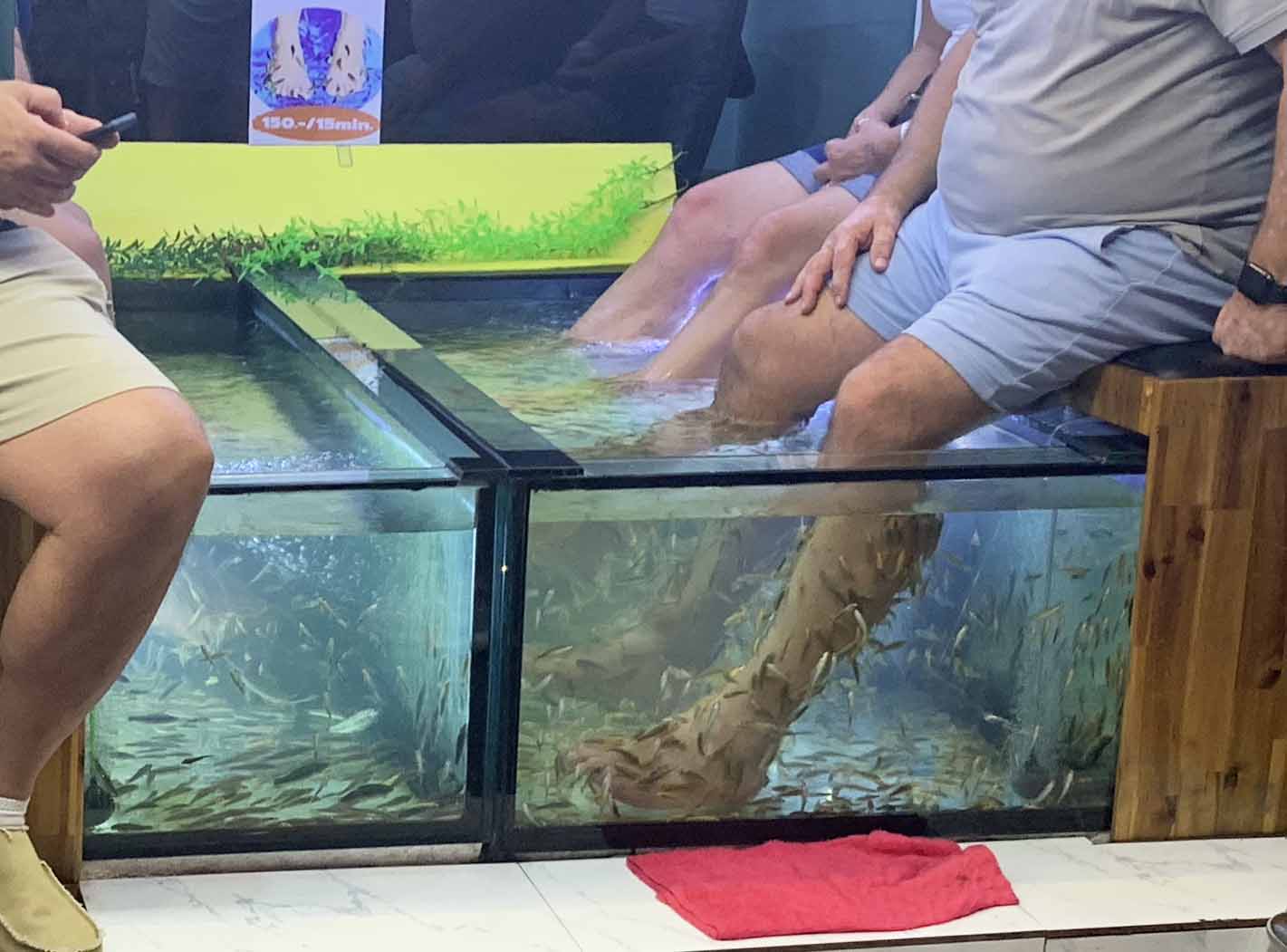 |
ドクターフィッシュ(正式名ガラ・ルファ)に足の角質層の掃除をしてもらう店があった。15分で200バーツ(800円)くらいとのこと。 |
 |
タイ式マッサージの店もあった。案内役の二人に勧められたが、私は普段から肩こり、腰痛、頭痛などがなくてマッサージを必要としない上に、体の柔軟性がとても乏しいので、ストレッチを強要されると痛そうに思えて、遠慮した。 |
 |
前期のレストランで完食したのでほぼ満腹状態ではあったが、せっかく来たので何か食べようと思ってあれこれ見ていたら、昆虫食の屋台に出くわした。 |
 |
サソリ。タガメも散見される。 |
 |
バッタ、芋虫、何かの蛹など。右上端はGと思われる。 |
 |
さすがにGを試す気にはならなかったが、サソリならいけそうに思えた。50バーツ(200円)だったと思う。貴重そうに思えるのに、意外に安い。注文すると、スプレーで醤油らしきものをかけてくれて、さらにスパイスらしきものをふりかけてくれた。 |
 |
変な臭いや妙な味はなく、パリパリとした食感で、結構美味しかった。かつて油で揚げたサワガニを丸ごと食べることがあったが、それに似た味だった。 |
 |
ホテルへの帰路は、トゥクトゥクに乗せてもらった。 |
 |
屋根の部分に掴まる手すりはあるものの、窓はないし、シートベルトもしない状態で、他の車に混じって大通りを50-60kmで走行するので、中々のスリルを味わえた。初日から、タイを満喫できた。 |
 |
ホテルに帰着後、部屋からの夜景。 |
 |
朝の景色。 |
 |
シリラート(Siriraj)病院。「Siriraj」と書いて日本語では「シリラート」と読むようだ。マヒドン大学の附属病院という位置付けであるらしい。今回の会場はこの病院の敷地内にあった。この病院の開設は1988年とのことで、タイでは最古の病院。京大病院の開設が1989年(2024年12月21日の記事参照)だから、1年だけではあるが京大病院より古いことになる。病床数は3000床もあるらしい(京大病院は1131床)。 |
 |
病院の中庭で、Loh先生と。 |
 |
受付。 |
 |
会場の入り口付近には実験機器類のメーカーが展示をしていた。 |
 |
会場。大学院生や研究員が聴きに来ているとの事であったが、全体に女性の割合が多い(8割くらい) という印象だった。 |
 |
マヒドン大学名誉教授でSiSCRのPresidentであるSurapol Issaragirisil先生による開会の辞。 |
 |
私は最初のスピーカーとしてのお務めを無事に終えた。写真は、演者用に用意された会食での料理。左端は、前出のトムカーガイ。真ん中の魚は、スズキだったと思う。 |
 |
料理(2)。 |
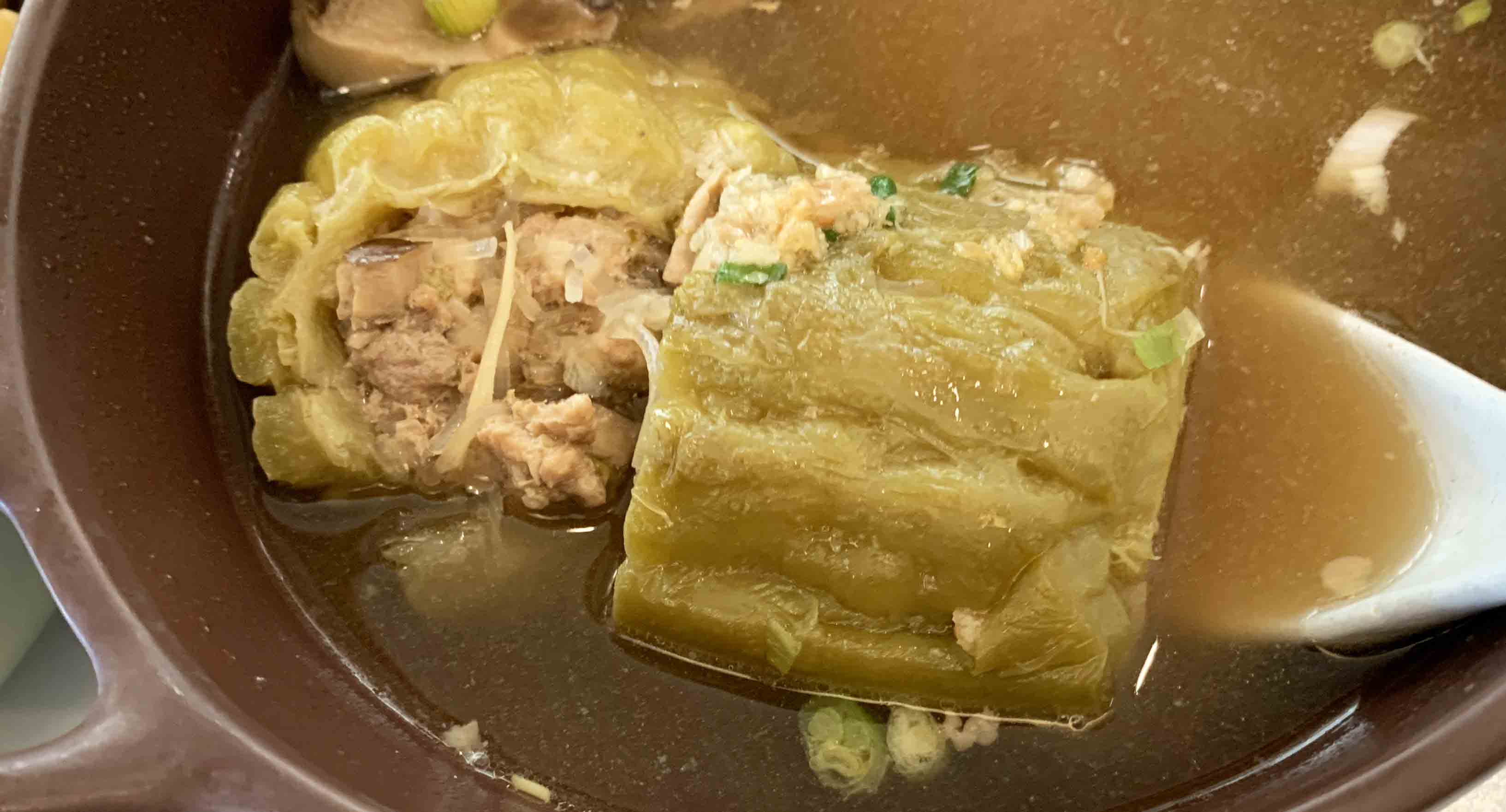 |
上記写真の手前の料理はニガウリ(ゴーヤ)のようなウリの肉詰め。ちょっと苦くて、美味しかった。 |
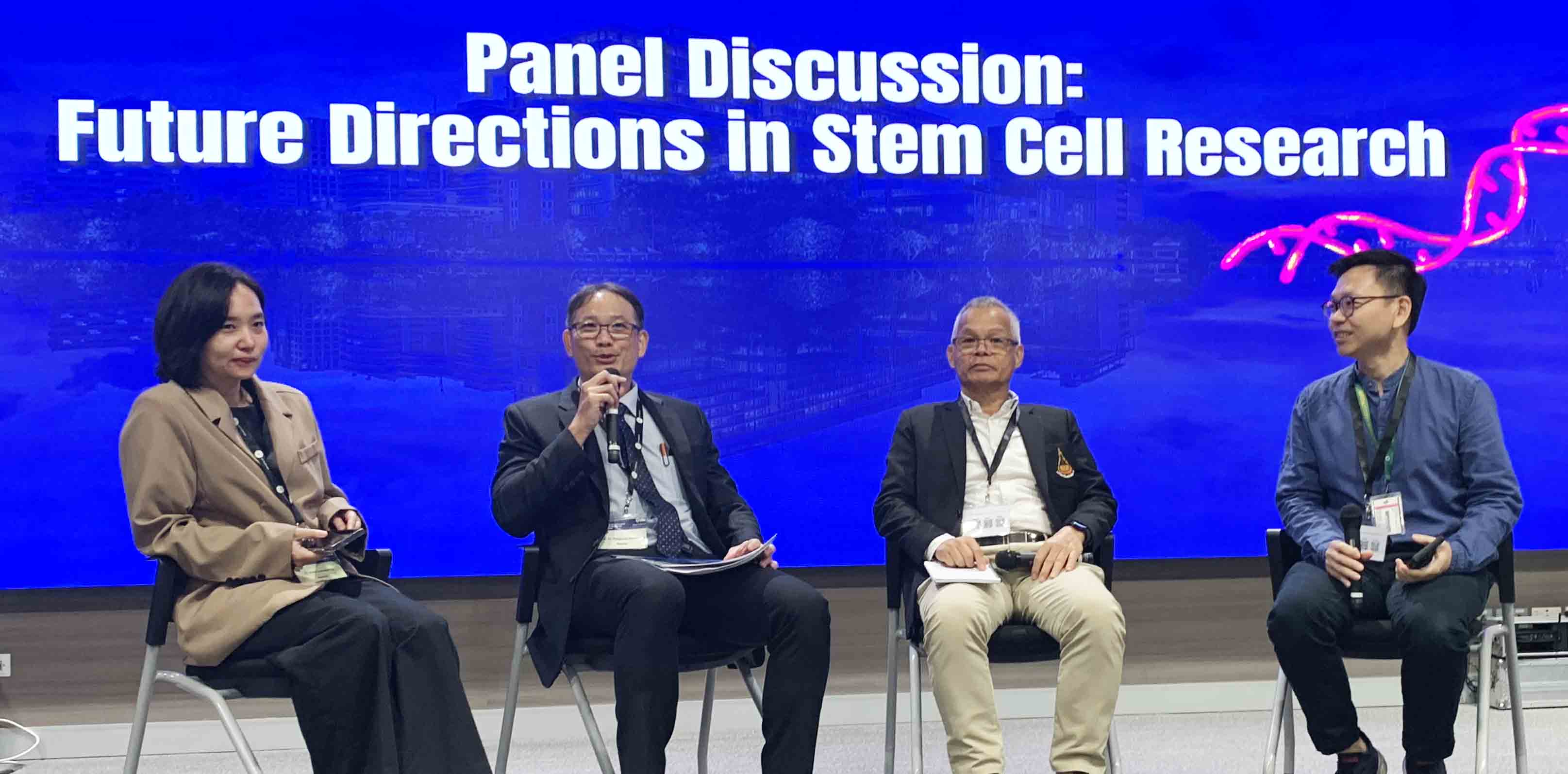 |
午後の最後は、幹細胞医療の未来についてのパネルディスカッション。タイでもiPS細胞を使った再生医療は進められているが、先行する間葉系幹細胞を用いた戦略が軸になっているようだった。 |
 |
SiSCRの関係者の人達で記念写真。 |
 |
シンポジウムは16時半頃に終わり、夕食はホテルのロビーに18時に集合との事。 ホテルに帰る途中、コンビニに立ち寄った。おにぎり(30バーツ=120円)や、その上のご飯(15バーツ=60円)の値段からすると、物価は日本の3分の2くらいか。 |
 |
夜食用のお酒を買おうと思ったら、セブンイレブンには置いてなかった。近くの商店では売っていると聞いてその店で購入しようとしたが、購入は17時まで待たなければならなかった。写真は10分ほど待ってから購入したところ。腕時計は日本時間のままにしているので19時を指している。 |
 |
会食までに時間があったので、病院とホテルの間にあるワンラン市場を散策することにした。ワンラン市場は朝から18時ごろまで開いている市場で、日用品や食品を売っている。この時はまだ閉店前だったので、あれこれ見て周れた。 |
 |
ワンラン市場にて、油で揚げた魚を売っている店。 |
 |
会食は、車で15分くらいの、「Methavalai Sorndaeng (メタワライ・ソンデーン) 」という、1957年創業の老舗タイ料理レストラン。ミシュランの星も獲得しているようだ。 |
 |
記念写真。 |
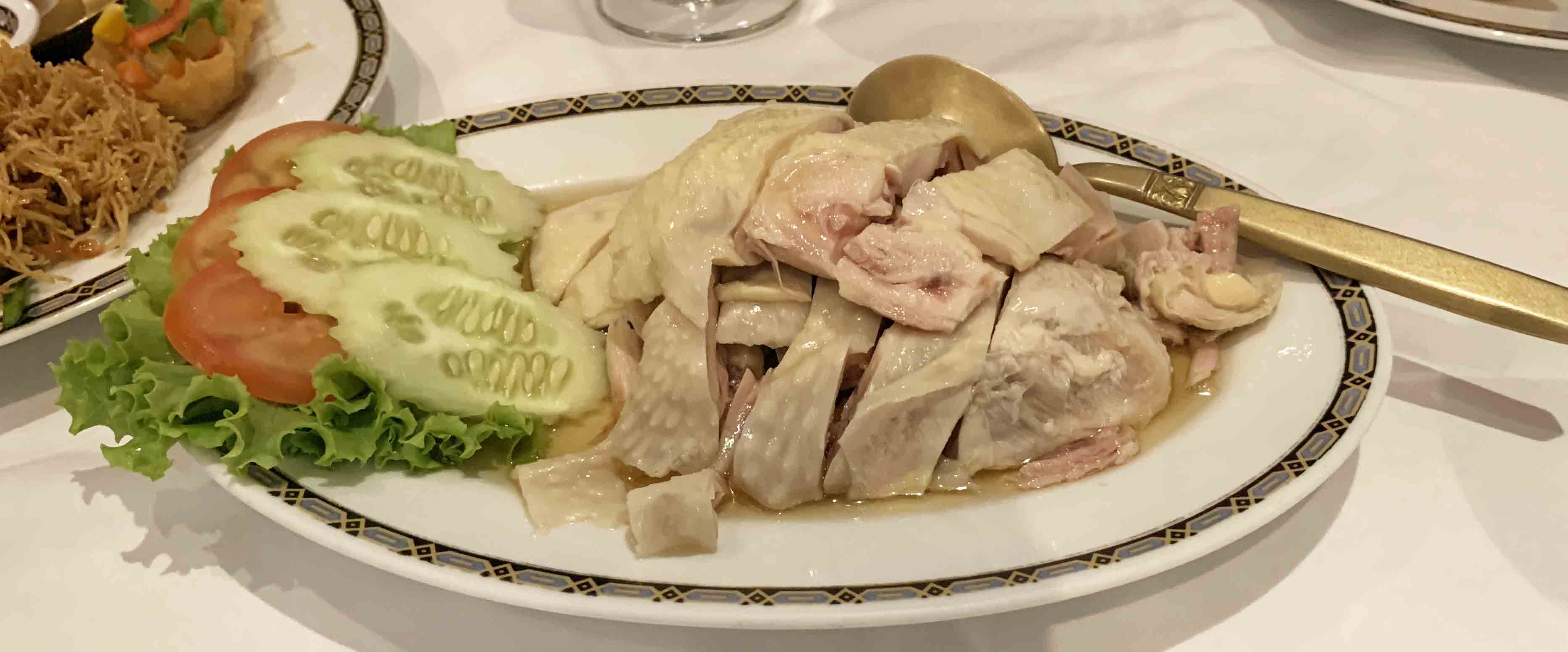 |
蒸し鶏。美味しかった。 |
 |
デザートで出されたマンゴーと餅米ケーキ。定番スイーツの一つとのこと。「カオニャオ・マムアン」というらしい。もち米の部分はココナッツミルクで甘く味つけられていた。サクラモチの外側のような感じの食感で、とても美味しかった。 |
 |
レストランの前にある民主記念塔。1932年の民主化を記念して1939年に作られた記念塔とのこと。 |
 |
ホテルに帰る途中で、車から派手な電飾のお祭りが見えた。聞けば病院のすぐ横の寺院のお祭りだとかで、年に1回、1週間くらい、食べ物や、日用品を売る雑貨店が並ぶ夜店として開催されるらしい。9時前にホテルに戻ってから、一人で繰り出した。ホテルからは歩いて10分くらい。全体にやたらと明るく、カラフルな蛍光灯が印象的だった。 |
 |
移動遊園地のような装置も設置されていた。基本的には子供の頃に見たお祭りや夜店のような懐かしを感じた。しかし、一方で、会場には念仏のような声がスピーカーで流れ続け、あちこちから音楽も鳴り響き、会食でのアルコールが残っていた事も手伝って、この世のものとは思えない感覚にとらわれた。ふと「自分は実は事故か病気で死にかけていて、これは死ぬ直前に見る夢なのでは」と思ったりした。こんな感じで勝手にトリップできる貴重な場所ではあったが、ただし、寺院のお祭りということで、残念ながら敷地内ではお酒は売っていないとのことだった。 |
 |
荘厳な感じの寺院の脇でブタやカバのマンガキャラの電飾がクルクルと回っている。尋常じゃない。 |
 |
日本のそれとそっくりの金魚すくいがあった。 |
 |
射的もあった。日本のものより的が遠い。 |
 |
メリーゴーラウンド。 |
 |
陶磁器も売られていた。20バーツは80円だから、安いように思える。 |
 |
写真の真ん中に写っているお坊さんが、マイクを使ってずっと念仏を唱えていて、それが会場中にずっと響き渡っていた。 |
 |
お寿司らしきものも売っていた。下段のハーフサイズのお寿司は1個5バーツ(20円)、上の段は1個10バーツ(40円)。さしみなどの高そうな素材は使ってないようであるが、それでも安く感じる。 |
 |
6個買った。40バーツ(160円)。 |
 |
会場の中ではステージでタイの曲を歌うライブも開催されていた。 |
 |
爆音が鳴り響く中、座り込んでお寿司を食した。結構美味しい。「ここはどこ、私はだれ」感が溢れてきて、心地いい。 |
 |
その後も敷地内を散策。ウズラと思われる鳥の丸焼きが売られていた。 |
 |
アップ。美味しそうだ。35バーツ(140円)。安い。 |
 |
一つ購入した。いくつかに切り分けられて、袋に入れた状態で渡された。店の奥のテーブルで、他の店で買った焼きおにぎりのようなものと一緒に食した。どちらも、とても美味しかった。 |
 |
12時前に帰路についた。写真は夜のワンラン市場。 |
 |
翌朝。ホテルの朝食会場。 |
 |
チャオプラヤー川に面したテーブルで朝食。 |
 |
3月4日の午前中は、SiSCRのメンバーと打ち合わせ。向かって左からChuti Laowtammathron(PI)、Chanchao Lorthingpanich(PI)、Sudjit Luanpitpong(PI)、Pakpoom Kheolamai(Professor)、Surapol Issaragrisil(President)、Phatchanat Klaihmon(Researcher)、私、Jonathan Yuin-Hun Loh(A*Star Professor)、Parinya Samart(Researcher)。Chanchaoさんは今回の訪問についてのメールでのやり取りを担当されていた。 |
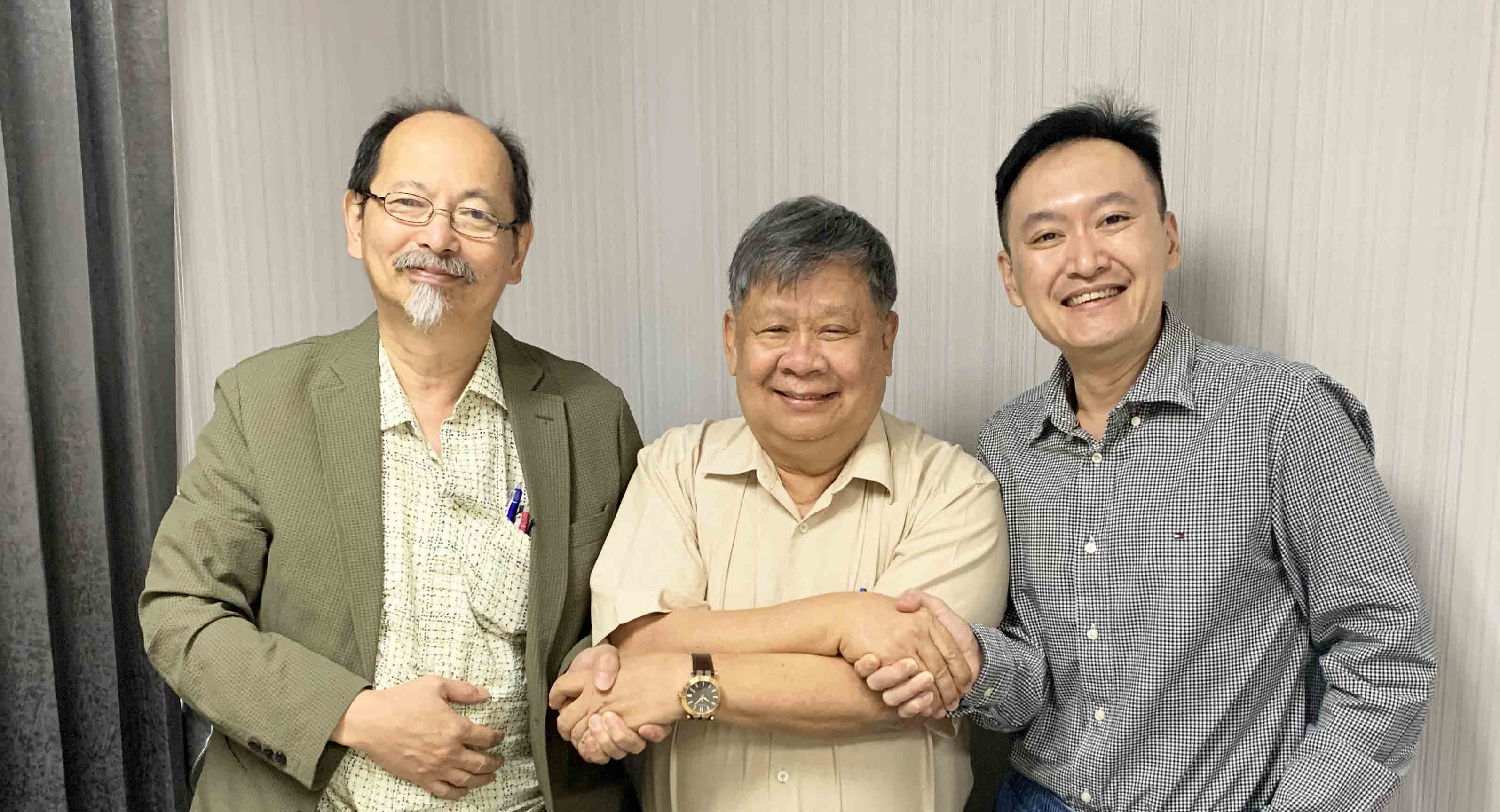 |
今後も3者でオンラインワークショップを催すなど、交流を続けようという事で合意。 |
 |
その後、いくかのラボを見学。Dr.Thidathip Wongsurawat(Siriraj Long-Read Lab)のラボでは、ナノポアを使ったシークエンス機器類を見せてもらった。 |
 |
研究室からは昨夜お祭りが開催されていた寺院が見えた。 |
 |
病院内のレストランで昼食。グリーンカレーを食した。 |
 |
病院のロビー。 |
 |
午後、空港に行くまでの時間に少し市内を観光。私のリクエストに応えて、スタッフの人が、近くのワット パークナム パーシーチャルーンという寺院に連れて行ってくれた。 |
 |
階段を上がっていくと、最上階では仏陀の生涯図(仏伝図)の天井画を観ることができる。 |
 |
近づくと、エメラルドグリーンに輝く荘厳な天井が観えてくる。映えるスポットとして人気があるらしい。 |
 |
近くで見上げると、吸い込まれそうになる。 |
 |
この日の午後に、案内役をしてくれたスタッフの方々。 |
 |
夜は何とかうろつくことができるが、お昼は日本の真夏と同じでとても蒸し暑く、歩き周るにはきつい。前記の荘厳な天井も、暑くてあまり長いことは居られなかった。喉が渇いたので、ココナッツジュースを飲んだ。採取したての原液だったようで、美味しかったが、少し青臭かった。 |
 |
この寺院の見どころの一つである真鍮製の大仏は、あいにく修復中だった。それでも大きさは十分わかる。69mあるらしい。 |
 |
ワットパークナムを観覧後、ルンピニー公園まで車で送っていただいた。この後は単独行動。この公園は街のど真ん中だが、ミズオオトカゲが生息している事で有名。写真の彫像は、ルンピニー公園の開園を記念して建てられた国王ラーマ6世の歴史的な像で、1942年建造とのこと。 |
 |
公園内の池。もっと周囲に草むらなどの自然が残してあるかと思っていたが、隅々まで刈り込まれていて、こんなところにオオトカゲがいるのかと訝った。 |
 |
暑かったので大変だったけど、せっかく来たので左図のように一通り周ってみることにした。 |
 |
実際、池の周辺の道を歩き始めると、すぐに見つけることができた。和名は「ミズオオトカゲ」であるが、よく「サルバトールモニター」と呼ばれているようだ。「サルバトール」というのは学名で、「モニター」というのはオオトカゲという意味。泳いでいる個体、岸をのっしのっしと歩いている個体、のんびりとしている個体など、様々だった。動画を何本か撮って繋いだので興味がある人はご覧いただきたい。 ルンピニー公園のミズオオトカゲ(泳ぐ、岸に上がる、岸辺を歩く、岸から水に入るなどの様子を収めた1分20秒の動画): |
 |
カメとのツーショット。アカミミガメと思われる。 |
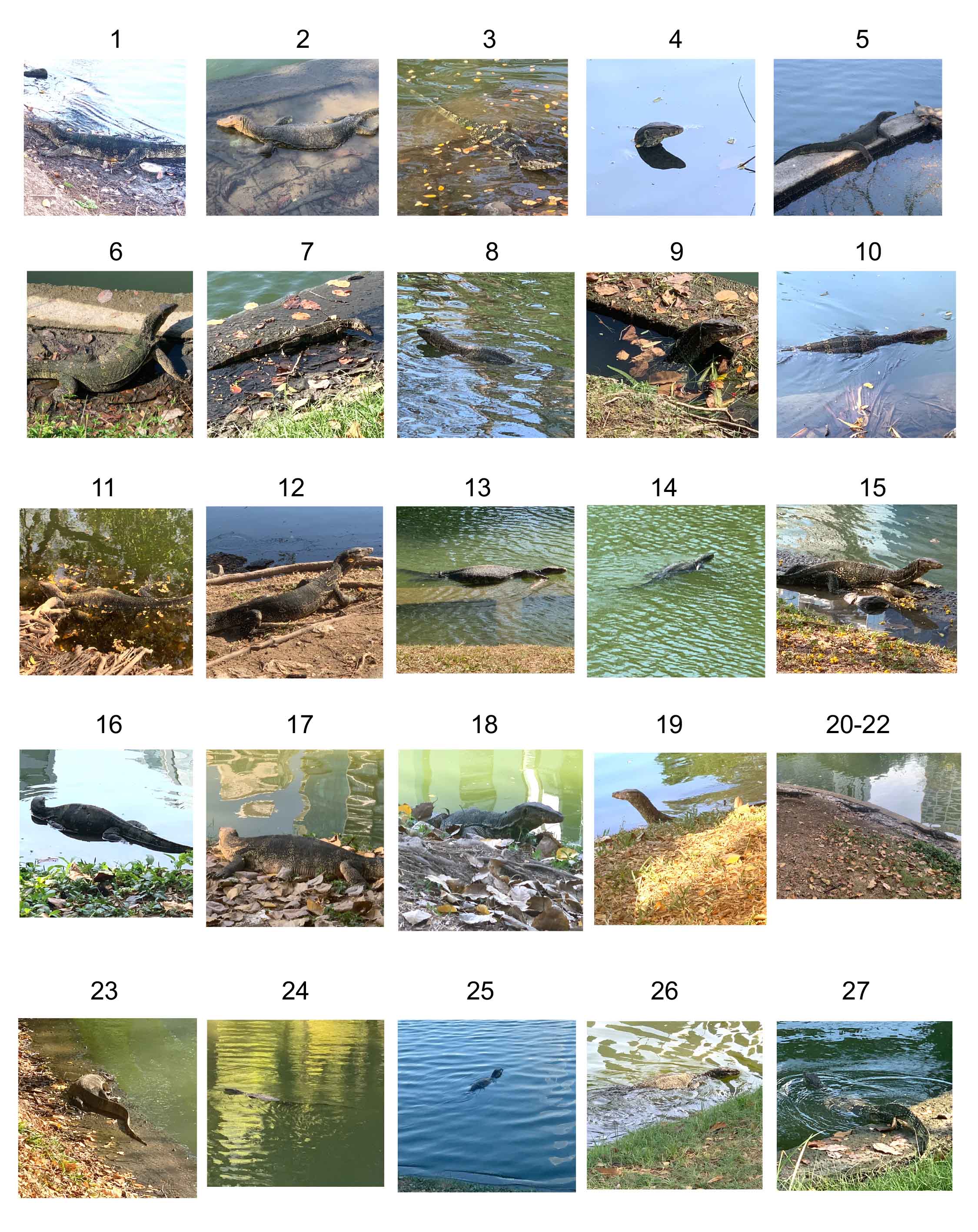 |
前述のルートを周るのに、約1時間かかった。その中でオオトカゲを何匹見れるかを、写真を撮りつつカウントしたところ、左のように27匹だった。同じ個体をカウントしている可能性はあるが、何であれ、池を一回りしたら沢山みることができるということは確かだ。 なお、「ちゃんねる鰐」という生き物系YouTuberがこの公園で見たオオトカゲの様子をおもしろおかしく紹介している動画あるので、興味のある人はどうぞ。ちゃんねる鰐「タイで野生のオオトカゲの尻尾打ちを食らってみた」: |
 |
電車に乗ってサイアムという駅で下車し、まずはサイアムスクエアという商業施設へ。 |
 |
次にその近くのMBKセンターという巨大なショッピングモールへ。 |
 |
MBKセンターの吹き抜け。 |
 |
平日(火曜日)の夕方だったが、すごい人だった。 |
 |
ルンピニー公園を歩き回って汗だくになり、かなりの脱水状態であったので、MBKセンターの入り口近くで、生ビールが飲めそうな日本式の居酒屋に入った。メニュー表を見ると、日本よりやや安いくらいか。 |
 |
17時すぎだったので、まだ店はすいていた。1リットルの生ビールが体に染み込んだ。夕食として、シラス丼、エビの天ぷらを食した。この後電車でパヤタイという駅に行き、そこから空港線でスワンナプーム空港へ。23時59分発、関空7時20分着。 |
 |
自分へのお土産は、ワンラン市場で見かけたトゥクトゥクの模型。この他に、病院の売店でガパオライス用のガパオのレトルトパック、空港でトムカーガイやイエローカレーなどのレトルトパック、ジャスミンライス(香り米)などを買った。2泊3日の出張で、業務をしっかりこなしつつも、タイを満喫することもでき、とても楽しかった。また来る機会がありそうなので、次回はもっと深掘りしたいものだ。 |
2025年3月1日(土)
第20回京都大学附置研究所・センターシンポジウム
 |
表記の会が、鹿児島で開催された。京都大学には18の附置研究所/附置研究センターがあり、一つの大学としては日本で一番多いとされている。その附置研究所/センターが連携して研究力を強化しようという目的で20年前に「京都大学附置研究所・センター会議」が発足し、その成果を社会に発信するイベントとして2005年から「京都大学附置研究所・センターシンポジウム」が始められた。以後、このシンポジウムは、連携基盤から社会への発信として、年に1回、いろいろな都市で開催されている。昨年は松本で開催された(2024年3月2日の記事参照)。 |
 |
今回の演者。医生研からは野々村恵子先生が参加。野々村先生は所用により現地参加が叶わず、オンラインでのライブ講演となった。 |
 |
今回の主催は防災研。桜島には防災研管轄の観測所があり、今回はその関係で鹿児島で開催という事になった。シンポジウムの前日の午後に、研究所長/センター長による防災研の桜島観測所の見学会が催された。鹿児島中央駅西口に集合。 |
 |
一行約20人で、貸切バスでのツアー。 |
 |
見学ツアーの概要。私は火山が大好きなので、気分は爆上がりだった。ツアーを世話してくれるのは「桜島ジオサルク」という活動で、これは「桜島サイエンスミュージム」という事業の中の一つ。このミュージアム事業は、防災研の桜島観測所(火山)と阿武山観測所(地震)、および兵庫県立大学減災復興研究科との協働プロジェクトとのこと。 |
 |
鹿児島港から桜島に渡る桜島フェリーはわずか15分という乗船時間であるが、その間に食べる「やぶ金」のうどんが名物であるという。昼食がまだだったので、食することに。 |
 |
メニュー表。 |
 |
山菜温玉うどんを食した。注文後30秒で提供という話通り、すぐに供された。 |
 |
せっかくだからと、景色のいい席を探した。 |
 |
前方のカウンター席が空いていた。徐々に近づいてくる桜島の風景を楽しみつつ、5分くらいでかき込んだ。 |
 |
この日は、午前中は曇っていて山体はほとんど見えなかったらしいが、幸運なことに、午後には天気は回復しつつあり、この時点では雲は山頂に少し残るだけになっていた。 |
 |
桜島側の港。こちらの港で課金される。 |
 |
港の近くにある防災研附属桜島火山観測所で記念写真。 |
 |
3つの班に分かれてローテーション形式で研究所の説明を受けた。中道治久先生(防災研教授)からは、地震計での火山活動を測定する意義などについての話を聴けた。 |
 |
ツアーには桜島ジオサルクで案内役をされている方々も説明役をして下さった。ローテーションで、別な場所では「チコちゃん」から地下のマグマだまりの構造と現状についての話を聴けた。大正噴火でマグマを大量に噴出して、その分一帯が30-50cmほど沈降したらしいが、現在その沈降分が元に戻っていることから、相当量のマグマがマグマだまりに補給されていて、いつ同規模の大噴火が起こってもおかしくない状態、とのこと。 |
 |
別な場所で「マーボーさん」から、地震計の記録法についての話を聴いた。右側にあるのはデータを管理するサーバー。 |
 |
桜島だけでなく南方に位置するいくつかの島々も観測の対象にしているとのこと。 |
 |
地震波の向きや振幅を記録したデータは、デジタルデータとして送られてくるらしい。デジタルのデータとしても何らかの媒体内に記録されるが、そういうデジタルデータは必ずしも長持ちするものではなく、意外と脆弱だという。それで、より堅牢なシステムとして、現在でも煤を塗った紙に針で引っ掻いて記録する方法も並行して行われているという。デジタルデータを、アナログデータに書き換えて保存するということだ。そんな方法がまだ生きているのかと、感心した。この煤紙上に記録されたアナログデータは、AIを使って読み込めば、簡単にデジタルデータに復帰できるらしい。 |
 |
10分くらいで一回りするドラムに貼り付けた紙に、地震波を記録していく。1日に1本使われるとのこと。 |
 |
針で書き込んでいる部分のアップ。 |
 |
ほとんどの観測箇所で大きな動きはなかったが、薩摩硫黄島は、現在活動期にあるらしく、火山性の地震がしっかり記録されている。 |
 |
波形のアップ。こうしてみると、よくみる地震波であることがわかる。それぞれが重なってしまっているが、AIを使って読み込むと、きれいに分離できるらしい。 |
 |
煤を塗った紙は、この部屋の右側のチャンバーで自作しているそうだ。また、回収した紙は、長期間の保存に耐えられるように、ニスを塗って煤を固定するらしい。左側にぶら下がっているの、ニスによる固定中の紙とのこと。このアナクロニズムな感じが、とても良い。 |
 |
2箇所目の、ハルタ山観測所。山体にかなり近い。 |
 |
記念写真。 |
 |
地震計を見せていただく予定であったが、鍵を間違えて持ってこられて、残念ながら中には入れなかった。このあたりには、地震計の他に、このあたりの坑道には、傾斜や距離の変化を精密に測定できる30mくらいの長さの計測器が設置してあるらしい。 |
 |
観測所の屋上から見た桜島。 |
 |
アップ写真。荒々しい山肌が大迫力で、素晴らしい。 |
 |
研究所の海側の道路には、路面が割れた跡が残されている。これは、以前に直径数十センチの火山弾が飛んできて、道の舗装面が粉砕されたのを、その記録ということであえて残してあるらしい。 |
 |
ハルタ山観測所見学後、島を時計回りに周った。午後2時あたりの場所から、東側を望む。 |
 |
桜島の北側の海は姶良カルデラというカルデラ地形の窪地に当たる。従って、見えている山並みは、姶良カルデラの外輪山という事になる。 左:原図はWikipediaより拝借 |
 |
上記の写真の右側に見えている島のアップ。新島(しんじま)という名前がつけられている。江戸時代の噴火の際に海底が隆起して出現したらしい。そのため、島を形成する岩石は、堆積岩であるとの事。少人数の住民がいて、京大の観測所もあるらしい。 |
 |
上記の写真の左側に写っている、海中から突き出た白い柱。水位を計測するための装置との事。設置箇所は、深さ30mくらいであるらしい。 |
 |
東側に回り込むと、昭和火口と呼ばれる火口から白っぽい噴煙がたちのぼるのが見えた。十数年前に訪れた時には、この火口から爆発的な黒い噴煙が上がるのを見ることができたが、現在は活動が沈静化していて、主な噴火は山頂の噴火口で起こっているらしい。 |
 |
大正噴火で火山灰と軽石に埋もれた鳥居で、記念写真。復旧しても良さそうなものであるが、当時の人達は、あえて残そうと考えたとのこと。 |
 |
桜島ダイコンの収穫の最盛期は少し前だったらしい。島内の道の駅では、いくつかに切り分けて売られていた。 |
 |
帰りのフェリーの進行方向右側に、海側が崖になっている山並が見られた。 |
 |
この山並は姶良カルデラの外輪山の一部。 |
 |
山本衛先生(生存研所長)と案内人のチコちゃん。 |
 |
鹿児島中央駅に帰着後、一旦散会して、夕食の会場で再集合。写真は会食で供されたキビナゴの刺身。新鮮なキビナゴが手に入る鹿児島ならではの料理。美味しかった。 |
 |
味噌を使った鹿児島おでん。 |
 |
懇親会に参加された皆様。 |
 |
辻井先生の後を継いで4月から連携基盤長を務められる中野伸一先生(生態研所長)による挨拶。 |
 |
シンポジウム当日。会場へは路面電車で移動した。 |
 |
会場があるカクイックス交流センター。 |
 |
会場となった県民ホール。今回は現地参加571名、うち中高生461名。オンラインは462名、うち中高生41名。計1033名が参加。大盛会だった。 |
 |
昼食時は、「研究者と語ろう」というイベントとして、参加者が10人ずつくらいの班になって、今回の演者や、参加している研究所長/センター長と対話する会が催された。前回の松本でのシンポジウムの時から始まったイベント。今回も、アンケートで大変好評だったらしい。私も、ラサール校や鶴丸高校の生徒さん達と、1時間近くあれこれと話をした。 |
 |
午後には、シンポジストによる講演が終わった後、今回のシンポジストに加えて、湊総長、時任副学長、山中伸弥先生を加えたパネルディスカッションを、辻井連携基盤長のMCにより開催された。とても豪華な布陣だ。テーマは「京都大学が提案する未来」。 |
 |
健康、自然、技術といテーマについての討論。「健康」というテーマでは、湊先生は「若い人が死ぬのは許せない」、山中先生も「誰もが天寿を全うする権利を有する」と、医学者としての矜持を語られた。若い人へのメッセージとして、山中先生は「失敗は自分を導いてくれる宝物」「30代でようやく天職につけた」という話をされた。湊先生は「大学で自分を知る」「京大は1を100にする研究ではなく0を1にする研究」「運を掴み取る力が大事」という話をされ、最後に「京大でお会いしましょう」と締めくくられた。 |
 |
これは桜島の道の駅で買ったお土産で、軽石でできた植木鉢。灰色のものが多かったが、赤茶色のものを選んだ。250円。 |
 |
鹿児島駅のお店で買った本枯節と削り器。少々値は張ったが、これでおかかご飯を作ってみたところ、とても美味しかった。 |
2025年2月26日(水)
大塚製薬との共同研究の成果報告会
 |
大塚製薬と京大との関係は、リバーセルも入れた三者共同研究ではなく、大塚製薬-京大との共同研究と、大塚製薬-リバーセルの技術導出に関する契約(下記参照)、という構図になっている。この日、大阪創薬研究センターで、成果の報告会があり、永野君と二人で参加。このセンターは大阪モノレールの彩都駅の近くで、2022年11月に竣工となった新しい研究所(2023年4月18日の記事参照)。共同研究は順調に進んでいる。 大塚-リバーセルの技術導出に関する契約についての大塚製薬からのニュースリリース(2021年12月16日): |
2025年2月25日(火)
日立製作所との共同研究の成果報告会
 |
日立-京大-リバーセルの三者共同研究では、2年前から自動培養装置でES/iPS細胞からT細胞を作ることを目指した開発研究を進めている。昨年11月に2024年度の中間報告会が開催された(2024年11月25日の記事参照)が、今回は最終報告会。順調に進んでいることが確認された。 日立・京大・リバーセルの3者共同研究についての日立からのニュースリリース(2023年3月14日): |
 |
会議後の会食。前回は京都駅近くの「弘」で催されたが、今回も京都駅近くの弘で、前回とは異なる店舗。コースにミニもつ鍋が付いていた。 |
2025年2月24日(月)
寒波が続く
 |
今季は寒い日が続く。この日も、朝、雪が降った。 |
2025年2月22日(土)
東進ハイスクールで講義
 |
東進ハイスクールは、オンラインでの講義を中心とした予備校であるが、新宿にある本社ビルには講義室があって、ここではオンサイトの講義が行われているらしい。ここでは、受験に向けた科目の講義とは別に、二ヶ月に一回くらいの頻度で、「トップリーダーと学ぶワークショップ」という講演会+討論会のようなイベントが開催されている。対象は、中学生と、高校生(1年生と2年生)。今回、このワークショップで講師を務めることになった。 「トップリーダーと学ぶワークショップ」HP: |
 |
ビルの15階に立派な階段教室があり、ここで講義。左の写真は後でスタッフの方から頂いたのもの。 |
 |
まずは90分の講義。時間がたっぷりいただけたので、左記のように盛りだくさんの内容にした。後半のワークショップでの討論は、講義内容に絡めた形になるからか、ほとんどの生徒さんがメモを取りながら、熱心に聴いてくれた。こんなに熱心に聴いてもらえる講義は、これまで経験がなく、とてもありがたく思った。 |
 |
講義の後は15分の質疑応答。鋭い質問が次々と繰り出された。今回はES細胞の話はしつつ移植免疫の話は省いたのであるが、ウイルス感染症の治療のスライドの中に「HLAを欠失したES細胞を材料にする」という文言をスライドに載せていて、それについて「HLAを欠失させたらNK細胞が攻撃するのではないですか」という質問をした生徒さんがいて、驚いた。左は東進のスタッフの方が撮ってくださったもの。 |
 |
質疑応答が終わってから、私がワークショップのテーマを出す。今回は、左のような課題にした。講義の中で答えを言ってしまっている課題だと、画一的な議論になってしまうので、テーマの設定には苦労をした。この課題について、4-5人ずつ、計20くらいのチームに分かれ、10分間の休憩後、まずは60分間、チームの中で議論し、論点をまとめる。次の30分で、各チームが1-2分、全生徒の前でプレゼンし、生徒自身の投票により、上位5チームに絞りこまれる。 |
 |
5チームに絞られた時点で、私が講義室に再登場。最前列で、5チームのプレゼンを、2-3分ずつ聴き、それに対して私が2-3分ずつ講評を加える。全て聴き終わったら、その中で一番良かったチームを即座に選んで、東進のスタッフに伝える。反射神経を要する、中々タフな作業だ。 |
 |
どのチームも予選で選ばれただけあって、それぞれに視点がユニークで、プレゼンも上手だった。最優秀チームとして選んだチームは、課題を論理的に、しっかりとした議論ができていた。その最優秀チームの各自に一人ずつ表彰状を渡した後、副賞として、講義の中で紹介したネガティブセレクションのセカンドアルバム「辺境の街から」と、「本の表紙になったイラストシリーズ」6枚の絵葉書セットを、進呈した。その後、記念写真。今回の会は、発表スライドの準備も、ワークショップでの審査も、結構きつかったが、多くの熱心な生徒さん達に接することができて、とても楽しかった。 |
2025年2月21日(金)
川瀬先生と打ち合わせ
 |
この日の夕刻、川瀬孝和先生と今後の新型コロナ及びサイトメガロウイルス感染症治療用のT細胞製剤の臨床試験に向けた戦略について打ち合わせをした。打ち合わせの後、くうかいで会食。くうかいは連日であるが、この店はラボに近くて、料理が美味しくお酒の品揃えもいいで、訪れる頻度が高い。 |
2025年2月20日(木)
中坊先生と打ち合わせ
 |
中坊周一郎先生(京大病院臨床免疫学特定助教、向かって右端)とは少し前に野沢で開催された骨免疫学会主催のIC2NEMO(2025年1月28日の記事参照)でお会いし、面白そうなアイデアを持っておられたので、この日、共同研究に向けての打ち合わせをすることになった。打ち合わせにはうちからは永野君、西村君、間宮さんが参加した。いい打ち合わせになった。 |
 |
打ち合わせの後、同じ面子でくうかいで壮行会。 |
2025年2月15日(土)
久保允人最終講義・囲む会に参加
 |
表記の会が千葉県柏市の柏の葉カンファレンスセンターで開催された。 |
 |
吉村昭彦先生による挨拶。かなり前から共同研究などをされてきたとのこと。 |
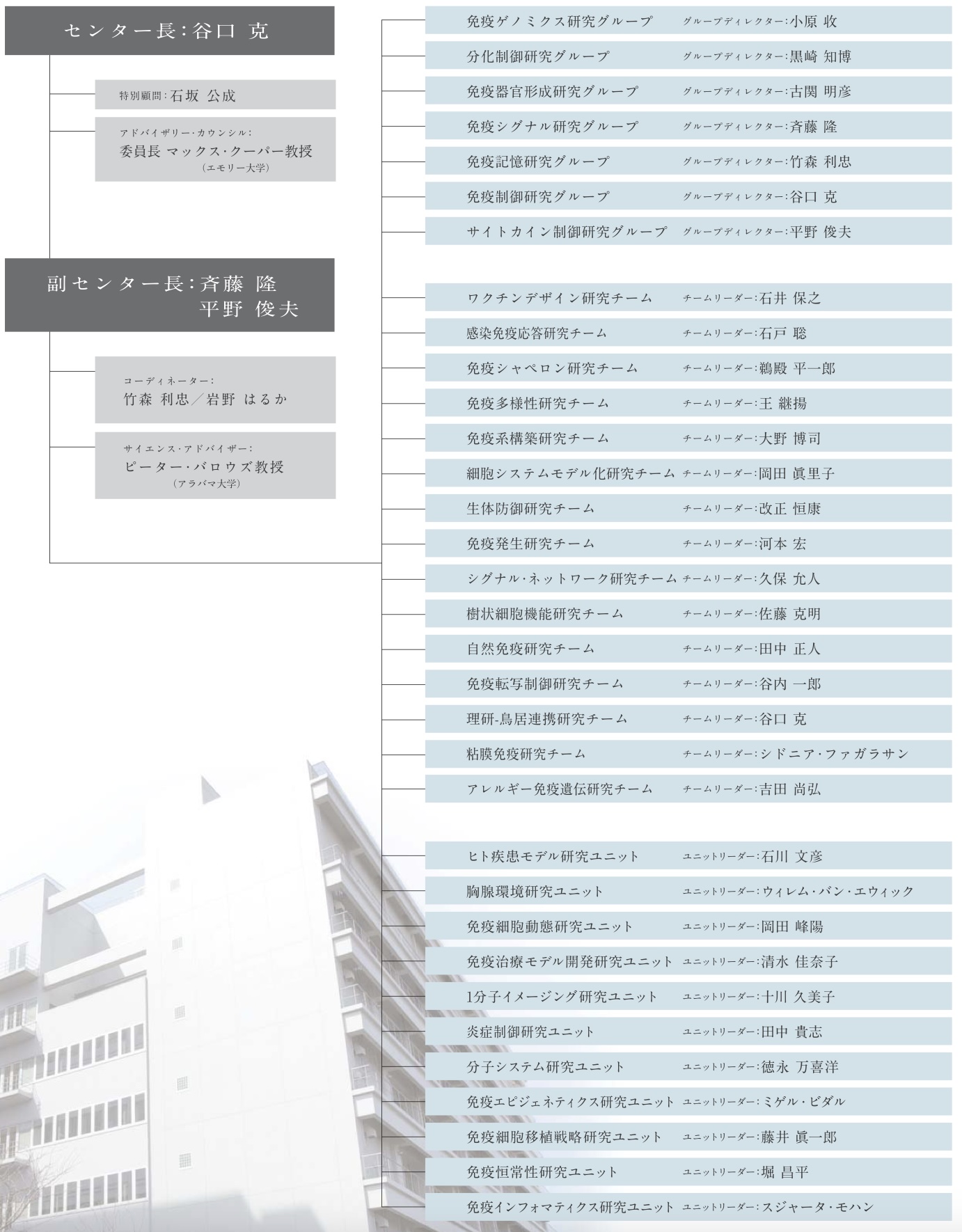 |
私も10分ほどの枠をもらって挨拶をした。左は最初のスライドの元ネタとして使った理研RCAIの組織図。発足当初(2002)のものではなく、2009年ごろのもの。久保先生とは理研のチームリーダーとして、同僚だった。理研RCAI時代(2002年からの約10年間)のことは、今でもよく、とても懐かしく思い出す。 |
 |
私は、記念写真集用に提供するためにラボニュース記事欄からかき集めた写真を、パワポを使って披露しつつ、久保先生が免疫ふしぎ未来展の打ち上げライブで「タイガー&ドラゴン」を歌われた時の動画のサビの部分(2番冒頭の「オレの、オレの、オレの話を聞け〜」)を動画で流した。 |
 |
久保先生がタイガー&ドラゴンを歌っている写真は、上記以外にもラボニュース記事の中に沢山あった。このスライドを見せた後は、右上の免疫学会学術集会非公式懇親会の時の動画も少し流した。 |
 |
2023年にKTCCの集会長をされた時は、裏医生研チャンネルで情報交換会の取材をしたので、左のスライドの後にその時の動画を少し流した。右側のQRコードはそれぞれの動画へのリンク。 |
 |
KTCCの抄録集の裏表紙のイラストの作成過程(2023年6月16日の記事参照)を説明。 |
 |
SCARDA事業の中のサポート機関として、京大がKICという機関を勧めている(2023年8月8日の記事参照)が、久保先生はKICのアドバイサー役を務められているので、京大ではよく会っている、ということを示すスライド。 |
 |
その後、久保先生による講演。 |
 |
講演の中でRCAI時代の写真。久保先生はIMSになってからも兼任で理研に在籍しておられた。 |
 |
懇親会。 |
 |
斉藤隆先生による挨拶。 |
 |
奥村康先生と。 |
 |
久保先生の奥様である鈴木しのぶ先生による挨拶。 |
 |
二次会は流山おおたかの森駅の近くのワインのお店。 |
 |
このショーケースの中のワインが飲み放題というありがたい形式だった。 |
 |
最後まで居た人で記念写真。楽しかった。 |
2025年2月14日(金)
松山さんと金子さん来訪
 |
松山祐輔さん(総合研究推進本部、向かって左から2番目)は、事務系の人の有志が参加している「お昼の校内放送」というのを主宰されている。参加者の中の一人あるいは招かれた講師がzoomで40分ほどプレゼンと討論を行う。私(河本)も一度講師をさせていただいたことがある(2024年10月23日の記事参照)。そのメンバーのお一人である金子沙代さん(吉田南構内共通事務部、左から3番目)が裏医生研チャンネルのファンだということで医生研に来られることになり、今回私と澄田先生でお迎えした。 |
 |
この少し前に金子さんがお昼の効果に放送でプレゼンされた時に一コマ。ピカチュウのマペットを使って裏チャンネルのYoutube動画を紹介しつつ、この「ゆるさ」が面白いということと、そして裏チャンネルのような動画が公式にアップされるのが京大らしくて良い、とうようなことを言っていただけた。 |
 |
せっかくなので、記念に裏チャンネルの装束で記念写真。 |
 |
ライムさんと握手。 |
2025年2月10日(月)
日立webメディア「Linking Society」の取材
 |
少し前に書いたが、日立は「Linking Society」というwebメディアで、未来に向けての課題を考える対談記事を、毎週発信している(2024年10月18日の記事参照)。内容は科学、文化、経済など、非常に広い分野をカバーしている。今回は、「細胞社会と人間社会」「科学コミュニケーション」「イノベーション」などをテーマに、日立の武田志津さん(日立神戸ラボ長)(写真前列向かって右端)、半澤宏子さん(日立神戸ラボ主管研究員)(前列左端)との鼎談のような形で話をした。この談話を元にした記事になるようだ。談話の後、3人で実験室での写真を撮ってもらったりした。最後に記念写真。楽しかった。 Linking Society HP: |
2025年2月9日(日)
鴨川のカワセミ
 |
まだ2月4日あたりから始まった今季最強最長の寒波が続いている。昨日は京都市内全域に10cmくらいの積雪があったようだ。この日の朝も、夜の間に降った雪が積もっていた。左は、朝8時ごろ、荒神橋から北を望んだ写真。 |
 |
この日の夕刻、秘書の宮武さんが鴨川でカワセミを見て写真を撮ったとのことで、その写真をラボニュースに載せさせて頂くことにした。これも荒神橋あたりらしい。 |
 |
カワセミのアップ。鮮やかな青がとてもきれいだ。鴨川で見かけることがあるという話は聞いたことがあるが、私自身は見たことがない。一度現物を拝んでみたいものだ。 |
2025年2月8日(土)
第44回日本胸腺研究会
 |
表記の会が福岡で開催された。集会のテーマの「温故知新」という字は、今回の集会長である瀬戸貴司先生(九州がんセンター)が書いたとのこと。素晴らしい。この会は胸腺腫/胸腺癌を対象にした外科系の先生方が中心の会であるが、これらの腫瘍の病理学や、胸腺腫に伴う重症筋無力症も扱っており、基礎医学系の先生方も参加している。そういう関係で、代表理事は臨床系と基礎系の二人が務めることになっており、2年前から基礎系の方は私が代表理事を務めている。 |
 |
前日入り。往路の新幹線では、新山口駅のあたりで積雪のため徐行運転となり、そのせいで20分くらいの遅れが生じた。 |
 |
理事会の後、理事懇親会。 |
 |
奥村明之進先生(大阪刀根山医療センター)は今回の理事会で代表理事を退任されることが決まった。時期代表理事は井上匡美先生(府立医大呼吸器外科)。 |
 |
懇親会の後、地元の先生の案内で近くの店に、有志でラーメンを食べに行くことになった。 |
 |
料亭でフルコースを終えた後だが、全員が完食。 |
 |
濃厚なスープで、とても美味しかった。 |
 |
九州がんセンター。私は天神のあたりに泊まったが、そこからは電車とバスの乗り継ぎで30分くらいかかった。 |
 |
会場。演題数51で、約100人の参加があったとのこと。 |
 |
集会長の瀬戸先生は、開会の挨拶で、スポーツ大会の宣誓風の挨拶をされた。ユニークだ。 |
 |
次回は徳島大学がホスト。次回の集会長の松井尚子先生が集会の最後に挨拶をされた。 |
2025年2月6日(木)
梶川社長、北村取締役と会食
 |
リバーセルの梶川社長、北村取締役と、久々に3人で会食。今年はいよいよ正念場なので、壮行会という感じだった。 |
2025年2月6日(木)
この冬一番強く長い寒波が襲来
 |
2月4日から始まった寒波であるが、この日は朝の気温が-4℃まで下がった。 |
 |
大学に着いてすぐに鴨川の一部が凍ってないかと思って見に行ったが、凍ってはいなかった。丸太町通りの橋の近くにユリカモメの群れがいた。 |
 |
一時期かなり減ったが、この何年かは、またよく見かけるようになった。鴨川にいるのはお昼の間だけで、夕方になると琵琶湖に戻るらしい。 |
 |
上の写真から少し後に、宮武さんが丸太町の橋から撮った写真。 |
2025年2月4日(火)
大阪大学の先導的学際研究機構主催のシンポジウムで講演
 |
表記の機構の創薬サイエンス部門が主催するシンポジウムに参加した。 |
 |
会場は大阪大学の薬学部の構内にある大阪大学MA-T共創センター(杏の社)の2階の講義室。 |
 |
2階のフロア。 |
 |
会場。オンサイトの参加者も多かったが、オンラインでも100人以上が聴講していたようだ。 |
 |
総合司会は井上豪先生(先導的学際研究機構・創薬サイエンス部門・副部門長)。 |
 |
尾上孝雄先生(先導的学際研究機構・機構長)による開会の挨拶。 |
 |
辻川和丈先生(先導的学際研究機構・創薬サイエンス部門・部門長)による創薬サイエンス部門の紹介。このシンポジウムはこの部門が主催で、二ヶ月に一回くらいの頻度で、各種モダリティに焦点を当てる形で開催されているらしい。 |
 |
高倉先生の講演の座長は熊ノ郷淳先生。熊ノ郷先生はこの4月から大阪大学の総長になられるらしい。 |
 |
シンポジウム終了後、講演者でグループフォト。最初の演者の佐藤俊朗先生(慶應大)はオンライン参加であったが、他の演者は現地参加。向かって左から高倉伸幸先生(大阪大微生物研所長)、安藤美樹先生(順天堂大血液内科教授)、寺井崇二先生(新潟大学消化器内科教授)、私、保仙直樹先生(大阪大学血液腫瘍内科学教授)。安藤先生は子宮頸癌に対してiPS細胞由来T細胞を使った臨床試験(医師主導治験)の患者の登録を始めたらしい。私達の戦略とはかなり異なっている(安藤先生らの戦略はT-iPS細胞法というT細胞から作ったiPS細胞を材料にする方法で、再生T細胞はCD8αα型T細胞、私達のはTCR-iPS細胞法というiPS細胞に外来TCR遺伝子を導入して材料にする方法で、再生T細胞はCD8αβ型CTL)が、とてもパワフルに進められており、感心した。寺井先生は臨床試験の進め方はさらにパワフルで、肝硬変で起こる線維化を骨髄移植で抑制する試験などを随分前から施行しておられる。昨年の再生医療学会では大会長をされていた(2024年3月21日の記事参照)。この日は強い寒波が来ていたので、復路の新潟までの飛行機が飛ぶかと心配されていたが、問題なく帰られたとのことだった。 |
2025年2月1日(月)
芝蘭会東京支部総会で講演
 |
芝蘭会は、京大医学部卒業生の会で、各地方に支部があって、年に1回、集会が開催される。今回は、竹橋のKKRホテル東京の11階の部屋で開催された。会場からの景色。 |
 |
プログラム。私は第一部の総会の中で約20分、医学部の最近の動向や、国際卓越研究大学への応募の状況などについて話をした。最近の動向については、伊佐先生にお願いして、伊佐先生が11月に滋賀支部で使われたスライドをいただいた。芝蘭会の方で用意をしてくれるとのことだった。それに加えて、中国医薬大学における京大オンサイトラボの開設の話(2024年11月19日の記事参照)、京大病院開設125周年の記念式典/祝賀会の話(2024年12月21日の記事参照)などをした。 |
 |
会場。 |
 |
第二部で、研究内容の紹介などを話した。 |
 |
イントロとして、S61(1986)卒の同級生に向けて、学生時代の写真と、最近会った同級生の写真を、数点示した。これは一年前に内視鏡外科学会の全体懇親会で撮った写真(2023年12月7日の記事参照)。 |
 |
新蔵先生(東大)とは毎年のように免疫学会でお会いしている。 |
 |
京大病院開設125周年の祝賀会にて、S61卒で集まって撮った写真(2024年12月21日の記事参照)。 |
 |
同級生ではないが、この会の直前のIC2NEMOという会にて、山村隆先生(国立精神神経センター)と鍔田武志先生(東京科学大)の写真。 |
 |
このスライドを使って、少しSTAP細胞事件について言及。「風化させてはいけない」というような話をした。 |
 |
研究内容の紹介をした後、最近テレビ番組に出演して、ウイルス感染症治療用のT細胞の話をした事を紹介した。これは「いまからサイエンス」(2024年10月17日の記事参照)。 |
 |
これは「林修の今知りたいでしょ」(2025年1月23日の記事参照)。 |
 |
今年12月に開催する免疫学会は私が大会長を務めるが、副大会長の4人も京大医学部出身者であるので、ポスターの中の似顔絵の部分を示した。 |
 |
もう一人の講演は水野篤先生(2005年京大卒)(聖路加国際病院循環器内科・QIセンター医療の質管理室室長)で、講演タイトルは「医療現場における実装科学と行動経済学」。医療の質をどう評価するかという話で、熱弁を振るわれて、とても面白かったが、私が少し講演時間を超過したために、水野先生の講演時間が短くなってしまい、申し訳なかった。 |
 |
懇親会。 |
 |
芝蘭会東京支部長である大髙道也先生(1972年卒)による挨拶。 |
 |
61卒で集まって記念写真。向かって左から大久保憲一先生(東京科学大病院呼吸器外科)、佐田文宏先生(中央大学保健センター)、金丸晶子先生(東京都健康長寿医療センターリハビリテーション科)、新蔵礼子先生(東京大学定量研)、私、森貴久先生(湘南鎌倉総合病院脳血管障害予防センター)。 |
 |
芝蘭会雑誌部の記者として木田雄大さん(3回生)(向かって右端)、西野純平さん(2回生)(右から3人目)が参加。向かって左端は板東徹先生(聖路加病院呼吸器科センター長)。 |
 |
ちゃんとした写真スタジオでグループフォト。 |
2025年1月28日(火)ー31日(金)
第一回IC2NEMOに参加
 |
表記の会が野沢温泉で開催された。この時期に開催されてきた骨免疫学会ウインタースクールの発展形。昨年の骨免疫学会ウインタースクールは、精神神経系の研究者との合同開催となり、「Neuro-osteoimmunology summit」と名打たれた(2024年2月1日の記事参照)。今年はさらにそれを発展させて、内分泌/代謝の人も加わって「International Conference on Immunity and Cognition: integration of multidisciplinary approaches in Neuroscience, Endocrinology, Metabolic biology and Osteoimmunology (IC2NEMO)」という名前の会になった。豪華な顔ぶれの招待演者が60名近くいて、とても豪勢な会だ。 |
 |
京都から野沢に行く経路としては、サンダーバード号で敦賀、敦賀から飯山まで新幹線、飯山からバス(野沢ライナー)を使う。写真はサンダーバード号の車窓から見えた琵琶湖の北端。雪が全くない。今年の雪は、正月の前後に東北や北陸の一部で被害が出るほどの豪雪だったのに、この辺りには降っていないようだ。 |
 |
会場の朝日屋旅館。野沢の中央バスターミナルのすぐ近く。 |
 |
集会場。 |
 |
今回の集会長である古屋敷智之先生(神戸大学)。オーガナイザーは小林泰浩先生(松本歯科大学)、澤明先生(Johns Hopkins University)、高柳広先生(東京大学)。古屋敷先生は近々東京科学大学に異動されるとのことだった。 |
 |
夕食の会場。 |
 |
瀬藤光利先生(浜松医大)と。瀬藤先生とは2014年のヒト細胞学会学術集会(2014年8月30日の記事参照)以来だ。 |
 |
北村先生、和田森由紀子(東大柳井秀元研大学院生)さんと。和田森さんは昨年8月のサマースクールと免疫学会に来ていて(2024年12月3日の記事参照)、免疫学会の時にウインタースクールの話を知って今回の参加となった。元気な人だ。 |
 |
夕食のホールの一部を仕切って作られたスペースで、23時までFree discussion。この日の宿泊は藤尾圭志先生(東大)と同室で、Free discussionの後、部屋に戻ってから日本酒を一献傾けつつ、あれこれと話をした。 |
 |
2日目、午前中のセッションが終わった後、お昼のポスターセッションの時間に、有志でゲレンデへ。あいにく天気があまり良くなく、早めに引き上げて、日影ゴンドラ乗り場の近くのゲレ食で遅い昼食。向かって左から、鍔田武志先生(東京科学大)、高柳先生、小林先生、小池進介先生(東京大学;東大医学部スキー部OB)、岡崎美音さん(東大医学部5回生;医学部スキー部)、大渕理真さん(東大医学部2回生;医学部スキー部)。この日は天気が悪く斜面の凹凸がうまく見えない上、雪とガスで視界が悪い中を、スキー部関係の人達はすごいスピードで滑っていて、激しく「置いていかれた感」を味わった。特に大渕さんは、話を聞けば中学生の時に八方でSAJの1級、大学に入って年齢制限があった準指導員に合格して、八方でスキーを教えたりしているという基礎スキーの強者で、とてもきれいなフォームでビュンビュンとばしていたのが印象的だった。私はスカイラインの入り口あたりで強風による地吹雪をくらい、メガネに雪がこびりついて見えなくなり、コース脇の新雪に突っ込んで転んでスキー板が外れたところを、大渕さんが駆けつけてくれて、助けてもらったりした。ありがとうございました。 |
 |
午後のセッションの直前、旅館からみた風景。この数時間で、新たに20-30cmくらい積もっている。 |
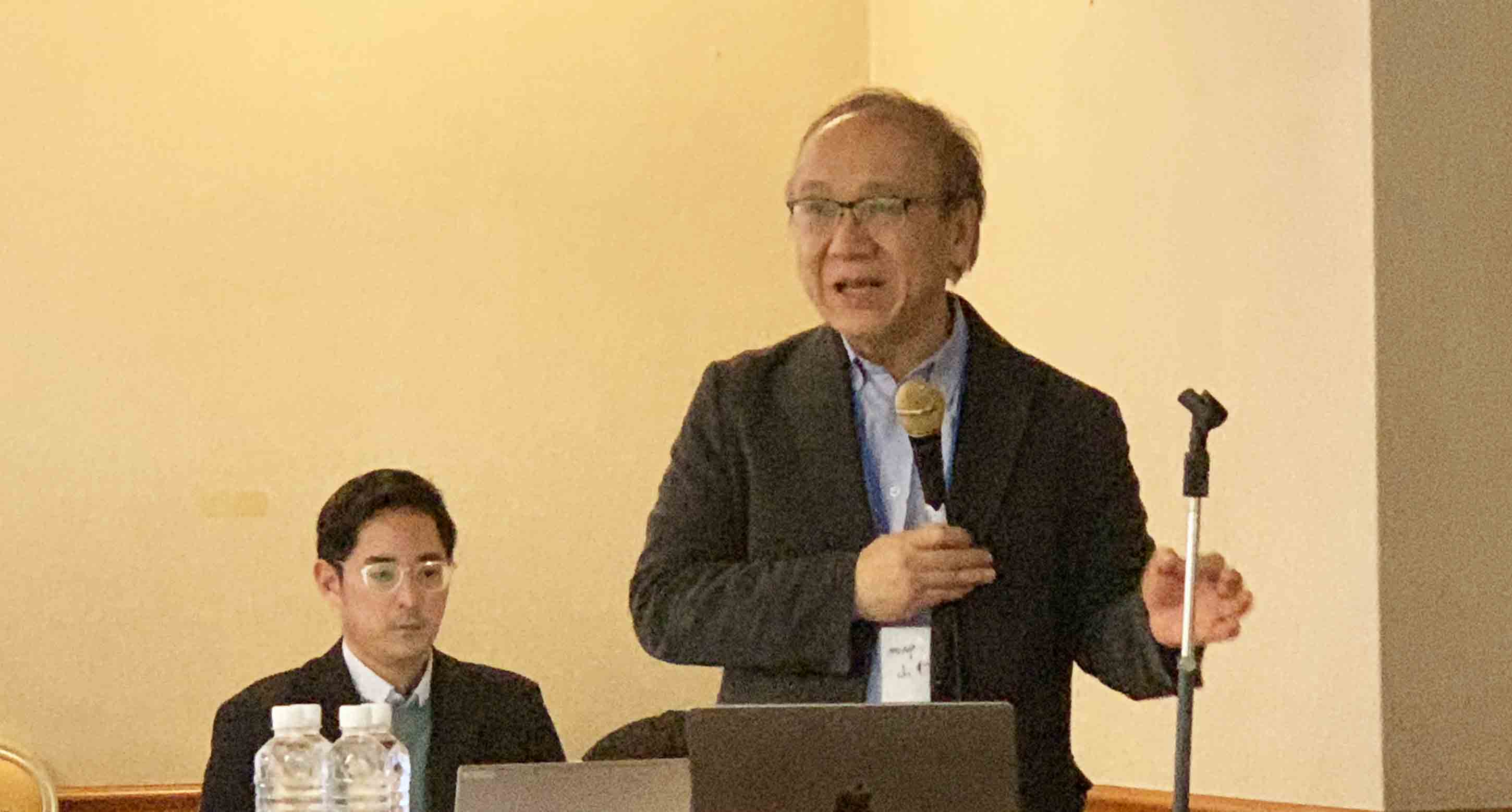 |
山村隆先生(国立精神神経センター)による講演。山村先生にはこの週末に東京で開催される芝蘭会東京支部総会での講演会でもお世話になる予定。ちなみに山村先生はジャズピアノの名手で、これまで何度かNegative Selectionと共演いただいている(2013年6月3日の記事参照)。 |
 |
会食時に、最優秀演題賞の表彰。受賞者は岩本莉奈先生(松本歯科大)、中村和貴先生(東大)、蘭子国先生(京大)、中野僚太先生(昭和大学)。写真は向かって左から小林先生、岩本先生、中野先生、中村先生、蘭先生、高柳先生、澤先生。 |
 |
Free discussion timeに、京大湊研関係者と。向かって左から石田昌義先生(松本歯科大)、私、山中宏二先生(名古屋大)。山中先生は私より6歳年下だが、湊研ではかなり上の先輩。 |
 |
写真向かって右から宮島倫生先生(東大高柳研准教授)、和田森さん、伏見萌音さん(高柳研大学院生)。伏見さんには免疫学会のポスターをもらって頂いた。 |
 |
2日目、3日目は笠井淳司先生(名古屋大学)(向かって右から二人目)と同室。流れで集まった人達と12時過ぎまで部屋飲み。笠井先生のお父上は杜氏であったとのことで、笠井先生はそれで日本酒に関しては味がよくわかる、というような話をされていた。笠井先生のお隣の女性は林朗子先生(理研脳センター)。 |
 |
3日目のお昼のポスターセッションの時間も、有志でゲレンデへ。私は正午頃まで研究所関係のオンライン会議があったので、昼食から合流。カレーを食べにパラダイスゲレンデのパノラマレストラン「ぶな」で集合の予定であったが、この日は休みだったので、その隣の「白銀」で昼食。向かって左から二人目が澤明先生(東大医学部スキー部OB)。 |
 |
この日は天気がよく、雪質もいい感じだった。荒瀬尚先生(大阪大学、写真向かって左端)は、相変わらずシュナイダーコースの最後の方の急斜面のコブをモーグルのような滑りでガンガン滑られていた。 |
 |
夕方のセッションの後の会食時、朝霧成挙先生(山口大)、本橋ほづみ先生(東北大)と。本橋先生からは河岡慎平先生(東北大)の活躍ぶりについての話を聴けた。 |
 |
今回は東大医学部スキー部の現役生らが学会の運営の手伝いに来てくれていた。Free discussionの時に、そのうちのお二人に免疫学会のポスターをもらって頂いた。写真中央は、昨日ゲレンデで私を介助してくれた大渕さん。左は湯淺芙紗子さん(東大医学部3回生)。 |
 |
Free discussionの最後の方に林先生(写真向かって右から二人目)らと話をしていたら、「カラオケに行こう」という話になり、ネットで検索してホテルから徒歩5分くらいのところに、一軒、夜1時までやっている店を発見。カウンターのある部屋の奥におあつらえ向きの個室があり、そこで閉店まで楽しんだ。 |
 |
最終日、オーガナイザーから医学部スキー部の現役生らに感謝の言葉がかけられた。ここに写っている四人と、前出の岡崎さん。質疑応答の時間にマイクを持って行ったり、高柳先生のお子様の世話をしたりと、大活躍だった。旅費や宿泊費は無料にしてもらっているということらしいが、結構大変だと思われる。スキー部の先輩(この場合高柳先生と澤先生)が企画するイベントに御奉仕、という感じであろうか。ありがとうございました。 |
2025年1月27日(月)
「感染現象と医学・生命科学研究会」に参加
 |
この日の午後、表記の医生研主催イベントが芝蘭会館稲盛ホールで開催された。 |
 |
会場。病原体が感染すると、体内では、細胞内、体細胞、免疫細胞などいろいろなレベルでのせめぎ合いが起こり、「感染症」という複雑な病態になる。今回は、そういう相互作用の話が沢山聴けて面白かった。 |
 |
オーガナイザーと演者によるグループフォト。 |
 |
芝蘭会館の向かいのシランカフェで情報交換会。医生研の教授と演者が参加。 |
 |
医生研の教授と演者によるグループフォト。 |
2025年1月27日(月)ー31日(金)
「京大100人論文」に参加
 |
この週、表記のイベントが時計台記念館で開催された。 |
 |
看板。 |
 |
会場。来場者は、それぞれの発表に、コメントを書き込んだ付箋を貼りつけることができる。開場してすぐだったので、まだ貼り付けられた付箋は少ない。発表者はできるだけ会場に来ることが推奨され、さらに会期中には「京都の企業50名と京大研究者50名の大交流会」という交流イベントや、グループセッションなどの発表者同士の交流イベントなどもあるようだ。ただし、今回私はずっと別な学会などがあって、最初の30分の来場だけだった。 |
 |
1枚の絵あるいは写真と、3枚の短文(200-300文字)だけの表示で、名前も所属も書かないという形式。絵/写真には、研究内容の説明などで使うポンチ絵はNGとのこと。私は「免疫細胞療法」をテーマにして、免疫学会のポスター用に描いたイラストの一部を使った。「皆に問いたい」「私が追っている不思議」「これまでやってきたこと、やろうとしていること」という三つの項目を、それぞれ、200字以内、300字以内、300字以内で作文する。発表者は、会の終了後、コメントの書かれた付箋をもらえるとのこと。 |
 |
一般的なコメントを書いて貼るボードもあった。面白いイベントだ。 |
2025年1月24日(金)
嘉島君来訪
 |
Yale大学に留学中の嘉島相輝君が河本研を来訪。ラボ内でセミナーを開催。David Braunという人のラボで、腎細胞がん特有のがん微小環境について、とてもいい研究をしている。 |
 |
教授室で記念写真。 |
 |
有志で「くうかい」で会食。 |
2025年1月23日(木)②
「林修の今知りたいでしょ!」に出演
 |
テレビ朝日系1月23日木曜日夜8時から放映の「林修の今知りたいでしょ」に出演した。今回のテーマは「緊急特集!感染拡大インフルエンザ&冬に気をつけたいアレルギー」ということで、私はインフルエンザの枠で関雅文先生(埼玉医科大学)と一緒に教壇に立った。1月30日夜8時までは番組の見逃し配信サイトか、Tverで観られる(以下リンク参照)。 番組見逃しサイト: Tver: |
 |
まずはインフルエンザに関する話題。 |
 |
関先生が、インフルとコロナのダブル感染は、単独感染と比べて特に症状がひどくなる訳ではないと解説。 |
 |
引き続いて関先生が、ダブル感染は怖くないが、インフル感染後に細菌による肺炎が起こることが多いという話をされた。 |
 |
隠れインフルエンザの話のところで登場。「山中先生がかつて在籍していた研究所の所長」として紹介された。 |
 |
免疫学の権威ということになっていた。「隠れインフルエンザ」について説明。 |
 |
2年間インフルエンザがほぼ発生がなかったことで免疫が弱っていることが今年の大流行の大きな原因であると説明。 |
 |
昨年(2024年)は夏にもだらだらとインフルエンザの感染が続いたので、抗体を持っている人が一定数いて、そういう人は症状が軽くなるので「隠れインフルエンザ患者」としてウイルスをばら撒いている可能性がある、と解説。 |
 |
ここで林先生は「自分はこの50年間一度もインフルエンザに罹ってない」という話をされ、「罹る人と罹らない人の差はどこから?」という話になった。 |
 |
「私も学生の時以後はほとんど風邪もインフルも罹らなくなった」という話をしてから、歳をとるにつれて免疫記憶が蓄えられるので、風邪やインフルエンザに罹りにくくなると説明。あまりにも当たり前の話だ。 |
 |
林先生は若い時に十分免疫記憶を獲得したと説明した。 |
 |
若い時にできた免疫記憶はしっかりしているという一般論を説明。 |
 |
すると林先生は幼稚園でとても沢山感染症に罹ったという話をされた。 |
 |
伊沢さんが「林君は免疫でも学習が早かったんですね」と発言。 |
 |
ここから「免疫力を上げるための方法」という話に。 |
 |
簡単で効果があるのが「お昼にリラックスすること」と解説。 |
 |
ここでバカリズムさんが水野さんと宮部さんに「どんな方法が一番効果があるでしょうか」と質問。水野さんは「音楽を聴きながら瞑想」と答え、宮部さんは「昼寝」と答えた。 |
 |
そこで「正解です」「寝るのが一番交感神経を緩める効果がある」と説明。 |
 |
ただし、瞑想、音楽鑑賞、散歩など、好きなことをしたてリラックスしたら同じような効果があると説明し、その流れで「私も昼休みに仕事をするふりをしてこっそりとYouTubeで音楽を聴いたりしている」とポロッと話をしたら、その部分はしっかりと採用されてしまった。 |
 |
何年か前に「ガッテン!」に出演した時に解説した「お昼は交感神経が働いてリンパ球がリンパ節にとどまる」「リラックスしたらリンパ球が出ていく」という話を紹介(2018年10月31日の記事参照)。これは鈴木一博先生(大阪大学)の研究成果。 |
 |
リンパ球は勉強しているばかりではダメで、「リンパ節から出してあげることも大事」と説明。 |
 |
伊集院さんが「免疫力を上げる薬はないんですか?」と質問。 |
 |
私は「免疫チェックポイント阻害剤を使うと免疫力を全体的に上げることができるが、自己免疫反応が出やすい」と説明したが、その部分はカットされた。その後、特定の免疫だけを与える治療法として、河本研が進めている再生キラーT細胞療法を紹介した。 |
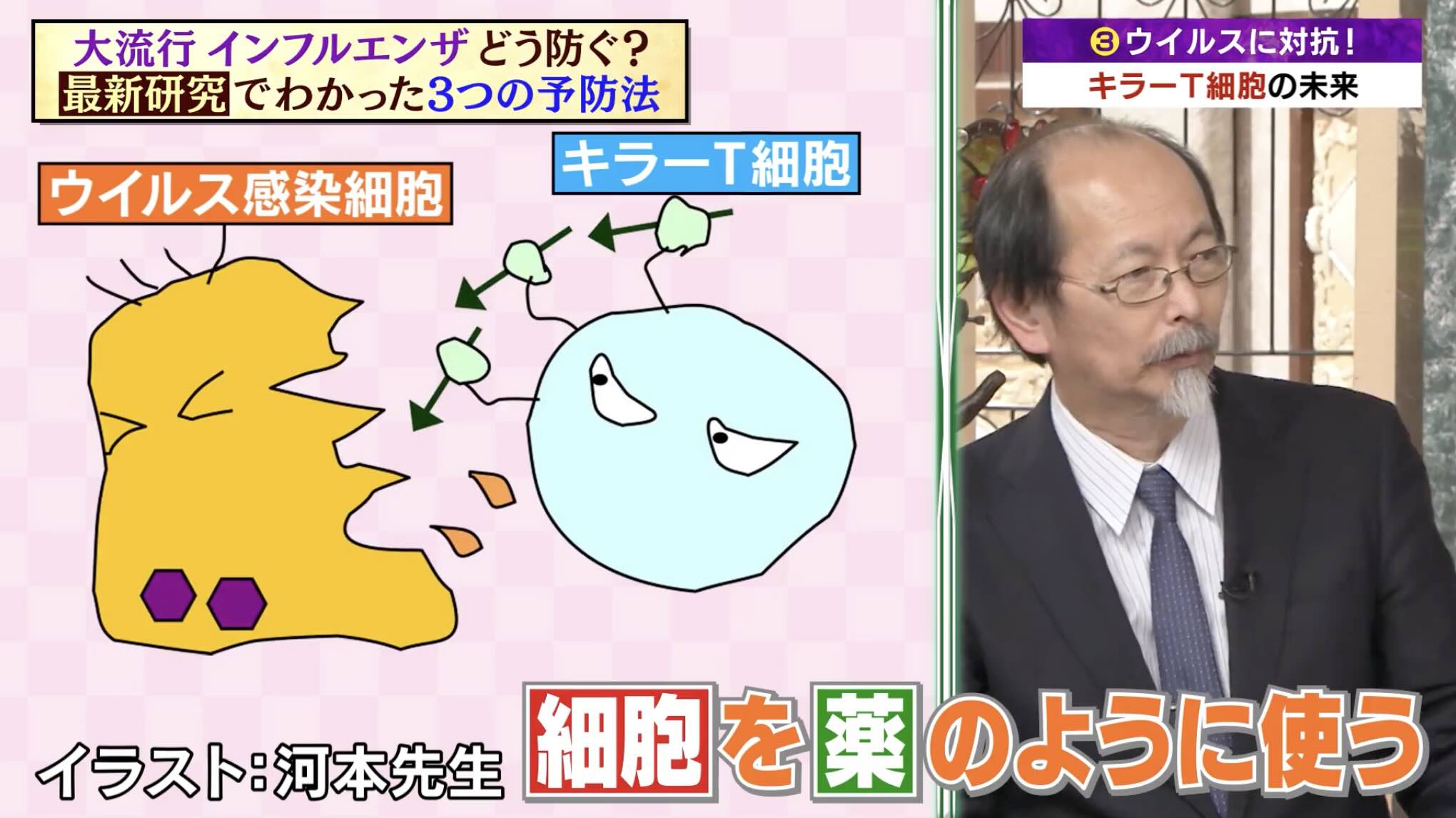 |
「キラーT細胞はウイルス感染細胞を殺すことで感染の拡大を防ぐ」「このキラーT細胞を薬のように使う」と解説。イラストを使ってもらえた。 |
 |
キラーT細胞はウイルス感染細胞やがん細胞を殺傷できるとナレーションが入る。 |
 |
医生研が登場。 |
 |
ラボの細胞培養室で撮ったシーン。 |
 |
板原君がディープフリーザーから細胞を取り出すシーン。 |
 |
再生キラーT細胞が入った凍結チューブ。 |
 |
再生T細胞がウイルス感染細胞(肺胞上皮細胞)を殺傷する動画が流された。板原君が撮ってくれた。写真は再生T細胞を加えた直後。 |
 |
感染細胞がどんどん死んで凝集塊になっていく。死んだ細胞が赤く染色されるようになっている。 |
 |
12時間後。感染細胞はほとんど死滅している。死細胞の凝集塊の横に丸く膨らんでいるのはアポトーシスを起こした細胞に見られるブレブという袋状の突起。以下のこの動画と、コントロール実験の動画のリンクを貼っておく。 この動画: コントロール実験の動画: |
 |
林先生が「他のウイルスにも使えますか?」と質問。 |
 |
このあたりが一番言いたかったところ。「SARS、MERS、鳥インフルなどのような怖いウイルスに対しても細胞製剤を作って備蓄しておけるし、未知のウイルスによるアウトブレイクが起こっても2-3ヶ月で日本人の9割以上をカバーできる細胞製剤を作れる」と話をした。 |
 |
そして、「ウイルス感染で死ぬことがなくなる時代が来る」と言わせてもらった。 |
 |
ここからは後半のアレルギーの話。私の出番はしばらく無し。6人の学友の血液中のIgE抗体が測定された。この3人は問題なし。 |
 |
この3人はアレルギー反応あり。 |
 |
そのうち一人の小島さんは色々な花粉に対するアレルギーが検出された。 |
 |
アレルギーの部の話題。 |
 |
解説は矢上晶子先生(藤田医大)。冬は肌が荒れがちなので、荒れた肌に食物が付着すると感作が起こって食物アレルギーを発症する機会が多くなるという話をされた。 |
 |
そこで、保湿が大事という話。 |
 |
次に、新しいタイプのアレルギーの話。一般の人で果物に対するアレルギーを持っている人を調べたところ、3人について、新しいタイプのアレルギーが見つかった。 |
 |
新しいタイプのアレルギーというのは、花粉へのアレルギーを持っていると、交差反応で果物などの食物アレルギーを発症するという話。 |
 |
花粉と果物の交差反応の対応表。 |
 |
次にアレルギーの「コップ理論」と「てんびん理論」の話。アレルゲンに対する反応が溜まってコップが溢れるくらいになると発症するというのがコップ理論ということらしく、従来はコップ理論が主流だったらしい。 |
 |
矢上先生は「現在の主流はてんびん理論」と解説。 |
 |
色々な要素が加わって免疫力を上回るとアレルギーが発症するというモデルらしい。 |
 |
上図であれば、免疫力を上げればアレルギーを治せるように見えるので、林先生がそのように質問。 |
 |
ここで私が再登場。アレルギーは過剰な免疫反応なので、単に免疫力を強めるだけではうまくいかないと説明。 |
 |
免疫力を単にあげるのではなく、うまく整えるとアレルギーを治せる可能性があると解説。 |
 |
ここで、「私の友人が理研でそういう研究をしている」と言って、大野先生を紹介。この時、スタジオでは「大野先生とはNegative Selectionというバンドを一緒にやっていて、大野先生はボーカリスト」と言って、その場でのウケは良かったが、さすがに、採用されなかった。 |
 |
ある栄養素がカギ、と前フリ。こういうのは、勿論、台本があって、私はその通りに話をしているだけ。 |
 |
どういう経路で入手されたのか知らないが、石井優先生(大阪大学)が撮られた、制御性T細胞(Tレグ細胞)が樹状細胞とT細胞の間に割り込んで免疫反応を抑制している動画が流された。 |
 |
その後、大野先生が登場。平成5年の紫綬褒章受賞者であることも紹介された。 |
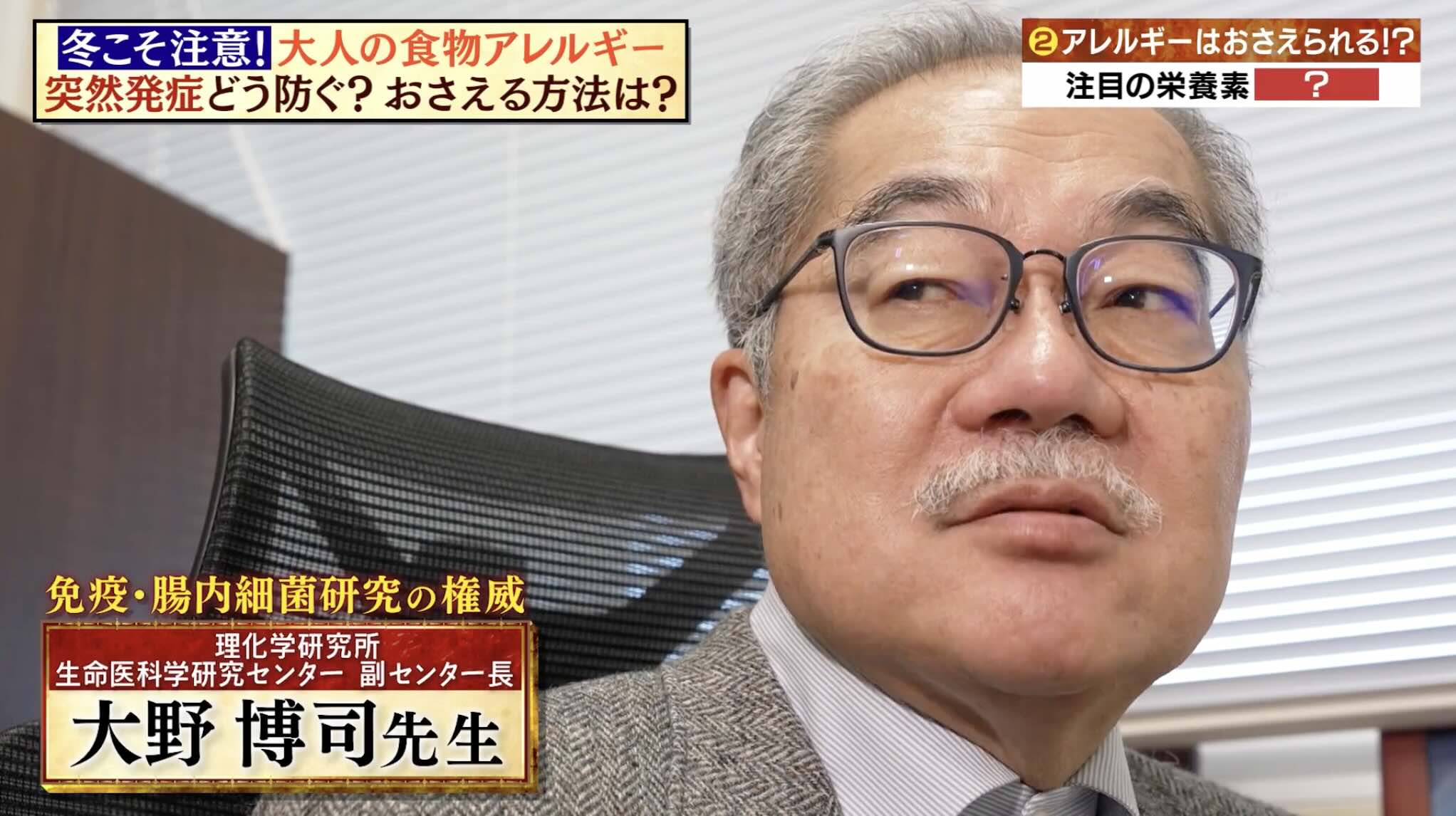 |
すごいドアップのショット。 |
 |
カギとなるのは食物繊維、と解説。 |
 |
食物繊維はクロストリジウム属の細菌の餌になって、酪酸が産生され、それが腸管でのTレグの生成を促進する、という話。マウスでの実験データが示された。 |
 |
エンディング。先週の水曜日に河本研でのロケ、金曜日にスタジオ収録で、今週の木曜日に放映という、すごいスケジュールで編集をされているのに、驚いた。もっとも、今回の話題は時事性があるので、タイミングを考えて突貫作業になったということらしく、普通はもう少し余裕を持って編集するらしい。 |
2025年1月23日(木)①
「林修の今、知りたいでしょ!」に出演
 |
テレビ朝日系1月23日木曜日夜8時から放映の「林修の今知りたいでしょ」に出演した。今回のテーマは「緊急特集!感染拡大インフルエンザ&冬に気をつけたいアレ
ルギー」ということで、私はインフルエンザの枠で関雅文先生(埼玉医科大学)と一緒に教壇に立った。1月30日夜8時までは番組の見逃し配信サイトか、Tverで観られる(以下リンク参照)。
番組見逃しサイト: Tver: まずは左のサムネイルと次の一枚の画像だけを出すが、来週にはもう少し詳しい記事を書く予定。 |
 |
私は「隠れインフルエンザ」が発生する仕組みの話と免疫記憶についての解説をした後、「免疫力を上げるにはお昼にリラックスするのが良い」という話をして、その流れで、「ウイルス治療用T細胞製剤」の話(2024年7月30日の記事参照)を紹介した。なお、ウイルス用T細胞製剤はES細胞をベースとしているが、この番組ではiPS細胞からT細胞を再生、という文脈での紹介になった。とはいえ、「未知のウイルスによるパンデミックが起こっても、2-3ヶ月で治療薬を作れる」「ウイルス感染による死が無くなる時代がくる」という大事なメッセージを言った部分は採用された。 後半のアレルギーの話では、矢上晶子先生(藤田医大)がずっと話をされたが、私は最後の方に、理研の大野博司先生の研究を紹介する役割で、少し登場した。大野先生はビデオで登場され、「食物繊維がTregを増やす」という話をされた。その大野先生の紹介の際、スタジオでは「Negative Selectionというバンドを一緒にやっていて、大野先生はボーカリスト」と言って、その場でのウケは良かったが、さすがに、採用されなかった。 |
2025年1月20日(月)
KICセミナーと新年会
 |
表記の会が南部総合研究棟で開催された。 |
 |
セミナーは、國澤純先生(医薬基盤研)によるセミナー。腸内細菌の話を沢山聴けた。一万人以上の人のデータを蓄えているのがすごい。年齢、性別、BMIなどのデータと、特定の菌種との相関関係などを解析することができる。 |
 |
新年会。 |
 |
國澤先生、濱崎洋子先生(CiRA)と。 |
 |
上野研と村川研の若い人達と。こういう交流が持てるのはいいことだ。 |
2025年1月17日(金)
「林修の今、知りたいでしょ」のスタジオ収録
 |
毎週木曜日20時からにテレビ朝日系で放映されている「林修の今、知りたいでしょ」に出演することになり、この日、六本木のスタジオで収録があった。 |
 |
放映は左の予告にあるように、テレビ朝日系で、1月23日木曜日夜8時から。インフルエンザの話とアレルギーの話ということで、私はインフルエンザの話で関雅文先生(埼玉医科大学)と一緒に教壇に立つ予定。ウイルス治療用T細胞製剤の話(2024年7月30日の記事参照)も紹介されると思われる。アレルギーの話では矢上晶子先生(藤田医大)が話をされる最後の方に少し登壇する予定。 |
2025年1月16日(木)
LiMe Happy Hour、初開催
 |
医生研の助教を中心とした若い人達の呼びかけで、交流の場として、定期的に「LiMe Happy Hour」と称する懇親会が開催されることになった。計画としては、各奇数月で、5月と9月はそれぞれ新所員歓迎会、リトリートがあるからパス。ポスターは、私が基本型をデザインした。「がんゲノム医療」という本のカバーイラストから拝借した。 がんゲノム医療やさしい系統講義(2023年4月11日刊行): |
 |
この会は医生研全体を対象にしていて、教員だけでなくテクニカルスタッフ、秘書、大学院生などにも参加をしてもらいやすくするため、教員は一律1000円、それ以外はタダという破格の企画。PIからの寄付はある程度期待できるものの、少しでも安く料理やお酒を用意する必要がある。そこで、「できるだけ安く、量があって、それほど手間もかからず、美味しい物を提供できる方法」を提示するということで、第一回については、食べ物に関しては私が受け持つことにした。ラボのスタッフと共に、近くのライフに買い出し。なお、この日は普段乗っているアウトランダーを息子に貸したために、妻が乗っているランエボXを借りた。 |
 |
あれこれネットなどで調べたが、オードブルのセットとして一番安いのが、ライフのセットで、4人前で税込1900円。一人前で500円くらいで、十分な量がある。他のケータリングでは多くが一人前1000円以上するので、かなり安いと思われる。8つ(32人前、約15000円)を1週間前に注文して、この日に受け取った。 |
 |
河本研のmeeting roomのテーブル(3つ)と椅子(22脚)を提供した。 |
 |
お酒はビール24缶x2(約1万円)がベース。それ以外は差し入れに期待。今回は坂口志文先生からワインやビールを寄付頂いた。 |
 |
お酒を飲めない人用に、ノンアルもしっかりビールやチューハイ味を用意されていた。カウンターの上に置いてあるボウルには、「ポテチ食べ比べ」というイベント用のポテトチップスが入っている。 |
 |
今回のメインは焼きそば。生麺の焼きそば3人前(180円)、豚肉の細切れ(300円)、もやし(40円)、カット野菜(130円)で三人前が作れるので、一人前200円強。安い。河本研のホットプレート2台を提供した。基本食材は3人前x10ラウンド分なので、約6000円。それ以外に、青のり、鰹節、紅生姜、マヨネーズなども用意した。 |
 |
坂口研からの寄付で、お菓子やおにぎり。 |
 |
河本研調達分とは別個の食料として、ピザも供された。 |
 |
17時から開始。 |
 |
受付役のスタッフテーブル。 |
 |
ロビー側に用意したテーブルも満席。 |
 |
焼きそばを1時間くらいで5ラウンド作り終わり、ほっこりしているテーブル。1ラウンドで3人前を作っているが、それを6人くらいに配っているので、30人分くらい作ったことになる。もう一つのテーブルでも同じくらい作ったので、焼きそば班としては、合計60人分くらい作ったことになる。 |
 |
17時に始まり、19時ぴったりには終了。Happy Hourの提唱者、松浦顕教先生が挨拶。真ん中あたりに、河本研のゲストとして参加された北村俊雄先生(東大名誉教授、神戸先端医療研究センター長、Negative Selectionのドラマー)が居られる。この後、皆でお片付け。 |
 |
片付けが終わった後、今回の会のオーガナイザー+有志で、河本教授室で反省会。今回は、第一回としては大成功だったと言えよう。次回に向けての建設的な意見が交わされた。 |
2025年1月15日(水)
Lecture Series The Immunology Alliance
 |
表記の会で話をさせて頂いた。日本語では免疫同盟セミナーシリーズというようだ。2ヶ月に一回の頻度で開催されているらしい。 |
 |
左上から、オーガナイザーのChristina Zielineki教授(Leibniz-HKI,Jena) 、竹内理先生、今回の演者である私と、Andreas Diefenbach教授(シャリテー – ベルリン医科大学)。 |
 |
Diefenbach教授はILC3によるIL-22産生の話をされた。その冒頭に、2018年の国際ILC学会用に私が描いたイラスト(2018年1月23日の記事参照)を示してくれた。 |
2025年1月15日(水)
「林修の今、知りたいでしょ」の取材
 |
毎週木曜日20時からにテレビ朝日系で放映されている「林修の今、知りたいでしょ」に出演することになり、この日、京大での撮影があった。 |
2025年1月14日(火)
日立製作所およびChildren’s National Hospitalの人達と打ち合わせ
 |
Children’s National Hospitalではthird partyのVirus-specific T cellを用いた治療法の開発を進めていて、米国のあちこちにネットワークを形成中との話だった。日立はそのための施設整備に関与しているようだ。将来的には多能性幹細胞由来のT細胞を使う戦略も検討したいという話で、この日の午後、医生研の会議室で打ち合わせを行なった。写真は、その後の会食。 |
2025年1月14日(火)
医生研チャンネルで「再生T細胞によるコロナ治療」の戦略を紹介
 |
2024年12月27日に、表医生研チャンネルに、「ES細胞由来再生キラーT細胞によるコロナ治療」の戦略を紹介する動画がアップされた。内容は、昨年7月にニュースリリースを出した時と同じ(2024年7月30日の記事参照)で、ファイル10(本編)は私の他に川瀬栄八郎先生、中馬新一郎先生、牧野晶子先生に出演頂いていて一般的な説明、番外編の方では、私が詳しく解説している。これらの2本は、お正月休みの間に視聴数の伸びが好調で、休み明けの1月6日に本編が3300再生、番外編が2200再生になっていた。その後数日間、再生回数は急激に伸び、1月9日には本編は1万再生を超えた。現在は、本編1万6千回、番外編は1万再生くらいで落ち着いている。多くの人に観ていただけているのは、ありがたいことだ。 File10:キラーT細胞製剤でウイルスと戦う 再生免疫学分野 File10番外編:河本教授による解説 |
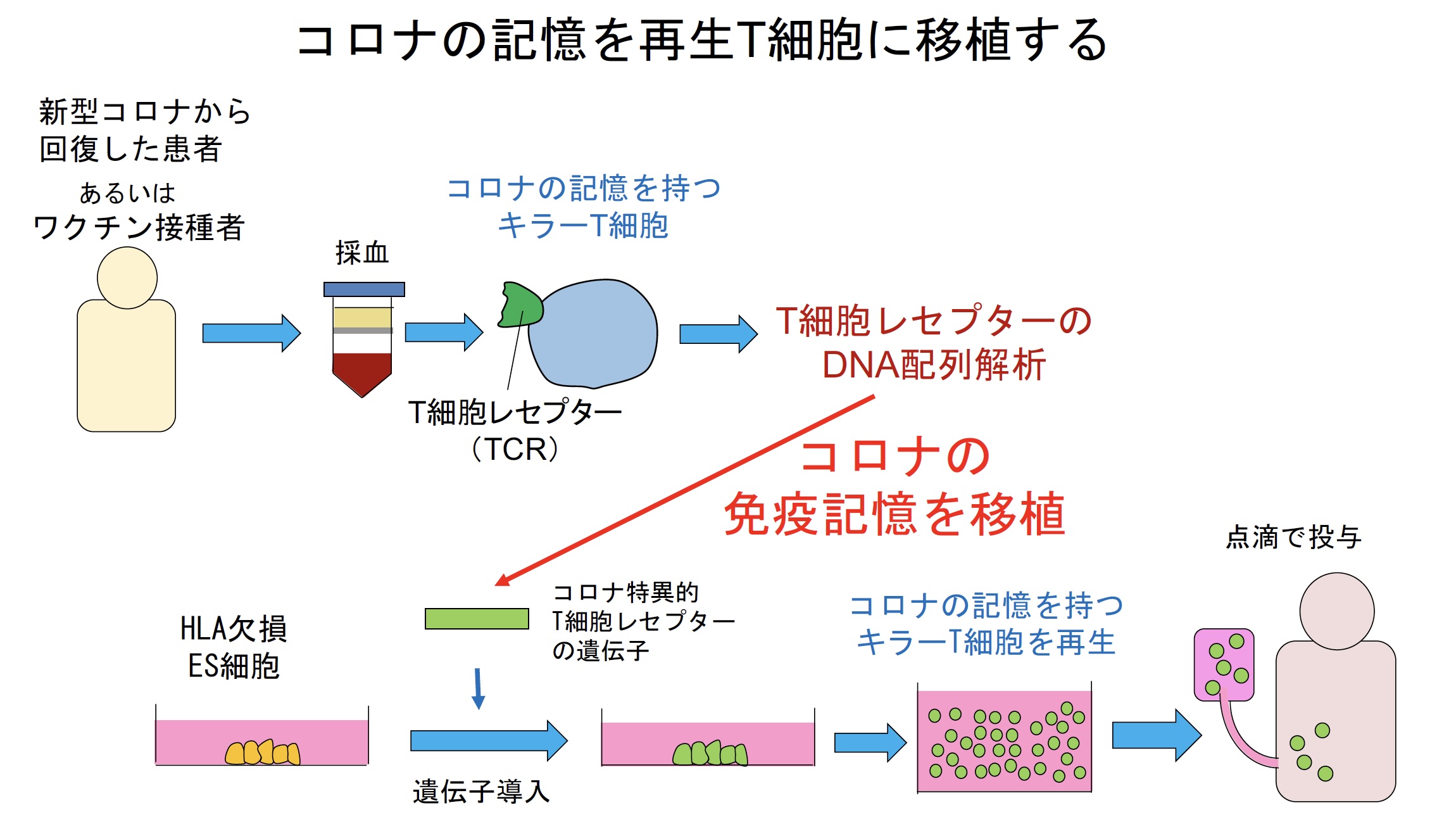 |
左図は戦略の概要。「治った人の免疫記憶をES/iPS細胞に移植する」という発想をベースにしている。 |
2025年1月13日(月・祝)
第一内科同窓会
 |
この日の昼食時に、表記の会が京都リーガロイヤルホテルで開催された。5年ぶりということらしい。100人以上が参加し、盛況だった。 |
 |
血液内科教授の高折晃史先生による挨拶。京大病院の病院長でもある。 |
 |
高折先生が現在の病院の状況などについて、スライドを使って説明。左図は、京大病院の施設整備が一通り終わったという話。 |
 |
高度急性期医療の体制が整ったという話。 |
 |
今回の同窓会参加者の中の最長老、吉田弥太郎先生(医仁会武田病院)による挨拶。1960年卒とのことなので、90歳が近いくらいのお歳だと思われるが、メモも見ないで、「血液学会は設立以来ずっと京都に事務所がある」という話や、昨年の血液学会集会で高折先生の奥様がフルートの演奏が素晴らしかった話(無伴奏でリベルタンゴを演奏された話)など、割と長い挨拶を整然とされていた。 |
 |
久々の同窓会ということで、コロナ以降に入局された先生方が、年度ごとに紹介された。写真は今年度入局した人達(確か一名欠席だったと思う)。多くの入局者があって、医局として安泰な感じだ。 |
 |
錦織桃子先生(人間健康科学科教授)と。錦織先生には、少し前、紹介した患者を診ていただいた。大変よくして頂いたようだった。ありがとうございました。 |
2025年1月10日(金)
佐治先生主宰の昼食会
 |
表記の会が久々に開催。前回(2024年7月19日の記事参照)に引き続き、リバーセル関連の会になった。 |
 |
窓からの景色。この日は前記のように冬型気圧配置で、朝方には雪が降ったりしたが、お昼には雪雲は少し北へと後退した。 |
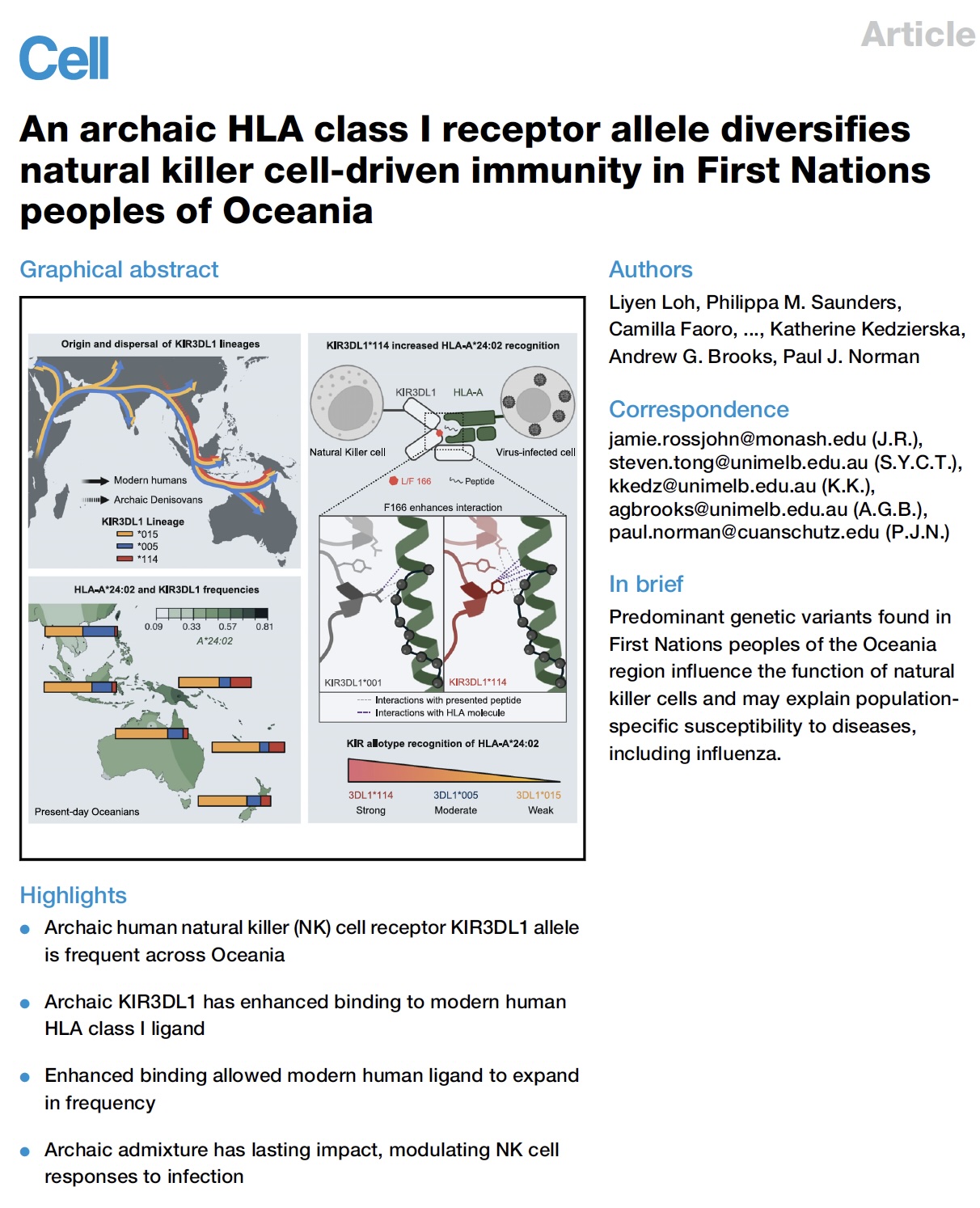 |
この昼食会は、勉強会を兼ねている。この日に私が紹介した論文は、少し前にCellに出た論文(187:7008-7024, 2024)で、KIRの変異型の出現がHLAの特定のアリルの拡大に繋がったという話。一般にはHLAの特定の遺伝子型が拡がって定着するのは、特定の病原体による感染症が契機とされるが、この研究では異なるメカニズムが紹介されている。具体的には、デニソワ人との交雑によってオセアニアの原住民であるアボリジニにKIR-3DL1の変異型が流入し、それに合わせて、KIR-3DL1のリガンドとしてその変異型への結合力が強いHLA-A*2402が、アボリジニの人達の中で拡大したという話。壮大な話で、佐治先生にも喜んで頂けたようだった。HLA-A*2402は東アジアにも多く、特に日本では近隣国に比して多い(日本人の約6割が保有)。これはおそらく別な淘汰圧がかかったということであろう。 |
2025年1月10日(金)
華中科技大学と京大の合同フォーラム
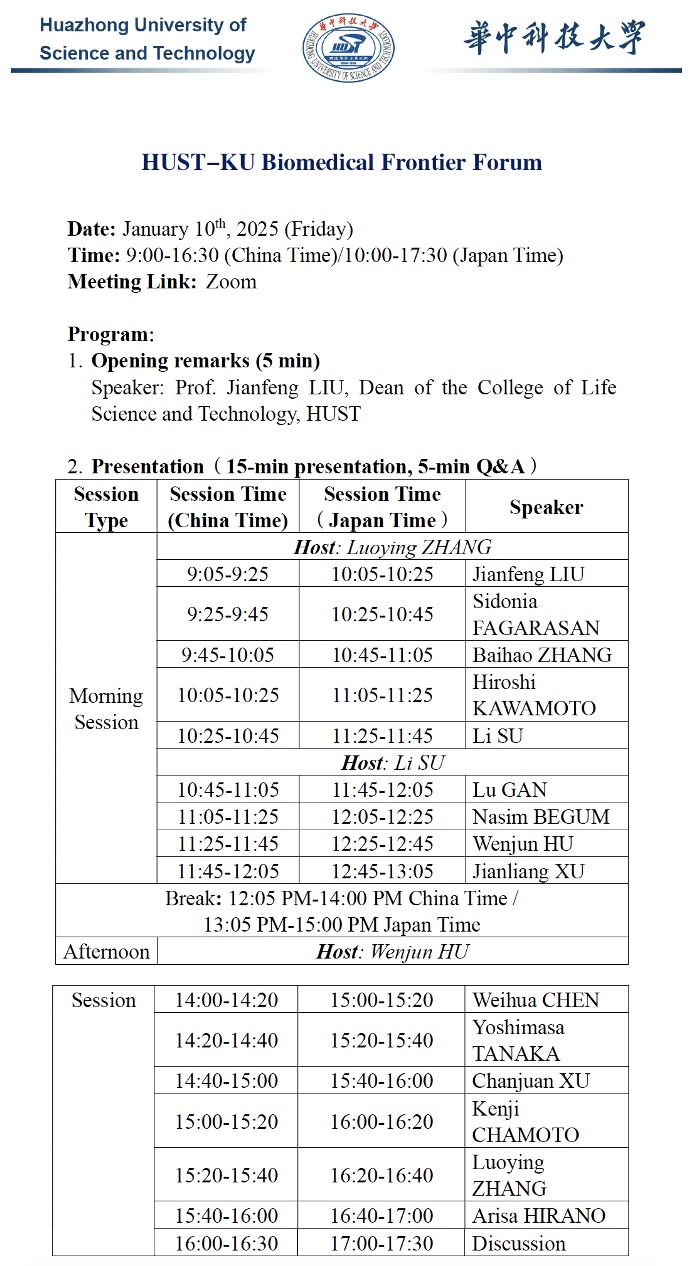 |
表記の会がオンラインで開催された。華中科技大学は武漢にある大学で、医学系と理工系を特徴とする。今回の会は、主にがん免疫に関する話題に焦点が当てられた。 |
 |
オーガナイザーの一人が、同大学のLi Su教授。 |
 |
Li Su先生はかつて私が湊研にいた頃に大学院生として在籍しておられた。左はその当時の写真。自分(河本)のプレゼンの際に、イントロのスライドとして用いた。 |
2025年1月10日(金)
京都で積雪
 |
今季最大の寒波の襲来ということで、この日の午前中、京都でも雪が降り、少しだけ積雪があった。写真は教授室から。 |
2025年1月7日(火)
中国医薬大学における京都大学オンサイトラボについての打ち合わせ
 |
少し前に記事にしたが、京都大学は中国医薬大学にオンサイトラボを持つ事になり、その件について昨年11月に先方のキャンパスで記念式典が行われた(2024年11月19日の記事参照)。この日、その維持管理についての打ち合わせが行われた。打ち合わせは萩原先生主導で行われ、部屋はCCIIの一室。CCIIは開所式の際には表玄関から1階のカンファレンスルームとロビーには入ったが、今回は西口から3階に入った(2024年11月12日の記事参照)。写真はCCIIの西面。 |
 |
打ち合わせの後、研究スペースなどを見学させていただいた。この建物の本体は円形で、その中心は螺旋階段になっている。かっこいい。 |
 |
螺旋階段を軸に研究スペースがあり、その外側に居室や打ち合わせスペースが配置されている。写真は萩原先生。 |